三雲成持
近江の戦国武将・三雲成持は六角家臣。主家滅亡後も織田信雄、蒲生氏郷に仕え、子孫は旗本として存続。乱世を生き抜いた適応力ある武将。
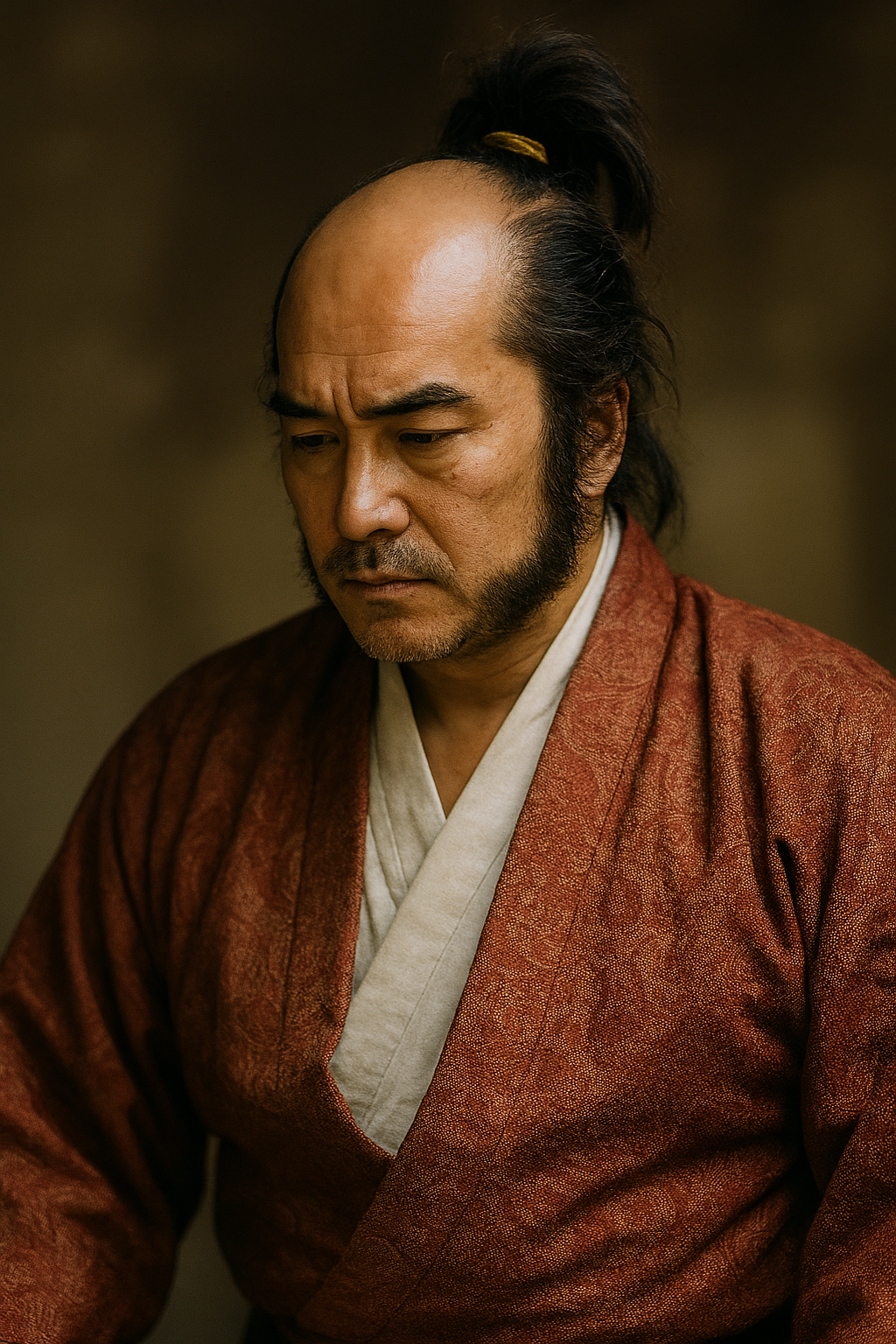
激動の時代を生き抜いた近江の将、三雲成持の生涯
専門家チーム
本報告書は、戦国時代の地域史、特に近江国(現在の滋賀県)の国人領主の動向に精通した歴史学研究者によって執筆されたものです。一次史料に近い文献と現地の伝承を多角的に分析し、一人の武将の生涯を、当時の政治的・社会的文脈の中に位置づけることを目的としています。
付属資料:三雲成持 関連年表
三雲成持の生涯は、主家の盛衰、一族の相次ぐ不幸、そして自身の立場の目まぐるしい変化を特徴とします。以下の年表は、本報告書で詳述される出来事の全体像を把握するための一助として作成されました。
|
西暦(和暦) |
成持の年齢(推定) |
関連事項 |
成持の立場・主君 |
|
1540年(天文9年) |
0歳 |
三雲定持の次男として誕生 1 。 |
六角家臣 |
|
1563年(永禄6年) |
23歳 |
観音寺騒動。父・定持が騒動の収拾に奔走 4 。 |
六角家臣 |
|
1566年(永禄9年) |
26歳 |
兄・賢持が浅井長政との戦いで戦死。成持が家督を相続 4 。 |
三雲家当主・六角家臣 |
|
1567年(永禄10年) |
27歳 |
父・定持と共に『六角氏式目』に署名。六角六宿老の一人となる 4 。 |
三雲家当主・六角家臣 |
|
1568年(永禄11年) |
28歳 |
織田信長が近江に侵攻。六角義賢親子が三雲城へ逃亡 4 。 |
三雲家当主・六角家臣 |
|
1570年(元亀元年) |
30歳 |
野洲河原の戦いで父・定持が戦死。三雲城は佐久間信盛に降伏開城 4 。 |
浪人 |
|
1570年~1584年 |
30歳~44歳 |
約14年間の浪人生活。この間の動向は不明。 |
浪人 |
|
1584年(天正12年) |
44歳 |
織田信雄に仕える。小牧・長久手の戦いで伊勢松賀島城に籠城 6 。 |
織田信雄家臣 |
|
天正12年以降 |
44歳以降 |
蒲生氏郷に仕える 5 。 |
蒲生氏郷家臣 |
|
1593年(文禄2年)頃 |
53歳頃 |
子・成長が徳川家康に召し出される 6 。 |
蒲生氏郷家臣 |
|
1603年(慶長8年) |
63歳 |
三雲成持、死去 1 。 |
(徳川家) |
|
1617年(元和3年) |
- |
子・成長が徳川幕府より千石の采地朱印状を拝領し、旗本となる 8 。 |
- |
|
1635年(寛永12年) |
- |
子・成長と孫・成時が相次いで死去し、嫡流が断絶。成時の弟・成賢が家名を継ぐ 6 。 |
- |
序章:近江国人・三雲成持という存在
戦国時代の日本列島の中心に位置する近江国は、京の都と東国を結ぶ交通の要衝であり、その支配権を巡って絶えず激しい争いが繰り広げられた地でした。この地を長く治めた守護大名・六角氏の支配下には、「甲賀五十三家」に代表されるような、強い独立性を持つ国人領主たちが存在し、彼らの動向は近江、ひいては天下の情勢をも左右する重要な要素でした。本報告書が主題とする三雲成持(みくも しげもち)は、まさにこの激動の時代の近江に生きた、そうした国人領主の一人です。
彼の名は、織田信長や豊臣秀吉といった天下人の影に隠れ、歴史の教科書で大きく扱われることはありません。しかし、彼の生涯を丹念に追うことで見えてくるのは、主家の滅亡、肉親との死別という度重なる苦難に直面しながらも、時代の変化を鋭敏に読み解き、一族の存続という最大の使命を果たそうとした、一人の武将の粘り強い生き様です。
利用者様がご提示された「六角家臣」「六角氏式目への署名」「織田信雄・蒲生氏郷への仕官」といった断片的な情報は、彼の生涯の重要な転換点を示しています [User Query]。本報告書は、これらの点を深掘りすると共に、彼が属した三雲一族の出自、主家・六角氏との特異な関係、そして彼の子孫が江戸時代に旗本として家名を繋いでいくまでの壮大な物語を、現存する資料に基づき網羅的かつ詳細に解き明かすことを目的とします。三雲成持は、単なる地方武将ではなく、戦国の乱世を生き抜き、近世へと続く橋渡しを成し遂げた「生存者」として、再評価されるべき人物なのです。
第一部:三雲一族の源流と権勢
三雲成持の人物像を理解するためには、まず彼が背負っていた「三雲氏」という家の歴史と、その権勢の源泉を解き明かす必要があります。三雲氏は、単なる六角氏の家臣ではなく、近江国甲賀郡に確固たる地盤を築いた独立性の高い勢力でした。
第一章:武蔵から近江へ ― 児玉党の末裔
三雲氏の出自は、遠く関東に遡ると伝えられています。『寛政重修諸家譜』などの江戸時代の系譜資料によれば、彼らは武蔵国(現在の埼玉県周辺)で活動した武士団「武蔵七党」の一つ、児玉党の分家であるとされています 8 。この伝承を裏付ける有力な証拠が、三雲氏の家紋です。彼らが用いた「軍配に一文字」の紋は、児玉党の代表紋である「軍配団扇」に由来するものであり、血脈を何よりも重んじた中世武士社会において、この家紋の一致は偶然とは考え難いものです 8 。
この児玉党の一族が近江国に土着し、「三雲」を名乗るようになったのは、室町時代の明応年間(1492年~1501年)のことでした。三雲新左衛門実乃(さねのり)という人物が甲賀郡下甲賀を領して三雲の地に住み、地名をもって自らの姓としたのがその始まりと記録されています 8 。実乃の子・行定(ゆきさだ)の代には、下甲賀のみならず野洲・栗太両郡にまで勢力を広げ、後に一族の拠点となる三雲城を築城しました 8 。関東から来た新興勢力は、わずか二代で近江の地に深く根を張り、有力な国人領主としての地位を確立したのです。
第二章:六角氏の「同盟者」としての実態
三雲氏が近江でその名を高めたのは、近江守護・六角氏との関係を通じてでした。特に、長享元年(1487年)に室町幕府9代将軍・足利義尚が六角高頼を討伐するために近江へ出兵した「鈎の陣(まがりのじん)」において、三雲氏は他の甲賀の地侍たちと共に六角氏に味方し、幕府軍を撃退する上で大きな役割を果たしました。この時に六角氏に味方した53の家は「甲賀五十三家」と総称され、三雲氏もその中核をなす一族として認識されるようになります 6 。
しかし、三雲氏と六角氏の関係は、単純な主従関係ではありませんでした。後藤氏や進藤氏といった六角氏譜代の家臣とは一線を画し、蒲生氏などと同様に、より独立性の高い「ゆるやかな同盟関係」にあったと見られています 8 。この特異な関係性は、三雲氏が持つ強大な経済力と、甲賀という地域の地政学的な特性に起因します。
第一に、成持の父である三雲定持は、独自に明(当時の中国)との貿易を手がけ、そこから得た莫大な利益を室町幕府に寄付するほどの経済力を有していました 4 。この財力は、六角氏からの経済的支援に依存することなく、独自の軍事力や政治力を維持するための強力な基盤となりました。さらに、領内の寺社の統制や家臣への恩賞の授与といった、通常は守護大名が持つ権限の一部を独自に行使していたことも記録されており 2 、彼らが一個の独立した領主として振る舞っていたことを示しています。
第二に、六角氏の戦略上、甲賀の地が極めて重要であったことが挙げられます。六角氏の本拠である観音寺城が敵の攻撃に晒された際、彼らは甲賀の山中へ退避し、地の利を活かしたゲリラ戦を展開することを常套手段としていました 9 。この戦略を成功させるためには、甲賀の地理と人脈を熟知した三雲氏ら甲賀武士団の全面的な協力が不可欠でした。そのため、六角氏は彼らを強権的に支配するのではなく、その独立性を尊重し、協力関係を維持するという、いわば互恵的な関係を築かざるを得なかったのです。この主家と一線を画す自立性こそが、後に成持が主家滅亡という危機に際して、独自の判断で道を切り拓いていく行動原理の源泉となったと考えられます。
第三章:観音寺城の奥座敷 ― 三雲城
三雲氏の権勢を象徴するのが、彼らの本拠地であった三雲城(現在の滋賀県湖南市吉永)です。この城は、単なる一族の居城ではなく、主家である六角氏にとって戦略的に極めて重要な意味を持つ「奥城(おくじょう)」、すなわち最終防衛拠点としての役割を担っていました。
三雲城の築城は、前述の「鈎の陣」に際し、長享元年(1487年)に六角高頼が三雲実乃(典膳)に命じて行われたと伝えられています 8 。標高334メートルの山上に築かれたこの山城は、六角氏の本拠・観音寺城が危機に陥った際の避難場所として、繰り返し歴史の舞台に登場します。実際に、天文6年(1537年)には六角義賢(承禎)が、そして永禄11年(1568年)には織田信長の侵攻を受けた義賢・義治親子がこの城に逃げ込んでおり、その重要性を物語っています 7 。城内の一角にある巨岩「八丈岩」の近くには、六角氏の家紋である「四つ目結」が刻まれた岩が存在することも、両家の密接な関係を今日に伝える貴重な物証です 12 。
城の構造は、土塁や堀切、井戸跡などが残る典型的な中世山城の様相を呈していますが 9 、その中でも特筆すべきは、城の入り口に設けられた「枡形虎口(ますがたこぐち)」です。巨大な石材を巧みに組み上げたこの防御施設は、敵兵を狭い空間に誘い込み、三方から攻撃を加えるためのもので、非常に高度な築城技術が用いられています 9 。このような大規模な石垣は、戦国時代中期の城郭としては異例であり、六角氏が滅亡した後、三雲成持が織田信雄や蒲生氏郷といった織豊政権下の大名に仕えた際に、最新の築城技術を取り入れて改修された可能性が研究者によって指摘されています 25 。三雲城は、六角氏の時代から織豊の時代へと、三雲氏の歩みと共にその姿を変えていった生きた城郭だったのです。
第二部:三雲成持の苦難と決断
三雲氏という強力な国人領主の家に生まれた成持でしたが、彼の人生は平坦なものではありませんでした。兄と父の相次ぐ死、そして主家の滅亡という逆境の中で、彼は一族の当主として重い決断を迫られることになります。
第一章:兄の死と家督相続
三雲成持は、天文9年(1540年)、六角家の重臣であった三雲定持の次男として生まれました 1 。本来、家督を継ぐべき立場にあったのは、兄の賢持(かたもち)でした。賢持は主君・六角義賢から「賢」の一字を拝領するほど将来を嘱望された武将であり、通称の「新左衛門尉」も三雲家代々の当主が名乗るものでした 5 。
しかし、成持の運命は、永禄9年(1566年)に大きく変わります。この年、江北の浅井長政との戦いにおいて、兄・賢持が討死してしまうのです 3 。この予期せぬ死により、当時26歳であった次男の成持が、急遽三雲家の家督を相続することになりました。それは、近江の情勢がますます緊迫化する中での、重責を伴う船出でした。
第二章:『六角氏式目』と三雲父子の役割
成持が家督を継ぐ直前、主家である六角氏の内部では、その屋台骨を揺るがす大事件が起こっていました。永禄6年(1563年)、当主の六角義治が重臣の後藤賢豊親子を誅殺したことに端を発する「観音寺騒動」です 4 。この事件は家臣団の激しい反発を招き、義治・義賢親子は一時、本拠の観音寺城から追放される事態にまで発展しました。この混乱を収拾するために、家臣団と六角氏の仲介役として奔走したのが、蒲生定秀と、成持の父・三雲定持でした 4 。
この騒動を経て、六角氏の権威は大きく揺らぎ、家臣団の合議によって大名の権力を制約するという、当時としては画期的な分国法(領国経営の基本法)が制定されることになります。これが『六角氏式目』です。永禄10年(1567年)、家督を継いだばかりの成持は、父・定持と共にこの式目の署名者に名を連ねました 4 。
この署名は、単なる形式的な行為ではありませんでした。それは、観音寺騒動の調停を通じて「六角家の安定に不可欠な存在」となった三雲氏の権威を、成持が当主として正式に継承したことを内外に示すものでした。この功績により、成持は「六角六宿老」の一人と称されるようになり 5 、若くして近江の国人領主の中でも重きをなす存在となったのです。しかしそれは同時に、弱体化した主家を支え、一族の存亡をかけた高度な政治的判断を常に迫られる、困難な立場の始まりでもありました。
第三章:主家の落日
成持が三雲家の舵取りを始めて間もなく、近江国は天下統一を目指す織田信長の巨大な軍事力の前に晒されることになります。
永禄11年(1568年)、足利義昭を奉じて上洛の途にあった織田信長の大軍が近江に侵攻します。六角義賢・義治親子は、本拠である観音寺城での決戦を避け、かつての例に倣って父・定持を頼り、三雲城へと逃げ込みました 4 。これに対し、三雲親子は主君を迎え入れ、甲賀の地の利を活かしたゲリラ戦を展開し、信長軍に抵抗を試みます 4 。
しかし、織田軍の圧倒的な物量の前に、六角氏の抵抗は長くは続きませんでした。元亀元年(1570年)、信長包囲網の形成を好機と見た六角軍は反攻に転じますが、柴田勝家や佐久間信盛が率いる織田軍と野洲河原で激突し、大敗を喫します。この「野洲河原の戦い」において、父・三雲定持は奮戦の末、討死しました 4 。
最大の支柱であった父を失い、主家も事実上崩壊したことで、成持に残された選択肢は限られていました。彼は織田方の将・佐久間信盛に降伏し、三雲城を開城します 9 。多くの甲賀武士たちが時勢を読んで信長に仕官する中、成持は信長の配下に入ることを潔しとせず、所領と城を失い、浪人の身となる道を選びました 8 。それは、父祖伝来の地を離れ、先の見えない雌伏の時へと入る、苦渋の決断でした。
第三部:再起と新たな主君
主家と父、そして領地を一度に失った三雲成持でしたが、彼の物語はここで終わりませんでした。約14年にも及ぶ浪人生活を経て、彼は時代の変化を巧みに捉え、再起の道を模索し始めます。
第一章:浪人から織田信雄の家臣へ
元亀元年(1570年)の三雲城開城から、天正12年(1584年)までの約14年間、三雲成持の具体的な動向を示す史料は乏しく、彼の人生における「空白の期間」となっています。この間、彼は旧主・六角氏の残党と共に抵抗を続けていたのか、あるいは近江のどこかで再起の機会を静かに窺っていたのか、定かではありません。
この長い雌伏の時を経て、成持が再び歴史の表舞台に姿を現すのは、天正10年(1582年)の本能寺の変によって織田信長が倒れ、天下の情勢が再び流動化した後のことでした。天正12年(1584年)、成持は信長の次男であり、羽柴秀吉と天下の覇権を争っていた織田信雄に仕官します 8 。この仕官に際して、信雄から旧領の回復を約束されたと伝えられています 6 。これは単なる再就職ではなく、反秀吉勢力の一翼を担うことで、失われた三雲家の栄光を取り戻そうとする、成持の明確な政治的決断でした。
第二章:小牧・長久手の戦役と松賀島城
成持が信雄に仕えた天正12年(1584年)、羽柴秀吉と、織田信雄・徳川家康の連合軍との間で「小牧・長久手の戦い」が勃発します。成持も信雄方の武将として、この天下分け目の戦いに身を投じました 6 。
彼の主戦場となったのは、信雄の領国であった伊勢国です。成持は、同じく信雄の重臣であった滝川雄利(かつとし)と共に、約700の兵を率いて伊勢湾に面した要衝・松賀島城(まつがしまじょう)に籠城し、秀吉方の大軍と対峙しました 6 。その後、浜田城の防衛にも加わったと記録されています 8 。
この籠城戦における成持の同僚、滝川雄利は、元は伊勢国司・北畠氏の一族であり、信長・信雄に仕えた伊勢の有力国人でした 26 。信雄が、成持のような近江の旧名族や、雄利のような伊勢の国人を動員して秀吉に対抗しようとしていたことは明らかであり、成持はその戦略の中で重要な駒として期待されていたことが窺えます。
しかし、戦いの末、信雄が家康に相談なく秀吉と単独で和睦を結んだため、連合軍は解体。これにより、成持が抱いていた旧領回復の望みは、またしても絶たれてしまうことになりました 6 。
第三章:蒲生氏郷、そして徳川の世へ
信雄の下での再起が叶わなかった成持は、次なる主君として蒲生氏郷を選びます 5 。氏郷もまた旧六角家臣の出身であり、近江日野(現在の滋賀県蒲生郡日野町)を本拠としていたことから、両者の間には地縁的な繋がりや旧知の間柄であった可能性が考えられます。氏郷は信長、秀吉にその才を高く評価され、破竹の勢いで出世を遂げた名将であり、彼に仕えることは、成持にとって安定した地位を得るための現実的な選択でした。
蒲生氏郷の家臣団における成持の具体的な活躍を記す史料は限られていますが、氏郷が後に会津92万石の大領主となった際にも、彼に付き従っていたと考えられます。しかし、文禄4年(1595年)に氏郷が急死し、蒲生家にお家騒動が勃発すると、成持は再び新たな道を模索する必要に迫られます。
この時期、成持は次なる天下人として台頭しつつあった徳川家康に接近します。史料によれば、成持の子である三雲成長(なりなが)は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いよりも前の時点、おそらくは文禄・慶長年間に家康に召し出されています 6 。これは、成持が蒲生家に仕えつつも、先を見越して徳川家との関係を構築していたことを示唆しており、彼の先見性と政治的手腕の高さが窺えます。慶長8年(1603年)、成持は63年の波乱に満ちた生涯を閉じました 1 。彼は自らの手で旧領を回復することはできませんでしたが、息子に一族再興の望みを託し、その礎を築いたのです。
第四部:三雲家のその後と成持の遺産
三雲成持の生涯は、一族の家名を近世へと繋ぐという大きな成果をもって幕を閉じました。彼の死後、三雲家は息子・成長によって再興され、江戸幕府の旗本として新たな歴史を歩み始めます。また、彼の生きた証は、史跡や伝説の中にもその面影を留めています。
第一章:旗本三雲家の成立と系譜
成持の跡を継いだ息子・三雲成長は、父が築いた徳川家康との関係を元に、見事に家を再興させます。成長は家康に仕え、関ヶ原の戦いやその後の戦役で功を挙げたとみられ、その功績によって近江国甲賀郡内にあった三雲氏の旧領のうち、千石の知行地を与えられました 6 。これにより、三雲家は徳川幕府の直参、すなわち旗本としての地位を確立しました。
成長はその後、大坂冬の陣・夏の陣にも徳川方として参陣し、戦後の元和3年(1617年)には、幕府から正式に所領を安堵する朱印状を拝領しています 8 。これは、三雲家が名実ともに関東から移り住んだ地で、再び領主としての地位を回復した瞬間でした。
しかし、再興された三雲家の嫡流には悲劇が待ち受けていました。寛永12年(1635年)、当主の成長と、その跡を継ぐはずだった嫡男・成時(なりとき)が、相次いでこの世を去ってしまったのです。これにより、成持から続く三雲家の直系は、無念にも断絶してしまいました 6 。
幸いなことに、成時の弟にあたる成賢(なりかた)が家督を継ぐことを許され、旗本としての三雲家は存続しました 8 。以後、この成賢の家系が三雲の家名を江戸時代を通じて後世に伝え、成持が命がけで守り抜いた一族の血脈は、途絶えることなく受け継がれていったのです。
第二章:伝説と史跡にみる面影
三雲成持と彼の一族が生きた証は、公式な歴史記録だけでなく、地域の伝説や史跡の中にも色濃く残されています。
最も有名なのが、講談や小説で人気の忍者「猿飛佐助」との関わりです。司馬遼太郎の小説『風神の門』などで描かれた説によれば、猿飛佐助のモデルは、成持の兄・賢持の子、すなわち成持の甥にあたる三雲佐助賢春(みくも さすけ かたはる)であるとされています 5 。三雲城跡に今も残る巨岩「八丈岩」は、この佐助が少年時代に忍術の修行を積んだ場所と伝えられ、「落ちそうで落ちない」その姿から、近年では合格祈願のパワースポットとしても人気を集めています 15 。この伝説は、三雲氏が属した甲賀武士団が、優れた諜報・戦闘技術を持つ集団として知られていた史実を背景に生まれたものと考えられます。
また、一族の菩提寺とされるのが、滋賀県湖南市三雲にある浄土宗の寺院、永照院(えいしょういん)です 22 。この寺は古くは「三雲寺」と呼ばれ、三雲氏が平時に暮らした居館「三雲館」の南東に隣接していました 31 。永照院の墓地には、現在も三雲一族のものと伝わる墓が残されており 22 、一族の末裔と称する人々が訪れることもあるようです。ただし、成持個人の墓所については特定されておらず、一部には広島の観音寺にあるとする情報も見られますが 38 、同姓同名の別人の可能性も否定できず、今後の研究が待たれます。
これらの伝説や史跡は、三雲成持と彼の一族が、単なる歴史上の存在に留まらず、地域の文化や人々の記憶の中に生き続けていることを示しています。
結論:乱世の生存者、三雲成持の歴史的評価
三雲成持の生涯を総括すると、彼は戦国時代を象徴するような華々しい武功や、天下の趨勢を左右するような大功を立てた武将ではありませんでした。むしろ彼の人生は、兄と父の戦死、そして絶対的な庇護者であった主家・六角氏の滅亡という、相次ぐ逆境と苦難の連続であったと言えます。
しかし、彼の真価は、そうした絶望的な状況から、いかにして一族を再興へと導いたかという点にあります。信長に仕えず浪人の道を選んだ気骨、反秀吉の旗頭であった織田信雄に再起の望みを託した政治的嗅覚、そして最終的に新たな天下人・徳川家康との繋がりを確保した先見性。彼は、その時々の情勢を冷静に見極め、自らが持つ「甲賀の有力国人・三雲氏」という家名の価値を最大限に利用しながら、巧みに主君を乗り換え、時代の荒波を乗り越えていきました。
彼の生涯は、中央の激しい権力闘争の渦中で、自らの家と血脈を守り抜くために奔走した、一人の地方国人領主の、粘り強く、そして現実的な生存戦略の実例として極めて興味深いものです。六角氏の「同盟者」という独立した立場から、織豊、徳川という巨大な権力機構に組み込まれる一員へと、その役割を柔軟に変化させながらも、ついに旗本として家名を後世に繋いだ三雲成持。彼の生き様は、戦国という「個」の力が支配した時代から、近世という「組織」の時代へと移行する、日本の大きな歴史の転換点を体現した、貴重な証人であると言えるでしょう。彼の物語は、歴史の勝者だけでなく、敗れ、あるいは翻弄されながらも、最後まで生き抜こうとした人々の姿にも光を当てることの重要性を我々に教えてくれます。
引用文献
- 三雲成持(みくもしげもち)『信長の野望・創造』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzou_data_d.cgi?equal1=6002
- 三雲成持 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/zh/articles/%E4%B8%89%E9%9B%B2%E6%88%90%E6%8C%81
- 三雲成持- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%89%E9%9B%B2%E6%88%90%E6%8C%81
- 三雲定持 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%9B%B2%E5%AE%9A%E6%8C%81
- 三雲成持 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%9B%B2%E6%88%90%E6%8C%81
- 歴史人物語り#86 甲賀五十三家の三雲氏は瓶割り柴田の由来にちょっと絡んでいたり六角六宿老でもあり猿飛佐助のモデルの人もいたりで意外とネタが豊富 - ツクモガタリ https://tsukumogatari.hatenablog.com/entry/2019/11/18/200000
- 三雲城の見所と写真・300人城主の評価(滋賀県湖南市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1844/
- 武家家伝_三雲氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mikumo.html
- 近江 三雲城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/oumi/mikumo-jyo/
- 蒲生氏郷とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7
- 日本の城探訪 三雲城 - FC2 https://castlejp.web.fc2.com/04-kinkityugoku/136-migumo/migumo.html
- 近江にあった三雲(みくも)城の所在地などのほか、その歴史を知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000098268
- 武家家伝_甲賀佐治氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sazi_koga.html
- 三雲城(近江国/滋賀県) - 日本の城写真集 https://castle.jpn.org/oumi/mikumo/
- 湖南市・三雲学区の城址紹介 https://mikumo-gakku.jp/smarts/index/102/
- 三雲城 http://yamajirooumi3.g2.xrea.com/2536209.html
- 三雲城の駐車場や御城印、見どころ(主郭の桝形虎口など)を紹介! https://okaneosiroblog.com/shiga-mikumo-castle/
- 三雲城址について https://hasesyouten-mikumojoushi.amebaownd.com/posts/53559510/
- 三雲城 丸岡城・丸岡東城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/siga/konansi.htm
- 三雲城址 | 滋賀県観光情報[公式観光サイト]滋賀・びわ湖のすべてがわかる! https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/880/
- 六角氏の家紋(四つ目結)を刻んだ岩 - 滋賀・びわ湖観光情報 https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/8624/
- 三雲家ルーツを探る遠足(3年前のお話) | どんぐり工房 こねこねらんどの夢冒険 https://plaza.rakuten.co.jp/dongurikobo/diary/202007100000/
- 三雲城 | 近江の城50選 - 滋賀・びわ湖観光情報 https://www.biwako-visitors.jp/shiro/select50/castle/d7/
- 新近江名所圖会 第30回 三雲城と八条岩 - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/shigabun-shinbun/best-place-in-shiga/%E6%96%B0%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%90%8D%E6%89%80%E5%9C%96%E4%BC%9A%E3%80%80%E7%AC%AC30%E5%9B%9E/
- 三雲城 - 近江の城めぐり - 出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 https://shiroexpo-shiga.jp/column/no11/
- 滝川雄利/戦国Xファイル https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x187.html
- マイナー武将列伝・滝川雄利 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/oda_039.htm
- 三雲城址探訪(2)(再録) - お気楽忍者のブログ 参ノ巻 https://okirakuninja.hatenablog.com/entry/2025/05/14/130000
- 三雲城・甲賀における六角氏の退避場所 https://ameblo.jp/bd20159/entry-12387855741.html
- 三雲城(吉永城)(滋賀県湖南市) https://masakishibata.wordpress.com/2013/05/26/mikumo/
- 三雲館(滋賀県湖南市) https://masakishibata.wordpress.com/2017/02/12/mikumo-yakata/
- 第278回:三雲城(六角氏が逃げ込んだ三雲氏の城) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-299.html
- 永照院(滋賀県湖南市)の永代供養墓・樹木葬・納骨堂・お墓・墓じまいの費用・評判と見学予約 https://eitaikuyo.jp/searcht/temple/T-0000070164
- 永照院(えいしょういん) | 滋賀県湖南市観光ガイド ぶらりこなん https://www.burari-konan.jp/kanko/shaji/eishoin/
- 三雲家大人だけの遠足~三雲家ルーツを探る~ | どんぐり工房 こねこねらんどの夢冒険 https://plaza.rakuten.co.jp/dongurikobo/diary/201705230000/
- 永照院 | 寺院を検索する http://otera.jodo.or.jp/temple/28-214/
- 正倉院文書に見える三雲寺の所在地について(小松葉子) - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/site-archives/download-kiyou-30_komatsu.pdf
- 三浦元忠 (みうら もとただ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12040340939.html