伊賀久隆
伊賀久隆は備前の戦国武将。松田氏から宇喜多直家に仕え、虎倉城を拠点に勢力を拡大。しかし直家に謀殺された。伊賀忍者とは無関係。
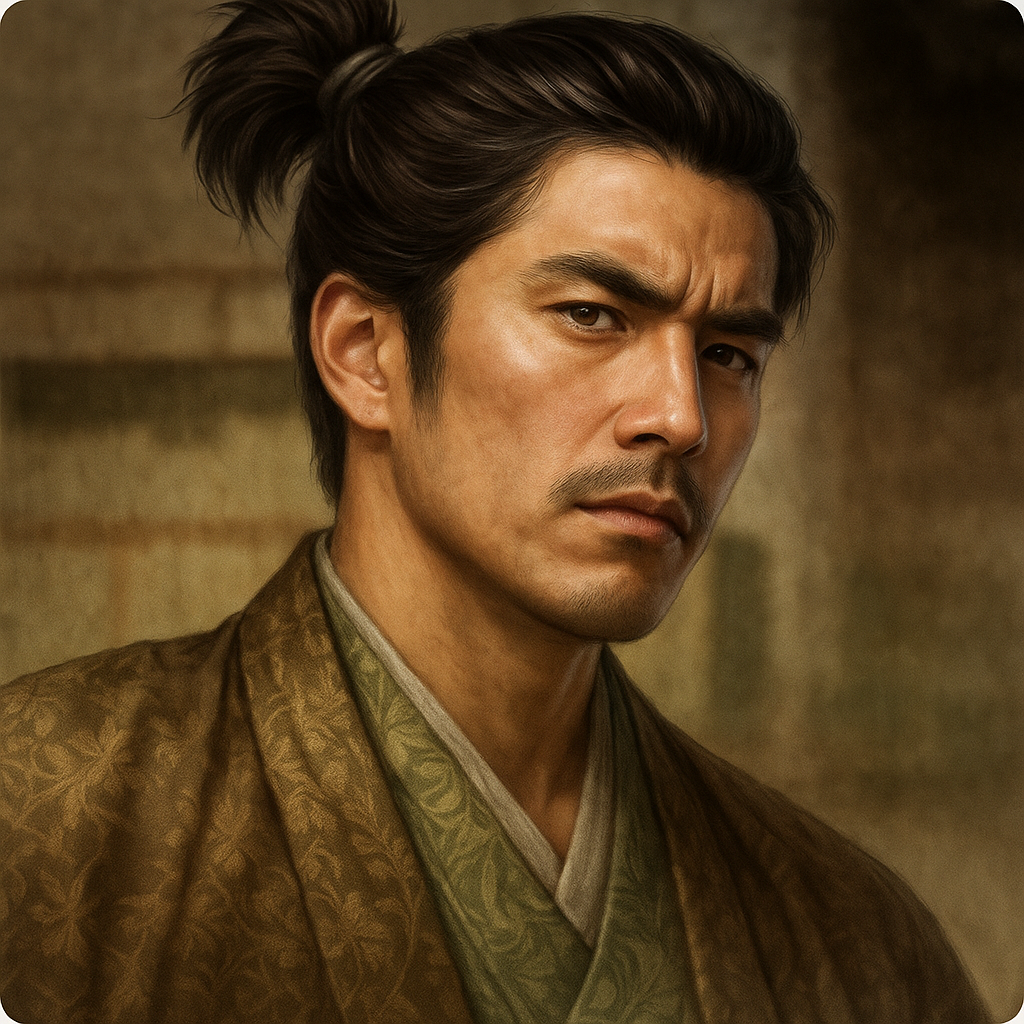
戦国武将 伊賀久隆の実像:備前における興亡
序章:伊賀久隆とは
本報告書は、戦国時代に備前国(現在の岡山県南東部)を舞台に活動した武将、伊賀久隆(いがひさたか)の生涯と事績について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その実像に迫ることを目的とする。伊賀久隆は、備前国の有力な国人領主であり、当初は松田氏に、後に宇喜多直家に仕え、津高郡虎倉城を拠点として大きな勢力を築いた人物である 1 。
特筆すべき点として、伊賀久隆はその姓から伊賀国(現在の三重県西部)や、同地で活動した伊賀流忍術との関連を想起させやすい。実際に、一部の調査依頼や資料の問いにおいて「天正伊賀の乱」(伊賀国における織田信長軍と伊賀衆との戦い)と伊賀久隆が結び付けられることがある 2 。しかしながら、史料によれば、彼が活躍したのは備前国であり、備前伊賀氏の出身である 1 。従って、本報告書で詳述する伊賀久隆は、伊賀忍者や「天正伊賀の乱」とは直接的な関係を持たない。この姓の類似性や、彼が「伊賀守」という官位を称していたこと 1 が、後世において混同を生じさせる一因となった可能性も考えられる。本報告書では、この点を明確に区別し、読者の誤解を招かぬよう留意する。
第一章:伊賀久隆の出自と備前伊賀氏
一. 備前伊賀氏の系譜と歴史的背景
伊賀久隆が属した備前伊賀氏は、その起源を鎌倉時代にまで遡るとされる。鎌倉幕府の政所執事を務め、後に「伊賀氏事件」を引き起こしたことで知られる伊賀光宗の子孫の一部が、備前国長田荘の地頭職を得て土着したことが、備前伊賀氏の始まりと伝えられている 1 。伊賀光宗自身は伊豆国を本拠とした御家人であり、その一族がどのような経緯で備前国に定着したのか、詳細な過程は未だ明らかではないものの、この伝承は備前伊賀氏が由緒ある家柄であったことを示唆している。
戦国時代に至るまでの備前伊賀氏の具体的な動向については、残念ながら史料に乏しい。しかし、一時期「式部氏」と名乗っていたが、戦国期には再び「伊賀氏」を称するようになったと記録されている 2 。武家が姓を変更する事例は戦国時代において珍しいことではなく、主君からの下賜、婚姻関係、あるいは任官など、様々な理由が考えられる。「式部」という名称は朝廷の官職である式部省を想起させ、何らかの公的な役職やそれに関連する人物との繋がりがあった可能性も推測されるが、現存する資料からはその具体的な背景を詳らかにすることはできない。伊賀氏への復姓は、祖先伝来の由緒ある姓を重視したか、あるいは当時の政治的状況の変化に対応した結果であったのかもしれない。この姓の変遷は、備前伊賀氏が固定的な存在ではなく、時代状況に応じて家のあり方を柔軟に変化させてきた可能性を示している。伊賀久隆の父は伊賀勝隆であったとされる 1 。
表1:備前伊賀氏 関連年表
|
年代 |
出来事 |
関連人物 |
典拠 |
|
鎌倉時代中期 |
伊賀氏事件 |
伊賀光宗 |
1 |
|
鎌倉時代 |
伊賀光宗の子孫が備前国長田荘の地頭となる(推定) |
|
1 |
|
不明 |
一時「式部氏」を名乗る |
備前伊賀氏 |
2 |
|
戦国時代 |
「伊賀氏」に復姓 |
備前伊賀氏 |
2 |
|
天文13年 (1544) |
伊賀久隆、清水寺本堂を再建(史料初見) |
伊賀久隆 |
1 |
二. 伊賀久隆の登場と初期の動向
伊賀久隆の名が歴史の表舞台に具体的に現れるのは、天文13年(1544年)のことである。この年、彼は清水寺(所在地は備前国内と推測されるが詳細は不明)の本堂再建を行ったと記録されている 1 。この事実は、久隆がこの時点で既に家督を継承し、地域社会において相応の財力と影響力を行使しうる立場にあったことを示している。中世から戦国時代にかけて、寺社の造営や修復への寄進は、武士にとって自身の権威と信仰心を示す重要な行為であった。この頃、伊賀久隆は松田元輝の麾下にあったと考えられている 1 。
第二章:戦国武将としての伊賀久隆
一. 勢力基盤と活動
伊賀久隆は、備前国津高郡に位置する虎倉城(現在の岡山県岡山市北区から加賀郡吉備中央町にかけての地域に比定される)を本拠地として、戦国武将としての活動を展開した 2 。虎倉城の具体的な構造や地理的条件に関する詳細な情報は現存史料からは得られないものの、彼の勢力圏の中心であったことは間違いない。
永禄11年(1568年)、宇喜多直家に加勢して旧主である松田氏を攻略した後、久隆の勢力は大きく伸張する。津高郡北部をはじめ、上房郡南部、さらには真島郡南部にまでその支配領域を広げ、その所領は推定で15万石にも及んだとされている 2 。この「推定15万石」という石高は、戦国時代の国人領主としては破格の規模であり、宇喜多家中においても彼が屈指の実力者であったことを物語っている。ただし、この数値はあくまで「推定」であり、その算出根拠については慎重な検討が求められる。仮にこの石高が実態に近いものであったとすれば、伊賀久隆は単なる一武将というよりも、方面軍を指揮する司令官クラスの重臣であった可能性も考えられる。そして、この強大な勢力こそが、後に主君である宇喜多直家の警戒心を招き、彼の悲劇的な最期に繋がる遠因となった可能性も否定できない。
表2:伊賀久隆 略歴
|
項目 |
内容 |
典拠 |
|
生年 |
不詳 |
1 |
|
没年 |
天正9年(1581年)4月 (異説あり、下記参照) |
1 |
|
時代 |
戦国時代 - 安土桃山時代 |
1 |
|
官位 |
伊賀守、左衛門尉 |
1 |
|
主君 |
松田元輝 → 宇喜多直家 |
1 |
|
氏族 |
備前伊賀氏 |
1 |
|
父 |
伊賀勝隆 |
1 |
|
妻 |
宇喜多直家の妹 |
1 |
|
子 |
家久、久道 |
1 |
|
拠点 |
備前国津高郡虎倉城 |
2 |
|
推定石高 |
15万石 |
2 |
二. 主要な合戦と政治的立場
伊賀久隆の武将としての生涯は、備前国における勢力争いと密接に関わっている。彼の政治的立場は、主君の変遷や周辺大名との力関係の変化に応じて、巧みに、あるいは必然的に変容していった。
松田氏との関係と離反
伊賀久隆は当初、備前国の有力国人であった松田元輝に仕えていた 1 。しかし、永禄11年(1568年)7月5日、新興勢力である宇喜多直家の調略に応じ、松田氏に反旗を翻す。久隆は金川城の道林寺丸に伏兵を潜ませて攻撃を仕掛け、この戦いで当主・松田元輝は討死し、金川松田氏は滅亡に至ったと『備前軍記』には記されている 3 。この記述において、調略の主体が「宇喜多秀家」とされている箇所があるが 3 、永禄11年当時、宇喜多直家の嫡男である秀家はまだ誕生していないか、ごく幼少であった(秀家は元亀3年・1572年生 5 )。従って、これは年代的に父である宇喜多直家の誤記である可能性が極めて高い。伊賀久隆の松田氏からの離反は、単に主君を乗り換えたという個人的な行動に留まらず、備前国内の勢力図を大きく塗り替える画期的な出来事の一部であった。宇喜多直家が備前国統一を進める過程において、久隆のような有力な在地領主を味方に引き入れる、あるいは寝返らせる工作は常套手段であった。久隆のこの行動は、滅びゆく勢力に見切りをつけ、新たな覇者に与することで自らの生き残りと勢力拡大を図るという、戦国武将の現実的な判断と、宇喜多直家の巧みな謀略が交差した結果と解釈できよう。
宇喜多直家への臣従とその影響
松田氏滅亡後、伊賀久隆は宇喜多直家の麾下に入り、その妹を妻として迎えた 1 。これにより、久隆は宇喜多氏と姻戚関係を結ぶこととなり、家中における地位を一層強固なものにしたと考えられる。直家の家臣として、前述の通り広大な所領を安堵され、宇喜多家の勢力拡大に貢献した。
毛利氏との戦いと共闘
伊賀久隆の対毛利氏との関係は、主君・宇喜多直家の外交戦略の転換を如実に反映している。天正2年(1574年)2月、宇喜多氏が織田信長と同盟し、毛利輝元と敵対していた時期には、上房郡竹庄から備前へ侵攻してきた毛利勢を虎倉城西麓で迎え撃ち、激戦の末にこれを撃退している 2 。これは、久隆が宇喜多軍の有力武将として、対毛利戦線で重要な役割を担っていたことを示している。
しかし、その後、宇喜多直家が織田方から離反し毛利氏に与すると、伊賀久隆の立場も一変する。天正6年(1578年)、久隆は毛利氏による播州上月城攻めに宇喜多軍の一翼として出陣している 2 。このように、ある時は毛利氏と干戈を交え、ある時はその指揮下で戦うという状況は、久隆個人の意思というよりも、主家である宇喜多氏の外交方針に忠実に従った結果であった。これは、戦国時代の家臣が、主家の存亡を賭けた外交戦略に大きくその運命を左右されたことを示す典型的な事例と言えるだろう。
三. 宇喜多家中における役割と評価
伊賀久隆は、推定15万石という破格の領地を支配し、主君・宇喜多直家の妹婿という立場にあったことから、宇喜多家中において重臣中の重臣とも言うべき地位を占めていたことは疑いない。軍事面においては、対松田氏戦での決定的な役割や、対毛利氏戦での活躍が記録されており、武勇にも優れた人物であったことが窺える。
官位としては伊賀守、左衛門尉を称した 1 。当時の武将が称する受領名の一つである「伊賀守」は、奇しくも彼の姓と同じであり、これが後世における伊賀国との混同を招く一因となった可能性も考えられる。宇喜多直家自身も和泉守を称した時期があり 6 、このような官位の受領は、武将が自らの権威を高めるための一つの手段であった。
第三章:伊賀久隆の最期とその影響
一. 宇喜多直家による謀殺の経緯
伊賀久隆の栄華は、しかし、突如として終焉を迎える。天正6年(1578年)の播州上月城攻めに出陣した後、主君である宇喜多直家によって毒を盛られ、本拠地の虎倉城へ逃げ帰ったものの、まもなく死去したと伝えられている 2 。この主君による謀殺という悲劇的な最期は、戦国時代の非情さ、とりわけ「梟雄」とも評される宇喜多直家の冷徹な一面を象徴する出来事として語られている。
久隆の没年については、史料によって記述に差異が見られる。ある資料では天正9年(1581年)4月とされている 1 。一方で、播州上月城攻め(天正6年)の直後に毒殺されたとする記述 2 は、天正6年(1578年)中、もしくは翌年始めの死没を示唆する。ここで重要なのは、宇喜多直家自身が天正9年(1581年)2月に病没しているという史実である。もし伊賀久隆の死が 1 の記述通り天正9年4月であったとすれば、それは直家の死後の出来事となり、「直家に毒を盛られた」という 2 、 2 の記述とは明確な矛盾が生じる。この点を考慮すると、直家存命中の出来事として記述されている天正6年(1578年)説の方が、状況的な整合性は高いと言えるかもしれない。ただし、 1 の情報の典拠が不明であるため、断定は困難である。この没年の矛盾は、伊賀久隆に関する研究における重要な論点の一つである。
表3:伊賀久隆 没年に関する諸説
|
史料/情報源 |
没年 |
死因 |
関連する出来事・背景 |
|
1 |
天正9年(1581年)4月 |
記載なし |
宇喜多直家は天正9年2月没。この説では直家による毒殺は時期的に困難。 |
|
2 |
天正6年(1578年)の播州上月城攻め後、まもなく |
宇喜多直家による毒殺 |
天正6年(1578年)の上月城攻めに出陣後、直家に毒を盛られ虎倉城へ逃げ帰り死去。直家存命中の出来事として整合。 |
二. 伊賀久隆の死が周辺勢力に与えた影響
伊賀久隆ほどの有力な重臣が、主君によって非業の死を遂げたという事実は、宇喜多家中に少なからぬ動揺を与えたであろう。特に他の有力家臣たちにとっては、宇喜多直家の冷酷さと、自らの将来に対する不安を抱かせるに十分な事件であったと推測される。また、久隆が支配していた広大な所領がその後どのように処遇されたのか、宇喜多家の権力構造にどのような変化が生じたのかについても、詳細な記録は残されていないものの、何らかの再編が行われたことは想像に難くない。
三. 子・伊賀家久の動向と備前伊賀氏のその後
伊賀久隆の死後、その子である伊賀家久は、父の仇を討ち、伊賀氏の勢力を保持すべく、虎倉城に籠城して宇喜多直家との対決姿勢を示した 2 。しかし、家久の妻の父であり、宇喜多氏の重臣でもあった明石景親の説得を受け、最終的には開城し、毛利氏を頼って落ち延びたとされる 2 。明石景親による説得という事実は、宇喜多家中の複雑な人間関係や、全面的な武力衝突を回避しようとする動きが存在したことを示唆している。また、家久が毛利氏を頼ったという行動は、当時の宇喜多氏と毛利氏の関係性(表向きは同盟下にあったものの、内部には依然として緊張関係が存在した可能性)を反映しているのかもしれない。
なお、伊賀家久については、久隆の実子ではなく、久隆の弟の子であったという説も伝えられている 2 。これが事実であれば、伊賀氏の家督相続の経緯が単純ではなかった可能性も考えられる。その後の備前伊賀氏の具体的な動向については、提供された資料からは詳らかではない。一部に、家久の娘が井原氏に嫁いだことを示す断片的な記述が見られるが 2 、これが備前伊賀氏本流のその後を物語るものか否かは不明である。
第四章:伊賀久隆に関する考察
一. 伊賀久隆の人物像と歴史的評価
伊賀久隆は、松田氏から宇喜多氏へと主君を巧みに乗り換え、ついには主君・宇喜多直家の妹を娶り、推定15万石とも称される広大な所領を手中に収めるなど、戦国武将としての時流を読む鋭敏な感覚と、巧みな処世術を兼ね備えた人物であったと評価できる。彼の行動は、激動の時代を生き抜くための現実的な選択であったと言えよう。
しかしながら、その強大過ぎる勢力が、結果として主君・宇喜多直家の猜疑心を招き、謀殺されるという結末は、戦国時代の武将が常に直面していた栄枯盛衰の理と、主従関係の非情さを如実に物語っている。また、毛利勢を撃退したとされる逸話 2 からは、単なる知謀の士ではなく、武勇にも優れた側面を持っていたことが窺える。
二. 関連資料における記述の検討と課題
伊賀久隆に関する史料は、総じて限定的であり、特に一次史料の不足は否めない。本報告書で参照した 2 、 2 、 3 といった記述の多くは、『備前軍記』などの後世に編纂された軍記物からの引用である可能性が考えられ、その記述の史実性については慎重な検討を要する。
特に、没年に関する天正6年(1578年)説と天正9年(1581年)説の矛盾は、今後の研究による解明が待たれる大きな課題である。また、「推定15万石」とされる所領の具体的な根拠や、その支配体制の実態についても、詳細な史料が不足しており、今後の研究の進展に期待が寄せられる。
三. 伊賀国及び伊賀忍者との関連性の再確認と明確化
本報告書において繰り返し強調してきた通り、備前国を拠点とした武将・伊賀久隆と、伊賀国(現在の三重県西部)を本拠地とする伊賀流忍者や、同地で発生した天正伊賀の乱とは、直接的な関係は認められない。
「伊賀守」という官位や「伊賀」という姓が、後世の研究や大衆的な伝承の中で、伊賀忍者や伊賀国のイメージと結びつき、混同を生じさせる要因となった可能性は否定できない。実際に、一部の資料調査の設問において「天正伊賀の乱 "伊賀久隆"」といった形で両者が関連付けられている例が見られることは 2 、この混同が実際に存在することを示している。「伊賀」という言葉が持つ、忍者の里や神秘性といった強いイメージに引かれ、関連付けようとする心理が働いた可能性も考慮すべきであろう。歴史研究においては、このような言葉のイメージや先入観に惑わされることなく、あくまで史料に基づいて客観的に事実を認定する厳密な姿勢が求められる。
終章:まとめ
伊賀久隆は、備前国における戦国時代の動乱期に、その巧みな政治手腕と武力を駆使して、一時は広大な勢力を築き上げた重要な地域領主であった。彼の生涯は、宇喜多直家の台頭と備前国平定という、より大きな歴史の潮流の中で展開し、最終的にはその主君・直家の手によって滅ぼされるという、戦国武将の典型的な盛衰の軌跡を辿ったと言える。
伊賀久隆に関する研究は、史料的な制約から未だ不明な点も多く残されている。しかし、彼が備前地域の戦国史を理解する上で欠くことのできない人物の一人であることは間違いない。本報告書で明らかにしたように、伊賀国や伊賀忍者との明確な区別を念頭に置いた上で、今後の更なる史料の発見と、より深い研究の進展が期待される。彼の生涯を丹念に追うことは、戦国という時代の複雑な様相と、そこに生きた武将たちの実像を明らかにする上で、重要な意義を持つであろう。
引用文献
- 伊賀久隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E4%B9%85%E9%9A%86
- 伊賀氏の居城 虎倉城 - 吉備の国探訪 https://www.kibi-guide.jp/okayama/kokura1.htm
- 松田氏の足跡をたどる2 https://www.yomimonoya.com/kaidou/okayama/matuda02.html
- 戦国武将官位総覧 http://kitabatake.world.coocan.jp/sengokukani1.html
- 宇喜多秀家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%A7%80%E5%AE%B6
- 宇喜多直家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6