加来統直
豊前国の国人。大友氏の家臣として島津勢と戦い、大畑城を拠点に活躍。豊臣秀吉の九州平定後、黒田官兵衛の政策に反発し豊前国人一揆に加担。敗走中に討たれた悲運の武将。
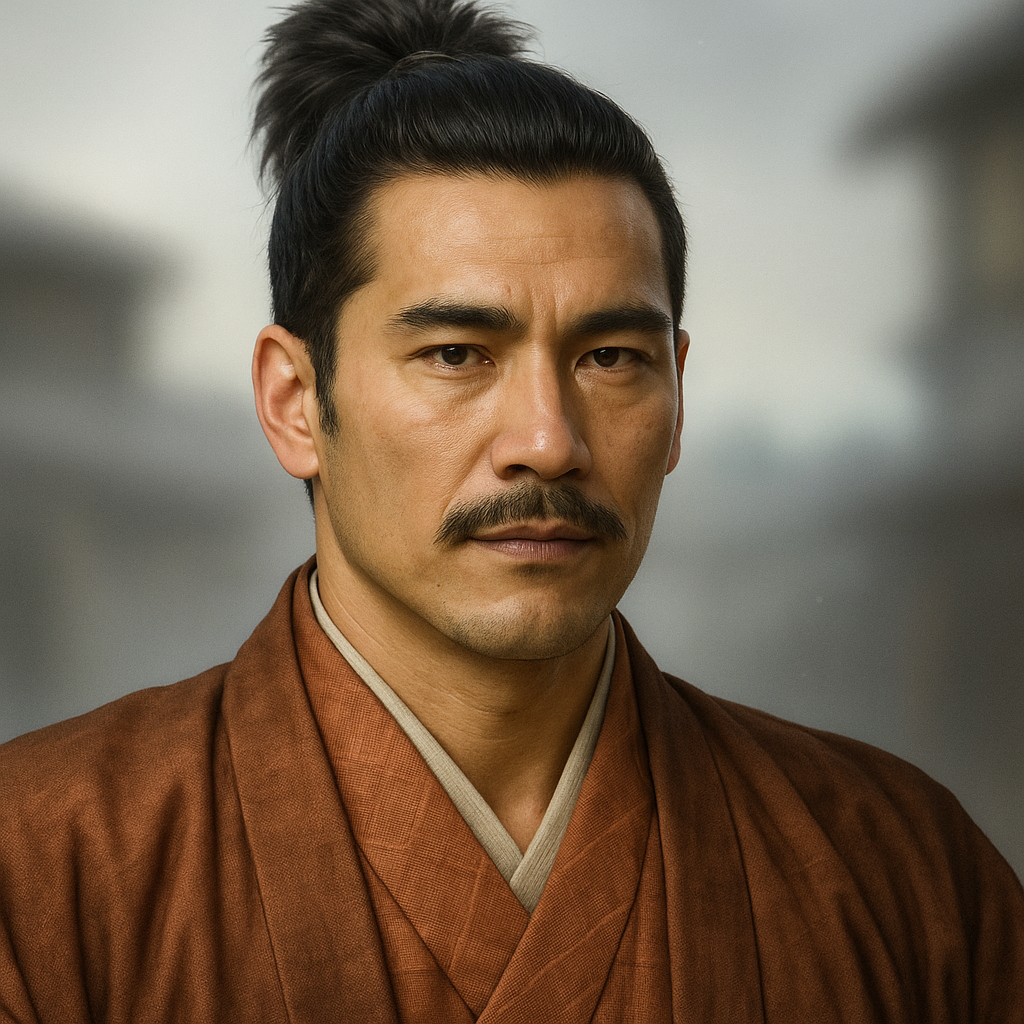
豊前国人 加来統直 ― 大友、黒田、時代の奔流に消えた豪族の生涯
序章:戦国期豊前の地政学的状況
日本の戦国時代の終焉期、九州北東部に位置する豊前国は、歴史の大きな転換点を迎えていた。本報告の主題である加来統直(かき むねなお)の生涯を深く理解するためには、まず彼が生きたこの土地の地政学的な特質を把握する必要がある。豊前国は、西に中国地方を望み、南は豊後国に接する地理的条件から、周防の大内氏、豊後の大友氏、そして後には安芸の毛利氏や薩摩の島津氏といった巨大勢力の利害が複雑に絡み合い、衝突する戦略的要衝であった 1 。この絶え間ない外部勢力からの圧力は、豊前の在地領主である「国人衆(こくじんしゅう)」の行動原理を規定し、彼らの存亡に直結する重要な要素となっていた。
豊前国内には、鎌倉時代に地頭職を得て以来、土着化した国人衆が数多く割拠していた。その中でも筆頭格と目されるのが、下野国(現在の栃木県)から源頼朝の命により下向した宇都宮信房を祖とする豊前宇都宮氏、通称「城井氏(きいし)」である 4 。城井氏は豊前北部に広大な勢力圏を築き、野仲(のなか)氏、佐田(さだ)氏、友枝(ともえだ)氏など多くの庶流を分出させ、一大同族連合体を形成していた 3 。加来統直が率いる加来氏もまた、この複雑な国人社会の一員として、時には豊後の大友氏に、またある時には周防の大内氏に属するなど、情勢に応じて巧みに立ち回りながら、自立と存続を模索していた一族であった 12 。彼らの動向は、単独の意思決定によるものではなく、常に上位権力との関係性の中で規定される、極めて流動的かつ危ういものであった。
第一部:加来氏の淵源と大畑城
第一章:加来一族のルーツを探る
加来統直の人物像に迫るにあたり、彼が背負っていた一族の歴史的背景を明らかにすることは不可欠である。加来氏の出自は、豊前という土地に深く根ざしながらも、その源流は豊後国に求められる。
大神氏の末裔という伝承
各種系図や伝承によれば、加来(賀来)氏は古代豊後の有力豪族であった大神(おおが)氏の系譜を引くとされている 13 。大神氏は、大和国三輪山の大神神社(おおみわじんじゃ)を祖とする神裔伝説を持ち、豊後国において強大な勢力を誇った一族である 13 。その中でも、源平合戦期に豊後武士団を率いて活躍した緒方三郎惟栄(おがた さぶろう これよし)は特に名高い 15 。加来氏の直接の祖は、この緒方惟栄の弟とされる惟興(これおき)に比定する説が有力である 13 。惟興は、豊後国大分郡にあった賀来荘(かくのしょう)の地名を姓とし、「賀来惟興」と称したのが賀来(加来)氏の始まりと推定されている 16 。この豊後賀来氏から分かれ、豊前国下毛郡(しもげぐん)に移住したのが、加来統直に繋がる豊前加来氏であった 13 。
「賀来」から「加来」へ
加来氏の姓の表記には、「賀来」と「加来」の二種類が見られる。史料を分析すると、豊後国では「賀来」、豊前国では「加来」の字を用いる家が多いという傾向が指摘されている 13 。これは単なる表記の揺れに留まらず、より深い意味を持つ可能性がある。豊前の地に根を下ろした一族が、本家筋である豊後の賀来氏とは異なる在地領主としてのアイデンティティを確立しようとする意識の表れであったとも考えられる。事実、加来統直の居城である大畑城の所在地は、現在の大分県中津市「加来」という地名として残っており、この一族がその土地に深く根を下ろしていたことの何よりの証左と言えよう 19 。
豊前宇都宮氏との関係
豊前国において、加来氏は単独で存在していたわけではない。豊前で最大の勢力を誇った宇都宮氏(城井氏)の被官、すなわち家臣団の一員として組み込まれていた時期があったと考えられている 13 。一方で、一族の結束を固めるための婚姻政策も積極的に行われていた。『大神姓系譜』によれば、加来統直の室(正室)は、豊後の賀来氏から嫁いだと記されており 13 、豊前の在地領主としての立場を固めつつも、豊後の本家筋との血縁関係を維持することで、一族の権威とネットワークを保持しようとしていたことが窺える。
この事実は、加来氏が「豊前」と「豊後」という二重のアイデンティティを持つ存在であったことを示唆している。彼らは豊前の国人として在地社会に溶け込み、宇都宮氏のような地域の大勢力との水平的な関係を築く一方で、豊後の大神氏・賀来氏という由緒ある出自を背景とした垂直的な権威も保持し続けていた。この二重性は、戦国の国人領主が、複雑な政治状況の中で自らの家を存続させるために駆使した、巧みで現実的な生存戦略の現れであったと言えるだろう。
第二章:本拠・大畑城
加来統直の生涯における主要な舞台となったのが、本拠地である大畑城(おおはたじょう)である。この城の立地と歴史は、加来氏の性格を物語る上で重要な要素となる。
立地と構造
大畑城は、現在の大分県中津市加来に位置する、典型的な中世の平山城である 19 。豊前平野を流れる駅館川(やっかんがわ)に近い微高地に築かれており、眼下に広がる平野部を一望できる、軍事・経済上の戦略的拠点であった 23 。城跡は現在、七社宮(しちしゃぐう)という神社の境内となっており、往時を偲ばせる明確な曲輪(くるわ)や堀切(ほりきり)といった遺構は多くは残存していない 12 。しかし、周囲より一段高いその地形は、まさしく城郭が存在したことを雄弁に物語っている 24 。
築城と歴史
城の起源に関する伝承は、加来氏の出自と密接に関連している。『日本歴史地名大系』などに引かれる「賀来系図」によれば、大畑城は元暦元年(1185年)頃、緒方三郎惟栄が平家の九州再上陸を阻止するために築いた「豊前五城」の一つとされている 21 。この伝承が事実であれば、大畑城は加来氏の豊前における歴史の始まりそのものと深く結びついていることになる。戦国時代を通じて、大畑城は加来氏代々の居城として機能し、加来統直の代には、南から迫る島津氏の軍勢や、後に豊前の新たな支配者となる黒田氏との激しい攻防の舞台となった 20 。
第二部:大友家臣としての加来統直
加来統直の生涯において、最も彼の立場を明確に示すのが、豊後の戦国大名・大友氏の家臣としての活動である。彼の武功や、他の在地領主との複雑な関係性は、大友氏の盛衰と分かちがたく結びついていた。
第一章:大友氏麾下での活躍
主君からの偏諱
加来統直の諱(いみな)である「統」の字は、当時の主君であった大友氏第22代当主・大友義統(おおとも よしむね)から与えられた一字(偏諱・へんき)と考えるのが最も妥当である 27 。戦国時代において、主君が家臣に自らの名の一字を与えることは、その忠誠と能力を認め、一門に準ずる特別な存在として遇する証であった。この事実は、統直が単なる従属的な国人ではなく、大友氏から直接認知され、信頼された立場にあったことを示す有力な証拠と言える。
島津勢との戦いと感状
統直の武将としての能力を示す具体的な記録として、島津氏との戦闘が挙げられる。天正十年(1582年)、耳川の戦いでの勝利以降、破竹の勢いで北上を続ける島津軍に対し、統直は大畑城を拠点に迎え撃ち、これに勝利したと伝えられる 15 。この戦功により、主君・大友義統から感状(かんじょう)、すなわち感謝状・表彰状を授与されたという記録が『賀来氏関係年表』に残されている 15 。これは、統直が大友家への忠誠を具体的な武功で示し、それが主君に高く評価されたことを物語るエピソードである。ただし、この感状の現物そのものは現存が確認されておらず、その存在は年表などの二次史料に依拠するものである点には留意が必要である 31 。
第二章:在地領主間の抗争 ― 野仲氏との関係
加来統直の動向を追う上で、同じく豊前の有力国人であった野仲氏との関係は非常に重要であるが、史料間には一見矛盾する記述が存在する。
史料間の矛盾①:抗争と共闘
統直と野仲氏の関係については、史料によって「抗争」と「共闘」という正反対の状況が記録されている。
- 抗争の記録 :ある史料によれば、天正七年(1579年)、野仲氏が大畑城に攻め寄せ、加来氏は大友氏からの援助を受けてこれを撃退したとされる 28 。これは、大友氏の支配に反発する野仲氏と、大友方としてこれを迎え撃つ加来氏という、典型的な主従関係に基づく対立構造を示している。
- 共闘の記録 :一方で、『賀来氏関係年表』には、そのわずか3年後の天正十年(1582年)、島津氏との戦いにおいて、加来統直は「野中重兼」なる人物と共に戦い、勝利を収めたと記されている 27 。
史料間の矛盾②:「野仲鎮兼」と「野中重兼」
この矛盾を解く鍵となるのが、史料に登場する「野仲鎮兼(のなか しげかね)」と「野中重兼(のなか しげかね)」という二つの名前である。野仲氏は豊前宇都宮氏の庶流であり 7 、当主であった鎮兼の「鎮」の字は、大友義鎮(宗麟)から与えられた偏諱である 5 。一方で、『両豊記』などの軍記物では、同じ人物を指して「野中重兼」と表記する例が見られる 37 。多くの研究では両者を同一人物と見なしているが、名前の変遷があったのか、あるいは史料が書き写される過程で誤記が生じたのか、断定には至っていない。
これらの史料間の矛盾は、一見すると不可解であるが、当時の九州全体の情勢を考慮に入れることで、合理的な説明が可能となる。天正六年(1578年)の耳川の戦いで大友氏が島津氏に歴史的な大敗を喫すると、その権威は大きく揺らぎ、支配下の国人衆の離反が相次いだ 8 。天正七年(1579年)の野仲氏の蜂起は、まさにこの権力の空白に乗じた動きであり、この時点では加来氏は大友方として野仲氏と戦ったのであろう 28 。しかし、その後、島津氏の脅威が豊前国にまで直接及ぶようになると、大友氏にとっての最優先課題は、国人衆の統制から対島津防衛へと移行する。そのため、大友氏は内輪の対立を一時的に棚上げさせ、加来氏や野仲氏といった在地領主たちに「共同戦線」を張るよう命じた可能性が極めて高い。
このことから、加来統直と野仲氏の関係は、単なる個人的なライバル関係ではなく、彼らの上位権力である大友氏の対外戦略によって大きく左右される、従属的なものであったことがわかる。これは、戦国期の国人領主が、自らの意思決定においていかに上位権力の影響を強く受けていたかを示す好例である。彼らの行動原理を理解するためには、局地的な関係性だけでなく、九州全体を覆う広域の政治・軍事状況を常に視野に入れる必要がある。
第三部:豊前国人一揆と加来氏の滅亡
大友氏の家臣として活動してきた加来統直の運命は、豊臣秀吉による九州平定と、それに続く黒田官兵衛の豊前入部によって、劇的な転回点を迎える。旧来の秩序が崩壊し、新たな権力が到来したとき、統直は一族の存亡を賭けた最後の戦いに身を投じることとなった。
第一章:黒田官兵衛の豊前入部と国人一揆の勃発
新秩序への反発
天正十五年(1587年)、豊臣秀吉の九州平定が完了すると、その軍功により、豊前国のうち六郡が黒田官兵衛(孝高)に与えられた 41 。官兵衛はただちに入国すると、太閤検地と呼ばれる新たな土地調査を実施した。これは、国人衆が先祖代々受け継いできた所領の所有権を一度豊臣政権に返上させ、新たな知行として再分配(知行割)するという、中央集権的な政策であった 43 。これにより、これまで半独立的な領主として君臨してきた国人衆は、実質的に黒田氏の家臣へと組み込まれることになり、その広範な支配権は大きく損なわれた 43 。この急進的な新秩序への強い反発が、豊前国人一揆の根本的な原因であった。
加来統直の決断
同年10月、豊前国人の盟主である宇都宮鎮房が、この新政策に反旗を翻して蜂起すると、加来統直もこれに呼応し、一揆に加担した 27 。この決断の背景には、大友家臣として長年培ってきた地位や所領を失うことへの強い危機感と、旧来の秩序と誇りを守ろうとする国人としての意地があったと考えられる。かつての主君・大友氏が島津氏に敗れ、秀吉に救援を求めた結果、かえって自らの領国を削られていくという皮肉な状況も、統直のような旧大友方国人の不満を増幅させた一因であろう。彼にとって、黒田氏への抵抗は、時代の大きな流れに抗う最後の選択であった。
第二章:大畑城の攻防と落城
加来統直が一揆に加わったことで、彼の居城・大畑城は、豊前国人一揆における重要な拠点の一つとなった。そして、一揆の鎮圧を目指す豊臣方の総攻撃を受けることになる。
黒田・吉川連合軍の攻撃
一揆鎮圧のため、新領主である黒田官兵衛・長政父子の軍勢に加え、毛利輝元の叔父であり、毛利家の重鎮であった吉川元春の軍勢(あるいはその一族が率いる軍)も動員されたという記録がある 20 。これは、豊臣政権が一揆を単なる黒田家の内政問題としてではなく、西国大名を動員してでも断固として鎮圧すべき、中央政権に対する重大な反乱と認識していたことを示している。大畑城は、この強力な連合軍による攻撃を受け、一揆の最終局面で陥落した 20 。
落城時期の考証
大畑城の具体的な落城時期については、史料によって記述が異なっており、慎重な検討を要する。主要な説は以下の通りである。
- 天正十五年(1587年)十二月説 :中津市の公式サイトや史跡案内板など、現代に編纂された資料に散見される 20 。
- 天正十六年(1588年)三月説 :江戸時代中期に成立した軍記物『両豊記』に「天正十六年三月廿四日大畑城陥落加来統直討ち死」と日付まで明記されている 48 。また、賀来氏の年譜など他の史料も天正十六年説を支持している 14 。
これらの相違点を整理するため、以下の表を作成した。
|
史料名 |
成立年代(推定) |
記録された落城時期 |
攻撃軍 |
記録された加来統直の最期 |
典拠 |
|
『両豊記』 |
江戸時代中期 |
天正十六年三月二十四日 |
(黒田軍) |
討ち死 |
48 |
|
『賀来氏関係年表』 |
- |
天正十六年 |
黒田氏 |
討ち死 |
27 |
|
中津市作成資料等 |
現代 |
天正十五年十二月 |
黒田・吉川両軍 |
敗走後、秣氏により討たれる |
20 |
|
郷土史研究サイト等 |
現代 |
天正十五年 |
黒田氏家臣・栗山大膳 |
豊後へ脱出を図るも秣氏に討たれる |
12 |
『両豊記』のような比較的同時代に近い軍記史料が具体的な日付を記していることから、天正十六年三月説は信憑性が高いと考えられる。一方で、後世の編纂物では、一揆全体の期間(天正十五年十月〜)の中で、他の城の落城時期と混同されたり、簡略化されたりした結果、天正十五年十二月という記述が生まれた可能性も否定できない。
第三章:加来統直、最期の謎
大畑城の落城時期と同様に、加来統直の最期についても、史料によって二つの異なる物語が伝えられている。これは、歴史がどのように記録され、記憶されるかという問題を考える上で非常に興味深い点である。
討死説と敗走説
- 討死説 :『両豊記』や賀来氏の年表は、統直が城の陥落時に城内で奮戦の末、討死したと記している 14 。これは、武将としての名誉を重んじた、軍記物によく見られる比較的定型的な記述である。
- 敗走・被殺害説 :一方、中津市の史跡案内や現地の郷土史料には、より具体的で悲劇的な伝承が記録されている。それによれば、統直は落城後に旧主である大友氏を頼って豊後へ敗走する途中、黒田方に寝返った在地土豪の秣(まくさ)氏によって討ち取られたという 12 。
秣氏の動向
この敗走説の鍵を握るのが秣氏である。秣氏はもともと宇都宮氏の一族(深水氏の庶流)で、長岩城の野仲氏に属していた国人であった 24 。しかし、黒田氏の豊前入部という新たな権力構造の出現に対し、彼らは旧来の主家(野仲氏)を見限り、いち早く黒田方に帰順した 24 。彼らが、かつての同盟者であった加来統直を討ち取ったのは、新領主である黒田氏への忠誠を具体的な「手柄」として示すための、冷徹な政治的判断であった可能性が高い 5 。これは、時代の転換期における在地社会の厳しい生存競争と、旧来の秩序や人間関係が崩壊していく様を象徴する出来事であった。
「加来どんの墓」の伝承
この敗走・被殺害説を裏付ける可能性のある物証として、中津市三光上秣の山中に、地元で「加来どんの墓」と呼ばれる一基の墓が伝わっている 41 。この墓の存在は、統直が城で華々しく討死したのではなく、落ち延びる中で非業の死を遂げたという、より生々しい記憶が地域に根付いていることを示している。
加来統直の最期を巡る二つの説は、単なる事実関係の相違に留まらない。討死説が、勝者である黒田氏の視点も含まれる「公式の歴史」に近い性格を持つのに対し、敗走・被殺害説は、秣氏という具体的な加害者の名や「加来どんの墓」という物証を伴う、敗者の地元で語り継がれた「地域の記憶」としての性格が強い。この二つの物語の相克は、歴史がどのように記録され、記憶され、そして変容していくのかという、歴史学の根源的な問いを我々に投げかける。
終章:加来統直が残した遺産
加来統直の滅亡は、盟主であった宇都宮鎮房の謀殺と並び、豊前国における中世的な国人領主の時代の完全な終焉を告げる、象徴的な出来事であった。これにより、在地領主が割拠する分権的な社会は終わりを告げ、豊前は黒田氏という近世大名の強固な支配体制下に組み込まれていくことになる。
加来統直は、織田信長や豊臣秀吉のような、歴史の表舞台で活躍した全国的な知名度を持つ武将ではない。しかし、彼の生涯は、中央の巨大な権力(織豊政権)が地方の旧来の秩序を塗り替えていく過程で、数多の在地領主が経験したであろう葛藤、抵抗、そして悲劇的な末路を凝縮している。大友氏の家臣として武功を挙げ、主君から信頼されながらも、時代の奔流には抗えず、最後はかつての同盟者の裏切りによって命を落とす。その生涯を詳細に追跡することは、戦国時代の終焉を、天下人の視点からではなく、翻弄され消えていった地方豪族の視点から立体的に理解するための、貴重な事例研究となる。
彼の名は、大畑城跡や「加来」という地名、そして山中にひっそりと佇む「加来どんの墓」といった形で、今なお故郷の地にその痕跡を留めている 41 。それは、時代の波に呑まれながらも、確かにその地で生きた一人の武将の記憶が、公式の歴史書とは異なる形で、地域の人々によって語り継がれていることの証なのである。
引用文献
- 野仲氏(のなかうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%8E%E4%BB%B2%E6%B0%8F-1389186
- 大内氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%B0%8F
- 豊前国戦国事典 - 版元ドットコム九州 https://kyu.hanmoto.com/bd/isbn/9784866560403/
- 31. 特別な名前 / 読みは同じで字を変える|加来各論 / Conclusion 結論 - note https://note.com/wisdom_freeride/n/nf439c1c5c6ec
- 豊臣秀吉の軍師として戦国の時代を生き、その天下統一を助けた黒田官兵衛孝高。 https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/document/doc_02.pdf
- 宇都宮氏の歴史 戦国のムラ城井谷 - 築上町 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s047/010/110/020/070/1.pdf
- 野中親孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E4%B8%AD%E8%A6%AA%E5%AD%9D
- 豊前長岩城 http://oshiro-tabi-nikki.com/nagaiwa.htm
- 城井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%BA%95%E6%B0%8F
- 【紀井一族の繁衍(はんえん)】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht040220
- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F
- 豊前 大畑城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/buzen/oohata-jyo/
- わが家の歴史を調べる(賀来、加来氏を例にして)会 http://kaku-net.jp/kakufacebook.pdf
- 賀来氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%80%E6%9D%A5%E6%B0%8F
- 賀来(加来)氏の研究 http://kaku-net.jp/kakusinokenkyuu.pdf
- 故郷忘じがたく候 http://tokyo-sansenkai.net/sp/zuisou/201310gatsu.html
- 賀来(加来)姓のホームページ http://kaku-net.jp/kakuh/kigen.htm
- 【踏査】姓と家紋・加来 | 地方史愛好家 ab.nan27 https://ameblo.jp/nihonsi-2012/entry-12835427048.html
- 中津城 犬丸城 大畑城 高森城 高田城 闇無浜神社 加茂神社 龍神社 - 大分の山・登山記 http://ooitanoyama.in.coocan.jp/sub3690.html
- 大畑城跡 - 中津耶馬渓観光協会 https://nakatsuyaba.com/?introduce=oohata
- 大畑城(大分県中津市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/s/8911
- 福岡県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_fukuoka.html
- 豊前国のお城一覧-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/buzen/
- 八並城 秣城 深水城 田島崎城 北平城 大畑城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/ooita/nakatusi02.htm
- 大畑城(大分県中津市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/8911
- 大畑城跡(おおはたじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E7%95%91%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3103579
- 賀来氏の起源と江戸初期までのまとめ http://kaku-net.jp/kakuh/nenpyou.pdf
- 豊前:大畑城址 | 九州の観光情報サイト:Kyusyu.sky.net https://kyusyu-sky-net.com/castle/castle_5_oita/post_1070/
- 吉弘嘉兵衛統幸について - 別府市 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=60
- 都 甲 谷 の 歴 史 - − 六郷満山と吉弘氏 - 豊後高田市 https://www.city.bungotakada.oita.jp/uploaded/attachment/4882.pdf
- 戦国期大友氏の軍事編成について : 「同心」感状 の分析を通じて - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/223197996.pdf
- 大友氏家臣団についての一考察 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7174450/0809_p059.pdf
- 大友吉統書状について - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/kiyo/27/kiyo0027-02.pdf
- 大友氏家臣団についての一考察 : 加判衆考 察の問題点 https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00010680/shigaku_15_akutagawa.pdf
- 的発展の後、義鑑・義鎮・義統三代に到って急激に上昇し、かつ、急速に衰微してゆくのである。私がここで述べようとする http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4794
- 【野仲鎮兼の独立】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041300
- 野中鎮兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E4%B8%AD%E9%8E%AE%E5%85%BC
- ぶらりくり -由布院・中津・別府編 - note https://note.com/imaginary_organ/n/nff354db73d7d
- 田島崎城跡(たしまざきじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E5%B3%B6%E5%B4%8E%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3103529
- 長岩城(中津市・旧耶馬溪町) | おすすめスポット - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/523258/
- 新発見!織豊系の陣!戦国の戦いを生々しく蘇らせる三保山城(大分県) - 城びと https://shirobito.jp/article/1681
- 知られざる福岡藩270年 第三回 黒田官兵衛と、ライバルたち|グラフふくおか(2013 冬号) https://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2013winter/walk/
- 豊前国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86
- ゆかりの人からの一言 - 中島家の歴史 http://www.nakashimarekishi.com/item/item06.html
- 中津城の歴史観光と見どころ - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/kyusyu/nakatsu/nakatsu.html
- 黒田官兵衛と九州|九州の旅 九州観光情報サイト - 九州旅ネット https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/connection/?mode=detail&id=14
- 【豊前の国一揆】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht050270
- 両豊記(豊前豊後について明和6年 1771 年に記された文書)第 18 ... http://kaku-net.jp/kakuh/buzeniki.pdf
- 豊前 秣城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/buzen/makusa-jyo/
- 【城跡シリーズ】ジモプチトリップvol.110 三光の町を見守る 秣(まくさ)城跡 【中津市】 - ジモッシュ https://zimosh.com/yosaroh20211003/