北里政義
北里政義は肥後の国衆。阿蘇氏に仕えつつ大友氏とも関係を持ち、島津氏侵攻で降伏。子の重義と対立するも、一族は加藤氏に仕え、惣庄屋として存続した。
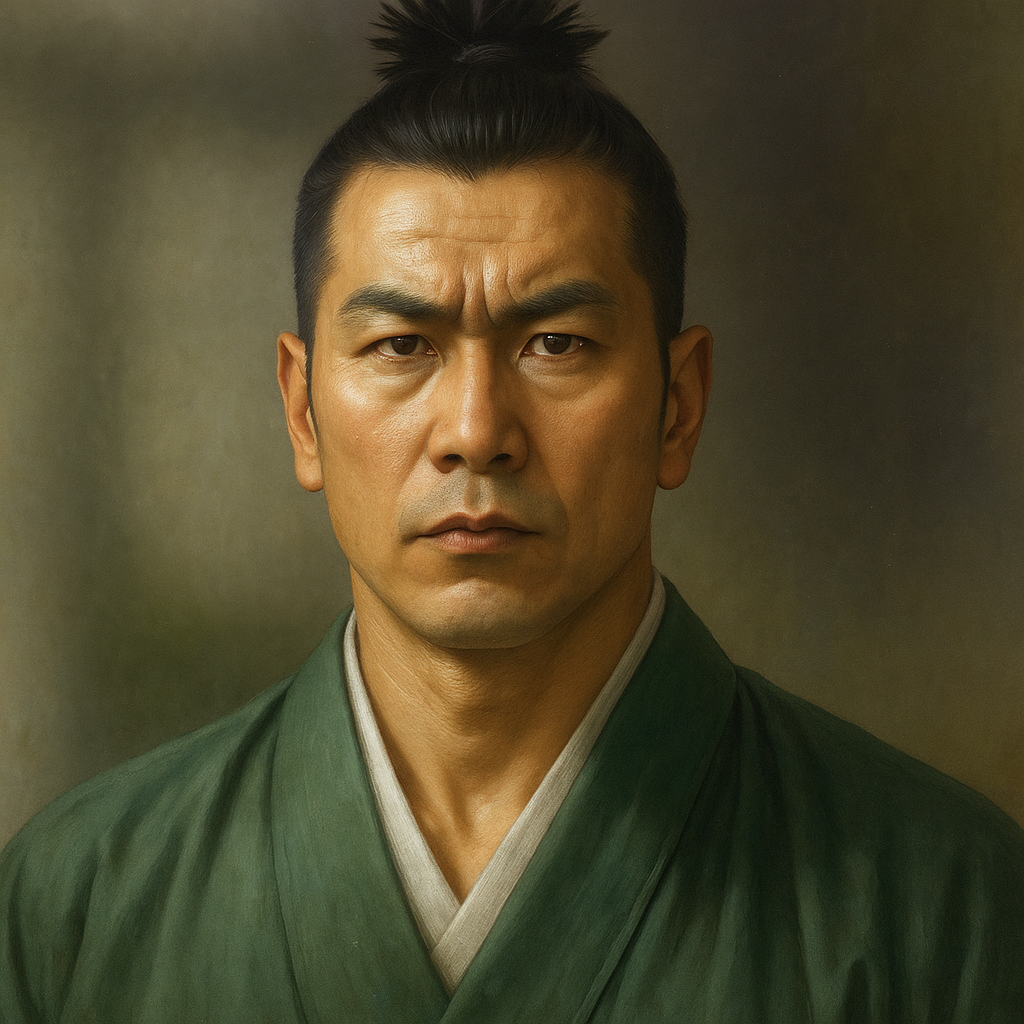
肥後の国衆・北里政義の生涯 ― 徹底調査報告
序章:戦国肥後、国衆・北里政義の実像を求めて
本報告書は、日本の戦国時代、肥後国阿蘇郡を本拠とした国衆(在地領主)である北里政義の生涯について、現存する断片的な史料を博捜・整理し、その人物像と歴史的役割を再構築することを目的とする。彼の人生は、阿蘇、大友、島津という三大勢力が鼎立する九州の激動期において、地方の小領主がいかにして一族の存続を図ったかを示す貴重な事例である。その行動原理を歴史的文脈の中に位置づけることで、これまであまり光の当てられてこなかった一武将の実像に迫る。
北里政義に関する記録は、その出自から主家の変遷、そして豊臣政権下での動向に至るまで、複数の史書や家伝に散見されるものの、断片的であり、特に後の加藤家への仕官については情報が錯綜している。本報告書では、これらの情報を丹念に比較検討し、複数の可能性を提示することで、より精緻な歴史像の構築を目指す。
なお、本報告書の主題である北里氏の居城は、肥後国(現・熊本県)阿蘇郡小国町に存在した「石櫃城(いしびつじょう)」である 1 。これは、しばしば真田氏との関連で知られる上野国(現・群馬県)の「岩櫃城(いわびつじょう)」とは全く異なる城郭である点を、冒頭で明確にしておきたい 2 。この混同を避けることは、北里政義の活動を正確に理解する上での第一歩となる。
第一章:北里氏の淵源と肥後国小国郷における勢力基盤
第一節:源姓綿貫氏から北里氏へ ― 一族のルーツと土着
北里氏の出自は、清和源氏の一流である大和源氏の源頼親に遡ると称されている 6 。『肥後人名辞書』や『肥後古城考』といった後世の編纂物によれば、その歴史は鎌倉時代、寿永年間(1182年-1184年)に、頼親の子孫とされる綿貫次郎左衛門妙義(あるいは信義とも伝わる)が、鎌倉より肥後国阿蘇郡小国郷に下向し、永住したことに始まるとされる 1 。
当初は「綿貫」姓を名乗っていたが、数代を経て、その本拠地である「北里」の地名を姓として名乗るようになった 7 。これにより、一族は名実ともに在地領主としての性格を強めていった。清和源氏という権威ある出自を称し、根拠地の名を姓とすることは、在地での支配の正当性を内外に示すための戦略であったと考えられる。これは、中央から下向した武士が地方に土着し、国衆として自らの勢力を確立していく過程の典型例と言える。南北朝時代には、北里氏は桜尾城を拠点とし、肥後国の有力大名である阿蘇氏に仕える地侍として、その歴史を刻み始めた 6 。
第二節:石櫃城の築城と国境の守り手
北里氏が戦国時代の肥後において確固たる地位を築く上で、その拠点となったのが石櫃城である。この城は、北里政義の父にあたる北里大蔵大輔永義が、主君である阿蘇大宮司家の阿蘇惟豊に仕えていた天文年間(1532年-1555年)に築城したと伝わる 1 。
城の所在地は、現在の熊本県阿蘇郡小国町北里にある囲(かこい)集落の背後に連なる山とされ、築城の際に石でできた櫃(ひつ)が出土したことから「石櫃城」と名付けられたという伝承が残っている 1 。
この城の地政学的な重要性は極めて高い。肥後国、豊後国、そして豊前国という三国が境を接する国境地帯に位置しており、特に東に隣接する豊後国の強大な戦国大名・大友氏に対する、阿蘇氏の最前線防衛拠点としての役割を担っていた 1 。北里氏は、この戦略的要衝を守ることで、阿蘇家の家臣団の中で重要な地位を占めていたと推察される。
第二章:三大勢力の狭間で揺れる阿蘇家臣
戦国時代の北里政義は、主家である阿蘇氏、隣国の大友氏、そして九州統一を目指す島津氏という三大勢力の狭間で、一族の存亡をかけた困難な舵取りを迫られた。彼の動向を理解するため、まずは関連する人物と勢力の相関関係を以下に示す。
【表1:北里政義関連人物・勢力相関図】
|
人物・勢力 |
北里政義との関係 |
概要 |
|
北里政義 |
- |
本報告書の主題。肥後国衆、石櫃城主。 |
|
北里永義 |
父 |
石櫃城を築城。阿蘇家臣。 |
|
北里重義 |
子 |
親大友派。父・政義と対立。 |
|
北里左馬亮 |
子(異説あり) |
後に加藤清正に仕官したとされる人物。 |
|
阿蘇惟将 |
主君 |
戦国時代の阿蘇大宮司。島津氏の侵攻により勢力を失う。 |
|
大友義鎮(宗麟)・義統 |
同盟・従属先 |
豊後の大名。北里氏と親交を結び、庇護。 |
|
島津義久・義弘 |
敵対→降伏先 |
薩摩の大名。九州統一を目指し肥後に侵攻。 |
|
加藤清正 |
後の主君 |
豊臣政権下で肥後北半国の領主となる。 |
第一節:主家・阿蘇氏と大友氏との二重属人的関係
北里政義は、父・永義の代から続く阿蘇神社の神領を治める大宮司・阿蘇氏の家臣であった 9 。阿蘇氏は肥後国の中央部から北部にかけて広大な領地を有し、南の島津氏や東の大友氏と対抗する一大勢力であった 9 。
しかし同時に、北里氏はその地理的条件から、国境を接する豊後の大友氏とも深い関係を築いていた。史料には、北里氏が戦国時代を通じて大友氏に属していたとの記述が見られる 6 。政義自身も大友家と親交を結び、その命に応じて豊前へ出陣したと伝えられている 1 。
このような「両属」ともいえる関係は、単なる日和見主義ではなく、国境地帯に生きる国衆の巧みな生存戦略であったと解釈すべきである。一方の勢力にのみ与することは、もう一方からの侵攻リスクを常に抱えることを意味する。主家である阿蘇氏と大友氏が協調関係にある間は問題ないが、両者が対立した際には極めて難しい立場に置かれることになる。この複雑な関係性が、後の政義の苦渋の決断へと繋がっていく。
第二節:島津氏の肥後侵攻と政義の決断
天正年間に入ると、九州の勢力図は大きく変動する。天正9年(1581年)に肥後南部の相良氏が島津氏に降伏し、さらに天正13年(1585年)には阿蘇氏を軍事的に支えてきた宿老・甲斐宗運が死去すると、九州統一を目指す島津氏の脅威は、阿蘇氏の領国に直接及ぶこととなった 10 。
島津軍は圧倒的な軍事力で肥後へ侵攻し、阿蘇氏の諸城は次々と陥落。主家は事実上、崩壊状態に陥った 10 。この抗いがたい情勢の中、多くの肥後国衆がそうであったように、北里政義もまた、一族と領民を守るために島津軍に降伏するという現実的な選択を下した 10 。これは主君への裏切りと見なされうる行為であるが、主家が領国を維持する能力を失った状況下では、在地領主としての責務を果たすための唯一の道であったとも言える。
第三章:一族を分かつ忠義 ― 親子相克の真相
第一節:親大友派の子・重義との対立
父・政義が下した島津への降伏という決断は、一族内に深刻な亀裂を生んだ。政義の子である北里重義は、父の方針に従わず、あくまで旧来からの主筋である大友氏への忠節を貫く道を選んだのである 11 。この対立は、単なる親子の意見の相違ではなく、島津につくか、大友につくかという、一族の存亡をかけた路線の対立であった。
この父子の相克を伝える貴重な史料として、熊本大学が所蔵する『下城遺跡調査報告書』に引用されている「北里文書」の記述がある。それによると、天正13年(1585年)、父・政義が「阿蘇氏にそむいた」(文脈上、島津方に与したことを指す)にもかかわらず、子の重義は曽祖父の代から続く大友氏への「忠意の覚悟」を貫いたと記されている 11 。これにより、北里家は父と子で異なる陣営に属するという異常事態に陥った。
第二節:大友義統からの感状が示すもの
この複雑な状況をさらに興味深いものにしているのが、豊後の大名・大友義統が発給した一通の感状である。この感状は、北里政義と重義の父子両名の「忠貞を賞せ」る内容となっている 11 。島津に降伏したはずの父・政義をも含めて賞賛している点は、極めて示唆に富む。
これは、大友氏の高度な外交戦略の現れと見ることができる。大友義統は、政義の降伏が本意ではなく、圧倒的な軍事的圧力によるやむを得ない選択であったと理解していた可能性が高い。その上で、子の重義の変わらぬ忠誠を公に称賛しつつ、父の政義をも「本来は味方である」というメッセージを送ることで、北里一族が完全に敵対勢力となることを防ぎ、将来的な離反や寝返りを促す布石を打ったと考えられる。敵の内部に楔を打ち込み、分断と懐柔を同時に行うこの手法は、戦国大名ならではの巧みな外交術である。
一方で、このような大国の思惑に翻弄され、父と子が袂を分かたざるを得なかった北里氏の苦悩は、戦国時代に生きた国衆たちが置かれた過酷な現実を浮き彫りにしている。
第四章:豊臣政権下の北里氏と加藤清正への仕官
第一節:九州平定と肥後国衆一揆の嵐
天正15年(1587年)、豊臣秀吉の九州平定軍が南下すると、九州の政治情勢は再び激変する。破竹の勢いであった島津氏も秀吉の前に降伏し、肥後は豊臣政権の支配下に入った。この過程で、北里氏の居城であった石櫃城も「落去」したと記録されている 1 。
秀吉は肥後の新領主として佐々成政を任命したが、成政が旧来の国衆の既得権益を無視して強引な検地を断行したため、国衆たちが一斉に蜂起した。これが「肥後国衆一揆」である 12 。この大規模な反乱は、秀吉が派遣した圧倒的な討伐軍によって鎮圧され、隈部氏をはじめとする多くの肥後国衆が滅亡、あるいは所領を失った 13 。北里氏がこの一揆に直接関与したか否かを示す明確な史料は見当たらないが、肥後の国衆としてこの未曾有の動乱と無関係であったとは考え難い。
第二節:加藤家臣としての再興 ― 錯綜する記録の分析
一揆鎮圧後、佐々成政はその失政の責任を問われて切腹。肥後北半国には加藤清正が、南半国には小西行長が新たな領主として入国した。この新たな支配者の下で、北里一族が存続の道を探ったことは確かであるが、誰がどのように加藤清正に仕えたかについては、史料によって記述が異なり、錯綜している。
-
説A:政義の子・左馬亮が仕官
『肥後古城考』には、石櫃城落去後、政義の子である「左馬亮(さまのすけ)」という人物が、後に加藤家に仕えたと記されている 1。 -
説B:政義と子が共に仕官
『肥後人名辞書』の系統を引く記述では、父である政義自身が、子と共に加藤清正に仕えたとされている 7。 -
説C:北里惟経が仕官
一方、Wikipediaの「北里氏」の項目や、それを参照したと思われる文献では、安土桃山時代に「北里惟経(これつね)」という人物が250石で加藤清正に召し出され、後の寛永10年(1633年)に小国郷の惣庄屋(そうじょうや)に任命されたとある 6。
これらの情報を整理すると、以下のようになる。
【表2:北里一族の加藤家仕官に関する史料比較】
|
史料/典拠 |
仕官者 |
内容 |
出典 |
|
『肥後古城考』 |
北里左馬亮(政義の子) |
天正15年の落城後、加藤家に仕官。 |
1 |
|
『肥後人名辞書』系 |
北里政義と子 |
政義が子と共に加藤清正に仕官。 |
7 |
|
『姓氏家系大辞典』等 |
北里惟経 |
安土桃山時代に250石で召し出され、寛永10年に惣庄屋となる。 |
6 |
この記録の錯綜は、単なる史料の誤伝や混乱と片付けるべきではない。むしろ、北里一族が時代の大きな転換期において、一族の存続をかけて取った多角的な戦略の結果である可能性が考えられる。肥後国衆一揆の後、旧来の国衆は新領主の下で極めて厳しい立場に置かれた。そこで北里氏は、一族全体が同じ道を歩むのではなく、リスクを分散させる戦略を採ったのではないか。すなわち、一族の一部(政義の子・左馬亮など)は新領主・加藤家の武士として仕官することで武門としての家名を保ち、別の一派(惟経の系統)は在地に残り、惣庄屋という新たな藩体制下の行政職に就くことで地域の支配権を維持する道を選んだ、という仮説が成り立つ。
これは、武士としての道が閉ざされるリスクをヘッジしつつ、在地領主としての家系は確実に存続させるという、したたかな生き残り戦略である。結果として、武士としての北里氏の系譜は歴史の中に埋もれていく一方で、惣庄屋となった系統が近世を通じてその地位を保ち、やがて近代日本を代表する医学者・北里柴三郎を輩出する土壌となった。この視点は、戦国から近世への移行期における国衆の現実的な生き様を浮き彫りにするものである。
終章:武士から惣庄屋へ ― 北里家のその後と歴史的意義
北里政義の生涯は、戦国時代末期の九州という激動の舞台で、小領主がいかにして生き残りを図ったかの縮図であった。主家への忠誠、大勢力への従属、そして一族内の路線対立という幾多の苦悩を経験しながら、彼は時代の変化に必死に対応しようとした。
政義の時代が終わり、加藤、そして細川の治世が始まると、北里氏は武士としてよりも、阿蘇郡小国郷の惣庄屋として地域を治める道を選択し、近世社会に適応していく 6 。北里惟経に始まり、その子孫は「北里伝兵衛」を代々襲名し、惣庄屋職を世襲した 6 。これは、戦国時代の武力による支配者から、近世の藩体制下における行政的支配者へとその役割を変えることで、在地における影響力を保持し続けたことを意味する。
北里政義の時代の苦闘と決断があったからこそ、一族は滅亡の危機を乗り越え、近世における惣庄屋としての北里家が存在し得た。そして、その惣庄屋家の分家から、近代日本の医学の礎を築き、「日本細菌学の父」と称されるに至った北里柴三郎が誕生するのである 6 。
戦国武将・北里政義の生涯は、単なる一地方武将の物語に留まらない。彼の苦闘は、数世紀の時を経て、日本の近代化に大きく貢献する偉人を輩出する遠因となった。彼の人生を追うことは、戦国、近世、近代という時代の大きな連続性の中に、一族の存続をかけた人々の確かな営みを見出すことであり、歴史の深遠さを我々に教えてくれる。
【巻末付録:北里政義の生涯と関連年表】
|
年代(西暦) |
北里政義・北里氏の動向 |
肥後・九州の動向 |
中央の動向 |
|
天文年間 (1532-55) |
父・永義が阿蘇惟豊に仕え、石櫃城を築く 1 。 |
阿蘇氏、大友氏、島津氏などが抗争。 |
|
|
永禄年間 (1558-70) |
政義、阿蘇家臣として活動。大友氏の命で豊前に出陣か 1 。 |
大友宗麟、九州北部で勢力を拡大。 |
|
|
天正9年 (1581) |
|
球磨の相良氏が島津氏に降伏 10 。 |
織田信長による天下統一が進む。 |
|
天正13年 (1585) |
島津軍の侵攻を受け、降伏。子の重義と対立 10 。大友義統より父子宛に感状が届く 11 。 |
島津氏が肥後へ本格侵攻。阿蘇氏の重臣・甲斐宗運が死去し、阿蘇家が劣勢に 10 。 |
豊臣秀吉、関白に就任。 |
|
天正15年 (1587) |
秀吉の九州平定により石櫃城落去 1 。 |
豊臣秀吉が九州平定を完了。佐々成政が肥後国主となるが、肥後国衆一揆が勃発 13 。 |
豊臣秀吉、九州平定を開始。 |
|
天正16年 (1588) |
|
佐々成政が失脚・切腹。加藤清正が肥後北半国、小西行長が南半国の領主となる 15 。 |
豊臣秀吉、刀狩令を発布。 |
|
安土桃山時代 |
子の左馬亮、または一族の惟経が加藤清正に仕官 1 。 |
加藤清正による領国経営が本格化。熊本城の築城が始まる。 |
文禄・慶長の役。 |
|
寛永9年 (1632) |
|
加藤氏が改易。細川忠利が肥後に入国。 |
|
|
寛永10年 (1633) |
北里惟経が小国郷の惣庄屋に任命される 6 。 |
細川藩体制が確立。 |
|
|
嘉永5年 (1853) |
惣庄屋・北里家の分家から北里柴三郎が誕生 17 。 |
|
ペリー来航。 |
引用文献
- 石櫃城跡(いしびつじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E6%AB%83%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3101950
- 岩 櫃 城 周 辺 図 http://iwabitsu-sanadamaru.com/file/iwabitsujoato_pamphlet.pdf
- 岩櫃城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%AB%83%E5%9F%8E
- 国指定史跡「岩櫃城跡」 | スポット一覧 | 心にググっと観光ぐんま https://gunma-kanko.jp/spots/37
- 真田/岩櫃の歴史 | 岩櫃(いわびつ)~大河ドラマ「真田丸」東吾妻町公式ホームページ~ http://iwabitsu-sanadamaru.com/history
- 北里氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%87%8C%E6%B0%8F
- 西行と遊行聖 : 熊本県小国町の西行伝説を中心に https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/97/files/kokugakuinzasshi_116_08_003.pdf
- 北里柴三郎の名字の読みは? - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-30460/
- 浜町史蹟めぐり(19) 御廟(阿蘇惟豊公の事績2) 井上清一 / お知らせ / 山都町郷土史伝承会 https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/ijyuuhp/a0022/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=286&OsNo=248
- 阿蘇氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%B0%8F
- 下城遺跡 I https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/22/22101/16337_1_%E4%B8%8B%E5%9F%8E%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf
- 〜中世肥後の終焉〜 肥後国衆一揆最後の砦⚔️田中城跡|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/nfcdcc25d3007
- No.043 「 肥後国衆一揆(ひごくにしゅういっき) 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/043.html
- No.110 「 清正入国以前の肥後 (肥後国衆一揆) 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/110.html
- 肥後国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86
- 博士について - 北里柴三郎記念館 https://s-kitazato.jp/about/
- 北里柴三郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%87%8C%E6%9F%B4%E4%B8%89%E9%83%8E
- 北里柴三郎の生涯 https://www.kitasato.ac.jp/jp/kinen-shitsu/shibasaburo/lifetime.html