有馬則頼
有馬則頼は播磨出身の武将。父の戦死後、秀吉に仕え中国攻めなどで活躍。茶人として秀吉御伽衆に。関ヶ原で東軍に属し三田藩主となる。
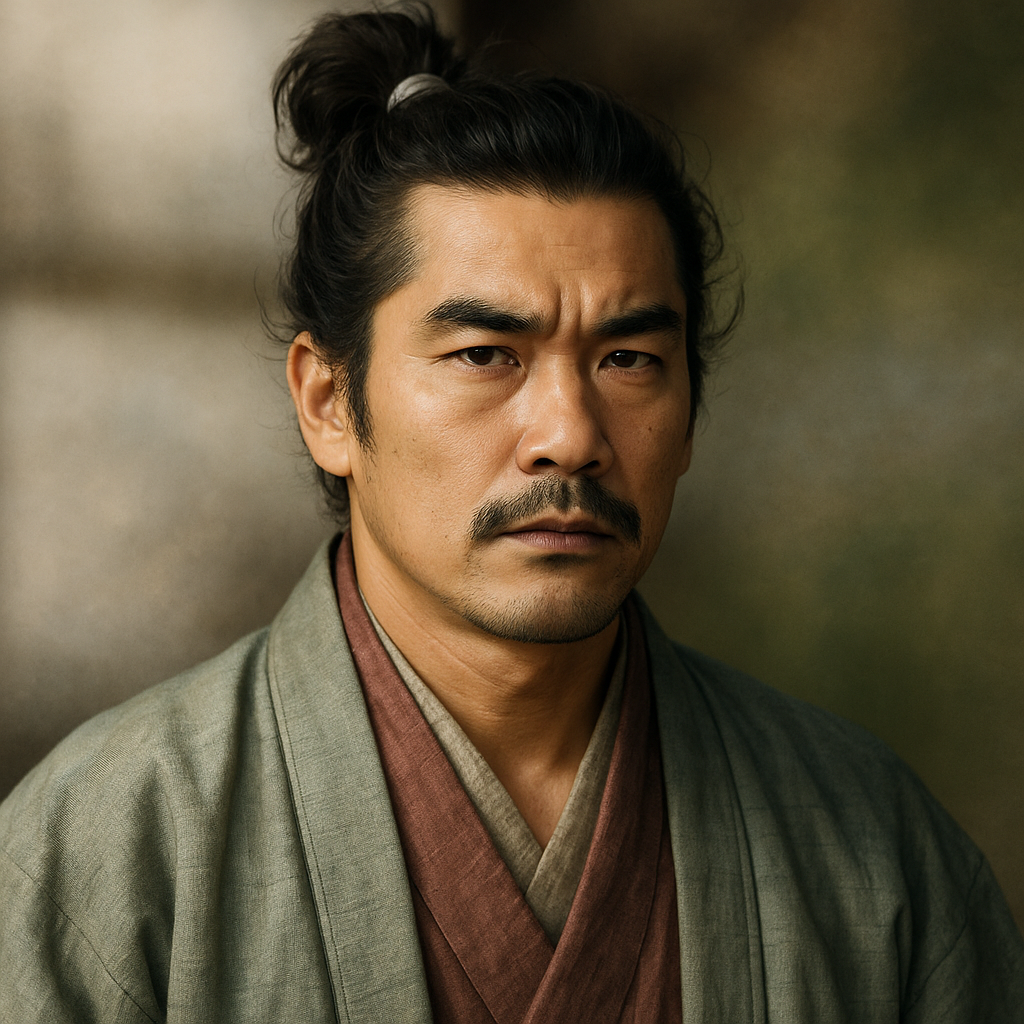
戦国武将 有馬則頼の生涯と事績
序章
本報告書は、戦国時代から安土桃山時代、そして江戸時代初期にかけて活躍した武将、有馬則頼(ありま のりより、天文2年(1533年) – 慶長7年(1602年))に関する詳細な調査結果をまとめたものである。則頼は、播磨国の出身で、赤松氏の庶流である摂津有馬氏にその血統を連ねる 1 。彼は、父の戦死という逆境を乗り越え、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)、次いで徳川家康という当代の覇者に仕え、武功を重ねるとともに、茶人としてもその名を知られた文化人であった。その生涯は、激動の時代を生き抜いた武士の典型的な立身出世の軌跡を辿る一方で、主君への忠誠と自己及び一族の存続を賭けた処世術の複雑な様相を映し出している。本報告書では、則頼が生きた時代の概略を背景としつつ、彼の出自、武将としての事績、文化人としての側面、そして後世に遺した影響について、現存する史料に基づき多角的に考察する。
第一章:生涯
一、出自と家系
生誕と一族の背景
有馬則頼は、天文2年2月23日(グレゴリオ暦1533年3月18日)、播磨国三津田城(満田城とも、現在の兵庫県三木市周辺と推定される)にて誕生した 2 。有馬氏の起源は、村上源氏の流れを汲み、室町時代に播磨守護職を務めた赤松則祐の子、義祐が摂津国有馬郡(現在の兵庫県神戸市北部)を領有し、有馬を名字としたことに始まるとされる 3 。則頼の家系は、この摂津有馬氏の庶流にあたり、播磨国に勢力基盤を持っていた 1 。
父は有馬筑後守重則(ありま ちくごのかみ しげのり)、母は室町幕府の管領家であった細川京兆家の細川澄元(ほそかわ すみもと)の娘である 2 。父重則は、播磨国美嚢郡(現在の兵庫県三木市)に進出し、同族の別所氏や淡河(おうご)氏と勢力を争ったが、戦国の常として、志半ばで戦乱の中に討死したと伝えられている 3 。この父の早すぎる死と、それに続く則頼の不遇な青年期は、彼のその後の処世術や、強力な主君(秀吉、家康)との個人的な結びつきを重視する行動様式を形成する上で、重要な背景となった可能性が考えられる。庇護者を失い、不安定な状況に置かれた経験は、自己の力のみでは生き残りがたい戦国社会の厳しさを則頼に痛感させ、有力な庇護者を希求する動機となったであろう。
父母、兄弟、妻子
有馬則頼の家族構成は以下の通りである。
- 父: 有馬重則 2
- 母: 細川澄元の娘 2
- 兄弟: 『寛政重修諸家譜』によれば、則頼の弟として則次(のりつぐ)、豊長(とよなが)がいたとされる 2 。
- 正室: 振(ふり)。梅窓院(ばいしょういん)と号した。播磨の国衆であった別所志摩守忠治(べっしょ しまのかみ ただはる)の娘である 2 。彼女は天正16年(1588年)に没し、当初は淡河の長松寺に葬られたが、後に則頼の菩提寺となる久留米の梅林寺に改葬された 2 。
- 子女: 正室梅窓院との間には四男五女がいたと伝えられるが、『寛政重修諸家譜』には四男四女が記録されている。それによると、則氏、豊氏、そして四人の女子が梅窓院の子であり、則次、豊長は庶子とされている 2 。
- 長男: 有馬則氏(ありま のりうじ)。通称は四郎次郎。羽柴秀吉の甥である羽柴秀次(後の豊臣秀次)に仕えたが、天正12年(1584年)4月9日、小牧・長久手の戦いに秀次に従って参戦した際、徳川軍の迎撃を受けて若くして戦死した 2 。
- 二男: 有馬豊氏(ありま とようじ)。幼名は万助。父則頼の死後、その遺領を継承し、後に関ヶ原の戦いや大坂の陣の功により筑後国久留米藩21万石の初代藩主となる、有馬家を発展させた重要人物である 2 。
- 三男: 有馬則次(ありま のりつぐ)。通称は九郎次郎。早世したと記録されている 2 。
- 四男: 有馬豊長(ありま とよなが)。江戸幕府に仕え、旗本・旗本寄合席となった 2 。
- 女子: 有馬重頼(ありま しげより)室 2 。
- 女子: 渡瀬繁詮(わたらせ しげあきら、豊臣秀次の家老)正室 2 。
- 女子: 石野氏満(いしの うじみつ)正室 2 。石野氏は赤松氏の庶流であり、この婚姻を通じて有馬家と石野家は姻戚関係を結んだ。この繋がりは後世にも影響し、久留米藩の第6代藩主となる有馬則維(のりふさ)は、この石野氏満の玄孫(孫の孫)にあたる 12 。
- 女子: 中山慶親(なかやま よしちか)室 2 。
幼名、別名、号、官位
則頼は生涯を通じて、いくつかの名や号、官位を称した。
- 幼名: 源次郎(げんじろう) 2 、あるいは九郎三郎(くろうさぶろう) 1 とも伝えられる。
- 別名: 無清(むせい) 2 。また、後に出家して法印となった後は、兵部卿法印(ひょうぶきょうほういん)、刑部卿法印(ぎょうぶきょうほういん)と称した 1 。
- 戒名・法号: 梅林院(ばいりんいん) 2 、または梅林院剣甫宗智(ばいりんいんけんぽそうち) 13 。この法号「梅林院」は、後に久留米藩主有馬家の菩提寺となる梅林寺(福岡県久留米市)の寺号の由来となった 14 。
- 官位: 従四位下・中務少輔、刑部卿に叙任された 2 。
表1:有馬則頼 略年表
|
年代(和暦) |
年齢 |
出来事 |
典拠 |
|
天文2年(1533年) |
1歳 |
2月23日、播磨国三津田城にて誕生 |
2 |
|
永禄年間(1558-70年) |
26-38歳 |
家督を継承。三好長慶、別所長治に従う |
2 |
|
天正8年(1580年) |
48歳 |
羽柴秀吉の中国攻めに際し嚮導役を務め、播磨国淡河3,200石を与えられる |
2 |
|
天正12年(1584年) |
52歳 |
小牧・長久手の戦いで長男・則氏を失う |
2 |
|
時期不詳 |
- |
九州平定、朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に参加 |
2 |
|
時期不詳 |
- |
豊臣氏による伏見城築城に功績。1万5,000石まで加増 |
2 |
|
天正18年(1590年) |
58歳 |
10月4日、有馬温泉における豊臣秀吉主催の茶会に招かれる |
15 |
|
慶長5年(1600年) |
68歳 |
関ヶ原の戦いに東軍として参戦 |
2 |
|
慶長6年(1601年) |
69歳 |
1月18日、戦功により1万石を加増され、摂津国有馬郡三田2万石に転封、三田藩を立藩 |
2 |
|
慶長7年(1602年) |
70歳 |
7月28日、三田にて死去。淡河の天正寺に葬られる(後に久留米梅林寺に改葬) |
2 |
図1:有馬則頼 略家系図
Mermaidによる関係図
二、青年期と初期の動向
有馬則頼の青年期は、父重則の討死という厳しい現実から始まった。一時は僧体となって不遇の時期を過ごしたと記録されている 3 。この経験は、後の則頼が「兵部卿法印」や「刑部卿法印」といった仏教系の法印号を称し、「梅林院」という戒名を持つに至ったこと、さらには茶人としての深い精神性を涵養する上で、何らかの影響を与えた可能性が考えられる。武人としての側面のみならず、内省的、文化的な側面を深める契機となったのかもしれない。
永禄年間(1558年~1570年)に家督を継承した則頼は、当初、播磨国において大きな勢力を有していた三好長慶や、後に織田信長に反旗を翻すことになる東播磨の雄、別所長治に従属した 2 。この時期の則頼の具体的な活動に関する詳細な記録は、提供された資料からは乏しいものの、播磨国内の地域勢力の一武将として、主家の命に従い軍事行動などに参加していたと推察される。
特に、別所長治への従属は、後の則頼の運命を大きく左右する布石となった。羽柴秀吉による播磨攻め、とりわけ三木城攻めの際には、則頼がかつて別所氏の麾下にあった経験が、播磨の地理や諸勢力の動向、さらには別所氏内部の事情に関する貴重な知識を提供することになったのである。この知識と経験が、秀吉の「嚮導役」として効果的に機能し、戦功を挙げることに繋がり、結果として秀吉からの信頼と新たな所領獲得に結びついたと考えられる。初期の従属関係が、後のキャリアにおける重要な転換点において、則頼にとって有利に働いたと言えよう。
第二章:豊臣秀吉への臣従と武功
一、中国攻めにおける役割と淡河城主就任
天正8年(1580年)、織田信長の命を受けた羽柴秀吉が中国地方の毛利氏攻略を開始すると、播磨の地理に明るい有馬則頼は、秀吉軍の嚮導役(道案内役)としてその軍事行動を支援し、戦功を挙げた 2 。則頼の中国攻めにおける嚮導役としての成功は、単に地理的知識に長けていたというだけでなく、播磨の在地勢力との既存の関係性や情報網を巧みに利用した結果である可能性が高い。秀吉にとって、外部から進軍する上で、このような現地の詳細な情報は戦略的に極めて重要であり、「嚮導役」は単なる道案内を超え、情報提供や在地勢力との交渉仲介といった役割も担っていたと考えられる。
この目覚ましい功績により、則頼は秀吉から播磨国淡河(おうご、現在の兵庫県神戸市北区)に3,200石の所領を与えられ、淡河城主となった 2 。淡河城は、三木城攻めの後、城主であった淡河氏が逃亡した後に則頼が入城したとされている 16 。秀吉は則頼を「叔父坊主」という綽名で呼ぶほど気に入っていたと伝えられており 9 、この中国攻めにおける協力関係の構築が、それまで不遇であった有馬氏の家運を一挙に好転させる大きな契機となったのである 11 。淡河城主となったことは、則頼にとって独立した領主としての第一歩であり、その後の有馬家の発展の確固たる基盤となった。
則頼はその後も秀吉に従って功績を重ね、その所領は最終的に1万5,000石まで加増された 2 。しかしながら、淡河城は則頼が関ヶ原の戦功により摂津国三田へ移る慶長6年(1601年)に伴い廃城となっており 16 、彼の拠点としては比較的短期間であった。これは、則頼の活動の中心が、秀吉政権下での中央との結びつきや、さらなる立身出世へと向かっていたことを示唆している。
二、主要な合戦への従軍
有馬則頼は、秀吉配下の武将として、数々の主要な合戦に従軍した。
- 小牧・長久手の戦い(天正12年・1584年): この戦いでは、則頼にとって悲劇的な出来事があった。長男である有馬則氏が、羽柴秀次(後の豊臣秀次)に従って参戦したが、長久手方面での戦闘において徳川軍の迎撃を受け、討死したのである 2 。則頼自身の具体的な戦闘への参加状況や役割についての詳細は、提供された資料からは明らかではない。
- 九州平定(天正15年・1587年頃): 豊臣秀吉による島津氏を中心とした九州の諸大名を制圧した戦役にも、則頼は参加し、功を挙げたとされている 2 。しかし、具体的な部隊編成や個別の戦功に関する詳細な記述は、提供された資料中には見当たらない。
- 文禄・慶長の役(朝鮮出兵、文禄元年~慶長3年・1592年~1598年): 秀吉が大陸進出を目指して行った朝鮮への二度にわたる出兵にも、則頼は参加し、功を挙げたとされる 2 。息子の有馬豊氏は文禄の役において200人の兵を率いて肥前名護屋城(佐賀県唐津市)に参陣した記録がある 11 。則頼自身の具体的な渡海状況、所属部隊、兵力、あるいは戦功に関する詳細な記録は、提供された資料からは明確ではない 17 。彼が秀吉の御伽衆として、前線ではなく名護屋城に在陣し、後方支援や軍議に参与していた可能性も考えられる 2 。
- 伏見城築城: 則頼の功績は軍事面に留まらず、豊臣政権の重要な拠点であった伏見城の築城事業にも貢献した。この功績も、彼の所領が1万5,000石へと加増される一因となったとされている 2 。
有馬則頼のこれらの主要な合戦への参加記録は存在するものの、具体的な戦場での詳細な武功や、彼が直接指揮した部隊に関する情報は、提供された資料群からは限定的である。これは、彼が最前線で勇名を馳せるタイプの武将というよりは、むしろ秀吉の側近としての役割や、後述する御伽衆、茶人としての活動がより記録に残りやすかった可能性を示唆している。小牧・長久手の戦いで長男を失っている事実は、彼が軍事活動から完全に離れていたわけではないことを示しているが、彼の名を際立たせたのは、武勇そのものよりも、むしろ主君への近侍や顧問、文化的な素養、そして知略や人間関係構築能力であったのかもしれない。
三、御伽衆としての則頼と秀吉との逸話
有馬則頼は、武将としての側面だけでなく、茶人としても高い名声を持ち、豊臣秀吉の御伽衆(おとぎしゅう、相伴衆とも呼ばれる)として近侍した 2 。御伽衆とは、大名の側近くに仕え、雑談の相手を務めたり、主君の求めに応じて自身の経験談や古典籍の講釈などを行う役職であり、主君の個人的な相談役や話し相手としての性格が強かった 18 。
秀吉は読み書きが不得手であったと伝えられており、それを補うために耳から学問を吸収する師として、多くの御伽衆を召し抱えていた。則頼もその重要な一員であったのである 18 。則頼は出家して薙髪した後、刑部卿法印と称したが、同じく秀吉の御伽衆を務めた文化人武将である金森長近(法印素玄)や徳永寿昌(式部卿法印)と共に、「三法師」と並び称されたという 2 。
則頼と秀吉の間には、その親密な関係を物語るいくつかの逸話が伝えられている。
- 清洲会議の際の逸話: 本能寺の変後、織田家の後継者問題と遺領配分を決定するために開かれた清洲会議の際、柴田勝家らが秀吉に対して敵対的な動きを見せ、害そうと企んだとされる。その緊迫した状況の中、会議に遅れて到着した則頼は、城門を強引に押し通って秀吉の側に駆けつけ、その護衛にあたった。秀吉はこの則頼の忠義心と機転を高く評価し、以後、則頼を厚遇したと伝えられている 2 。
- 名器下賜の逸話: 秀吉は、則頼の茶人としての才能を愛で、しばしば則頼が大坂に構えていた屋敷の茶席に自ら赴いたという。その際、秀吉は自身が所蔵する名高い茶道具である「附藻茄子茶入(つくもなすちゃいれ)」や、南宋の画僧・牧谿(もっけい)筆と伝えられる貴重な画軸など、様々な名品を則頼に下賜したとされている 2 。
これらの逸話は、則頼が単なる家臣としてではなく、秀吉にとって信頼できる側近であり、文化的なパートナーでもあったことを示している。御伽衆としての則頼の役割は、秀吉の個人的な信頼を得る上で極めて重要であり、これが彼の政治的地位の安定と所領の加増に繋がったと考えられる。また、「三法師」の一人として数えられたことは、彼の武将としてだけでなく、教養人、特に茶人としての評価が当時非常に高かったことを物語っている。
第三章:徳川家康への接近と関ヶ原
一、家康との関係構築とその背景
慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去すると、豊臣政権内では後継者問題や大名間の対立が顕在化し、政情は急速に不安定化していった。このような状況下で、有馬則頼は次男の豊氏と共に、五大老筆頭として大きな影響力を持っていた徳川家康への接近を図った 2 。
則頼と家康の関係は、秀吉の死以前から伏線があったことを示唆する逸話が残されている。
- 家康の江戸帰還取り計らいの逸話: 文禄年間(1592年~1596年)、秀吉が家康を伏見城に留め置き、本拠地である江戸への帰国を許さなかった時期があった。この際、家康からの依頼を受けた則頼が、秀吉との間を取り持ち、家康の江戸帰還を実現させるために奔走したという。この出来事が、則頼と家康が個人的な信頼関係を築く契機になったとされている 2 。秀吉政権下でこのような行動を取ることは大きな危険を伴うものであり、則頼の相当な覚悟と政治的判断があったものと推察される。
- 紅粉屋肩衝茶入贈答の逸話: 『寛政重修諸家譜』によれば、上記の出来事の後、家康が再び上洛した際に、則頼に対して名高い茶道具である「紅粉屋肩衝茶入(べにや かたつき ちゃいれ)」を贈ったと記されている 2 。茶道具の贈答は、単なる物質的な交換を超え、当時の武将間における深い信頼関係や同盟関係を象徴する儀礼的な意味合いを持つことが多く、則頼が茶人であったことも、家康との文化的な接点となり、関係構築に有利に働いた可能性がある。
これらの逸話は、則頼が秀吉存命中から家康と何らかの接点を持ち、一定の信頼を得ていたことを示している。この先見性と高度な政治的バランス感覚が、秀吉死後の激動の政局を乗り切り、徳川政権下でも家の地位を確保する上で決定的な要因となったと言えよう。慶長4年(1599年)には、島津氏に関連する家康の意向を伝える書状の宛先として、則頼の名が見えることから 20 、この頃には既に家康の信頼を得て、重要な連絡役を担っていたことがうかがえる。
秀吉の御伽衆という側近中の側近であった則頼が、同時に家康とも個人的な繋がりを持っていたという事実は、当時の大名間の情報網の複雑さや、必ずしも主君への一元的な忠誠だけではなかった武将たちの現実的な行動様式を物語っている。特に茶の湯の場は、しばしば政治的な情報交換や交渉の場としても機能したため、則頼が茶人であったことは、こうした多角的な関係構築に有利であった可能性が高い。これは、戦国末期から江戸初期にかけての権力移行期において、武将たちが生き残りと家の安泰のために、複数の有力者との関係を維持・構築しようとしていた現実を反映している。
二、関ヶ原の戦いにおける戦功
慶長5年(1600年)9月15日、天下分け目の戦いとされる関ヶ原の戦いにおいて、有馬則頼は子の豊氏と共に東軍(徳川方)に与し、本戦に参戦した 2 。
しかしながら、則頼の具体的な布陣や戦闘行動に関する詳細な記録は、提供された資料からは乏しい 21 。池田輝政の布陣に関する記述として「本戦では桃配山に陣した家康の後方に陣取り、南宮山に拠った毛利軍に備えた」というものがあるが 21 、則頼自身の具体的な配置や役割については明確ではない。
この情報不足は、則頼が大規模な部隊を率いて戦局を直接左右するような役割を担ったのではなく、むしろこれまでの家康との個人的な関係性を踏まえ、家康本隊の周辺や遊軍的な立場で、信頼に基づく配置に就いていた可能性を示唆する。彼の当時の石高(1万5千石)から考えても、大軍を率いる立場ではなかった。戦闘における華々しい武功というよりは、東軍への参加という政治的判断と、これまでの家康との関係性が総合的に評価された結果、戦後の恩賞に繋がったものと考えられる。東軍としての参戦と、その勝利への貢献は疑いのないところである。
三、三田藩の立藩
関ヶ原の戦いにおける東軍勝利への貢献が認められ、有馬則頼は慶長6年(1601年)1月18日、1万石を加増された。そして、有馬氏にとって祖先伝来のゆかりの地である摂津国有馬郡三田(さんだ、現在の兵庫県三田市)において2万石(これまでの1万5千石と合わせてか、純増1万石で合計2万石かは資料により解釈の幅があるが、多くの資料で2万石とされている 2 )を与えられ、三田藩を立藩した 2 。これにより、則頼は三田藩初代藩主となったのである。
この三田2万石への移封は、則頼の摂津有馬氏としての家系の正統性と、徳川家康による論功行賞の巧みな政治的配慮が結びついた結果と言える。有馬氏の故地に封じられたことは、則頼個人にとって大きな名誉であると同時に、有馬家の伝統を再興するという象徴的な意味合いも持っていた。家康にとっては、豊臣恩顧の大名であった則頼に対し、その出自に配慮した恩賞を与えることで、より一層の忠誠心を引き出し、他の豊臣系大名への示威ともなり得た。石高自体は2万石と大大名とは言えないものの、畿内に近い戦略的にも重要な地域に、信頼できる則頼を配置する意図もあったと考えられる。
則頼の石高の変遷を追うと、中国攻めの功で淡河3,200石を得たことに始まり 2 、その後、伏見城築城などの功により1万5,000石まで加増され 2 、関ヶ原の戦功を経て最終的に三田2万石となっている 2 。秀吉政権下で約5倍に増加し、家康政権への移行期にさらに微増したこの石高の推移は、彼がそれぞれの権力者から継続的に評価されていたことを示している。しかし、爆発的な加増ではなかったことは、彼の役割が主に最前線での軍事的なものではなく、主君の側近としての働きや文化的な貢献、そして何よりも時勢に応じた的確な政治判断によるものであったことを裏付けていると言えよう。関ヶ原の論功行賞が、より大きな武功を挙げた武将や、戦略的に重要な大大名に対して大規模な加増・転封が集中したこと 26 、そして則頼の当時の立場や兵力がそれらとは異なっていたことを反映している可能性がある。彼の価値は石高以上に、新政権における安定した地位の確保にあったのかもしれない。
第四章:文化人としての則頼
一、茶人としての活動と交流
有馬則頼は、戦場における武勇や政治的手腕のみならず、当代一流の文化人、特に茶人としてもその名を広く知られていた 2 。彼の茶の湯への深い造詣は、単なる趣味の域を超え、豊臣秀吉や徳川家康といった最高権力者との個人的な信頼関係を構築し、時には政治的な影響力を間接的に行使するための重要な手段となっていた可能性が高い。
則頼は豊臣秀吉の御伽衆として仕える中で、茶を通じて秀吉と深い交流を持った。秀吉自身も則頼の大坂屋敷の茶席にしばしば臨み、名器を下賜されるなど、その寵愛ぶりは特筆に値する 2 。
その代表的な例として、天正18年(1590年)10月4日に摂津国有馬温泉の湯山阿弥陀堂で催された豊臣秀吉主催の茶会への参加が挙げられる 15 。この茶会は、秀吉が小田原の北条氏を平定し、名実ともに関白として天下統一を果たした直後、長期間にわたる戦陣の疲れを癒すために有馬に滞在した際に催されたものであった。秀吉自身も愛用の名茶器「鴫肩衝(しぎかたつき)」をわざわざ持参するなど、並々ならぬ力の入れようであったと記録されている 15 。この格式高い茶会において、則頼は「有馬法印」として、当代随一の茶匠である千利休や、中国地方の雄であった小早川隆景と共に、一番目の客として招かれるという栄誉を得ている 15 。茶堂は千利休が務め、床には虚堂智愚(きどうちぐ)の墨蹟が掛けられ、名物裂で知られる鳴肩衝などが道具として用いられたという 15 。このような場に同席したことは、則頼が当時の茶の湯の世界において非常に高い地位にあったことを示している。また、このような場での交流は、情報収集や人脈形成にも繋がったはずである。
徳川家康からも紅粉屋肩衝茶入を贈られていることからも 2 、茶の湯が家康との関係構築にも一役買っていたことがうかがえる。戦国時代から江戸初期にかけて、茶の湯は武将にとって必須の教養であると同時に、重要な外交・交渉の舞台でもあった。則頼が茶人として高名であったことは、彼の武将としてのキャリアを補強し、円滑な人間関係を通じて政治的な目的を達成する上で有利に働いたと考えられる。
ただし、千利休や古田織部といった他の著名な茶人との具体的な交流の詳細や、有馬温泉以外での茶会への参加記録、あるいは則頼自身が詠んだ和歌や漢詩の作品については、提供された資料からは残念ながら詳細を見出すことが困難であった。
二、信仰と精神性
有馬則頼の人物像を理解する上で、彼の信仰心と精神性も重要な要素である。則頼は武人としての生涯を送る一方で、仏教、特に禅宗に深く帰依していたことがうかがえる。
彼は出家して薙髪した後、兵部卿法印、刑部卿法印といった法印号を称し、梅林院剣甫宗智(ばいりんいんけんぽそうち)という法号(戒名)を持っていた 2 。法印とは、仏教の僧位の一つであり、学識や徳行の高い僧に与えられるものである。則頼がこれを称したことは、彼の仏教への深い関与を示している。
特筆すべきは、京都大学総合博物館に所蔵されている有馬則頼像に寄せられた賛である。この賛は、臨済宗大徳寺派の高僧であり、大徳寺第111世住持を務め、大徳寺山内に三玄院を開いた春屋宗園(しゅんおくそうえん)によって、則頼の死後間もない慶長7年(1602年)10月上旬に書かれたものである 13 。賛には則頼の法名「梅林院殿前刑部法印剣甫宗智之肖像」と明確に記されており、これは則頼が禅宗、とりわけ臨済宗大徳寺派に深く帰依していた可能性が高いことを強く示唆している 13 。春屋宗園のような高名な禅僧が、一武将の死後すぐにその肖像画に賛を寄せるということは、両者の間に単なる形式的な関係を超えた、個人的な親交や、則頼の信仰に対する宗園の深い理解、あるいは師檀関係に近い精神的な繋がりがあったことをうかがわせる。この肖像画と賛は、則頼が武人としての側面だけでなく、内面的な精神性や信仰を重んじる人物であったことを後世に伝える貴重な資料と言える。
そして、この則頼の法号「梅林院」は、後に彼の次男である有馬豊氏が筑後国久留米藩の初代藩主となった際、久留米における有馬家の菩提寺として建立された梅林寺の寺号の由来となった 14 。これは、則頼の信仰心が後世の有馬家においても尊重され、記憶された証左である。
なお、則頼が金森長近、徳永寿昌と共に「三法師」と称された背景や、彼らとの具体的な交流を示す逸話については、提供された資料からは見出すことができなかった。
第五章:晩年と遺産
一、最期と埋葬地
摂津国三田藩の初代藩主となった有馬則頼であったが、その治世は長くは続かなかった。三田藩立藩の翌年である慶長7年7月28日(グレゴリオ暦1602年9月13日)、則頼は居城である三田城において、70年の生涯を閉じた 2 。
則頼の遺体は、当初、彼がかつて城主を務めた播磨国淡河(現在の兵庫県神戸市北区)の天正寺に葬られた 2 。しかし、後に彼の次男であり、関ヶ原の戦いや大坂の陣での功績により筑後国久留米藩21万石の初代藩主となった有馬豊氏によって、その墓は久留米(現在の福岡県久留米市)の梅林寺に改葬された 2 。
この改葬は、単に息子豊氏による父祖への敬意の表明であるに留まらず、より深い意味合いを持っていたと考えられる。新たに久留米に拠点を築き、大藩の藩主となった有馬家にとって、藩祖である則頼の権威と霊的庇護を新しい領地にもたらし、家の正統性と永続性を領内外に示威するという、政治的な意図も含まれていたと推察される。藩祖の墓を新たな本拠地の菩提寺に移すことは、家の歴史と権威を新領地に根付かせ、家臣団や領民に対する求心力を高める効果があったであろう。また、父の霊を丁重に祀ることにより、豊氏自身の統治の正当性を強化する意味合いも込められていたに違いない。
二、菩提寺梅林寺と則頼
筑後国久留米(現在の福岡県久留米市京町)に位置する臨済宗妙心寺派の寺院である梅林寺は、江戸時代を通じて久留米藩主有馬家の菩提寺として栄えた 14 。この寺号「梅林寺」は、有馬則頼の法号「梅林院」に由来するものであり、則頼とこの寺院の深い結びつきを今に伝えている 14 。
梅林寺の境内には、有馬家の歴代藩主やその一族を祀る壮麗な墓所、有馬家霊屋(ありまけたまや)が現存する。そのうち、「有馬家霊屋 五棟」は平成30年(2018年)12月に国の重要文化財に指定されており、江戸初期の大名墓所の様相を伝える貴重な建築群である 28 。この五棟のうち、「梅林院霊屋(納塔廟)」と呼ばれる建物には、藩祖である有馬則頼、その室(梅窓院)、そして則頼の娘の五輪塔が安置されている 28 。霊屋の前に立つ石燈籠の銘文から、この梅林院霊屋は寛永7年(1630年)に建立されたことが判明している 28 。
注目すべきは、この霊屋の建立時期である。則頼が死去したのは慶長7年(1602年)であり、梅林院霊屋が建てられたのはその死後28年も経過した寛永7年(1630年)である。この時期は、次男の有馬豊氏が久留米藩主として入封(元和6年・1620年)してから10年が経過し、藩の統治基盤がある程度固まり、藩体制が安定してきた頃にあたる。このような時期に大規模な霊屋が建立されたことは、豊氏が久留米藩主としての地位を確立し、改めて藩祖である父則頼の権威を顕彰するとともに、有馬家の永続的な繁栄を祈念する一大事業としてこれに取り組んだことを示唆している。
三、子孫と有馬家の展開
有馬則頼の死後、彼が築いた基盤は、その子孫たちによって受け継がれ、有馬家は江戸時代を通じて存続・発展していくことになる。
則頼の遺領である摂津国三田藩2万石は、次男の有馬豊氏が、自身が領していた丹波国福知山藩6万石に加えて継承した 2 。これにより、則頼が開いた三田藩は一時的に廃藩(福知山藩に併合)という形になった 23 。
その有馬豊氏は、その後、慶長19年(1614年)の大坂冬の陣、翌慶長20年(1615年)の大坂夏の陣において徳川方として参戦し、軍功を挙げた。この功績により、元和6年(1620年)、田中吉政の系統が断絶した後の筑後国に転封となり、北筑後21万石を与えられて久留米藩の初代藩主となった 3 。以後、有馬家は外様大名として幕末に至るまで約250年間にわたり久留米藩を治め、則頼はその藩祖として位置づけられている 3 。
一方、則頼の長男であった有馬則氏は、小牧・長久手の戦いで若くして戦死したが、その血筋は途絶えなかった。則氏の娘は叔父である豊氏の養女となり、後に建部光重(たけべ みつしげ)に嫁いだ。そして、この則氏の女系の子孫から、後に紀州徳川家に仕え、8代将軍徳川吉宗の側近として享保の改革期に活躍し、最終的には1万石の大名に取り立てられた有馬氏倫(ありま うじのり)が出ている 6 。氏倫は伊勢国西条藩の初代藩主となり、その後の子孫は下野国吹上藩を立藩するに至った 34 。これは、一度は嫡流から外れたかに見えた血筋が、女系を通じて別の形で再興し、再び大名の列に加わるという、武家の家系としては興味深い展開である。
また、則頼の四男である有馬豊長は、江戸幕府の直臣である旗本となり、旗本寄合席に列した 2 。
このように、有馬則頼の血筋は、21万石の大藩である久留米藩主家として続く本流だけでなく、旗本家や、さらには分家から再び大名に列する家系(有馬氏倫の伊勢西条藩・吹上藩)も輩出しており、彼が戦国乱世を生き抜き築き上げた基盤と、その後の子孫たちの活動が、有馬一族の広範な存続と多岐にわたる発展に大きく寄与したことを示している。
第六章:有馬則頼の人物像と歴史的評価
有馬則頼は、戦国時代から安土桃山時代という激動の時代を生き抜き、一介の地方武士から2万石の大名へと立身した人物である。彼の生涯と事績を振り返ると、多面的な人物像が浮かび上がってくる。
人物像の総括
- 武人としての側面: 父・有馬重則が戦死するという逆境の中で育ちながらも、羽柴秀吉、そして徳川家康という当代の天下人に仕え、中国攻めでの嚮導役、九州平定、朝鮮出兵、関ヶ原の戦いへの参加など、数々の軍役に従事し、戦功を挙げてきた 2 。特に、清洲会議において秀吉を護衛したという逸話は 2 、彼の武人としての勇敢さや忠誠心の一端を示している。
- 文化人としての側面: 則頼は単なる武辺者ではなく、当代一流の文化人、特に高名な茶人であった 2 。豊臣秀吉の御伽衆として近侍し、秀吉自身としばしば茶席を共にするなど、深い文化的素養を有していたことがうかがえる 18 。天正18年(1590年)に有馬温泉で開催された秀吉主催の茶会に、千利休らと共に主要な客として招かれたことは 15 、彼の茶人としての地位の高さを物語っている。また、徳川家康とも茶道具を通じて交流があったことは 2 、文化が武将間のコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしていたことを示している。
- 政治的才覚と処世術: 則頼の生涯は、時勢を読み、巧みに主君を選び、強固な信頼関係を構築することで家を存続させ、さらには発展させた見事な処世術の連続であったと言える。秀吉から「叔父坊主」と綽名されるほどの信頼を得 9 、また家康からはその江戸帰還を助けた返礼として名物茶入を贈られるなど 2 、最高権力者との個人的な結びつきを重視し、それを自身の立身に繋げた。彼の人間関係構築能力と政治感覚の鋭さは、特筆すべきものがある。
- 信仰心: 薙髪して法印を名乗り、「梅林院剣甫宗智」という法号を持っていたこと、そして臨済宗大徳寺派の高僧である春屋宗園と深い交流があったことなどから 13 、禅宗への深い帰依が見て取れる。この精神性が、彼の行動規範や人格形成に少なからぬ影響を与えていた可能性も考えられる。
歴史的評価
有馬則頼は、戦国時代から江戸時代初期にかけての典型的な立身出世を果たした武将の一人として評価することができる。彼の成功は、単に戦場での武勇によるものだけではなく、時勢を的確に読む洞察力、主君との個人的な信頼関係を築き上げるコミュニケーション能力、そして茶の湯に代表される文化的な素養といった、多面的な資質が複合的に作用した結果であると言えよう。
特に重要なのは、彼が筑後国久留米藩主有馬家の藩祖として、その後の有馬家250年にわたる繁栄の礎を築いたという点である 3 。則頼自身は久留米を治めることはなかったものの、彼の子豊氏が久留米藩初代藩主となったことで、則頼の血筋と家名は江戸時代を通じて確固たるものとなった。
ただし、提供された資料からは、則頼が直接統治した淡河や三田における具体的な藩政(検地、寺社政策、民政など)に関する記録は乏しい。また、主要な合戦における詳細な戦功についても限定的である。このため、彼の歴史的評価は、主に豊臣・徳川という二大政権の中枢との関係性や、文化人としての側面からなされることが多い。
有馬則頼の歴史的評価は、彼が直接統治した領地の規模や期間、あるいは戦場での華々しい武功そのものよりも、むしろ豊臣・徳川という二つの巨大権力の中枢と巧みに結びつき、その権力移行期を乗り越えて家名を高め、次代の繁栄への道筋をつけた点に集約されると言える。彼の生涯は、武力だけでなく、知略、人脈、そして文化資本がいかに戦国武将の存続と発展に不可欠であったかを示す好例である。
なお、有馬則頼自身に特化した学術的な研究論文や専門的な伝記に関する情報は、提供された資料からは、彼の子孫である和算家の有馬頼徸に関するもの 36 や、一般的な歴史評価論 38 が散見されるものの、則頼個人を深く掘り下げた専門研究の存在は、今回の調査範囲では確認できなかった。今後の研究による新たな発見が期待される。
終章
有馬則頼の生涯は、天文2年(1533年)の生から慶長7年(1602年)の死に至るまで、まさに戦国乱世の終焉と江戸幕府による泰平の世の黎明期という、日本史における一大転換期と重なっている。播磨の一地方領主の子として生まれ、父の戦死という逆境を経験しながらも、彼は類稀なる政治感覚と文化的素養、そして時勢を読む的確な判断力をもって、この激動の時代を巧みに生き抜いた。
豊臣秀吉の下では、中国攻めの嚮導役としての功績を皮切りに、御伽衆として近侍し、茶人としても重用され、秀吉個人の深い信頼を得るに至った。秀吉の死後は、いち早く徳川家康に接近し、関ヶ原の戦いでは東軍に与して勝利に貢献、その結果として摂津国三田に2万石の所領を得て三田藩を立藩し、大名としての地位を確立した。
則頼の功績は、単に武将としての立身出世に留まらない。彼の子、有馬豊氏は後に筑後国久留米21万石の大封を得て久留米藩初代藩主となり、則頼はその藩祖として、以後約250年にわたり続く久留米有馬家の礎を築いた。また、則頼の法号「梅林院」は、久留米藩の菩提寺である梅林寺の名の由来となるなど、その名は文化的な遺産としても後世に刻まれている。さらに、長男則氏の血筋は女系を通じて有馬氏倫を輩出し、大名家として再興するなど、則頼の血脈は多岐にわたって受け継がれた。
有馬則頼の物語は、個人の能力と時勢への適応が複雑に絡み合う中で、一人の武将がいかにして家名を高め、その遺産を次代へと繋いでいったかを示す、歴史的に貴重な事例である。彼の武人として、文化人として、そして政治家としての多面的な生き様は、戦国武将の多様な生存戦略と、近世大名家成立のダイナミズムを理解する上で、重要な示唆を与えてくれる。彼が遺した有形無形の遺産、すなわち菩提寺、繁栄した家系、そして数々の逸話は、戦国という時代を生きた人々の姿を現代に伝える上で、今後も研究され語り継がれていくべき価値を持つと言えよう。
引用文献
- 有馬則頼はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E9%A0%BC
- 有馬則頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E9%A0%BC
- 有馬家の歴史 https://www.arimakinenkan.or.jp/histories/
- 有馬氏 - 姓氏家系メモ - Miraheze https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F
- 有馬家 http://himuka.blue.coocan.jp/daimyou/arimakurume.htm
- 有馬氏倫 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/arima.html
- 有馬豊氏とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E8%B1%8A%E6%B0%8F
- 有馬則氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E6%B0%8F
- かっぱ通信 (128号)【平成24年11月01日付け】 - 全国法人会総連合 https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/kurume2/files/2019/12/%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1128.pdf
- 有馬豊氏(ありま・とようじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E8%B1%8A%E6%B0%8F-1051460
- 久留米藩・有馬家の名刀 繁慶/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/48782/
- 有馬則維 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E7%B6%AD
- 有馬則頼像 | 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00033867
- [リニューアルオープン記念展]久留米・有馬発見伝 | 展示案内 | 有馬 ... https://arimakinenkan.or.jp/information/detail/29
- 天正十八年十月豊臣秀吉湯山阿弥陀堂茶会について https://monjo.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/164
- 1月 2019 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2019/01/
- 文禄・慶長の役 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9
- 御伽衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%BC%BD%E8%A1%86
- 『カーナビが行く手を邪魔をする』秀吉大明神 - 眠りが改善する丹後の寝具専門店ーふとんのえびすやー https://futon-ebisuya.com/%E3%80%8E%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%93%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%81%8F%E6%89%8B%E3%82%92%E9%82%AA%E9%AD%94%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8F%E7%A7%80%E5%90%89%E5%A4%A7%E6%98%8E%E7%A5%9E/
- 1599年 家康が権力を強化 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1599/
- 大関ヶ原展 - テレビ朝日 https://www.tv-asahi.co.jp/sekigahara/
- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 三田藩(さんだはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E7%94%B0%E8%97%A9-71034
- にしのみや山口風土記「有馬郡・幕末藩領」 - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~lu1a-hdk/yamaguti-tonari.hudoki-bakumatu-han.htm
- 有馬則頼(ありま のりより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E9%A0%BC-1051466
- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86
- 太閤豊臣秀吉は如何に有馬温泉を愛したか http://alimali.jp/2016/12/09/hideyoshi-arimaonsen/
- 梅 林 寺 外 苑 筑 梅 林 寺 外 苑 梅 林 寺 有馬家墓所 - 久留米市 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3050kurumeshishi/files/bairinji3.pdf
- 梅林寺 | 久留米の観光スポット | 久留米公式観光サイト ほとめきの街 https://welcome-kurume.com/spots/detail/4ec3b2dd-9c8e-49e5-86bc-3075af7d95b4
- 有馬家霊屋 梅林院霊屋 春林院霊屋 春林院位牌廟 長壽院位牌廟 瓊林院位牌廟 - 福岡県文化財データベース https://www.fukuoka-bunkazai.jp/frmDetail.aspx?db=1&id=199
- 梅林寺有馬家霊屋 - 久留米市 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3050kurumeshishi/files/historywalk044.pdf
- 久留米藩主 有馬家の歴史 - 東林寺天満宮へようこそ! https://www.torinji-tenmangu.com/2021/05/15/%E4%B9%85%E7%95%99%E7%B1%B3%E8%97%A9%E4%B8%BB-%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/
- 久留米藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E7%95%99%E7%B1%B3%E8%97%A9
- 有馬家(摂津有馬氏、吹上有馬家、氏倫系)のガイド | 攻城団 https://kojodan.jp/family/160/
- 有馬氏倫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E5%80%AB
- 有馬頼徸による弓形の研究とその情報源について https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2006038/files/tkr025001.pdf
- 林 窓 - 東京都立学校 https://www.metro.ed.jp/mita-h/assets/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%97%E5%B9%B4%E5%BA%A6%20_%E6%9E%97%E7%AA%93_.pdf
- 日本評価研究 https://evaluationjp.org/wp-content/uploads/2024/07/Vol24_No1.pdf
- 北洋大学紀要 https://hokuyo.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2025/04/%E5%8C%97%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B4%80%E8%A6%814%E5%8F%B7.pdf
- 星槎道都大学研究紀要 https://www.seisadohto.ac.jp/20026/uploads/2023/04/kiyouall.pdf