清野清秀
清野清秀は北信濃の国人領主。村上義清の重臣として武田信玄と戦うが、武田氏に降伏と帰参を繰り返す。最終的に武田家臣となり、清野氏の存続を図った。
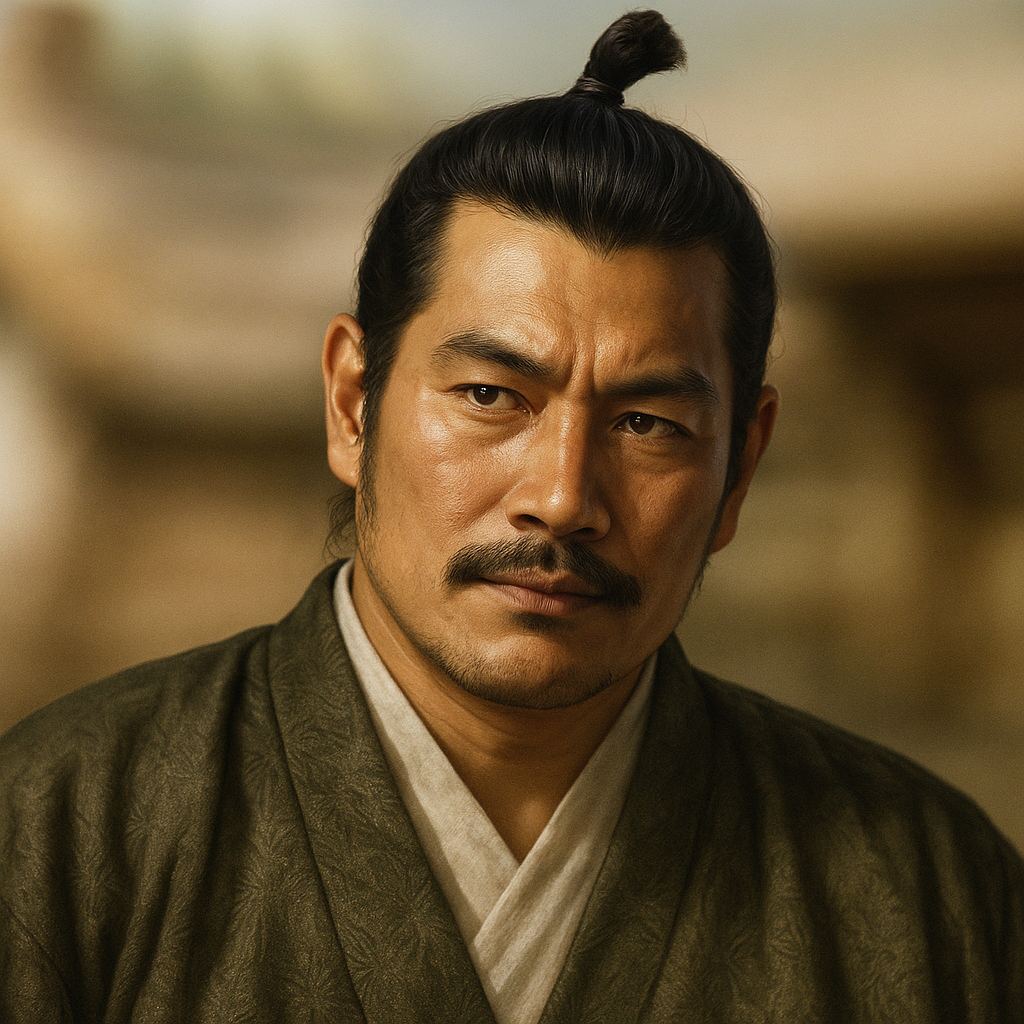
戦国武将・清野清秀(信秀)の生涯と実像 ― 北信濃の動乱を生き抜いた国人領主の選択 ―
序章:北信濃の雄、清野氏の台頭
戦国時代の信濃国、特に甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信が激しく覇を競った北信濃の地は、数多の国人領主たちが自家の存亡を賭けて激動の時代を生き抜いた舞台であった。その中にあって、清野清秀(後の信秀)は、主家への忠誠と一族の存続という相克する命題の間で揺れ動き、複雑な政治的遍歴を辿った象徴的な人物である。本報告書は、村上氏の重臣として、また武田氏の家臣として生きた彼の生涯を、史料に基づき多角的に検証し、その実像に迫るものである。
まず、彼の生涯を概観するため、その経歴を以下の表にまとめる。
【表1】清野清秀(信秀)の生涯と主家の変遷
|
年代 (西暦) |
元号 |
主な出来事 |
所属勢力 |
備考 |
|
生年不詳 |
|
清野国俊の子として誕生 1 。 |
村上氏 |
初名は「清秀」。通称は伊勢守。 |
|
1548年 |
天文17年 |
上田原の戦いで村上軍が武田軍に大勝。清秀も先陣として参戦したと伝わる 3 。 |
村上氏 |
|
|
1550年 |
天文19年 |
9月1日、砥石城の戦いの最中に武田氏に降伏(第一次離反) 1 。 |
武田氏 |
『高白斎記』に「辛卯。申刻、清野出仕。」と記録される。 |
|
(時期不詳) |
天文年間 |
村上氏に再従属 2 。 |
村上氏 |
砥石崩れにおける村上方の勝利後と推測される。 |
|
1553年 |
天文22年 |
主君・村上義清と共に越後へ亡命 1 。 |
上杉氏 |
|
|
1555-57年 |
弘治元年-3年 |
川中島の戦いに上杉方信州先方衆として参戦 6 。 |
上杉氏 |
|
|
1559年 |
永禄2年 |
武田氏に再度降伏し、旧領に復帰(第二次離反) 1 。 |
武田氏 |
この頃、信玄から一字を賜り「信秀」に改名した可能性が高い。 |
|
1565年 |
永禄8年 |
逝去 1 。 |
武田氏 |
出家し「美作入道道寿軒」と号した。 |
清野氏の出自と系譜
清野氏は、信濃国に古くから根を張る清和源氏村上氏の支流と位置づけられる、由緒ある武家一族である 2 。村上氏は平安時代末期に信濃国更級郡村上郷に土着して以来、鎌倉・室町時代を通じて北信濃に強固な地盤を築き上げた名門であった 8 。清野氏はその数ある庶家の中でも特に有力な存在として、主家の支配体制を支える中核を担っていた。本報告の主題である清野信秀の父は、清野国俊と伝わっている 1 。
この出自は、信秀の行動原理を解明する上で決定的に重要である。彼は単なる被官ではなく、村上氏という広範な血族共同体の一員であり、その中でも筆頭格という重い立場にあった 5 。この事実は、彼の決断が常に「村上家」全体への忠誠と、自らが当主を務める「清野家」の存続という、時に相克する二つの命題の間でなされたことを示唆している。戦国時代の国人領主にとって、主家との関係性とは別に、独立した「家」の存続こそが至上命題であった。信秀の度重なる主家の変更は、この「村上一門の重鎮」と「清野家の当主」という二つのアイデンティティの狭間で、究極的には後者を優先せざるを得なかった苦渋の選択の結果と解釈できる。
村上家中の筆頭格
諸史料において、清野氏は村上氏の支配体制を構成した「村上九家」の筆頭格であったと記されている 5 。これは、主君・村上義清の政権下で、清野氏が軍事・政治の両面で他の追随を許さない中心的な役割を担っていたことを明確に示している。
後世、長野郷土史研究会の機関誌『長野』において、彼が「村上氏最後の執事」と評されているのは、この筆頭家臣としての地位に由来するものであろう 12 。中世武家社会における「執事」とは、単なる家臣を指す言葉ではなく、主家の家政・財政・軍政を統括する「家宰(かさい)」に相当する最高位の職責を意味する言葉であった 13 。この評価は、清野氏が村上氏の所領経営や家臣団統制において、いかに不可欠な存在であったかを雄弁に物語っている。
本拠地・鞍骨城と清野庄の経済力
清野氏の軍事的な拠点(詰城)は、川中島平の南西、千曲川西岸に聳える鞍骨山に築かれた山城・鞍骨城であった 1 。この城は、伝承によれば永正年間(1504-1521年)に清野山城守勝照なる人物によって築かれたとされる 14 。山麓の清野・西条地区には清野氏の居館(現在の古峰神社周辺と伝わる)が構えられ、政治・経済の中心地として機能していた 6 。
その所領は、西条・清野・岩野・土口・生萱・森・倉科・矢代といった9カ村に及び、石高は慶長7年(1602年)の『川中島四郡検地打立之帳』によれば8,658石余に達したと記録されている 6 。これは戦国時代の北信濃における国人領主として、傑出した経済力と、それを背景とした強大な軍事力を有していたことの動かぬ証拠である。
清野氏が有したこの強大な経済基盤は、村上家中の筆頭格という地位を支える物理的な源泉であった。しかし同時に、この豊穣な所領を守り、一族の血脈と共に次代へ継承することこそが、当主である信秀に課せられた至上命題であったと言える。彼の複雑な政治的遍歴を理解する鍵は、この「守るべきものの大きさ」にこそある。武田信玄という強大な脅威を前に、この広大な所領をいかにして守り抜くか、その一点に彼の行動原理は収斂されていくのである。川中島平の豊かな農業生産力は、武田信玄にとって垂涎の的であり、この豊かな所領を失うことへの恐怖と、それを維持するための必死の策が、彼の行動を規定したとみることができる。
第一章:主家への忠節 ― 村上義清の懐刀として
武田信玄の信濃侵攻が本格化する以前、清野清秀は主君・村上義清の信頼篤い重臣として、その勢力拡大と維持に多大な貢献を果たした。特に、甲斐武田氏との存亡をかけた戦いにおいて、彼は村上軍の中核を担う武将としてその名を馳せることになる。
武田信玄の信濃侵攻と対峙
天文10年(1541年)、武田信虎(信玄の父)は村上義清らと連合し、小県郡の海野氏を駆逐した 4 。しかし、父を追放して家督を継いだ武田晴信(信玄)が信濃侵攻を本格化させると、北信濃の覇者・村上義清との衝突は避けられない運命となった 18 。清野清秀は、主君・義清の麾下にあって、この甲斐の虎との存亡をかけた戦いの最前線に立つことになったのである。
上田原の戦いと砥石崩れ ― 村上軍の中核として
天文17年(1548年)の上田原の戦いは、村上義清の名を戦国史に刻んだ戦いであった。この戦いで村上軍は、常勝を誇った武田軍に初めて黒星をつけ、武田方の重臣・板垣信方、甘利虎泰といった宿将を討ち取るという大金星を挙げた 17 。この歴史的な戦いにおいて、清野清秀は高梨政頼らと共に村上軍の先陣を務めたと記録されており、彼が義清から絶大な信頼を寄せられた勇将であったことが窺える 3 。
続く天文19年(1550年)、武田軍が義清の重要拠点・砥石城を包囲すると、義清は救援に駆けつけ、巧みな戦術で武田軍を再び撃破する(砥石崩れ) 21 。この一連の戦いにおける清秀の具体的な武功を記す史料は限定的であるが、村上軍の中核として奮戦したことは疑いようがない。
この時期の清秀は、政治力や経済力に優れた領主であると同時に、戦場での働きを期待される武将でもあった。上田原の戦いで先陣を任されたという事実は、彼の軍事的能力と主君からの信頼の厚さを物語る。この「武勇の人」という側面を理解することは、後の離反という政治的決断を、単なる臆病や裏切りではなく、より複雑で深みのある人間的葛藤の産物として捉えることを可能にする。
「村上氏最後の執事」という評価の萌芽
この時期の清秀は、まさしく村上義清の懐刀として、主家の勢力維持に身を粉にして尽力した [ユーザー提供情報]。軍事面での目覚ましい活躍は、彼が村上家中において「執事」と称されるに足る重責を担っていたことの証左と言えるだろう。
しかし、この輝かしい勝利の影で、武田方の調略の魔手は、水面下で着実に北信濃の国人衆に伸びていた。村上氏の栄光が頂点に達した瞬間と、その足元で進行する崩壊の予兆が交錯する中で、清秀は「忠臣」としての役割を全うしようとしていた。しかし同時に、広大な所領を持つ「国人領主」として、自家の将来に対する深刻な不安を募らせていたはずである。軍事的には村上氏が勝利を収めたにもかかわらず、武田氏は調略という別の戦線を展開していた 21 。驚くべきことに、砥石城攻防のまさにその最中に、清秀自身も武田方からの接触を受け、内応へと傾いていくのである 4 。この内面の葛藤こそが、次章で詳述する彼の劇的な転身の伏線となる。
第二章:離反と帰参 ― 激動を生き抜くための選択
本章では、清野清秀の生涯で最も劇的かつ重要な局面である、主家の離反と帰参の往復運動を詳細に分析する。彼の行動は、戦国時代の国人領主が直面した絶え間ない選択の厳しさと、その中で下された苦渋の決断を象徴している。
第一次離反:天文19年(1550年)、砥石城の戦いにおける武田氏への降伏
砥石城を力攻めにした武田晴信は、同時に真田幸隆を起用し、村上方の国人衆の切り崩しを図った 23 。同じ信濃国人である幸隆は、清野氏や寺尾氏らに巧みに降伏を働きかける 4 。武田の圧倒的な国力の前に、村上氏の将来を悲観する空気が国人衆の間に蔓延していたことが、この調略を成功させる土壌となった 18 。
武田方の一次史料である『高白斎記』には、天文19年(1550年)9月1日条に「辛卯。申刻、清野出仕。」と、彼の降伏が簡潔かつ明確に記録されている 1 。これは、清秀が武田の陣営に出頭し、臣従を誓ったことを示す動かぬ証拠である。
この第一次離反は、衝動的な裏切りではなく、周到な調略の末の政治的決断であった。特筆すべきは、村上軍が軍事的に大勝利を収めた「砥石崩れ」の直前に降伏している点である。これは、彼が短期的な戦況の優劣に惑わされることなく、長期的な勢力図の変化、すなわち武田の力が最終的に北信濃全域を覆うであろうことを見越していた可能性を示唆している。たとえこの一戦に勝っても武田の再侵攻は必至であり、国力差を考えれば長期的には勝ち目がないと判断したのかもしれない。大局的な視点から「家」の生き残りを図った、極めて戦略的な降伏であったと考えられる。
主家への復帰と越後への亡命
武田方へ降伏した後、清秀は再び村上氏の麾下に復している 1 。この復帰の具体的な経緯を記す史料は見当たらないが、砥石崩れで村上方が大勝し、武田軍が一時的に後退したことが影響したと推測される。義清から罪を許され帰参したのか、自発的に戻ったのかは不明であるが、彼の立場が極めて流動的であったことは確かである。
天文22年(1553年)、屋代氏や塩崎氏といった他の重臣たちが次々と武田方に寝返ったことで、村上義清は完全に孤立する 30 。ついに本拠・葛尾城を捨て、越後の長尾景虎(上杉謙信)を頼って落ち延びることを決断する 17 。この時、一度は武田に降ったはずの清秀が、義清に付き従い、共に越後へと亡命したのである 1 。
一度裏切ったにもかかわらず、主君が最も困窮した場面で行動を共にしたという事実は、清秀の人物像を一筋縄ではいかないものにしている。これは、単なる利害勘定だけでは説明できない、村上氏一門としての最後の情義や、筆頭家臣としての責任感の表れだったのかもしれない。あるいは、武田方での処遇に不満があったか、上杉方に付く方が将来的により有利と判断した、さらなる戦略的転身であった可能性も否定はできない。
上杉家臣としての雌伏と第二次離反
越後において、清秀は上杉方の「信州先方衆」として遇され、弘治元年(1555年)や同3年(1557年)の川中島の戦いでは、上杉軍の一員として故郷の地で武田軍と矛を交えた 6 。失地回復を目指す上杉謙信にとって、信濃の地理や国人衆の動向に精通した彼の存在は、非常に価値が高かったはずである。
しかし、その忠誠も長くは続かなかった。永禄2年(1559年)、清秀は再び武田氏に降伏し、ついに旧領復帰を果たす 1 。これが彼の生涯における最終的かつ決定的な転換点となった。
この頃、武田信玄は川中島に海津城(後の松代城)を築城し、北信濃の支配体制を盤石なものにしつつあった 6 。上杉方の有力国人であった高梨氏の本拠・中野城も攻略され、北信濃における武田の優位は動かしがたいものとなっていた 29 。清秀は、もはや上杉の力に頼っても旧領回復は絶望的と判断し、一族と家名を存続させるためには武田の軍門に降る以外に道はない、と最終決断を下したのだろう。武田方から旧領安堵という具体的な好条件が提示されたことも、彼の背中を押したに違いない。
この第二次離反と前後して、彼は名を「清秀」から「信秀」へと改めたと考えられている 1 。この「信」の一字は武田信玄からの偏諱(主君が家臣に自分の名前の一字を与えること)と見るのが最も自然であり、これは彼が名実ともに武田家の家臣団に組み込まれたことを示す、極めて象徴的な出来事であった。
第三章:武田家臣としての後半生と清野氏のその後
武田氏への最終的な帰属を決断した清野信秀は、その後半生を武田家の信濃支配の一翼を担う重臣として過ごす。彼の選択は、清野一族の運命を決定づけ、武田氏滅亡後の動向にも大きな影響を与えた。
武田信濃先方衆としての役割
武田氏に帰属した清野信秀は、「信濃先方衆」の一員として、北信濃の最前線における支配と防衛の重責を担った 37 。信濃先方衆とは、元々信濃の有力国人であった者たちで構成された部隊であり、地元の地理や人脈に精通していることから、武田氏の信濃統治において不可欠な存在であった。
彼の本拠・鞍骨城は、武田方の対上杉拠点である海津城の重要な支城群の一角を成し、その広域防衛網を担った 14 。武田信玄は永禄4年(1561年)の第四次川中島合戦に際し、戦勝を祈願して清野の地に風雲庵を建立したと伝わっており、信秀が武田方として地域支配に深く関与していた様子がうかがえる 38 。
一族の動向と信秀の死
信秀の決断は、一族の運命をも決定づけた。子の一人、雨宮正利は雨宮氏の養子となり、唐崎城主として武田方に仕えている 39 。また、孫の満成も信玄・勝頼の二代にわたって仕えた 5 。これにより、清野氏一族は武田家臣団の一員として、その血脈を未来へと繋ぐことに成功したのである。
信秀自身は、その後出家して「美作入道道寿軒(みまさかにゅうどうどうじゅけん)」と号し、永禄8年(1565年)にその波乱の生涯を閉じたとされている 1 。
清野信秀の現実主義的な生存戦略は、結果として清野氏の家名を武田支配下の信濃において存続させることに成功した。これは、最後まで武田への抵抗を続け、ついに故郷の地を踏むことなく越後で客死した主君・村上義清の運命とは実に対照的である 33 。この事実は、彼の選択が、少なくとも「家の存続」という目的においては功を奏したことを示している。戦国時代における「忠義」と「家の存続」という二つの価値観の相克を浮き彫りにする事例と言えよう。
清野氏のその後
天正10年(1582年)に武田氏が織田信長によって滅ぼされると、清野氏は再び大きな転機を迎える。彼らは旧主筋である上杉景勝に属し、その支配下に入った 6 。武田氏滅亡後、再び上杉氏に仕えている点は非常に興味深い。これは、かつて上杉方に属していた経緯や、武田氏亡き後の北信濃における上杉氏の勢力回復という状況を的確に判断した結果であろう。
そして慶長3年(1598年)、上杉景勝が豊臣秀吉の命により会津へ移封されると、清野一族もこれに従い、永らく本拠としてきた信濃の地を離れた 6 。上杉家の家臣として、文禄元年(1592年)に景勝の命で清野氏の名跡を継いだ清野長範といった人物の名が記録に見える 43 。主家を次々と変えながらも、その時々の政治情勢を読み、最適解を見出して一族の存続を図っていく姿は、まさに戦国国人のしたたかさを体現していると言える。
第四章:歴史的評価と後世の記憶
清野信秀の生涯は、同時代人だけでなく、後世の人々にも様々な形で記憶され、評価されてきた。その複雑な行動は、多様な解釈を生み、彼の人物像に深い奥行きを与えている。
「村上氏最後の執事」という評価の再検討
長野郷土史研究会の機関誌『長野』において、清野美菜子氏による「村上氏最後の執事 清野信秀とその一族」と題された一連の論文が発表されている 12 。この「最後の執事」という呼称は、清野信秀の歴史的評価を考察する上で、極めて示唆に富むものである。
この評価は、単に「最後まで義清に仕えた忠臣」という意味合いで使われているのではないだろう。むしろ、村上氏という一大名家が武田の侵攻によって実質的に解体されていく動乱の過程において、その「執事=家宰」として、最後まで「家」の行く末に責任を負い、一族の存続のために苦渋の決断を下し続けた人物、というニュアンスを色濃く含むと解釈すべきである。彼の離反は、主君・義清個人を見限ったのではなく、村上氏の有力支族である清野家を守るという「執事」としての重責を果たした結果である、という新たな視座を提供する。
主君の子・村上国清(山浦景国)との関係 ― 傅役説の検証
依頼者が当初把握していた「義清の子・国清の教育係を務めた」という説について、今回収集・分析した史料からは、残念ながらその直接的な証拠を見出すことはできなかった 45 。
前述の通り、清野信秀が武田家臣となった永禄2年(1559年)以降、敵対する上杉家中にいる国清の傅役(教育係)を務めることは、物理的にも政治的にも不可能である。義清と共に越後にいた短い期間(天文22年~永禄2年)に傅役であった可能性も皆無ではないが、それを裏付ける史料はなく、また国清の年齢を考えても不自然さが残る。この「傅役」説は、信秀の複雑な生涯を「主家への忠義」という一面的な物語に回収しようとする、後世の人々の願望が生んだ美しい伝承である可能性が高いと考えられる。
故郷に残る記憶 ― 遺愛碑と菩提寺
信秀の死から実に280年もの歳月が流れた江戸時代後期の弘化2年(1845年)、地元の松代藩家老・鎌原桐山によって、清野氏の旧居館跡に「清野氏遺愛之碑」が建立された 6 。碑文は、旧領主であった清野氏の由緒を讃え、その霊を慰め、村の平和を祈願する内容である。これは、江戸時代を通じて清野氏が地元の人々から深く敬愛され、その記憶が大切に語り継がれていたことを示す何よりの証拠である。
また、信秀とその一族が開基となった菩提寺が、信濃の地に複数現存している。
- 禅透院 (長野県千曲市森):天文11年(1542年)、清野山城守勝照が開基したと伝わる 48 。清野氏および同じく村上支族の雨宮氏の菩提寺となっている 50 。
- 法泉寺 (長野市松代町西条):永禄7年(1564年)、清野山城守宗頼が開基したと伝わる 52 。墓地の最上段には、開基である清野氏の墓が今も静かに並んでいる 6 。
度重なる主家の変更という、一見すると節操のない行動にもかかわらず、故郷で長く敬愛されたという事実は、彼が単なる裏切り者ではなく、領民にとっては良き領主であった可能性を強く示唆する。彼の現実主義的な選択は、結果として自らの領地を無用な戦火から守り、民の生活の安定に繋がったのかもしれない。その善政の記憶が、後世の「遺愛碑」建立に結実したと考えることができる。戦国領主の評価は、主君への忠誠という一面的な価値観だけでなく、領地経営の手腕や領民への配慮といった多角的な視点からなされるべきことを、清野信秀の事例は教えてくれる。
結論:清野清秀(信秀)の実像 ― 忠臣か、それとも稀代の現実主義者か
清野清秀(信秀)の生涯は、忠誠と裏切り、情義と計算、理想と現実が複雑に絡み合った、まさに戦国乱世の縮図であった。村上氏筆頭家臣としての輝かしい前半生、そして武田・上杉という二大勢力の狭間で揺れ動き、苦渋の決断を重ねた後半生。そのいずれもが、清野信秀という一人の武将を形成する不可分な要素であり、単純な二元論で割り切れるものではない。
彼は、主君個人への玉砕的な忠誠を貫くことよりも、自らの一族と所領という「家」を次代へ継承することを最優先した。これは、戦国時代を生きる多くの国人領主が共有していた価値観であり、清野信秀はその選択を成功させた典型例と位置づけることができる。彼の行動を「裏切り」という現代的な倫理観で断罪することは、当時の歴史的文脈を見誤ることに繋がる。彼は、忠臣であることと、現実主義者であることを両立させようと最後まで苦闘した、極めて人間的な深みを持つ武将であったと言えるだろう。その複雑な生き様は、戦国という時代の過酷さと、そこで生きる人々のしたたかさ、そして人間性の奥深さを我々に示している。
引用文献
- 清野信秀- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B8%85%E9%87%8E%E4%BF%A1%E7%A7%80
- 清野信秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E9%87%8E%E4%BF%A1%E7%A7%80
- 真田氏の始祖 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96
- 小助の部屋/滋野一党/信濃大井氏/信濃村上氏/信濃高梨氏 http://koskan.nobody.jp/teki_hokusin.html
- 鞍骨城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/entry/000522.php.html
- 清野氏居館跡(古峰神社) /【川中島の戦い】史跡ガイド - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/siseki/entry/000233.html
- 清野信秀- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B8%85%E9%87%8E%E4%BF%A1%E7%A7%80
- 信濃村上氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E6%9D%91%E4%B8%8A%E6%B0%8F
- 村上義清 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%C2%BC%BE%E5%B5%C1%C0%B6
- らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ - 鞍骨城(長野市) https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-150.html?sp
- 清野氏居館跡 - 長野市誌 第九巻 旧市町村史編 旧更級郡/旧埴科郡 https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100090/ct00000009/ht004700
- 『長野』総目次(5)201号~最新号 | 長野郷土史研究会 | 長野市 https://naganokyodoshi.wixsite.com/my-site/%E9%95%B7%E9%87%8E-%E7%B7%8F%E7%9B%AE%E6%AC%A1-5
- 「管領」って何? 執権・執事との違いや成り立ち、三管領についても解説【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/544832
- 鞍骨城 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/TokaiKoshin/Nagano/Kurahone/index.htm
- 鞍骨城の見所と写真・全国の城好き達による評価(長野県長野市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1597/
- 城・館 - 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[史跡ガイド] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/list/jouseki.php%3Fpage=all.html
- 村上義清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E6%B8%85
- 【武田の侵攻と村上義清】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100020/ht003010
- 武田信玄は何をした人?「戦国最強の甲斐の虎と呼ばれ風林火山の旗をなびかせた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/shingen-takeda
- 武田信玄の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91120/
- 村上義清は何をした人?「信玄に二度も勝ったけど信濃を追われて謙信を頼った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshikiyo-murakami
- 砥石崩れ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E7%9F%B3%E5%B4%A9%E3%82%8C
- 武田軍の歴史 - 武田信玄軍団 最強武将~山縣三郎右兵衛尉昌景 https://ym.gicz.tokyo/takedahistory?id=
- らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ - 葛尾城(坂城町) https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
- 第15話 砥石崩れ - 真田幸綱(じ~じ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054886793212/episodes/1177354054886793415
- 車山高原レア・メモリーが語る戦国時代前期 https://rarememory.sakura.ne.jp/justsystem/takeda1/ta1.htm
- 砥石城の戦い古戦場:長野県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/toishijo/
- 第29話 終結 - 戦国日本を世界一豊かな国へ!(わびさびわさび) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16818093079190990925/episodes/16818093091400077251
- 川中島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 屋代氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%B0%8F
- 葛尾城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/TokaiKoshin/Nagano/Katsurao/index.htm
- 塩崎城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%B4%8E%E5%9F%8E
- 村上義清~武田信玄を二度負かした信濃の勇将 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4908
- 海道龍一朗 - web 集英社文庫 https://bunko.shueisha.co.jp/serial/kaitou/97_31.html
- 川中島の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7085/
- 武田信玄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84
- 武田信玄の家臣団 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3
- 武田軍関連 - 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[史跡ガイド] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/list/takedagun.php%3Fpage=all.html
- 雨宮正利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A8%E5%AE%AE%E6%AD%A3%E5%88%A9
- 『雨宮家のルーツ』を辿る旅 《後編》 | 天川 彩の こころ日和 https://ameblo.jp/aya-tenkawa/entry-12706738587.html
- 武田信玄と上杉謙信の激戦の地に残る名城「葛尾城」【長野県埴科郡坂城町】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/25589
- 信濃 清野屋敷-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shinano/kiyono-yashiki/
- 清野長範 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E7%AF%84
- 身柄を預けられた。十二月十七日、義光は志村光安に https://www.kinokuniya.co.jp/banner/9784490109214_contents.pdf
- 近世軍記 (国枝清軒) - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E8%BF%91%E4%B8%96%E8%BB%8D%E8%A8%98_(%E5%9B%BD%E6%9E%9D%E6%B8%85%E8%BB%92)
- 1949年 - 中国新文学研究中心 https://njucml.nju.edu.cn/_upload/article/files/a0/f0/a799ce0c4231aa1380bd2d565418/b0eedbbf-d001-4297-b607-bd521ee46f8a.pdf
- 多田家資料 - 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1204524/8645.pdf
- 禅透院 永代供養合祀墓(千曲市)の費用・口コミ・アクセス - いいお墓 https://www.e-ohaka.com/detail/id1389237265-001774.html
- 当院のご案内 - 曹洞宗 禅透院 http://www.zentouin.jp/about/index.html
- 長野県の御朱印・神社・お寺 人気ランキング2025 (426位~450位) | Omairi(おまいり) https://omairi.club/pref/nagano/page/18
- 禅透院 - 千曲市/長野県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/101311
- 法泉寺の歴史 https://www.housenji-m.com/about
- 法泉寺 (長野市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%B3%89%E5%AF%BA_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82)
- 松代町 - 長野市立西条小学校 https://www.nagano-ngn.ed.jp/nishijjs/tiiki.html
- 松代の寺院 - 松代文化財ボランティアの会 https://ma-vol.jp/rekibun/%E6%9D%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%AF%BA%E9%99%A2/