細川通薫
細川通薫は野州細川家当主として、父晴国の死後、備中で再起。毛利氏の客将となり、杉山城合戦などで武功を挙げる。長府細川家筆頭家老の祖となる。
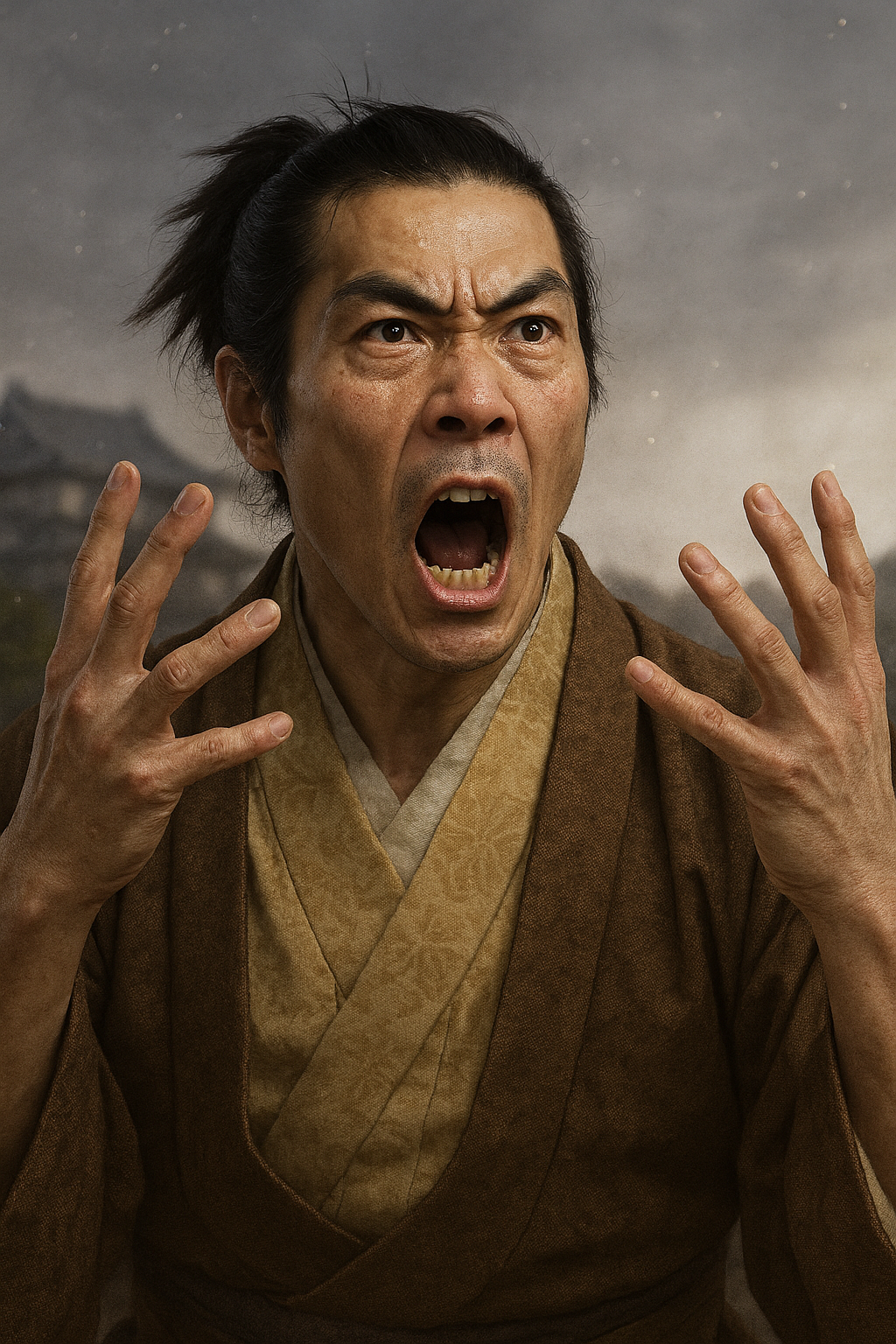
細川通薫(通董)の生涯 ― 名門の凋落と、備中における再生の軌跡
序章:失われた京の栄光 ― 細川通薫とは何者か
導入:通薫と通董、二つの名を持つ武将
日本の戦国時代、数多の武将が歴史の舞台で興亡を繰り返した。その中に、細川通薫(ほそかわ みちただ)という人物がいる。彼の名は、史料によって「通董」とも記されるが、これは同一人物を指す 1 。本報告書では、彼の活動が備中国で本格化して以降、より多く用いられる「通董」の表記を主として採用する。
細川通董の生涯は、室町幕府の中枢を担った名門「細川氏」が、戦乱の中でその栄光を失い、一族の血脈を繋ぐために地方で必死の再生を図る、まさに激動の時代を象徴する物語である。彼の人生を追うことは、中央政権の崩壊と地方勢力の台頭という、戦国時代の大きな構造転換の中で、名家の末裔がいかにして生き抜いたかを解き明かすことに繋がる。
野州細川家 ― 栄光と凋落の系譜
通董が属した細川氏は、清和源氏足利氏の支流であり、室町幕府において三管領の一角を占めた屈指の名門である 3 。その中でも通董の家系は「野州家(やしゅうけ)」と称される分家であった 5 。
野州家は、室町幕府管領・細川頼元の子である満国を祖とする 5 。満国の子・持春、その子・教春が二代にわたって下野守(しもつけのかみ)に任官したことから、下野国の雅称である「野州」を冠して「野州家」の名が定着した 6 。この家系は、細川宗家である京兆家(けいちょうけ)に次ぐ高い家格を誇り、幕政においても重きをなした。
さらに、通董の祖父にあたる細川政春の代には、断絶した分家の所領であった備中国の守護職を継承した 6 。政春が安房守(あわのかみ)を名乗ったことから、この家系は「房州家(ぼうしゅうけ)」とも呼ばれるようになる 6 。この備中との関わりが、後に中央での足場を失った通董にとって、再起を期すための重要な伏線となったのである。
第一章:悲運の父・細川晴国 ― 中央政界からの訣別
通董の生涯を決定づけたのは、彼の父・細川晴国が巻き込まれた中央政界の激しい権力闘争であった。
背景:両細川の乱と京兆家の内訌
16世紀初頭の畿内は、細川京兆家の家督と室町幕府管領の座を巡り、細川高国(晴国の兄)と、阿波細川家の細川澄元・晴元親子が壮絶な抗争を繰り広げていた。これは「両細川の乱」と呼ばれ、畿内を焦土と化す長期の内乱であった 7 。通董の父・晴国は、この渦中に生まれ、兄・高国の運命に翻弄されることとなる。
高国は一時、将軍を擁して権勢を誇ったが、細川晴元が阿波の三好元長ら有力家臣を率いて畿内に進出すると、その勢力は次第に揺らぎ始める 8 。
父・晴国の短い生涯と非業の死
享禄4年(1531年)、摂津国で起こった「大物崩れ」において、高国は晴元・三好元長連合軍に大敗を喫し、潜伏先の尼崎で捕らえられ自害に追い込まれた 7 。この時、高国派の残存勢力は、高国の実弟であり、野州家を継ぐ立場にあった晴国を新たな旗頭として擁立した 11 。当時、晴国はまだ若年であったが、兄の無念を晴らすべく、細川晴元との戦いにその身を投じることになったのである。
天文2年(1533年)、晴国は摂津・丹波の旧高国派勢力を結集して挙兵する。当初は石山本願寺と手を結び、晴元方の武将を討ち取るなど優勢に戦を進めた 11 。しかし、晴元の巧みな外交戦略により、石山本願寺と和睦が成立。さらに晴元の要請を受けた京都の法華一揆が蜂起すると、晴国は一転して窮地に陥る 7 。
求心力を失い、味方の離反が相次ぐ中、天文5年(1536年)8月、晴国はかねてより晴元に内通していた家臣・三宅国村の裏切りに遭い、摂津天王寺にて自害した。享年21という、あまりにも短い生涯であった 7 。
晴国の死は、単に一人の武将が戦に敗れたという事実以上の、重い意味を持っていた。それは、畿内における細川高国派の組織的抵抗が完全に終焉したことを意味し、同時に、名門・野州細川家が中央政界における政治的影響力と、その基盤となる所領をすべて失った決定的瞬間であった 11 。この敗北により、晴国の後継者である通董は、生まれながらにして「帰るべき場所」を失った流浪の貴公子となった。彼の生涯は、栄光の継承者としてではなく、失われた一族の権威と故地を取り戻すという、極めて困難な課題を背負うことから始まったのである。この過酷な出発点こそが、後の通董の現実的な政治判断、すなわち、もはや回復不可能な中央での栄光を追うのではなく、地方(備中)に確固たる足場を築き、より大きな権力(毛利氏)に庇護を求めるという、生き残りを最優先する行動原理を形成したと考えられる。
表1:野州細川家 略系図(戦国期)
|
関係 |
人物名 |
備考 |
|
祖父 |
細川 政春 |
野州家4代当主。備中守護職を継承し、房州家とも称される。 |
|
伯父 |
細川 高国 |
政春の長男。細川京兆家を継ぎ、幕府管領となるも晴元に敗れ自害。 |
|
父 |
細川 晴国 |
政春の次男。野州家5代当主。兄の死後、高国派に擁立されるも敗死。 |
|
当主 |
細川 通董(通薫) |
晴国の子、またはその後継者。備中で再起し、毛利氏の客将となる。 |
|
子 |
細川 元通 |
通董の子。父の跡を継ぎ毛利氏に仕え、長府藩家老家の祖となる。 |
出典:
5 に基づき作成。
第二章:雌伏の時 ― 旧領回復に向けた苦闘
父・晴国の非業の死により、野州細川家は壊滅的な打撃を受けた。その混乱の中、一族の未来を託されたのが細川通董であった。
曖昧な出自と継承の謎
通董が野州家の家督を継承した経緯には、いくつかの不明瞭な点が存在する。彼は晴国の子であると一般に認識されているが 5 、一方で、晴国の死後、野州家の嫡流は「絶家に近い状態」に陥り、通董は「傍流」から、あるいは「同家の伝統と無関係の人物」が後継として入ったとする見解も存在する 2 。
名門であればあるほど、家督継承は厳格に記録されるのが常である。通董の出自や継承の経緯に複数の説が存在するという事実そのものが、晴国の死後、野州細川家が組織としていかに深刻な窮状にあったかを物語っている。おそらく、血縁の近さといった形式的な正統性よりも、混乱した家中をまとめ上げ、備中の旧領回復という困難な事業を指導できるだけの器量を持つ人物として、通董が分家や有力家臣団によって擁立された可能性が考えられる。
さらに注目すべきは、通董が当初は「尼子氏方であった」という記録である 2 。最終的に毛利氏の客将となる彼が、一時期はその最大版図を争った尼子氏に与していたという事実は、彼の置かれた立場の不安定さを象徴している。これは、彼が特定の思想や勢力に殉じるのではなく、一族の生き残りと旧領回復という目的のためには、利用できるあらゆる勢力と接触を図っていた、極めて現実的で柔軟な戦略家であったことを示唆している。
備中への帰還と国人領主としての再起
畿内での望みを絶たれた通董は、かつて一族が守護職として支配した備中国に活路を見出す。彼は父祖伝来の地である備中国浅口郡に帰還し、一介の国人領主として再起の第一歩を踏み出した。
その道のりは平坦ではなかった。当初は瀬戸内海を渡り、一族の所領があった伊予国宇摩郡の川之江城に一時身を寄せたとされる 14 。その後、尼子氏の勢力が備中から後退する好機を捉えて帰還。まずは青佐山城を拠点とし、永禄9年(1566年)には鴨方町の龍王山城を築いて9年間在城した 14 。そして天正3年(1575年)、ついに父祖伝来の居城であった鴨山城に入城し、備中南部に確固たる地歩を築くに至る 14 。この拠点移動の軌跡は、彼が着実に勢力を回復・拡大させていった過程を物語っている。
第三章:毛利の客将へ ― 生き残りを賭けた決断
備中である程度の勢力を回復した通董であったが、単独で旧領の完全回復を成し遂げるには、時代の潮流はあまりにも厳しかった。彼の前には、中国地方の覇権を巡る巨大な権力闘争が横たわっていた。
中国地方の覇権争いと通董の選択
16世紀半ばの中国地方は、長らく覇を唱えてきた出雲の尼子氏が衰退し、代わって安芸の毛利元就が急速に勢力を拡大していた 16 。毛利氏は山陽・山陰の両方面から尼子氏を圧迫し、中国地方の新たな覇者としての地位を確立しつつあった。
この巨大なパワーバランスの変化の中で、通董は重大な決断を迫られる。備中旧領の回復という一族の宿願を達成するためには、もはや単独での活動には限界があった。生き残るためには、この新たな地域覇者である毛利氏の力を借りる以外に道はなかったのである。通董は、毛利氏の麾下に加わることを決断する 1 。
「客将」という立場
通董は毛利氏に臣従するにあたり、単なる一配下ではなく、「客将」という特別な待遇で迎えられた 1 。この事実は、彼の置かれた状況と毛利氏の戦略を理解する上で極めて重要である。
毛利氏のような新興勢力にとって、なぜ一介の国人領主に過ぎない通董が特別な存在だったのか。その理由は、通董個人の武力以上に、彼が背負う「細川」という名、とりわけ室町幕府管領家一門という「名門の血」に、毛利氏が大きな価値を見出していたからに他ならない。当時、武力で領土を切り取った新興大名が、その支配の正当性を内外に示す上で、足利将軍家や管領家といった旧来の権威を利用することは極めて有効な政治的戦略であった。通董を客将として自陣営に丁重に迎え入れることは、毛利氏による備中支配を円滑に進めるための、象徴的な意味合いを持っていたのである。
一方、通董にとってもこの「客将」という待遇は、単なる名誉ではなかった。それは、他の備中・備後の国人衆とは一線を画す特別な地位を毛利家中で保証されることを意味した。これにより、彼は毛利家中で一定の発言力を維持し、ひいては一族の存続と旧領の安堵を確実にするための、重要な政治的資産を手に入れたのである。これは、中央では失われた「名門の権威」という無形の価値を、地方の新たな権力構造の中で巧みに活用した、通董の見事な生存戦略であったと言えよう。
第四章:戦陣に生きた生涯 ― 細川通董の武功
毛利氏の客将となった通董は、その期待に応えるべく、数々の戦場で武勇を示した。彼の武功は、単なる一国人領主の枠を超え、毛利軍の重要な一翼を担うものであった。
杉山城の戦い(元亀元年/1570年)
通董の武名を高めた代表的な戦いが、元亀元年(1570年)の杉山城(すぎやまじょう)合戦である。この年、織田信長に追われた尼子氏の残党(尼子再興軍)が山中幸盛らに率いられ、備前の宇喜多直家と結んで備中へ侵攻してきた 19 。
当時、杉山城に拠っていた通董に対し、尼子方は使者を送り、味方になるよう降伏を勧告した。しかし、通董は毛利方としての信義を貫き、この誘いを毅然として拒絶する 19 。これに激怒した尼子・宇喜多連合軍は、7,000余騎ともいわれる大軍で杉山城を包囲した 20 。
城兵は圧倒的に劣勢であったが、通董の指揮のもと果敢に反撃を繰り返した。この籠城戦において、通董の軍勢は敵将の**津々加賀守(つつ かがのかみ) や 福井孫左衛門(ふくい まごさえもん)**らを討ち取るという目覚ましい武功を挙げた 20 。最終的に衆寡敵せず、城を支えきれなくなった通董は、味方が籠る幸山城へと退却するが、この奮戦は毛利方から高く評価され、彼の武将としての名声を不動のものとした。
備中兵乱と対織田戦線での働き
その後も通董は、毛利軍の主戦力として各地を転戦する。天正2年(1574年)から始まった、毛利氏と備中最大の国人・三村氏が争った「備中兵乱」においても、毛利方として従軍した 2 。翌天正3年(1575年)の国吉城(くによしじょう)攻めでは、毛利軍全体が討ち取った敵兵305人のうち、通董の部隊が3つの首級を挙げるという具体的な戦功が記録されている 2 。その数は少なくとも、彼の部隊が激戦の中で確実に戦果を挙げる精鋭であったことを示している。
さらに彼の活動は、中国地方に留まらなかった。天正4年(1576年)、毛利氏が織田信長と敵対する石山本願寺への兵糧輸送作戦を展開した際には、通董もその一員として摂津国へ出陣した。この時の功績により、当時毛利氏が庇護していた亡命将軍・足利義昭から直接、褒美として肩衣と袴を賜っている 2 。この事実は、彼が毛利軍の一員として忠実に働きつつも、その出自である「細川」の名によって将軍家との個人的な繋がりを維持し、自身の権威付けに巧みに利用していたことを示す興味深い事例である。
最後の出陣 ― 九州平定
天正15年(1587年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉が九州平定の軍を起こすと、毛利氏もその麾下として出陣した。この時、通董は毛利家の重鎮である小早川隆景の軍勢に加わり、先鋒を務めるまでに至っている 2 。これは、彼が長年の忠勤と武功によって、毛利家中で確固たる信頼と地位を築き上げていたことの証左に他ならない。
第五章:赤間関の落日と、長府細川家の成立
戦国の世を駆け抜け、一族再興に生涯を捧げた細川通董であったが、その最期は志半ばで訪れた。
陣中での最期
九州平定に従軍し、豊後の敵城を攻め落とすなど活躍した通董であったが、その戦いの最中、病に倒れる。天正15年(1587年)、軍が帰還する途上の長門国赤間関(現在の山口県下関市)に停泊中の船中にて、その波乱の生涯を閉じた 15 。父祖の地・備中旧領の完全な回復を見届けることなく陣中で没した彼の胸中には、いかばかりかの無念があったことであろう。彼の墓所は、晩年の居城であった鴨山城を望む菩提寺・長川寺(岡山県浅口市)に築かれ、今もその功績を伝えている 15 。
子・元通への継承と「長府細川家」の誕生
通董の死後、その跡を継いだ子・細川元通もまた、父同様に毛利氏に仕えた 13 。時代は豊臣政権から徳川の世へと大きく移り変わる。関ヶ原の戦いを経て、毛利氏は大幅に減封され、長州藩を立藩。元通は、毛利輝元の子・秀元が初代藩主となった支藩・長府藩(現在の山口県下関市)に移り住んだ 13 。
そして元通とその子孫は、長府藩において代々筆頭家老職を務める家柄となり、「長府細川家」として幕末維新に至るまで家名を存続させることに成功したのである 1 。
結論:再生の物語としての評価
細川通董の生涯を振り返る時、「野州家の備中旧領の回復に奔走するが叶わなかった」という評価は、一面の真実を捉えている。彼が、かつて一族が有した守護大名としての広大な所領と権威を、そっくりそのままの形で取り戻すことは、ついに叶わなかった。
しかし、彼の生涯を「失敗」の一言で片付けるのは、あまりにも早計であろう。彼の真の功績は、父・晴国の死によって中央政界から完全に駆逐され、断絶の危機に瀕した「野州細川家」という名門の血筋と家名を、戦国乱世の荒波を乗り越えて、形を変えながらも江戸時代を通じて存続させる道筋を確実につけた点にある。
通董は、失われた過去の栄光に固執するという非現実的な夢を追うのではなく、時代の変化を冷静に見極め、名門としてのプライドを内に秘めながらも、新興勢力である毛利氏の庇護下に入るという現実的な選択をした。その結果、一族は長府藩の筆頭家老という、新たな時代の新たな秩序における確固たる地位を確保したのである。滅亡か存続かという二者択一が日常であった戦国時代において、これは紛れもない「成功」の物語である。細川通董の生涯は、時代の激変に対応し、一族を見事に再生させた、名門武家のしたたかな適応と不屈の軌跡として、高く再評価されるべきである。
表2:細川通董 生涯年表
|
西暦(和暦) |
細川通董の動向・出来事 |
関連する中央・中国地方の情勢 |
|
1536年(天文5年) |
父・細川晴国が摂津天王寺で自害。通董が家督を継承か。 |
細川晴元が畿内での権勢を確立。 |
|
時期不詳 |
伊予川之江城に一時滞在後、備中国に帰還し青佐山城を拠点とする。 |
尼子氏が備中への影響力を保持。 |
|
1555年(弘治元年) |
- |
厳島の戦いで毛利元就が陶晴賢を破り、中国地方の覇権争いで優位に立つ。 |
|
時期不詳 |
毛利氏に属し、客将となる。 |
毛利氏が尼子氏を圧迫し、備中への進出を本格化。 |
|
1566年(永禄9年) |
備中鴨方に龍王山城を築城し、居城とする 14 。 |
- |
|
1570年(元亀元年) |
杉山城合戦 。尼子・宇喜多連合軍を迎え撃ち、敵将を討つ武功を挙げる 20 。 |
織田信長と足利義昭が対立。尼子再興軍が活発化。 |
|
1574年(天正2年) |
備中兵乱 が勃発。毛利方として三村氏と戦う 2 。 |
宇喜多直家が毛利氏から離反し、織田方につく。 |
|
1575年(天正3年) |
国吉城攻めに参加し、戦功を挙げる 2 。父祖の居城・鴨山城に入城 15 。 |
備中兵乱が終結し、三村氏が滅亡。 |
|
1576年(天正4年) |
毛利氏の石山本願寺支援作戦に参加。足利義昭から褒賞を受ける 2 。 |
第一次木津川口の戦いで毛利水軍が織田水軍に勝利。 |
|
1582年(天正10年) |
- |
本能寺の変で織田信長が死去。備中高松城の戦いの後、毛利氏と羽柴秀吉が和睦。 |
|
1587年(天正15年) |
豊臣秀吉の 九州平定 に従軍し、先鋒を務める 2 。長門国赤間関の船中で病没 15 。 |
豊臣秀吉が九州を平定し、天下統一をほぼ完成させる。 |
|
死後 |
子・元通が跡を継ぎ、後に関ヶ原の戦いを経て長府藩筆頭家老となる 13 。 |
徳川家康が江戸幕府を開府。 |
出典: 2 等の情報を基に編纂。
引用文献
- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F
- 細川通董 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%80%9A%E8%91%A3
- 細川氏発祥の地 | 散策侍 https://ameblo.jp/rekisi-kentiku/entry-12611910120.html
- 細川氏(ほそかわうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F-133254
- 管領細川家とその一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hosokawa
- 野州家とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%8E%E5%B7%9E%E5%AE%B6
- 細川晴国 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HosokawaHarukuni.html
- 細川晴元は何をした人?「将軍を追い出して幕府にかわって堺公方府をひらいた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/harumoto-hosokawa
- 【より道‐71】戦乱の世に至るまでの日本史_「足利一門」三管領・細川氏 - note https://note.com/vaaader/n/nd4c48f30c471
- 細川晴元(ほそかわ はるもと) 拙者の履歴書 Vol.67~管領の座から転落、激動の宿命 - note https://note.com/digitaljokers/n/na9233d991bf6
- 細川晴国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%99%B4%E5%9B%BD
- 畿内を駆ける!細川晴国―知られざる悲運の若武者【室町時代ゆっくり解説#21】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wyf0O8TJpKo
- 特別展おすすめ資料(3)(ブログ) SHIMOHAKU Web Site - 下関市立歴史博物館 https://www.shimohaku.jp/blog241020091636.html
- 鴨山城(岡山県浅口市鴨方町鴨方) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html
- 細川通董(ほそかわみちただ)公墓所 | 長川寺 【公式サイト】は岡山県浅口市鴨方にある曹洞宗のお寺です。 https://chosen-ji.com/?page_id=173
- 毛利元就が結ぶ石見銀山と嚴島神社 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/video.data/R2sekaiisannkouza_siryou.pdf
- 備中兵乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%85%B5%E4%B9%B1
- 【特集】毛利元就の「三矢の訓」と三原の礎を築いた知将・小早川隆景 | 三原観光navi | 広島県三原市 観光情報サイト 海・山・空 夢ひらくまち https://www.mihara-kankou.com/fp-sp-sengoku
- 備中 杉山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bicchu/sugiyama-jyo/
- 杉山城(岡山県浅口市鴨方町大字小坂東) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html
- 高梁川流域連盟 細川通董墓所|Takahashi River Basin League https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%EF%BC%88%E5%8F%B2%E8%B7%A1%EF%BC%89/%E6%B5%85%E5%8F%A3%E5%B8%82/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%80%9A%E8%91%A3%E5%A2%93%E6%89%80/
- 浅口市 戦後時代武将 細川通董墓所 - 高梁川流域デジタルアーカイブ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Y6pkYFBgA3c
- 長川寺の歴史 | 長川寺 【公式サイト】は岡山県浅口市鴨方にある曹洞宗のお寺です。 https://chosen-ji.com/?page_id=46
- 長府細川家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%BA%9C%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%AE%B6