飯尾乗連
飯尾乗連は今川義元家臣で遠江引間城主。桶狭間の戦いで戦死したとされる。松下加兵衛の主であり、若き日の秀吉と間接的な接点があった。
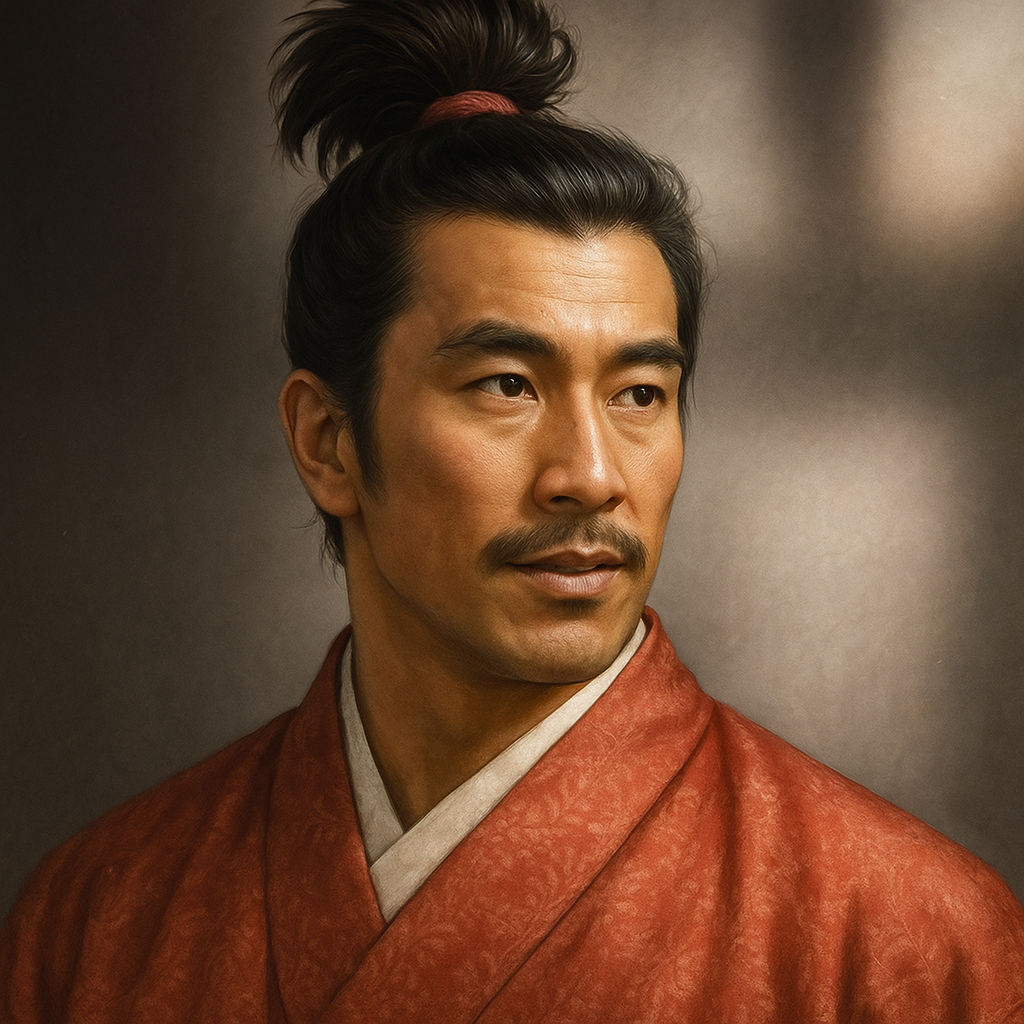
戦国武将・飯尾乗連の実像:遠江国衆の興亡と桶狭間の衝撃
序章:飯尾乗連という武将
本報告書は、戦国時代の遠江国において今川氏の重臣として活動した武将、飯尾乗連(いのお のりつら)の生涯と、その歴史的背景を詳細に解明することを目的とする。利用者より提供された情報、すなわち飯尾乗連が今川家臣であり、賢連の子、豊前守と称し、松下加兵衛らを寄騎としていたこと、そして桶狭間の戦いで戦死したとされる点を起点とし、現存する史料に基づいてその実像に迫る。
飯尾乗連単独での研究は決して多くはない。しかしながら、その子である飯尾連龍やお田鶴の方の悲劇的な逸話、あるいは寄騎であった松下氏と若き日の豊臣秀吉との関連など、著名な歴史事象の周辺に位置する人物を丹念に追うことは、戦国時代の地域社会や武士団の様相をより深く理解する上で不可欠である。特に、中央の大きな歴史的潮流の中で、地方の武士がどのように生き、そして時代の波に翻弄されたかを示す好例として、飯尾乗連の研究は現代においても意義を持つと言えよう。本報告では、飯尾氏の出自から説き起こし、乗連の活動、そしてその死後の飯尾氏の運命を辿ることで、一人の武将とその一族を通して戦国時代の一断面を明らかにする。
第一部:飯尾氏の出自と遠江国
一、飯尾氏のルーツと家系
飯尾氏の出自を辿ると、その淵源は渡来系の氏族である三善氏にまで遡るとされている 1 。三善氏は、古くから朝廷に仕え、算道や法律などの実務的な学問を家学とした家系であり、飯尾氏もまた室町幕府において奉行衆を務めた家柄であったと伝えられている。この事実は、飯尾氏が単なる地方の武辺一辺倒の土豪ではなく、中央政権との繋がりを持ち、一定の教養や実務能力を備えた家系であったことを示唆している。今川氏が遠江国の支配を確立する過程で、このような背景を持つ飯尾氏を招聘したことは、戦略的にも理に適った判断であったと考えられる。史料 には「三善為康→・・・・飯尾長連(駿府下向)」という系譜が断片的ながら示されており、三善姓から飯尾姓への変遷と、駿河国への移住、そして遠江国へと活動の場を移した経緯がうかがえる。
飯尾氏が遠江国の歴史において明確にその名を現すのは、今川氏親(うじちか)の時代である。飯尾善左衛門尉長連(おさつら)、すなわち乗連の祖父にあたる人物が、引間(ひくま、後の浜松)の奉行としてその地に在ったことが記録されている 2 。長連は元来、三河国の有力氏族である吉良氏の家臣として浜松荘の代官を務めていたが、今川義忠(よしただ、氏親の父)による遠江侵攻を支援し、その戦いの中で命を落としたとされる 2 。この飯尾長連の行動と犠牲が、飯尾氏と今川氏の間に主従関係を築く端緒となった。史料 1 によれば、長連の没年は1476年(文明8年)とあり、これは今川義忠が遠江国塩買坂で戦死した年と一致しており、両者の運命が深く結びついていたことを物語っている。
長連の死後、一時的に大河内備中守貞綱が引間城主となったが、彼は後に今川氏親に反旗を翻し、その地位を失った 2 。その後、今川氏の命により、戦死した長連の子である飯尾賢連(ただつら、乗連の父)が吉良氏から浜松荘の代官に任じられ、引間城に入った 2 。これにより、飯尾氏による引間支配の基礎が確立され、以後、引間城は賢連から乗連、そしてその子連龍へと受け継がれていくことになる。
飯尾氏略系図
|
人物名 |
続柄・役職など |
主な事績・生没年(判明分) |
典拠例 |
|
(三善為康) |
飯尾氏遠祖とされる |
|
S6 |
|
飯尾長連 |
乗連の祖父、善左衛門尉 |
今川義忠の遠江侵攻を支援し戦死(1476年没) |
S2, S3, 1 |
|
飯尾賢連 |
乗連の父、善四郎 |
引間城主、浜松荘代官 |
S5, 2 |
|
飯尾乗連 |
本報告書の主題、善四郎、豊前守 |
引間城主、今川義元に仕える、桶狭間の戦いに参陣し戦死(永禄3年・1560年?諸説あり) |
S2, S13, S19 |
|
松井宗親室 |
乗連の娘 |
松井宗親(左衛門)に嫁ぐ |
S2, 4 |
|
飯尾連龍 |
乗連の子、善四郎、豊前守 |
引間城主、今川氏真に反旗を翻し、後に謀殺される(永禄8年12月20日・1566年1月11日没) |
S1, S4, 4 |
|
お田鶴の方 |
連龍の妻、鵜殿長持の娘とされる |
連龍死後、引間城を守り徳川家康軍と戦い討死(永禄11年・1568年)、「椿姫」 |
S16, 9 |
|
辰之助 |
連龍の子 |
氏真の娘との婚姻話が連龍謀殺の一因との説あり |
S1, S15 |
|
辰三郎 |
連龍の子 |
|
S1 |
|
義廣 |
連龍の子 |
浜松まつりの起源伝説に関連(近年の研究では創作とされる) |
S1, S16 |
|
正宅(弥太夫) |
連龍の子 |
天正年間に移住し、源氏山と名付ける |
S1 |
この系図は、飯尾氏が数代にわたり遠江国で活動し、婚姻関係を通じて他の有力氏族とも結びつきながら家名を維持しようとした様相を示している。特に、乗連の父祖が今川氏との関係を築き、乗連自身がその中で重きをなした一方で、子・連龍の代には主家との対立に至るという、戦国武家の盛衰の典型を垣間見ることができる。
二、今川氏による招聘と引間城
引間城は、後の浜松城の「古城」と呼ばれる部分にあたり 3 、遠江国の西部、三河国との国境にも近い交通の要衝に位置していた。そのため、今川氏が遠江国全域の支配を安定させ、さらに西方の三河国への影響力を確保する上で、この地を抑えることは極めて重要な戦略的意味を持っていた。信頼のおける家臣を引間城に配置することは、今川氏の遠江経営における喫緊の課題であった。
飯尾氏が元々室町幕府の奉行人であったという出自 は、彼らが単なる武勇に優れた武士であるだけでなく、統治や行政に関する実務能力にも長けていた可能性を示唆している。今川氏が、かつて吉良氏の所領であった浜松荘の支配を円滑に進めるにあたり、代官として飯尾氏を起用したことは、彼らのそうした能力への期待があったからこそと考えられる。史料 2 によれば、今川氏親は遠江国の在地土豪たちの勢力に苦慮しており、その抑えとして飯尾氏を招いたと記されている。これは、飯尾氏が今川氏の遠江経営における尖兵、あるいは支配体制を安定させるための楔としての役割を期待されていたことを明確に示している。
飯尾氏の立場を考える上で興味深いのは、彼らが今川家中でどのような位置づけにあったかという点である。飯尾氏は、今川氏が遠江国に進出する以前からの在地領主ではなく、外部から招聘された家系である 2 。当初は吉良氏の代官であり、その後、今川氏の支配体制に組み込まれたという経緯を持つ。これは、今川氏の勢力拡大に伴い、様々な出自を持つ武士団がその支配体制に編入されていった戦国時代の典型的な事例の一つと言える。乗連の代までは比較的安定した主従関係が維持されていたと考えられるが、その子である連龍の代になると、今川本家の衰退と軌を一にするかのように、主家への離反の動きを見せることになる 4 。この行動の背景には、譜代家臣としての意識の希薄さがあったのか、あるいは激動する情勢の中で家名を存続させるための現実的な判断があったのか、一概には断定できない。しかし、こうした飯尾氏の立場性は、後の連龍の行動を理解する上での一つの伏線となり得るため、乗連の時代の今川家との関係性をより深く考察する必要がある。彼らが譜代の家臣とは異なる背景を持つ「外様」的な存在であったとすれば、主家の勢力にかげりが見えた際に、より自律的な行動を選択する余地が大きかったのかもしれない。
第二部:飯尾乗連の生涯
一、今川家臣としての乗連
飯尾乗連は、父・賢連から家督を相続し、遠江国引間城主となった 2 。通称は善四郎を名乗り、官位としては豊前守を称したことが知られている。彼は主君である今川義元に仕え、遠江国における今川氏の勢力基盤の維持と拡大に貢献したものと考えられる。
乗連の具体的な活動を示す史料の一つとして、彼が遠江国宇間郷向宿(現在の浜松市中央区向宿町周辺か)に存在した寺院、受領庵に対して寄進を行った記録が挙げられる。この事実は、乗連が引間城主として一定の領域支配を行い、その範囲内の寺社に対しても影響力を行使し、保護を加えていたことを示す具体的な証左である。この寄進状が現存していれば、その文面から乗連自身の花押(署名の一種)や、寄進の具体的な内容、日付などを知ることができ、当時の彼の信仰心や領内統治の実態、さらには当時の武家文書の様式などを窺い知る上で極めて貴重な史料となるであろう。
また、軍事面での活動としては、天文14年(1545年)に今川義元と関東の雄・北条氏康との間で繰り広げられた「狐橋合戦(きつねばしがっせん)」において、飯尾乗連が奮戦したと伝える記述がある 5 。この戦いは、今川氏と北条氏が駿河国東部を巡って激しく争った一連の抗争の一部であり、乗連がそのような重要な戦役に動員され、かつ善戦したという記録は、彼の武将としての側面を明らかにする上で注目される。史料 6 に見られる今川義元発給の感状写しは、宛所こそ天野安芸守となっているものの、同じく狐橋合戦に関するものであり、当時の戦況や論功行賞の様子を補完する情報を提供してくれる。
しかしながら、飯尾乗連の具体的な軍功や政務に関する記録は、総じて断片的と言わざるを得ない。彼が主君・今川義元からどの程度の信任を得ていたのか、また遠江国衆の中でどのような地位を占めていたのかを正確に把握することは、現存史料のみからは困難である。乗連は引間城主として、今川氏の遠江支配における重要な戦略拠点の一つを任されていたことは間違いない。前述の寺社への寄進状の存在も、彼が在地領主としての権限を確かに有していたことを示している。狐橋合戦での善戦が事実であれば、武勇に対する一定の評価も受けていたはずである 5 。
一方で、今川家の中枢における具体的な役職名や、義元の側近として常に近侍していたことを示すような史料は、現在のところ確認されていない。このことは、乗連が主に遠江国における地域支配に特化した役割を担っていた武将であった可能性を示唆している。彼の評価は、中央政界での華々しい活躍や、主君の側近くでの献策といった形ではなく、むしろ在地領主として、任された地域を堅実に統治し、軍事動員の際には忠実に兵を率いて参陣するという、実直な働きにあったのかもしれない。戦国時代の武将の評価は、その立場や役割によって多岐にわたるものであり、乗連のような地域に根差した武将の存在もまた、今川氏のような大勢力の支配体制を支える上で不可欠であったと言えよう。
二、松下加兵衛との関係と豊臣秀吉の萌芽
飯尾乗連の配下には、後に豊臣秀吉が最初に仕えた人物として知られる松下加兵衛(之綱)がいた。松下氏は飯尾氏の寄騎(よりき)、あるいは寄子(よりこ)であったとされている 7 。寄騎とは、比較的大きな武家の軍事指揮下に属する小規模な領主や武士のことであり、この関係は飯尾乗連が松下氏を自身の軍事力の一部として従える立場にあったことを明確に示している。松下加兵衛は、遠江国頭陀寺(ずだじ)城(現在の静岡県浜松市中央区)を本拠としていた 7 。
この松下加兵衛に、木下藤吉郎と名乗っていた若き日の豊臣秀吉が仕えていたという逸話は、広く知られているところである 7 。秀吉が松下氏に仕えたのは、10代半ば頃、天文年間(1532年~1555年)の後半から永禄年間(1558年~1570年)初頭にかけてのことと推測される。史料 には、引間城(飯尾氏の本拠地)で催された宴席で、秀吉が猿の物真似をして栗を食べる芸を披露し、それを松下加兵衛が気に入って召し抱えるきっかけになったという興味深い逸話も紹介されている。この逸話の真偽はともかくとして、もし秀吉が松下氏の供として引間城に出入りしていたとすれば、彼は飯尾乗連の勢力圏内でそのキャリアの第一歩を踏み出したことになる。
さらに興味深い史料として、「今川手負注文(いまがわておいちゅうもん)」と呼ばれる文書の存在が指摘されている 5 。これは、前述の天文14年(1545年)の狐橋合戦における今川方の負傷者を記録したリストとされ、その中に「木下藤次郎(きのした とうじろう)矢傷」という記述が見られるという。もしこの「木下藤次郎」が後の豊臣秀吉(木下藤吉郎)と同一人物であるとすれば、彼の知られている経歴よりもかなり早い時期に、しかも今川方の、飯尾乗連が率いた可能性のある部隊に属して戦闘に参加し負傷したことになる。この点は、秀吉の初期の経歴を考える上で極めて重要であり、慎重な検討を要する。
「今川手負注文」における木下藤次郎に関する考察
|
項目 |
内容 |
典拠例 |
|
史料の記述 |
「今川手負注文」(天文14年・1545年、狐橋合戦に関連するとされる)。飯尾乗連の部隊、あるいはその関連部隊に「木下藤次郎矢傷」との記載あり。 |
5 |
|
同一人物説の根拠 |
姓(木下)、名(藤次郎と藤吉郎の音韻的類似性)、飯尾氏との関連(後の松下氏への仕官という間接的な繋がり)。 |
5 |
|
同一人物説への疑義 |
年齢の問題: 豊臣秀吉の生年を天文6年(1537年)とすると、天文14年(1545年)には満8歳となる。この年齢で戦闘に参加し、負傷者リストに載ることは極めて考えにくい。<br> 呼称の問題: 「藤次郎」という呼称が、後の「藤吉郎」と同一人物を指すとしても、当時の命名慣習や通称の使用実態との整合性を検討する必要がある 5 。<br> 史料の信憑性: 「今川手負注文」とされる史料そのものの現存状況、書写年代、他の確実な史料との比較検討が必要。一次史料としての確実性がどの程度担保されているかが鍵となる。 |
|
|
結論 |
現時点では、この「木下藤次郎」が後の豊臣秀吉であると断定するには証拠が著しく不十分であり、特に年齢的な矛盾点が大きい。偶然の一致、あるいは同姓同名に近い別人の可能性も考慮すべきであり、今後の史料発見や研究の進展が待たれる。 |
|
この「木下藤次郎」の記述は、豊臣秀吉の謎に包まれた青年期に関する通説に一石を投じる可能性を秘めており、歴史ファンの関心を強く惹くものではある。しかしながら、史料批判の観点からは、特に年齢という基本的な事実との整合性が取れない以上、安易に同一人物と見なすことはできない。この表によって論点を整理し、多角的な情報を提供することで、歴史研究が一つの史料から様々な可能性と疑問が生じうる奥深いものであることを示している。
たとえ「今川手負注文」の木下藤次郎が豊臣秀吉でなかったとしても、秀吉が飯尾乗連の寄騎である松下氏に仕えたという事実は、歴史の大きな流れの中で興味深い伏線となっている。秀吉は松下之綱に仕えた後、織田信長に転仕し、やがて天下人へと駆け上るが、その過程でかつての主君であった松下之綱を召し出し、厚遇したことが知られている 7 。この恩義を忘れない姿勢は、秀吉の人間性の一面を示すものと言えよう。松下氏は飯尾氏の寄騎であったため 7 、秀吉は間接的ながら飯尾氏の勢力範囲内で活動していたことになる。秀吉が後に天下統一事業を進める中で、この遠江国での若き日の経験や、そこで得た人脈、あるいは地域の情報などが、彼の政策や戦略に何らかの影響を与えた可能性は皆無とは言えない。例えば、飯尾氏の旧臣や、その周辺の人物で、後に秀吉に仕えた者がいなかったか、あるいは遠江国衆の動向を把握する上で、かつての縁が役立ったのではないか、といった点は、本報告書の直接の範囲を超えるかもしれないが、飯尾乗連という一地方武将の存在が、巡り巡って中央の歴史にも微かながら影響の糸を投げかけていた可能性を示唆している。
三、桶狭間の戦い
永禄3年(1560年)5月、今川義元は数万とも言われる大軍を率いて尾張国への侵攻を開始した。この大規模な軍事行動の目的は、上洛にあったとも、尾張の織田信長を討伐し勢力圏を拡大することにあったとも言われるが、いずれにせよ今川氏の威勢を天下に示すものであった。飯尾乗連もまた、今川軍本隊の一員としてこの歴史的な戦役に従軍したことが記録されている。
これに先立つ天文21年(1552年)頃、尾張国の有力国衆であった山口教継(やまぐち のりつぐ)が織田信長から離反し今川方に寝返った際、飯尾乗連は葛山長嘉(かづらやま ながよし)、岡部元信(おかべ もとのぶ)、三浦義就(みうら よしなり)ら今川氏の諸将と共に軍勢を率い、山口氏の拠点である鳴海城(現在の名古屋市緑区)に入ったとされている。この事実は、乗連が桶狭間の戦い以前から、尾張方面における今川氏の軍事活動に継続的に関与し、一定の役割を担っていたことを示している。
しかし、今川義元率いる本隊は、同年5月19日、油断していたところを桶狭間山(あるいは田楽ヶ窪)において織田信長の奇襲を受け、総大将の義元自身が討死するという衝撃的な結末を迎えた。これにより今川軍は総崩れとなり、戦国時代の勢力図を大きく塗り替える転換点となった。
この桶狭間の戦いにおける飯尾乗連の最期については、複数の説が存在し、判然としない部分が多い。
飯尾乗連の桶狭間の戦い(及びその後)における最期に関する諸説
|
説 |
没年(推定) |
根拠・状況 |
典拠例 |
|
説1:桶狭間にて戦死 |
永禄3年(1560年) |
今川義元本隊に所属しており、本隊壊滅時に他の多くの将兵と共に討死したとする説。利用者提供情報もこれに合致する。 |
S13 |
|
説2:桶狭間から落ち延びた |
不明 |
戦死したとも、あるいは戦場から落ち延びることに成功したとも言われる。もし落ち延びていた場合、その後の動向が焦点となるが、具体的な記録は乏しい。 |
S19 |
|
説3:永禄8年、子・連龍と共に今川氏に討たれた |
永禄8年(1565年) |
息子の飯尾連龍が今川氏真に反旗を翻し、駿府で謀殺された際に、父である乗連も共に討たれた、あるいは連座して処刑されたとする説。この説が正しければ、乗連は桶狭間後も5年間生存していたことになる。 |
S19 |
史料 では、桶狭間の戦いの前哨戦において、織田方の鷲津砦を守っていた飯尾定宗(さだむね)が討死し、飯尾尚清(ひさきよ)が敗走したと記されているが、これらの人物は飯尾豊前守乗連とは別系統の飯尾氏であるか、あるいは同族であっても別部隊として行動していたと考えられる。乗連自身は今川義元の本隊に所属していたことが確認されている。
乗連の最期に関するこれらの諸説は、彼の生涯を締めくくる重要な出来事でありながら、確定的な結論を出すことが難しい状況を示している。もし説3の「永禄8年(1565年)死亡説」が有力であるとすれば、乗連は桶狭間の大敗を生き延び、その後5年間にわたって存命し、息子である連龍が今川氏に対して反逆を企てた際に、何らかの形で関与した、あるいはその影響を受けた可能性が出てくる。これは、飯尾乗連という人物像を大きく変える可能性を秘めており、今後の研究によって新たな史料が発見されることが期待される。
桶狭間の戦いにおける今川軍の具体的な編成や、その中での飯尾乗連率いる部隊の規模、位置づけ、役割については、残念ながら詳細な記録は乏しい。今川軍は数万の大軍であり、駿河、遠江、三河の国衆を中心とした連合軍の性格を持っていた 8 。乗連が「本隊」に所属していたということは、今川義元の直属に近い、信頼された部隊の一翼を担っていた可能性が高いが、その中での序列や具体的な任務が何であったのかは不明である。また、天文21年に鳴海城に入った際に名を連ねていた他の武将たち(葛山長嘉、岡部元信、三浦義就など)と、桶狭間の戦いにおいてどのような連携関係にあったのかも詳らかではない。これらの情報は現存する史料からは判明しにくいものの、飯尾乗連の今川軍における立場を推測する上で重要な問いである。桶狭間の戦いという歴史的転換点における彼の具体的な行動を詳細に復元することは困難であるが、可能な範囲で状況証拠から推察を試みることは、戦国期の国衆の動向を理解する上で意義深い作業と言えるだろう。
第三部:飯尾乗連亡き後の飯尾氏
一、嫡男・飯尾連龍の時代
飯尾乗連の死後(桶狭間の戦いでの戦死説が一般的であるが、前述の通り異説も存在する)、その嫡男である飯尾連龍(つらたつ)が家督を継承し、引間城主となった 4 。連龍もまた、父と同じく善四郎を通称とし、豊前守を名乗ったとされる。
しかし、連龍が家督を継いだ時期は、今川家にとってまさに激動の時代であった。永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで総大将・今川義元が織田信長に討たれるという衝撃的な敗北を喫した後、今川氏の勢力は急速に衰退の一途を辿る。義元の子・今川氏真(うじざね)が後を継いだが、父ほどの器量はなく、領国内の求心力は著しく低下し、各地で動揺が広がった 4 。
このような状況下で、遠江国においても今川氏の支配に対する不満や離反の動きが顕在化し始める。永禄6年(1563年)頃になると、飯尾連龍もまた今川氏から離反する動きを見せた 4 。その背景には、隣国・三河国で台頭し、織田信長と同盟を結んで今川氏からの独立を確固たるものにしつつあった松平元康(後の徳川家康)への内通があったとされる 4 。一説には、氏真が三河へ出兵した際に連龍が病と称して勝手に帰国し、さらに白須賀宿(現在の静岡県湖西市)に放火したという疑惑をかけられたことが離反の直接的な原因であったともいう 4 。
この連龍の離反に対し、今川氏真は軍勢を派遣して引間城を攻撃した。この戦いは「遠州忩劇(えんしゅうそうげき)」あるいは「引間一変」などと呼ばれる遠江国における一連の反乱の一つであり、今川方は主将の新野親矩(にいの ちかのり)が戦死するなど苦戦を強いられ、引間城を攻略することはできなかった 2 。結果として、両者は一時的に和睦し、連龍は今川氏に帰順したかのように見えた 2 。
しかし、一度生じた亀裂は容易には修復されなかった。今川氏真は連龍に対する疑念を払拭することができず、永禄8年(1565年)12月、ついに連龍を駿府の今川館に呼び寄せ、謀殺するという強硬手段に出た 2 。一説によれば、氏真の娘と連龍の子である辰之助との婚姻話を持ちかけ、その祝宴にかこつけて誘い出し、だまし討ちにしたとも伝えられている。この悲劇的な最期は、今川氏の支配体制の脆弱化と、猜疑心に駆られた氏真の苦境を象徴する出来事であった。
飯尾連龍の離反は、単なる裏切り行為として片付けることはできない。その背景には、桶狭間の戦い以降急速に変化した遠江国におけるパワーバランスが存在した。今川氏の権威が失墜し、西からは徳川家康、東からは武田信玄という新たな勢力が遠江国に触手を伸ばしつつあった。このような状況下で、遠江国内の国衆たちは、生き残りをかけて自らの進むべき道を選択せざるを得なかった。連龍が徳川氏に内通したのは、こうした大きな歴史の流れの中で、自らの所領と家名を保つための現実的かつ戦略的な判断であった可能性が高い。父・乗連が今川義元に対して(少なくとも表向きは)忠実に仕えたとされる姿とは対照的であるが、それは時代の変化、そして主君の器量の違いを色濃く反映したものと言えるかもしれない。連龍の行動は、戦国時代の国衆が常に直面していた、主家への忠誠と自家の存続という二律背反の狭間での苦悩を体現している。
二、お田鶴の方と引間城の終焉
飯尾連龍が駿府で非業の死を遂げた後、引間城に残された人々は大きな動揺に見舞われた。その中で、城の運命を一身に背負うことになったのが、連龍の妻・お田鶴の方(おたづのかた)であった。彼女は三河国上ノ郷城主・鵜殿長持(うどの ながもち)の娘とされ、その母は今川義元の妹または義妹にあたるとも伝えられている 9 。この血縁関係が事実であれば、お田鶴の方は今川家と深い繋がりを持っていたことになるが、近年の研究ではこの点に疑問も呈されている 9 。
夫・連龍の死後も、お田鶴の方は屈することなく引間城に留まり、城兵を鼓舞して城の守りを固めたとされる 9 。やがて永禄11年(1568年)12月、遠江国平定を目指す徳川家康が大軍を率いて引間城に来攻した。この時、お田鶴の方は自ら武具をまとい、侍女たちにも武装させ、城兵の先頭に立って防戦の指揮を執ったと伝えられている。彼女の勇猛果敢な戦いぶりは「椿姫(つばきひめ)」という異名と共に、多くの記録や伝説として後世に語り継がれることとなった 9 。
徳川軍の猛攻に対し、お田鶴の方と城兵たちはしばしば城から討って出て激しく抵抗し、一時は家康軍を押し返すほどの奮戦を見せたという。しかし、衆寡敵せず、城は次第に追い詰められていく。最期を悟ったお田鶴の方は、緋縅(ひおどし)の鎧に身を固め、薙刀を振るって侍女たちと共に敵陣に突入し、壮絶な討死を遂げたとされる 9 。このお田鶴の方の死をもって、飯尾氏による引間城支配は完全に終焉を迎え、城は徳川家康の手に落ちた。家康はその後、引間城を拡張・改修し、浜松城と名を改めて遠江支配の拠点とした 2 。
飯尾氏の血筋としては、連龍とお田鶴の方の間には、辰之助(たつのすけ)、辰三郎(たつさぶろう)、義廣(よしひろ)、そして正宅(まさいえ、弥太夫とも)といった子らがいたと伝えられている。しかし、彼らのその後の詳細な動向については不明な点が多い。史料 の記述によれば、次男とされる飯尾弥太夫(正宅)が天正年間(1573年~1592年)に遠江国内の別の地に移住し、その地を飯尾氏が源氏の血を引く(三善氏は清和源氏の一流ともされる)という伝承をもって源氏山と名付け、江戸幕府三代将軍徳川家光に言上したという話が残されているが、これは飯尾氏本宗家の滅亡後の後日談である。
お田鶴の方の抵抗は、単なる玉砕戦として片付けることはできない。彼女の行動の背景には、どのような思いがあったのだろうか。夫・連龍は今川氏真によって謀殺されたため、その氏真に対して最後まで忠義を尽くすという動機は薄いように思われる。しかし、前述の通り、彼女自身が今川家の血を引くという説もあり、もしそれが事実であれば、今川家への複雑な思いが彼女の行動に影響した可能性も否定できない。あるいは、飯尾家の当主代行として、家臣や領民を守るための最後の務めとして、武家の妻としての意地と誇りを示したものだったのかもしれない。徳川家康からの降伏勧告を「女と雖(いえど)も弓馬の家の者」として拒否したとされる言葉 9 は、まさに武家の女性としての気概を象徴している。彼女の奮戦と悲劇的な死は、飯尾氏の滅亡を鮮烈に彩り、後世の人々の記憶に強く残り、様々な講談や伝説の格好の題材となった。それはまた、戦国という時代に生きた女性の、一つの壮絶な生き様を示すものとして、今日まで語り継がれているのである。
第四部:飯尾乗連をめぐる史料と顕彰
一、関連古文書の分析
飯尾乗連とその一族に関する歴史を紐解く上で、現存する古文書は極めて重要な手がかりとなる。乗連自身が発給した文書としては、前述の通り、遠江国宇間郷向宿(現在の浜松市中央区向宿町周辺か)に存在した寺院、受領庵(じゅりょうあん)に対して寄進を行ったことを示す書状が知られている。この寄進状が現存し、その内容を詳細に分析することができれば、寄進の具体的な目的、日付、宛所、そして何よりも差出人である飯尾乗連自身の花押(かおう、署名の一種)などを確認することができる。これらは、乗連の信仰心や領内支配の実態、さらには当時の武家文書の様式などを具体的に知る上で、第一級の史料的価値を持つ。
また、天文14年(1545年)の狐橋合戦に関連するとされる「今川手負注文」も注目される史料である 5 。この文書については、先に「木下藤次郎」という記述の真偽を巡って考察したが、史料全体としての信憑性の検証はもとより、もし飯尾乗連がこの合戦に参加していたならば、彼が率いた部隊の他の構成員に関する情報や、部隊の規模、損害の程度などが記されている可能性も探る必要がある。
その他、直接飯尾乗連に言及するものではなくとも、関連する文書は存在する。例えば、史料 6 で言及されている天文24年(1555年)付の今川義元感状写(天野安芸守殿宛)は、同じく狐橋合戦に関するものであり、当時の今川軍の動向や論功行賞の状況を知る上で参考となる。飯尾氏全体に関する古文書については、浜松市博物館が発行した研究報告書「遠州引間飯尾氏の興亡」 10 などで、ある程度まとめられている可能性があり、こうした先行研究の成果も参照することが不可欠である。ただし、これらの出版物は直接の一次史料ではなく、研究者による編纂・解釈を経た二次史料である点には留意が必要である。
二、後世の記録と伝承
飯尾乗連とその一族は、古文書だけでなく、後世の記録や地域に伝わる伝承の中にもその名を留めている。静岡県浜松市中央区(旧東区)に位置する東漸寺(とうぜんじ)には、飯尾乗連の供養塔が存在すると伝えられている。また、同寺は飯尾氏、特にその子である飯尾連龍を篤く祀っているとも言われ、連龍の墓所も同寺にあるとされる 4 。これらの供養塔や寺院に残る伝承は、飯尾氏が滅亡した後も、地元の人々によってどのように記憶され、供養されてきたかを示す貴重な手がかりとなる。史料 には、飯尾氏の墓塔とされる五輪塔の形状に関する具体的な記述(上部のみ宝篋印塔状相輪が伸びるタイプ、石材は伊豆石とは異なり比較的明るく少々赤みがある等)も見られ、美術史的、あるいは考古学的な観点からの分析も可能かもしれない。
さらに興味深いのは、史料 に紹介されている、東漸寺の住職が飯尾連龍の末裔を探しているという現代の逸話である。これは、歴史上の人物の子孫が数百年を経た現代において、先祖の顕彰や供養にどのように関わっているのか、あるいは関わろうとしているのかという、歴史と現代を繋ぐ一つの視点を提供してくれる。
飯尾乗連自身に関する直接的かつ大規模な顕彰は、現時点では多く確認されていないかもしれない。しかし、飯尾氏一族、特にその子である飯尾連龍や、その妻であるお田鶴の方(椿姫)の悲劇的な物語は、引間城、すなわち後の浜松城の歴史の一部として、地域社会で語り継がれている。乗連は、その飯尾氏という一族の歴史の中で、今川氏の勢力下で引間城を維持し、桶狭間の戦いに参陣するなど、重要な役割を果たした人物として位置づけられるべきである。東漸寺に残る供養塔の存在 は、彼が歴史の中で完全に忘れ去られたわけではないことを示している。
地域の歴史の中で、飯尾氏は「浜松城前史」における重要な担い手として記憶されている 3 。飯尾乗連もまた、その文脈の中で理解されるべき存在であろう。史料が乏しい人物について、後世の顕彰や伝承がどのように形成され、時には変容しながら受け継がれていくのかを考察することもまた、歴史研究の重要な一環である。飯尾乗連とその一族の物語は、古文書に残る客観的な記録と、地域に根付いた伝承という二つの側面から光を当てることで、より豊かな歴史像として立ち現れてくるに違いない。
結論:歴史における飯尾乗連の評価
飯尾乗連は、戦国時代の遠江国において、今川氏配下の有力な国衆として引間城を拠点に活動した武将である。その出自は室町幕府の奉行衆を務めた三善氏に遡り、祖父・飯尾長連の代から今川氏との関係を築き、父・賢連を経てその地位と役割を継承した。乗連は、主君・今川義元の指揮下で軍事活動に従事し、特に永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いには今川軍本隊の一員として参陣したことが特筆される。その最期については、桶狭間での戦死説が有力視されるものの、異説も存在し、今川家の盛衰と深く関わった生涯であったことは間違いない。また、寄騎として松下加兵衛を抱え、その松下氏に若き日の豊臣秀吉が仕えたという事実は、間接的ながらも後の天下人と微かな接点を有していたことを示唆しており、歴史の偶然と必然を感じさせる。
戦国期の遠江国における飯尾氏の役割は、今川氏による同国支配を支える重要な支柱の一つであったと言える。しかし、その立場はあくまでも今川氏という巨大な権力構造に従属するものであり、主家の勢力変動は飯尾氏自身の運命に直結した。乗連の時代は比較的安定した主従関係が維持されていたように見受けられるが、その子・連龍の時代には、今川氏の急激な衰退と徳川氏の台頭という外部環境の激変の中で、主家との対立、そして最終的には謀殺と城の陥落による一族の滅亡へと至る。これは、戦国時代の多くの国衆が常に直面していた、主家への忠誠と自家の存続という厳しい現実を色濃く反映している。
飯尾乗連に関する今後の研究課題としては、まず彼自身が発給したとされる古文書、特に受領庵への寄進状などの現物の確認と、その内容のより詳細な分析が挙げられる。これにより、彼の花押の確定や、具体的な領地支配の実態、信仰心などが明らかになる可能性がある。また、「今川手負注文」とされる史料についても、その現物の確認と史料批判、そして内容の総合的な検討が求められる。桶狭間の戦いにおける飯尾乗連率いる部隊の具体的な動向や規模に関する新たな史料の発見も期待されるところである。さらに、飯尾氏と、井伊氏、天野氏、松井氏といった遠江国の他の有力国衆との関係性について、より詳細な研究が進めば、戦国期における地域社会の構造や武士団の動態がより明確になるであろう。
飯尾乗連は、戦国時代の歴史の表舞台で華々しい活躍を見せた英雄ではないかもしれない。しかし、彼の生涯と彼が率いた飯尾氏の興亡は、地方の国衆が中央の巨大権力の動向に翻弄されながらも、必死に生き残りを図ろうとした戦国時代の一つの典型を示している。そのような視点から飯尾乗連とその時代を見つめ直すことは、戦国史の理解をより深く、豊かなものにする上で、依然として重要な意義を持つと言えるだろう。
引用文献
- 戦国!室町時代・国巡り(18)遠江編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/nc20ee9d6b843
- 引間城 と 飯尾氏四代 l 遠江守護 遠州鎧仁會 代表のブログ https://yoroikokoro.hamazo.tv/e6532025.html
- 徳川家康を巡る旅~浜松編~/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/tokugawaieyasu-aichi-shizuoka/ieyasu-journey-hamamatsu/
- 飯尾連龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E5%B0%BE%E9%80%A3%E9%BE%8D
- 今川手負注文と天正18年の朱印状に見る秀吉の前身① - 戦国徒然 ... https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/16817330663666052258
- Google Drive - historical_resource_rev063 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uhQErkLeU6Ckgow9p6rR9MH_My9QIeDExcPZnxXYK8E
- 松下之綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%B8%8B%E4%B9%8B%E7%B6%B1
- レジメ桶狭間 - 横浜歴史研究会 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2022/11/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E6%A1%B6%E7%8B%AD%E9%96%93.pdf
- お田鶴の方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E7%94%B0%E9%B6%B4%E3%81%AE%E6%96%B9
- 浜松市博物館報のご案内 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hamahaku/05publish/kanpoh.html