中島両以記文
豪商中島両以の『記文』は、江戸初期に戦国美濃の都市・経済史を記した自叙伝。道三・信長の記憶を再構築し、商人の経営哲学と地域アイデンティティを示す貴重な史料。
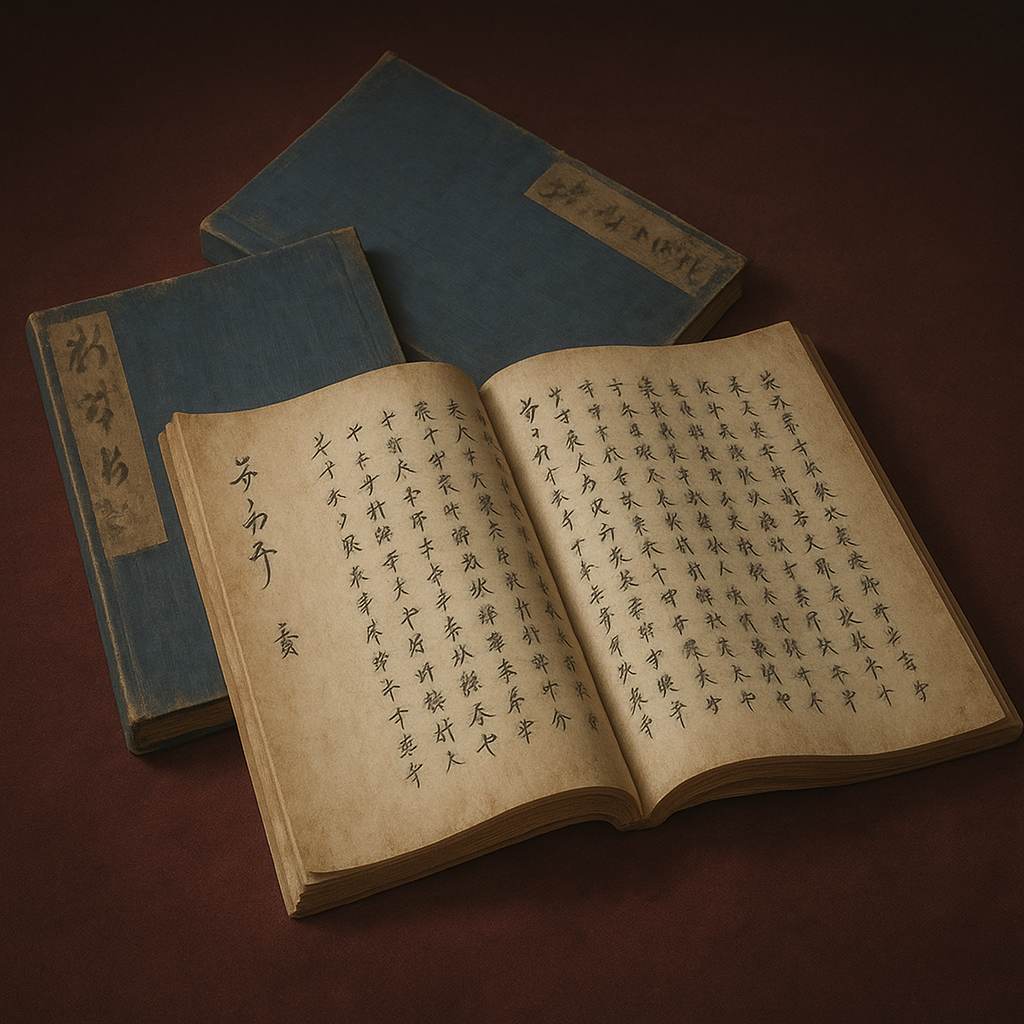
『中島両以記文』の総合的考察 ―江戸初期の豪商が見た美濃戦国時代の記憶―
第一章:序論 ―『中島両以記文』とは何か
史料の基本情報と本質的課題の提示
『中島両以記文』(なかじま りょうい きぶん)は、江戸時代前期の美濃国(現在の岐阜県)の豪商・中島両以(なかじま りょうい、1604年生)が、延宝3年(1675年)に刊行したとされる自叙伝である 1 。その内容は、中島家の由来、両以自身の成功譚、そして子孫への戒めとして町人としての心得を記したものであり、近世初期における商人階級の思想を知る上で貴重な史料とされている 2 。
しかし、この史料の真価を理解するためには、その構成の核心にある一つの特徴、すなわち著者が生きた「江戸時代前期」と、記述の主要な対象の一つである「戦国時代」との間に存在する、約一世紀にも及ぶ時間的な隔たりを認識することが不可欠である。両以が筆を執ったのは、斎藤道三や織田信長が美濃を支配した時代から100年以上が経過し、徳川幕府による泰平の世が確立された後であった。この時間的な「ズレ」こそが、『中島両以記文』を単なる一代記や家訓としてではなく、より深く多層的な歴史史料として分析するための鍵となる。
この時間的隔たりを考慮すると、『中島両以記文』は客観的な歴史記録というよりも、戦国時代の「社会的な記憶」が江戸時代という新たな社会秩序の中でいかに形成され、継承されたかを示す類稀な事例として浮かび上がる。中島両以にとって、斎藤道三による都市建設や織田信長の経済政策は、単なる過去の出来事ではなかった。それらは、自らが商いを営む岐阜という町の成り立ちを説明し、自身の事業の歴史的基盤を裏付けるための、いわば「創世神話」として機能していたのである。江戸時代の商人が、なぜ100年以上も前の戦国武将の事績に詳細に言及する必要があったのか。その動機は、過去の偉大な為政者の権威を引用することで、現在の町の正統性や自らの商業活動の歴史的連続性を確立しようとする意図にあったと考えられる。これは、客観的な歴史記述というより、自らのアイデンティティを輝かしい過去に接続するための、主観的で意図的な「物語り」の側面を強く持つ。この視座に立つことで、本史料の価値を「記述された事実の正確性」という一面的な基準だけでなく、「記憶のあり方とその機能」という、より高次の次元で捉えることが可能となる。
本報告書が解き明かす論点
本報告書は、以上の問題意識に基づき、『中島両以記文』について以下の論点を多角的に解き明かすことを目的とする。
第一に、なぜ一介の商人が記した私的な文書が、後世の『岐阜市史』などに引用され、岐阜の都市史や経済史を語る上で一級の史料として扱われるに至ったのか、その理由を具体的に検証する 3 。
第二に、『記文』の記述を通して、斎藤道三や織田信長といった戦国時代の出来事が、泰平の世に生きる江戸時代の人々、特に勃興しつつあった商人階級にとってどのような意味を持ち、いかに解釈されていたのかを解明する。
第三に、本書を近世初期に自らの社会的地位と職業倫理を確立しようとした商人階級の自己認識と、その経営哲学の形成過程を示す一事例として位置づけ、その歴史的意義を考察する。
これらの分析を通じて、『中島両以記文』という一つの史料が、個人の記録、商家の経営訓、そして地域の歴史的記憶の結晶という、三重の価値を持つことを明らかにしていく。
第二章:著者・中島両以の実像
中島両以の生涯と事業
『中島両以記文』の著者である中島両以は、慶長9年(1604年)2月、京都に生を受けた 1 。通称を助右衛門と称した彼は、元和5年(1619年)、16歳の時に父祖の地である美濃国に移り住んだ。当初は酒や味噌の醸造業、あるいは金融業を手掛けていたが、寛永16年(1639年)に大きな転機を迎える。36歳で材木商に転身し、当時、巨大な経済圏を形成しつつあった名古屋藩(尾張藩)の御用達商人となったのである 1 。
彼の商才は、この材木商への転身によって大きく開花した。美濃の特産品である美濃茶の取引に加え、長良川の水運を駆使して、遠くは奥州の南部藩や津軽藩から木材を仕入れ、尾張藩へ納入することで巨万の富を築いたと伝えられている 1 。彼の事業の拠点は、戦国時代から長良川の水運の要衝であった長良(現在の岐阜市長良)にあり、彼はこの地で代官的な役割も担うほどの豪商であった 6 。
両以が生きた時代背景
中島両以の生涯(1604年~?)は、日本の歴史が大きな転換点を迎えた時期と完全に重なっている。彼が生まれたのは、徳川家康が江戸幕府を開いた翌年であり、その後の彼の人生は、大坂の陣(1615年)を経て、戦乱の世が終わり、幕藩体制という新たな政治秩序が盤石になっていく過程と並行して進んだ。それは、社会の価値観の中心が「武」から「経済」へと大きく移行していく過渡期であった。
この時代は、戦国時代の記憶が人々の間にまだ生々しく残存している一方で、2世紀以上にわたる平和な世を前提とした、新たな社会システムと経済原理が構築されつつあった。両以の成功は、このような時代の特性と分かちがたく結びついている。彼のキャリア転換と事業の拡大は、単に彼個人の才覚によるものだけではない。それは、戦国時代に整備されたインフラと、江戸時代の安定した政治体制がもたらした新たな需要とが、奇跡的に結びついた結果であったと分析できる。
具体的に考察すると、彼が材木商として大成した背景には、二つの時代の遺産が関係している。一つは、斎藤道三や織田信長の時代から、美濃・飛騨の木材を伊勢湾へと運び出すための大動脈として機能していた長良川の物流網である 6 。これは「戦国時代の遺産」と言える。もう一つは、徳川体制下で日本有数の大都市へと発展した名古屋城下の建設と維持、そして武家屋敷や町家の普請に伴う、安定的かつ巨大な木材需要である。これは「江戸時代の産物」に他ならない。両以は、既存の物流ルートという戦国時代のインフラを、尾張藩という巨大で安定した大口顧客と結びつけることで、他の商人には真似のできないスケールの事業を展開し得たのである。この意味で、彼の事業そのものが、戦国と江戸という二つの時代の結節点に成立したハイブリッドであり、彼自身がその歴史の連続性を体現する存在であった。この文脈を理解することこそ、彼が自らの書物で100年以上前の戦国時代に繰り返し言及した動機を、より深く理解するための鍵となる。
表1:中島両以と関連年表
中島両以の生涯と、彼が『記文』で記述した戦国時代の主要な出来事、そして『記文』執筆時点との時間的関係を明確にするため、以下に年表を示す。この年表は、本報告書の中心的な論点である「時間的隔たり」と「記憶の継承」というテーマを視覚的に理解する上で不可欠なツールである。
|
西暦(和暦) |
主要な出来事(戦国時代) |
中島両以の動向 |
|
1542年(天文11年) |
斎藤道三が土岐頼芸を追放し美濃国主となる(『記文』が言及する都市計画の開始時期) |
(未生) |
|
1556年(弘治2年) |
斎藤道三、長良川の戦いで息子・義龍に敗れ死去 |
(未生) |
|
1567年(永禄10年) |
織田信長が稲葉山城を攻略し、城下を「岐阜」と改名 |
(未生) |
|
1603年(慶長8年) |
徳川家康が江戸幕府を開く |
(未生) |
|
1604年(慶長9年) |
|
中島両以、京都に生まれる 1 |
|
1619年(元和5年) |
|
父祖の地、美濃へ移住 1 |
|
1639年(寛永16年) |
|
材木商に転身、尾張藩御用達となる 1 |
|
1675年(延宝3年) |
|
『中島両以記文』を刊行 1 |
この年表が示す通り、両以が『記文』を著したのは、斎藤道三による美濃統治から実に130年以上、織田信長の岐阜統治からも100年以上が経過した後のことである。この事実は、『記文』が同時代史料ではなく、歴史的記憶を後世に伝えるための書物であることを明確に物語っている。
第三章:『中島両以記文』の内容分析 ―商家経営哲学の確立
自叙伝・家訓としての構成要素
『中島両以記文』は、その表題が示す通り、著者である両以自身の言葉で綴られた記録である。その内容は、大きく三つの要素から構成されている。第一に、中島家の出自や先祖の来歴、そして両以自身が美濃で身を立て、事業を拡大していく過程を記した自伝的記述である 2 。第二に、その成功体験を通じて得られた教訓として、商売における正直さ、勤勉、倹約の重要性、そして顧客や取引先との信頼関係をいかに築くべきかといった、実践的な「町人としての心得」が述べられている 2 。第三に、これらの教えを中島家が永続するための普遍的な原理として体系化し、子孫への「戒め」として遺した家訓としての側面である 2 。
近世商家における家訓の思想的背景
両以が生きた江戸時代初期は、商人階級が経済的な実力を背景に、社会的な存在感を急速に高めていった時代であった。武士階級が「武士道」という独自の倫理体系を持っていたのに対し、商人たちもまた、自らの職業の正当性や社会的役割を定義し、家の存続と繁栄を盤石にするための行動規範を言語化する必要に迫られていた。三井家の家訓『宗竺遺書』や、鴻池家の家訓などがその代表例であり、『中島両以記文』もまた、このような時代思潮の中で生まれた、商人の自己肯定とアイデンティティ確立のための文書として位置づけることができる。
これらの家訓に共通するのは、単なる道徳論にとどまらず、家業を永続させるための極めてプラグマティックな視点である。なぜ子孫への「戒め」という形式が好まれたのか。それは、当時の商家にとって最大の経営リスクが、世襲した跡継ぎの放蕩や経営能力の欠如によって、先祖が一代で築き上げた有形無形の資産が瞬く間に散逸してしまうことにあったからだ。中島両以もまた、自らの才覚と努力で築いた巨富と事業(信用、暖簾、ノウハウといった無形資産を含む)を、個人の一代の成功で終わらせることなく、「家」として次世代、さらにその先の世代へと永続させることを強く願っていた。
そのために彼は、自らの成功体験と、そこから得られた教訓を体系化し、子孫が遵守すべき行動規範として明文化する必要があったのである。これは、現代企業が自社の理念や価値観を「ミッション・ステートメント」や「行動規範(Code of Conduct)」として成文化し、組織の求心力を維持しようとする経営戦略と本質的に通底する。この視点から『中島両以記文』を読み解くとき、それは単なる精神論や道徳訓ではなく、事業の持続可能性(サステナビリティ)を追求した、極めて高度で実践的な経営戦略書としての一面が浮かび上がってくるのである。
第四章:「戦国時代」の証言者として
『中島両以記文』が他の商家家訓と一線を画し、歴史史料として特に高い価値を持つ理由は、その記述が単なる商売の心得にとどまらず、著者の生きた時代から遡ること約1世紀前の「戦国時代」の美濃、特に斎藤道三と織田信長の治世に関する具体的な情報を含んでいる点にある。
斎藤道三の城下町建設 ―都市史への貢献
本書は、岐阜の都市形成史を研究する上で、しばしば参照される基本史料の一つである。特に、斎藤道三が井ノ口(後の岐阜)の城下町を本格的に整備した際の様子を生々しく伝えている点は重要である 3 。
『記文』によれば、道三はまず、金華山の山頂にあった伊奈波神社を麓の現在地に移転させ、その跡地を利用して城郭を拡張したとされる。さらに、城下の町割りを計画的に実施した。特筆すべきは、道三がそれまで美濃の支配者であった土岐氏の最後の本拠地・大桑城(現在の山県市)から町人たちを強制的に移住させ、彼らのために城下の北側に東西に延びる「百曲り通り(ひゃくまがりどおり)」を建設したという記述である 3 。この通りは、現在の上大久和町や中大桑町といった地名にその名残をとどめている。一方で、元々井ノ口にあった町人たちは、その南側に平行して作られた「七曲り通り(ななまがりどおり)」に集められたという 3 。
これらの記述は、道三が単なる権力者ではなく、商業の重要性を理解し、計画的な都市開発を行う能力を持った為政者であったことを示唆している。一介の商人の記録でありながら、その具体性と地名の正確さから、後世の『岐阜市史』をはじめとする公的な歴史書にも重要な典拠として引用され、岐阜の町の骨格が道三の時代に形成されたという通説の根拠となっている 4 。
道三・信長時代の経済政策 ―経済史への貢献
『記文』は都市史だけでなく、戦国時代の経済史を解明する上でも貴重な情報を提供している。その一つが、長良川の鵜飼に関する記述である。本書によれば、長良川の鵜飼に対しては、美濃守護・土岐氏の時代から「役鮎(やくあゆ)」、すなわち税として鮎を上納する制度が存在していた。そして、斎藤道三、織田信長の時代になると、その役鮎の徴収量が増加したと記されている 5 。これは、戦国大名が地域の重要な産業や特産品をいかに正確に把握し、それを自らの財源として組み込んでいったかを示す具体的な証左である。
また、両以自身の生業とも深く関わるが、長良川が戦国時代末期から近世にかけて、郡上や飛騨方面から産出される材木や木製品を搬出するための極めて重要な物流路であったことが、『記文』の記述からうかがえる 6 。これは、両以が材木商として成功した基盤が、決して江戸時代に入ってから突然生まれたものではなく、戦国時代にまで遡る歴史的・地理的条件の上に成り立っていたことを示している。
史料としての価値と限界 ―史料批判の視点
もちろん、『中島両以記文』を戦国時代の史料として利用する際には、史料批判の視点が不可欠である。
その 価値 は、道三・信長の時代から約100年後の記録でありながら、当事者に近い立場の者しか知り得ないような具体的な地名(百曲り、七曲り)や制度(役鮎)に言及している点にある。これは、両以が全くの創作で記述したのではなく、長良の豪商として地域に代々伝わる古老の伝承や、失われた古い記録などを参照した可能性が高いことを示唆している。たとえ事実そのものではなかったとしても、江戸時代初期の岐阜の町人たちが、自らの町の起源をどのように認識し、語り継いでいたかを示す「伝承の記録」として、他に代えがたい史料的価値を持つ。
一方で、その 限界 は、あくまで後世の記録であるという点に尽きる。100年以上の時を経る中で、両以の記憶違いや、伝承が語り継がれる過程での潤色・脚色が含まれている可能性は常に念頭に置かなければならない。
しかし近年、この『記文』の記述の信憑性を再評価する動きも出ている。岐阜城跡で進められている発掘調査において、道三の時代に遡る石垣や建物の遺構が発見されており、その配置などが『記文』の記述と整合性を持つ可能性が指摘されている 3 。これにより、『記文』を単なる伝承として片付けるのではなく、考古学的な物証と照らし合わせることで、戦国時代の岐阜城下町の実像をより立体的に復元しようとする研究が進展している。
これらの分析から見えてくるのは、中島両以による斎藤道三の記述が、単なる過去の事実の報告ではないということである。そこには、下剋上の梟雄として知られる道三を、「商都・岐阜の偉大な創業者」として積極的に再評価し、その事業を継承する自分たち商人の社会的地位を歴史的に正当化しようとする、明確な意図が込められている。江戸時代の泰平の世においては、道三の武力闘争の側面は後景に退き、代わりに経済的繁栄の礎を築いた都市計画者としての側面がクローズアップされた。道三を「偉大な創業者」として描くことは、その都市で商売を営む両以自身の活動を、歴史的に意義深く、価値あるものとして位置づける効果を持っていた。これは、歴史上の人物の評価が、後の時代の社会状況や価値観によっていかに変容するかを示す、格好の事例と言えるだろう。
第五章:近世初期における商家経営と家訓の系譜
『中島両以記文』に見られる思想をより深く理解するためには、それを同時代の他の商家家訓と比較し、近世初期という時代における商人思想の大きな潮流の中に位置づけることが有効である。その格好の比較対象となるのが、博多の豪商・島井宗室(しまい そうしつ、1539-1615)が遺した『遺訓十七ヵ条』である。
同時代の豪商との比較 ―博多・島井宗室『遺訓十七ヵ条』
島井宗室は、中島両以より半世紀ほど前に活躍した人物であるが、その経歴には多くの共通点が見られる。宗室もまた、大友宗麟、豊臣秀吉、黒田長政といった時の権力者と深く結びつき、金融や貿易で巨富を築いた 8 。同時に、千利休らとも交流のあった当代一流の茶人であり、戦火で荒廃した博多の町の復興に尽力するなど、地域の経済と文化に大きな影響力を持った人物であった 8 。
彼が養嗣子・信吉に遺した『遺訓十七ヵ条』(1610年成立)は、近世商家家訓の祖型とされ、その後の商人道徳に大きな影響を与えた 8 。その内容は、質素倹約を旨とし、正直で誠実であること、家内の和合を保つこと、賭博などの身を滅ぼす行為を厳しく禁じることなど、商人が守るべき処世訓が具体的に示されている 8 。
表2:近世初期の代表的な商家家訓の比較
『中島両以記文』と島井宗室の『遺訓十七ヵ条』を比較することで、両者に共通する普遍的な商人の倫理と、それぞれの独自性を浮き彫りにすることができる。
|
項目 |
中島両以『中島両以記文』の教え(推定) |
島井宗室『遺訓十七ヵ条』の教え |
典拠 |
|
基本姿勢 |
家の由来を重んじ、家業に専心する。 |
貞心(正直さ)、律義、家内の和合を第一とする。 |
2 |
|
商売倫理 |
正直さ、信用の重視。 |
嘘をつかない。人の悪口を言わない、聞かない。 |
2 |
|
金銭感覚 |
倹約の奨励。 |
質素倹約を旨とし、無駄遣いを戒める。 |
2 |
|
対人関係 |
顧客や地域との関係構築の重視。 |
交友の心得をわきまえ、無礼な振る舞いを禁じる。 |
2 |
|
リスク管理 |
放蕩や怠惰を戒め、家の存続を願う。 |
賭けごとを厳しく禁止する。 |
2 |
この比較から明らかなように、両者の教えには多くの共通点が存在する。正直、倹約、勤勉、信用の重視といった徳目は、武士の「忠義」とは異なる、商人独自の職業倫理、すなわち「商人道」とも言うべき思想の中核をなすものであった。
『記文』にみる商人のアイデンティティ
これらの家訓の根底に流れているのは、商人という身分に対する強い自負と、家業を永続させることへの執念である。彼らは、武士が世襲の「禄」によって生活の安定を得ているのに対し、商人は定まった禄を持たず、自らの才覚と努力、そして日々の商いで積み重ねる「信用」のみを資本として富を築く存在であると認識していた。
中島両以や島井宗室が説いた「家」の永続という思想は、武士の家意識とは質的に異なる。それは、単なる血筋の存続ではなく、暖簾や信用、経営ノウハウといった無形の経営資産を次代へ継承していくことを意味した。そのために、経済的合理性と道徳的規範が分かちがたく結びついた、商人独自の価値観が形成されていったのである。『中島両以記文』は、まさにこの近世初期の商人が自らのアイデンティティを確立していく過程を記録した、貴重な証言文書なのである。
第六章:結論 ―『中島両以記文』が現代に伝えるもの
本報告書では、美濃の豪商・中島両以が遺した『中島両以記文』について、戦国時代という視点を軸に多角的な分析を行ってきた。その結論として、本史料が持つ重層的な価値を改めて確認し、今後の展望を述べたい。
史料の多角的価値の再確認
第一に、『中島両以記文』は、中島両以という一個人の立志伝であると同時に、江戸時代初期の商人がいかにして事業を興し、それを維持・発展させようとしたかを示す、生きた 経営史の史料 である。その家訓には、現代の経営学にも通じる、信用創造、リスク管理、そして事業承継という普遍的なテーマが内包されている。
第二に、本書は斎藤道三による岐阜の都市計画や、道三・信長時代の経済政策(役鮎制度など)に関する具体的な記述を含んでおり、戦国時代の美濃を研究する上で欠かせない 都市史・経済史の史料 としての価値を持つ。後世の記録という限界はありながらも、その記述は地域の歴史的景観や制度を復元するための重要な手がかりを提供している。
第三に、そして最も重要な点として、『記文』は、戦国という激動の時代が、後の平和な江戸時代に生きる人々にどのように「記憶」され、自らのアイデンティティの拠り所として再構築されていったかを示す、 社会史・文化史の貴重な史料 である。両以は、下剋上の梟雄・斎藤道三を「商都・岐阜の創業者」として意味づけ直し、その歴史的遺産の上に自らの商売が成り立っていると語ることで、自己の存在を正当化した。これは、歴史が常に後の時代の人々によって解釈され、意味を与えられ続ける動的なプロセスであることを我々に教えてくれる。
歴史の連続性の体現者としての中島両以
中島両以という人物は、まさに歴史の連続性を体現した存在として評価できる。彼は、戦国時代に形成された都市の骨格や長良川の物流網という「遺産」を最大限に活用し、江戸時代の安定した社会体制と新たな経済需要という「機会」を捉えて大成した。そして彼は、自らの記録を通じて、戦国と江戸という断絶しているように見える二つの時代を鮮やかに繋ぎ、後世にその記憶を伝えた。彼の存在と記録は、歴史が一つの時点で完結するのではなく、過去の遺産が未来の創造の礎となることを雄弁に物語っている。
今後の研究への展望
『中島両以記文』をめぐる研究には、まだ多くの可能性が残されている。
まず、『記文』の原本、あるいは信頼性の高い写本の詳細な本文研究を進めることで、これまで知られていなかった記述を発掘し、より緻密な内容分析を行うことが期待される。
次に、近年目覚ましい成果を上げている岐阜城跡周辺の考古学的発掘調査と、『記文』の記述をさらに詳細に突き合わせる学際的な研究は、戦国時代の岐阜城下町の実像を解明する上で極めて重要となるだろう。
最後に、日本全国に残る同時代の他の商家文書や家訓との比較研究をさらに推し進めることで、『中島両以記文』を個別の事例研究にとどめることなく、「近世商人思想」の全体像をより深く、かつ立体的に理解することに繋がるであろう。
『中島両以記文』は、一人の商人が遺したささやかな記録でありながら、その行間には、経営、都市、そして歴史的記憶をめぐる豊饒な物語が刻まれている。その声に耳を傾けることは、過去を理解するだけでなく、現代社会における事業承継や地域アイデンティティの創出といった課題を考える上でも、多くの示唆を与えてくれるに違いない。
引用文献
- 中島両以(なかじま りょうい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E4%B8%A1%E4%BB%A5-1096619
- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html
- www.jia-tokai.org http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2008/10/kinka.html
- 山県市の大桑町と岐阜市の大桑町の町名が同じことの由来は何か https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?pg=3096&type=reference&page=ref_view&id=1000175672&ldtl=1
- 第2章 文化財の概要 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/875/2.pdf
- 長良川|日本歴史地名大系 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2144
- 鷺山の休日 昔から月の一日一五日が休日と記した文書があり、昭和三〇年頃まで職人と百姓はその日を休日とし た。 https://sagiyama.jp/wp-content/uploads/2013/04/11%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%AB%A0%E3%80%80%E9%B7%BA%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BF%97.pdf
- 島井宗室(シマイソウシツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4-75103
- 「井氏年録」という名称は、便宜上のもので、田中健夫は - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/74336/shomotsu0002903090.pdf
- 島井 宗室(しまい そうしつ) https://fukuoka.kyushu-jinzai.com/shimai_soushitsu/