南遊紀行
『南遊紀行』は貝原益軒による元禄期の紀行文。泰平の世の畿内を実証的に巡り、河内・和泉の繁栄、高野山の武将墓碑、吉野の南朝史跡を通じ、戦国時代の記憶と近世社会の変容を活写した。
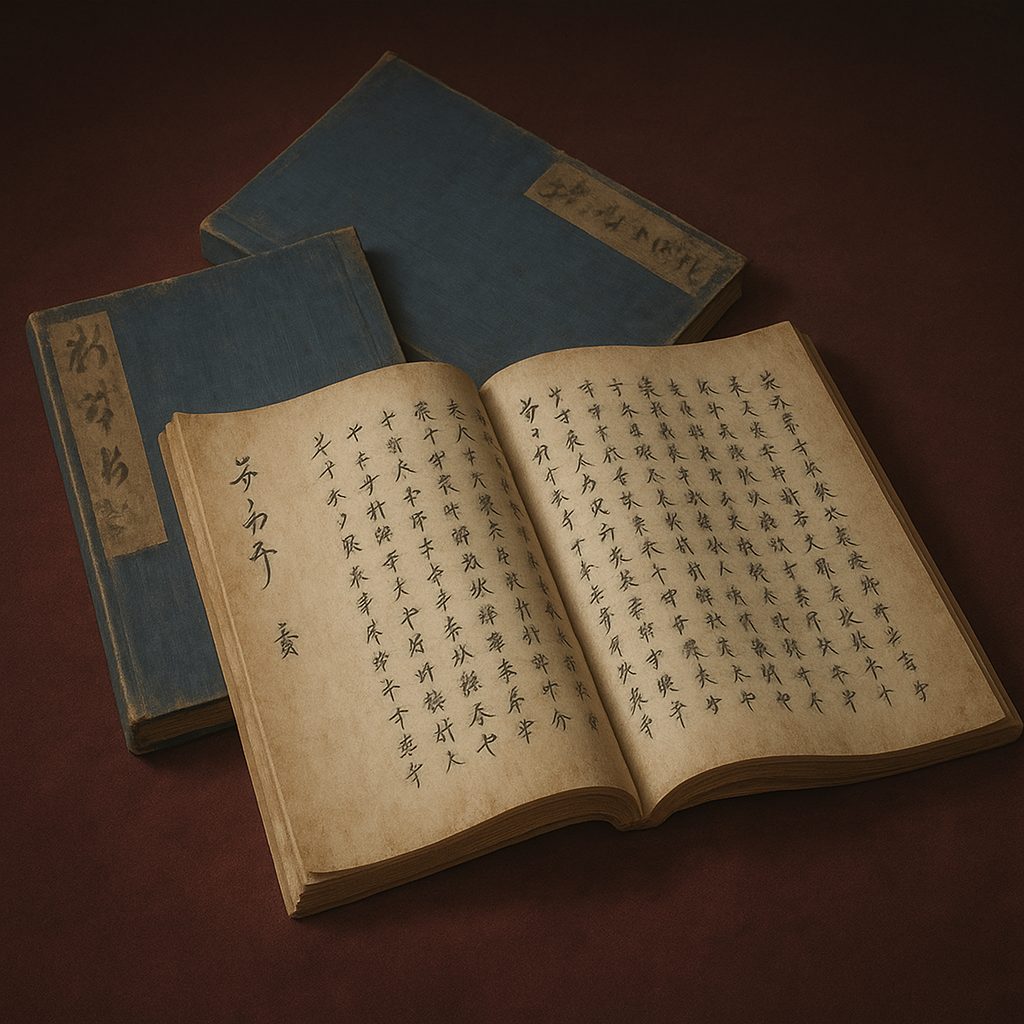
『南遊紀行』に視る戦国の残影:貝原益軒が歩いた元禄期畿内の歴史地理
序章:旅人の眼差し――泰平の世から戦乱の跡を訪ねて
本報告書は、江戸時代初期の儒学者であり本草学者でもある貝原益軒が著した紀行文『南遊紀行』を、単なる旅の記録として解説するものではない。元禄という徳川の治世が盤石となった安定期に生きた知識人、貝原益軒の眼を通して、彼の時代からわずか七、八十年前に終焉した「戦国時代」の記憶と遺産が、当時の風景にいかに刻まれていたかを読み解く試みである。益軒の旅路を追体験し、その冷静な記述の背後に横たわる歴史の地層を明らかにすることを目的とする。
貝原益軒(1630-1714)は、戦国の記憶が未だ生々しい寛永年間に生を受け、徳川の治世が安定し元禄文化が爛熟期を迎えた時代に、その知的好奇心の赴くままに旅をした人物である 1 。彼の学問は、書斎での思弁に留まることなく、実地踏査と客観的観察を重んじる、いわば「科学者の眼」を特徴とする 2 。この実証的な姿勢こそが、彼の紀行文の性格を決定づけている。
『南遊紀行』に記された旅は元禄2年(1689年)に行われ、その刊行は24年後の正徳3年(1713年)であった 4 。この長い歳月の間に、旅の見聞は彼の内で熟成され、思索が深められたであろう。益軒が記す城跡の静寂、寺社の由緒、街道の賑わい。それら風景の一つひとつは、戦国期の動乱を経て再編成された社会の到達点であり、彼の筆は、その静かなる結果を淡々と記録している。
元禄期に「旅」や「地誌編纂」が盛んになった背景には、戦乱が終息し、国土と文化の全体像を把握することで自らの時代のアイデンティティを再確認しようとする、社会全体の知的な欲求があった。益軒の旅と著述活動は、この時代の要請を象徴するものであった。彼の客観的で実証的な記述スタイルは、戦国時代の不確実で伝説に満ちた物語から、より確かな知見を求める近世的な知性の現れと言える。彼の旅は、伝説を検証し、過去を「科学」の対象として捉え直すプロセスでもあった。
益軒は福岡藩の儒学者であり、本草学者として多岐にわたる著作を残し、実用的な知識を平易な言葉で説くことを信条とした 1 。その学問的態度は「知行併進」、すなわち知識と実践の一致を重んじるものであり、旅は書物で得た知識を実地で検証するための重要な「実践」の場であった 2 。したがって、『南遊紀行』は単なる物見遊山の記録ではない。それは、益軒という一個の知性が、畿内という広大な「テクスト」を読み解き、その歴史的・地理的文脈を検証するフィールドワークの報告書なのである。彼が戦国時代の史跡に注目するのは、それが最も劇的な変化を遂げた「テクスト」の最たる部分であったからに他ならない。
第一章:旅の前提――黒田家臣・貝原益軒の形成
貝原益軒の旅と思索を理解する上で、彼が福岡藩黒田家の家臣であったという事実は決定的に重要である。藩祖である黒田官兵衛(如水)と初代藩主・長政は、播磨の小大名から身を起こし、豊臣秀吉の軍師として、そして関ヶ原の戦いにおける抜群の功績によって、筑前国に52万石余の大封を得た、まさに戦国乱世を勝ち抜いた体現者であった 9 。益軒は、藩命によりこの黒田家の栄光の歴史を『黒田家譜』として編纂する大任を担っている 2 。この作業を通じて、彼は戦国武将の興亡、調略、合戦の実態について、一次史料に依拠した深い知識を蓄積していたはずである。
『黒田家譜』の編纂という事業は、益軒に歴史家としての厳密な訓練を施した。史料を批判的に扱い、客観的な歴史記述を追求する経験は、『南遊紀行』における史跡や古文書に対する冷静な観察眼を養う土台となった 2 。主君の輝かしい戦国史をまとめる一方で、益軒自身は泰平の世に生きる学者である。この立ち位置が、戦乱の時代を客観的に、時には批判的に考察する複眼的な視点を与えたことは想像に難くない。
彼の学問的態度は、実証主義に貫かれている。益軒は「天性の旅行好き」と評されるほど、生涯を通じて精力的に旅を続けた 2 。その紀行文は、主観的な感動の吐露よりも、地理、産物、そして各地に伝わる伝説の真偽といった客観的な事実の記録に重きを置く 2 。例えば、『南遊紀行』において、和泉国久米田にある橘諸兄公の墓とされる塚について、彼は里人の伝承を記録しつつも、「不審(いぶかし)」と断じ、山城国井手の本墓の存在を根拠に、これは諸兄を慕う人々が後に築いた「仮の墓」であろうと合理的な推論を下している 4 。これは、伝承を鵜呑みにせず、自らの知識と照らし合わせて検証しようとする彼の科学的・実証的な姿勢を如実に示す一例である。
益軒が黒田家に仕え、『黒田家譜』を編纂したという事実は、彼の旅の動機や視点に深い影響を与えていたと考えられる。黒田官兵衛・長政父子は、秀吉の天下統一事業において、畿内でも数々の戦功を挙げている 15 。益軒が畿内を旅する際、その風景を単なる名所としてではなく、かつて主君の先祖が駆け巡った「歴史の舞台」として認識していた可能性は極めて高い。彼の旅は、個人的な知的好奇心を満たすものであると同時に、福岡藩黒田家という「戦国の勝者」の家臣として、かつての主戦場を巡るという、ある種の巡礼の性格を帯びていたと解釈することも可能である。彼の冷静な筆致は、すでに過去となった戦乱の地を、勝利者の子孫たる藩の重臣として静かに検分しているかのようでもある。歴史への深い理解が、現在の風景をより重層的に見る眼を養わせたのであり、『黒田家譜』という「過去に向き合う仕事」が、益軒を『筑前国続風土記』や数々の紀行文という「現在の国土を記録する仕事」へと向かわせた原動力の一つであったと言えよう。
第二章:河内国――覇権争奪の地の静寂
益軒の旅は京都を発ち、淀、八幡を経て河内国へと入る 17 。彼が目にした元禄期の河内は、平和と豊穣を謳歌する土地であった。私市に宿り、天野川の風景を「あたかも天上の銀河の形のごとし」と詩的に描写し 18 、久宝寺村周辺については「河内の国は平広で荒野が無く土地よく肥えて民家は富み豊かである」と、その経済的な繁栄を賞賛している 20 。この静かで豊かな風景は、しかし、わずか一世紀前には想像もつかないほどの戦乱に明け暮れた土地であった。
戦国時代の河内は、室町幕府の有力守護であった畠山氏の内紛の主戦場となり、長きにわたって国人衆が割拠する不安定な地域であった。戦国中期には、三好長慶が飯盛城を拠点として畿内に覇を唱え、一時は天下に号令した 21 。飯盛城は、その後の織豊系城郭の先駆けとも言える先進的な構造を持ち、戦国城郭史において極めて重要な遺跡である。また、河内は南北朝時代の英雄・楠木正成の故地でもあり、その記憶は戦国時代の在地武士たちにとって、自らのアイデンティティを支える精神的な拠り所として、あるいは権威の源泉として機能し続けていた 22 。
益軒が賞賛した河内の豊かさは、戦国時代の度重なる戦乱を乗り越え、近世的な灌漑技術や新田開発によって達成されたものであった。彼の記述は、戦乱からの「復興」が完了し、新たな時代の繁栄が始まっていることを力強く証言している。彼が通過した東高野街道もまた、戦国期には軍事路として、また高野山への巡礼路として重要な役割を果たした道であったが、益軒の旅においては、もっぱら平和な時代の経済と信仰の道として機能していた 18 。道の用途の変遷そのものが、時代の劇的な転換を物語っている。
興味深いのは、益軒の記述における「城跡の不在」である。彼は天野山金剛寺のような由緒ある寺社には言及するが、三好長慶の栄華を象徴する飯盛城跡のような、戦国期の城跡には直接触れていない。これは、元禄期において、もはや軍事拠点としての役割を終えた城が、人々の生活の中心から外れた過去の遺物となっていたことを示唆している。あるいは、彼の関心が、為政の象徴としての「現役の城」や、由緒来歴の確かな「寺社」に向いており、打ち捨てられた廃城には向かなかったという、彼の価値観の現れかもしれない。
益軒が描く河内の平和な風景と、その土地が持つ血塗られた歴史との間には、強烈な断絶が存在する。この断絶こそが、戦国から元禄へという短い期間に日本社会が経験した、巨大な変化そのものである。益軒の筆は、意図せずして、戦乱の記憶を覆い隠すかのように広がる近世の「平和」と「豊かさ」を描き出した。そして、彼の沈黙、すなわち城跡への言及の欠如は、逆説的に時代の転換を雄弁に物語っているのである。
第三章:和泉国――城下町と寺内町の変貌
河内国を南下した益軒は、和泉国に入る。ここで彼は、成り立ちの異なる二つの都市、岸和田と貝塚を訪れ、その対照的な姿を記録している。この記録は、戦国時代の多様な都市形成のパターンが、江戸時代の安定した社会秩序の中でいかに継承され、変貌を遂げたかを示す貴重な証言となっている。
益軒はまず、岸和田について「岡部美濃守殿居城也」と記し、続けて「町長く、富家多し」「此所海辺にて、且紀州より大坂への海道なる故にうり物多し」と、その繁栄ぶりを描写する 4 。戦国時代、岸和田城は紀伊と大坂を結ぶ要衝に位置し、支配者がめまぐるしく変わる戦略拠点であった。特に織田信長の紀州攻めの際には前線基地となり、豊臣秀吉の時代に本格的な近世城郭として整備が進められた 25 。益軒が見たのは、戦国期の軍事拠点が、岡部氏の統治下で藩政と商業の中心地として完成された、平和な城下町の姿であった。
岸和田を南に出ると、益軒は貝塚に至る。ここでの記述は「町長し。民屋多くは瓦ぶき也」と簡潔だが、示唆に富む 4 。「瓦ぶき」の家々が立ち並ぶ様は、この町が持つ高い経済力を物語っている。貝塚は、戦国時代に一向宗の道場(後の願泉寺)を中心に形成された寺内町であり、石山合戦の際には本願寺側の有力な拠点の一つであった。環濠を巡らせた自衛的な性格の強い都市であり、商工業の発達によって高い経済力と自治能力を誇っていた 26 。益軒が見た貝塚の繁栄は、戦国時代に宗教的結束と経済活動によって蓄積されたエネルギーが、泰平の世に開花した姿を象徴している。
益軒は、権力(武家)が計画的に作り上げた城下町・岸和田と、宗教と民衆(商人)が自治的に形成した寺内町・貝塚という、成り立ちも性格も全く異なる二つの都市が、紀州街道沿いに隣接し、共に繁栄している様子を記録した。戦国期には、岸和田城の武家勢力と貝塚の寺内町勢力は、潜在的な対立関係にあった。しかし、益軒の時代には、両者は紀州街道という経済の大動脈で結ばれ、城下町の武士や民衆の需要が貝塚の商工業を潤し、貝塚の商業活動が岸和田藩の経済基盤を支えるという、相互補完的な共存関係へと移行していた。徳川の平和が、戦国時代の多様な社会エネルギーを、軍事的な対立から経済的な競争と協調へと転換させることに成功した証左が、ここにある。
また、益軒は岸和田に至る手前、久米田寺に立ち寄り、そこに所蔵される古文書に強い関心を寄せている。彼は、行基が開いたという里人の伝承と共に、南北朝・室町期に遡る多数の古文書、特に「大塔ノ宮令旨、楠正成の添状」や足利尊氏、義満らの文書が存在することを詳細に記録している 4 。これは、彼の歴史家としての一面を強く示すものであり、伝承と文献史料の両方から、土地の歴史を多角的に捉えようとする実証的な姿勢の現れである。彼の簡潔な描写は、戦国という巨大な社会変革を経て成立した、近世社会の複合的な構造を見事に凝縮して示している。
第四章:紀伊国――聖地・高野山の戦国と近世
和泉国を後にした益軒は、紀伊国へと足を進め、高野山を抜けて旅の目的地である吉野へと向かう 4 。『南遊紀行』における高野山の具体的な記述は比較的簡潔であるが、彼がこの地で目にした風景は、戦国時代の終焉を何よりも雄弁に物語るものであった。
戦国時代の高野山は、単なる宗教的聖地ではなかった。広大な寺領と数千人に及ぶ僧兵を擁し、高度な自治権を確立した、独立した武装勢力であった。その力ゆえに、天下統一を目指す織田信長と激しく対立し、焼き討ちの危機に瀕したこともあった。最終的には豊臣秀吉の紀州征伐によってその軍事力は解体され、武装勢力としての歴史に終止符を打った 27 。
しかし、武力を失った高野山は、弘法大師空海への信仰を核とした「聖地」としての性格を、むしろ一層強めていく。秀吉が亡き生母の菩提を弔うために青巌寺(後の金剛峯寺の一部)を建立したのを皮切りに、全国の戦国大名たちが競ってこの地に宿坊や菩提寺を建立し、自らや一族の墓所、供養塔を建てた 27 。益軒が訪れた元禄期の高野山、特に奥之院の参道には、武田信玄と上杉謙信、織田信長、豊臣家、明智光秀、伊達政宗、石田三成といった、かつて天下を争った武将たちの墓碑が、敵味方の別なく林立していた 29 。高野山は、文字通り「天下の総菩提所」へと変貌を遂げていたのである。
この現象は、単なる信仰心だけでは説明できない。戦国時代が終わり、徳川の治世が安定すると、各大名家は自らの家の歴史を「正史」として編纂し、その権威を確立する必要に迫られた。高野山に墓所を設けることは、弘法大師の威光によって自家の家格を証明し、その歴史を聖地に刻み込むという、極めて政治的な意味合いを持つ行為であった。戦国時代の勝者も敗者も、ここでは弘法大師の弟子として平等に扱われる。この「聖なる空間」に身を置くことで、生前の裏切りや殺戮といった生々しい記憶は浄化され、後世に語り継がれるべき輝かしい「歴史」へと転換される。高野山は、いわば戦国武将たちの「記憶の洗浄装置」として機能したのである。徳川家自身が家康と秀忠のための壮麗な霊台を建立したことは、この新たな秩序を象徴している 30 。
益軒が歩いた奥之院の杉木立の参道は、単なる墓地ではなかった。それは、戦国という時代の記憶が再編され、近世的な秩序の中に組み込まれていく、巨大な歴史編纂の現場そのものであった。彼はその風景の中に、かつて天下を争った者たちが、弘法大師という一つの絶対的な権威の下に静かに眠るという、戦国時代の完全な終焉を象徴する光景を見たはずである。彼の目には、これが徳川による泰平の世の秩序が、死後の世界にまで及んでいる証と映ったに違いない。
第五章:大和国――古都に残る武士たちの夢の跡
高野山を越えた益軒は、旅の主要な目的地の一つである大和国吉野山へと至る。ここで彼は、他の訪問地では見られない、深い感慨を記録している。満開の桜を眼前にし、「再び眼にすることは難しい」との思いから、「久しくやすらひて去りがたし」と、名残を惜しむ心情を吐露しているのである 4 。この感傷的な言葉は、彼の紀行文全体を通じて際立っており、その背景には吉野という土地が持つ特別な歴史的意味が横たわっている。
戦国時代の大和国は、有力な守護大名が存在せず、興福寺や東大寺といった強大な寺社勢力と、筒井氏、越智氏、十市氏といった国人衆が複雑に争う、特異な政治状況にあった 32 。織田信長の畿内進出後は、信長に仕えた梟雄・松永久秀と、在地勢力を代表する筒井順慶が、信貴山城や郡山城を舞台に激しい抗争を繰り広げた 33 。この混乱に終止符を打ったのが、豊臣秀吉の弟・秀長である。彼は郡山城主として大和に入り、100万石を領有。徹底した検地や城下町の整備を行い、近世大和国の基礎を築いた 34 。
しかし、益軒の心を捉えたのは、こうした戦国の覇権争いの記憶ではなかった。彼の感慨は、吉野が南北朝時代に後醍醐天皇が開いた「南朝」の中心地であったという、より古い歴史に向けられていた 36 。儒学者である益軒にとって、君臣の義を重んじる朱子学の素養は、その思想の根幹をなすものであった。天皇への忠義を貫いた南朝の歴史、そしてその悲劇的な結末は、江戸時代の知識人にとって特別な意味を持つ物語であった。
益軒の「去りがたし」という言葉には、儚く散る桜の花に、後醍醐天皇や楠木正成をはじめとする南朝の忠臣たちの運命を重ね合わせていた可能性が色濃く窺える。彼の感慨は、単なる自然美への感動に留まらず、時代を超えて語り継がれるべき「大義」への共感であった。戦国時代の武将たちが実力で天下を争ったのに対し、南朝の公家や武士たちは「義」のために戦い、散っていった。益軒の心に深く響いたのは、後者の精神性であったと考えられる。
彼の旅程そのものが、彼の歴史観を物語っている。戦国の覇権争いの跡である河内、和泉、紀伊を巡った後、最後に南朝の故地である吉野で深い感慨にふける。この構成は、彼が武力による支配よりも、道義に基づく秩序を高く評価していたことを示唆している。益軒の旅は、単なる名所巡りではなく、日本の歴史における「義」とは何かを問う、壮大な思索の旅でもあったのである。
終章:紀行文が映し出す歴史の連続性と断絶
貝原益軒の『南遊紀行』を、「戦国時代」という特定の歴史的視座から読み解くことで、この紀行文が持つ多層的な価値が明らかになる。本作は、単なる元禄期の旅行案内や名所記ではない。それは、戦国という激動の時代が終焉し、近世という新たな社会秩序が確立した歴史の転換点に立って、一人の優れた知識人が自らの足と眼で確認した「時代の報告書」と評価することができる。
益軒の記録からは、戦国時代の記憶が、古文書、寺社の縁起、そして里人の伝承といった多様な形で、元禄の世にも確かに継承されていたことがわかる 4 。久米田寺の古文書群や、各地に残る楠木正成の逸話は、過去が現在と断絶することなく、人々の意識の中に生き続けていたことを示している。
しかし同時に、その記憶は大きく変容していたことも事実である。かつて生死を分かつ軍事拠点であった城は、藩政を象徴する建造物や、過去を偲ぶ名所となり、独立した武装勢力であった高野山は、全国の大名家が帰依する一大霊場へと姿を変えた。戦乱の生々しい記憶は次第に薄れ、物語や伝説として、あるいは家の権威を飾る由緒として、平和な時代の文脈の中に再配置されていった。
この歴史の連続性と断絶を、益軒の客観的な筆致は極めて効果的に映し出している。彼が自らの感情を抑制し、実証的な観察に徹したことで、かえって彼が見た元禄の風景と、その背景にある戦国時代の現実との間の、巨大な溝が際立つ結果となった。彼の冷静な眼は、時代の劇的な変化を映し出す、曇りのない鏡として機能している。
結論として、『南遊紀行』を戦国時代という視座から読むことは、元禄の平和な風景の下に、今なお息づく戦国の地層を発見する知的探求である。貝原益軒の旅は、過去と現在が交錯する歴史の連続性そのものを歩く行為であり、彼が遺したこの紀行文は、その類稀なる証言として、後世の我々に豊かな示唆を与え続けているのである。
添付資料
表1:『南遊紀行』主要訪問地と戦国時代における意義対照表
|
訪問地 |
益軒の記述の要点 |
戦国時代における意義・関連事項 |
|
河内国 |
「土地よく肥えて民家は富み豊かである」と平和と繁栄を記す。飯盛城跡など戦国の城跡への言及はない。 |
畠山氏の内紛、三好長慶の覇権(飯盛城)、楠木正成の記憶が色濃い地域。畿内における覇権争奪の主戦場。 |
|
久米田寺(和泉) |
「大塔ノ宮令旨、楠正成の添状有」など、南北朝期の古文書に強い関心を示す。 |
寺社勢力として一定の力を保持。楠木氏との関連が深く、南北朝の記憶を継承する場。 |
|
岸和田(和泉) |
「岡部美濃守殿居城也」「町長く、富家多し」と、安定した城下町の繁栄を記す。 |
紀伊と大坂を結ぶ戦略拠点。織田・豊臣政権下で近世城郭として整備され、紀州勢力への抑えとなる。 |
|
貝塚(和泉) |
「民屋多くは瓦ぶき也」と、民衆の経済的な豊かさを象徴的に描写する。 |
一向宗の寺内町として成立。石山合戦では本願寺側の拠点。環濠を持つ自衛・自治都市であり、高い経済力を有した。 |
|
高野山(紀伊) |
旅程の通過点として記録。元禄期には全国の武将の墓碑が林立する聖地となっている。 |
戦国期には僧兵を擁する独立武装勢力。信長と対立し、秀吉に平定される。近世には「天下の総菩提所」として、諸大名の墓所が建立された。 |
|
吉野山(大和) |
「久しくやすらひて去りがたし」と、紀行文中で際立って感傷的な言葉を残す。 |
南北朝時代に南朝の中心地。その歴史的記憶は後世まで強く残り、後南朝勢力の活動拠点ともなった。儒教的価値観における「大義」の象徴。 |
引用文献
- 日本の経済思想史家シリーズBIOGRAPHIES OF JAPANESE SCHOLARS OF ECONOMIC THOUGHT http://shjet.ec-site.jp/historian.html
- 7 第1章 貝原益軒の生涯 https://www.musashino.ac.jp/mggs/wp/wp-content/uploads/2024/03/hakase_you_1syou.pdf
- 小島鳥水と山の紀行文-三つの山旅をめぐって- - 明治大学学術成果リポジトリ https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/8132/files/kyouyoronshu_398_261.pdf
- 貝原益軒(かいばらえきけん)の『南遊紀行』(ミニ岸和田再発見第28弾) https://www.city.kishiwada.lg.jp/site/toshokan/mini-28.html
- 南遊紀行 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100347346
- 貝原益軒の女訓思想について https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/12687/files/KU-1100-20140930-11.pdf
- 貝原益軒の『養生訓』。江戸時代のベストセラーが教えてくれる、健康長寿の心得とは? https://www.axa.co.jp/100-year-life/health/20181029/
- 貝原益軒の教育思想への一考察 https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/record/465/files/07_MATSUDA_%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6_%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7.pdf
- 黒田官兵衛ゆかりの地、福岡県 | 旅の特集 https://www.crossroadfukuoka.jp/feature/fukuokakanbe
- 黒田長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF
- 黒田官兵衛が息子に激怒した理由とは?活躍しても𠮟られた黒田長政の関ヶ原の戦い逸話 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/108610/
- 福岡市 魅力発信中央区 第9回 貝原益軒 https://www.city.fukuoka.lg.jp/chuoku/kikaku/charm-kankou/miryokuhasshin_chuo-ku/miryokudai9kai.html
- 貝原益軒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92
- 「九州の出版文化」に見る 儒家・文人 - 福岡大学図書館 https://www.lib.fukuoka-u.ac.jp/e-library/tenji/kyusyu/kyu/kai.htm
- 黒田官兵衛に学ぶ経営戦略の奥義“戦わずして勝つ!” https://sengoku.biz/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9%E6%88%A6%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%97%E3%81%A6
- 19.黒田官兵衛 ~戦国時代を生きぬいた三軍師 其の3 - 猩々の呟き http://shoujou2017.blogspot.com/2014/05/19.html
- 貝原益軒は、江戸時代前・中期に活躍した儒学者・博物学者・大衆教育家で - 枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/367/6074.pdf
- 交野市文化財保存活用地域計画 【本編】 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2022120600036/file_contents/katano_bunkazai.pdf
- 歴史文化遺産の保存と活用のための整備構想 - 枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000002/2858/63494.pdf
- 久イオ守オ、力雪童麻 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/6/6924/5158_1_%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E5%A0%B1%E5%91%8A80.pdf
- 河内長野駅周辺の文化史跡・遺跡ランキングTOP10 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/sta_990209/g2_30/
- 烏帽子形城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%BD%A2%E5%9F%8E
- 細川頼之と楠正行 - 四條畷市立教育文化センター http://nawate-kyobun.jp/event2_h30.html
- 楠木正成、正行ゆかりの地 https://gururinkansai.com/kusunokimasashigeyukari.html
- 岸和田城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E
- 楠木正成と戦国時代の武士・松浦氏 - 貝塚市 https://www.city.kaizuka.lg.jp/material/files/group/38/tempus67.pdf
- 世界遺産 高野山とは?見どころや歴史、宿坊など、多彩な魅力を徹底解剖!|特集 - 和歌山県公式観光サイト https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/koyasan
- 高野山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1
- 近畿文化会「高野山奥之院を歩く」(和歌山県高野町) - やいちの歴史探訪 http://mahorama.info/posts/post138.html
- 024高野山 奥之院参道と戦国武将 - わかやま歴史物語 http://wakayama-rekishi100.jp/story/024.html
- 山内案内 https://gururinkansai.com/sannaiannai.html
- 戦国期大和の古豪にして磯城の王者・十市氏~大和武士の一族(2) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatonobuke02_toichi
- 奈良の城・信貴山城と郡山城をたずねて - ええ古都なら https://www.nantokanko.jp/tokushu/19005.html
- 天下人の右腕 豊臣秀長と城下町の旅|奈良県観光[公式サイト] あをによし なら旅ネット|生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア|モデルコース http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/18course/05history-journey/02west_area/3udhbkghkn/2day/
- 天下人の右腕 豊臣秀長と城下町の旅|奈良県観光[公式サイト] あをによし なら旅ネット|生駒・信貴・斑鳩・葛城エリア|モデルコース http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/18course/05history-journey/02west_area/3udhbkghkn/1day/
- 吉野 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E9%87%8E