古今和歌集
『古今和歌集』は勅撰和歌集として成立し、平安貴族の教養の頂点に。戦国時代には「古今伝授」が武将の権威となり、細川幽斎の命を救った。武威の世における文雅の権威を象徴。
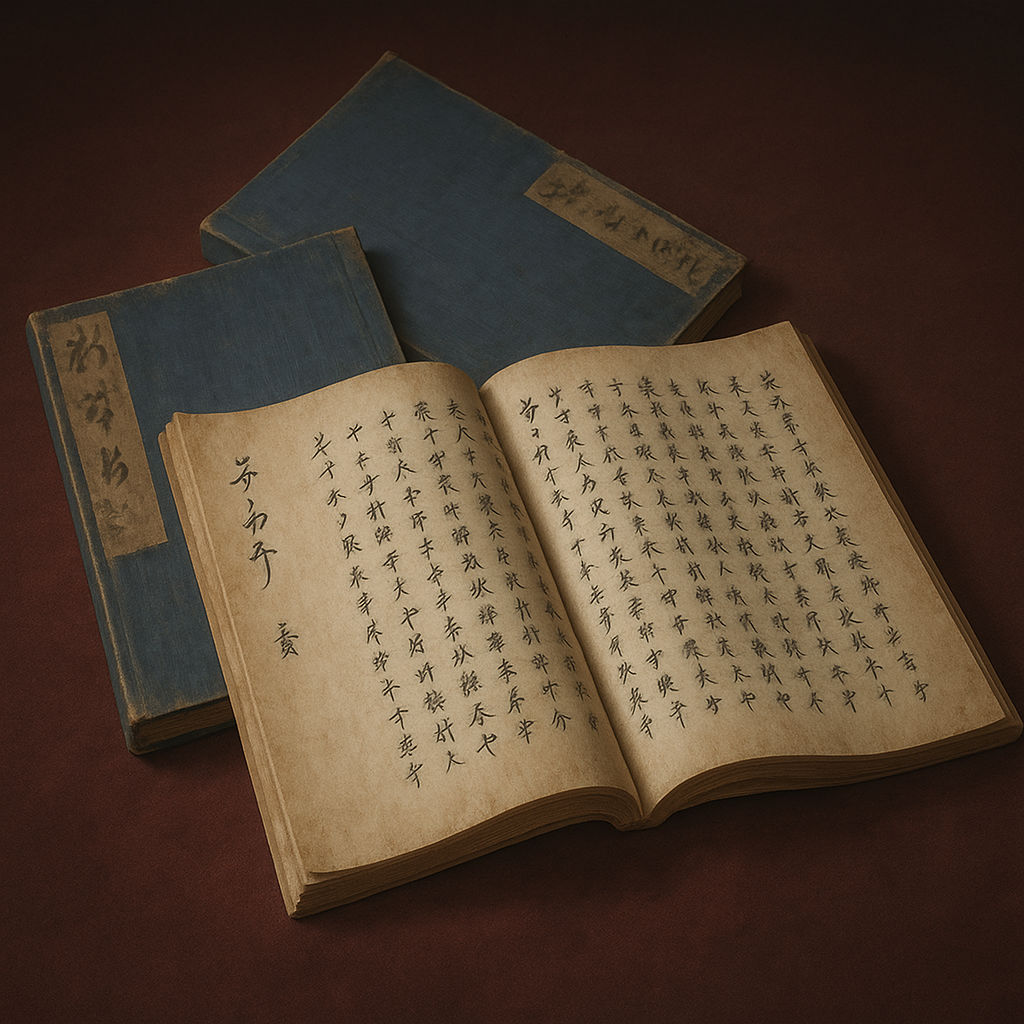
『古今和歌集』と戦国時代—武威の世における文雅の権威—
序論:平安の雅、戦国の威光—時代を超越する『古今和歌集』
本報告書は、平安時代初頭の延喜5年(905年)に編纂された優美な和歌集が、それから約500年の時を経て、武力こそが全てを決定する下剋上の戦国時代において、なぜ武将たちが渇望する最高の文化的権威として君臨し得たのか、という壮大な歴史的パラドックスを解明することを目的とする。雅(みやび)を極めた宮廷文化の精華が、血で血を洗う武威の世で、いかにして絶大な価値を持つに至ったのか。この問いは、日本文化における権威の構造と、その変容の本質を我々に突きつける。
この謎を解く鍵は、『古今和歌集』の解釈を巡る秘伝の授受、すなわち「古今伝授」にある。古今伝授は、単なる文学研究や学問の継承に留まるものではなかった。それは、特定の師から選ばれた弟子へと、厳格な儀礼を経て相伝される「秘中の秘」であり、授けられた者には計り知れない権威と名誉が与えられた。それは、政治的・社会的な力を帯びた一種の文化資本であった 1 。
本報告書は、この壮大な問いに答えるため、四部構成を採る。第一部では、『古今和歌集』そのものが持つ本質的な性格、すなわち後世に絶大な権威を持つに至った源泉を明らかにする。第二部では、一介の文学作品であった『古今和歌集』が、いかにして神秘的な「秘伝」へと姿を変え、その価値を飛躍的に高めていったのか、その権威化の過程を追う。第三部では、報告書の核心として、戦国という実力主義の時代に、なぜ「古今伝授」が武将たちにとって死活的に重要な意味を持ったのかを、具体的な事例を通して解き明かす。そして第四部では、『古今和歌集』が戦国武将の精神性や、後世に残る「モノ」や「制度」に与えた影響を探る。これらの分析を通じて、時代を超えて価値を変容させ続けた『古今和歌集』の力学を、深く、そして多角的に論じていく。
第一部:『古今和歌集』の成立と本質—「やまと歌」の規範
この部では、『古今和歌集』がなぜ後世、特に戦国時代において絶大な権威を持つに至ったのか、その源泉となる本質的な性格を、成立の背景、歌風、そして古典としての地位確立という三つの側面から明らかにする。
第一章:勅撰という国家事業
『古今和歌集』の権威の根源は、その文学的価値のみならず、その出自に深く根差している。それは、天皇の命による「勅撰」、すなわち国家事業として編纂された日本初の和歌集であったという事実である 3 。
延喜の治と国風文化
平安時代初期は、奈良時代から続く唐風文化が極盛期を迎え、勅撰漢詩集が三度にわたり編纂されるなど、漢詩文が公的な文学の中心を占めていた 7 。和歌は私的な表現形式と見なされ、公の場からは後退していた。しかし、9世紀末から10世紀にかけて、遣唐使の廃止などを契機に、日本の風土や感性に基づいた独自の文化、いわゆる「国風文化」が確立していく 8 。この大きな時代の趨勢の中で、延喜5年(905年)4月18日、醍醐天皇は国家事業として新たな和歌集の編纂を命じた 4 。この勅命は、それまで私的な領域に留まっていた「やまと歌(和歌)」を、漢詩文と並ぶ公的な国家文学へと引き上げる画期的な出来事であった。当初は『続万葉集』とも擬されたが、天皇の意向により『古今和歌集』と名付けられた 6 。
撰者たちの役割と「仮名序」の宣言
この国家的な大事業の撰者として選ばれたのは、紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑という、いずれも当代一流の宮廷歌人たちであった 3 。編纂作業は9年近くに及び、延喜13年(913年)から14年頃に完成したとされるが、その中心的な役割を担ったのが紀貫之である 4 。
貫之の功績の中でも特筆すべきは、彼が執筆した「仮名序」である 7 。漢文で書かれた「真名序」(紀淑望執筆)とは別に、平易な仮名文で書かれたこの序文は、日本初の本格的な歌論として、後世の文学に絶大な影響を与えた 13 。その冒頭に記された「やまとうたは、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」という一文はあまりにも有名である 13 。ここで貫之は、和歌が人間の自然な感情の発露であることを述べ、さらには「力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をもなぐさむるは、歌なり」と続け、和歌が天地や神々、そして人の心をも動かす絶大な力を持つことを高らかに宣言した 14 。これは、和歌の地位を漢詩文と同等、あるいはそれ以上に高めようとする、文化的な独立宣言に他ならなかった。
権威の源泉としての「国家性」
なぜ数ある歌集の中で『古今和歌集』がこれほどまでに特別視されたのか。その最大の理由は、それが日本初の「勅撰」和歌集であるという点にある。これは単なる編纂形式の違いではない。「勅撰」とは、和歌が個人の趣味や私的な遊戯の領域を脱し、時の最高権力者である天皇が公的にその価値を認め、国家の文化として位置づけたことを意味する。この天皇による権威付け、いわば「国家のお墨付き」こそが、『古今和歌集』の揺るぎない権威の源泉となったのである。
この事実は、後世、特に中央の権威が揺らぎ、武士が実力で覇を競った戦国時代において、逆説的にその価値を増大させた。下剋上によって成り上がった武将たちは、自らの権力基盤の脆弱性を常に意識していた。武力による支配を盤石なものにするためには、武力以外の「権威」によって自らを正当化する必要があった 15 。その彼らが求めたのが、揺るぎないはずの伝統的権威、すなわち天皇の権威であった。そして、その天皇の権威に自らを接続するための最も象徴的で有効な文化的媒体が、初の勅撰和歌集である『古今和歌集』だったのである。
第二章:理知と情趣の歌風
『古今和歌集』の美学は、先行する『万葉集』とは対照的な性格を持つ。その歌風は、優美で繊細、そして極めて知的なものであり、平安貴族の洗練された美意識を体現していた。
「たおやめぶり」の美学と高度な修辞
『万葉集』の歌風が、素朴で力強い「ますらをぶり(丈夫ぶり)」と評されるのに対し、『古今和歌集』のそれは、優美で繊細な「たおやめぶり(手弱女ぶり)」と称される 8 。そこには、自然や人事をありのままに詠うのではなく、理知のフィルターを通して再構成し、洗練された言葉で表現しようとする貴族的な美意識が貫かれている。
その最大の特徴が、掛詞(一つの言葉に二つ以上の意味を持たせる)、縁語(ある言葉と関連の深い言葉を同じ歌に詠み込む)、見立て(あるものを別のものになぞらえる)といった修辞技法を駆使した、理知的・観念的な作風である 4 。例えば、
袖ひちて むすびし水の こほれるを 春立つ今日の 風やとくらむ (紀貫之) 5
この歌では、夏に袖を濡らして手ですくった水が冬に凍り、それを立春の風が解かすだろうと想像する。実際の情景ではなく、頭の中で時間を超えて組み立てられた知的な構成が見て取れる。こうした知的遊戯性は、歌の表面的な意味の奥に、さらなる解釈の余地を生み出した。この「解釈の必要性」こそが、後の「古今伝授」という専門的な知の体系が成立する豊かな土壌となったのである。歌に込められた深い意味を読み解く能力は、教養の証とされた。
代表的歌人とその多様性
『古今和歌集』には、撰者の四人をはじめ、約127人の歌人の作品が収められている 4 。中でも、撰者たち以前の時代を代表するのが、「六歌仙」と呼ばれる僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主である 5 。
ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原業平) 5
花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町) 5
業平の歌は情熱的であり、小町の歌は華麗さと無常観を併せ持つ。彼らの多様な個性が、歌集全体に豊かな彩りと深みを与えている。興味深いのは、紀貫之が「仮名序」の中で六歌仙を批評している点である。特に在原業平については「その心余りて、詞たらず。しぼめる花の色なくて、にほひ残れるがごとし」と評した 19 。これは、歌に込める情熱は豊かだが、それを表現する言葉の技巧が追いついていない、という評価である。この批評は、まさに『古今和歌集』が「心(内容・情熱)」と「詞(言葉・技巧)」のバランス、とりわけ「詞」の洗練を重視する美学を持っていたことを示す好例と言えよう。
第三章:古典としての地位確立
『古今和歌集』は、単なる一歌集に留まらず、その後の和歌の歴史における絶対的な「規範」となり、揺るぎない古典としての地位を築いていった。
後続勅撰集の模範
『古今和歌集』が確立した構成は、後世の勅撰和歌集の基本的な手本となった。春(上・下)、夏、秋(上・下)、冬、賀、離別、羈旅、物名、恋(一〜五)、哀傷、雑(上・下)、雑体、大歌所御歌という全二十巻の構成と、四季の歌から始まり恋の歌で中心をなし、雑歌で締めくくるという部立(分類)の形式は、その後の勅撰集に基本的に継承された 7 。平安時代から室町時代にかけて編纂された『後撰和歌集』から『新続古今和歌集』に至る二十の勅撰和歌集は、総称して「二十一代集」と呼ばれるが、『古今和歌集』はその全ての始まりに位置する「始祖」なのである 6 。
表1:二十一代集一覧
|
番号 |
名称 |
主な撰者 |
成立年代(西暦) |
|
1 |
古今和歌集 |
紀貫之、紀友則 他 |
905年頃 |
|
2 |
後撰和歌集 |
梨壺の五人 |
951年頃 |
|
3 |
拾遺和歌集 |
花山院(諸説あり) |
1005-1007年頃 |
|
4 |
後拾遺和歌集 |
藤原通俊 |
1086年 |
|
5 |
金葉和歌集 |
源俊頼 |
1124-1127年頃 |
|
6 |
詞花和歌集 |
藤原顕輔 |
1151年頃 |
|
7 |
千載和歌集 |
藤原俊成 |
1187年頃 |
|
8 |
新古今和歌集 |
藤原定家、藤原家隆 他 |
1205年頃 |
|
9 |
新勅撰和歌集 |
藤原定家 |
1235年頃 |
|
10 |
続後撰和歌集 |
藤原為家 |
1251年 |
|
11 |
続古今和歌集 |
藤原為家 他 |
1265年 |
|
12 |
続拾遺和歌集 |
二条為氏 |
1278年 |
|
13 |
新後撰和歌集 |
二条為世 |
1303年 |
|
14 |
玉葉和歌集 |
京極為兼 |
1312年頃 |
|
15 |
続千載和歌集 |
二条為世 |
1320年 |
|
16 |
続後拾遺和歌集 |
二条為藤、二条為定 |
1326年 |
|
17 |
風雅和歌集 |
花園院 |
1344-1349年頃 |
|
18 |
新千載和歌集 |
二条為定 |
1359年 |
|
19 |
新拾遺和歌集 |
二条為明、二条為遠 |
1364年 |
|
20 |
新後拾遺和歌集 |
二条為遠、二条為重 |
1384年 |
|
21 |
新続古今和歌集 |
飛鳥井雅世 |
1439年 |
出典: 6 に基づき作成
この表が示すように、『古今和歌集』は単独の作品ではなく、約500年にわたる長大な「国家事業」の第一号であった。この歴史的スケールと、全ての始まりとしての圧倒的な第一性こそが、戦国武将たちが他のいかなる歌集でもなく、この『古今和歌集』の権威にこだわった根本的な理由を物語っている。
平安貴族社会の必修教養
『古今和歌集』は、編纂後まもなく平安貴族社会における最高の古典、そして必須の教養としての地位を確立した。『枕草子』には、当時の貴族が『古今和歌集』二十巻をすべて暗唱していることを当然の教養と見なしていた様子が描かれている 8 。また、日本文学の最高峰である『源氏物語』においても、『古今和歌集』の歌は物語の重要な場面で頻繁に引用され、登場人物の心情や情景を効果的に表現するために用いられている 8 。これは、当時の貴族社会において、『古今和歌集』を深く理解し、自在に引用できることが、洗練された文化人であることの何よりの証であったことを示している。この「教養の頂点」としての位置づけが、後世、文化的な権威を求める人々にとって、到達すべき目標として仰ぎ見られる素地を形成したのである。
第二部:「古今伝授」の誕生と権威化—秘伝としての文化資本
この部では、公的な文学作品であった『古今和歌集』が、いかにして神秘性を帯びた「秘伝」へと姿を変え、その価値を飛躍的に高めていったのかを解明する。この変容のプロセスこそが、戦国武将たちがそれを渇望する背景を理解する上で不可欠である。
第一章:解釈から秘伝へ
『古今和歌集』が成立してから100年以上が経過した平安時代中期以降、その本文や語句の解釈を巡って、様々な問題が生じ始めた 20 。写本が重ねられる過程で本文に異同が生じ、また、時代が下るにつれて言葉の意味も変化し、歌の正確な解釈が困難になっていったのである。
こうした状況の中で、和歌を家業とする専門家、すなわち「歌学の家」が登場する。その代表格が、鎌倉時代初期に活躍した歌人、藤原俊成・定家親子を祖とする御子左家(みこひだりけ)である 6 。彼らは、自らの家系に伝わる『古今和歌集』の解釈を「秘説」として体系化し、それを嫡子や高弟にのみ伝えるという慣習を確立していった 1 。やがて御子左家は二条、京極、冷泉の三家に分かれるが、特に二条家が和歌の家として主流となり、その秘伝は最高の権威を持つと見なされるようになった 22 。こうして、誰もが享受できるはずの文学作品の解釈が、特定の家系によって独占され、閉鎖的な「秘伝」として権威化されていく道筋がつけられたのである。
第二章:東常縁から宗祇へ—「伝授」の形式化
「古今伝授」が今日知られるような、厳格な儀礼を伴う一つの完成されたシステムとして確立されたのは、室町時代中期のことである。その中心人物が、武士でありながら当代随一の歌人であった東常縁(とうのつねより)である 2 。
応仁の乱(1467-1477年)という未曾有の動乱の最中、常縁は、二条派の正統な歌学を集大成し、その伝授形式を整えた 1 。そして文明3年(1471年)、この「古今伝授」の歴史において一大転機となる出来事が起こる。常縁が、当代最高の連歌師であった宗祇(そうぎ)に、その秘伝の全てを授けたのである 2 。この相伝は、古今伝授が公家の閉ざされた世界から、武士や連歌師といったより広い階層へと開かれる可能性を示唆する画期的な出来事であり、これをもって常縁は「古今伝授の祖」と称されるようになった 6 。
この時確立された伝授のプロセスは、極めて厳格かつ儀式的なものであった。まず、弟子は師に対して誓状を提出し、伝授された内容を他言しないことを固く誓わされる 26 。その上で、『古今和歌集』の本文の正確な読み方(清濁や句読点など)から、語句の深い意味についての講釈を受ける。弟子は講義内容を「聞書(ききがき)」、すなわちノートにまとめ、それを師に提出する。師は内容を精査し、必要な補筆訂正を加えた上で、伝授を証明する「奥書」を記して弟子に返却した 26 。そして最終段階では、書くことすら許されない秘説が口伝(くでん)で伝えられ、さらに特に重要な秘中の秘は、一枚一枚の短冊状の紙に記した「切紙(きりがみ)」という形で授与され、伝授は完了した 1 。この複雑で神秘的なプロセスこそが、古今伝授の神聖性と、授けられた者に与えられる絶大な権威を演出する装置として機能したのである。
第三章:「三木三鳥」の謎—秘中の秘
古今伝授の数ある秘説の中でも、その中核をなし、最も神秘のヴェールに包まれていたのが「三木三鳥(さんぼくさんちょう)」と呼ばれる、三種の植物と三種の鳥に関する解釈であった 2 。
具体的には、三木とは「おがたまの木」「めどに削り花」「かはなぐさ」、三鳥とは「よぶこどり」「ももちどり」「いなおほせどり」を指す 6 。これらは『古今和歌集』の歌中に登場する言葉であるが、その正体は定かでなく、様々な解釈がなされてきた。例えば、「おがたまの木」はモクレン科の常緑樹、「よぶこどり」はカッコウのことなどとされるが、特に「いなおほせどり」に至っては「秋に来る渡り鳥」というだけで正体不明とされる 6 。
ここで重要なのは、なぜ「梅・桜・紅葉」や「鶯・ほととぎす・雁」といった、和歌で頻繁に詠まれる馴染み深い動植物ではなく、これほどまでに難解で、ほとんど誰も知らないような奇妙な言葉が秘伝の中心に据えられたのか、という点である 21 。その理由は、まさにその「分からなさ」にこそあった。一般的な知識や教養では到底到達できない「特別な知」であることを演出するために、あえて難解な題材が選ばれたのである。誰もが知っている事柄に希少価値はない。この「特別な知」を授けられるということは、数多いる歌人の中から選ばれた、特別な存在であることの証明に他ならなかった。それは、文化的なエリートとしてのアイデンティティを授与する、一種の通過儀礼であった。
したがって、「三木三鳥」の謎は、その解釈内容の合理性や実用性に価値があったのではない。むしろ、その難解さ、神秘性、そして何よりも「秘されている」という事実そのものが、権威を生み出すための巧妙な「文化的装置」として機能していたのである。その内容は、ある意味で空疎であったかもしれない 2 。しかし、その周りに構築された秘儀性のオーラこそが、人々を惹きつけ、戦国武将をしてそれを渇望させる力の源泉となったのであった。
第四章:権威の系譜
宗祇に授けられた古今伝授は、その後、複数の系統に分かれて継承されていく。この「権威の系譜」を理解することは、なぜ戦国時代に細川幽斎という一人の武将が、文化的に絶大な影響力を持つに至ったのかを解明する上で決定的に重要である。
表2:古今伝授の主要な相承系図
Mermaidによる相承系図
graph TD; A[二条家(御子左家嫡流)] --> B[頓阿]; B --> C[東常縁「古今伝授の祖」]; C --> D[宗祇(連歌師)]; D --> E[三条西実隆(公家)]; D --> F[牡丹花肖柏(連歌師)]; E --> G[三条西家]; G --> H[三条西実枝]; H --> I[細川幽斎(武将)]; I --> J[八条宮智仁親王「御所伝授」の確立]; F --> K[堺伝授(堺の町衆へ)]; F --> L[奈良伝授(奈良の文化人へ)]; style A fill:#e6e6fa,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style C fill:#fffacd,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style I fill:#ffb6c1,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style J fill:#add8e6,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style K fill:#90ee90,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style L fill:#90ee90,stroke:#333,stroke-width: 4.0px
出典: 1 に基づき作成
この系図が示すように、宗祇から公家の三条西実隆に伝えられた流れが、古今伝授の正統な本流と見なされるようになった。一方、同じく宗祇から連歌師の牡丹花肖柏に伝えられた系統は、堺の富裕な町衆などに広まり、「堺伝授」「奈良伝授」として分派していく 1 。
戦国時代、三条西家の当主であった実枝は、自らの子が幼かったため、後年子孫に返すという約束のもと、当代きっての文化人武将であった細川幽斎(藤孝)にこの正統な古今伝授を相伝した 1 。これにより、細川幽斎は、公家社会が保持してきた最高の文化的権威の、唯一の正統な継承者となったのである。この系図は、幽斎が帯びていた文化資本の「血統書」に他ならず、後に朝廷や他の武将たちが彼をいかに特別視したか、その根拠を雄弁に物語っている 27 。
第三部:戦国武将と『古今和歌集』—武威と文雅の交錯
この部では、報告書の核心として、戦国という武力と実力主義が支配した時代に、なぜ平安の雅の象徴である『古今和歌集』と、その秘伝たる「古今伝授」が、武将たちにとって死活的に重要な意味を持ったのかを、具体的な事例を通して解き明かす。
第一章:なぜ武将は和歌を求めたのか
下剋上が常態化し、旧来の室町幕府の権威が失墜した戦国時代、武将たちは自らの支配を正当化するための新たな権威を渇望していた 15 。領国を切り取り、軍事力で他者を圧倒するだけでは、人心の完全な掌握は難しかった。支配には、武力だけでなく、それを裏付ける「正統性」が必要だったのである。
その正統性の源泉として、武将たちが目を向けたのが、政治的実権を失ってもなお、最高の文化的権威を保持し続けていた天皇と公家社会であった 15 。そして、その朝廷文化の精髄に触れ、自らをその伝統的権威に接続するための最も有効な手段が、和歌、とりわけその頂点に立つ『古今和歌集』の奥義「古今伝授」を学ぶことであった 29 。古今伝授を受けることは、単なる教養の習得ではなく、自らの地位に文化的な箔をつけ、田舎の成り上がり者ではない、洗練された支配者であることを内外に示すための、極めて戦略的な行為だったのである。
また、和歌や、そこから派生した連歌は、武将間のコミュニケーション、情報交換、そして同盟関係を強化するための、洗練された外交・社交ツールとしても重要な機能を果たした 31 。歌会や連歌会は、互いの教養の深さを探り合い、腹の内を読む高度な政治の場でもあった。したがって、和歌の素養は、一流の戦国武将として生き抜くための必須の教養であり、戦略的スキルの一つとさえ見なされていたのである 28 。
この和歌への関与は、一部の特異な武将に限られたものではなく、多くの有力大名に共通する戦略的な行動であった。
表3:主要戦国武将と和歌・古今伝授への関与
|
武将名 |
古今伝授との関わり |
著名な和歌・文化政策 |
|
細川幽斎(藤孝) |
三条西家より古今伝授を相伝。唯一の継承者となる。 |
自身も当代一流の歌人。田辺城籠城戦でその価値が証明される。茶道、能楽にも通じた文化人 28 。 |
|
今川義元 |
直接の相伝はないが、冷泉家など公家との交流が深い。 |
駿府に京文化を移植し、多くの文化人を招聘。自らも和歌や連歌を嗜み、領国支配に文化政策を活用した 22 。 |
|
大内義隆 |
連歌師・宗碩(宗祇の弟子)から古今伝授を受ける。 |
山口を「西の京」として繁栄させ、勘合貿易で得た富で文化を保護。和歌や連歌に傾倒したが、後にそれが仇となる 35 。 |
|
伊達政宗 |
直接の相伝はないが、和歌の才能は高く評価される。 |
秀吉主催の歌会にも招かれるほどの実力。能楽なども愛好し、武だけでなく文にも秀でた教養人であった 35 。 |
|
織田信長 |
自身は和歌より実利を重んじるが、文化の政治利用には長ける。 |
「人間五十年」の幸若舞を好む一方、朝廷との関係維持のため文化行事を利用。和歌も残している 42 。 |
出典: 28 等に基づき作成
第二章:細川幽斎と田辺城の戦い—文化が命を救う時
古今伝授が持つ政治的・軍事的な価値が、最も劇的な形で発揮されたのが、関ヶ原の戦いの前哨戦として知られる「田辺城の戦い」である。
慶長5年(1600年)7月、天下分け目の戦いが迫る中、徳川家康方についた細川幽斎は、子の忠興が上杉征伐で留守にしている間、居城である丹後田辺城に立て籠もった 44 。これに対し、石田三成方の西軍は、小野木重次らを大将とする1万5千もの大軍を差し向け、城を完全に包囲した。城内の兵力はわずか500。兵力差は30倍であり、落城は時間の問題と誰もが考えていた 27 。
しかし、ここで事態は誰もが予想しなかった展開を見せる。この時、細川幽斎は、三条西家から相伝された古今伝授を継承する、地上でただ一人の人物であった 27 。もし幽斎がここで戦死すれば、和歌の最高奥義である古今伝授は永遠に地上から失われてしまう。この事態を最も憂慮したのは、時の後陽成天皇であった 27 。天皇は、文化的な至宝の断絶を恐れ、朝廷の権威をもってこの軍事衝突に介入することを決意する。
天皇はまず、幽斎の歌道の弟子でもあった八条宮智仁親王を派遣して開城を勧告させるが、幽斎はこれを拒否 27 。死を覚悟した幽斎は、逆に古今伝授に関する資料などを朝廷に献上し始めた 27 。ここに及び、天皇はついに勅使として公家の三条西実条らを派遣し、東西両軍に対して「講和せよ」との勅命を下したのである 27 。天皇の命令は絶対であり、西軍の諸将もこれに逆らうことはできず、城の包囲を緩めた。幽斎も勅命を奉じ、ついに城を開け渡した 48 。
この一連の出来事は、文化の力がこれほど直接的に戦局に影響を与えた、日本史上極めて稀な事例である。ここで「古今伝授」という無形の文化資本は、単に幽斎の命を救う「お守り」として機能しただけではなかった。それは、より具体的で戦略的な軍事効果をもたらしたのである。幽斎が約二ヶ月にわたり籠城を続けた結果、1万5千という西軍の兵力は田辺城に釘付けにされた 27 。彼らは、9月15日に行われた関ヶ原の主戦場に駆けつけることができず、西軍敗北の一因になったとさえ言われている 27 。つまり、幽斎が独占していた「古今伝授」という他に替えのきかない文化資本は、失われる危機に瀕したことで天皇を動かし、その天皇の権威が敵軍の軍事行動を停止させ、結果として具体的な軍事的成果を生み出す「戦略兵器」へと転換されたのである。
第三章:今川氏・大内氏の文化戦略
細川幽斎の事例は突出しているが、文化、特に和歌を自らの権威付けと領国経営に利用しようとした大名は他にも存在した。
「海道一の弓取り」と恐れられた駿河の今川義元は、その武威だけでなく、卓越した文化政策家でもあった。彼は京都から公家や高名な僧、連歌師らを積極的に駿府に招き、領国を「東国の京」と呼ぶにふさわしい文化都市として発展させた 36 。義元自身も和歌や連歌を深く嗜み、冷泉家などの公家とも緊密な関係を築いていた 22 。彼の文化政策は、単なる趣味ではなく、領国の安定と支配の正当性を確保するための、高度な政治戦略であった。
また、西国に巨大な勢力圏を築いた周防の大内義隆も、文化の力を重視した大名であった。彼は勘合貿易で得た莫大な富を背景に、山口に京文化を移植し、華やかな「大内文化」を花開かせた 40 。義隆もまた、連歌師の宗碩から古今伝授を受けており、和歌や芸能に深く傾倒した 38 。しかし、彼の場合は、後に軍事を軽んじ文化的な遊興に溺れたことが家臣団の離反を招き、陶晴賢の謀反によって自害に追い込まれるという悲劇的な結末を迎えた 35 。これは、文化の力が権威となり得る一方で、そのバランスを誤れば身を滅ぼす危険性をも孕んでいたことを示している。
第四章:連歌会という社交場
戦国時代、武士の教養として茶の湯とともに重要視されたのが連歌であった 28 。連歌会は、単なる文芸の会ではなく、武将たちにとって重要な社交の場として機能した 32 。特に出陣前に戦勝を祈願して神仏に奉納する「出陣連歌」は、士気を高め、結束を固めるための重要な儀式であった 32 。
この連歌を詠む上で、極めて重要だったのが古典の知識である。連歌では、前の句を受けて次の句を詠むだけでなく、「本歌取り」といって、有名な古歌(古典和歌)の一節を巧みに自らの句に織り込む技法が賞賛された 15 。この「本歌」の最大の供給源こそが、『古今和歌集』や『伊勢物語』、『源氏物語』といった古典文学であった。したがって、『古今和歌集』に精通していることは、連歌という武士社会の重要なコミュニケーションツールを使いこなし、教養ある人物として認められるための、いわば「共通言語」であり、必須の知識だったのである。
第四部:戦国時代における『古今和歌集』の美学的・物質的遺産
この部では、『古今和歌集』が戦国武将の精神性、すなわち死生観にどのような影響を与えたか、そして「古今伝授」が後世に残る「モノ」や「制度」として、どのようにその権威を刻みつけたのかを探る。
第一章:辞世の句にみる「もののあはれ」
死と常に隣り合わせに生きた戦国武将たちは、その生涯の最期に、自らの心情を詠んだ「辞世の句」を残すことが多かった。驚くべきことに、その壮絶な死に様とは裏腹に、彼らの辞世の句には、平安貴族の優雅な感傷であったはずの「もののあはれ」の美学が色濃く反映されている 52 。
散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ (細川ガラシャ) 52
筑摩江や 芦間に灯す かがり火と ともに消えゆく 我が身なりけり (石田三成) 52
限りあれば 吹かねど花は 散るものを 心みじかき 春の山風 (蒲生氏郷) 52
細川ガラシャは、自らの死を桜の花が最も美しい時に散る様に重ね合わせ、潔い死こそが人間を人間たらしめると詠んだ。石田三成は、故郷の風景の中のかがり火が消えていく様に、自らの命のはかなさを託した。若くして病に倒れた蒲生氏郷は、いずれ散る運命の花を急かす春の山風に、自らの無念を投影した。
ここに共通して見られるのは、『古今和歌集』以来、日本の文学を貫いてきた、移ろいゆくもののはかなさ(無常)の中にこそ、深い趣や美を見出すという価値観である 17 。平安貴族にとっての「もののあはれ」が、季節の移ろいや恋の行方に対する繊細な感傷であったとすれば、戦国武将にとっては、それは自らの「死」という究極の現実と向き合うための、より切実で実践的な精神的支柱へと昇華されていた。彼らは、自らの過酷な運命をただ嘆くのではなく、『古今和歌集』的な美学のレンズを通して捉え直した。自らの死を、散りゆく花や消えゆく露、かすみに重ね合わせることで、単なる敗北や絶命ではなく、一つの美的な完結として意味づけようとしたのである。したがって、彼らの辞世の句は、単なる遺言ではない。それは、平安の雅を自らの死生観の核心に取り込み、壮絶な生涯を美しく締めくくろうとする、最後の自己表現であり、究極の美学の実践であったと言える。
第二章:「古今伝授の太刀」—権威の象徴物
古今伝授という無形の権威は、やがて有形の「モノ」にその価値を託され、物語化されていく。その最も象徴的な例が、国宝「太刀 銘 豊後国行平作」、通称「古今伝授の太刀」である 36 。
この太刀は、前述の田辺城籠城の際、講和の勅使として訪れた公家・烏丸光広に対し、細川幽斎が城中で古今伝授の奥義を授けた証として贈ったものと伝えられている 36 。本来、知識や解釈といった無形であるはずの「伝授」が、一振りの太刀という物質的な形を与えられたのである。この逸話により、この太刀は単なる美術品や武器ではなく、「古今伝授の権威そのもの」を体現する神聖な象徴物となった。後に烏丸家から人手に渡っていたこの太刀を、昭和に入って細川家が買い戻したという事実も、この太刀に付与された物語的価値の大きさを物語っている 58 。これは、文化資本が物質的な価値へと転換し、一族の権威を象徴する宝物(レガリア)として後世に伝えられていく典型的なプロセスを示している。
第三章:堺・奈良伝授と地下への流布
細川幽斎に伝えられた三条西家の系統が「御所伝授」として宮中を中心にその権威を保った一方で、古今伝授は別のルートを辿って、より広い社会階層へと拡散していった 1 。
宗祇から連歌師の牡丹花肖柏に伝えられた系統は、当時、経済的に大きく発展していた自治都市・堺の富裕な町衆へと伝授され、「堺伝授」と呼ばれた 1 。また、そこからさらに奈良の文化人へと伝わったものは「奈良伝授」と称された 1 。これにより、古今伝授はもはや公家や武家といった支配階級だけの独占物ではなく、経済力を背景に文化の担い手として台頭してきた新興の町人階級へと広がっていったのである。これは、近世における町人文化の形成に大きく寄与した一方で、秘伝であったはずの権威が拡散し、その希少価値が薄れていく、すなわち形骸化の第一歩でもあったことを示唆している 2 。後には、内容の伴わない形式的な伝授や、大げさで内容に乏しい教えの比喩として「古今伝授」という言葉が使われることさえあった 2 。
結論:権威の変容と再評価
本報告書で詳述してきたように、『古今和歌集』の価値と権威は、時代と共にその核心をダイナミックに変容させ続けた。
成立期である平安時代には、それは国家事業として編纂された「文学的規範」であり、和歌の絶対的な手本としての価値を持っていた。中世に入ると、その解釈は特定の家系によって独占され、神秘的な儀礼を伴う「秘伝的知識」としての価値を高めた。そして戦国時代、その秘伝は、武力で成り上がった武将たちが自らの支配を正当化するための「政治的・社会的権威」へと、その性格を大きく転換させた。細川幽斎の事例が示すように、それは時に軍事力をも左右するほどの絶大な力として機能したのである。
しかし、徳川幕府による平和な世が訪れると、その政治的価値は次第に薄れていく。さらに江戸時代中期以降、本居宣長に代表される国学者たちが、技巧的で理知的とされた『古今和歌集』よりも、素朴で力強い『万葉集』の価値を高く評価するようになると、その権威は一度大きく失墜することになる 8 。
だが、その価値が完全に失われたわけではない。近代以降、その文学史的、そして文化史的な重要性は再び見直され、日本人の美意識の源流を形成した不朽の古典として、今日に至るまで研究され続けている。『古今和歌集』の物語は、一つの文学作品が、時代の要請に応じていかにその意味を変え、社会の中で多様な役割を果たし得るかを示す、壮大な証言なのである。
引用文献
- 古今伝授 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88
- 古今伝授(コキンデンジュ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88-63700
- www.city.nomi.ishikawa.jp https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000621/index.html#:~:text=%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BB%B6%E5%96%9C5,%E7%AC%AC1%E5%8F%B7%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
- 古今和歌集(コキンワカシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86-63702
- 古今和歌集とは?成り立ちや代表的な歌人たちについて - ワノココロ https://wanococoro.jp/blog/5h3-qes-rvg/
- 古今伝授とは http://www.kokindenju.com/kokindenju.html
- 古今和歌集 - 古典文学 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=529
- 古今和歌集- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
- 古今和歌集- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
- 古今集(正式には「古今和歌集」) | 文学マップ | ネットミュージアム兵庫文学館 - 兵庫県立美術館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/bungaku/jousetsu/bungakumap/koten/k16/
- 古今和歌集(清輔本)|能美ふるさとミュージアム https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000621/index.html
- 八代集の世界:古今和歌集 - 関西大学 http://kul01.lib.kansai-u.ac.jp/library/etenji/hachidaisyu/kokin/index.html
- 紀貫之と百人一首/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/hyakunin-isshu-kajin/kajin-kino-tsurayuki/
- 【古典コラム】~和歌(みそひともじの文学)~ | オンライン個別指導の個別教師Camp https://kobetsukyoushicamp.jp/blog/4787/
- 【橋本麻里のつれづれ日本美術】「古今伝授の太刀」の物語(前編) なぜ武士が和歌を追求したのか | 紡ぐプロジェクト https://tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/%E3%80%90%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%BA%BB%E9%87%8C%E3%80%91%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88%E3%81%AE%E5%A4%AA%E5%88%80%E3%81%AE%E7%89%A9%E8%AA%9E%E5%89%8D%E7%B7%A8/
- 武士はなぜ歌を詠むか:[慶應義塾大学 大学院文学研究科] https://www.gsl.keio.ac.jp/research/spotlight/25/index.html
- 古今和歌集|日本の文学史いちらん|国語の部屋 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/bungaku/kokinwakasyuu.htm
- 「三大和歌集の特徴|個別指導Wam吉備校」 - WAM ブログ https://www.k-wam.jp/blogs/2021/07/post-64096/
- 心と詞で知る、三大集(万葉、古今、新古今)と玉葉集(京極派)の歌風 https://wakadokoro.com/learn/%E5%BF%83%E3%81%A8%E8%A9%9E%E3%81%A7%E7%9F%A5%E3%82%8B%E3%80%81%E4%B8%89%E5%A4%A7%E9%9B%86%EF%BC%88%E4%B8%87%E8%91%89%E3%80%81%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E3%80%81%E6%96%B0%E5%8F%A4%E4%BB%8A%EF%BC%89%E3%81%A8/
- 古今伝授の里フィールドミュージアム - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/information/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88%E3%81%AE%E9%87%8C%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0/
- 「古今伝授」と秘伝ブランディング - 令和和歌所 https://wakadokoro.com/learn/%E3%80%8C%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E7%A7%98%E4%BC%9D%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/
- 【京の国宝 知られざる物語 vol.1】家宝継承、1000年の闘い~冷泉家を訪ねて | 紡ぐプロジェクト https://tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/reizeikewotazunete/
- 044「歌を詠んで城を取り戻した男」 https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x044.htm
- 和歌 | 第一部 学ぶ ~古典の継承~ | 国立国会図書館開館60周年記念貴重書展 学ぶ・集う・楽しむ https://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy1/2waka.html
- 古今伝授ってなんだろう? - 大和 http://www.gujoyamato.com/whatskokin.html
- (第184号) 「古今伝授とは」 ~古今伝授のまち三島~ (平成15年9月1日号) - 三島市 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn001151.html
- 美談とされる細川幽斎が籠もった田辺城籠城の真相【前編】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/3390
- 冷静な判断で戦国を生き抜いた細川藤孝の処世術|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-037.html
- 戦国大名・細川幽斎は関ヶ原の戦いの功労者?生涯や評価・本能寺の変のときの行動も解説 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/61747/
- 戦国時代きってのエリート武将・細川藤孝。光秀を裏切って摑んだ「子孫繁栄」の道【麒麟がくる 満喫リポート】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1016156
- 戦国武将、高山右近や蒲生氏郷もキリシタン!茶道とキリスト教の関係はものすごく深かった! https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/99490/
- 連歌師とは何者?連歌会とはどんな場?戦国時代の不思議な職業の ... https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/63285/
- 戦国武将の娯楽/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96766/
- 伊達政宗、織田信長ら名武将は教養も一流だった|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-051.html
- 武将茶人・大名茶人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/99966/
- 今川義元(いまがわ よしもと) 拙者の履歴書 Vol.14〜桶狭間の悲劇 ... https://note.com/digitaljokers/n/na5c8b2d30004
- 桶狭間の戦いで知られる今川義元とは? 「マロ眉」の戦国武将の素顔を探る【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/418271
- 「大内義興」乱世の北九州・中国の覇権を確立。管領代として幕政にもかかわった西国最大の大名 https://sengoku-his.com/811
- 今八幡宮 - 山口市/山口県 の見どころ。国指定重要文... by 勝野武士 https://omairi.club/posts/1201399
- 「大内義隆」西国の覇者として全盛期を迎えるも、家臣のクーデターで滅亡へ。 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/796
- 伊達政宗は漢詩・和歌・能にも頭抜けていた!?文化人としての政宗 https://sengoku-his.com/700
- 戦国武将の内面を「和歌」で垣間見る|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-092.html
- 織田信長を祀る「建勲神社」と信長の「和歌(狂歌)」 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wFsmgEj9aMg
- 舞鶴ふるさと発見館(郷土資料館)だより 令和4年9月号 | 舞鶴市 公式ホームページ https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kyouiku/0000010324.html
- 第3話 時の天皇が命を救った知勇兼備の武将・細川幽斎とは - 小倉城ものがたり https://kokuracastle-story.com/2019/12/story3-hosokawayusai/
- 和歌が上手すぎて命拾いした戦国のスーパーマン、細川幽斎。ゆかりの地、京都と彼を支えた人を追ってみた - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/121463/
- 武士にして最高峰の歌人! 文武両道ゆえに戦国で生き残った細川幽斎 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/6040/
- 田辺城の戦い ~細川幽斎の関ヶ原~ http://www.m-network.com/sengoku/sekigahara/tanabe.html
- 田辺城 細川幽斎 - 舞鶴市 http://www.ginsuikaku.com/kanko/tanabe-castle/index.htm
- 大内義隆(おおうち よしたか) 拙者の履歴書 Vol.157~文雅と戦の狭間に生きて - note https://note.com/digitaljokers/n/n213f8e065d51
- 大内義隆が家臣の陶隆房(陶晴賢)に討たれたのはなぜ?戦国時代の山口で発生した謀反の経緯 https://articles.mapple.net/bk/22575/
- 辞世の句 - Wikiquote https://ja.wikiquote.org/wiki/%E8%BE%9E%E4%B8%96%E3%81%AE%E5%8F%A5
- 辞世の句・和歌シリーズ~小野小町・紫式部・お市の方・細川ガラシャ~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DiikLVIjIX8
- 女性が遺した辞世の句-細川ガラシャ・紫式部・小野小町の最後の言葉 - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/10136/
- 著名人が遺した辞世の句/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/historical-last-words/
- 死ぬ前に戦国武将が残した心震える言葉【辞世の句 】をさくっと解説「名言・辞世・和歌シリーズ」 https://m.youtube.com/watch?v=icj3hT8p9ag&pp=ygUfI-aIpuWbveatpuWwhuWQjeiogOOCueOCv-ODs-ODiQ%3D%3D
- 平安時代の貴族文化: 和歌と物語の世界 - 歴史の教室 https://yamatostudy.com/japan/japan-ancient/nara/heian-literature/
- 国宝-工芸|太刀 銘 豊後国行平作(古今伝授の太刀)[永青文庫/東京] | WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-00293/
- 永青文庫美術館 https://www.eiseibunko.com/collection/bugu3.html
- 古今伝授の太刀 - 日本刀や刀剣の買取なら専門店つるぎの屋 https://www.tsuruginoya.net/stories/kokinndennjunotachi/
- 古今伝授行平/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/search-noted-sword/kokuho-meito/56084/
- 古今和歌集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
- 本居宣長と和歌 - 富山市立図書館 https://www.library.toyama.toyama.jp/file/pdf/kenkyu/yamaki22.pdf