唐船日記
唐船日記は、尋尊が記録した遣明船貿易の詳細な記録。戦国前夜の経済・文化・国際関係、寺社の経済力と貿易参画を示す貴重な史料。
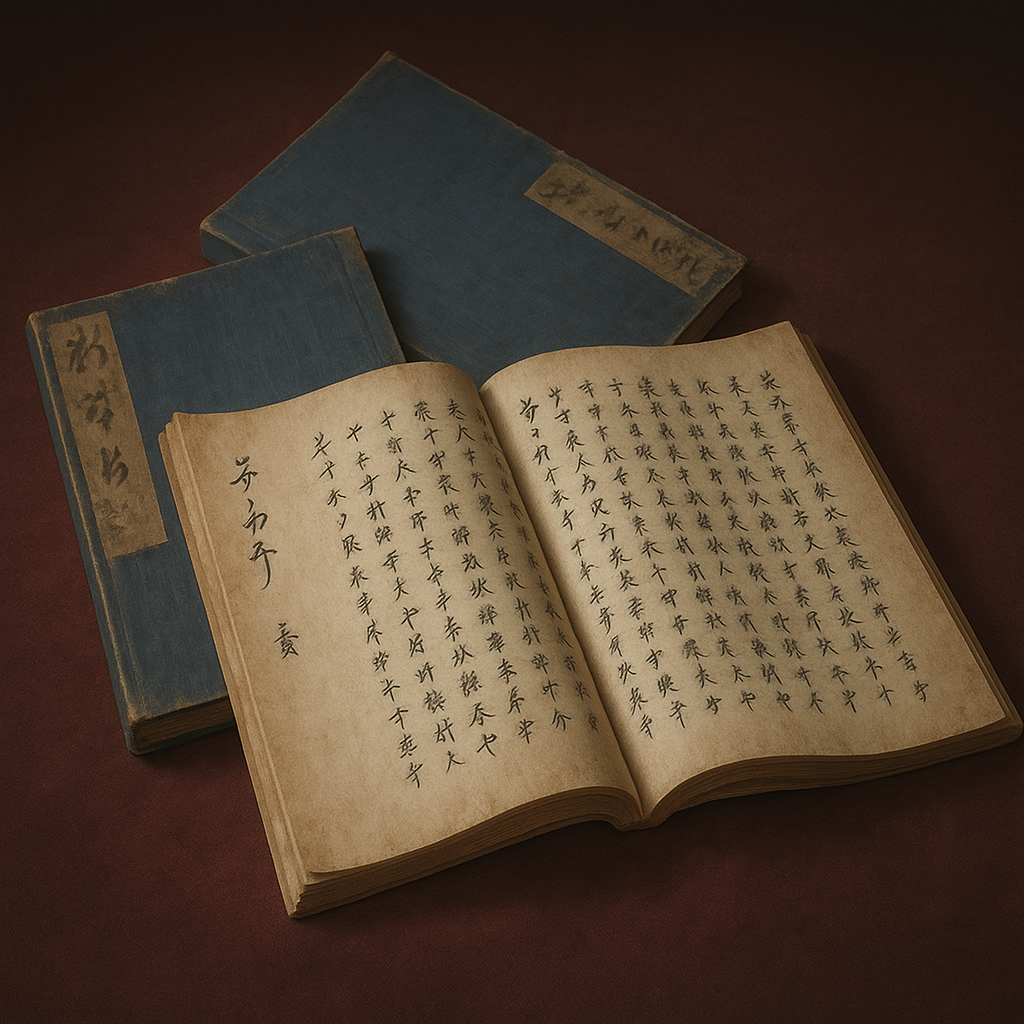
『唐船日記』の徹底分析:戦国前夜の経済・文化・国際関係
序論:『唐船日記』とは何か
概要と史料的価値の再定義
『唐船日記』は、一般に興福寺の別当であった尋尊が、遣明船貿易で活躍した商人・楠葉西忍からの聞書を記録したものとして知られている 1 。この理解は正確であるが、その歴史的価値は単なる貿易実務の記録という範疇を遥かに超える。本書は、15世紀半ばという、室町幕府の権威が揺らぎ始め、守護大名や有力寺社といった新たな権力主体が経済的実権を掌握していく「戦国前夜」とも呼ぶべき時代の社会構造を、具体的な人物、費用、交易品といった生々しいデータを通して活写した第一級の史料である。
この記録が持つ真の価値は、後の戦国時代を特徴づける諸要素、すなわち実力主義的な社会の流動性、経済力と軍事力の直結、そして文化が政治的権威として機能するメカニズムの萌芽を、極めて具体的な形で示している点にある。したがって、『唐船日記』を分析することは、戦国という時代の力学が、どのような経済的・国際的土壌から生まれたのかを解明する上で不可欠な作業となる。
『大乗院寺社雑事記』内の記録としての位置づけ
『唐船日記』という名称で知られる記録は、独立した一冊の書物として存在したわけではない。これは、奈良興福寺大乗院の門跡であった尋尊が、宝徳2年(1450年)から永正5年(1508年)までの半世紀以上にわたって書き継いだ膨大な日記『大乗院寺社雑事記』の中に含まれる、特定主題に関する聞書、あるいはその抜粋を指すものである 3 。『大乗院寺社雑事記』は、応仁の乱を挟む室町時代後期の政治、経済、社会風俗を伝える根本史料として極めて高い価値を持つが、『唐船日記』はその中でも特に日明貿易という経済活動の最前線に焦点を当てた、特異な性格を持つ部分である 2 。
この事実は、『唐船日記』が単なる個人の好奇心による記録ではなく、大和国に絶大な影響力を持った興福寺という巨大な権門勢家による、体系的な情報収集活動の一環として生み出されたことを示唆している。寺社の荘園経営や財政維持という現実的な要請を背景に、富の新たな源泉として注目されていた海外貿易の実態を、当事者から直接聞き取るという極めて合理的な目的がそこにはあったと考えられる。
本報告書が目指す多角的分析の視座
本報告書は、『唐船日記』を単一の古文書としてではなく、戦国時代を準備した歴史的ダイナミズムを解明するための「窓」として位置づける。そのために、経済史、文化史、国際関係史という三つの視点を統合し、多角的な分析を試みる。
経済史の視点からは、遣明船一艘にかかる具体的なコスト構造、交易品とその利益率を分析し、勘合貿易が当時の経済主体にとってどれほど魅力的な事業であったかを定量的に明らかにする。文化史の視点からは、貿易によってもたらされた「唐物」が、いかにして茶の湯という文化的文脈の中で権威の象徴へと転化し、戦国大名の政治力学に影響を与えていったのかを追跡する。国際関係史の視点からは、日明間の朝貢貿易という公式な枠組みと、その中で蠢く多様なプレイヤーたちの実態、さらには琉球王国が主導する中継貿易との比較を通じて、15世紀東アジアの多元的な交易ネットワークの中に『唐船日記』を位置づける。
これらの分析を通じて、一介の僧侶による聞書というミクロな記録から、戦国という時代の扉を開いたマクロな歴史の潮流を読み解くこと、それが本報告書の目指すところである。
第一部:『唐船日記』の内部構造
この部では、『唐船日記』そのものを解剖し、その成立に関わった人物の背景と、記録された具体的な内容を徹底的に分析する。この記録がなぜこれほどまでに詳細かつ信頼性の高い情報を内包し得たのか、その源泉を探る。
第一章:『唐船日記』の成立背景:記録者・尋尊と情報提供者・楠葉西忍
『唐船日記』の比類なき価値は、記録者である尋尊と、情報提供者である楠葉西忍という、二人の特異な人物の邂逅によって生み出された。最高の知性と情報網を持つ貴族出身の僧侶と、現場の生々しい実務知識と国際経験を持つハイブリッドな商人の組み合わせが、この奇跡的な記録を可能にしたのである。
記録者・尋尊(1430-1508)の人物像
尋尊は、永享2年(1430年)に生まれ、永正5年(1508年)に没した室町時代中期から戦国時代にかけての法相宗の学僧である 3 。彼の人物像を理解する上で重要な点は三つある。
第一に、その出自である。尋尊の父は、関白・太政大臣を歴任した当代随一の知識人、一条兼良であった 7 。この出自は、尋尊が幼少期から中央の政治・文化の最高レベルの情報に日常的に接する環境にあったことを意味する。彼の持つ広範な知識と鋭い分析眼は、こうした環境で培われたものであり、貿易という専門外の分野に対しても的確な問いを発し、情報を整理する能力の基盤となった。
第二に、興福寺大乗院門跡という地位である 4 。興福寺は、大和一国を支配するほどの強大な権力と経済力を持つ寺社勢力であり、その中でも大乗院は筆頭格の門跡寺院であった。尋尊は康正2年(1456年)に興福寺のトップである別当に就任し、長谷寺や薬師寺の別当も兼務するなど、巨大な宗教組織の経営者としての顔も持っていた 3 。寺社の荘園経営や財政運営に深く関与する中で、新たな財源としての海外貿易に強い関心を抱いたことは想像に難くない。
第三に、彼の「筆まめな性格」と評されるほどの、並外れた記録への情熱である 9 。彼は自らの見聞を詳細に日記に書き留めるだけでなく、応仁の乱の際には父・兼良の日記を兵火から守り、大乗院に伝わる古記録を整理して目録を作成するなど、記録の保存と編纂に生涯を捧げた 3 。この知的好奇心と後世に情報を伝えんとする使命感こそが、楠葉西忍という稀有な人物から、貿易の極めて具体的な内実を聞き出し、『唐船日記』として結実させた原動力であった。
情報提供者・楠葉西忍(1395-1486)の特異な貌
『唐船日記』に生きた情報をもたらした楠葉西忍は、15世紀の日本において極めて特異な経歴を持つ人物である 1 。
彼の最大の特徴は、その国際的な出自にある。西忍の父は「ヒジリ」という名の天竺人であった 1 。この「天竺」がインドを指すのか、あるいは東南アジアやアラビアを指すのかは定かではないが、彼が異邦人であったことは確かである 12 。父ヒジリは3代将軍足利義満の時代に来日し、相国寺の禅僧・絶海中津の仲介で義満の庇護を受けた貿易商人とされる 13 。一方、母は河内国楠葉(現在の大阪府枚方市)の女性であった 1 。西忍が「楠葉」を姓としたのは、この母の出身地に由来する。彼の幼名が「ムスル」であったことも、その異国的な背景を物語っている 1 。
4代将軍足利義持の代には、父と共に将軍の意に沿わなかったとして一色氏に預けられるという不遇の時期も経験したが、父の死後に許されている 1 。その後、彼は興福寺大乗院門跡の経覚(尋尊の師)のもとで出家して「西忍」と号し、大乗院に仕える「坊人」となった 1 。
彼の活動は多岐にわたる。1432年(永享4年)と1453年(享徳2年)の二度にわたり遣明船で明に渡航し、特に二度目の渡航では、後述する興福寺末寺の船の「外官」(貿易監督官)として30名余りの商人を率い、北京まで赴いて貿易を指揮した 1 。その一方で、大和国平群郡立野に拠点を持ち、現地の武士団である「立野衆」の一員としての性格も有していた 1 。
楠葉西忍のハイブリッドな存在が象徴する時代性
楠葉西忍の経歴を詳細に分析すると、彼が単なる「商人」という枠には収まらない、複数の社会階層の属性を一身に体現した「ハイブリッドな存在」であったことが浮かび上がる。この事実は、室町時代後期の社会の流動性、すなわち後の戦国時代を準備した「下剋上」の社会的前提条件を理解する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる。
第一に、彼は国際貿易の専門家である「商人」であった 13 。二度にわたる渡明経験、特に貿易船の監督官を務めた事実は、彼が航海術、商品知識、交渉術に長けたプロフェッショナルであったことを証明している 1 。
第二に、彼は興福寺大乗院に仕える「坊人」という「寺社関係者」であった 1 。これは、彼が南都の強大な宗教権門の後ろ盾を得て活動していたことを意味する。彼の貿易活動は、興福寺の経済的利益と密接に結びついていたのである。
第三に、彼は大和の在地武士団「立野衆」の一員であり、武士の一族である戌亥氏から妻を娶っていた 1 。これは、彼が土地に根差した「武士」としての側面も持ち、必要とあれば軍事的な活動にも関与しうる立場にあったことを示唆している。
これら「商人」「寺社関係者」「武士」という三つの属性は、固定化された身分制度の下では通常、混在しがたいものである。しかし、楠葉西忍という一人の人物の中に、これらの要素が矛盾なく共存している。この事実は、15世紀半ばの日本社会が、家柄や身分といった旧来の秩序が揺らぎ、個人の実力や才覚、そして人脈さえあれば、身分の境界を越えて多様な領域で活躍できた、極めて流動的な社会であったことを物語っている。楠葉西忍の存在そのものが、出自や階層よりも経済力や専門知識が重視される、戦国時代の価値観の先駆けであったと言えるだろう。
第二章:『唐船日記』の内容分析:景泰四年(1453年)遣明船の航海実態
『唐船日記』が記録する中心的な内容は、明の景泰4年(日本の享徳2年、西暦1453年)に派遣された遣明船、具体的には「八号船」に関する極めて詳細な経済データである 15 。この記録を丹念に読み解くことで、当時の勘合貿易が、いかに大規模な資本を要するハイリスク・ハイリターンな事業であったか、その実態が明らかになる。
航海の主体
この遣明船の派遣主体は、室町幕府ではなかった。記録には「一今度八号船ハ長谷寺・多武峰ヨリ申テ渡之」とあり、航海の主体が興福寺の有力な末寺である長谷寺と多武峰寺であったことが明記されている 15 。これは、15世紀半ばには、すでに勘合貿易の主導権が幕府の手を離れ、経済力を持つ有力寺社が独自の判断で貿易事業に乗り出していたことを示す動かぬ証拠である。楠葉西忍は、この寺社が派遣した船の貿易監督官、すなわち「外官」として乗り込んでいたのである 1 。
航海経費の徹底解剖
『唐船日記』の白眉は、この航海にかかった経費の内訳が、1貫文単位で克明に記録されている点にある。その総額は1450貫文に上る 15 。この詳細な会計記録は、当時の貿易事業のコスト構造を可視化し、何に重点が置かれていたかを具体的に示している。
|
項目 |
金額(貫文) |
全体に占める割合 |
考察 |
|
船方(船員)給分 (40人) |
400貫 |
27.6% |
航海事業における最大のリスク要因であり、最も価値のある資源が「人材」であったことを示している。40人もの船員を確保し、一人当たり10貫文という報酬を支払う必要があった。 |
|
油ワウ(硫黄)五万斤 |
400貫 |
27.6% |
主要な輸出商品である硫黄の調達コストが、人件費と並んで最大の支出項目となっている。このうち200貫文が硫黄そのものの代金、残りの200貫文が輸送のための船賃とされている。 |
|
船カリチン(借賃) |
300貫 |
20.7% |
船のレンタル費用。自前で大型の外航船を所有するのではなく、安芸国の業者から借り上げていたことがわかる。これも大きな固定費であった。 |
|
船作事(建造・修理) |
300貫 |
20.7% |
借り上げた船を、危険な外洋航海に耐えられるように補強・修理するための費用。材木代もこれに含まれる。船体の安全確保に多額の投資が必要だったことを示す。 |
|
渡粮物米 (100石) |
100貫 |
6.9% |
航海中の食糧費。米100石分が計上されている。 |
|
炭・木・油・水樽等 |
100貫 |
6.9% |
燃料や飲料水、その他の消耗品にかかる費用。 |
|
匠事(職人)給分 (2人) |
60貫 |
4.1% |
船の修理などを担当する専門技術者(大工など)への報酬。 |
|
船頭・カチトリ(梶取) |
50貫 |
3.4% |
航海の責任者である船長と操舵手への報酬。 |
|
合計 |
1450貫 |
100% |
|
この内訳を分析すると、遣明船事業のコストは大きく三つの要素に分けられることがわかる。第一に、船員や船頭、職人といった「人件費」(合計510貫文、全体の35.2%)。第二に、船の借賃や修理費といった「船体関連費」(合計600貫文、全体の41.4%)。そして第三に、主要な積荷である「商品調達費」(硫黄代200貫文、全体の13.8%)。このコスト構造は、遣明船事業が、①熟練した航海技術者、②大量の輸出商品、③堅牢な大型船、という三要素が不可欠な、高度に専門的かつ資本集約的な投機事業であったことを明確に示している。これほどの初期投資を賄える経済主体は、幕府や有力守護大名、そして興福寺のような巨大寺社に限られていたのである。
積荷の実態
経費の内訳からは、この航海の主要な輸出品が「油ワウ(硫黄)五万斤」であったことが具体的にわかる 15 。硫黄は、仏具の装飾などに使われるほか、火薬の重要な原料でもあった。当時の日本は世界有数の硫黄産出国であり、この貿易が単なる経済活動に留まらず、東アジアにおける軍事技術の伝播とも密接に関連していたことが窺える。この一点からも、戦国時代を目前にしたこの時期の貿易が、すでにきな臭い様相を帯びていたことがわかる。
第二部:『唐船日記』を取り巻く時代状況
『唐船日記』という一点の記録を深く理解するためには、そのレンズを通して、記録が生まれた15世紀半ばの日本の政治・経済・国際関係という、より広大な風景を捉える必要がある。この部では、視点を『唐船日記』の外部へと広げ、勘合貿易の構造、寺社の経済力、そして当時の東アジア交易網の中にこの記録を位置づける。
第三章:室町・戦国期の国際秩序と勘合貿易
『唐船日記』が記録する遣明船事業は、「勘合貿易」と呼ばれる特殊な貿易システムの中で行われた。このシステムは、室町幕府と明王朝の間の政治的力学と、東アジアの国際秩序を色濃く反映したものであり、その「建前」と「実務」を理解することが不可欠である。
朝貢形式という「建前」
日明間の公式貿易は、中国が世界の中心であるという「中華思想」を前提とした「朝貢」という形式を取っていた 16 。これは、対等な国家間の自由な通商ではなく、日本の支配者(足利将軍)が明の皇帝から「日本国王」として冊封され、臣下として貢物を献上し、皇帝がその返礼として恩恵的に品物(頒賜品)を与えるという、極めて儀礼的かつ政治的な枠組みであった 18 。
3代将軍足利義満は、この「日本国王」という称号が、実質的に明の臣下となることを意味すると理解しつつも、貿易がもたらす莫大な経済的利益を優先し、この形式を受け入れた 17 。まさに「名分を捨てて実利を取る」という、極めて現実的な外交判断であった。しかし、この点は国内で常に議論の的となり、義満の死後、4代将軍足利義持は一時的に貿易を中断するなど、その受容は決して一枚岩ではなかった 17 。
勘合符という「実務」
朝貢という建前の上で、実際の貿易を機能させていたのが「勘合(勘合符)」と呼ばれる割符式の証明書であった 16 。これは、当時東シナ海で活動していた倭寇(海賊・密貿易商人)による略奪や密貿易と、幕府が派遣する公式な使節船を区別するために明側が発行したものである 19 。
勘合符は、二枚の紙をずらして重ね、両紙にまたがるように印を押し、文字を書き入れたもので、一方を明が「底簿」として保管し、もう一方を日本側が所持した 17 。日本の遣明船は、中国の唯一の指定港であった寧波に入港する際、この勘合符を提示し、明側が保管する底簿と照合することで、初めて正式な使節として認められた 16 。この勘合符なくして、公式な貿易は不可能であり、まさに貿易の安全を担保する生命線であった。
貿易主導権の流動化
足利義満によって始められ、当初は幕府が独占的に利益を享受していた勘合貿易であったが、15世紀半ばから後半にかけて、その構造は大きく変化する。幕府の権威が応仁の乱(1467-1477)を境に決定的に失墜すると、貿易の主導権は、経済力と軍事力を蓄えた有力守護大名や寺社へと移っていった 16 。
特に、貿易の利権を巡って激しく対立したのが、和泉国堺の商人と結んだ管領家の細川氏と、筑前国博多の商人を後ろ盾とする西国の大大名・大内氏であった 18 。両者の対立は、大永3年(1523年)、それぞれが派遣した遣明船が寧波の港で刃傷沙汰に及ぶという「寧波の乱」を引き起こすに至る 20 。この事件の結果、勘合貿易の利権は大内氏が独占することになるが、それも1551年の大内氏の滅亡によって終焉を迎えた 18 。
『唐船日記』が記録した「権力の真空地帯」
このような歴史的文脈の中に『唐船日記』が記録された景泰4年(1453年)を位置づけると、その時代の持つ特別な意味が浮かび上がってくる。この時点は、幕府による貿易の独占が崩れ始め、後の戦国大名による覇権争いが本格化する以前の、いわば「権力の過渡期」あるいは「権力の真空地帯」であった。
その具体的な証拠が、『唐船日記』の遣明船の主体が幕府でも守護大名でもなく、興福寺系の寺院であったという事実である 15 。これは、中央の政治的統制が緩み始めた好機を捉え、独自の経済力を持つ様々な勢力が、富の源泉である貿易利権へ参入しようと蠢いていた状況を如実に示している。
この時代の力学を整理すると、以下のようになる。
- 本来、勘合貿易は足利将軍家、すなわち室町幕府が主導する国家事業であった 16 。
- しかし、幕府の財政難と政治的権威の低下に伴い、自前で遣明船を派遣する能力が衰退していく。
- その隙を突く形で、広大な荘園と金融機能によって富を蓄積した興福寺のような巨大寺社が、自らの財源で貿易事業に乗り出す 15 。
- ほぼ時を同じくして、細川氏や大内氏といった有力守護大名も、それぞれの拠点港(堺・博多)の商人と結びつき、貿易利権の獲得に乗り出す 18 。
- 1453年という時点は、これらの多様なプレイヤーが、まだ決定的な衝突には至らず、それぞれが独自に貿易を試みていた、いわば「群雄割拠の黎明期」であった。
『唐船日記』は、この権力の移行期における、寺社勢力という非武家勢力による経済活動の一断面を切り取った、極めて貴重なスナップショットなのである。それは、来るべき戦国時代が、単なる武士同士の争いではなく、多様な経済主体を巻き込んだ、より複雑な社会変動であったことを示唆している。
第四章:寺社の経済活動と遣明船事業への参画
『唐船日記』の遣明船が興福寺の末寺によって派遣されたという事実は、中世の寺社が単なる宗教団体ではなく、強大な経済力を持つ一大パワーであったことを示している。遣明船事業への参画は、彼らの多様な経済活動の延長線上に位置づけられるものであった。
中世寺社の経済的実力
鎌倉時代から室町時代にかけて、有力な寺社は国家や武家政権と並び立つほどの社会的・経済的影響力を持っていた。その力の源泉は、多角的な経済活動にあった。
第一に、全国に広がる「荘園」からの収入である 23 。寺社は、寄進などによって獲得した広大な私有地を所有し、そこから上がる米や布、銭貨といった年貢が、安定した財政基盤となっていた。興福寺もまた、尼崎周辺に富松荘や武庫荘など多くの荘園を有し、その経営に関する記録が『大乗院寺社雑事記』に豊富に残されている 5 。
第二に、金融業への進出である 23 。当時の金融を担っていたのは「土倉」や「酒屋」といった高利貸業者であったが、寺社は彼らに元手となる資金を貸し付け、利息を得ていた。いわば、当時の「銀行の銀行」のような役割を果たしており、貨幣経済の根幹を握っていたのである 23 。
第三に、商業・流通への関与である。例えば、比叡山延暦寺は、京と北陸を結ぶ交通の要衝である琵琶湖に「湖上関」という関所をいくつも設け、通行する船から通行料を徴収していた 25 。これは、物流の動脈を支配することによる直接的な利益獲得であった。
これらの活動を通じて、寺社は莫大な富を蓄積し、一個の独立した「経済体」として機能していたのである 24 。
興福寺の財政と貿易投資
南都・奈良の大寺である興福寺も、こうした強力な経済基盤を持つ寺社の一つであった 26 。『唐船日記』を記した尋尊自身が、大乗院門跡として、その巨大な財政の運営に日々心を砕いていた。彼が残した『大乗院寺社雑事記』には、荘園からの年貢徴収をめぐる国人との紛争や、寺社の財政状況に関する生々しい記述が数多く見られる 5 。
このような状況下で、興福寺が遣明船貿易に投資したのは、極めて合理的な経営判断であったと言える。荘園収入が武士の侵略などによって不安定化する中で、貿易がもたらす桁違いの利益は、寺社の財政を潤し、その権威を維持するための新たな、そして極めて魅力的な財源と映ったのである。
「寄合」形式の投資
遣明船の派遣には、莫大な初期投資と、遭難や海賊の襲撃といった高いリスクが伴った。そのため、単独の主体がすべてのリスクを負うのではなく、複数の出資者が共同で事業を行う「寄合」という形式がしばしば取られた 14 。
尋尊の記録によれば、当時の遣明船には、大内氏や細川氏といった大大名の船に交じって、様々な公家、商人、そして寺社などが相乗りし、それぞれの投資額に応じて帰国後に利益を分配する仕組みがあったという 14 。これは、航海に伴うリスクを分散すると同時に、より多くの資本を集めて事業規模を拡大するための、当時としては高度な金融スキームであった。
『唐船日記』に記された長谷寺・多武峰寺による遣明船も、おそらくはこの「寄合」の形式を取り、興福寺本体や、楠葉西忍のような貿易に通じた商人、さらには他の出資者たちが共同で資金を出し合って実現したプロジェクトであったと考えられる。これは、寺社が単独で活動していたのではなく、多様な人々とネットワークを形成し、共同で経済活動を展開していたことを示している。
第五章:『唐船日記』から読み解く日明間の交易品と価格差
勘合貿易が、幕府、守護大名、寺社といった多様な権力主体を惹きつけてやまなかった最大の理由は、その圧倒的な利益率にあった。『唐船日記』や、その情報提供者である楠葉西忍が残した証言は、日明間で取引された商品が、いかに大きな価格差を生み出していたかを具体的に物語っている。
日本の輸出品とその価値
日本から明へ輸出された品々は、日本の天然資源や高度な手工業技術を反映したものであった。
- 銅: 日本からの最大の輸出品の一つ。楠葉西忍は「銅を持って行き、明州・雲州糸にかえると4、5倍に売れた」と語っている 28 。日本の銅が高値で取引された背景には、特殊な事情があった。当時の日本の銅鉱石には、少なからず銀が含まれていたが、日本にはまだ銀を効率的に分離・精錬する技術(灰吹法)が普及していなかった 17 。一方、明側はその技術を持っていたため、日本の銅を輸入し、そこから銀を抽出することができたのである。結果として、日本の銅は明側にとって「銀にしては安く、銅にしては高い」という、極めて有利な商品となっていた 17 。
- 硫黄: 『唐船日記』に「油ワウ(硫黄)五万斤」と明記されている重要輸出品である 15 。硫黄は火薬の原料として高い軍事的価値を持ち、日本の重要な輸出品目であった。
- 刀剣・槍: 日本の刀剣や槍は、その切れ味と品質の高さから、明で非常に高く評価された。公定価格では、刀剣一振が鈔10,000文、槍一筋が鈔3,000文と定められていた記録もある 30 。多い年には年間3万から4万本も輸出されたといい、日本の武器が重要な輸出品であったことがわかる 31 。
- その他: 扇や漆器といった日本の精巧な工芸品も、人気の輸出品であった 16 。
明からの輸入品とその魅力
一方、明から日本へもたらされた品々は、当時の日本の経済や文化に計り知れない影響を与えた。
- 生糸: 楠葉西忍の証言によれば、生糸は最も利益の大きい輸入品であった。「一斤250文で入手した唐糸を持ち帰ると、日本で二十倍の五貫文で売れる」とあり、まさに一攫千金の花形商品だった 28 。この莫大な利益が、商人たちを危険な航海へと駆り立てた最大の動機であった。
- 銅銭: 永楽通宝に代表される明の銅銭は、当時の日本国内で事実上の基軸通貨として広く流通していた 31 。日本は自国で十分な量の貨幣を鋳造していなかったため、勘合貿易による銅銭の輸入は、日本の貨幣経済そのものを支えるという重要な役割を担っていた。
- 唐物: 絹織物、陶磁器、書画、工芸品といった中国の文物は、総称して「唐物(からもの)」と呼ばれ、珍重された 16 。これらは単なる輸入品ではなく、後に詳述するように、所有者の社会的ステータスを示す文化的・政治的な価値を帯びていくことになる。
日明間 主要交易品の価格差と利益率の推定
楠葉西忍の証言などの断片的な情報を統合すると、勘合貿易がもたらした利益の大きさがより具体的に見えてくる。
|
品目 |
明での仕入価格(推定) |
日本での売却価格(推定) |
利益率(推定) |
典拠・考察 |
|
生糸 |
1 |
20 |
1900% |
楠葉西忍の証言 28 。当時の貿易における最大の利益が見込める花形商品。この驚異的な利益率が、多くの勢力を貿易に駆り立てた。 |
|
銅 |
1 |
4~5 |
300-400% |
楠葉西忍の証言 28 。日本の輸出品の主力。銀を含有するという特殊な価値が付加されていた。 |
|
刀剣 |
- |
- |
- |
1振が鈔10,000文という公定価格が存在 30 。日本の高い鍛冶技術が評価され、安定した輸出品となっていた。 |
|
蘇木 |
- |
- |
- |
赤色の染料や薬剤として重要な商品。銅とほぼ同価格帯で取引された記録もあり、需要が高かったことが窺える 30 。 |
この表が示すように、勘合貿易は単に「儲かる」というレベルではなく、現代の感覚からしても「桁違いの利益」を生み出す可能性を秘めた、巨大な投機事業であった。この莫大な利益こそが、戦国大名たちが貿易の主導権を巡って文字通り命を懸けて争った根本的な理由であり、彼らが戦乱の時代を勝ち抜くための軍資金の重要な源泉となったのである。
第三部:勘合貿易が社会・文化に与えたインパクト
勘合貿易がもたらしたものは、経済的な利益だけではなかった。その富は、日本の社会構造、文化、そして政治のあり方を根底から変容させる力を持っていた。この部では、貿易によってもたらされた富と文物が、いかにして日本の権力構造を規定する新たな価値観を生み出していったのかを論じる。特に、戦国時代の政治・文化を象徴する「茶の湯」との関係に焦点を当てる。
第六章:勘合貿易がもたらした文化的影響:「唐物」と茶の湯の隆盛
『唐船日記』に記録された経済活動は、最終的に日本の文化、特に「茶の湯」の発展と密接に結びつき、新たな権威の形を創出した。貿易で得られた経済資本が、文化資本、そして政治資本へと転換していくプロセスは、戦国時代の権力闘争を理解する上で極めて重要である。
ステータスシンボルとしての「唐物」
勘合貿易によって輸入された中国の美術工芸品、すなわち「唐物」は、その希少性と洗練された美しさから、室町時代後期から戦国時代にかけて、大名や有力商人の間で絶大な価値を持つようになった 34 。特に、茶の湯で用いられる青磁の茶碗や天目茶碗、精巧な茶入などは、単なる道具ではなく、所有者の富と教養、そして権威を示す最高のステータスシンボルと見なされた。
茶の湯と政治
戦国時代に入ると、茶の湯は単なる芸道や趣味の域を超え、高度に政治的な意味合いを帯びるようになる。茶室は、武将たちが密談を交わし、同盟を結び、情報を交換し、そして互いの格付けを行う、極めて重要な政治空間へと変貌した 35 。豪華な唐物道具を使い、趣向を凝らした茶会を催すことは、自らの勢威を内外に誇示するための効果的な手段であった。戦場の殺伐とした雰囲気から離れ、一椀の茶を通じて精神を落ち着けるという個人的な癒しの側面と、他者との関係性を構築する社交・政治の側面が、茶の湯には共存していたのである 36 。
名物道具の価値
茶会における唐物の価値は、時に異常なレベルにまで高騰した。優れた茶道具は「名物(めいぶつ)」と呼ばれ、その中でも特に有名なものは、城一つ、あるいは一国に匹敵するほどの価値があるとされた 34 。
この価値を巧みに利用し、政治的に活用したのが織田信長である。信長は、武力で征服した地域から名物を強制的に集める「名物狩り」を行う一方で、大きな功績を挙げた家臣に対して、領地や金銭の代わりに名物道具を与えるという手法を用いた 35 。例えば、難攻不落であった但馬攻めを成功させた羽柴秀吉には『乙御前釜』を、安土城の築城を指揮した丹羽長秀には『珠光茶碗』を与えている 35 。これにより、信長から名物を下賜されることは、武士にとって最高の栄誉となり、名物の価値は信長の権威と直結するものとなった。茶道具が、忠誠心を測り、家臣団を統制するための強力なツールとなったのである。
経済資本から文化資本、そして政治資本への転換
この一連の現象は、勘合貿易が生み出した富が、日本の権力構造の中でいかにしてその性質を変化させていったかを示す好例である。このプロセスは、三つの段階に分けて理解することができる。
-
第一段階:経済資本の獲得
『唐船日記』が詳細に記録しているように、勘合貿易は、銅や硫黄といった日本の産品を輸出し、生糸や銅銭、陶磁器を輸入することによって、莫大な富、すなわち「経済資本」を生み出した。この段階では、富はまだ純粋に経済的な価値を持つに過ぎない。 -
第二段階:文化資本への転換
輸入された陶磁器などの「唐物」は、村田珠光、武野紹鴎、そして千利休といった茶人たちによって見出され、茶の湯という洗練された文化的文脈の中に位置づけられる 34。彼らは、単に中国のものを珍重するだけでなく、そこに「わび」「さび」といった日本独自の美意識を加え、道具の取り合わせや作法を体系化していった 37。このプロセスを通じて、単なる輸入品であった唐物は、その背景にある物語や由緒、美意識といった付加価値をまとい、「名物」という特別な「文化資本」へと昇華された。 -
第三段階:政治資本への転換
織田信長や豊臣秀吉といった天下人は、この形成された「文化資本」を独占・管理し、それを戦略的に利用した。名物を所有すること自体が権威の証となり、それを家臣に与える行為が主従関係を確認・強化する儀式となった。茶会は、同盟国や敵対勢力に対する政治的デモンストレーションの場ともなった。こうして、文化資本は、権力闘争を有利に進めるための具体的な力、すなわち「政治資本」へと転換されたのである。
この視点から見れば、『唐船日記』は、単なる貿易の記録ではない。それは、戦国時代の権力闘争の根源にあった、この「資本の転換プロセス」のまさに第一段階、すなわち経済資本の蓄積過程を記録した、極めて重要なドキュメントであると結論づけることができる。硫黄を積んだ一艘の船が、巡り巡って天下人の政治を動かす礎となっていたのである。
第七章:貿易商人の実像:楠葉西忍と博多・堺の商人たち
勘合貿易という巨大な経済活動を現場で支えていたのは、多様な背景を持つ商人たちであった。『唐船日記』の情報提供者である楠葉西忍は、その中でも特異な存在であったが、彼を当時の代表的な商人たちと比較することで、その独自性と時代の多様性がより鮮明になる。
多様な商人たち
勘合貿易の担い手は、決して一枚岩ではなかった。その出自や活動拠点は様々であり、それぞれが有力な権門と結びつくことで、貿易への参入を果たしていた。
- 博多商人: 筑前国博多は、古くから対外交易の拠点であり、多くの経験豊かな商人が集積していた。彼らは主に西国の守護大名・大内氏と強く結びつき、その庇護の下で活動した 18 。博多商人の代表的な人物としては、日朝・日明貿易で活躍した宗金一族などが知られている 39 。彼らは大内氏の政治力・軍事力を背景に、勘合貿易の利権を巡って堺商人と激しく争った。
- 堺商人: 和泉国堺は、畿内における経済・流通の中心地として発展した自治都市であった。堺の商人たちは、主に室町幕府の管領家であった細川氏と結託し、その政治的影響力を利用して貿易に参入した 18 。千利休に代表されるように、堺の商人(会合衆)は茶の湯文化の担い手でもあり、経済力と文化力を兼ね備えた有力な勢力であった 36 。
- その他の商人: 上記の二大勢力以外にも、3代将軍足利義満に貿易の利益を進言した博多商人・肥富(こいずみ)のように、幕府と直接結びついた商人もいた 17 。また、寺社勢力も独自のネットワークを通じて商人を組織し、貿易に参加していた。
楠葉西忍の独自性
このような多様な商人たちの中で、楠葉西忍の立ち位置は際立ってユニークである。博多や堺の商人が、それぞれ大内氏や細川氏といった特定の守護大名と強く結びつき、彼らの政治的・軍事的な代理戦争の一翼を担っていたのに対し、西忍の基盤はあくまで南都・興福寺という宗教権門にあった 1 。
彼の活動は、大名間の熾烈な政争の渦中から、ある意味で一歩引いた場所で行われていた。彼の目的は、特定の大名家の勢力拡大に貢献することではなく、あくまで所属する興福寺大乗院の財政に貢献することであったと考えられる。この立場が、彼に特定の政治色に染まらない、比較的自由な活動を許した可能性がある。
また、天竺人の父を持つという彼の出自は、他の日本人商人にはない、言語能力や国際感覚、あるいは海外の商人ネットワークとの繋がりをもたらしていたかもしれない。彼が単なる一介の坊官ではなく、遣明船の「外官」という貿易監督官の重責を任された背景には、こうした彼の持つ特殊な能力や背景が高く評価された結果であると推測される。楠葉西忍は、大名と結びついた政商とは異なる、寺社という宗教権門を基盤とした、もう一つの「国際派プロフェッショナル」の姿を我々に示してくれるのである。
第八章:東アジア交易網における『唐船日記』の位置づけ:琉球王国との比較
日本の勘合貿易は、15世紀の東アジアに張り巡らされた、より広大で多元的な交易ネットワークの一部であった。その全体像を理解するためには、当時、日本以上に活発な海洋交易を展開していた琉球王国との比較が不可欠である。『唐船日記』をこの広い文脈の中に位置づけることで、その歴史的意義はさらに深まる。
中継貿易国家・琉球
14世紀末から16世紀にかけての東アジア海上世界において、最も輝かしい成功を収めたのは琉球王国であった。沖縄本島の三山(北山、中山、南山)を統一した中山王・尚巴志は、明王朝から正式に冊封され、極めて優遇された朝貢関係を築いた 40 。明は、倭寇対策として民間人の海外渡航を厳しく制限する「海禁政策」をとっていたが、琉球に対しては例外的に頻繁な来航を許可した 41 。
この特権的な地位を利用し、琉球は中国、日本、朝鮮、そしてシャム(タイ)やマラッカ、パレンバンといった東南アジア諸国を結ぶ「中継貿易」の拠点として空前の繁栄を遂げた 42 。琉球の船は、まず福州で大量の中国産品(陶磁器、絹織物など)を仕入れ、それを那覇に持ち帰る。そして、那覇を拠点として、それらの中国産品を日本や朝鮮、東南アジアへ運び、現地の特産品(日本の硫黄や銅、東南アジアの胡椒や蘇木など)を仕入れて再び那覇に集積し、それらを明への次の朝貢の際の貢物としたり、各国の商人へ販売したりしたのである 42 。那覇の港は、まさに「万国津梁(世界の架け橋)」として、東西の富が集まる国際的なハブ港であった 40 。
朝貢回数の圧倒的な差
琉球が明からいかに特別な扱いを受けていたかは、朝貢の回数に端的に表れている。『明実録』などの中国側史料によれば、明代を通じて琉球が朝貢した回数は171回に達する 40 。これに対し、2位の安南(ベトナム)は89回、朝鮮は30回、そして日本はわずか19回に過ぎなかった 40 。
この圧倒的な回数の差は、明王朝の対外政策において、琉球が日本よりも遥かに重要なパートナーと見なされていたことを示唆している。明にとって琉球は、海禁政策の枠組みを維持しつつ、東南アジアの物産を安定的に入手するための、信頼できる公式な交易ルートであった。一方、日本との勘合貿易は、倭寇の禁圧という政治的・軍事的な要請が主であり、その回数も10年に一度、船は3隻までと厳しく制限されていた 18 。
多元的な東アジア交易ネットワーク
これらの事実を統合すると、15世紀の東アジアには、少なくとも三つの異なる交易圏が重層的に存在していたことがわかる。
- 日明間の勘合貿易ルート: 日本と明を直接結ぶ、政治的・儀礼的性格の強い公式ルート。貿易は厳しく管理・制限されていた 17 。『唐船日記』が描くのは、このルートの実態である。
- 琉球の中継貿易ネットワーク: 琉球王国をハブとし、明の特恵的な地位を最大限に活用して、東アジアと東南アジア全域を結んだ多国間交易ルート 43 。日本の商人や物産も、この琉球のネットワークに組み込まれていた。
- 東南アジアのイスラム商人ネットワーク: ジャワやマラッカを拠点とするイスラム商人が、香辛料諸島(モルッカ諸島)などから産出される香辛料貿易を担っていた 46 。彼らはマラッカなどで琉球の商人と接触し、交易を行っていた記録も残っている 48 。
このように、日本の勘合貿易は、活気に満ちた15世紀アジアの海洋世界における、一つのルートに過ぎなかった。しかし、その一方で、『唐船日記』のような、航海の経費から積荷、商人の活動までを当事者の視点から克明に記録した内部資料は、他の交易圏にはほとんど現存していない。琉球の公式な外交文書である『歴代宝案』などと比較検討することで、『唐船日記』は、この複雑で多元的な東アジア交易の全体像を、より立体的かつ具体的に復元するための、かけがえのない「日本の視点」からの証言として、その価値を一層高めるのである。
結論:『唐船日記』が照らし出す戦国前夜の日本の姿
本報告書は、『唐船日記』という15世紀半ばの一点の記録を多角的に分析することを通じて、それが単なる貿易の聞書ではなく、来るべき戦国時代を準備した社会の構造変動を映し出す、極めて重要な歴史的ドキュメントであることを論証してきた。最後に、本分析から得られた結論を総括する。
1453年という時点の歴史的意義
『唐船日記』が記録した景泰4年、すなわち1453年は、日本史上、極めて重要な転換点に位置する。全国規模の内乱である応仁の乱(1467-77)が勃発するわずか14年前であり、室町幕府の政治的権威が決定的に失墜する直前の、いわば「嵐の前の静けさ」の時代であった。しかしその水面下では、社会の地殻変動が静かに、しかし確実に進行していた。『唐船日記』は、その変動の核心を捉えている。
権威の流動化と経済的実力者の台頭
分析が明らかにしたように、『唐船日記』は、旧来の権威が揺らぐ中で、新たな実力者が台頭してくる時代の空気を鮮やかに切り取っている。
- 政治権威の空洞化: 勘合貿易の主体が、本来の担い手であるべき幕府ではなく、興福寺という寺社勢力であった事実は、幕府の統制力がすでに形骸化し、権力に「真空地帯」が生じていたことを示している。
- 経済的実力者の躍進: 興福寺のような寺社勢力、そして楠葉西忍のような専門知識を持つ商人が、その真空地帯にいち早く進出し、貿易という新たな富の源泉を掌握しようとしていた。彼らの活動は、家柄や身分といった旧来の秩序に代わり、経済力と実力が社会を動かす新たな原理となりつつあったことを物語っている。
- ハイブリッドな人物の登場: 楠葉西忍が体現した、商人・寺社関係者・武士という複数の属性を併せ持つ「ハイブリッドな存在」は、社会の流動化が進み、身分の境界が曖昧になっていたこの時代の特徴を象徴している。
戦国時代への序章として
『唐船日記』が照らし出すこれらの事象は、すべてが戦国時代の本質へと繋がっている。
第一に、勘合貿易がもたらした莫大な富は、戦国大名たちが領国を経営し、軍備を拡張するための経済的基盤となった。桁違いの利益を生む貿易利権を巡る争いは、大内氏と細川氏の対立に見られるように、それ自体が戦乱の直接的な原因ともなった。
第二に、貿易によってもたらされた「唐物」は、茶の湯という文化的装置を通じて、経済資本から文化資本、そして政治資本へと転換された。名物道具の所有と贈与は、大名たちの権威を可視化し、主従関係を規定する重要な政治的ツールとなった。戦国時代の権力闘争が、単なる軍事力の衝突だけでなく、高度な文化戦略を伴っていたことの起源がここにある。
第三に、楠葉西忍のような実力主義的な人物の活躍は、戦国時代の最大の特徴である「下剋上」の風潮の先駆けであった。出自を問わず、才覚と行動力さえあれば富と名声を得られるという社会の到来を、『唐船日記』は予感させている。
結論として、『唐船日記』は、戦国時代という激動の時代が、決して突発的に始まったのではなく、15世紀半ばの経済活動、国際関係、そして文化の変容の中に、その全ての萌芽を宿していたことを教えてくれる。一艘の唐船の航海記録は、日本の歴史が大きく舵を切る、その潮目の瞬間を捉えた、かけがえのない羅針盤なのである。
引用文献
- 楠葉西忍(くすばさいにん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A5%A0%E8%91%89%E8%A5%BF%E5%BF%8D-1071651
- 楠葉西忍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E8%91%89%E8%A5%BF%E5%BF%8D
- 尋尊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8B%E5%B0%8A
- 27.大乗院寺社雑事記 - 歴史と物語:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/27.html
- 大乗院寺社雑事記 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E9%9B%91%E4%BA%8B%E8%A8%98
- 「史 乗」に関連した英語例文の一覧と使い方 - Weblio英語例文検索 https://ejje.weblio.jp/sentence/content/%E5%8F%B2+%E4%B9%97
- 尋尊とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8B%E5%B0%8A
- 尋尊 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b588526.html
- 尋尊 / 安田 次郎【著】/日本歴史学会【編】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784642053044
- 尋尊 【人物叢書(新装版)311】 - 法藏館 おすすめ仏教書専門出版と書店(東本願寺前) https://pub.hozokan.co.jp/smp/book/b596562.html
- 楠葉西忍(くすばさいにん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ku/entry/031608/
- 室町時代、混血の若者天竺天次の活躍!|hiranosyu - note https://note.com/hiranosyu/n/nfecd4d9cd38d
- 室町時代の商人で - 楠葉西忍[くすばさいにん]は https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/367/77381.pdf
- 大航海時代前夜 飛鳥・奈良の昔から,日本 http://kinnekodo.web.fc2.com/link-17.pdf
- 唐船日記 | khirin C https://khirin-c.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E14613
- 勘合 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kango/
- 日明貿易 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%98%8E%E8%B2%BF%E6%98%93
- 勘合貿易 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kango-boeki/
- 「日明貿易、日朝貿易、勘合貿易」とは? それぞれの特徴、違いがスッキリ分かる! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/325
- 寧波の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A7%E6%B3%A2%E3%81%AE%E4%B9%B1
- 戦国時代と海外貿易 http://www.cwo.zaq.ne.jp/bface700/hs1/Zipangu/Zagd_04.html
- サタデー日本史~高校日本史をゆるーく解説【 28.室町時代の対外関係と幕府政治の推移 】① https://ameblo.jp/tanytakachan/entry-11395551594.html
- 中世日本の「中央銀行」?寺社勢力が果たした経済的役割とは|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n8f7365cef0d4
- 寺社勢力の経済パワーの歴史と現代 ~かつての繁栄から現在の課題まで~|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n05de96f38b9f
- 中世寺社勢力の実力 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/296/296toku_kiko.pdf
- 史料保存館デジタルギャラリー - 文化財 - 奈良市ホームページ https://www.city.nara.lg.jp/site/bunkazai/99017.html
- 東大寺図書館所蔵記録部など解題(抄、中世関連史料編) https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/personal/endo/2012-15kaken/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%89%80%E8%94%B5%E8%A8%98%E9%8C%B2%E9%83%A8%E7%AD%89%E8%A7%A3%E9%A1%8C%EF%BC%88%E6%8A%84%E3%80%81%E4%B8%AD%E4%B8%96%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%8F%B2%E6%96%99%EF%BC%89ver2.pdf
- 勘合貿易(カンゴウボウエキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8B%98%E5%90%88%E8%B2%BF%E6%98%93-48728
- 中世の金融 https://www.imes.boj.or.jp/cm/exhibition/2009/mod/2009c_l8_10.pdf
- わが室町期における私鋳銭 https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/9535/files/0586_9749_168_03.pdf
- 遣明船 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A3%E6%98%8E%E8%88%B9
- 日本刀の地鉄(科学的考察) http://ohmura-study.net/007.html
- 室町後期の博多商人道安と東アジア - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1148/KJ00000699918-00001.pdf
- 茶道の歴史~戦国武将達のド派手なギャンブルから、千利休の侘び寂び文化へ https://kingyotei.sakura.ne.jp/japan/?p=3968
- 戦国時代のたしなみ「茶の湯文化」と、信長様の外交戦略の要「名茶器」について! https://san-tatsu.jp/articles/242429/
- なぜ、武士に茶の湯が? http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_26.pdf
- 油滴天目 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/uploads/r_press/169.pdf
- 戦国武将と茶の湯/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90457/
- 室町期の博多商人宗金と東アジア - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1866707/p101.pdf
- 琉球王国 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD/
- 東アジアの海洋世界 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/world_history/%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E4%B8%96%E7%95%8C/
- 高良 倉吉氏 - 日本海事センター https://www.jpmac.or.jp/file/105_3.pdf
- 時代の大きなうねり https://www.town.kadena.okinawa.jp/kadena/soukan/book/17.html
- 【中継貿易とは】琉球王国での歴史やシンガポールが栄えた背景を簡単にわかりやすく解説 https://www.digima-japan.com/knowhow/world/20648.php
- 東アジア交易圏の中の琉球 | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所 - 笹川平和財団 https://www.spf.org/opri/newsletter/470_2.html
- トメ・ピレス『東方諸国記』を読む http://koekisi.web.fc2.com/column2/page012.html
- 15世紀のモルッカ・バンダにおける イスラム化と丁香・肉董藏貿易 - 国際大学リポジトリ https://iuj.repo.nii.ac.jp/record/764/files/1_41-67.pdf
- 史料でよむ世界史 7.4.3 東南アジア交易の発展 - note https://note.com/sekaishi/n/nc6e4bdd3a45c