岸和田流砲書
岸和田流砲術は薩摩商人が創始。砲術と戦傷医術を融合した実践的技術で、上杉謙信も採用。早期に普及したが、後発流派に取って代わられ歴史に埋没した先駆的流派。
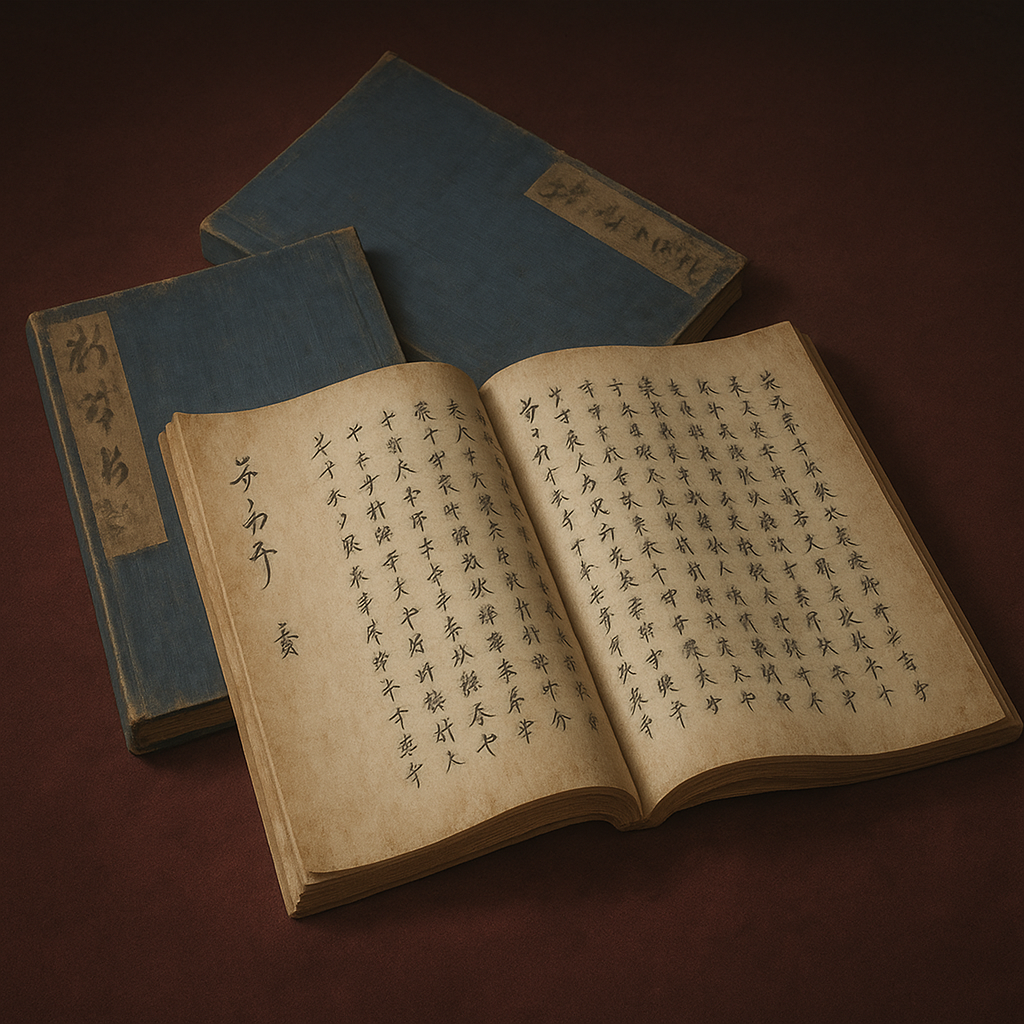
岸和田流砲術と「鉄炮之大事」の謎 —戦国初期、商人が興した砲術流派の実像—
序章:幻の「岸和田流砲書」を追って
日本の戦国時代、合戦の様相を一変させた新兵器、鉄砲。その運用技術である砲術は、瞬く間に全国へ広がり、数多の流派を生み出した。その中にあって、「岸和田流」は、特に謎に包まれた存在として知られる。一般には、この流派は「岸和田左京進盛高」なる人物が創始し、その秘伝を記した『岸和田流砲書』なる書物が存在したと伝えられてきた。
しかし、この広く知られた伝承は、近年の研究によって大きな疑問符が付けられている。現存する信頼性の高い史料を精査する限り、戦国期に「岸和田左京進盛高」という名の武士が活動した記録は見出せない 1 。さらに致命的なことに、岸和田流の具体的な技術を記したとされる『岸和田流砲書』そのものも、今日に至るまで発見されていないのである 1 。
すなわち、我々の調査は「不在の創始者」と「幻の伝書」という二重の謎から出発せざるを得ない。この状況は、岸和田流という存在そのものを歴史の霧の中へと追いやるかに見える。だが、それは同時に、新たな問いを我々に投げかける。なぜ、実在の不確かな武士の名が創始者として語り継がれてきたのか。それは、江戸時代に入り泰平の世が訪れる中で、多くの武芸の流派がその出自を権威付けるため、由緒を飾り、創始者を著名な武士に仮託する風潮があったことの現れかもしれない。武術の歴史とは、単なる技術の変遷史ではなく、その時々の社会情勢を反映した「言説の歴史」でもあるのだ。
本報告書は、この伝承の霧を払い、断片的に残された史料の点と点を繋ぎ合わせることで、これまで知られてこなかった岸和田流の真の姿を再構築する試みである。その鍵を握るのは、薩摩の「商人」という意外な創始者像であり、そして遠く信濃国の古社に秘蔵されてきた一対の古文書である。この謎を解き明かす旅は、我々を戦国初期の技術革新の最前線へと誘うであろう。
第一章:創始者の実像 — 薩摩の商人「岸和田」
伝承上の「岸和田左京進盛高」という武士像とは対照的に、現存する史料が指し示す岸和田流の創始者は、全く異なる出自を持つ人物であった。その最も確かな手がかりは、長野県長野市に鎮座する守田神社に伝来した文禄年間(一五九二~一五九六年)の文書『鉄炮之大事』の中に見出される。この古文書によれば、岸和田流を興したのは「薩摩国人で商人であった岸和田なる人物」と明記されている 1 。
この「商人創始者説」は、戦国時代の技術伝播の文脈において、極めて高い蓋然性を持つ。天文十二年(一五四三年)、ポルトガル商人を乗せた船が種子島に漂着し、日本に鉄砲がもたらされたことは広く知られている 4 。この種子島を領していたのは薩摩の島津氏であり、以降、薩摩(鹿児島)はキリスト教の伝来も含め、南蛮からもたらされる新技術・新文化の玄関口としての役割を担った 6 。
この歴史的背景において、鉄砲という新兵器の輸入、販売、そしてその操作法や製造法といった技術情報の伝播において、決定的な役割を果たしたのは、既存の武士階級ではなく、国際交易の現場にいた商人たちであった。彼らはポルトガル商人や中国人通訳と直接交渉し、誰よりも早く、そして深く鉄砲に関する知識を吸収し得たのである 8 。堺の商人、橘屋又三郎が鉄砲伝来直後に種子島に赴き、その製法を学んで堺での量産化の礎を築いた逸話は、商人が単なる仲介者ではなく、技術の理解者であり実践者であったことを象徴している 9 。したがって、日本における最初期の砲術流派が、薩摩という鉄砲伝来の地を拠点とする商人によって創始されたことは、偶然ではなく、当時の社会経済的、技術的状況における一つの必然であったと結論付けられる。
しかし、ここにもう一つの謎が浮上する。「岸和田」という姓である。薩摩藩の主要な家臣団の名簿や地名に、「岸和田」という名は見当たらない 12 。一方で、「岸和田」は和泉国の地名であり、一大鉄砲生産地として名を馳せた堺に隣接する、商業的にも重要な拠点であった 10 。戦国時代、雑賀衆や根来衆、国友鍛冶のように、地名がその集団の持つ技術力や専門性を保証する一種の「ブランド」として機能していた例は数多い 15 。
この事実から、一つの大胆な仮説が導き出される。薩摩出身のこの商人は、自らが編み出した砲術を一つの「商品」として各地の大名に売り込むにあたり、出身地である「薩摩」ではなく、先進的な鉄砲生産地を想起させ、高い技術力を保証するイメージを持つ「岸和田」を、屋号や流派名として戦略的に名乗ったのではないだろうか。これは、自身の技術に先進性と信頼性という付加価値を与えるための、極めて巧みなブランディング戦略であったと解釈できる。創始者の出自と名称の謎は、戦国時代を生きた商人の、したたかで合理的な思考様式を我々に垣間見させるのである。
第二章:現存する唯一の手がかり — 長野・守田神社蔵『鉄炮之大事』
岸和田流の実態に迫る上で、現存する唯一かつ最重要の史料が、長野県長野市七二会(なにあい)に鎮座する守田神社所蔵の『鉄炮之大事』である。岸和田流の具体的な砲術を記した秘伝書そのものは未発見であるが、この『鉄炮之大事』は、岸和田流と密接な関係を持ち、その流派の成立に関わる情報を含む、現存する最古の技術文書群として極めて高い価値を持つ 1 。
この貴重な史料を現代に伝えた守田神社は、信濃国水内郡の式内社に比定される古い由緒を持つ古社である 16 。平安時代の貞観元年(八五九年)には神階を授けられた記録が残り、中世以降も地域の武将から篤い崇敬を集めていた 17 。『鉄炮之大事』が文禄年間(一五九二~一五九六年)の成立とみられることから 2 、戦国末期においても、重要な文書を奉納し、その永続を祈願するに足る神威を持つ神社と認識されていたことがうかがえる。
しかし、なぜ薩摩の商人が興した流派の伝書が、遠く離れた信濃国の山中にある神社に現存するのか。この一見不自然な伝来経路の謎を解く鍵は、戦国大名・上杉氏の動向にある。
まず、史料が所蔵される信濃国水内郡は、善光寺平、通称「川中島」を含む地域であり、戦国時代を通じて武田信玄と上杉謙信が覇を競った最前線であった 18 。この地は、上杉氏にとって越後を防衛し、信濃へ進出するための極めて重要な戦略拠点であり、飯山城や長沼城などを拠点として勢力を保持していた 18 。
次に、上杉家は武田氏との抗争の過程で、信玄に領地を追われた信濃の国衆や武将を多数庇護し、家臣団に組み込んでいた。中でも、信濃高井郡の豪族であった須田満親は、武田に敗れた後に謙信を頼り、以後上杉家臣として川中島の戦いなどで活躍した代表的な人物である 21 。上杉家臣団には、こうした信濃出身者が数多く含まれていた 22 。
そして決定的な事実は、第四章で詳述する通り、この上杉家が初期に導入した砲術こそが、岸和田流であったという記録である 24 。
これらの事実を繋ぎ合わせることで、史料の伝播経路が合理的に浮かび上がってくる。すなわち、「薩摩の商人・岸和田」によって創始された岸和田流砲術は、まずその実用性を高く評価した上杉謙信に採用された。そして、その技術を修得した上杉家臣(その中には、土地勘のある信濃出身の武将、例えば須田氏の一族などが含まれていた可能性も考えられる)が、川中島地域の防衛拠点に駐留する中で、自らが学んだ流派の秘伝や心得を記した文書を、所領内における由緒ある守田神社に戦勝祈願や技術の永久保存を願って奉納した。これが、幾多の戦乱を乗り越え、奇跡的に現代まで伝来した、というのが最も蓋然性の高いシナリオであろう。
このように、薩摩から信濃へという、地理的に飛躍した史料の伝来の謎は、戦国時代の政治・軍事史のダイナミズムの中に位置づけることで、一つの明快な答えを見出すことができるのである。
第三章:砲術と医術の融合 — 『南蛮流秘伝一流』という異色の伝書
『鉄炮之大事』の発見がもたらした衝撃は、岸和田流の起源を明らかにしたことだけに留まらない。さらに驚くべきは、この文書が単独ではなく、『南蛮流秘伝一流』と題されたもう一つの書物と一対(セット)で伝来したという事実である 1 。そして、この『南蛮流秘伝一流』の内容こそ、岸和田流の本質を理解する上で決定的な鍵を握っていた。
分析の結果、この『南蛮流秘伝一流』は砲術書ではなく、戦場で負った傷、特に銃創などの治療法を記した「金瘡医術」の伝書であることが判明した 1 。その内容は、傷の縫合術や外科的な手術法にまで及んでおり、当時の日本で主流であった漢方医学とは異なる、ポルトガル医学など南蛮由来の知識体系に基づいていた可能性が示唆されている 1 。
この事実は、極めて重要な意味を持つ。天文十二年(一五四三年)の鉄砲伝来は、合戦における殺傷能力を飛躍的に向上させたが、それは同時に、防御側にとっても新たな脅威の出現を意味した。従来の刀槍による切り傷や刺し傷とは異なり、高速で飛来する鉛玉がもたらす銃創は、骨を砕き、内臓を深く損傷させる、より深刻で治療の困難な傷であった 26 。戦場における兵士の死傷率は増大し、負傷兵の治療と戦線復帰は、大名にとって喫緊の課題となったのである。
多くの武術流派の伝書が、技の形(かた)の解説や、心の持ちようといった精神論に多くの紙幅を割いているのとは対照的に 27 、岸和田流の伝承体系は、敵を殺傷する「砲術」と、味方を救う「医術」という、戦場で即座に役立つ二つの実践的技術を不可分のものとして捉えていた。この特異性は、岸和田流が単なる射撃術の流派ではなかったことを雄弁に物語っている。
ここに、岸和田流の真の姿が浮かび上がる。武術の究極の目的が「敵を倒し、自らが生き残ること」であるならば、岸和田流はまさにその目的を最も直接的に追求した流派であったと言える。彼らが提供したのは、単なる射撃の技法ではない。それは、最新兵器である鉄砲を効果的に用いて敵を制圧する「攻撃」のノウハウと、銃創という新たな脅威から兵士の命を救い、部隊の戦闘能力を維持するための「回復・防御」のノウハウを統合した、包括的な「戦闘技術パッケージ」だったのである。
この視点は、創始者が商人であったという事実と見事に符合する。顧客である大名や武将たちが戦場で直面している最大の問題、すなわち「いかにして勝ち、いかにして生き残るか」という根源的なニーズを的確に捉え、それに対する総合的な解決策を「商品」として提供する。これは、後の時代に精神性や様式美が重視される「武道」へと昇華していく武術とは一線を画す、戦国時代ならではの即物的で合理的な発想である。岸和田流の本質とは、射撃の「術」に留まらず、戦場での「生存術」そのものであった。この発見は、岸和田流の歴史的価値を根本から再定義するものである。
第四章:「軍神」上杉謙信が選んだ砲術 — 越後上杉家との深い関係
「軍神」あるいは「越後の龍」と称され、生涯のほとんどを戦場で過ごし、その戦術眼は戦国時代でも屈指と評される上杉謙信。彼が率いた上杉軍が、その初期段階において、一介の商人が興したに過ぎない岸和田流砲術を導入していたという事実は、この流派の価値を客観的に評価する上で極めて重要な指標となる。
米沢市に残る史料や、上杉家伝来の武具などを収蔵する宮坂考古館の記録には、上杉家が最初に導入した砲術流派が岸和田流であったことが明確に記されている 24 。謙信の後継者である上杉景勝が上洛する際には、岸和田流で訓練された鉄砲組を編成しており、上杉家にとって鉄砲が「戦用第一の利器」と認識されていたことがわかる 24 。
もちろん、上杉家は岸和田流のみに固執したわけではない。時代が下るにつれて、種子島流の丸田九左ェ衛門盛次や、当時最新の砲術として名高かった稲富流の大熊伝兵衛といった専門家を招聘し、鉄砲頭として召し抱えている 24 。江戸時代に入り米沢藩となってからも、関流や森重流など複数の流派が伝わり、藩士たちは互いに技を競い合った 24 。しかし、重要なのは、これら数多の流派に先駆けて、上杉家がその砲術の基礎を岸和田流に置いたという歴史的事実である。
では、なぜ上杉謙信は、当時勃興しつつあったであろう他の数ある選択肢の中から、出自も不確かな商人の流派を選んだのか。その理由は、謙信の合理的な戦略眼と、岸和田流が持つ時代的な先進性に求めることができる。
第一に、謙信は宿敵・武田信玄との熾烈な抗争の渦中にあり、常に最新かつ最強の軍事技術を渇望していた。岸和田流は、後に主流となる稲富流や田付流といった流派が体系化され、広く普及する以前に登場した、極めて初期の砲術流派の一つであった 1 。先進技術の導入競争が熾烈であった戦国時代において、謙信は流派の家柄や創始者の身分といった権威よりも、戦場で即座に効果を発揮する実用性と即効性を重視したと考えられる。当時、最も早く、実践的な鉄砲運用ノウハウを提供できたのが、商人「岸和田」であった可能性が高い。
第二に、前章で論じた「金瘡医術との融合」という岸和田流の持つ比類なき付加価値である。絶え間なく続く合戦において、熟練兵の損耗は軍事力の低下に直結する。兵士の生命を救い、戦線復帰を早めるための具体的な医療技術が、砲術とセットで提供されるという提案は、部隊の維持に心を砕く軍事指導者にとって、計り知れないほど魅力的に映ったはずである。
結論として、上杉謙信が岸和田流を導入したのは、出自や権威に捉われない徹底した実利主義と、敵に先んじて新技術を導入しようとする鋭い戦略的判断の結果であった。そしてこの歴史的事実こそが、岸和田流が単なる初期の未熟な技術ではなく、戦国最強と謳われた武将をも納得させるだけの、最先端の実用性を備えていたことの何よりの証明と言えるだろう。
第五章:戦国砲術史における岸和田流の位置付け
岸和田流の歴史的意義をより明確にするためには、同時代に存在した他の主要な砲術流派との比較が不可欠である。その比較を通じて、岸和田流の独自性と、戦国砲術の発展史におけるその特異な立ち位置が浮き彫りになる。
岸和田流は、天文二十年(一五五一年)以前には既に関東地方に伝わっていたという記録が残っている 33 。これは鉄砲が日本に伝来してからわずか八年後のことであり、その伝播の速度は驚異的である。この事実は、岸和田流が極めて初期に成立し、かつ実践的な内容ゆえに、広域にわたって急速に需要を獲得したことを示唆している。
これに対し、後に砲術の二大流派と称されることになる稲富流と田付流は、やや遅れて登場する。稲富流の祖である稲富一夢は、丹後一色氏の家臣であり、その技術は照尺(照準器)を用いた遠距離射撃の正確さに特徴があった 34 。彼の流派は細川忠興や徳川家康にも仕え、体系的な伝書を伴うことで武家の砲術として高い評価を得た。一方、田付流の祖・田付景澄も近江の武士であり、徳川家康に仕えて大坂の陣で活躍した 36 。田付流は特に大筒の扱いに長け、その家系は幕府の鉄砲方として代々その技術を伝承した。
その他にも、上杉家臣であった関之信が創始し、大筒の名手として知られた関流 33 、荻野六兵衛安重が興し、射撃の所作や礼法を重視して武士の嗜みとしての側面を強めた荻野流 38 、黒田藩のお留め流として秘匿された陽流 40 など、多くの流派が武士によって創始され、特定の藩の庇護の下で洗練されていった。
これらの流派と岸和田流を比較すると、その異質性は明白である。
主要砲術流派 比較一覧表
|
流派名 |
創始者(出自) |
成立時期の目安 |
技術・思想的特徴 |
主要採用大名・組織 |
|
岸和田流 |
岸和田(薩摩商人) |
天文期(1543-) |
砲術と金瘡医術の融合、実践主義 |
上杉家(初期) |
|
稲富流 |
稲富一夢(武士) |
天正期(1573-) |
遠距離射撃、体系的伝書 |
細川家、徳川家 |
|
田付流 |
田付景澄(武士) |
慶長・元和期(1596-) |
大筒、外国産銃の扱い |
徳川幕府 |
|
関流 |
関之信(武士) |
慶長・元和期(1596-) |
大筒の名手 |
土屋家、上杉家 |
|
荻野流 |
荻野安重(武士) |
寛永期(1624-) |
礼法・所作を重視 |
幕府、諸藩 |
|
陽流 |
不明(黒田家臣) |
不明 |
日輪紋を流印とする、城門破壊等 |
黒田藩 |
この表が示すように、岸和田流は「商人創始」「医術との融合」「極めて早期の成立」という三点において、他の武士創始の主要流派とは一線を画している。この差異が、岸和田流のその後の運命を決定づけたと考えられる。
岸和田流は、実用性を武器にいち早く普及した「先駆者(パイオニア)」であった。しかし、その教えは口伝や『鉄炮之大事』のような実践的な手引書の形で伝承され、稲富流のような体系化された「砲書」としては整備されなかった可能性が高い。やがて、より理論的で、武士としての権威を持つ創始者たちが興した「後発」の流派が台頭すると、大名家は実用性だけでなく、自家の武威を示すための「ブランド価値」をも求めるようになる。技術が一定水準に達し一般化する中で、より体系的で権威のある後発流派へと乗り換えていったことは想像に難くない。
結果として、岸和田流はその先駆者としての歴史的役割を終え、後発の洗練された流派にその技術的要素を吸収されるか、あるいは単に歴史の表舞台から忘れ去られていった。これは、技術革新の初期段階で市場を切り拓いた先駆者が、市場の成熟と共に、より組織力とブランド力を持つ後発の強力なプレイヤーに淘汰されていくという、現代の産業史にも通じる「パイオニアの딜레마」である。岸和田流の盛衰の物語は、戦国時代という激動期における技術革新の光と影、そして「創造的破壊」のダイナミズムを象徴する、一つの貴重な事例として捉えることができるのである。
結論:再構築される岸和田流の全体像
本報告書は、戦国時代における砲術の一流派「岸和田流」と、その秘伝を記したとされる『岸和田流砲書』の謎を、現存する断片的な史料を基に徹底的に調査・分析したものである。その結果、これまで一般に信じられてきた伝承とは大きく異なる、新たな歴史像が浮かび上がってきた。
第一に、 『岸和田流砲書』という名の特定の書物は現存せず、その創始者も「岸和田左京進盛高」という武士ではなかった。 史料が示す創始者の実像は、鉄砲伝来の地である薩摩を拠点とした、名もなき一人の「商人」であった。これは、戦国初期の技術革新が、身分や家柄を超えて、時代の要請に応え得た実践者によって担われたことを示している。
第二に、 岸和田流の核心は、失われた一冊の「砲書」にあるのではなく、砲術と金瘡医術を組み合わせた、戦国初期の戦場における極めて実践的な「総合戦闘技術体系」そのものであった。 敵を倒す技術と味方を救う技術を統合したこの流派は、後の時代に様式化・精神化していく「武道」とは一線を画す、戦国時代ならではの即物的合理主義の産物である。
第三に、 この流派の価値は、出自を問わず最新技術を求めた上杉謙信のような先進的な大名に、他の主要流派に先駆けて採用された点にこそ示されている。 これは、岸和田流が当時、最先端の実用性を備えていたことの何よりの証左である。
そして最後に、 岸和田流は先駆者であったがゆえに、より体系化され、武家の権威をまとった後発の流派に取って代わられ、歴史の中に埋没していった。 その歴史は、技術革新の初期段階におけるパイオニアの栄光と悲哀を物語っている。
結論として、「岸和田流砲書」を探すという試みは、一つの書物を超えて、戦国時代という社会の流動性、技術革新がもたらした社会的インパクト(商人の地位向上や新しい専門職の出現)、そして武術という概念そのものの変容を明らかにするものであった。岸和田流は、幻の砲書としてではなく、戦国という時代を象徴する、生々しくも合理的な「生存の技術」として、日本の軍事技術史の中に再評価されるべきである。
引用文献
- 中近世移行期の 鉄 一流﹄にみる技術と呪術 - 国立歴史民俗博物館 ... https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1335/files/kenkyuhokoku_121_01.pdf
- 岸和田 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/hito1/kisiwada.html
- 岸和田 きしのわだ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/05/08/113851
- 鉄砲伝来の諸説/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40366/
- 鉄砲伝来 [たねがしま-Wiki-] - 種子島 https://www.e-tanegashima.com/dkwiki/teppoudenrai
- 鉄砲とキリスト教の伝来 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/josetsu/theme/chusei/christ/index.html
- 鉄砲伝来と南蛮貿易の真の理解者とは? | 株式会社stak https://stak.tech/news/12369
- 1 、鉄砲伝来と定義 - 日本の武器兵器 http://www.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp/part1/archives/5
- ものの始まりなんでも堺|ようこそ堺へ! - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/about-sakai/origin/main.html
- ~堺の「鉄砲」~ - Made In Local https://madeinlocal.jp/area/sakai-senshu/knowledge/095
- 鉄砲伝来 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5
- 薩摩藩家臣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9%E5%AE%B6%E8%87%A3
- 鹿児島藩(薩摩藩)家臣のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_kagosima.html
- 和式銃、火縄銃、幕末に揺らした岸和田銃 - 岸ぶら https://kishibura.jp/umeda/2021/04/kishiwada_jyu/
- 起業時のポジショニング戦略|戦国時代の専門集団に学ぶ差別化の方法 https://www.room8.co.jp/sengoku-specialization-strategy/
- 守田神社 (七二会) - 玄松子の記憶 https://genbu.net/data/sinano/morita2_title.htm
- 守田神社 - 延喜式神社の調査 http://engishiki.org/shinano/bun/shn250605-01.html
- 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[戦いを知る] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/tatakai/nenpyou.php.html
- 川中島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 信玄と謙信の川中島合戦 - 飯山市 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/dourokasen/kawamachi/50210/R6map.pdf
- 須田満親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E7%94%B0%E6%BA%80%E8%A6%AA
- 上杉家の武将 http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/uesugi.html
- 【定納員数目録のなかの信州衆】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100020/ht003320
- 宮坂考古館|火縄銃 https://www.miyasakakoukokan.com/hinawaju.html
- 人文系サイエンスマップ https://smap.nihu.jp/docs/search?q=%E6%96%B0%E9%A0%98%E5%9F%9F
- 日本の近代整形外科が生れるまで - ~1. 先史社会から中世まで https://www.joa.or.jp/joa/files/beginning.pdf
- 【内容編①】兵法家伝書 ~殺人刀の巻 ~ 前編 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho2/
- 第4回 精神性の展開とその背景 | 全日本剣道連盟 AJKF https://www.kendo.or.jp/knowledge/books/tokenshiso_04/
- 居合術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E5%90%88%E8%A1%93
- 直江兼続の鉄砲鍛造遺跡 - 米沢市 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/10/1034/5/5/287.html
- 別 紙 米沢藩上杉砲術について (概要・特色) 鉄砲(火縄銃)は、天文 12 年(1543)に種子島 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/material/files/group/35/H29besshi.pdf
- 米沢に伝わる稲富流砲術 | 米沢の歴史を見える化 https://ameblo.jp/yonezu011/entry-11296519994.html
- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93
- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/
- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411
- [田付流砲術書] たつけりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470720
- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81
- 荘内藩荻野流砲術隊(鶴岡) https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/kohojigyou/koho/koho-tsuruoka-h29/soumu0120170829.files/20170901-20-21.pdf
- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554
- 陽流砲術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/072/