徳本医方
永田徳本は戦国時代の医聖。牛に乗り民を救済。古医方「徳本医方」を確立し、簡潔な治療で民衆に寄り添う。現代の製薬会社名にも影響。
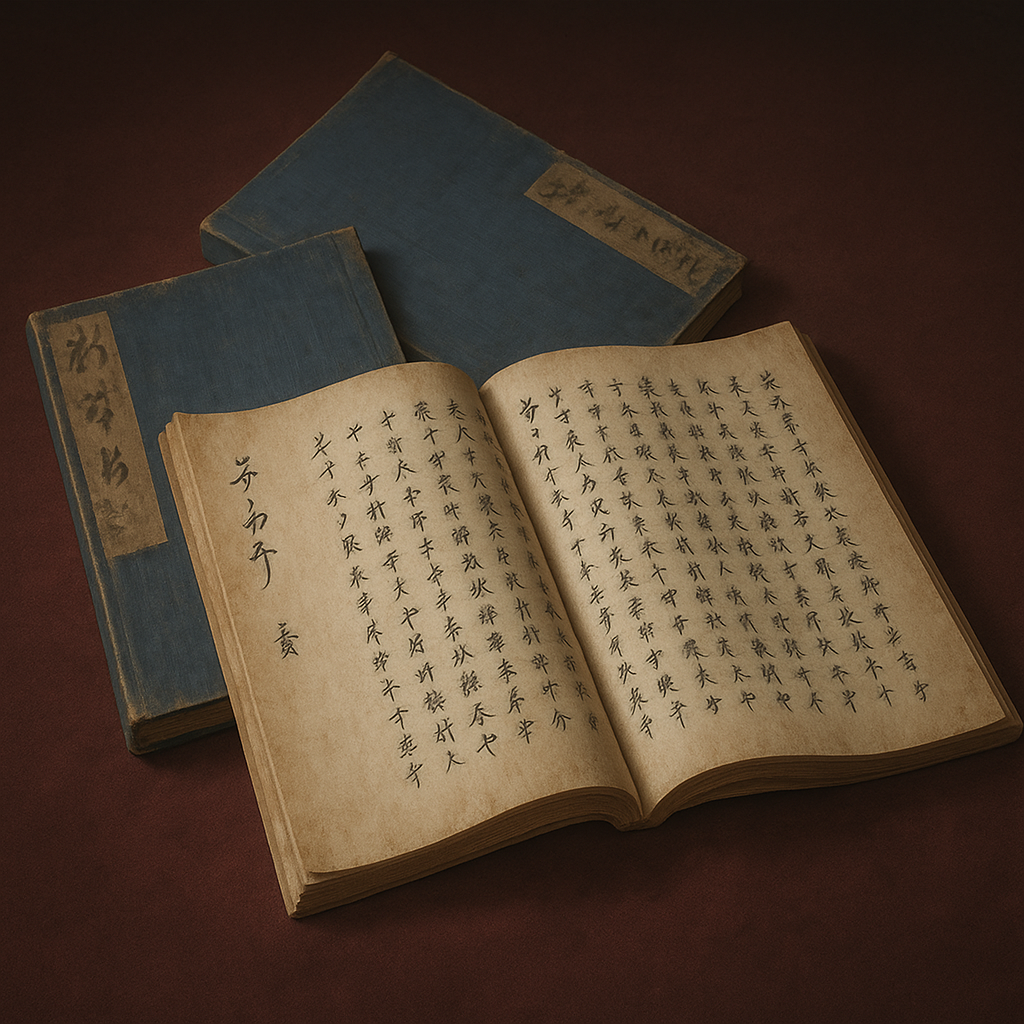
戦国を駆け抜けた異端の医聖―永田徳本と「徳本医方」の総合的研究
序論:乱世の医聖、永田徳本
戦国時代、すなわち応仁の乱に端を発し、百有余年にわたって続いた動乱の時代は、人の命が極めて軽く扱われた時代であった。そのような社会状況下にあって、一人の医師が「医聖」として民衆から深く敬愛され、118歳という驚異的な長寿を全うしたと伝えられている 1 。その名は、永田徳本。牛にまたがり「一服十六文(あるいは十八文)」と書いた薬袋を首から下げ、貧富の差なく人々を救療して回ったという伝説は、今日に至るまで語り継がれている 3 。
彼の生涯は、こうした民衆に寄り添う放浪の医師という側面を持つ一方で、甲斐の戦国大名・武田信玄の侍医を務め、後には二代将軍・徳川秀忠の重病を治癒したという、歴史の中枢に関わる記録も残されている 5 。伝説と史実が複雑に交錯するその人物像は、多くの謎に包まれている。
本報告書は、この永田徳本という稀有な人物の実像に迫ることを目的とする。彼が確立した独自の医学体系「徳本医方」とは、具体的にどのような思想と実践に基づいていたのか。なぜ彼は、同じく「医聖」と称えられながらも、医学界の主流を歩んだ曲直瀬道三とは全く異なる道を歩んだのか。そして、彼の思想と行動は、戦国という特異な時代といかに深く結びついていたのか。これらの問いに対し、残された著作や各地の伝承、そして同時代の医学史的文脈を多角的に分析し、その全体像を解き明かすものである。
第一章:永田徳本の生涯と時代背景
永田徳本の特異な医学思想と行動様式を理解するためには、まず彼という人物を形成した出自、修学の過程、そして彼が生きた時代の特異性を把握する必要がある。本章では、伝説の背後にある徳本の人間像に迫る。
第一節:出自の謎と修学の道―異端の源流
永田徳本の生涯は、その出自からして謎に満ちている。最も広く知られているのは、永正10年(1513年)に三河国大浜(現在の愛知県碧南市)で生まれたとする説である 1 。一方で、甲斐国谷村(現在の山梨県都留市)などを出生地とする異説も存在する 1 。
彼の姓が「長田」とも記されることは、その出自を考察する上で重要な手がかりとなる 2 。三河出生説によれば、徳本は平治の乱で源義朝を討ったとされる長田親政の子孫、長田広正の子であったという 1 。さらに、徳川家康に仕えた武将・永井直勝は徳本の兄・重元の子、すなわち甥にあたる 1 。この「長田」という姓が持つ、源氏の棟梁を討ったという歴史的背景は、武家社会において複雑な立場を意味したであろう。徳本が「永田」を名乗ったのは、この悲劇的な響きを持つ姓を避けたためとも考えられ、彼が権力と一定の距離を置く反骨精神を育んだ遠因となった可能性は否定できない 8 。彼の「放浪の医者」としての生き方は、単なる個人的信条のみならず、その出自がもたらした武家社会との宿命的な距離感に根差していたとも解釈できる。
徳本の修学遍歴もまた、彼の異端性を物語っている。彼は若くして陸奥国で仏門に入り、出羽国(あるいは常陸国鹿島)で修験道を学んだとされる 1 。その後、医学を志し、当時明からもたらされた最新の漢方医学である李朱医学(後世派医学)を、田代三喜、玉鼎、月湖道人といった当代一流の医家たちから学んだ 1 。
ここに、徳本の医学思想を理解する上で極めて重要な矛盾、あるいは「ねじれ」が見出せる。彼は当時の医学界における最先端の学問であった後世派医学の体系的な教育を受けていながら、後に彼が標榜し、実践したのは、それとは思想的に対極に位置する「古医方」であった 8 。これは、単なる知識不足や学問的未熟さからくるものではなく、最新の学問体系を習得した上で、それを批判的に乗り越え、より本質的と信じる古代の医方へと回帰するという、明確な思想的選択であったことを強く示唆している。
第二節:甲斐武田家との関わり―戦国大名の医療
医学を修めた徳本は、甲斐国に移り、国主であった武田信虎・信玄の父子二代に侍医として仕えたと伝えられる 5 。この時期の活動から、彼は「甲斐の徳本」として広く知られるようになった 2 。江戸時代後期に編纂された甲斐国の地誌『甲斐国志』には、徳本が易学をも用いて武田家の将軍(信虎・信玄)の診察にあたっていたとの記述が見られる 10 。
しかし、彼の侍医としての生活は長くは続かなかった。天文10年(1541年)、信玄が父・信虎を駿河へ追放するクーデターを起こすと、徳本はこの主家の内紛を嫌い、甲斐を去ったとされる 8 。この行動は、彼が単に主君に盲従する家臣ではなく、高い倫理観を持つ自律した知識人であったことを示す重要なエピソードである。
甲斐を去った徳本は、信濃国諏訪郡東堀村(現在の長野県岡谷市)に移り住み、地元の御子柴家に寄寓した。そこでその家の娘と結婚し、一子をもうけたと伝えられる 5 。武田氏滅亡までの約40年間にわたるこの諏訪での生活は、徳本の医学が真に円熟した時期であったと考えられている 5 。
第三節:放浪の医聖「十六文先生」―伝説と実像
天正10年(1582年)の武田家滅亡後、徳本の人生は新たな段階に入る。彼は特定の主君に仕えることをやめ、諸国を巡る放浪の医師となった。牛の背に横たわり、「一服十六文(あるいは十八文)」と大書した薬袋を掲げ、極めて安価な治療を行ったという彼の姿は、数々の伝説を生んだ 1 。貧しい者からは治療費を受け取らず、無料で薬を与えたともいう 3 。
この行動は、単なる慈善活動としてのみ捉えるべきではない。当時の医者が権門勢家に媚びへつらい、富裕な患者を優先する風潮があった中で、徳本の振る舞いは、医の原点とは何かを問い直す痛烈な社会批判であり、医の倫理を自らの身体をもって体現する一種の示威行動であった 8 。戦乱に疲弊した民衆にとって、彼の姿はまさに救世主、すなわち「医聖」として映ったであろう。
その一方で、徳本は孤高の変人ではなかった。若き日の林羅山(儒学者)を一時的に弟子として預かりながらも、その非凡な才能を見抜いて医学以外の道に進むよう諭したという逸話 1 や、京都で医学界の権威であった曲直瀬道三と往来があったとの記録 6 は、彼が当代の知識人ネットワークの中に確固たる位置を占めていたことを示している。
晩年、徳本は再び諏訪の地、東堀村に戻り、寛永7年(1630年)に118歳でその長い生涯を閉じたとされる 1 。岡谷市の尼堂墓地に現存する彼の墓(藍塔、あるいは籃塔)は、後世、その石粉を削り取って飲むと病が治ると信じられた 6 。墓石が著しく摩耗しているのは、彼が歴史上の人物から民俗信仰の対象へと昇華したことを示す何よりの証左である。
第二章:「徳本医方」の思想的源流と核心
永田徳本が確立した「徳本医方」は、彼の特異な生涯と分かちがたく結びついている。本章では、彼の医学理論の根幹をなす思想を、主著『医之弁』の記述を中心に解き明かす。
第一節:後漢・張仲景への回帰―『傷寒論』と古医方
前述の通り、徳本は田代三喜らから最新の李朱医学(後世派医学)を学んだ。しかし、彼は当時主流であったこの学派の、ややもすれば煩雑な理論体系に飽き足らず、中国・後漢時代の医師、張仲景が著したとされる医学古典『傷寒論』の医説にこそ、医学の本質があるべきだと主張した 5 。これは、医学史において「古医方」と呼ばれる立場への明確な回帰であった。
『傷寒論』に基づく古医方は、金元代以降に発展した精緻で複雑な陰陽五行説や臓腑経絡説よりも、患者が示す具体的な症状と、それに対応する処方を直結させる実践性を何よりも重視する。病の兆候(証)を鋭く捉え、薬物の力を最大限に活用して体内の病邪を迅速かつ強力に排除することを目指す、攻撃的ともいえる治療スタイルを特徴とする。
この直接的で即効性を重んじるアプローチは、戦国という時代背景と深く共鳴していた。一刻を争う戦場での負傷兵治療や、体力のある若者の急病に対しては、複雑な理論に基づく悠長な治療よりも、迅速で効果的な処方が求められた。徳本の古医方への傾倒は、単なる学問的嗜好ではなく、彼が生きた時代の社会的要請に応えようとする、極めて実践的な選択であったと考えられる。
第二節:「万病は鬱滞に起こり、風寒に感ず」―『医之弁』の病理観
徳本の医学思想の核心は、天正13年(1585年)に成立したとされる主著『医之弁』の中に凝縮されている 13 。この書で彼は、「あらゆる疾病は、体内の気・血・水の流れが滞る『鬱滞(うったい)』が根本的な原因であり、それが『風寒(ふうかん)』、すなわち風邪や冷えといった外的なきっかけに触れることで発病に至る」と断じた 8 。
この病理観は、一見すると単純に過ぎるように思えるかもしれない。しかし、その思想的意義は極めて大きい。万病の原因を「鬱滞」という一つの概念に集約することで、診断から治療方針の決定に至るプロセスが劇的に迅速化される。これは、理論の精緻化・複雑化を重ねる一方であった後世派医学に対する強烈なアンチテーゼであり、医学の世界における一種の「原点回帰」を志向する思想的転換であった。
彼が主たる活動の場とした戦場や庶民医療の現場では、複雑な弁証論治(病態を多角的に分析して治療方針を決める方法)よりも、迅速かつ効果的な治療こそが最も重要であった。徳本の理論は、そうした現場のニーズに最適化された、強力で実践的な思想体系だったのである。
第三節:汗・吐・下・和―攻撃的な治療法
徳本は、病の根本原因である「鬱滞」を排除するため、具体的ないくつかの治療法を提唱した。それが、「汗(かん)・吐(と)・下(げ)・和(わ)」として知られる四つの治療法である 8 。
- 汗法(かんぽう): 発汗を促す薬物(麻黄、桂枝など)を用いて、体表部にある病邪を汗と共に体外へ追い出す方法。
- 吐法(とほう): 薬物を用いて意図的に嘔吐させ、胸郭や胃の中に停滞する病邪や毒物を排出する方法。
- 下法(げほう): 下剤を用いて、腹中に滞留する病邪や宿便を便と共に排出する方法。
- 和法(わほう): 上記の三法が病邪を直接攻撃する方法であるのに対し、この方法は諸薬の作用を調和させたり、体の諸機能のバランスを整えたりすることで、病からの回復を促す方法である。
特に汗・吐・下の三法は、病邪を直接的に攻撃する強力な手段であり、徳本はこれらの治療法を実践するにあたり、作用の激しい薬物、現代でいえば劇薬に相当するものも躊躇なく用いたとされる 8 。これは、病の根本原因に対して正面から戦いを挑み、力をもってこれを駆逐するという、彼の古医方に基づく攻撃的な治療思想の明確な現れであった。
第三章:徳本医方の実践―主著の徹底解剖
徳本の医学思想が、具体的にどのような処方として結実したのか。本章では、彼の代表的な著作とされる『徳本翁十九方』と、謎に包まれた『梅花無尽蔵』を分析し、徳本医方の実践面に光を当てる。
第一節:戦場の必携書―『徳本翁十九方』
徳本の著作の中でも、その実践的な性格を最もよく示しているのが『徳本翁十九方』である。この書は別名を『救急十九方』とも称し、武田信玄が陣中の必携書としていたと伝えられる 14 。その名の通り、平時の医療のみならず、戦時下における救急医療にも即応できるよう工夫された、まさに戦国時代ならではの医学書であった。
この処方集の大きな特徴は、携帯性に優れた丸薬や散薬の形をとるものが多い点である 14 。これは、常に移動を伴う軍陣での使用を強く意識したものであろう。徳本は、27種類という比較的限られた生薬を巧みに組み合わせることで、19の基本処方を構築し、様々な疾病に対応しようとした 14 。
徳本が用いた薬物(武器)と、それらを組み合わせた処方(戦術)の概要を以下に示す。
|
No. |
生薬名 (読み) |
主な薬能 14 |
|
1 |
桂枝 (ケイシ) |
体を温め、発汗を促す。健胃作用。 |
|
2 |
甘草 (カンゾウ) |
諸薬を調和させ、作用を緩和する。止渇作用。 |
|
3 |
大棗 (タイソウ) |
強壮・鎮静作用。諸薬の作用を緩和する。 |
|
4 |
生姜 (ショウキョウ) |
発散作用、健胃作用、鎮吐(吐き気止め)作用。 |
|
5 |
芍薬 (シャクヤク) |
消炎、鎮痛、鎮痙作用。 |
|
6 |
葛根 (カッコン) |
発汗、解熱、鎮痙作用。 |
|
7 |
麻黄 (マオウ) |
強力な発汗・解熱作用。鎮咳、喘息を鎮める。 |
|
8 |
杏仁 (キョウニン) |
鎮咳、去痰作用。 |
|
9 |
半夏 (ハンゲ) |
強力な鎮吐作用。去痰作用。 |
|
10 |
桔梗 (キキョウ) |
去痰、排膿(膿を出す)作用。 |
|
11 |
橘皮 (キッピ) |
健胃、去痰、鎮咳作用。気の巡りを良くする。 |
|
12 |
黄芩 (オウゴン) |
消炎、解熱作用。 |
|
13 |
柴胡 (サイコ) |
解熱、鎮痛、消炎作用。肝機能の調整。 |
|
14 |
茯苓 (ブクリョウ) |
利尿、鎮静作用。健胃作用。 |
|
15 |
細辛 (サイシン) |
体を温め、鎮痛、鎮咳作用。 |
|
16 |
五味子 (ゴミシ) |
鎮咳、去痰作用。滋養強壮。 |
|
17 |
乾姜 (カンキョウ) |
体を強く温める。健胃作用。 |
|
18 |
附子 (ブシ) |
強力な強心、鎮痛、体を温める作用。毒性が強い。 |
|
19 |
人参 (ニンジン) |
滋養強壮、体力増強、健胃作用。 |
|
20 |
当帰 (トウキ) |
補血、血行促進、鎮痛作用。 |
|
21 |
白朮 (ビャクジュツ) |
健胃、利尿作用。消化吸収を助ける。 |
|
22 |
蒼朮 (ソウジュツ) |
健胃、利尿作用。体内の余分な水分を除く。 |
|
23 |
防己 (ボウイ) |
利尿、鎮痛作用。むくみを除く。 |
|
24 |
沢瀉 (オモダカ) |
利尿、止渇作用。 |
|
25 |
瞿麦 (クバク) |
消炎、利尿作用。 |
|
26 |
天花 (テンカフン) |
清熱、生津(潤いを生む)作用。 |
|
27 |
琥珀 (コハク) |
鎮静、安神作用。利尿、血行促進。 |
|
|
|
|
これらの生薬を用いて構成された19の処方は、風邪の初期症状から胃腸障害、化膿性の疾患、さらには精神神経症状に至るまで、幅広い病態をカバーしている。
|
処方名 |
主な適応症・特徴 14 |
|
發陳湯 (発陳湯) |
吐き気、嘔吐、めまいなど。胃の水分停滞を改善する。 |
|
榮陽湯 (栄陽湯) |
気力・血の不足。疲労倦怠、顔色が悪い、空咳、動悸など。 |
|
青龍湯 (小青龍湯) |
アレルギー性鼻炎、気管支喘息。水様の鼻水や痰を伴う咳。 |
|
理中散 |
胃腸の冷えによる腹痛、下痢、嘔吐。 |
|
容平丸 |
(詳細不明) |
|
瀉心円 |
胃腸炎、消化不良、二日酔い。みぞおちのつかえ、下痢。 |
|
解毒丸 |
風邪による喉の痛み、咳、発熱。 |
|
救疝飲 |
疝気(腹部の激痛)の治療。 |
|
直行丸 |
(詳細不明) |
|
芍薬散 |
貧血、冷え性。婦人科系の疾患(月経不順など)。 |
|
清済子湯 |
(詳細不明) |
|
当帰散 |
婦人科系の処方。貧血、冷え、腹痛、むくみ。 |
|
順気散 |
気の巡りを良くし、栄養を補助する。 |
|
禹余粮丸 |
慢性の下痢、脱肛の治療。 |
|
癇虫丸 |
小児のひきつけ、かんのむし。 |
|
玉丹 |
強心作用。ウイルス性心筋炎など。水銀などを含む劇薬。 |
|
磁石丸 |
耳鳴り、めまい。特に腎虚(老化など)によるもの。 |
|
排膿散 |
化膿性の皮膚疾患、歯肉炎など。 |
|
治瘡丸 |
梅毒などの性病による皮膚症状。 |
|
|
|
第二節:謎多き医書―『梅花無尽蔵』を巡る考察
徳本の著作として、『医之弁』『徳本翁十九方』と並んで『梅花無尽蔵』の名が挙げられることがある 1 。しかし、この書名を巡ってはいくつかの混乱が見られる。最も著名なのは、室町時代後期の五山文学を代表する禅僧・万里集九が著した漢詩文集『梅花無尽蔵』であり、全くの別物である 16 。
しかし、永田徳本が著したとされる同名の医書が存在した可能性は高い。名古屋市立大学図書館の大神文庫や国立公文書館に、永田徳本著とされる『梅花無尽蔵』の所蔵記録が残っている 15 。また、国立国会図書館や国立情報学研究所のデータベースにも、徳本を著者とする『梅花無尽蔵』が登録されている 18 。
その具体的な内容は不明な点が多いものの、現存する『甲斐流眼目之書』という眼科の秘伝書に記された処方の一部が、『梅花無尽蔵』の眼目門に掲げられたものと類似しているとの指摘がある 20 。このことから、徳本著の『梅花無尽蔵』には、少なくとも眼科治療に関する詳細な記述が含まれていたと推察される。また、「眼ヲ丈夫二致ス方」といった養生訓が「徳本翁之博」として伝わっていることからも 21 、特定の分野に特化した専門的な内容や、民衆向けの養生法などを記した医書であった可能性が考えられる。
この徳本著『梅花無尽蔵』は、同名の著名な先行作品の存在ゆえに、その実態が見過ごされがちである。しかし、複数の所蔵記録が存在する以上、その内容は徳本医方の全体像を理解する上で重要な鍵を握っているに違いない。今後の研究による内容の解明が待たれる、学術上の重要な課題である。
第四章:戦国医学史における永田徳本の位置づけ
永田徳本という医師の特異性を理解するためには、彼を同時代の医学史の中に位置づけ、他の医家と比較することが不可欠である。特に、同じく「医聖」と称えられた曲直瀬道三との対比は、戦国時代における医学の二つの潮流を浮き彫りにする。
第一節:対比される医聖―曲直瀬道三との比較
曲直瀬道三(1507-1594)は、徳本とほぼ同時代に生き、後世派医学を大成させた巨星である 22 。彼もまた徳本と同様に田代三喜に師事し、李朱医学を学んだが、その後の道は全く対照的であった 23 。
道三は、師から受け継いだ医学をさらに発展させ、実証的な臨床医学の体系を築き上げた 23 。彼の主著『啓迪集』は、その三十余年にわたる臨床記録をまとめたもので、日本医学史上の古典として高く評価されている 25 。彼は京都に医学教育機関「啓迪院」を設立し、数百人もの門人を育成した 22 。さらに、足利将軍、織田信長、豊臣秀吉、正親町天皇といった時の最高権力者たちの侍医を務め、医学界に確固たる地位を築いた 22 。道三は、医学を学問として体系化し、その社会的地位を確立した、いわば医学界の「アカデミズム」を体現する存在であった。
これに対し、永田徳本は全く異なる道を歩んだ。両者の違いは、以下の表に集約することができる。
|
項目 |
永田徳本 |
曲直瀬道三 |
|
通称 |
甲斐の徳本、十六文先生 1 |
日本医学中興の祖 22 |
|
医学流派 |
古医方(張仲景への回帰) 8 |
後世派(李朱医学の発展・大成) 23 |
|
主要拠点 |
諸国を放浪、甲斐・諏訪 1 |
京都 22 |
|
主な患者 |
武田信虎・信玄、一般民衆、徳川秀忠 5 |
足利将軍、織田信長、豊臣秀吉、天皇 22 |
|
教育活動 |
特定の学校は設立せず、個人的な弟子のみ 1 |
啓迪院を設立し、数百人の門人を育成 22 |
|
思想的特徴 |
医の倫理を説き、医家の風俗矯正に熱心 8 |
医学の体系化、学問としての確立 23 |
|
主著 |
『医之弁』、『徳本翁十九方』 1 |
『啓迪集』 25 |
|
|
|
|
この対比から浮かび上がるのは、戦国時代における「医聖」の二つの異なるモデルである。道三が「知」の力で医学を体系化し、中央の権力と結びつくことで医学の社会的地位を高めた「体制派の改革者」であったとすれば、徳本は「行」の力で医の原点を問い直し、地方や民衆の側から医学のあり方を革新しようとした「反体制の革命家」であったと言えよう。戦国という激動の時代は、この両極端ともいえる二人の「医聖」を同時に必要としていたのである。
第二節:医の倫理と社会への眼差し
徳本の安価な医療や貧者への無償の施しは、単なる個人的な慈善や美談に留まるものではない。それは、「医者が権門勢家にへつらい、貧困者に見向きもしなかったのを改めさせようとした」 8 という、当時の医療界のあり方に対する明確な批判と、社会を改革しようとする強い意志に基づいていた。彼の行動は、医術の技術論だけでなく、医家のあるべき姿、すなわち医の倫理を世に問うものであった。
また、彼の関心は人間の病だけに留まらなかった。山野を巡って薬草を自ら採取し研究した彼は、本草学(薬物学)にも深く精通していた 8 。その植物に関する深い知識は、医学の領域を超え、甲州における葡萄栽培法の改良(棚架け法の考案)にも活かされたと伝えられている 8 。これは、彼の知が人々の病を癒すだけでなく、その生活(生業)を豊かにすることにまで及んでいたことを示している。徳本の眼差しは、常に民衆の暮らしに向けられていたのである。
結論:伝説から歴史へ―永田徳本が現代に遺したもの
本報告書で詳述してきたように、永田徳本は、牛にまたがる奇人といった伝説的なイメージの裏で、確固たる医学思想を持つ実践家であった。彼は、当時の最先端であった後世派医学を学んだ上で、戦国という時代の要請に応えるべく、あえて古代の医方へと回帰するという思想的選択を行った。彼が確立した「徳本医方」は、「鬱滞」と「風寒」という極めてシンプルかつ強力な病理観に基づき、作用の強い薬を用いて迅速に病根を叩く、直接的で実践的な医療体系であった。
彼の特異な生き様と、民衆に寄り添う医の倫理は、時代を超えて人々の記憶に刻まれた。権威に屈せず、仁術を貫いたその姿は、後世の医師たちにとって一つの理想像となり、その名は「医聖」として語り継がれた。また、岡谷の墓所や各地に祀られた徳本稲荷は、彼が歴史上の偉人から民俗信仰の対象へと昇華したことを物語っている 6 。
そして、永田徳本が現代に遺した最も具体的で広範な影響は、外用消炎鎮痛薬で知られる製薬会社「トクホン」の社名であろう 31 。創業者が徳本の「徳」という字が持つ人々への恩恵と、痛みを「解く」という言葉の響きに深く感銘を受けて命名したこの名は、戦国時代の異端の医聖の精神が、形を変えて現代の家庭薬の中に生き続けていることを象徴している 33 。
永田徳本の物語は、単に過去の歴史の中に埋もれることなく、医の倫理、民衆への眼差し、そして現代の商品名という形で、今なお我々の生活の一部として息づいているのである。
引用文献
- 永田徳本 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E5%BE%B3%E6%9C%AC
- 永田徳本(ナガタトクホン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E5%BE%B3%E6%9C%AC-107731
- www.okayacci.or.jp http://www.okayacci.or.jp/tokuhon/about/profile/#:~:text=%E6%B0%B8%E7%94%B0%E5%BE%B3%E6%9C%AC%EF%BC%88%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%9F,%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
- 徳本翁 (PDFファイル: 117.7KB) - 碧南市 https://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/group/58/13_nagatatokuhon.pdf
- 徳本先生について: プロフィールアーカイブ http://www.okayacci.or.jp/tokuhon/about/profile/
- 1. 永田 徳本 http://www.okayacci.or.jp/docs/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E5%BE%B3%E6%9C%AC%E6%A7%98%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB.pdf
- 徳本上人の足跡と名号碑 - 諏訪形誌 https://suwagata.ueda-common.net/tokuhon_all.pdf
- 徳本翁 | 歴史 | みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/tokumoto.html
- 永田徳本とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E7%94%B0%E5%BE%B3%E6%9C%AC
- 甲斐国志 - Translation into English - examples Japanese | Reverso Context https://context.reverso.net/translation/japanese-english/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%9B%BD%E5%BF%97
- 易学 - Translation into English - examples Japanese | Reverso Context https://context.reverso.net/translation/japanese-english/%E6%98%93%E5%AD%A6
- 真中が永田徳本のお墓(籃塔) https://hiramatu-hifuka.com/iboibo/iboibo01/tokuhon.html
- 医之弁(いのべん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%BB%E4%B9%8B%E5%BC%81-1505547
- 徳本先生について: お薬 十九方についてアーカイブ http://www.okayacci.or.jp/tokuhon/about/medicine/
- 大神文庫(田辺通分館所蔵) | 図書館・病院・附属施設 - 名古屋市立大学 https://www.nagoya-cu.ac.jp/affiliate/library/search/ooga/
- 梅花無尽蔵|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=974
- 梅花無尽蔵 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1237574
- 梅花無尽蔵 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000136-I1460585172448990720
- 梅花無尽蔵 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000136-I1460303697472320000
- 研医会通信87号 http://ken-i-kai.org/homepage/index1301.htm
- 研医会通信134号 - 公益財団法人 研医会 http://ken-i-kai.org/homepage/index1609.html
- 曲直瀬道三 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/WorldWide/HumanManaseDouzan.html
- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89
- 曲直瀬道三~信長、秀吉、家康も診察した戦国最強ドクター - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4345
- 曲直瀬道三の『啓廸集』 | 長崎県歯科医師会「8020ながさき」 https://www.nda.or.jp/study/history/dousan
- 啓迪集〈自筆本〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/231828
- <更新しました>校長コラム | 鍼灸・針治療・あん摩マッサージ指圧師の専門学校なら【東洋鍼灸専門学校】 https://www.toyoshinkyu.ac.jp/info/10213/
- 曲直瀬家文書 - 港区文化財総合目録 https://www.minato-rekishi.com/museum/2019/09/R01-03.html
- 徳本先生について: 逸話アーカイブ http://www.okayacci.or.jp/tokuhon/about/anecdote/
- 金龍山 宝珠寺 | 【愛知県碧南市公式観光サイト】へきなん観光ナビ https://www.hekinan-kanko.jp/highlight/detail/30/
- www.tokuhon.co.jp https://www.tokuhon.co.jp/company/#:~:text=%E7%A4%BE%E5%90%8D%E3%83%BB%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%90%8D%E3%80%8C%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%80%8D,%E3%81%AB%E7%94%B1%E6%9D%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- トクホン|企業情報 https://www.tokuhon.co.jp/company/
- トクホン|家庭薬ロングセラー物語 https://www.hmaj.com/kateiyaku/tokuhon/
- トクホン ニッポン・ロングセラー考 - COMZINE by nttコムウェア https://www.nttcom.co.jp/comzine/no076/long_seller/index.html