水軍戦法要領
『水軍戦法要領』はゲーム内の架空書だが、村上水軍の海戦術がモデル。能島・来島・因島の三島村上氏が瀬戸内海を支配し、潮を制する戦術やほうろく火矢で名を馳せた。海賊停止令で終焉するも、近代に継承。
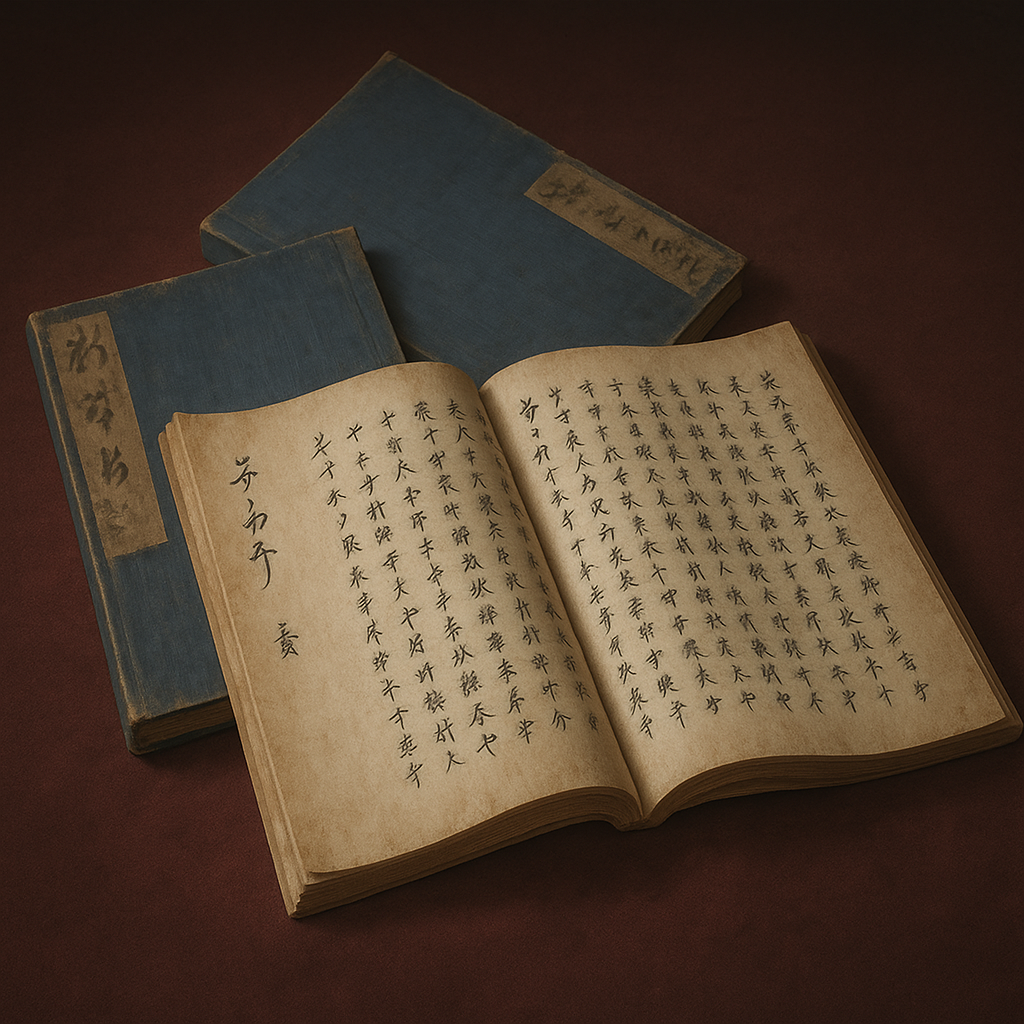
日本戦国史の深淵:「水軍戦法要領」と村上水軍の兵法体系に関する総合的考察
序論:幻の兵法書「水軍戦法要領」を追って
日本の戦国時代、陸の武将たちが覇を競う一方で、海を支配し、時に天下の趨勢をも左右した勢力が存在した。その筆頭が、瀬戸内海に君臨した村上水軍である。彼らの強さの秘密を解き明かす鍵として、一つの名が伝えられている。それが「水軍戦法要領」である。これは、村上水軍の船団編成法や陣形が、詳細な絵と共に記された図であるとされている 1 。
しかし、この「水軍戦法要領」という名は、特定の単一の書物を指すというより、村上水軍、特にその中核を成した能島村上氏が実践した海戦術の要点をまとめた図や文書の総称、あるいはその一部を指す概念である可能性が高い。本報告書は、この「水軍戦法要領」を調査の入り口とし、その背後に横たわる村上水軍の広範な兵法体系、すなわち「能島流(のしまりゅう)」を探求する 2 。そして、その戦術思想、それを運用した組織の実態、歴史的合戦における実践、さらには後世への影響までを包括的に解明することを目的とする。
第一部:「能島流」兵法の探求 ― 文献に見る村上水軍の知恵
1.1. 「水軍戦法要領」の実体と現存する兵法伝書
「水軍戦法要領」は、村上水軍の頭領・村上武吉が記したとされる水軍書を指す一般的な呼称として認識されている 1 。しかし、現存する史料群を精査すると、その実体は単一の書物ではなく、より広範で体系的な知識の集成であったことが明らかになる。
その核心的な証拠が、広島県立文書館に所蔵される「能島家伝」である 4 。この兵法書は5巻1冊から成り、その写本が内閣文庫や神戸大学、東北大学などにも所蔵されている事実は、高度に体系化された兵法知識が、家伝として大切に継承されていたことを物語っている 4 。さらに、海上自衛隊第一術科学校には「野島流不審」「野島流兵守微船録」といった「野島流(能島流の別称)」の名を冠する文献群が保管されており、これらが水泳術ではなく、海戦術を主眼とした書物であることが確認されている 3 。
これらの事実から導き出されるのは、「水軍戦法要領」とは、特定の孤立した図や書物ではなく、能島村上家に伝わる「能島流」または「野島流」と呼ばれる、口伝と複数の文書から成る総合的な海戦術体系の、特に図解された「要点(要領)」部分を指すものと解釈するのが最も妥当であるという結論である。それは、巨大な知識体系への入り口であり、その視覚的な表現に他ならない。
1.2. 兵法各流派の成立と特徴
村上水軍の兵法は、能島・来島・因島の三家が瀬戸内海の覇権を争う中で実践的に研究し、体系化したものを源流とし、これらは総称して「三島流」と呼ばれた 3 。三島流は、多くの海賊(水軍)流派の中でも最も強大で、戦法としても優れていたとされる 5 。
時代が下り、江戸時代に入ると、能島村上氏は毛利氏の船手組(正規の海軍部隊)として存続する。その船奉行となった能島元信(村上武吉の孫)が、三島流の伝統を基に一流を立て、「能島流(野島流)」として大成させたと伝えられている 3 。
この能島流を他の水軍流派と比較することで、その独自性がより鮮明になる。例えば、村上武吉らが毛利元就に呈上し、毛利家の秘伝となった「一品流」は、大名家の軍事体系に組み込まれた兵法であった 3 。また、織田信長に仕えた九鬼嘉隆が創始した「九鬼流」は、焙烙火矢を無効化する「鉄甲船」の運用を前提とした、火力と防御力を重視する革新的な兵法であった 3 。これらに対し、能島流は芸予諸島の複雑な地形と激しい潮流を最大限に利用し、小型船の機動力を駆使して敵を翻弄することに主眼を置いた、地理的特性に深く根差した兵法であったと言える 1 。
第二部:瀬戸内の覇者、村上水軍の実像
2.1. 「海賊」にあらず ― 海の領主としての実態
イエズス会宣教師ルイス・フロイスが、その著作の中で村上武吉を「日本最大の海賊」と評したことは、彼らの武威が遠く欧州にまで伝わっていたことを示す有名な逸話である 6 。しかし、この「海賊」という言葉から現代人が想起する無法な略奪者というイメージは、彼らの実態とは大きく異なる。
彼らの本業は、瀬戸内海という大動脈の秩序を維持し、航行の安全を保障する「海の領主」としての活動であった。具体的には、複雑な海流を熟知した水先案内人として船を導き、他の海賊からの襲撃を防ぐ海上警固を行い、その対価として「帆別銭(ほべちせん)」や「警固料」と呼ばれる通行料を徴収していた 6 。これは、陸の大名が農民から徴収する年貢によって経済基盤を築いたのと同様に、村上水軍は海上交通の支配権から得られる通行税を収入源とする、独自の経済システムを持つ独立した権力主体であったことを意味する 7 。
彼らは毛利氏や大友氏といった大大名からの要請に応じ、傭兵集団として合戦に参加することもあったが、それはあくまで契約に基づくものであり、特定の主君に隷属することのない、誇り高き独立勢力であった 2 。戦国期の「海賊」とは、無法者ではなく、独自の経済基盤と統治システムを持つ「海上領主」とも言うべき存在であり、戦国社会の秩序を構成する重要な要素だったのである。
2.2. 天然の要塞「能島」と船団編成
村上水軍の強さを物理的に支えたのが、本拠地である能島とその周辺の地理的環境である。芸予諸島に位置する能島の周辺海域は、最大で時速18キロメートル(約10ノット)にも達する激しい潮流と、海底の複雑な岩礁が「湧き潮」と呼ばれる予測不能な渦を生み出す、日本有数の海の難所であった 10 。村上水軍はこの潮の干満や流れの速さを完全に把握し、潮が止まるわずかな時間帯を狙って安全に出入りする術を心得ていた 10 。これにより、能島は攻め寄せる敵にとっては近づくことすら困難な、天然の要塞と化していたのである 11 。
彼らが駆使した船団は、目的と戦況に応じて多様な艦船で柔軟に編成された。船団の旗艦として司令塔の役割を担い、多くの兵員と武装を搭載した大型の「安宅船(あたけぶね)」。機動力と戦闘力のバランスに優れ、海戦の主力となった中型の「関船(せきぶね)」。そして、その俊足を生かして偵察や奇襲、伝令といった任務で活躍した小型の「小早(こばや)」が、その中核を成した 12 。これらの船は、単に戦闘のためだけではなく、兵員や兵糧を前線に輸送するという、兵站においても決定的な役割を果たした 14 。
第三部:村上水軍の海戦術と陣形
能島流兵法の中核を成すのは、瀬戸内海の特性を知り尽くした彼らならではの、合理的かつ実践的な海戦術であった。それは、特異な兵器の活用と、状況に応じた巧みな陣形操作によって支えられていた。
3.1. 海戦の主役 ― 焙烙火矢と火攻め戦術
村上水軍の代名詞とも言える兵器が「焙烙火矢(ほうろくひや)」である。これは、素焼きの壺や玉(焙烙)に火薬を詰め、導火線に火をつけて敵船に投げ込む、現代の手榴弾や焼夷弾に近い炸裂兵器であった 16 。
木造船が主体であった当時、この焙烙火矢の効果は絶大であった。敵船の帆や甲板、船体そのものを直接炎上させる物理的な破壊力に加え、至近距離での轟音と爆風、そして飛び散る陶器の破片は、敵兵に甚大な恐怖を与え、その士気をくじき、組織的な戦闘能力を奪った 11 。この火攻め戦術こそが、村上水軍の戦術的優位性の源泉であり、彼らが瀬戸内の覇者として恐れられた最大の理由の一つであった。
3.2. 鶴翼の陣 ― 包囲殲滅の海戦陣形
陸戦でも広く知られる「鶴翼の陣」は、海戦においては敵船団をV字型に包み込む陣形として応用された 19 。鶴が翼を広げたような形で左右に部隊を展開し、敵を待ち受ける防御的な陣形であり、兵力で優勢な場合に特に有効とされた 21 。
海戦における鶴翼の陣の戦術的意図は、単に敵を包囲することに留まらない。その真の目的は、敵船団の先頭部隊の進路を塞ぎ、自軍の多数の船の側面(舷側)を敵に向けることにあった 24 。船は前方に比べて側面に多くの火器(鉄砲や弓)を配置できるため、この体勢を取ることで、敵の先頭艦に対して自軍の火力を最大限に集中させることが可能となる。これは、敵の縦隊の進路を自軍の横隊で遮る、後の近代海軍における「丁字戦法」の思想的源流とも言える、極めて合理的な戦法であった 25 。
3.3. 魚鱗の陣 ― 中央突破の攻撃陣形
鶴翼の陣とは対照的に、「魚鱗の陣」は攻撃に特化した陣形である。魚の鱗のように部隊を三角形に配置し、その鋭角な先端を敵陣に向けることで、敵の中央を一点突破することを目的とした 26 。
この陣形は、戦力を一点に集中させるため、兵力で劣勢な場合でも、敵の指揮系統を分断し、大将船を直接叩くことで一挙に戦局を覆す可能性を秘めていた 29 。ただし、側面や後方からの攻撃には脆弱であるという欠点も併せ持っていた 31 。陸戦ではあるが、三方ヶ原の戦いにおいて、武田信玄が鶴翼の陣を敷いた徳川家康の軍を、魚鱗の陣で打ち破った事例は、この陣形の攻撃力の高さを物語っている 32 。
3.4. 方円の陣とその他の陣形
「水軍戦法要領」には、鶴翼や魚鱗以外にも、戦況に応じた多様な陣形が記されていたと考えられる。その一つが「方円の陣」である。これは、船団を円形または方形に配置する全方位防御陣形であり、中心に大将船や護衛対象の輸送船を置き、敵の奇襲や包囲から守るために用いられた 28 。
その他にも、狭い水道を縦一列で突破するための「長蛇の陣」や、大将が自ら先陣を切って突撃し、部隊の士気を最大限に高める「偃月(えんげつ)の陣」など、地形や戦況、目的に応じて様々な陣形を使い分けていたことが、兵法書の記述からうかがえる 29 。
戦国期水軍の主要陣形一覧
|
陣形名 |
目的 |
特徴 |
利点 |
欠点 |
|
鶴翼の陣 |
防御・包囲 |
船団をV字型に広げ、敵を待ち受ける。 |
敵を包囲し、側面からの集中砲火を浴びせやすい。兵力優勢時に有利 23 。 |
中央部が薄くなるため、敵の強力な中央突破に弱い 33 。 |
|
魚鱗の陣 |
攻撃・突破 |
船団を鋭角な三角形に編成し、一点突破を図る。 |
攻撃力を一点に集中でき、兵力劣勢でも敵中枢を破壊できる可能性がある 27 。 |
側面や後方からの攻撃に脆弱で、包囲されやすい 30 。 |
|
方円の陣 |
全方位防御 |
船団を円形または方形に配置し、中央を守る。 |
どの方向からの攻撃にも対応可能。奇襲への備えや輸送船団の護衛に適する 28 。 |
機動力が低下し、攻撃的な行動には移りにくい。 |
|
長蛇の陣 |
特殊(突破) |
船団を縦一列に並べる。 |
狭い海峡や水路を通過する際に有効。前後の連携が取りやすい 29 。 |
側面からの攻撃に極めて弱い。平水域での海戦には不向き 30 。 |
|
偃月の陣 |
攻撃(突撃) |
弓なりに部隊を配置し、大将が先頭に立つことが多い。 |
大将が先陣を切るため、部隊の士気が非常に高まる。高い攻撃力を発揮する 29 。 |
大将が討たれる危険性が高く、陣形全体の崩壊に繋がりやすい。 |
第四部:歴史的合戦にみる戦法の神髄
能島流兵法の真価は、机上の理論ではなく、日本の歴史を揺るがした数々の合戦において証明された。
4.1. 厳島の戦い(天文二十四年、1555年)
毛利元就が、自軍の数倍に及ぶ陶晴賢の大軍を奇襲によって破ったこの合戦において、村上水軍の役割は勝敗を決定づけるものであった。彼らは単なる戦闘部隊ではなく、毛利方の戦略そのものを可能にするパートナーとして機能した。
村上水軍は、その卓越した航海術を駆使し、闇夜と激しい潮流に乗じて毛利軍の本隊を密かに厳島へと上陸させた 34 。そして、夜が明けると同時に陶軍の背後に回り込み、海上を完全に封鎖。これにより、陶軍は退路を断たれ、陸の毛利軍と海の村上水軍によって挟撃され、壊滅した 6 。これは、潮の流れを読み切る村上水軍ならではの地理的知識と操船技術がなければ、決して成り立たない作戦であった。
4.2. 第一次木津川口の戦い(天正四年、1576年)
織田信長による石山本願寺の兵糧攻めを打開するため、毛利氏が兵糧輸送を敢行した際に発生した海戦である。この戦いで、毛利方に与した村上水軍は、その戦闘能力の真価を天下に示した。
九鬼嘉隆率いる織田水軍に対し、村上水軍は得意の焙烙火矢を駆使した火攻め戦術を展開 17 。焙烙火矢の雨を浴びた織田方の安宅船は次々と炎上し、船団は壊滅的な打撃を受けて敗走した 16 。この勝利により、石山本願寺への兵糧搬入は成功し、信長の戦略は大きく頓挫した。これは、伝統的な水軍戦法がその頂点に達した瞬間であった。
4.3. 第二次木津川口の戦い(天正六年、1578年)
第一次の惨敗に衝撃を受けた織田信長は、九鬼嘉隆に命じて村上水軍の火攻めへの対策を徹底的に講じさせた。その結果として生まれたのが、船体の主要部を厚さ3ミリメートルの鉄板で覆った、6隻の巨大軍船「鉄甲船」であった 2 。
二年後、再び木津川口で両軍は激突する。村上水軍は前回同様、焙烙火矢による攻撃を仕掛けたが、鉄甲船には全く通用しなかった。火矢は鉄板に弾かれ、投げ込まれた焙烙も船上で燃え広がる前に消し止められてしまった 39 。逆に、鉄甲船に搭載された大砲や多数の鉄砲による圧倒的な火力の前に、村上水軍の小早や関船は次々と撃ち破られ、大敗を喫した 2 。
木津川口における二度の海戦は、戦国時代の「戦術」と「技術」の相互作用を象徴する劇的な事例である。第一次では村上水軍の伝統的な「戦術(火攻め)」が勝利し、第二次ではそれに対抗するために生まれた織田方の革新的な「技術(鉄甲船)」が勝利を収めた。これは、一つの戦術的優位性が永続するものではなく、常に対抗策(カウンター)を生み出し、新たな軍事パラダイムを創出するという、軍事史における普遍的な法則を如実に示している。
第五部:水軍戦法の遺産 ― 近代海軍への影響
5.1. 海賊禁止令と船手衆への再編
豊臣秀吉による天下統一事業が進展する中、天正十六年(1588年)、全国に「海賊禁止令」が発布された 6 。これは、大名の支配下にない海上武装勢力の存在を禁じ、海上交通の支配権を中央集権体制の下に置くことを目的としたものであった。これにより、村上水軍のような独立勢力としての「海賊衆」は歴史の表舞台から姿を消し、各大名に仕える正規の海上戦力「船手衆(ふなてしゅう)」へと再編成されていった 3 。これは、中世以来続いてきた独立海洋国家の時代の終わりを意味する、歴史的な転換点であった。
5.2. 秋山真之と日本海海戦
村上水軍が歴史の表舞台から去って約300年後、彼らの兵法思想が思わぬ形で再び脚光を浴びることになる。時代は明治、日露戦争の雌雄を決した日本海海戦において、連合艦隊の作戦を立案した天才参謀・秋山真之は、作戦研究に行き詰まった際、村上水軍の兵法書、特に『能島流海賊古法』という写本を取り寄せて研究したと伝えられている 40 。
能島流の兵法には、「敵の先頭に立つ一艘に、味方の数艘が攻めかかり、やにわにそれを撃ち破るべし」という思想があった 25 。これは、戦力を一点に集中させ、敵の最も脆弱な部分を叩くという「戦力集中の原則」である。この思想は、秋山が考案し、東郷平八郎司令長官が決断した「丁字戦法(T字戦法)」と軌を一にする。丁字戦法とは、敵艦隊の進路を自艦隊が横切る形で占位し、味方全艦の側面火力を敵の先頭艦に集中させて、各個撃破を狙うものであった 24 。
村上水軍の陣形や戦法と、近代海軍の丁字戦法の間には、もちろん焙烙火矢と弩級戦艦の主砲という圧倒的な技術的断絶が存在する。しかし、その根底には「敵の戦力を分断し、自軍の火力を一点に集中させて局所的優位を確立する」という、時代を超える普遍的な戦術思想の連続性を見出すことができる。秋山真之が、先人の知恵の中に海戦の本質を見出し、それを近代兵器の運用に昇華させたことは、村上水軍の遺産が日本の歴史に与えた影響の大きさを物語っている。
結論
本報告書で詳述した通り、「水軍戦法要領」は、単なる一枚の図や一冊の書物ではなく、村上水軍が瀬戸内海の過酷な自然環境と激動の時代の中で培った、合理的かつ実践的な海戦術と思想の集大成である「能島流」兵法の精髄を象徴するものである。
彼らの強さの源泉は、鶴翼や魚鱗といった個々の陣形、焙烙火矢という特異な兵器にのみ求められるべきではない。それは、激しい潮流を読み切る卓越した航海術、海上交通を支配することで成立した強固な経済力、そして大大名間の力学を巧みに利用する高度な戦略眼が一体となった、総合的な「システム」にあった。
そして、その戦術思想、特に「火力の集中」という普遍的原則は、戦国時代の終焉と共に完全に消え去ったわけではなかった。それは兵法書の中に息づき、時代を超えて受け継がれ、近代日本の存亡をかけた日本海海戦において、再びその輝きを放ったのである。村上水軍が残した知恵と戦法の遺産は、日本の海戦史、ひいては世界の海戦史においても、不滅の足跡を刻んでいると言えよう。
引用文献
- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html
- 水軍の将ベスト5 勇猛果敢な海の武将たち - YouTube https://m.youtube.com/live/EudQkVAKle0
- 第41 回 日本泳法研究会資料 http://navykuro.html.xdomain.jp/z103hamasui/nojima1.pdf
- 安芸国 賀茂 郡 風早村 能島家 文書 仮目録 - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/mokuroku/199606nojima.pdf
- (3)水軍戦法の諸流派 http://navykuro.html.xdomain.jp/z103hamasui/hamasuihome/23suigunsenpou.htm
- 日本の海賊【村上水軍】の歴史やライバルに迫る! 関連観光スポットも紹介 - THE GATE https://thegate12.com/jp/article/494
- 瀬戸内海に見る村上水軍の歴史的役割 - IMG2PDF document https://cres.hiroshima-u.ac.jp/06-kichoukouen.pdf
- 村上海賊と大山祇神社|ISSA - note https://note.com/msdf_issa/n/n5010eed42c5c
- 【やさしい歴史用語解説】「水軍」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1590
- 潮の流れを味方にした村上海賊! - 放送内容|所さんの目がテン!|日本テレビ https://www.ntv.co.jp/megaten/oa/20180617.html
- 芸予諸島 -よみがえる村上海賊 “Murakami KAIZOKU” の記憶-|日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/129/
- 村上海賊ミュージアム|愛媛のスポット・体験 https://www.iyokannet.jp/spot/212
- 九鬼嘉隆と鳥羽湊 http://v-rise.world.coocan.jp/rekisan/htdocs/ryokoindex/iseshima/toba.htm
- 天下人に重宝され一財を築いた「塩飽水軍」の実力|Biz Clip(ビズクリップ)-読む・知る・活かす https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-100.html
- 近世における水陸両用作戦について - 1592年の文禄 (朝鮮)の役を例として https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2013_12_07.pdf
- [合戦解説] 5分でわかる木津川口の戦い 「毛利水軍の焙烙火矢に敗北した信長は巨大鉄甲船で立ち向かう」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=tCpQZIc-N5I&pp=ygUKI-mJhOeUsuiIuQ%3D%3D
- 第一次木津川口の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 海賊が最強艦隊に?知られざる戦国時代の海上戦と英雄たち | レキシノオト https://rekishinote.com/naval-battle/
- 【写真】これが李舜臣将軍の鶴翼陣 | Joongang Ilbo - 中央日報 - 중앙일보 https://s.japanese.joins.com/JArticle/90198?sectcode=400&servcode=400
- 村上海賊 - 日本海難防止協会 https://www.nikkaibo.or.jp/pdf/592_2022-2.pdf
- 「鶴翼の陣」で尹氏弾劾 韓国左派 総選挙で戦術示す - 世界日報DIGITAL https://www.worldtimes.co.jp/global/korean-peninsula/20240422-180772/
- 「魚鱗の陣」と「鶴翼の陣」で集客しよう|売れるネットショップ運営のコツ20 | コマースデザイン https://www.commerce-design.net/knowhow/column/netshop-column-20/
- 鶴翼の陣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E7%BF%BC%E3%81%AE%E9%99%A3
- 秋山真之-丁字戦法 - WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/1899180/
- 秋山真之 - 白砂糖と黒砂糖 - 坂の上の雲 http://www.sakanouenokumo.com/saneyuki_denki8_13.htm
- 戦国の陣形、八陣とは? - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2024/07/28/hachijin/
- 八陣を現代ビジネス戦略に活かす:三方ヶ原の戦いと「どうする家康」|経営グロースハッカー - note https://note.com/starly/n/nab16ef74a66d
- 戦国時代の合戦の基本陣形について | ミリタリーショップ レプマート https://repmart.jp/blog/formation-2/
- 合戦の陣形「八陣」について|刀箱師の日本刀ブログ 中村圭佑 - note https://note.com/katana_case_shi/n/n36fc081db66e
- 武田信玄の戦国八陣/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18700/
- 陣形 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A3%E5%BD%A2
- 「魚鱗の陣」や「鶴翼の陣」とは?|三方ヶ原の戦いで家康・信玄が使った陣立【戦国ことば解説】 https://serai.jp/hobby/1125778
- 孫子に学ぶ、景気の潮目が変わった時の経営とマネジメント戦略の切り替え方(鶴翼 魚鱗 方円 の3つの陣形でシンプルにご説明します - note https://note.com/yasutasukeya/n/nb4a1d7216415
- 激闘!海の奇襲戦「厳島の戦い」~ 勝因は村上水軍の戦術 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11740
- 「村上武吉」 毛利水軍の一翼を担った、村上水軍当主の生涯とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1187
- 第47回 織田水軍 最強伝説!鉄甲船の謎 - BS11 https://www.bs11.jp/lineup/2019/08/post-8748.html
- 信長の鉄甲船 https://www2.memenet.or.jp/kinugawa/ship/2300.htm
- 鉄甲船伝説 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/koramu/koramu-tekkousen.htm
- 燃えない甲鉄船で毛利船団を殲滅! 九鬼嘉隆は日本一の海賊大名と呼ばれたが… - 歴史人 https://www.rekishijin.com/18021
- 頼朝聖観音 https://j-reimei.com/kanon.htm
- 秋山真之の“参謀たるの心構え”とは? https://wedge.ismedia.jp/articles/-/657?layout=b