神伝忍術秘書
甲賀忍術の『神伝忍術秘書』は呪術的伝承群。地侍連合と修験道が背景。九字護身法など精神操作を重視し、一子相伝を否定し共同体維持と術の進化を図った。
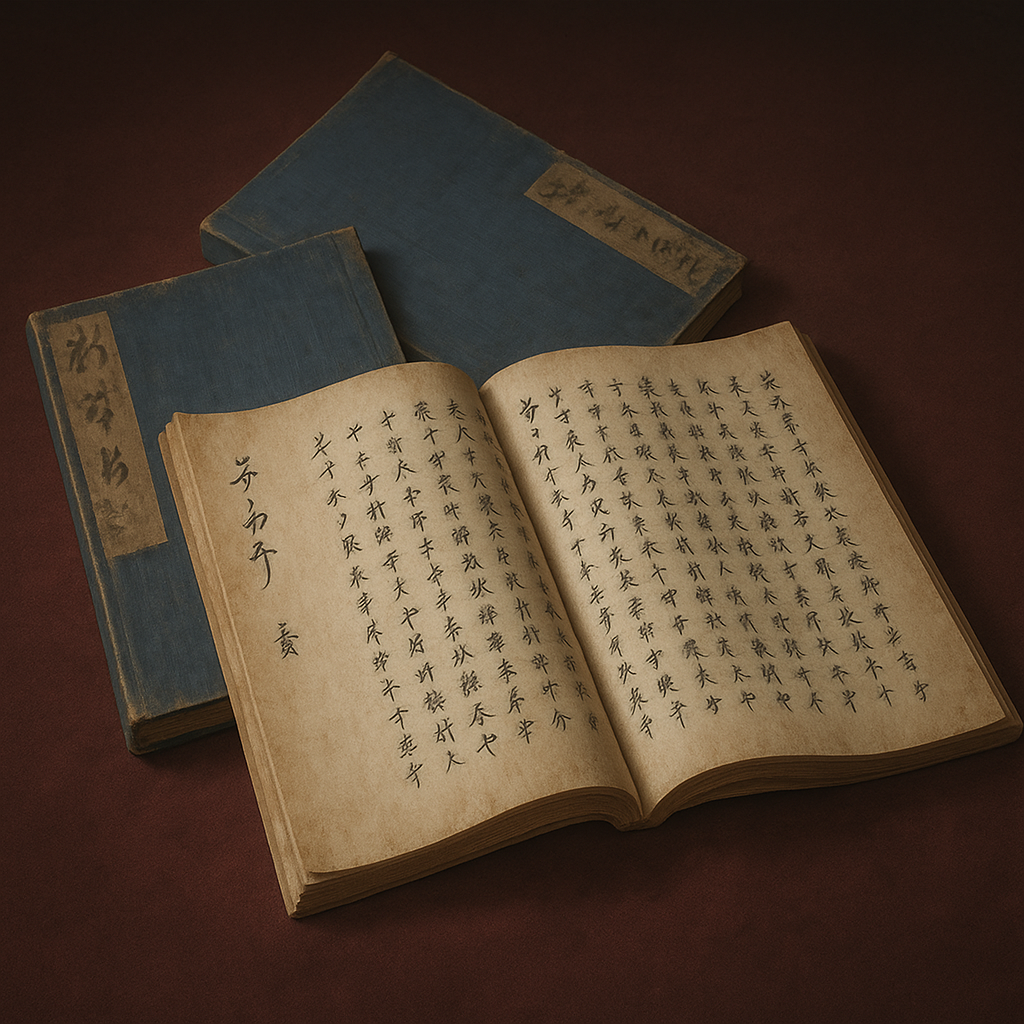
『神伝忍術秘書』の総合的研究―戦国期甲賀忍術における呪術と思想の深層―
序論:『神伝忍術秘書』を巡る謎と研究の現在地
甲賀流に伝わるとされる忍術伝書『神伝忍術秘書』。その名は、忍術に関心を寄せる者にとって、ある種の神秘的な響きを伴って知られている。作者不詳、成立年代不詳、その内容の多くは呪術的な要素に占められ、かつ「一子相伝も許されぬ」という特異な伝承形態を持つ、という断片的な情報は、この伝書の謎を一層深めてきた。本報告書は、これらの既知の概要を遥かに超え、『神伝忍術秘書』の実体、その思想的背景、そして日本の戦国時代という特異な時代が生んだ歴史的意義を、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。
近年の忍者研究は、三重大学国際忍者研究センターの設立や、山田雄司教授をはじめとする研究者たちの精力的な活動により、従来の大衆文化における創作上の忍者像から、史料に基づいた「忍び」の実像を解明する学術的領域へと大きな変貌を遂げている 1 。本報告書もまた、この学術的潮流の上に立ち、特に『神伝忍術秘書』が重視するとされる「呪術」の側面を、単なる迷信やオカルトとしてではなく、戦国武士の精神文化史、兵法思想、そして実践的な心理操作術という観点から再評価を試みるものである。
この探求を進めるにあたり、我々はいくつかの核心的な問いを立てる。第一に、なぜ甲賀の地で、その起源を「神伝」、すなわち神代に求める伝書が生まれ、また必要とされたのか。第二に、江戸時代に編纂された『萬川集海』のような実践的技術の集大成とは一線を画し、なぜ本書は呪術をその核に据えたのか。そして第三に、「一子相伝も許されぬ」という、他の武芸流派とは著しく異なる伝承の掟は何を意味するのか。これらの問いへの答えを探ることこそ、『神伝忍術秘書』という謎多き存在を通じて、戦国期甲賀忍術の深層に横たわる思想そのものを理解する鍵となると確信する。本報告書は、この伝承を単一の書物としてではなく、甲賀という土地の歴史と精神が生んだ「伝承群」として捉え直し、その本質に迫るものである。
第一章:甲賀という土壌―忍術伝書が生まれる歴史的・地理的背景
『神伝忍術秘書』のような特異な思想を持つ伝承が生まれた背景を理解するためには、まずその土壌となった甲賀という地域の歴史的・地理的特性を深く考察する必要がある。甲賀の地は、単なる一地方ではなく、戦国時代において独自の社会構造と精神文化を育んだ稀有な空間であった。
甲賀郡中惣と地侍の自立
戦国期の甲賀は、特定の戦国大名による一元的な支配を受けず、「甲賀郡中惣(こうかぐんちゅうそう)」と呼ばれる地侍たちの連合体によって、一種の自治が行われていたことで知られる 4 。これは、中央集権的な支配構造とは対極にある、水平的な協力と合議に基づく共同体であった。この自立と連帯の精神こそが、後に「甲賀衆」や「甲賀者」として知られる忍者集団の独特な組織形態と行動原理の基盤を形成した。彼らの集団としての実力は、長享元年(1487年)に六角氏と足利義尚が争った「鈎(まがり)の陣」において、ゲリラ戦や夜襲を駆使して幕府軍を苦しめたことで天下に示された 5 。個々の戦闘技術だけでなく、この「惣」という共同体をいかに維持し、その力を結集させるかという課題が、甲賀独自の技術と思想、そして規範を生み出す土壌となったのである。
この甲賀の社会構造は、忍術の伝承形態に決定的な影響を与えたと考えられる。強力な権威を持つ特定の家や個人が、秘術を独占し、それを血縁によって継承していくことは、地侍たちの水平的な連合という「惣」のパワーバランスを根底から覆しかねない危険性を孕んでいた。後述する『神伝忍術秘書』の「一子相伝の否定」という思想は、まさにこの共同体の構造を反映したものである可能性が高い。それは、知識や技術を特定の血筋に集中させることを防ぎ、術を「惣」全体の共有財産、あるいは誰も私有できない神聖な領域とすることで、共同体の結束を維持するための、極めて高度な社会的安全装置として機能したと解釈できるのである。
修験道と密教の聖地として
甲賀の精神文化を語る上で、宗教的背景は不可欠である。この地域には、古くから修験道の一大霊場である飯道山(はんどうさん)が存在し、山伏たちの活動が非常に盛んであった 6 。忍術における精神的な支柱、呼吸法や身体操作の技法、そして本書の核となる呪術の多くは、この山岳修行を通じて培われた修験道にその源流を見出すことができる 7 。
手で印を結び(印相)、口で真言を唱えるといった忍者の象徴的な行為は、密教や修験道の儀軌(ぎき)が直接的な源泉である 9 。甲賀は天台密教の布教拠点でもあり、忍術と密教は深く結びついていた 9 。『神伝忍術秘書』が色濃く反映する呪術性は、決して突飛なものではなく、この地域の宗教的風土と分かちがたく結びついた、必然的な帰結であった。忍者は、山に籠もり厳しい修行を行う修験者から、自然の力を引き出し、極限状況を生き抜くための術を学んだのである 7 。
薬学と実利の精神
一方で、甲賀忍術は神秘性や精神性のみに偏っていたわけではない。彼らは薬学に精通し、日常的には薬売りとして諸国を巡り、その過程で情報収集を行っていたとされる 12 。甲賀地方に現在も製薬会社が多いのは、その名残である 12 。この事実は、彼らが極めて実利的かつ現実的な側面を持ち合わせていたことを示している。神仏の力を信奉し、呪術を実践する精神性と、薬草の効能を見極め、それを生業とする科学的・実利的な精神。この一見矛盾する二つの要素が、甲賀忍者という存在の中で複雑に融合していた。この現実的な技術と呪術的な精神性の共存こそが、甲賀忍術の多層的な性格を形成しており、『神伝忍術秘書』を理解する上での重要な視点となる。
第二章:『神伝忍術秘書』の正体―伝承と現存史料からの考察
『神伝忍術秘書』という名称は広く知られているものの、その実体は多くの謎に包まれている。単一の書物として存在するのか、あるいはより広範な概念を指すのか。本章では、関連する史料や伝承を基に、その正体に迫る。
「神伝」という権威付け
本書がその名を「神伝」と称することは、極めて重要な意味を持つ。いくつかの伝承によれば、その起源は神代にまで遡り、大己貴命(おおなむちのみこと、大国主命の別名)や少彦名命(すくなひこなのみこと)、あるいは素戔鳴尊(すさのおのみこと)に求められるという 14 。これは、甲賀の忍術を単なる人間の技術(人術)の範疇に留めず、神々から直接授けられた神聖な術であると位置づけるための、壮大な「創始神話」に他ならない。
このような神話的な権威付けは、他の武芸流派においても、流派の正当性と超越性を確立するためにしばしば用いられた手法である。術の起源を神仏に結びつけることで、その効能に対する絶対的な信頼性を修行者に与え、同時に、他流派に対する優位性を主張する効果があった。特に、生死の境をさまよう実戦の場で活動する忍者にとって、自らの術が神聖なものであるという信念は、恐怖を克服し、任務を遂行するための強力な精神的支柱となったであろう。
書物か、伝承群か
『神伝忍術秘書』という名の、完結した単一の書物が現存するという確固たる証拠は、現在のところ見つかっていない。むしろ、甲賀に伝わる複数の伝書、例えば『甲賀古流武門必要神秘忍術』 14 や、甲賀五十三家の一つである頓宮家に伝わった『忍術秘書応義伝之巻』 15 などに共通して見られる、神話と呪術を最重要視する思想体系、あるいはそれらの伝承群の総称こそが『神伝忍術秘書』の実体であると考えるのが、より妥当な解釈であろう。
滋賀県甲賀市にある甲賀流忍術屋敷には、甲賀忍術の奥義を記したとされる『甲賀流伝書』(虎の巻)が展示されているが 5 、これもまた、この広範な伝承群の一部と見なすことができる。これらの伝書や伝承は、個別の書物としてよりも、甲賀忍術の根底に流れる一つの大きな思想的潮流として捉えるべきなのである。
この『神伝忍術秘書』の特異性をより明確にするため、他の主要な忍術伝書との比較を行うことは極めて有益である。以下の表は、各伝書の特色を整理したものである。
|
伝書名 |
主な伝承流派 |
推定成立年代 |
呪術的要素 |
内容の特色と備考 |
関連史料 |
|
神伝忍術秘書(伝承群) |
甲賀流 |
不詳 |
極めて多い |
神話に起源を求め、呪術を重視。一子相伝を許さないなど特異な伝承形態を持つ。特定の書物ではなく思想体系の可能性。 |
14 |
|
萬川集海(まんせんしゅうかい) |
伊賀・甲賀流 |
江戸時代(1676年) |
意図的に排除 |
伊賀甲賀四十九流を集大成した百科事典的伝書。実践的な技術・道具論が中心。泰平の世における技術保存と体系化が目的。 |
17 |
|
正忍記(しょうにんき) |
紀州流 |
江戸時代(1681年) |
比較的少ない |
忍びの精神論、情報収集、変装術に重点。実践的かつ哲学的な内容で、武士の心得としての側面も持つ。 |
20 |
|
忍秘伝(にんぴでん) |
伊賀・甲賀流 |
不詳 |
含まれる |
服部半蔵著と伝わる。伊賀・甲賀の術を記すとされるが、その実体は謎に包まれている部分が多い。 |
20 |
|
間林清陽(かんりんせいよう) |
伊賀・甲賀流 |
不詳(江戸前期か) |
要分析 |
『萬川集海』の原典とされる幻の忍術書。近年、甲賀市で写本が発見され、今後の研究が待たれる。 |
23 |
|
老談集(ろうだんしゅう) |
甲賀流 |
江戸時代(1845年写) |
少ない(実用寄り) |
『甲賀流忍法伝書老談集』とも。武田信玄の軍師山本勘助らの秘伝と称す。馬術や兵糧丸の製法など実用的な内容が多い。 |
19 |
この比較から浮き彫りになるのは、『神伝忍術秘書』と、忍術書の代名詞ともいえる『萬川集海』との思想的な対立である。『萬川集海』は、1676年(延宝4年)という江戸幕府の体制が安定し、儒教的合理主義が重んじられ始めた時代に編纂された 17 。編者である藤林保武は、伊賀・甲賀四十九流の忍術を「すべての川が海に集まるように」集大成しようとしたが、その過程で、忍術の根幹をなすはずの呪術に関する記述を意図的に排除したと指摘されている 18 。これは単なる編集方針の違いではない。忍術を兵法の一分野として客観的かつ網羅的に記述し、後世に「学問」として伝えようとする藤林にとって、神話や呪術といった非合理的な要素は、体系化の妨げとなる「前近代的」なものと映った可能性がある。
これに対し、『神伝忍術秘書』が象徴する伝承は、神仏の加護や呪いの力を現実的なものとして信じていた、戦国時代の混沌とした世界観を色濃く残している。したがって、両者の違いは「古いか新しいか」という単純な問題ではなく、「忍術の本質をどこに求めるか」という、より根本的な哲学的問いに対する二つの異なる回答と見なすことができる。『萬川集海』が忍術を「技術の体系」として捉えたのに対し、『神伝忍術秘書』はそれを「心身一如の神聖な術」として捉え続けた。この思想的相克こそが、近世における忍術の多様性と複雑性を象徴しているのである。
第三章:呪術と忍術―『神伝忍術秘書』の思想的核
『神伝忍術秘書』が他の忍術伝書と一線を画す最大の要因は、その思想の中核に「呪術」を据えている点にある。ここでいう呪術とは、単なる非科学的な迷信ではなく、極限状況を生き抜くための精神操作技術であり、敵を欺き、味方を鼓舞するための高度な心理戦術であった。
九字護身法(くじごしんほう)の実践と意味
忍術における呪術の代表格として、九字護身法が挙げられる。「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前(りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん)」の九つの文字を唱えながら、両手で複雑な印(印相)を結び、最後に刀に見立てた指で空間を九文字に切り裂く 26 。この儀式は、中国の道教にその源流を持ち、日本へ伝来した後に密教や修験道に取り入れられ、独自の発展を遂げたものである 8 。
その目的は、単なる気休めや神頼みではなかった。敵地に潜入する際や、強大な敵と対峙する際など、極度の緊張と恐怖に晒される状況において、この儀式的な所作を正確に行うこと自体が、精神を統一し、雑念を払い、冷静さを取り戻すための強力な手段となった。これは、自己暗示によって自らの身体能力を最大限に引き出すための心理的技法であり、現代のスポーツ心理学においてトップアスリートが試合前に行うルーティンや、特定の動作で精神状態を切り替えるアンカリングの概念にも通じる、極めて実践的な効果を狙ったものであったと考えられる。
呪術の多様性―精神操作から幻術まで
忍術における呪術の範囲は、九字のような自己の精神を対象とするものに留まらない。例えば、甲賀忍者が得意としたとされる「手妻(てづま)」は、現代でいう手品や奇術のように、素早い手の動きや巧みな話術で人の注意を逸らし、人心を惑わす術であった 13 。また、伊賀には京都からの亡命者によって呪術や奇術がもたらされ、発展したという伝承もある 28 。
これらの技術は、物理的な戦闘力に頼るのではなく、敵の認知を歪め、心理を操り、情報を攪乱することによって、戦わずして目的を達成するという、忍術の本質的な側面を体現している。火薬を用いて煙幕を張り、敵の視界を奪って姿をくらます「火術」も 28 、物理的な効果と心理的な効果を組み合わせた、広義の呪術的技法と見なすことができるだろう。これらはすべて、人間の知覚や心理の隙を突くという点で共通しており、『神伝忍術秘書』が重視した呪術とは、こうした広範な心理操作技術の総称であった可能性が高い。
口伝の重要性
多くの忍術伝書、特に『萬川集海』などには、「口伝あり」という記述が頻繁に見られる 18 。これは、術の真髄や奥義が、文字情報だけでは決して伝達しきれない深遠なものであることを示唆している。特に呪術においては、この傾向が顕著であったと考えられる。印の結び方の微細な角度や力加減、真言の正確な発声法、術と連動させるべき呼吸法、そして何よりも精神集中の具体的な要諦といった事柄は、師から弟子へと、対面で直接的に伝授されるべき「秘中の秘」とされていた。
文字に記された情報は、あくまで術の骨格に過ぎない。その術に生命を吹き込む魂は、口伝によってのみ受け継がれる。呪術を最重要視する『神伝忍術秘書』の伝承群において、その核心部分の多くが文字として記録されることなく、師資相承の口伝によってのみ伝えられてきたことは想像に難くない。このことが、現存する史料からその全体像を掴むことを一層困難にしている一因でもある。
第四章:「一子相伝も許されぬ」―伝承の断絶と流派の権威
『神伝忍術秘書』を巡る謎の中で、最も特異で示唆に富むのが、「一子相伝も許されぬ」という掟の存在である。これは、自らの流派の血統や正統性を何よりも重んじ、系図や免許皆伝といった形でその権威を継承しようとした戦国から江戸時代の多くの武芸流派とは、全く逆の方向を向いた思想である。この不可解な掟の背後には、甲賀という共同体の特殊なあり方と、忍術そのものに対する深い洞察が隠されている。
掟の多角的解釈
この特異な掟は、単一の理由からではなく、複数の意図が複合的に絡み合って生まれたものと推察される。
第一に、 共同体維持説 である。第一章で詳述したように、甲賀は地侍たちの連合体「惣」によって治められていた。このような水平的な社会において、特定の家系が「神伝」という絶大な権威を持つ秘術を独占することは、共同体内に深刻な亀裂を生み、内部対立の火種となりかねない。したがって、「一子相伝の否定」は、術を特定の個人の私有物とすることを禁じ、それを共同体全体の、あるいは神仏に属するものと位置づけることで、組織の結束と秩序を維持するための、極めて政治的な社会規範であった可能性が最も高い。
第二に、 術の陳腐化防止説 が考えられる。いかなる優れた術も、一人の人間や一つの家系に固定化され、その型が絶対視されるようになると、応用や発展が止まり、やがては形骸化してしまう危険性がある。あえて特定の継承者を定めず、術をいわば「オープンソース」の状態に置くことで、術が常に流動的であり続け、時代の変化や状況に応じて進化し続ける「生きた術」であることを目指したのかもしれない。
第三に、 神聖性の担保説 である。「神伝」の術は、そもそも人間ごときが私有し、子孫に相続させることなどおこがましい、という宗教的な思想の表れである可能性も否定できない。術の所有権を人間が放棄し、その源泉である神仏に常に返し続けるという謙虚な姿勢こそが、術の神聖性を保ち、その力を引き出すために不可欠だと考えられていたのかもしれない。
武芸流派の伝承形態との比較
この伝承形態の特異性は、他の武芸流派と比較することで一層際立つ。例えば、剣術の新陰流や柳生新陰流、あるいは柔術の竹内流など、多くの著名な流派は、流祖から代々の宗家へと血縁や高弟への一子相伝を基本とし、その系譜を記した巻物や免許状によって、流派の正統性と権威を証明してきた。これは、泰平の世となった江戸時代において、武芸が藩に仕えるための「商品」としての価値を持つようになり、そのブランド価値を保証するシステムが必要とされたからでもある。
しかし、『神伝忍術秘書』の掟は、こうした権威主義的なあり方を明確に否定する。これは、甲賀の忍術が、個人の立身出世の道具や、家名を高めるための手段としてではなく、あくまで「惣」という共同体を守るための公的な術として認識されていたことを強く示唆している。この掟は、単なる技術伝承の方法論ではなく、甲賀という共同体の理念そのものと深く結びついた、一種の「共同体憲章」のような性格を帯びていたのである。
第五章:戦国時代の「忍び」と江戸時代の「忍者」―伝書の役割の変容
忍術伝書の性格や役割は、時代と共に大きく変容した。『神伝忍術秘書』が象徴する思想の歴史的役割を理解するためには、戦乱の世の「忍び」と、泰平の世の「忍者」との違いを認識し、その中で伝書が果たした機能の変化を追う必要がある。
実戦の「術」から泰平の「術」へ
戦国時代、彼らは「忍者」ではなく「忍び(しのび)」と呼ばれていた 30 。彼らの技術は、諜報、潜入、破壊工作、奇襲といった、明日をも知れぬ実戦の中で磨かれた、文字通り生き残るための「術(すべ)」であった。この段階では、洗練された理論体系や長大な伝書よりも、即応性、実用性、そして何よりも結果を出すことが最優先された。知識の伝承は、戦場や修行の場における口伝や実地訓練が中心であり、体系的な書物の価値は低かったと考えられる 18 。
しかし、関ヶ原の戦いを経て徳川の世となり、大規模な戦闘が終息すると、「忍び」の役割も大きく変化する。彼らは大名家に召し抱えられ、城下の警備や国内情報の収集といった、より限定的で定常的な任務に就くようになる 32 。この過程で、彼らの技術は「忍術」として体系化され、流派の権威付けや後進の育成、そして何よりも技術の散逸を防ぐ目的で、伝書が盛んに編纂されるようになった。江戸時代中期に成立した『萬川集海』や『正忍記』は、まさにこの時代の要請が生んだ代表的な産物である 17 。これらの伝書は、実戦の知恵を、後世に伝え得る客観的な知識へと変換する試みであった。
『神伝忍術秘書』の歴史的役割
この歴史的な変容の中で、『神伝忍術秘書』が象徴する呪術的・精神主義的な伝承は、どのような役割を果たしたのだろうか。それは、忍術の「原点」や「精神的支柱」としての役割であったと推察される。
技術が合理化・体系化され、『萬川集海』のように呪術的要素が意図的に排除されていく中で、忍術は単なるスパイ技術や戦闘技術の集合体に矮小化されてしまう危険性があった。そのような時代にあって、『神伝忍術秘書』の伝承は、失われがちな神仏との繋がりや、極限状況を乗り越えるための超合理的な精神の術の重要性を、頑なに説き続けたのではないだろうか。それは、忍術が単なる技術論に堕することを防ぎ、その深みと神秘性、そして何よりも術者の精神性を問うという本質を保持するための、いわば忍術における「保守本流」の思想であったと言えるかもしれない。技術が「術(じゅつ)」から「道(どう)」へと昇華していく他の武芸と同じように、この伝承は忍術がその魂を失わないための、最後の砦としての役割を担っていたのである。
結論:『神伝忍術秘書』が現代に問いかけるもの
本報告書を通じて行ってきた多角的な分析の結果、『神伝忍術秘書』は、特定の完結した一冊の書物を指すのではなく、戦国期甲賀の地に根差した、神道・仏教・修験道が融合した神仏習合的な精神文化と、それを核とする呪術的技法群の総称、あるいはその伝承体系そのものであると結論づけることができる。それは、戦国乱世の混沌の中から生まれ、泰平の江戸時代において合理化・体系化されていく忍術とは明確に一線を画し、術の根源的な神聖性と精神性を守り続けようとした、思想の結晶であった。
特に「一子相伝も許されぬ」という特異な掟は、単なる秘匿の規則ではなく、甲賀郡中惣という水平的な共同体の社会構造と不可分であり、知識の独占を防ぎ、共同体の結束を維持するための、極めて高度で洗練された社会的知恵であったと再評価できる。それは、術を個人の所有物とせず、常に共同体と、その上位にある神仏へと開き続けるという、甲賀忍術の公的な性格を象徴している。
この古の伝承が、現代に問いかけるものは決して少なくない。『神伝忍術秘書』が重視した呪術は、現代的な視点から再解釈すれば、極限状況における心理コントロール術であり、集中力を飛躍的に高めるための技法として、その有効性を見出すことができる 33 。その精神性と実践的な知恵は、大規模災害への備えや、ストレスに満ちた現代社会における危機管理など、我々が直面する様々な課題に応用可能な、普遍的な示唆を含んでいる。忍術とは「総合的な生活術・生存術」だったのである 33 。
今後の展望として、近年その存在が確認された幻の忍術書『間林清陽(かんりんせいよう)』の研究が待たれる 24 。『萬川集海』の原典とされるこの書物の解読が進むことで、江戸初期における忍術思想の全体像、特に技術の体系化のプロセスがより明確になるであろう。その研究成果と、本報告書で論じてきた『神伝忍術秘書』が象徴する呪術的・精神主義的な伝承とを比較検討すること。それこそが、合理と非合理、技術と精神という、忍術が内包する二つの極を架橋し、その真の姿を解明するための、次なる重要な一歩となるに違いない。
引用文献
- 三重大学国際忍者研究センター センター員 酒井裕太さん | 伊賀人バンザイ! https://www.igaportal.co.jp/igabito/28943
- 山田雄司 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%9B%84%E5%8F%B8
- 忍者学大全 - 山田雄司, 三重大学国際忍者研究センター - Google Books https://books.google.com/books/about/%E5%BF%8D%E8%80%85%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%85%A8.html?id=7o3cEAAAQBAJ
- 全国の忍術流派 http://www.eonet.ne.jp/~bankeshinobi/ryugi.html
- 甲賀流忍術屋敷(甲賀市・旧甲南町) | おすすめスポット - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/779899/
- 忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA-INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/
- 『忍者学大全』はじめに|東京大学出版会 - note https://note.com/utpress/n/neec99a076deb
- 忍者とは何か? – 忍者の里 伊賀市公式観光案内 - IGA Official Travel Guide https://www.iga-travel.jp/ja/?page_id=10
- 知られざる忍者の世界 https://www.kepco.co.jp/corporate/report/yaku/32/pdf/yaku32_P25_28.pdf
- 平安朝・源平期を経て 鎌倉期までの忍術の変遷 - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2018/10/171-rekishi-1.pdf
- 九字印・「闘」・ 外獅子印 by FuturEvoLab | Suno https://suno.com/song/9083dccd-1f02-4f44-9592-1a58a60573ea
- 甲賀流忍術屋敷 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E6%B5%81%E5%BF%8D%E8%A1%93%E5%B1%8B%E6%95%B7
- 平成芭蕉の日本遺産 忍びの里 伊賀・甲賀のリアル忍者Real Ninja https://nihonisankentei.com/chugoku/shinobinosatoigakoga/
- 忍術・忍者の起源と発達 - 大陸よりの伝来説・・・・ 武経七書の間諜 https://www.city.iga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8887/kawakami.pdf
- 忍術秘書応義伝之巻 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%BF%8D%E8%A1%93%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E4%BC%9D%E4%B9%8B%E5%B7%BB
- 甲賀流忍術屋敷 - スポット詳細 | KANSAI MaaS https://app.kansai-maas.jp/spots/13045
- 萬川集海(まんせんしゅうかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%90%AC%E5%B7%9D%E9%9B%86%E6%B5%B7-1596669
- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/bou/bou/kemuri/8.html
- 伊 賀 と 忍 者 - 三重大学附属図書館 https://www.lib.mie-u.ac.jp/tenji201906.pdf
- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://iganinja.jp/2007/12/post-39.html
- 忍者の教科書2 新萬川集海 | 書籍検索 http://shop.kasamashoin.jp/bd/isbn/9784305707680/
- 伊賀流(いがりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%B5%81-201767
- 忍術書「間林清陽」が発見されました! - 甲賀市 https://www.city.koka.lg.jp/21508.htm
- 「忍び込むなら子の刻」“幻”の忍術書の写本を甲賀市で発見…どんな秘伝があったのか発見者に聞いた - FNNプライムオンライン https://www.fnn.jp/articles/-/379427?display=full
- 【甲州流忍法伝書老談集】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/iga-city/catalog/mp000060-100020
- 忍者とは?本来の役割や歴史に迫る。日本で最も有名な忍者は?忍術を体験できる場所もご紹介! | 株式会社アミナコレクション https://aminaflyers.amina-co.jp/list/detail/1515
- 不動明王-真佛宗TBSN https://ch.tbsn.org/master/detail/22/Acala.html
- これを読めばわかる!忍者【伊賀流と甲賀流】の違い - THE GATE https://thegate12.com/jp/article/154
- 忍術、忍者とは | 伊賀流忍者屋敷と忍者博物館 https://www.iganinja.jp/ninja/ninja/index.html
- 忍びの里 甲賀へようこそ https://www.city.koka.lg.jp/10977.htm
- 忍者 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E8%80%85
- 忍者の歴史/著者:山田 雄司(KADOKAWA) - 電子文庫パブリ https://www.paburi.com/android/bin/product.asp?pfid=29126%2D122147499%2D001%2D001
- 三重大Rナビ -三重大学の研究最前線- | 災害を含む自然との共生と忍者・忍術学 https://www.mie-u.ac.jp/R-navi/column/cat455/post-9.html
- 第6回 『忍者はすごかった‒忍術書81の謎を解く‒』 - 伊賀ポータル https://www.igaportal.co.jp/ninja/1687