都のつと
『都のつと』は南北朝期の僧・宗久による紀行文。観応の擾乱下の旅で無常観を深め、古典に精神的拠り所を求めた。戦国時代との比較で、中世から近世への社会変容と旅の意味の変遷を映し出す。
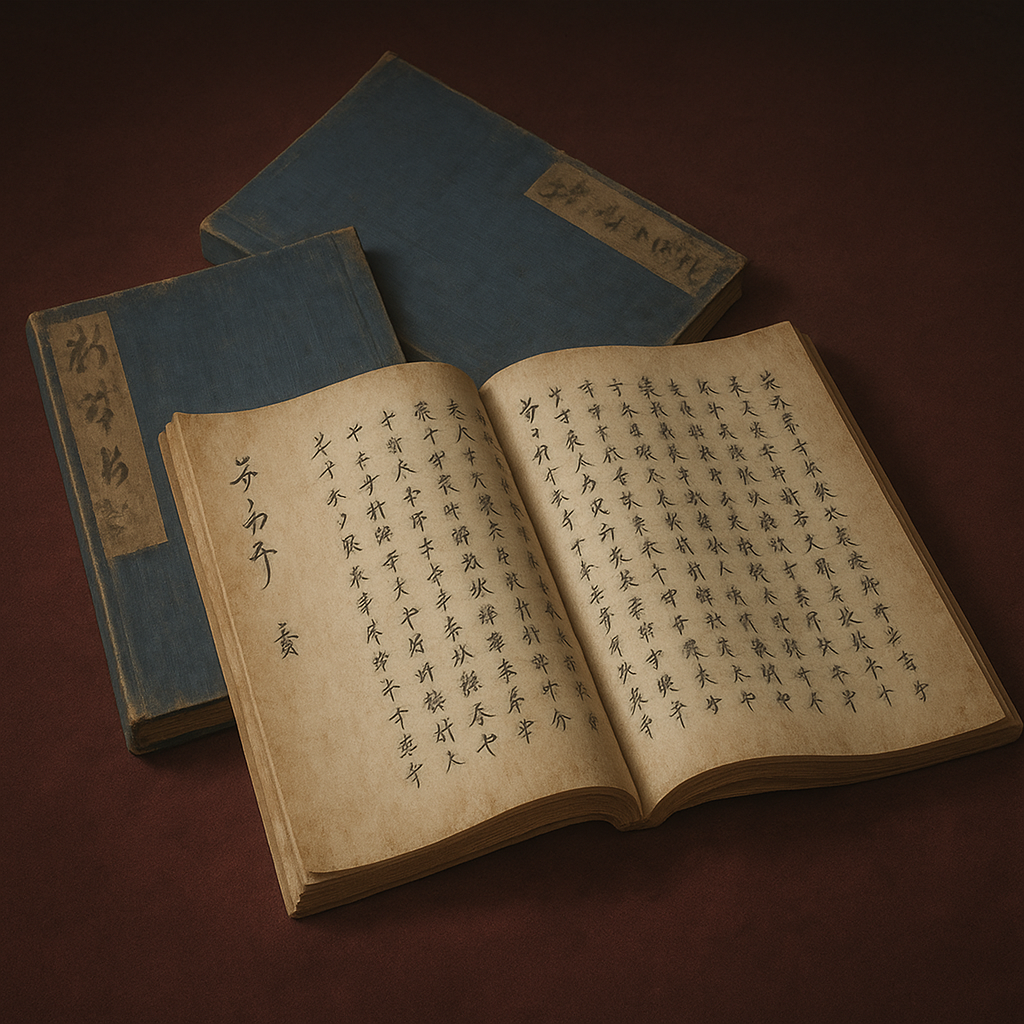
『都のつと』― 乱世の旅路、戦国の眼差し ―
序章:南北朝の旅人をめぐる問い
本報告書は、南北朝時代に僧・宗久によって記された紀行文『都のつと』を、単にその時代の産物として捉えるのではなく、後の「戦国時代」という比較軸を通して多角的に分析し、その歴史的・文学的意義を再評価することを目的とする。異なる時代の視点から古典を読むという試みは、比較対象を持つことで、それぞれの時代の社会構造、価値観、そして「旅」という行為の意味の変遷を、より鮮明に浮かび上がらせるために不可欠である。宗久の旅が持つ特異性を、戦国時代の「常識」と対比させることで、その本質を炙り出す。
本報告書は三部構成をとる。第一部では作品世界そのものを探訪し、作者の実像と旅路の文学的再現を論じる。第二部では、作品が成立した南北朝時代の過酷な社会環境を明らかにし、戦国時代との比較分析を通じて、社会の構造的変容を考察する。第三部では、この紀行文が後世に与えた影響を追跡し、その文学的遺産としての価値を論じる。この構成を通じて、『都のつと』という一つの文学作品を鏡として、中世から近世へと至る日本の大きな歴史的転換を映し出すことを目指すものである。
第一部:『都のつと』の世界 ― 文学空間の探訪
第一章:作者・宗久の実像 ― 乱世に生きる「世捨人」
『都のつと』の作者である宗久は、南北朝期に活動した歌僧であるが、その伝記は詳らかではない 1 。『勅撰作者部類』には俗名を平吉大炊助、『扶桑拾葉集系図』には大友兵部少輔頼資とする説が記されているが、確証はない 1 。この出自の不確かさは、彼が自らを規定した「世捨人(よすてびと)」というアイデンティティを、かえって際立たせる効果を持つ。
しかし、彼が単なる無名の隠遁僧でなかったことは確かである。『新拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に四首が入集している事実は、彼が中央の歌壇からもその実力を認められた一流の歌人であったことを示している 1 。その作品と思索には、南北朝という動乱の時代を生き抜いた文人的な僧侶の、複雑な陰影を帯びた生き様が投影されている 2 。
宗久の人物像を理解する上で最も重要な鍵は、彼が自らの旅を文学的伝統の中に位置づけようとした点にある。『都のつと』の冒頭は、「観応の比、一人の世捨人あり」という一文で始まる 3 。これは明らかに、平安時代の古典『伊勢物語』の有名な書き出し「昔、男ありけり」を意識したものである 3 。しかし、宗久はその形式を借りながらも、内容を巧みに読み替えている。『伊勢物語』の主人公である「昔男」が、二条の后との恋愛に破れて都を去り東下りしたのに対し、宗久の旅は仏道修行に志す「真摯な人間」の求道の旅として描かれる 3 。これは、古典の形式を継承しつつも、その動機を平安貴族の「雅」から、中世の武士や僧侶が重んじた「求道」へと転換させる、意図的な文学的営為であった。宗久にとって「世捨人」という自己規定は、単なる現実からの逃避ではなく、古典世界に精神的な拠り所を求め、自らの旅に普遍的な意味を与えるための、積極的な文化的行為だったのである。
第二章:旅路の再現 ― 筑紫から奥州へ、心象風景の変遷
『都のつと』は、筑紫(現在の九州)を出立し、都を経て東海道を下り、鎌倉、常陸(茨城県)から浜街道を通り、陸奥の松島・塩竈へと至る長大な旅の記録である 5 。その道程は、具体的な地名と、そこで詠まれた和歌によって彩られている。
旅の途中、宗久は近江の鏡山で「立寄りて見つと語るな鏡山名を世に留めん影も憂ければ」と詠み、東路の名所である不破の関を越え、佐夜の中山では「こゝはまたいづくと問へば天彦の答ふる声も佐夜の中山」と土地の神との対話を幻視する 5 。これらの歌は、古典に詠まれた歌枕の地を実際に訪れた旅人の感慨を示している。
特に注目すべきは、旅の過程で深まっていく無常観である。駿河の宇津の山を越え、清見が関を経て富士山を望んだ宗久は、次のように詠んだ。
富土の嶺の煙の末は絶えにしを降りける雪や消えせざるらん 5
平安時代の和歌において、富士の煙は恋心などの比喩として「絶えず燃え続けるもの」として詠まれるのが常であった 7 。しかし宗久は、噴煙活動が途絶えたという現実の観察に基づき、雪をいただく静かな富士の姿を詠んでいる。これは、古典和歌の伝統を踏まえつつも、旅人としての実感を何よりも重視する、中世的リアリズムの表れと言える。
この無常観は、鎌倉で頂点に達する。かつての幕府の所在地であったこの地で旧友を訪ねた宗久は、友が既にこの世にないことを知る。
見し人の苔の下なる跡問へば空行く月もなを霞むなり 5
友の死という個人的な悲嘆は、鎌倉幕府が滅亡し、往時の繁栄を失った都市の荒廃と重なり合い、人の世の儚さという普遍的な感慨へと昇華されている。
旅の終着点である松島・塩竈では、その美しい風景の中に、これまでの旅路で繰り返してきた数々の出会いと別れを重ね合わせる。
誰となき別れの数を松島や雄島の磯の涙にぞ見る 5
旅の終わりに、宗久は宿の壁に向かい、残り灯を頼りに道中の心に残った事々を書き留めた、という体裁で物語は結ばれる 5 。この紀行文そのものが、旅先から持ち帰るべき精神的な土産、すなわち「都のつと」なのである。それは都に残してきた人々へ、そして何よりも自己の記憶のために綴られた、魂の記録であった。
第二部:旅を取り巻く時代環境 ― 南北朝と戦国の比較
第三章:観応の擾乱と旅の現実 ― 沈黙の背景
『都のつと』が記された「観応の頃」、すなわち西暦1350年前後は、日本史上でも稀に見る激しい内乱の時代であった。室町幕府内部の対立から、足利尊氏・高師直派と、尊氏の弟・足利直義派が全国規模で争った「観応の擾乱」(1350-1352年)が勃発したのである 9 。
宗久が旅した東海道は、まさにこの擾乱の主戦場であった。駿河の薩埵山や府中では両軍の激戦が繰り広げられ 12 、それに先立つ南北朝の動乱では、南朝方の北畠顕家が率いた大軍の行軍によって、東海道沿いの村々は「在家の一時も残らず、草木の一本もなかりけり」と『太平記』に記されるほどの徹底的な破壊を受けていた 13 。このような状況下では、街道の治安は崩壊し、旅は常に生命の危険と隣り合わせであった。在地領主や武士団が好き勝手に設置した関所では法外な関銭(通行税)が徴収され、山中には盗賊が跋扈していた 14 。
しかし、驚くべきことに、『都のつと』には、こうした合戦の様子や兵士の姿、戦乱に苦しむ民衆といった生々しい現実がほとんど描かれていない。これは単なる偶然ではなく、作者による意図的な選択であったと考えられる。鎌倉で友の死に直面した際も、宗久はそれを戦乱と直接結びつけることなく、あくまで普遍的な「人の世の果敢なさ」として詠んでいる 5 。
この「沈黙」こそが、『都のつと』の本質を理解する鍵である。宗久は、耐え難い現実から意識的に目を逸らし、和歌や古典文学という美的なフィルターを通して世界を再構成することで、精神の平衡を保とうとしたのではないか。彼の旅は、物理的な空間移動であると同時に、現実の地獄から古典的な美の世界へと精神を退避させるための巡礼であった。作品全体を覆う深い無常観は、単なる抽象的な仏教思想ではなく、この過酷な現実を生き抜く中で体得された、切実な実感から生まれたものなのである 15 。
第四章:戦国時代という視点から見た『都のつと』 ― 隔絶と変容
宗久が生きた南北朝時代から約150年後の戦国時代と比較することで、日本の社会、経済、文化がいかに劇的に変容したか、そして宗久の旅がいかに特異な環境下で行われたかが一層明確になる。
節一:街道の変容 ― 混沌から支配へ
宗久の時代の街道は、統一的な権力によるインフラ管理が存在しない混沌とした空間であった。各地の在地領主や寺社は、自らの財源確保のために勝手に関所を乱立させ、通行人から関銭を徴収した 14 。例えば、京都と大坂を結ぶ淀川には数百ヶ所もの関所があったとされ、交通や物流を著しく阻害していた 20 。街道は、旅人にとっては安全が保障されない「収奪の場」であった。
これに対し、戦国時代の大名たちは、領国経営の一環として交通網の整備を戦略的に進めた。軍勢の迅速な移動や物資輸送のため、街道の維持管理は重要な政策課題となったのである。後北条氏や今川氏は、領国間で協定を結び、公用のための伝馬制を整備した 21 。さらに、織田信長は領国内の関所を撤廃し、「楽市・楽座」令によって商工業の自由化を推し進めた 22 。これにより、人流・物流は飛躍的に活性化し、城下町は繁栄した。街道は、南北朝時代の「収奪の場」から、戦国時代には「支配と経済振興の手段」へと、その社会的意味を根本的に変えたのである。
節二:旅する文化人の位相 ― 遁世僧から職業文化人へ
宗久の旅は、特定の庇護者を持たず、個人の求道と歌枕探訪を目的とした、内省的で私的な営みであった。彼の身分は「僧」であり、その旅は一遍上人の遊行にも通じるような、宗教的実践の側面を色濃く持っていた 1 。彼は既存の権力構造から距離を置く「世捨人」として、自らの精神世界を探求するために旅に出た。
一方、戦国時代の代表的な旅する文化人である連歌師・宗祇の旅は、全く様相が異なる。宗祇は、周防の大内氏や越前の朝倉氏といった有力な戦国大名の庇護を受け、彼らの文化的権威を高める役割を担った 29 。彼の旅は、各地で連歌会を興行するという「仕事」であり、大名たちを結ぶ文化・情報ネットワークを構築するという高度に社会的な、そして時には政治的な目的を持っていた。
この変化の背景には、文化と権力の関係性の変容がある。戦国時代、文化は単なる個人の教養に留まらず、大名が自らの権威を飾り、他者と差別化するための「戦略的資源」として認識されるようになった。これにより、連歌師や茶人といった高い専門性を持つ文化人が職業として成立し、大名に庇護される存在となったのである。宗久の個人的な旅は、このような時代の到来以前の、古風な文人のあり方を今に伝えている。
節三:名所の運命 ― 鎌倉と松島の変容
宗久が訪れた名所もまた、時代の変遷とともにその姿と意味を変えていった。
14世紀半ばの鎌倉は、鎌倉幕府滅亡後の政治的空白と、北条時行が幕府再興を掲げて蜂起した中先代の乱(1335年)などの度重なる戦乱により、往時の勢いを失い、荒廃の影が色濃い都市であった 11 。宗久が友の死を悼んだ背景には、こうした都市全体の衰退があったと推察される。これに対し、戦国時代の鎌倉は、関東一円を支配した後北条氏によって、その権威の象徴として戦略的に復興された。里見氏の攻撃で焼失した鶴岡八幡宮の再建をはじめ、多くの寺社が修復・創建され、「古都」としての景観と宗教的中心性が回復されたのである 37 。
また、宗久が純粋な歌枕、美的景観として和歌に詠んだ松島も 5 、戦国時代には奥州の覇者・伊達氏の領国の一部となっていた。伊達家の内紛である「天文の乱」(1542-1548年)は、南奥州の諸大名を巻き込む大乱となり、伊達家の勢力を大きく減退させた 42 。松島周辺もその政治的・軍事的文脈と無縁ではいられなかった。南北朝時代には文学的空間であった名所は、戦国時代には大名の勢力圏に組み込まれた政治的空間へと変貌を遂げていたのである。
|
比較項目 |
南北朝時代(宗久の旅) |
戦国時代 |
|
交通制度 |
関所の乱立、統一制度の欠如(私的収奪) |
大名による伝馬制、宿駅制度の整備(公的支配) |
|
街道の治安 |
極めて不安定(在地領主の抗争、盗賊) |
領国支配の強化による相対的安定化 |
|
旅の目的 |
個人的な求道、遁世、歌枕探訪(内省的) |
文化・政治活動、庇護者への奉仕、情報収集(社会的) |
|
文化人の立場 |
独立した「世捨人」(権力からの離脱) |
庇護下の専門職能者(連歌師など)(権力への参与) |
|
経済政策 |
関銭など通行への課税(流通阻害) |
楽市・楽座、関所撤廃など(流通促進) |
|
名所の意味 |
古典世界の追体験の場(文学的空間) |
大名の勢力圏、権威の象徴(政治的空間) |
第三部:文学的遺産としての『都のつと』
第五章:後世への影響と再評価
『都のつと』は、中世紀行文学の隠れた名作として、後世の文学に静かな、しかし確かな影響を与えた。その最も顕著な例が、江戸時代の俳聖・松尾芭蕉の『おくのほそ道』である。宗久が陸奥への旅の最終目的地として松島や塩竈を訪れ、優れた和歌を残していることは、後の芭蕉の旅路と明確に重なる 5 。西行や宗祇といった先人の跡を慕い、歌枕の地を巡った芭蕉が、同じく奥州を目指した宗久の紀行文を深く学んでいたことは想像に難くない。『おくのほそ道』に貫かれる、旅を精神的な探求の場とする姿勢や、歌枕への深い憧憬において、宗久の作品は重要な先駆として位置づけられる。
また、江戸時代に入ると、古典研究、すなわち国学が隆盛する。契沖や本居宣長といった国学者たちは、文献に依拠した実証的な研究手法を確立し、『万葉集』や『古事記』といった上代の古典に新たな光を当てた 46 。この学問的気運の中で、『都のつと』のような中世の忘れられていた文献もまた、その価値を再発見されていく。これらの紀行文は、王朝文学と近世文学をつなぐ重要な環(ミッシングリンク)として、また、動乱の時代を生きた日本人の精神性を知るための貴重な史料として評価されるようになった。近世の学者である今井似閑が、自らの紀行文の中で『風土記』に言及しているように、江戸時代の文人たちは中世の紀行文学を知識の源泉として積極的に活用していたのである 51 。
終章:乱世の鏡としての『都のつと』
『都のつと』は、単なる南北朝時代の旅の記録ではない。それは、観応の擾乱という極度の混乱期において、一人の文人僧が和歌と古典文学という内的世界に拠り所を求め、現実の惨禍を精神的に乗り越えようとした、切実な営みの証左である。
本報告書で試みた戦国時代との比較分析は、日本の歴史における「中世の終わり」と「近世の始まり」が、単なる政治体制の変化に留まるものではなく、交通インフラ、経済システム、そして文化と権力の関係性といった社会の根幹における構造的な大変革であったことを明らかにした。宗久が旅した道は、物理的には後の時代へと繋がっているが、その道が持つ意味、旅を取り巻く環境、そして旅する人の立場は全く異なっていた。
宗久の旅路を追体験することは、現代人が自明のものとして享受している社会基盤がいかにして形成されてきたかを問い直し、また、混乱の時代に人が何を心の支えとして生きるのかを考える上で、時代を超えた示唆を与えてくれる。『都のつと』は、遠い過去を映すだけでなく、現代を生きる我々自身を映し出す、乱世の鏡なのである。
引用文献
- 一、本稿は今川了俊の紀行文 「道行きぶり」の注釈である。 https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/0/9507/20160527184104840218/093_0301_0317.pdf
- 宗久論 「都のつと」の作者 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390853650323967360
- Untitled https://uec.repo.nii.ac.jp/record/9293/files/AN10016842_4_1_179.pdf
- 伊勢物語~原文全文・比較対照 - 古典の改め:Classic Studies https://classicstudies.jimdofree.com/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E7%89%A9%E8%AA%9E/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%85%A8%E6%96%87/
- 宗久の都のつと - 伊達宗弘ホームページ/随筆・エッセイ https://www.toyoma-date.jp/zuihitsu/txt18.html
- 陸奥日記 https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/130490/files/toh-bun-sou-2018-3-31.pdf
- 解説 - 裾野市 http://www.city.susono.shizuoka.jp/static/shishi/shishi0201-2cyuseihen-05kaisetsu.pdf
- 「都のつと」(宗久) - ukiyobanare https://ukiyobanare.com/2019/book/miyakonotsuto/
- 戦国!室町時代・国巡り(2)美濃編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/ndf88f88b33a5
- 宮城中世郷土史(伊達一族物語編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/date1000.html
- 南北朝の動乱をわかりやすく解説!対立が60年続いた理由とは - 学びの日本史 https://kamitu.jp/2023/08/31/sn-upheaval/
- 特 別 展 の 記 録 - 藤枝市 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/125/houkoku20210617.pdf
- 観応の擾乱 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/kannonojoran/
- 南朝勢を守った関所 - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2012/07/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E9%96%A2%E6%89%80%E5%9D%80.html
- 無常観の二面性について 六年 S・K 祇園精舎の鐘の声 https://www.keisen.jp/news/wp-content/uploads/2016/10/e43bb3c4a380f6e170c30b0b78782c1c.pdf
- 平家物語 諸行無常から考える私にとって本当に大切なこととは - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/buddhism/2017061998.html
- 小林秀雄 「無常ということ」 と古き美しいかたち|tetsuyaf - note https://note.com/tetsuyaf/n/n25c73627c040
- 織田信長の関所撤廃と物流支配【戦国ロジ其の3】 - LOGI-BIZ online https://online.logi-biz.com/9621/
- 関銭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E9%8A%AD
- 試し読み | 『室町は今日もハードボイルド―日本中世のアナーキーな世界―』清水克行 | 新潮社 https://www.shinchosha.co.jp/book/354161/preview/
- 大分市歴史資料館年報 https://www.city.oita.oita.jp/o205/bunkasports/rekishi/documents/h13.pdf
- 楽市・楽座 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%B8%82%E3%83%BB%E6%A5%BD%E5%BA%A7
- 楽市楽座 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/rakuichirakuza/
- 楽市楽座とは?簡単に!織田信長の目的、なぜ?政策のメリット - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/rakuichi-rakuza
- 関所の廃止 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC32%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%93%EF%BC%89%E3%80%8F.pdf
- 関所 http://www.mapbinder.com/Dictionary/Sekisyo.html
- 通行税(関銭)っていくら?戦国、江戸の関所事情 - 読書生活 https://www.yama-mikasa.com/entry/2018/03/31/%E9%80%9A%E8%A1%8C%E7%A8%8E%EF%BC%88%E9%96%A2%E9%8A%AD%EF%BC%89%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%EF%BC%9F%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%80%81%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E9%96%A2%E6%89%80%E4%BA%8B
- お坊さん、教えて! 第6回 時宗[3/7] - オンラインサンガ https://online.samgha-shinsha.jp/contents/df456d9b3a3e
- 連歌師という旅人 https://www.miyaishoten.co.jp/main/003/3-11/rengasitoiutabibito.htm
- 紹巴富士見道記 https://swu.repo.nii.ac.jp/record/4102/files/KJ00004435245.pdf
- 大内義興 史上最強、最大、最高の西国の覇者 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/ouchi-yoshioki/
- それなりの戦国大名家は合戦で負けても滅亡しない(ことが多い) - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/11/14/100349
- 南北朝時代|世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1690
- 南北朝略年表(鎌倉時代末期) - 楠木正成と南木の謎 https://kusunoki.komusou.jp/nenpyo.html
- 【歴史】鎌倉幕府の滅亡と南北朝、室町幕府のはじまり - 家庭教師のやる気アシスト https://www.yaruki-assist.com/tips/regular-exam/post-0038/
- 北条時行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%99%82%E8%A1%8C
- 2021年度特別展 開基500年記念 早雲寺-戦国大名北条氏の遺産と系譜- 特設サイト | 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/souun-ji/plus.html
- <戦国時代の鎌倉、その検証と発見> - 玉縄城址まちづくり会議 https://tamanawajo.jp/wp-content/uploads/2019/06/bb8de4ad075f38aee184d15933253f28.pdf
- 鎌倉時代、戦国時代を生きた北条氏に思いをはせる旅 - モデルコース - Tokyo Day Trip https://trip.pref.kanagawa.jp/ja/trip/step-into-the-past-and-follow-the-footsteps-of-the-hojo-clan/895
- 小田原城を本拠に関東一円を支配した戦国大名 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/409637/1-20210610160019.pdf
- 松島町景観計画 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/7,14800,c,html/14800/20191212-134234.pdf
- 三分一所館(宮城県東松島市浅井字大手) | NPO法人市民活動ネットワーク相馬 https://satobatake.fc2.net/blog-entry-1108.html?sp
- 伊達氏天文の乱 - 福島県伊達市公式ホームページ https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/87/1145.html
- 「天文の乱(1542~48年)」伊達氏当主父子が争った内乱はなぜ起きたのか? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/968
- 都のつと - 文化の港 シオーモ https://shiomo.jp/archives/1276
- 古典文学の POPULARIZATION ―江戸時代庶民文芸の再評価― https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3818/files/KK603.pdf
- 本居宣長 - 松阪市観光協会 https://www.matsusaka-kanko.com/information/information/motoorinorinaga/
- 本居宣長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B1%85%E5%AE%A3%E9%95%B7
- 過去の宣長十講|本居宣長記念館(公式ホームページ)へようこそ! https://www.norinagakinenkan.com/pages/55/
- 21世紀における国学研究の新展開 国際的・学際的な研究発信の可能性を探る - 國學院大學 https://www2.kokugakuin.ac.jp/oardijcc/archives/pdf/Forum-NCDKS2019.pdf
- 論文の内容の要旨 - 東京大学 http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h18/121734/121734a.pdf