下間仲孝
下間仲孝は本願寺坊官。石山合戦で武将として活躍し、和平を推進。能楽の名手「少進」として天下人と交流し、本願寺と下間家の存続に尽力した。
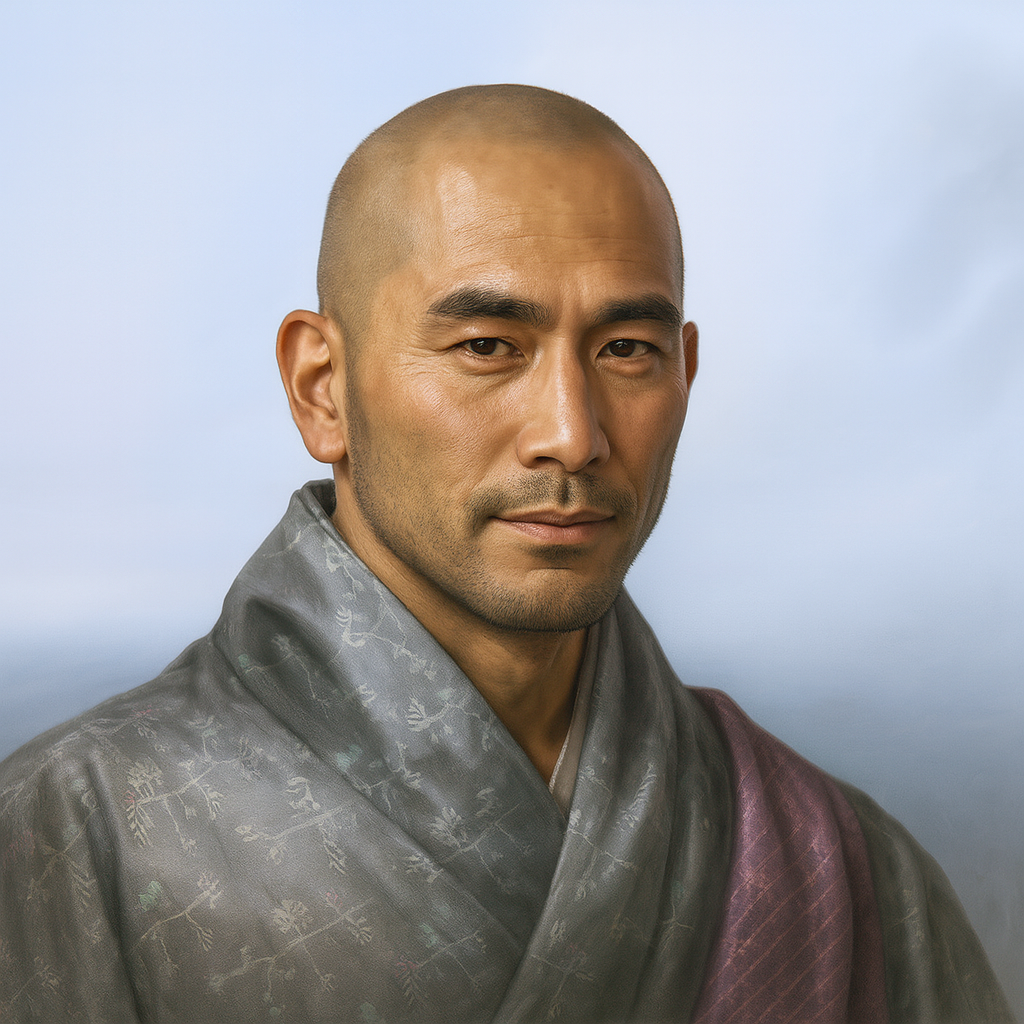
下間仲孝 ― 武と芸に生きた本願寺坊官、その生涯の全貌
序章:二つの顔を持つ男、下間仲孝
戦国時代から江戸時代初期という、日本の歴史上、未曾有の変革期を駆け抜けた一人の人物がいた。その名は下間仲孝(1551-1616)。彼は、巨大宗教勢力・本願寺の武将であり政治家としての「仲孝」という顔と、当代随一と謳われた能楽の名手「少進」という、二つの顔を持っていた 1 。この二つの名は、単に多才な人物であったことを示すに留まらない。むしろ、信仰、武力、そして文化が複雑に絡み合う激動の時代にあって、彼が自らの一族と本願寺教団を存続させるために駆使した、密接に連関する生存戦略そのものであった。
本報告書は、現存する多様な史料を基に、この下間仲孝という人物の生涯を多角的に再構築することを目的とする。第一部では、織田信長との十年にも及ぶ石山合戦を戦い抜き、本願寺の内紛と権力闘争の渦中で辣腕を振るった武将・坊官としての「仲孝」の姿を追う。第二部では、豊臣秀吉や徳川家康ら時の天下人を魅了し、能楽の世界に不滅の足跡を遺した文化人「少進」としての活動を詳らかにする。そして終章において、これら二つの側面を統合し、武と芸を両輪として乱世を生き抜いた戦略家としての仲孝の実像に迫るものである。
表1:下間仲孝 関連年表
|
元号 |
西暦 |
仲孝年齢 |
本願寺・天下の動向 |
下間仲孝の活動(坊官として) |
下間仲孝の活動(少進として) |
主な典拠 |
|
天文20 |
1551 |
1 |
|
下間頼照の子として生まれる。幼名は千代寿 1 。 |
|
|
|
元亀元 |
1570 |
20 |
石山合戦始まる。 |
織田信長との10年にわたる抗争に参加し、各地で門徒を指導する 5 。 |
|
|
|
天正3 |
1575 |
25 |
父・頼照が越前で織田軍に敗れ戦死 7 。 |
|
|
|
|
天正6 |
1578 |
28 |
第二次木津川口の戦いで本願寺方が敗北。 |
頼龍との連署で紀伊門徒へ出陣を命じるも、参陣を得られず海上封鎖を許す 1 。 |
|
|
|
天正8 |
1580 |
30 |
正親町天皇の勅命により、信長と本願寺が和睦。 |
顕如の代理として、頼廉・頼龍と共に和睦の誓紙に署名 9 。和平に反対する教如と対立 1 。 |
和平推進派として信長の知遇を得る 2 。 |
『信長公記』 |
|
天正10 |
1582 |
32 |
本能寺の変、信長死去。 |
顕如の使者として安土城へ赴く 4 。法印に昇進 2 。 |
|
『鷺森日記』 |
|
天正13 |
1585 |
35 |
豊臣秀吉が関白に就任。 |
顕如の奏者として、秀吉の家臣・寺沢広高と顕如の対面を取り次ぐ 4 。 |
|
『宇野主水記』 |
|
天正16 |
1588 |
38 |
|
|
演能記録『能之留帳』の記述を開始 5 。 |
|
|
天正20/文禄元 |
1592 |
42 |
顕如死去。教如が法主を継承。 |
教如と対立し、奏者を罷免され閉門処分となる 5 。 |
演能活動が本願寺周辺に限定される 12 。 |
『大谷嫡流実記』 |
|
文禄2 |
1593 |
43 |
秀吉の命で教如が隠居、准如が法主となる。 |
奏者に復帰 5 。 |
秀吉の肥前名護屋城に招かれ演能。豊臣秀次が能の師として師事 2 。 |
|
|
慶長元 |
1596 |
46 |
|
|
能楽伝書『童舞抄』『舞台之図』『叢伝抄』を著す 1 。 |
|
|
慶長5 |
1600 |
50 |
関ヶ原の戦い。 |
嫡男・仲世が西軍に加担したため、連座を問われ仲世を廃嫡し自身も謹慎 5 。 |
演能活動が一時的に停滞 2 。 |
|
|
慶長7 |
1602 |
52 |
本願寺が東西に分裂。 |
謹慎を解かれ奏者に復帰。准如の西本願寺に従う 5 。 |
|
|
|
慶長9 |
1604 |
54 |
|
|
禁裏にて能を演じ、後陽成天皇や公家衆が観覧する 4 。 |
『慶長日件録』 |
|
慶長11 |
1606 |
56 |
|
西本願寺家臣6人の出仕拒否事件に際し、准如への忠誠を誓う誓書を提出 1 。 |
|
|
|
元和2 |
1616 |
66 |
|
5月15日、死去。享年66。家督は五男の仲此が継承 1 。 |
|
|
第一部:本願寺の武将 ― 信仰と権力の世界
第一章:血脈と戦場の黎明
出自と家系
下間仲孝の生涯を理解する上で、彼が属した下間氏の特異な立場をまず把握する必要がある。下間氏は、摂津源氏の流れを汲むと自称し、浄土真宗の宗祖・親鸞の時代から本願寺に仕えてきた譜代の家臣団であった 15 。本願寺が永禄2年(1559年)に門跡寺院の格式を得ると、下間氏はその世俗的な側面、すなわち外交、軍事、行政といった実務を統括する「坊官」としての地位を確立する 15 。彼らは法主の意向を伝える「御印書」などの公文書を発給する権限を持ち、事実上、本願寺という巨大組織の運営を担う家臣団の筆頭格であった 11 。
仲孝の父、下間頼照(法名:述頼)は、この下間一族の中でも特に武勇に優れた人物であった。本願寺門主・顕如の命を受け、越前一向一揆の総大将として現地に派遣され、一時は織田方の勢力を駆逐して越前一国を支配下に置くほどの勢威を誇り、「守護代」とまで見なされた 3 。しかし、その栄光は長くは続かない。天正3年(1575年)、織田信長が満を持して大軍を率いて越前に侵攻すると、頼照は奮戦空しく敗死する 8 。
父の劇的な敗死は、当時25歳で石山本願寺に籠城していた仲孝にとって、単なる肉親の喪失に留まらない、重大な意味を持ったと考えられる。それは、信長が率いる圧倒的な軍事組織と、純粋な信仰心だけでは乗り越えられない戦国社会の冷徹な現実を、身をもって知る原体験となったであろう。武力抵抗の象徴であった父が壮絶な最期を遂げたという事実は、仲孝が後に単なる武断派ではなく、和議や外交を重視する現実主義的な道を歩む、一つの契機となった可能性は否定できない。父が選んだ「武」の道と、後に息子が切り拓く「芸」と「政」の道。この対比こそ、仲孝の人物像を深く理解する鍵となる。
石山合戦と軍事指導者として
父の死後、仲孝は本願寺教団の中枢で急速に頭角を現していく。元亀元年(1570年)から始まった10年にも及ぶ石山合戦において、彼は各地に赴き、門徒を指導する軍事指揮官として活動した 5 。やがて、同族の下間頼廉、下間頼龍と共に「下間三家老」とも称される指導体制の一翼を担い、戦略の立案から実戦の指揮に至るまで、籠城戦の中核を支えた 16 。
その活動の一端は、天正6年(1578年)の第二次木津川口の戦いにおいて見ることができる。織田軍による海上封鎖を打破すべく、仲孝は頼龍との連名で、本願寺の生命線であった紀伊の門徒衆(雑賀衆など)に対し、出陣を命じる「御印書」を発給した 5 。しかし、門徒衆はこれに応じず、本願寺水軍は九鬼嘉隆が率いる鉄甲船の前に大敗を喫し、大坂湾の制海権を完全に失ってしまう 5 。この敗北は、単なる軍事的な失策以上の問題を露呈させた。法主の代理として発給した最高命令が、現地の門徒に実行されなかったという事実は、本願寺教団の統制力が決して一枚岩ではなかったことを示している。この経験は、仲孝ら指導者層に、強硬な主戦論だけでは教団全体をまとめきれないという冷徹な現実認識を植え付けたことだろう。
和平への道と「三家老」の重責
戦況が絶望的になる中、天正8年(1580年)、朝廷を介した和平交渉が本格化する。この時、仲孝は和平推進派の中心人物として交渉を主導した。そしてついに、正親町天皇の勅命講和という形で、10年戦争の幕引きが図られることとなる。この歴史的な和睦において、仲孝は法主・顕如の代理として、下間頼廉、下間頼龍と共に和睦の誓紙に署名した 9 。これは、彼が本願寺教団を代表する最高幹部の一人として、敵対した織田信長からも公的にその立場を認められたことを意味する、極めて重要な出来事であった。
第二章:権力の中枢 ― 激動の政治と本願寺の内紛
和平を巡る内部対立と「謀略説」
信長との和睦は、石山本願寺に平和をもたらす一方で、教団内部に深刻な亀裂を生じさせた。法主・顕如とその側近である下間頼廉、そして仲孝ら和平派が教団の存続を最優先したのに対し、顕如の嫡男・教如と下間頼龍ら主戦派は、和睦を屈服と捉え、徹底抗戦を主張した 1 。この対立は、後の本願寺東西分裂の直接的な原因となる。
この対立の過程で、仲孝の政治家としての一面をうかがわせる興味深い説が浮上する。顕如が大坂を退去した後も、教如が石山に籠城を続けたことについて、「和平に反対する教如を厄介払いするため、仲孝が父子の意思疎通を巧みに妨害し、教如が籠城せざるを得ない状況に追い込んだ」とする「下間仲孝謀略説」である 1 。この説の真偽を確定することは史料上困難であるが、重要なのは、このような説が生まれるほど、仲孝が教団内で大きな影響力を持つ策略家と見なされていたという事実である。彼は単に法主の意向に従うだけの人物ではなく、自らの政治的判断で教団の方向性を左右しうる、いわば「黒幕」と目される存在であった。この評価は、後に見る文化人としての一面とは対照的であり、彼の人物像の多面性を際立たせている。
天下人との渡り合い
信長との和睦後、仲孝は本願寺の外交官として重要な役割を担う。顕如の使者として安土城へ赴き、信長との関係正常化に努めた 4 。信長も彼の能力を評価し、厚遇したと伝えられる 2 。
信長の死後、天下人となった豊臣秀吉との関係はより複雑なものとなる。仲孝は下間頼廉と共に本願寺の奏者、そして天満本願寺の町奉行として、豊臣政権との折衝にあたった 5 。しかし、秀吉からは寺内町の特権を制限されるなど、その関係は常に緊張をはらんでいた 5 。
本願寺指導者層の変遷と仲孝の浮沈
天正20年(1592年)に顕如が死去し、主戦派であった教如が法主を継承すると、和平派の重鎮であった仲孝は即座に奏者の職を罷免され、失脚の憂き目に遭う 5 。しかし、その翌年、秀吉の裁定によって教如が隠居させられ、穏健派の三男・准如が新たな法主となると、仲孝は劇的な復権を果たす 5 。この一連の出来事は、仲孝の政治生命が、本願寺内部の権力構造と、それを左右する天下人の意向によって激しく揺れ動く、極めて不安定なものであったことを示している。
関ヶ原の戦いと一族の危機
慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、下間家は最大の危機を迎える。仲孝の嫡男・仲世が西軍の石田三成に与したため、准如が率いる西本願寺も徳川家康から西軍加担の嫌疑をかけられたのである 5 。この絶体絶命の窮地において、仲孝は非情ともいえる決断を下す。本願寺と下間家の存続のため、愛息・仲世を廃嫡し、自らも謹慎したのである 5 。
この断固たる処置が功を奏し、家康の許しを得た仲孝は、慶長7年(1602年)に謹慎を解かれ、再び奏者として復帰する 5 。そして、五男の仲此を後継とすることで、自らの血脈を西本願寺の重臣「少進家」として後世に繋ぐことに成功した 1 。この一連の動きは、仲孝が個人の情よりも「家」と「組織」の存続を最優先する、戦国末期の指導者としての冷徹な現実感覚と、卓越した政治手腕を併せ持っていたことを如実に物語っている。
第二部:文化人「下間少進」 ― 芸能と生存戦略
第三章:芸道の探求 ― 天下一の素人能役者「少進」の誕生
下間仲孝のもう一つの顔、それは能楽の世界で「下間少進(しもつましょうしん)」として知られる文化人の姿であった 1 。少進とは彼の官位名であり、能役者としての芸名は「素周(そしゅう)」と称した 1 。
彼は若い頃から当代随一の能楽流派である金春流の宗家、金春大夫笈蓮(ぎゅうれん)に師事し、その奥義をことごとく伝授されたと伝えられる 1 。特に、重傷を負った師を手厚く看護したことから深い信頼を得て、秘伝の伝授に繋がったという逸話も残っている 2 。
織豊期は、武士や町衆などプロではない人々が能楽を嗜む「手猿楽」が隆盛を極めた時代であった 1 。玄人(プロ)と素人の垣根が低く、互いに芸を競い合う活気に満ちた状況の中で、少進は「手猿楽の第一人者」として、その実力はプロをもしのぐと高く評価された 1 。彼が「素人」であったことは、むしろその活動に有利に働いた側面がある。プロの役者のように座の制約や興行のしがらみに縛られることなく、本願寺坊官という高い身分と独自の人脈を最大限に活用し、自由な演能活動を展開できたのである。豊臣秀吉や徳川家康といった最高権力者の前で舞う機会を容易に得られたのは、一介のプロ役者には望めない、彼の身分ならではの特権であった。
その驚異的な活動の軌跡は、彼自身が天正16年(1588年)から死の前年まで克明に記録した演能記録『能之留帳(のうのとめちょう)』によって知ることができる 1 。これによれば、約30年間で演じた能は1200番近くに及び、その精力的な活動ぶりがうかがえる 2 。この記録は、共演者、観客、演目、場所が詳細に記されており、安土桃山時代の能楽の実態を知る上で比類なき一級史料となっている 5 。
少進の卓越した技量と学識を示す逸話として、秘曲中の秘曲であった「関寺小町」の復曲上演が挙げられる。当時、金春流では上演が途絶えていたこの難曲を、時の関白・豊臣秀次の所望に応えるかたちで見事に復曲し、自ら演じてみせたのである 1 。これは、彼が単なる演者ではなく、能楽研究者としての側面も持ち合わせていたことを示している。
第四章:能楽を通じた生存戦略と文化的遺産
下間少進の能楽は、単なる趣味や芸事の域を超え、本願寺と下間家の存続をかけた高度な生存戦略であった。彼は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人や、その子弟である豊臣秀次、松平忠吉らに能を教え、また彼らの前で度々演能することで、個人的な信頼関係を築き上げた 2 。慶長9年(1604年)には、後陽成天皇や多くの公家が見守る中、禁裏(御所)で能を演じるという最高の栄誉にも浴している 4 。
戦国武将にとって、能楽や茶の湯は重要な教養であり、大名間の社交や外交を円滑に進めるための不可欠なツールであった 31 。石山合戦を経て武力を背景とした影響力を失った本願寺にとって、文化は新たな権力へのアクセス手段となった。少進は、能楽という共通の言語を媒介として、支配者層の懐に深く入り込むことに成功したのである。能の師として、また一座する演者として築いたこの文化的な人脈は、公式な外交ルートでは得られない情報や便宜をもたらし、本願寺の政治的立場を安定させ、ひいては下間家の存続を盤石にする上で、計り知れない価値を持った。徳川家康の四男・忠吉に秘伝書『童舞抄』を伝授した行為は 5 、単なる芸の伝承ではなく、徳川幕府との間に強固なパイプを築くための、極めて戦略的な外交活動であったと評価できる。
少進の功績は、その演能活動だけに留まらない。彼は、後世に多大な影響を与えた数々の著作を残した。
その代表格が、慶長元年(1596年)に著された能の型付(演出ノート)である『童舞抄』である 1。全三巻からなるこの伝書は、能の演目ごとに使用する面や装束、具体的な所作や舞の型などを詳細に記述したもので、現存する能の型付としては最古級に属する 34。織豊期の具体的な演能スタイルを今日に伝える、極めて貴重な史料である 34。
この他にも、舞台装置や小道具を図解した『舞台之図』、師である笈蓮からの聞書をまとめた『笈蓮江問日記』、そして自らの見聞を記した『少進聞書』など、数多くの伝書を著した 1 。これら一連の著作群は、一人の演者の記録という枠を超え、中世から近世へと移行する能楽の変容を伝える、文化史上の重要な遺産となっている。少進の活動と著作は、それまで口伝や一子相伝が主であった能楽の「型」を整理・明文化し、後世に正しく伝える上で、決定的な役割を果たしたのである。
終章:武と芸の狭間で ― 下間仲孝の生涯と現代に続く血脈
下間仲孝の生涯を振り返るとき、我々は彼が単なる「戦う坊官」でも「器用な能役者」でもなかったことを知る。彼は、本願寺という巨大宗教組織が、戦国大名に比肩する独立した政治・軍事勢力から、近世的な幕藩体制下の一宗教法人へと変質していく歴史の転換点を、その中枢で体現し、乗り切った稀有な人物であった。彼の生涯は、権力維持の源泉が、剥き出しの「武」から洗練された「文化」へと移行する時代の、一つの象徴であったと言えよう。
和平交渉の主導、教如との対立、准如への忠誠、そして息子・仲世の廃嫡。彼が下した一連の政治的決断は、すべて「本願寺」と「下間家」の存続という、明確な目的意識に貫かれている。そして、天下一とまで称された能楽の名声すら、その目的を達成するための最も効果的な手段として、戦略的に活用されたのである。武将「仲孝」と文化人「少進」は、別々の人格ではなく、一つの目的のために機能する、分かちがたい両輪であった。
この老練な戦略家の目論見は、見事に成功を収めた。仲孝の死後、家督を継いだ五男・仲此の子孫は「少進家」として西本願寺の重臣の地位を代々世襲し、その血脈は現代にまで続いている 1 。これは、仲孝の生涯をかけた生存戦略が、400年以上の時を超えて結実した何よりの証左である。彼の物語は、戦国という時代の終焉と新たな時代の幕開けを、一人の人間の類まれなる生き様を通して、我々に鮮やかに語りかけてくれるのである。
引用文献
- 下間仲孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D
- 下間少進(しもつましょうしん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E5%B0%91%E9%80%B2-167866
- 下間仲孝(しもつま・なかたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D-1081437
- 歴史の目的をめぐって 下間仲孝 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-12-shimotsuma-nakataka.html
- 下間仲孝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D
- G114 下間宗重 - 清和源氏 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/g114.html
- 下間頼照 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn16326
- 下間頼照とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E7%85%A7
- 石山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6
- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E5%AD%9D-1081437#:~:text=%E5%A4%A9%E6%96%87(%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93)20%E5%B9%B4,%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E8%AA%93%E7%B4%99%E3%81%AB%E7%BD%B2%E5%90%8D%E3%80%82
- 下間氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F
- 〈関寺小町〉上演記録 - 能楽金春流情報サイト金春ニュース http://www.komparunews.com/komparusekidera
- 能楽(金春)史年表 - 能楽 金春流|公益社団法人 金春円満井会(こんぱるえんまいかい) 公式ウェブサイト|公演 https://www.komparu-enmaikai.com/%E9%87%91%E6%98%A5%E5%86%86%E6%BA%80%E4%BA%95%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E8%83%BD%E6%A5%BD-%E9%87%91%E6%98%A5-%E5%8F%B2%E5%B9%B4%E8%A1%A8/
- 准如とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%87%86%E5%A6%82
- 下間氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F
- 「本願寺」影の内閣:下間三家老 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page125.html
- 下間氏(しもつまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F-1172629
- 下問氏加署文書の一考察 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%8F%B7/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%8F%B7%E3%80%80003%E7%89%87%E5%B1%B1%E3%80%80%E4%BC%B8%E3%80%8C%E4%B8%8B%E9%96%93%E6%B0%8F%E5%8A%A0%E8%91%97%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%80%83%E5%AF%9F%E3%80%8D.pdf
- ︿ 性 乗 ﹀ 下間少進仲之 文書の 一考察 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%96%E5%8F%B7/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%93%EF%BC%96%E5%8F%B7%20003%E5%90%89%E4%BA%95%E5%85%8B%E4%BF%A1%E3%80%8C%E4%B8%8B%E9%96%93%E5%B0%91%E9%80%B2%E4%BB%B2%E4%B9%8B%EF%BC%88%E6%80%A7%E4%B9%97%EF%BC%89%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%80%83%E5%AF%9F%E2%80%95%E2%80%95%E8%8A%B1%E6%8A%BC%E5%A4%89%E9%81%B7%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%E2%80%95%E2%80%95%E3%80%8D.pdf
- 下間頼龍とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E9%BE%8D
- 下間頼龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E9%BE%8D
- 木津川口の戦い古戦場:大阪府/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kidugawaguchi/
- 教如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E5%A6%82
- 下間少進 (しもつましょうしん)とは:the能ドットコム:能楽用語事典 https://db2.the-noh.com/jdic/2012/10/post_335.html
- 下間仲世 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E4%BB%B2%E4%B8%96
- 下間少進仲之の家系再考 - The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/96502/egrs_21_019.pdf
- カードリスト/本願寺/本007下間仲孝 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/514.html
- 武家手猿楽の系譜 : 能が武士の芸能になるまで - CORE https://core.ac.uk/download/223195794.pdf
- 1588(天正16)年の出来事 - 年表 戦国時代 https://nrekishi.yoka-yoka.jp/e788679.html
- 5.史料 - 野上記念法政大学能楽研究所 https://nohken.ws.hosei.ac.jp/nohken_material/htmls/index/pages/cate5.html
- 滝川一益-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44324/
- 【解説マップ】伊達政宗はどんな人?性格や生涯など図解でわかりやすく - マインドマイスター https://mindmeister.jp/posts/datemasamune
- 童舞抄 3卷 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000054-I040_51988
- 整版本﹃童舞抄﹄‑本能寺版古活字本との関連を中心にー https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/28033/files/003.pdf
- 金春こぼれ話 - 能楽金春流情報サイト金春ニュース https://www.komparunews.com/koborebanashi
- https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541025
- [収蔵品]小出文庫 - 南丹市立文化博物館 https://nantan-museum.jp/wp/col-koidebunko-1/
- 4.付 - 野上記念法政大学能楽研究所 https://nohken.ws.hosei.ac.jp/nohken_material/htmls/index/pages/cate4.html
- 下間少進の末裔ナレーター下間都代子が祖先から学ぶ - note https://note.com/toyobar0714/m/m5573cea5f4d6