亀田高綱
亀田高綱は柴田勝家、浅野家に仕えた武将。蔚山城や大坂夏の陣で活躍。同僚との手柄争いで浅野家を致仕。晩年は自らの武功を記録し、武士の意地を貫いた。
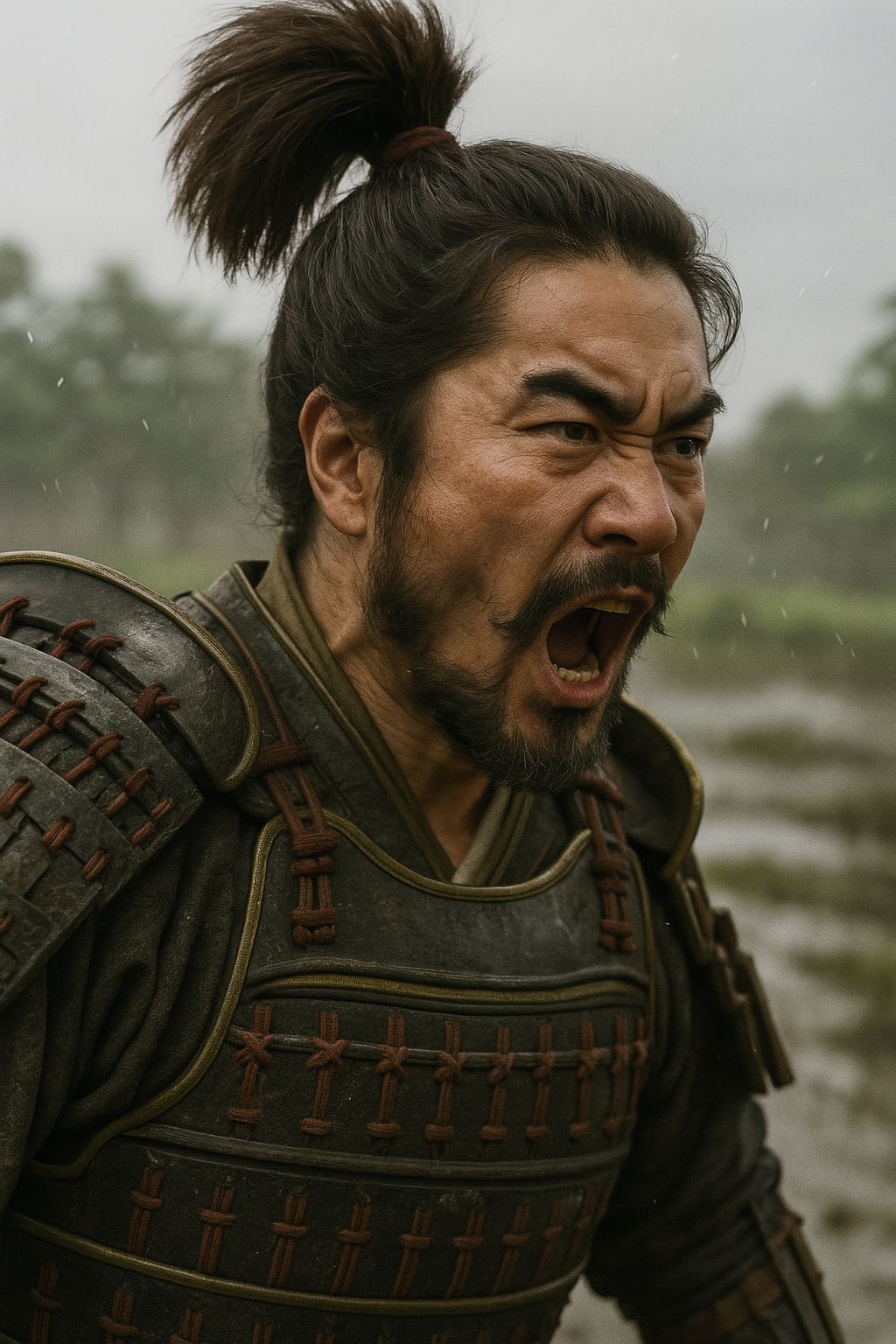
戦国武将 亀田高綱の生涯 ― 忠義と意地に生きた武士(もののふ)の実像
序章:最後の戦国武将、亀田高綱 ― 時代の黄昏に生きた武士(もののふ)の意地
戦国の動乱が終息し、徳川による泰平の世が築かれようとしていた時代の転換期。多くの武士が新たな価値観への適応を迫られる中、旧来の武士道、すなわち己の武辺(ぶへん)と名誉をこそ至上の価値とする生き様を頑なに貫いた一人の武将がいた。その名は亀田大隅守高綱(かめだおおすみのかみたかつな)。彼の生涯は、織豊政権下で数多の戦功を重ねながらも、最後は同僚との対立の末に主家を去るという、劇的なものであった。それは、戦場で槍を交えることこそが本分と信じた武士が、新たな時代の秩序と相克する姿を象徴している 1 。
本報告書は、この亀田高綱という人物の生涯を、その出自から説き起こし、柴田家臣時代、浅野家への仕官、朝鮮出兵や関ヶ原合戦、そして彼の名を不動のものとした大坂夏の陣「樫井の戦い」における活躍を丹念に追う。さらに、彼の人生を大きく左右した同僚・上田重安との対立、そして浅野家を致仕した後の晩年に至るまで、現存する史料、とりわけ彼自身が後世に残した『亀田大隅一代働覚』や『泉州樫井表合戦次第覚書』といった記録を手がかりに、その功績と行動原理、そして武士としての矜持の内面にまで迫ることを目的とする 2 。
第一章:出自と柴田家臣時代 ― 忠義の在り方と武名の萌芽
1-1. 溝口半之丞、誕生
亀田高綱は、永禄元年(1558年)、尾張国葉栗郡に生を受けた 3 。本姓を溝口といい、父は織田家の宿老・柴田勝家に仕えた溝口半左衛門であった 3 。幼名を半之丞(はんのじょう)と称した高綱は、父と同じく柴田家に身を投じ、勝家の養子である柴田勝豊の配下として、その武士としての第一歩を踏み出した 1 。勝豊は当時、羽柴秀吉から譲られた近江長浜城を居城としており、高綱の青年期は、この地で武勇を磨きながら形成されたものと考えられる。
1-2. 賤ヶ岳の戦い ― 主家への忠節
天正11年(1583年)、織田家の主導権を巡り、羽柴秀吉と柴田勝家の間で賤ヶ岳の戦いが勃発する。この時、高綱の直接の主君であった柴田勝豊は、戦況不利と見るや秀吉方に寝返るという挙に出た 3 。主君の裏切りという絶望的な状況下で、多くの将兵がそれに従う中、高綱は異なる道を選んだ。彼は勝豊に従うことを良しとせず、柴田本家への忠義を貫き、勝家方として最後まで奮戦したのである 3 。
この行動は、彼の武士としてのキャリアを方向づける極めて重要な決断であった。それは単なる主君への盲目的な忠誠ではなく、誰が真に忠義を尽くすべき主であるかを自ら判断し、己の信条に基づいて行動するという、彼の生涯を貫く強固な意志の最初の現れであった。直接の上司である勝豊の命令よりも、柴田一門の棟梁たる勝家への忠節を優先したこの選択は、組織の命令系統よりも個人の価値判断を重んじる彼の気質を如実に示している。この頑固なまでの自己の正義感こそが、後の浅野家において論功行賞を巡り、藩の公式見解や同僚の主張を受け入れられずに致仕する遠因となったと見ることができる。
1-3. 初期の武功 ― 『亀田大隅軍功之覚』に見る自己認識
高綱は、若き日から自らの武功を記録し、後世に伝えようとする強い意識を持っていた。彼が晩年に著したとされる『亀田大隅軍功之覚』には、天正6年(1578年)に行われた越前丸岡城攻めにおいて、自らが「一番乗り」の功名を果たし、城の大手門で敵と槍を合わせたという武勇伝が記されている 5 。
この記録の真偽を完全に証明することは困難であるが、重要なのは、彼が自身のキャリアの早い段階から、武功を立てたという事実そのものだけでなく、それが「記録される」ことによって初めて武士としての名誉(武名)が完成すると考えていた可能性である。武士の名誉が他者からの評価によって成り立つという側面を深く理解し、その評価を自らの手で形に残そうとする強い自己顕示欲の現れとも言えよう。この「記録への執着」が、後年、彼の人生の集大成ともいえる『泉州樫井表合戦次第覚書』の執筆へと繋がっていくのである 1 。
第二章:浅野家への仕官と朝鮮での武功 ― 不動の評価の確立
2-1. 亀田権兵衛、再起
賤ヶ岳の戦いで柴田家が滅亡すると、高綱は浪々の身となった。しかし、その武勇を惜しまれ、彼は「亀田権兵衛」と名を変えて、豊臣政権下で五奉行の一人として重きをなしていた浅野長政・幸長父子に仕えることとなる 3 。天正18年(1590年)の小田原征伐に従軍したのを皮切りに、彼は浅野家の家臣として新たなキャリアを輝かせていくことになる 3 。
2-2. 蔚山城の戦い ― 主君の窮地を救う
高綱の武名を決定的なものとしたのが、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)における蔚山城の戦いであった 1 。慶長2年(1597年)12月、浅野幸長が率いる部隊は、数万にも及ぶ明・朝鮮連合軍の夜襲を受け、絶体絶命の危機に陥った。この時、幸長自身も負傷し、軍の象徴である馬印まで奪われるという惨状であった 6 。
部隊が崩壊の危機に瀕する中、高綱は獅子奮迅の働きを見せる。彼は敵陣に突入し、敵将を自らの手で討ち取るという大功を挙げた。これにより敵軍に混乱が生じた隙を突き、幸長は九死に一生を得て、蔚山城内へと撤退することに成功したのである 6 。この活躍は単なる武功ではない。主君・幸長の生命を救い、部隊の全滅を防いだという「救世主」的な功績であった。これが、元は外様の家臣であった高綱が浅野家中で絶対的な信頼を勝ち取り、後に家老という最高幹部にまで昇進する最大の要因となった。この「主君の命の恩人」という特別な立場が、彼の自負心を一層強固なものにしたことは想像に難くない。
2-3. 関ヶ原の戦いと戦後の処遇
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、東軍に与した浅野幸長に従い、美濃国垂井に布陣した。彼らの任務は、南宮山に陣取る西軍の毛利勢を牽制することであり、本戦での直接的な戦闘には参加していない 6 。
戦後、浅野家はその功により紀伊国和歌山37万6500石に封ぜられた。これに伴い、高綱も蔚山での功績をはじめとする数々の働きを高く評価され、慶長6年(1601年)、7,000石という破格の知行を与えられて家老職に就任した 1 。この頃から「大隅守」を称するようになる 7 。この高禄と家老という地位は、彼が浅野家にとって、もはや単なる一介の武将ではなく、家中の中核を担う不可欠な存在と見なされていたことの証左である。また、彼が単なる戦闘員に留まらず、家中の人事にも影響力を持っていたことを示唆する記録も存在する。関ヶ原で西軍の小西行長配下として戦った淡輪六郎兵衛という人物が、戦後、浅野家に仕える際に、高綱が特に目をかけていたと記されているのである 7 。これは、高綱が家老として、人材の評価や登用といった政治的な役割をも担っていたことを示す貴重な記録と言える。
第三章:大坂夏の陣「樫井の戦い」 ― 栄光と論争の戦場
3-1. 戦いの背景と浅野軍の動向
慶長20年(1615年)、大坂夏の陣が勃発した。冬の陣の和睦条件により大坂城の外堀を全て埋められてしまった豊臣方は、城を出て野戦を挑むほかなく、大野治房を主将とする一隊を紀伊国へと差し向けた 8 。その狙いは、徳川方の紀州藩主・浅野長晟(幸長の弟で後継者)を討ち、同時に紀州の土豪一揆を煽動して後方を攪乱することにあった 8 。
これに対し、浅野長晟は兵5,000を率いて和歌山城を出発。しかし、偵察によって豊臣軍の兵力を20,000と誤認したこと、また領内での一揆蜂起の兆候があったことから、慎重策を採る 8 。軍議の結果、少数での迎撃に適した和泉国樫井まで計画的に軍を退却させることを決定した。
3-2. 高綱の戦術 ― 殿(しんがり)としての誘引
この退却戦において、亀田高綱は最も危険で重要な任務である殿(しんがり)を任された。彼は和泉国安松村に陣を構え、追撃してくる豊臣方の先鋒を、樫井に布陣する浅野軍主力のもとまで巧みに誘引する遅滞戦術を展開したのである 8 。この作戦は見事に成功する。豊臣方の先鋒を務めた塙団右衛門(直之)と岡部則綱は、手柄を競うあまり突出。後続の本隊との連携を完全に欠いた状態で、樫井の地で待ち構える浅野軍主力と激突することになった 8 。
3-3. 塙団右衛門討ち取りの真相 ― 記録のなかの合戦
4月29日の夜明けと共に始まった樫井での激戦は、浅野軍の圧勝に終わった。豊臣方の塙団右衛門、淡輪重政といった名だたる武将が討死し、豊臣軍の紀州方面からの攻撃は完全に頓挫した 8 。この戦いの最大の戦功は、まぎれもなく敵将・塙団右衛門を討ち取ったことであった。しかし、この功績を巡り、史料によって記述は異なり、長く論争の的となってきた。
塙団右衛門は、ただの武将ではない。「夜討ちの大将」としてその名を天下に轟かせた著名な武将であり、その首級は、大坂夏の陣の緒戦における勝利を象徴する、最高の「栄誉」であった 12 。この象徴的な価値を持つ戦果を誰が得たのかが、戦後の藩内における発言力や名誉に直結することは自明であり、これが高綱と、同じくこの戦いで大功を挙げたとされる同僚・上田重安との間に、修復不可能な亀裂を生むことになる。
この論争を理解するため、各史料の記述を比較検討する必要がある。
表1:樫井の戦いにおける塙団右衛門の最期に関する史料比較
|
史料名 |
成立時期 |
記述の要点(討ち取ったとされる人物) |
史料の性格と背景 |
|
『泉州樫井表合戦次第覚書』 |
江戸初期 |
亀田高綱の部隊の功績として詳細に記述。高綱自身が指揮し、豊臣軍を誘引、撃破した過程を正当化 。 |
高綱自身による一次史料。自己の功績を主張し、異なる見解に反論する意図が明確である 。 |
|
『芸藩輯要』など広島藩公式記録 |
江戸中期以降 |
上田重安(宗箇) の戦功として記録される傾向が強い。重安自身、あるいはその配下が挙げた功績として扱われる 。 |
藩の公式史書。藩内の序列や政治的バランス、藩主の意向が反映された記述の可能性がある。 |
|
『難波戦記』 |
江戸中期 |
横井平左衛門という浅野家臣が討ち取ったとされる 。 |
後世に成立した軍記物語。英雄譚としての脚色や、講談的な要素が含まれる可能性を否定できない。 |
|
『常山紀談』 |
江戸中期 |
浅野家の武功として総括的に記述。個別の武将の名は挙げるものの、誰が討ち取ったかまでは断定していない。 |
武将の逸話集。個別の功績の帰属よりも、武士としての働きや教訓的な側面を重視する傾向がある。 |
この論争は、単なる手柄争いという側面だけでなく、より大きな時代の変化を映し出している。それは、戦国時代から江戸時代への「合戦報告システム」の変容である。個々の武士が自己の働きを直接主張する戦国的な「自己申告制」の論理と、藩という組織全体として戦果を管理・公認し、藩内の秩序を優先する近世的な「公式記録」の論理。高綱は前者の論理に立脚して自己の絶対的な武功を主張し、一方の浅野家(藩)は後者の論理に基づき、藩内の融和や序列を考慮した見解を採用した。結果として高綱の主張は退けられ、彼のプライドは深く傷つけられた。彼の後の致仕は、この新しい時代のシステムに対する、最後の抵抗であったのかもしれない。
第四章:浅野家家老として ― 紀州から安芸へ
4-1. 広島藩の成立と家老配置
大坂の陣が終結し、世に泰平が訪れると、大名配置にも大きな動きがあった。元和5年(1619年)、広島藩主であった福島正則が武家諸法度違反を理由に改易されると、その後任として浅野長晟が紀州和歌山から安芸広島42万6500石余へと転封された 16 。
新たな領地に入った長晟は、藩の統治体制を固めるため、重臣たちの配置を決定した。当初、広島藩は浅野知近、浅野忠吉、上田重安、そして亀田高綱の四家老体制で発足した 16 。高綱は、浅野家が甲斐、紀州、そして安芸へと移る中で、常に家老として重用され続けた宿老であった。
4-2. 備後東城の領主として
知行割において、高綱は備後国東城(現在の広島県庄原市東城町)に7,000石(『元和五年 広島藩浅野家分限帳』によれば7,300石)の知行地を与えられた 16 。東城は広島藩の北東端、備中との国境に位置する軍事上の要衝であった。藩境に譜代の重臣を配置するのは、外敵の侵入を防ぐという明確な軍事的意図に基づくものであり、高綱が藩の防衛線において極めて重要な役割を期待されていたことがわかる 16 。
しかしこの配置は、別の側面も持っていた。藩主長晟が、高綱の能力を藩政を統括する「官僚」としてよりも、あくまで国境を守る「将帥」として高く評価していたことを示唆している。これは、泰平の世にあっても彼が純粋な武人として扱われたことを意味し、彼の自己認識を強固にする一方で、広島城下で展開される藩の中枢における政務や複雑な人間関係からは、物理的に距離を置かせる結果となった。この城下との距離が、後に上田重安との対立が先鋭化した際に、彼を情報戦や派閥力学において不利な立場に置き、孤立を深める一因となった可能性は十分に考えられる。
4-3. 逸話:江戸城の石垣普請
後世に編纂された逸話集『続々戦国武将逸話集』には、「亀田高綱、江戸城の石垣を築く」という一節が見られる 22 。これは、幕府が諸大名に命じた天下普請の一環として、浅野家が担当した江戸城の石垣工事に、高綱が奉行などの責任者として関わったことを示唆するものである。しかし、この逸話は同時代の一次史料で確証を得ることが難しく、彼の武人としての名声から後世に生まれた伝説である可能性も考慮に入れる必要がある。とはいえ、彼が武功だけでなく、土木普請のような行政手腕も期待される立場にあったことを窺わせる興味深い伝承である。
第五章:上田重安との対立と致仕 ― 武士の意地
5-1. 対立の構図:武辺一徹と風流武人
高綱の運命を決定づけたのが、同僚家老である上田重安との対立であった。上田重安、後の茶人・上田宗箇は、高綱と同じく数々の戦場を渡り歩いた歴戦の武将でありながら、茶道上田宗箇流の流祖としてその名を馳せた、当代一流の文化人でもあった 15 。
二人の対立は、単なる樫井の戦いの論功を巡る個人的な確執に留まらない。それは、二つの異なる武士像の衝突であったと解釈できる。一方は、戦場での武功のみを絶対的な価値とし、それに誇りを持つ旧来の「武辺一徹」な武士像を体現する亀田高綱。もう一方は、武芸百般に通じながらも、茶の湯や作庭といった風流の道にも深く通じた、近世的な「風流武人」としての新たな武士像を体現する上田重安。時代の変化の中で、どちらの価値観が藩の重臣としてふさわしいかと見なされるか、という問題でもあった。
5-2. 寛永元年の決裂
対立の背景には、浅野家内部の権力構造の変化も大きく影響していた。高綱を高く評価し、蔚山城で命を救われた恩義を感じていた旧主・浅野幸長は既にこの世になく、藩主は弟の長晟に代わっていた。長晟にとって高綱は「父の恩人」ではあるが、直接的な主従の絆は幸長の時代ほど強くはなかった。さらに、広島入封直後には筆頭家老であった浅野知近が長晟によって粛清される事件が起こるなど、藩内の統制は未だ不安定な状態にあった 16 。
このような状況下で、幸長時代の「恩人」という立場や、自らが絶対と信じる武功だけでは、高綱の主張はもはや通らなくなっていた。そして寛永元年(1624年)、ついに樫井の戦いの論功を巡って上田重安と公の場で激しく争った末、高綱は自ら浅野家を退去するという道を選ぶ 1 。7,000石を超える大身の家老という地位を投げ打ち、自らの名誉が認められないことに納得できず全てを捨てて藩を去るという決断は、彼の戦国武将としての矜持がいかに強烈なものであったかを物語っている。彼の致仕は、旧主との個人的な信頼関係に依存した権威が、新しい時代の藩政システムの中ではもはや通用しなくなったことの悲しい証明であった。それはまた、戦乱の時代に絶大な功績を挙げた創業の功臣が、泰平の世ではその剛直な気性がかえって統治の妨げと見なされ、組織の中で居場所を失っていくという、近世初期の大名家が抱えた普遍的な問題の一例でもあった。
第六章:晩年と遺されたもの ― 筆による最後の戦い
6-1. 鉄斎員徳として
浅野家を去った高綱は、俗世との縁を断ち、出家して「鉄斎員徳(てっさいいんとく)」と号した 3 。はじめは商都・和泉国堺に身を寄せ、その後、聖地・高野山に隠棲したと伝えられる 1 。かつて戦場を駆け巡った老武将は、静かな余生を送ることを選んだかに見えた。
6-2. 二つの覚書の執筆
しかし、彼の戦いはまだ終わっていなかった。物理的な戦場からは引退したものの、彼の精神は、自らの名誉を回復するための最後の戦いに挑んでいた。隠棲生活の中で、彼は筆をとり、自らの生涯と武功を後世に伝えるための二つの重要な記録を執筆した。
一つは**『亀田大隅一代働覚』。これは、柴田家臣時代から浅野家での活躍に至るまで、彼の生涯全体の軍功をまとめた自伝的な記録である 1 。もう一つが、
『泉州樫井表合戦次第覚書』**である。これは、彼の人生の頂点であり、同時に挫折の原因ともなった樫井の戦いの詳細な経過を、自らの視点から克明に記したものであった 1 。
これらの執筆活動は、単なる過去の回顧録ではない。それは、藩の公式見解によって汚された自らの名誉に対する「歴史への上訴」であり、「筆によって失われた名誉を回復しようとする最後の戦い」であった。藩という公的な場での評価に敗れた彼が、後世の評価という別の土俵で、自らの正当性を訴えたのである。これらの記録は、客観的な史実を伝えるという以上に、一人の武士が「名誉」をいかに重んじ、それを守るために人生の最終盤で何をしたかを示す、極めて人間的なドキュメントとして、計り知れない価値を持っている。
6-3. 最期と供養塔
筆による最後の戦いを終えた高綱は、寛永10年(1633年)8月13日、76年の波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。その墓所(供養塔)は、和歌山県の高野山奥の院に現存しており、苔むした五輪塔が、時代の激流に抗い続けた一人の武士の生き様を静かに今に伝えている 4 。
終章:亀田高綱という生き方 ― 時代に殉じた武士の矜持
亀田高綱の生涯を振り返るとき、我々が目にするのは、自己の武勇とそれによって得られる名誉に絶対的な価値を置く、「戦国武将」の理想像そのものである。彼は、主君の危機には身を挺してこれを救い、自らの手柄は正当に評価されるべきだと信じて疑わなかった。その生き方は、戦乱の世においては最高の美徳であった。
しかし、彼の悲劇は、その理想像が、中央集権化と官僚制化を推し進める近世封建社会の新たな秩序とは、必ずしも相容れないものであった点にある。個人の武功よりも藩全体の調和が優先され、主君との個人的な絆よりも組織の論理が重んじられる時代において、彼の「武辺一徹」な生き方は、次第に「扱いにくい」ものと見なされるようになった。
彼は、新しい時代に自らを合わせるのではなく、自らの信条に殉じる道を選んだ。その結果、泰平の世に安住の地を失うことになった。しかし、その頑固なまでの生き様と、自らの手で真実を記録し後世に遺そうとした執念は、時代の転換期における武士の「名誉」のあり方とは何かを、我々に鋭く問いかける。亀田高綱の物語は、単なる一武将の伝記に留まらない。それは、近世社会が成立する過程で生じた価値観の変容と、その中で生きることを余儀なくされた人間の葛藤を映し出す、一つの優れた歴史的証言なのである。
引用文献
- 亀田高綱(かめだ・たかつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%80%E7%94%B0%E9%AB%98%E7%B6%B1-1067250
- 近世軍記生成の一過程 (二) https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/4826/files/KU-1100KB-20080300-14.pdf
- 亀田高綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%80%E7%94%B0%E9%AB%98%E7%B6%B1
- 亀田大隅守供養塔 https://gururinkansai.com/kamedaosuminokami.html
- 3. 丸岡城天守の大工に関する言い伝え - 坂井市 https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kokuhou/maruokajyou/documents/no9-ab.pdf
- 浅野幸長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E5%B9%B8%E9%95%B7
- 落穂集第十一巻 http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_otiboa11g.html
- 樫井の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AB%E4%BA%95%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 大坂夏の陣、樫井の戦い - ホテルアストンプラザ関西空港 https://www.aston-kix.com/blog/3269
- 第54話 団右衛門討死す - 豊臣秀頼と七人の武将ー大坂城をめぐる戦いー(木村長門) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054884619343/episodes/1177354054888206747
- 大阪夏の陣 - 泉佐野市立図書館:いずみさのなんでも百科 https://library.city.izumisano.lg.jp/izumisano/nandemo/o/oosakanatunojin.html
- 塙団右衛門 - 泉佐野市立図書館:いずみさのなんでも百科 https://library.city.izumisano.lg.jp/izumisano/nandemo/ha/bandanemon.html
- 塙直之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%99%E7%9B%B4%E4%B9%8B
- 研究叢書371 軍記物語の窓 第三集 - 和泉書院 https://www.izumipb.co.jp/smp/book/b571837.html
- 上田重安とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%AE%89
- 広島県立文書館紀要 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/kiyo/kiyo_08.pdf
- 平成30年度歴史講座「江戸時代の広島~浅野家と広島藩~」(前期)第1回「浅野長晟・光晟の政治と藩体制の確立」 - 広島市立図書館 https://www.library.city.hiroshima.jp/hiroshima/asano/asano400/20180609.html
- 広島藩家臣のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_hirosima.html
- 備後東城の歴史 - BIGLOBE http://www2s.biglobe.ne.jp/~yappon/tohjoh4.html
- 元和五年 広島藩浅野家分限帳 https://shiryobeya.com/edo/asanobungen_g5.html
- 広島県立文書館紀要 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/kiyo/kiyo_12.pdf
- 続々 戦国武将逸話集 [978-4-585-05443-6] - 勉誠社 https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100262
- 上田重安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%AE%89
- 宮本地車噺 http://www.eonet.ne.jp/~shiro-emj/zigurumabanashi.html
- 2019年の歴史楽会講義内容概略 https://4351gakureki.jimdofree.com/%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%A6%82%E7%95%A5%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1/
- 史籍集覧 : 改定 第16冊 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000527930