二木重高
二木重高は信濃の国人領主。塩尻峠で武田に寝返るも、野々宮合戦で小笠原氏に忠節を示し、主君の密命を受け武田に仕えた。子の代で小笠原家再興を果たす。
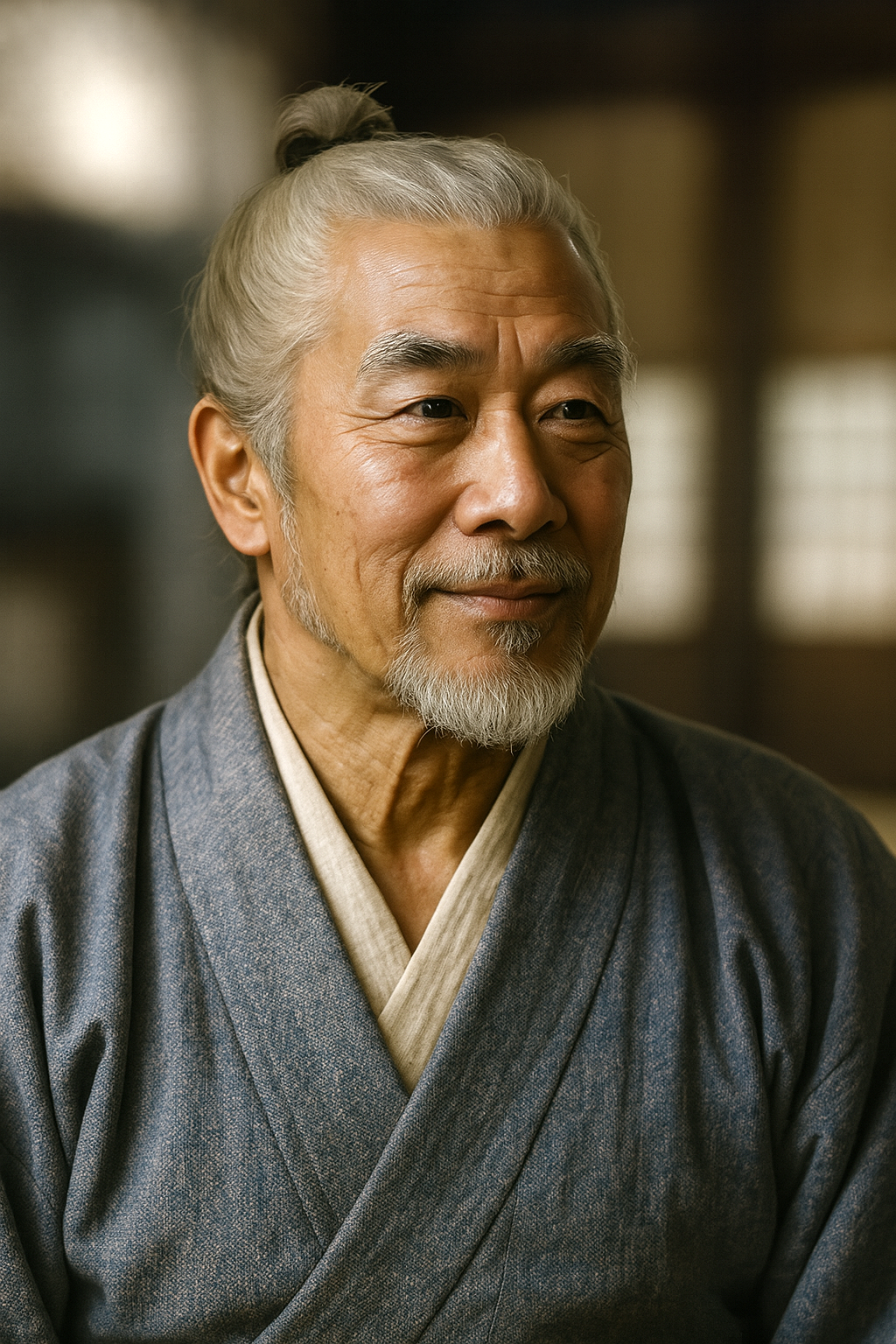
信濃の風雲児、二木重高の実像:裏切りと忠節の狭間で生きた武将の生涯
序章:信濃の風雲と二木重高
戦国時代の信濃国は、まさに群雄割拠の様相を呈していた。守護たる小笠原氏の権威は、府中の宗家と伊那の松尾家との内訌などによって著しく低下し、その統制力は国内の隅々まで及ばなくなっていた 1 。この力の空白を突くように、隣国・甲斐の武田晴信(後の信玄)が、その版図拡大の野望を信濃へと向け、猛烈な勢いで侵攻を開始する。信濃の国人領主たちは、旧来の主家である小笠原氏に殉じるか、新興の武田氏に降るか、あるいは独自の活路を見出すかという、過酷な選択を迫られていた。
このような激動の時代、信濃国安曇郡を本拠とした一人の武将がいた。その名を二木重高(ふたつぎ しげたか)という。小笠原氏配下の有力な国人でありながら、その生涯は「裏切り」と「忠誠」という、一見すると矛盾に満ちた行動の連続であった。主家を裏切り大敗の要因を作りながら、後には一族を挙げて主君を支え、ついにはその主君の宿敵であった武田氏に仕える。彼の行動は、単純な忠奸の二元論では到底測ることができない。
本報告書は、この二木重高という複雑な人物の生涯を、断片的な逸話の紹介に留めることなく、その出自から、彼が生きた時代の地政学的状況、そして彼を取り巻く人間関係を深く掘り下げることで、その行動の背後にあった論理と戦略を解き明かすことを目的とする。彼の生涯は、単なる一個人の物語ではない。それは、大勢力の狭間で翻弄されながらも、一族の存続という至上命題と、主家再興という遠大な目標を両立させようとした、ある国人領主の壮大な生存戦略の記録なのである。
付属資料:二木重高 関連年表
本編に入るに先立ち、二木重高の生涯と彼を取り巻く情勢の変遷を理解するため、関連年表を以下に記す。
|
西暦(和暦) |
二木重高・一族の動向 |
小笠原氏の動向 |
武田氏の動向 |
関連事項 |
|
南北朝時代 |
小笠原貞宗の子・政経が安曇郡二ツ木郷の地頭となり、二木氏の祖となる 2 。 |
小笠原貞宗が足利尊氏に従い、信濃守護職を得る。 |
|
|
|
1440年(永享12) |
二木貞明が結城合戦で小笠原政康に従い出陣 3 。 |
幕府の命により結城氏討伐に参加。 |
|
|
|
1548年(天文17) |
塩尻峠の合戦で武田方に寝返る 2 。 |
小笠原長時、武田軍と塩尻峠で戦うも大敗。 |
武田晴信、小笠原軍を撃破。 |
|
|
1550年(天文19) |
野々宮合戦で小笠原方として戦功を挙げる 。長時を中塔城に匿う 2 。 |
長時、村上義清の援軍を得て府中奪還を図るも、林城を攻略され敗走。 |
晴信、長時の本拠地・林城を攻略し、筑摩郡を制圧 3 。 |
|
|
1550-1554年 |
長時を中塔城で庇護。 |
長時、中塔城に籠城後、越後の長尾景虎(上杉謙信)を頼る 2 。 |
|
|
|
1554年(天文23) |
長時の密命を受け、武田氏に臣従 2 。 |
長時、越後へ流亡。 |
|
|
|
1555年(弘治元/天文24) |
三村長親の讒言を受けるも、潔白を証明。長親の謀反鎮圧に功を挙げる 2 。 |
|
三村長親を粛清。 |
|
|
1555年以降 |
三村勢との戦功により加増を受けるが、 以降の消息は不明となる 2 。 |
長時、京で三好長慶を頼り、足利将軍家の師範役となる 1 。 |
|
|
|
1582年(天正10) |
一族の岩波平左衛門が武田勝頼に反旗を翻す 2 。子の重吉らが貞慶擁立を画策。 |
長時の子・貞慶が徳川家康を頼り、信濃帰還の機を窺う 4 。 |
織田信長の甲州征伐により武田氏滅亡。 |
本能寺の変。天正壬午の乱が勃発。 |
|
1582年(天正10) |
子の重吉らが貞慶を迎え入れ、深志城奪還に成功 7 。 |
貞慶、旧臣の支援を得て深志城を奪還し、松本城と改名 4 。 |
|
|
|
1590年(天正18) |
小笠原秀政の古河移封に従う 3 。 |
小笠原秀政(貞慶の子)、徳川家康の関東移封に伴い下総古河へ。 |
|
|
|
1611年(慶長16) |
子の二木重吉が、主君・秀政の命で『二木家記』を著す 8 。 |
|
|
|
第一章:清和源氏小笠原氏の支流、二木氏の出自
二木重高の行動原理を理解する上で、その出自を看過することはできない。二木氏は、信濃国に深く根を張った名門、清和源氏小笠原氏の支流にあたる一族である 3 。この事実は、彼らが単なる在地土豪ではなく、信濃守護家と血の繋がりを持つ、誇り高き武士団であったことを示している。
その起源は、鎌倉幕府が滅亡し、新たな秩序が模索されていた南北朝時代にまで遡る。当時、小笠原氏の惣領であった小笠原貞宗は、足利尊氏に従って「中先代の乱」などで軍功を挙げ、信濃守護としての地位を確立した。この貞宗が、四男である政経に対し、自身の所領であった安曇郡住吉庄内にある二ツ木郷の地頭職を分与した 2 。これが、二木氏の直接の始まりである。二ツ木郷に居を構えた政経の子孫は代を重ね、やがて小七郎貞明の代に至り、その地名にちなんで「二木」を家号(苗字)として名乗るようになったと伝えられている 2 。
二木氏が小笠原宗家の単なる分家ではなく、譜代の重臣として重要な役割を担ってきたことは、その後の歴史が証明している。室町時代中期、関東で将軍家と鎌倉公方との対立が激化して勃発した永享の乱(1438年)や、それに続く結城合戦(1440年)において、二木氏は小笠原宗家の当主に従って関東へ出陣し、軍の先鋒を務めるなど、その武勇を示した記録が残っている 3 。これは、二木氏が代々にわたり、小笠原家の軍事力の中核を担う存在であったことを物語るものである。
彼らが単なる家臣ではなく、主家と血縁を共有する「御一門」であったという事実は、後の二木重高の行動を読み解く上で極めて重要な鍵となる。彼らの忠誠心は、主君個人というよりも、「小笠原家」という血族共同体そのものに向けられていた可能性が高い。したがって、主君である小笠原長時の判断が、必ずしも「小笠原家」全体の利益に繋がらないと考えた時、彼らが一門の有力支族として、宗家の衰退を座視できずに独自の判断を下すことは、彼ら自身の論理においては、より高次の忠誠の発露と見なされたのかもしれない。この視点こそ、重高の生涯に付きまとう「裏切り」と「忠誠」の矛盾を解き明かすための出発点となるのである。
第二章:裏切りと忠節 ― 塩尻峠と野々宮合戦の狭間で
二木重高の名を戦国史に刻みつけた最初の出来事は、天文17年(1548年)に勃発した塩尻峠の合戦である。この戦いにおいて、重高は主君を裏切るという、後世にまで語り継がれる行動に出る。
天文17年(1548年)塩尻峠の合戦と重高の寝返り
当時、武田晴信の信濃侵攻は熾烈を極めていた。これに対し、信濃守護の小笠原長時は、武田軍を領内で迎撃すべく大軍を率いて出陣する。二木重高もまた、小笠原配下の有力武将としてこの軍勢に加わり、塩尻峠で武田軍と対峙した 2 。しかし、合戦の最中、重高は突如として武田方に寝返った。この予期せぬ内応は、小笠原軍の指揮系統を混乱させ、結果として軍は総崩れとなり、長時は惨敗を喫した 2 。
この寝返りは、重高一人の気まぐれや臆病さによるものではなかった。当時、圧倒的な軍事力で信濃に迫る武田氏を前に、多くの信濃国人衆が動揺していた。実際に、この合戦では二木氏だけでなく、洗馬の三村氏や山家氏といった他の小笠原配下の国人たちも、雪崩を打って武田方に降っている 3 。これは、小笠原氏の統率力がもはや限界に達しており、国人たちが自らの領地と一族の存続のため、より強大な勢力である武田氏に靡くのは、いわば自然な流れであったことを示している。重高の行動は、この大きな潮流の中の一つとして捉えるべきであろう。
天文19年(1550年)野々宮合戦での戦功
ところが、塩尻峠での「裏切り」からわずか2年後、重高は再び歴史の表舞台に、今度は全く逆の立場で登場する。天文19年(1550年)、小笠原長時は武田氏に奪われた本拠地・府中の回復を目指し、北信濃の雄・村上義清の支援を得て反撃に転じた。この野々宮(現在の松本市)で行われた合戦において、二木重高は一転して小笠原方として奮戦し、武田軍を撃退する上で大きな武功を挙げたのである 2 。
この戦功は長時から高く評価され、ある記録では、この功績によって正式に「二木」の姓を許されたとさえ記されている 5 。また別の記録では、この戦いを契機に、長時を守るための拠点として中塔城を築き、その守りを任されたとも伝えられている 4 。いずれにせよ、この時点での重高は、紛れもなく小笠原家への忠節を尽くす武将として振る舞っていた。
一見すると、この二つの行動は全くの矛盾であり、重高を「風見鶏」のような日和見主義者と断じることもできよう。しかし、これは戦国時代の国人領主が置かれた厳しい現実を色濃く反映した、極めて合理的な生存戦略であったと解釈できる。武田という抗いがたい軍事力の前に、まずは一時的に恭順の意を示すことで自領と一族の安全を確保する(塩尻峠での寝返り)。そして、主家が反撃の好機を得て、勝機が見えたと判断すれば、再び馳せ参じて旧主への恩義を果たすと共に、武田方から離反する(野々宮での忠節)。彼の行動は、忠誠心や大義といった抽象的な理念よりも、変化する戦況を冷静に分析し、その都度、自らの一族にとっての最適解を選択し続けた結果なのである。この冷徹なまでの現実主義と柔軟性こそが、二木重高という武将が乱世を生き抜くために身につけた、最大の武器であったと言えるだろう。
第三章:主君の流浪と「草の種」の密命
野々宮合戦で一時的に武田軍を退けた小笠原氏であったが、大勢を覆すには至らなかった。武田晴信はすぐさま体勢を立て直し、天文19年(1550年)7月には長時の本拠地である林城を攻略。これにより、長時はついに拠点を失い、流浪の身となる 3 。この絶体絶命の窮地において、長時に救いの手を差し伸べたのが、二木重高であった。
最後の拠点・中塔城
重高は、敗走してきた主君・長時を、自らの本拠地である中塔城に迎え入れ、一族を挙げて庇護した 3 。中塔城は、現在の長野県松本市梓川地区に位置し、標高1200メートルを超える険峻な山上に築かれた天然の要害であった 6 。周囲を切り立った谷に囲まれ、容易に大軍が近づくことのできないこの山城は、まさに「日本中の軍勢が攻め寄せても決して落ちることはない」と評されるほどの難攻不落の拠点であった 14 。この城の存在こそが、二木氏が武田軍の追撃から長時を守り抜くことを可能にした物理的な基盤となった。長時はこの山中の「小屋」とも呼ばれる質素な城で、再起の機会を窺いながら、約2年間にわたる籠城生活を送ったとされている 4 。
「草の種」の逸話
しかし、信濃の大半が武田の手に落ちた状況では、中塔城での抵抗にも限界があった。天文23年(1554年)頃、長時はついに信濃からの脱出を決意し、再起を期して越後の長尾景虎(後の上杉謙信)を頼ることになる。この越後へ落ち延びるに際して、長時が重高に下したとされる密命が、二木氏の運命を決定づけることになった。
複数の史料が伝えるところによれば、長時は重高に対し、次のように語ったという。
「そなたは信濃に残り、法を講じて晴信に属し(降伏して)、本領を維持せよ。そして、予が他年本意を達するの日(私がいつか本懐を遂げる日)の、『草の種』となってくれ」 4。
これは、重高に敢えて武田氏に偽りの降伏をさせ、信濃国内に小笠原再興の拠点を潜伏させるという、壮大な潜伏戦略の指示であった。重高は涙ながらに上方への供を願い出たが、長時は「そなたはこらえ性のある人物だ。だからこそ晴信に仕え、我が本意の日を待って欲しい」と懇願したと伝えられる 15 。この密命を受け入れた重高は、主君と袂を分かち、信濃の地に留まる道を選んだのである。
この「草の種」の逸話は、二木重高のその後の全ての行動、すなわち武田への臣従を、「裏切り」や「変節」ではなく、「主君の密命に基づく忍従」として再定義する、極めて重要な物語装置となっている。この逸話の歴史的真実性については、慎重な検討を要する。なぜなら、この物語は主に二木氏自身が後年に編纂した『二木家記』などの史料に見られるものであり、武田に仕えたという一見「不忠」に見える行為を、主君の密命という「至忠」の物語に転換するための、後世の脚色や正当化である可能性も否定できないからである 16 。
しかし、たとえこの逸話が史実そのものではなかったとしても、この物語が二木一族の中で固く信じられ、世代を超えて語り継がれたという事実こそが、歴史的にはより重要である。この「草の種」という共通の目的意識があったからこそ、二木一族は武田の支配下にあっても小笠原家への帰属意識を失わず、約30年後の天正10年(1582年)、武田家滅亡という千載一遇の好機が訪れた際に、一族が一丸となって迅速に行動を起こすことができたのである。史実性の問題を越えて、「草の種」の逸話は、二木一族のその後の歴史的運命を方向づけた、精神的な支柱であったと評価することができる。
第四章:武田家臣としての忍従 ― 讒言事件と知略
主君・小笠原長時を越後へ送り出した二木重高は、「草の種」となるべく、その身を翻して武田信玄の傘下に入った。これは、彼の人生において最も困難で、かつ知略が試される時代の幕開けであった。
武田信玄への臣従と猜疑
長時が去った後、重高は信濃の国人・大日方上総の仲介を経て、正式に武田氏に降伏した 5 。信玄は彼の降伏を受け入れ、旧領である安曇郡二木の地を安堵し、その所領を保証した 5 。しかし、信玄は重高を完全には信用していなかった。「猜疑心の強い信玄は、この一族に心を許さなかった」と記録されるように、一度は主家を裏切り、そして再び主家のために戦った重高の複雑な経歴は、信玄にとって常に警戒の対象であった 5 。
この信玄の猜疑心に火を注いだのが、同じく小笠原旧臣でありながら武田に降っていた、洗馬の三村長親であった。三村氏は小笠原時代から二木氏とは犬猿の仲であり、この機に乗じてライバルを蹴落とそうと画策する 5 。弘治元年(1555年)、三村長親は信玄に対し、「二木氏は、ひそかに旧主・小笠原長時を飛騨まで呼び寄せ、武田家への謀反を企てております」と、根も葉もない讒言を行ったのである 5 。
讒言事件と重高の決断
この報告に激怒した信玄は、直ちに二木一族の主だった者たちに対し、甲府へ出頭せよとの厳命を下した 5 。当時の信濃において、謀反の疑いをかけられて甲府に召喚され、無事に帰還できた者はほとんどいなかった。一族内は騒然となり、「甲府へ行けば必ず殺される。いっそ中塔城に籠城し、一戦交えようではないか」という主戦論が巻き起こった 5 。
しかし、この絶体絶命の危機において、重高は冷静であった。彼は一族を制し、こう述べたという。
「それでは一族の全滅は火を見るより明らかである。甲府へ出頭し、精一杯の申し開きをし、運を天にまかそうではないか」 5。
これは、武田家との圧倒的な軍事力の差を的確に認識し、武力での抵抗が無益であることを理解した上での、極めて現実的な判断であった。同時に、自らの潔白に対する強い自信の表れでもあった。
対決と潔白の証明、そして消息
重高の予想通り、甲府で彼らを待っていたのは一方的な処刑ではなかった。信玄は、重臣の山県昌景を検分役とし、訴えた三村長親と訴えられた二木重高を直接対決させ、その真偽を究明させようとしたのである 5 。この対決の場で、重高は少しも臆することなく、冷静沈着に三村の讒言が偽りであることを論証し、見事に身の潔白を証明した 2 。
皮肉なことに、この事件の後、讒言を弄した三村長親自身が武田家に対して謀反を起こした。信玄は当初「重高に図られた(してやられた)」と嘆いたが、その重高が馬場信春らと共にこの反乱を鎮圧する上で大きな功績を挙げたと聞くに及び、自らが重高の至誠を見抜けなかったことを深く恥じたという逸話が残されている 2 。この事件は、重高が単なる武辺者ではなく、窮地において冷静な判断力と弁舌で道を切り開く、優れた知将であったことを証明している。
この功績もあり、同年、三村勢が武田方の深志城(松本城)を攻撃した際には、重高は城に入って防戦に努め、戦功によって八十貫文の加増を受けた 5 。しかし、この記録を最後に、二木重高個人の消息は歴史の表舞台から忽然と姿を消す 2 。その後の彼がいつ、どこで、どのように生涯を終えたのか、それを伝える確かな史料は現存していない。彼は「草の種」としての役目を全うし、静かに歴史の陰へと退いていったのである。
第五章:重高没後の二木一族と小笠原家再興の実現
二木重高個人の記録は途絶えるが、彼が蒔いた「草の種」は、信濃の地に深く根を張り、静かに発芽の時を待っていた。その物語は、重高の子の世代へと受け継がれ、約30年の時を経て、劇的な形で結実することになる。
天正壬午の乱と好機の到来
重高の消息が不明となった後も、二木一族は武田家の家臣として、信濃安曇郡の旧領を維持し続けた。そして天正10年(1582年)、戦国の情勢は一気に動く。織田信長の甲州征伐によって、あれほど強大を誇った武田氏があっけなく滅亡。さらにそのわずか3ヶ月後には、信長自身が本能寺で横死する。強大な支配者を相次いで失った信濃国は権力の空白地帯と化し、越後の上杉氏、小田原の北条氏、三河の徳川氏、そして地元国人の木曽氏らが覇権を争う「天正壬午の乱」と呼ばれる大混乱に陥った 6 。この混乱こそ、二木一族が待ち望んでいた千載一遇の好機であった。
「草の種」の発芽 ― 小笠原貞慶の帰還
この機を逃さず、迅速に行動を起こしたのが、重高の子で家督を継いでいた二木重吉(豊後守を襲名)であった。彼は一族を率い、同じく小笠原家の再興を願う旧臣たちと連携し、かつての主君・小笠原長時の嫡男で、当時は三河で徳川家康の庇護下にあった小笠原貞慶を、信濃の主として迎え入れるべく画策を始める 3 。
二木一族をはじめとする旧臣たちの決死の働きかけにより、貞慶は徳川家康の後援を得て信濃へ進軍。同年7月、武田氏滅亡後に深志城を支配していた木曽氏の勢力を駆逐し、ついに父祖の地である府中を奪還することに成功した 4 。貞慶は、この城の名を「深志城」から「松本城」へと改名。ここに、長時が信濃を追われてから約30年、二木重高が「草の種」の密命を受けてから実に28年の歳月を経て、小笠原家の府中復帰という悲願が達成されたのである。
小笠原家重臣としての二木氏
主家の再興に最大の功績を挙げた二木一族は、貞慶から絶大な信頼を寄せられ、新生小笠原家の中核を担う重臣として重用された。武田氏滅亡後に小笠原氏に敵対した西牧氏が討伐されると、その旧領の代官職に任命され、地域の支配を任された 4 。また、天正12年(1584年)に貞慶が麻績城を攻めた際には、重吉は松本城の留守居を命じられるという、軍事上の要職を託されている 3 。さらに、千見城の普請奉行を務めるなど、小笠原家の領国経営において不可欠な存在となっていった 4 。
この一連の出来事は、二木重高の深謀遠慮がいかに正鵠を射ていたかを証明している。彼がもし、目先の感情に駆られて武田氏に玉砕覚悟の抵抗を試みていれば、一族は滅亡し、小笠原家再興の礎となることもなかったであろう。彼の忍従があったからこそ一族は存続し、その子の世代が好機を捉えて主家再興を成し遂げることができたのである。重高の行動は、30年後を見据えた長期的な投資であり、それは「近世大名小笠原氏の誕生」という、この上ない形で結実したと言える 5 。
そして慶長16年(1611年)、二木重吉は主君である小笠原秀政(貞慶の子)の要請に応じ、一族の波乱に満ちた歴史を後世に伝えるため、その記録を『二木家記』として著した 8 。この書物こそ、父・重高から受け継いだ「草の種」の物語の、集大成であった。
終章:再評価 ― 裏切り者か、至誠の武将か
二木重高の生涯を振り返る時、我々は「裏切り者」か「忠臣」かという、単純な問いの前に立つ。塩尻峠での寝返りという一点を切り取れば、彼が「裏切り者」の汚名を着ることは避けられない。しかし、その後の野々宮合戦での忠功、窮地の主君・長時を難攻不落の中塔城で庇護した献身、そして「草の種」となるべく武田家臣として耐え忍んだ知略、さらには彼が蒔いた種が子の代で見事に開花し、主家再興という大事業に結実した一連の生涯を俯瞰する時、その人物像は全く異なる様相を呈してくる。
二木重高は、単なる裏切り者でもなければ、盲目的な忠臣でもなかった。彼は、戦国という激動の時代において、「一族の存続」という国人領主としての絶対的な使命と、「小笠原家への忠誠」という名門としての矜持を両立させるために、時に非情とも思える現実的な選択を厭わなかった、深謀遠慮の戦略家であったと結論付けるのが最も妥当であろう。彼の行動原理の根底には、常に「家」の存続と繁栄があった。主君に背くことも、敵に仕えることも、全ては「二木家」そしてその本家である「小笠原家」という、より大きな共同体を守り抜くための手段に過ぎなかったのである。
彼の生涯は、戦国時代の人物を現代の倫理観や「忠臣」「奸臣」といった単純なレッテルで評価することの危うさを我々に教えてくれる。彼らの行動は、個人の道徳よりも「家」の存続を最優先する当時の価値観と、弱肉強食という厳しい現実の中で理解されねばならない。
また、彼の物語を紐解く上で、『二木家記』のような一族によって編纂された史料が果たす役割の大きさも浮き彫りになる。これらの記録は、一族の行動を正当化する意図を含む一方で、同時代の断片的な記録だけでは窺い知ることのできない、彼らの内面的な動機や行動原理を伝えてくれる貴重な証言でもある。これらの史料を批判的に吟味し、多角的な視点から歴史を再構築することの重要性を、二木重高の複雑で魅力的な生涯は、雄弁に物語っているのである。彼はまさしく、信濃の風雲が生んだ、稀代の武将であった。
引用文献
- 小助の部屋/滋野一党/信濃諏訪氏/信濃小笠原氏/信濃木曽氏 http://koskan.nobody.jp/teki_nansin.html
- 二木重高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9C%A8%E9%87%8D%E9%AB%98
- 武家家伝_二木氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hutagi_k.html
- 安曇野市 二木氏 - 長野県の歴史を探し求めて http://osirozuki.blog.fc2.com/blog-entry-246.html?sp
- 二木重高/戦国Xファイル - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x139.html
- 二木家記 https://kamanasi4321.livedoor.blog/archives/23419094.html
- 舞台保存会だより90 三郷二木の舞台 - 信州松本 天神 深志神社 https://www.fukashi-tenjin.or.jp/hozonkai/2015/10/90/
- 二木重吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9C%A8%E9%87%8D%E5%90%89
- 武家の家紋_二木氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/bukemon/bk_hutagi.html
- 二木重高(ふたつぎしげたか)『信長の野望・創造』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzou_data_d.cgi?equal1=9004
- 二木重高 (ふたつぎ しげたか) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12036151603.html
- 武家家伝_溝口氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/og_mizo.html
- 小笠原一族(小笠原一族と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16988_tour_069/
- 桐原城 林城 林大城 犬甘城 埴原城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/nagano/matumotosi.htm
- 中塔城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/TokaiKoshin/Nagano/Nakatou/index.htm
- 松本市 西牧氏③ | 長野県の歴史を探し求めて http://osirozuki.blog.fc2.com/blog-entry-180.html