天草四郎
天草四郎は江戸初期の島原・天草一揆の指導者。16歳で3万人を率い、原城に籠城。幕府軍の水攻めに抵抗したが、食糧尽き落城し戦死。日本初のキリシタン大名ではない。
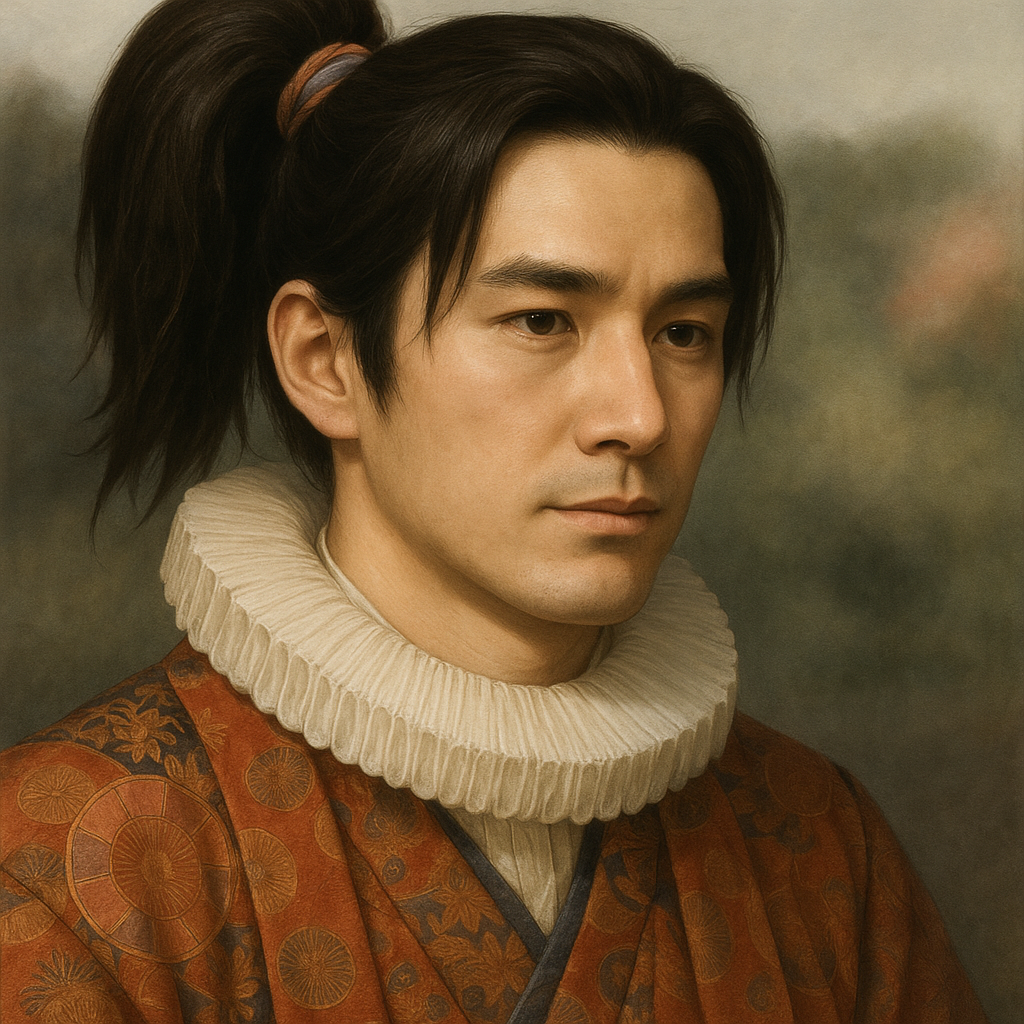
天草四郎の実像:島原・天草一揆とその時代背景に関する詳細調査報告
序章
-
本報告の目的と構成
本報告書は、江戸時代初期の日本において、大規模な民衆蜂起である島原・天草一揆を指導したとされる天草四郎(益田四郎時貞)について、現存する史料や研究成果に基づき、その人物像、一揆における役割、そして歴史的背景と影響を多角的に検証し、総合的にまとめることを目的とする。天草四郎の活躍した時代は、一般に戦国時代と認識されることもあるが、正確には江戸時代初期の寛永年間(1624年~1644年)であり、本報告書ではこの時代認識に基づき論を進める。
特に、天草四郎の実在性、そのカリスマ性の源泉、島原・天草一揆の性格(宗教一揆か農民一揆か、あるいはその複合か)、そして後世における天草四郎像の形成過程に焦点を当てる。
構成としては、第一部で天草四郎の人物像に迫り、その出自、背景、指導者としての資質や役割を明らかにする。第二部では、島原・天草一揆そのものを取り上げ、その勃発の背景、具体的な経過、そして歴史的な意義と評価について詳述する。第三部では、一揆が江戸幕府の政策に与えた影響や、後世の文学、芸術、大衆文化の中で天草四郎のイメージがどのように形成され、変遷していったのかを考察する。 -
天草四郎という人物:歴史的意義と現代における関心
天草四郎は、寛永14年(1637年)に勃発した島原・天草一揆において、当時16歳という若さで3万人以上の一揆軍を率いたとされる点で、日本の歴史上、際立って特異な存在である 1。彼の指導者としての具体的な実態や、一揆における実際の役割については、史料的な制約や後世の脚色も影響し、未だ多くの謎に包まれているのが現状である 3。
島原・天草一揆は、徳川幕府の支配体制を揺るがしかねない大規模な武力蜂起であり、その後の幕府によるキリスト教政策や対外政策のあり方に決定的な影響を及ぼした重要な事件であった 5。
天草四郎自身は、その悲劇的な結末と、若き指導者としてのカリスマ性から、現代に至るまで小説、映画、演劇、漫画、ゲームなど、多岐にわたる創作物の題材とされ、時代ごとに多様なイメージで語り継がれている 8。このことは、天草四郎という人物と彼が関わった歴史的事件が、現代社会においてもなお人々の関心を引きつけてやまない魅力と普遍的なテーマ性を有していることを示している。 -
時代背景の概観:江戸幕府初期の社会状況とキリスト教
島原・天草一揆(寛永14年~寛永15年、1637年~1638年)は、徳川家康による江戸幕府開府から約30年が経過し、三代将軍家光のもとで幕藩体制による全国支配が確立しつつあった時期に発生した。この時代は、武断政治から文治政治への移行期にあたり、社会の安定化が図られる一方で、農民に対する支配と収奪は依然として厳しいものがあった。
キリスト教は、16世紀半ばのフランシスコ・ザビエル来日以降、日本各地に広まり、特に九州地方では多くの信者を獲得し、キリシタン大名の出現も見た。しかし、豊臣秀吉による天正15年(1587年)の伴天連追放令を皮切りに、江戸幕府もキリスト教を禁教とし、その弾圧政策を段階的に強化していった 4。慶長17年(1612年)には幕府直轄領に禁教令が発布され、その後全国へと拡大、キリシタンに対する取り締まりは厳しさを増し、多くの殉教者を出した。
島原半島および天草諸島は、かつて有馬晴信や小西行長といったキリシタン大名の所領であった歴史的経緯から、キリスト教信仰が民衆の間に深く浸透していた地域であった 5。それゆえに、幕府の禁教政策はこれらの地域において特に深刻な影響を及ぼし、住民の生活と信仰に大きな圧迫を加えることとなった。このような時代背景と地域特性が、島原・天草一揆という未曽有の大規模蜂起が発生する土壌を形成したと言える。天草四郎と島原・天草一揆を理解するためには、当時の徳川幕府による支配体制の確立過程、厳しさを増す禁教政策、そして当該地域の領主による苛政と、そこに生きた人々の信仰の実態を多角的に把握することが不可欠である。
第一部:天草四郎の人物像
- 第一章:出自と背景
-
本名、生年、没年、出身地に関する諸説
天草四郎の本名は益田四郎時貞とされ、一般には天草四郎、あるいは天草時貞の名で知られている 1 。彼の生年については、寛永元年(1621年)頃と推定されており、島原・天草一揆が勃発した寛永14年(1637年)には16歳であったとされる 1 。最期を遂げたのは、原城が陥落した寛永15年2月28日(西暦1638年4月12日)である 5 。
その出身地に関しては複数の説が存在する。父である益田甚兵衛(好次)が上天草市大矢野町の出身であり、母マルタも同地の出身であることから、上天草市大矢野町が四郎の生誕地であるとする説が有力視されている 4 。一方で、肥後国宇土(現在の熊本県宇土市)や、当時海外との窓口であった長崎で生まれ育ったとする説も存在する 15 。『長崎地名考』には、四郎が長崎の浜町に居住していたとの記述が見られるが、その信憑性については低いと評価されている 16 。このように出身地について諸説が存在する背景には、天草四郎の幼少期に関する確実な一次史料が乏しいという事情に加え、島原・天草一揆という広範囲にわたる蜂起の指導者であったが故に、後世において各地のキリシタンコミュニティや縁のある地域が、彼との繋がりを強調しようとした可能性が考えられる。特に一揆の中心地の一つであった天草地方では、地域の英雄として四郎を位置づけようとする意識が働いたことも想像に難くない。
|
項目 |
内容 |
典拠例 |
|
本名 |
益田四郎時貞 |
1 |
|
通称 |
天草四郎、天草時貞 |
|
|
生年 |
寛永元年(1621年)頃(推定) |
1 |
|
没年 |
寛永15年2月28日(1638年4月12日) |
5 |
|
出身地 |
諸説あり(肥前国または肥後国天草諸島など。上天草市大矢野町が有力説の一つ) |
4 |
|
父 |
益田甚兵衛(好次)(小西行長旧臣) |
3 |
|
母 |
マルタ(洗礼名) |
4 |
|
養父 |
天草甚兵衛(異説あり) |
8 |
|
洗礼名 |
ジェロニモ(ヘロニモ)、フランシスコ(異説あり) |
3 |
* **家族構成:益田甚兵衛(好次)、母マルタ、養父・天草甚兵衛**
天草四郎の父は益田甚兵衛(本名:益田好次)とされ、キリシタン大名として知られる小西行長の家臣であったと伝えられている [3, 4, 8, 15]。関ヶ原の戦いで小西行長が敗死し、小西家が改易された後は浪人となったと考えられている。この出自は、四郎がキリスト教信仰に親和性を持ち、また新体制に不満を抱く浪人層との間に繋がりを持つ可能性を示唆している。島原・天草一揆においては、小西行長や有馬氏の旧臣といった浪人たちが指導的な役割を果たしたとの記録もあり [5]、四郎の父がその一人であったことは、彼が一揆の指導者として擁立される上で重要な要素であったかもしれない。
母はマルタという洗礼名を持つ女性であった [4, 8, 15]。原城落城後、四郎の首実検が行われた際、母マルタは「四郎は白鳥となって天主の国へ行った」と繰り返し唱えながらも、息子の首を目の当たりにして崩れ落ち、号泣したという悲痛な逸話が残されている [8]。
また、天草甚兵衛という人物の養子となり、それゆえに「天草四郎」と名乗るようになったという説もあるが [8]、これには異説も存在する。
* **幼少期と教育、キリスト教への入信**
天草四郎は幼少の頃から並外れて聡明であり、「神童」と称されていたという [8]。長崎で学問を修めたとされ [4, 16, 17]、この地でキリスト教の教えに触れ、入信したと推測されている [16]。当時の長崎は、鎖国体制が進む中でも海外との交易が行われた唯一の窓口であり、キリスト教文化や南蛮文化の影響が比較的色濃く残っていた地域であった。そのような環境で学んだ経験が、四郎の人格形成や思想に影響を与えた可能性は十分に考えられる。
洗礼名はジェロニモ(Jerônimo、日本の記録ではヘロニモとも)であったとされるが [8]、後にフランシスコに変わったという説も存在する [3]。
父の益田甚兵衛も優れた人物であったとされ、四郎はその父にも劣らない秀才として、学問のみならず剣道にも長けていたという。伯父である甚兵衛(父と同名か、あるいは別の親族か詳細は不明)に親しみ、千々石ミゲルの縁者ともされる千々輪(人物不詳)の弟子となって剣術を学び、また蘆塚某(人物不詳)に師事して軍学を修めたとの記録も残されている [17]。これらの教育が、後に彼が説いたとされる「天地本同根、万物是一体、其間並無尊卑之別」といった平等思想を含む教え [8] の基盤となった可能性も否定できない。
- 第二章:指導者としての天草四郎
-
カリスマ性と求心力:「神童」「救世主」としての評価
天草四郎は、島原・天草一揆において、わずか16歳という若さで3万人から4万人ともいわれる一揆軍を統率したとされている 1。この数は資料によって若干の差異が見られるものの 1、その規模の大きさと指導者の若さは特筆すべき点である。彼はキリシタンの間で強いカリスマ性を有し、熱狂的に崇められていた 2。民衆からは「天童」あるいは「救世主」として奉られ、その言葉や行動は大きな影響力を持った 4。
四郎は「天地本同根、万物是一体、其間並無尊卑之別」という、身分制度を否定するかのような平等思想を含む教義を説いたと伝えられている 8。このような教えは、領主による苛政や厳しい身分制度に苦しむ民衆にとって、大きな希望を与えるものであったと考えられる。
しかし、四郎のカリスマ性は、単に彼個人の資質のみに由来するものではなく、当時の社会状況と深く結びついた複合的な現象であったと捉える必要がある。島原・天草地方は、松倉氏や寺沢氏による過酷な支配とキリシタン弾圧、さらには度重なる飢饉によって、民衆は極度の困窮と絶望の淵に立たされていた 4。このような極限状態は、超自然的な力による救済や、現状を打破してくれる指導者の出現を切望する民衆心理を生み出しやすい。そこに、後述する「ママコフ神父の予言」や、四郎自身の聡明さ、そして端麗であったとも伝えられる容姿 3 などが結びつき、彼を神格化する動きが加速したと考えられる。さらに、一揆の指導的立場にあった浪人たちが、民衆の宗教的情熱を利用し、一揆の結束力を高めるための戦略として、四郎を象徴的な総大将として意図的に擁立したという側面も指摘されている 4。したがって、天草四郎のカリスマ性は、彼自身の持つ資質、時代の要請、そして周囲の演出が相互に作用し合って形成されたものと理解するのが妥当であろう。 -
予言と伝説:ママコフ神父の予言、四郎にまつわる奇跡譚
天草四郎の登場と指導者としての地位確立には、予言や奇跡といった超自然的な要素が深く関わっていたとされる。その中でも特に有名なのが、マルコス・フェレイラ神父(通称ママコフ神父、またはママコス神父)がマカオへ追放される際に残したとされる予言である。「25年の後、一人の神童が現れ、パライゾ(天国)を実現するであろう」というこの予言は 3、困窮と弾圧に苦しむ民衆の間で語り継がれ、16歳で現れた天草四郎こそがその予言の成就者であると信じられるようになった。
さらに、天草四郎は数々の奇跡を行ったという伝説が残されている。「盲目の少女に触れただけで目が見えるようになった」「海の上を歩いて渡った」「手に止まった小鳥が生んだ卵からキリスト教の経文を取り出した」といった奇跡譚がそれである 3。これらの奇跡譚は、キリスト教の福音書に見られるイエス・キリストの奇跡と類似しており、四郎の神格性を高め、民衆の信仰心を煽るために、周囲の者たちによって創作、あるいは既存の物語が四郎に結び付けられて流布された可能性が高いと考えられている 3。
これらの予言や奇跡譚は、絶望的な状況下にあった民衆にとって、天草四郎を現世における救世主として信奉する強力な動機となった。宗教的言説が、社会運動においていかに大きな動員力を持ち得るかを示す顕著な事例と言えよう。厳しい弾圧と貧困に喘ぐ民衆は、超自然的な力による救済を求めやすい心理状態にあり、奇跡譚はこうした民衆の期待に応え、四郎への絶対的な帰依を促し、一揆への参加と団結を強固にするための強力なイデオロギー装置として機能したと考えられる。 -
島原・天草一揆における役割と実像
島原・天草一揆において、天草四郎は総大将として擁立されたものの、実際の軍事的な指揮や戦略立案は、父である益田甚兵衛や、小西行長・有馬氏の旧臣といった経験豊富な浪人たちが担っていたとする説が有力である 4。四郎の役割は、むしろ一揆軍の象徴であり、精神的な支柱としての側面が大きかったと考えられている 4。
原城での籠城中、四郎は特異な姿をしていたと記録されている。歯にお歯黒を施し、髪を後ろで束ねて前髪を垂らし、額には十字架を立て、白い衣を身にまとっていたという 4。このような呪術的とも言える装束で、城内においてミサを執り行い、洗礼を授け、説教を行うなど、宗教的指導者としての役割を果たしていた。
天草四郎の役割が象徴的なものであったとすれば、一揆の実際の戦略や組織運営は、戦闘経験を持つ浪人層が主導していた可能性が高い。これは、島原・天草一揆が単なる農民の自然発生的な暴動ではなく、ある程度の計画性と組織性を持った反乱であったことを示唆している。浪人たちは、宗教的権威を持つ天草四郎を前面に押し立てることで民衆を結束させ、自らは軍事面での実務を担うという、効果的な役割分担を行っていたのかもしれない。四郎の特異な装いや儀式的な行動もまた、兵士たちの士気を高揚させ、神がかり的な力を信じさせるための、計算された演出であった可能性も考えられる。
第二部:島原・天草一揆
- 第三章:一揆勃発の背景
-
島原藩(松倉氏)と天草(寺沢氏)の苛政
島原・天草一揆の直接的な引き金の一つは、島原藩主松倉勝家(及びその父・重政)と、天草を所領としていた唐津藩主寺沢堅高(及びその父・広高)による領民への過酷な支配、すなわち「苛政」であった。
松倉氏は、島原城の新築、江戸城改修の公儀普請役負担、さらには実現しなかったもののルソン(フィリピン)遠征計画など、莫大な費用を要する事業を次々と行った 5。これらの費用を捻出するため、領民に対しては本来の石高を大幅に上回る過酷な年貢を取り立てた 5。年貢を納められない農民に対しては、水牢(手足を縛って水の中に浸ける拷問)や、蓑を着せて火を放つ「蓑踊り」といった残虐な拷問や処刑が日常的に行われたと記録されている 5。
一方、天草地方は唐津藩主寺沢氏の飛び地であり、ここでも実際の石高の2倍にあたる重税が課せられていたとされる 4。
これらの領主による度を越した収奪は、農民の生活基盤を根底から破壊し、多くの人々を生存の危機へと追い込んだ。この極度の経済的困窮と生命の危機感が、一揆勃発の最も直接的な要因の一つとなった。そして、この経済的搾取への反発が、後述する宗教的要素と結びつくことで、島原・天草一揆という大規模な武力蜂起へと発展する爆発的なエネルギーを生み出したのである。 -
キリシタン弾圧の強化と信仰の状況
徳川幕府は、慶長17年(1612年)に直轄領に対して禁教令を発布して以降、全国的にキリスト教の禁止と信徒への弾圧を強化していった。島原・天草地方においても、この禁教政策は厳しく実行された 4。
島原藩主松倉氏、天草を支配した寺沢氏は、幕府の方針に従い、領内のキリシタンに対して厳しい弾圧を加えた。改宗を拒否する者に対しては、拷問や処刑も辞さなかったとされる 5。
しかしながら、これらの地域はかつてキリシタン大名の支配下にあり、キリスト教信仰が民衆の間に深く根付いていた。そのため、多くの信徒は潜伏キリシタンとして、あるいは表向き改宗を装いながらも内面では信仰を守り続けていた。記録によれば、「コンフラリア」と呼ばれるキリシタンの相互扶助的な信仰組織も存在し、密かに活動を継続していた 1。
一揆発生時には、弾圧によって一度は棄教したものの、再び信仰に立ち返った「立ち帰りキリシタン」が多数参加したとされている 1。この事実は、禁教政策が信仰を完全に根絶するどころか、かえって信仰の結束を強め、抑圧からの解放を求める強い動機となった可能性を示唆している。特に「立ち帰りキリシタン」の存在は、一度は権力に屈したことへの後悔と、再び信仰に生きようとする強い決意が一揆の原動力の一つとなったことを物語っている。彼らにとって、一揆への参加は単なる経済的抵抗だけでなく、信仰を取り戻し、殉教をも覚悟した宗教的な戦いであった側面も否定できない。 -
飢饉と民衆の困窮
島原・天草地方は、一揆勃発前の数年間にわたり、天候不順による凶作や飢饉が続いていた 4。この自然災害は、ただでさえ領主の重税に苦しんでいた民衆の生活をさらに圧迫し、極度の困窮状態へと追い込んだ。
領主は、このような状況下においても年貢の取り立てを緩めることなく、むしろその厳しさを増したため、民衆の不満と絶望感は限界に達していた。そのような中で、口之津村(現在の長崎県南島原市口之津町)において、年貢未納を理由に捕らえられた庄屋の妊婦が、厳寒の中で水牢に入れられて死亡するという残虐な事件が発生した 4。この事件は、民衆の怒りに火をつけ、一揆勃発の直接的な引き金の一つとなったとされている。
飢饉は、領主の苛政とキリシタン弾圧という既存の圧迫要因をさらに深刻化させ、民衆を蜂起へと駆り立てる最後の決定打となった。生存そのものが脅かされる極限状態において、天草四郎というカリスマ的指導者の出現と、彼が説いたとされる「パライゾ(天国)」の実現というメッセージは、現世での苦しみからの解放を求める民衆にとって、他に選択肢のない最後の望みと映ったのであろう。このように、飢饉は経済的要因と宗教的要因を結びつけ、一揆の規模と勢いを増大させる触媒として機能したと考えられる。
- 第四章:一揆の経過と天草四郎
-
蜂起から原城籠城まで
寛永14年10月25日(西暦1637年12月11日)、島原半島の有馬村(現在の長崎県南島原市有家町)において、キリシタン農民らが蜂起し、代官であった林兵左衛門を殺害した。これが島原・天草一揆の始まりである 5。
一揆の報は瞬く間に広がり、島原半島南部を中心に各地で農民が武器を取って立ち上がった。一揆勢は島原城を攻撃するなど、当初は破竹の勢いを見せた 5。
ほぼ時を同じくして、対岸の天草諸島でも一揆が蜂起した。天草の一揆勢は、益田四郎時貞、すなわち天草四郎を総大将として擁立し、寺沢氏の支城であった富岡城(現在の熊本県苓北町)を攻撃した。しかし、富岡城の守りは堅く、攻略することはできなかった 4。
富岡城攻略に失敗した天草の一揆勢は、有明海を渡って島原半島へ移動し、島原の一揆勢と合流した。彼らは、かつて有馬氏の居城であったものの、一国一城令によって廃城となっていた原城(現在の長崎県南島原市南有馬町)に立てこもった。原城に集結した一揆勢の数は、老若男女合わせて約3万7千人に達したとされている 4。
一揆の指導者たちは、蜂起に先立ち、島原と天草の間に位置する湯島(通称「談合島」)で会談し、天草四郎を一揆全体の総大将とすることを決定したと伝えられている 4。
富岡城攻略の失敗と、その後の原城への移動・籠城という戦略転換は、一揆軍が当初の攻撃的な勢いを維持することが難しくなり、防御的な持久戦へと移行せざるを得なかった状況を示している。原城が籠城地として選ばれた理由としては、三方を海に囲まれた天然の要害であり防御に適していた点、そしてかつてキリスト教の祝別を受けた城であり、キリシタンにとって聖地的な意味合いを持っていた可能性などが考えられる 5。この戦略転換は、短期決戦を目指した初期の蜂起から、長期的な抵抗戦へと一揆の様相が変化したことを物語っている。 -
原城の攻防戦と幕府軍の対応(オランダの関与を含む)
一揆勢が原城に籠城すると、江戸幕府はこれを重大な反乱と見なし、鎮圧のために本格的な軍事行動を開始した。当初、幕府は京都所司代であった板倉重昌を討伐軍の上使(総司令官)として派遣した。しかし、重昌は数度にわたる原城への攻撃に失敗し、寛永15年(1638年)正月元旦の総攻撃の際には自らも戦死するという結果に終わった 5。
板倉重昌の戦死という事態を重く見た幕府は、老中の一人であった松平信綱を新たな上使として派遣し、九州諸藩から総勢12万人以上ともいわれる大軍を動員して原城を完全に包囲した 1。松平信綱は、力攻めだけでなく、兵糧攻めによって城内の食料を枯渇させる作戦を採った。
この攻防戦において特筆すべきは、幕府軍がオランダ商館に対して協力を要請し、オランダ船「デ・ライプ号」による海上からの砲撃を行わせたことである 5。これは、国内の反乱鎮圧に外国の軍事力を利用するという、江戸幕府としては極めて異例の措置であった。この背景には、原城の防御が堅固であったこと、そして幕府軍の攻城能力に限界があったことなどが考えられる。オランダ側は、当時日本との貿易独占を目指しており、カトリック国であるポルトガルやスペインと対立していたため、幕府の要請に応じやすかったという事情もあった。
一方、原城内の一揆軍は、食料や武器弾薬が不足する劣悪な状況下にあっても、幕府軍の攻撃に対して果敢に抵抗を続けた。例えば、幕府軍が城内に向けて坑道を掘り進めようとすると、一揆軍は迎え撃つための横穴(「迎え穴」)を掘り、煙で燻したり人糞を流し込んだりしてこれを妨害したという記録も残っている 18。
幕府がオランダの軍事力を借用したという事実は、幕府が一揆の鎮圧をいかに重視し、また当時の日本の軍事技術だけでは攻略が困難であった可能性を示唆している。この出来事は、後の鎖国政策との関連において、複雑な意味合いを持つものと評価できる。国内問題に外国勢力を介入させたという事実は、幕府の権威に関わる問題であり、必ずしも好ましい前例ではなかったはずだが、一揆の早期鎮圧という目的が優先された結果と言えよう。 -
一揆の終焉と天草四郎の最期
約3ヶ月に及ぶ籠城戦の末、原城内の食料と弾薬は完全に底をついた。寛永15年2月28日(西暦1638年4月12日)、松平信綱率いる幕府軍は原城に対して総攻撃を開始した。飢餓と疲労により抵抗力を失った一揆軍は、幕府軍の圧倒的な兵力の前に次々と討ち取られ、原城はついに陥落した 5。
総大将であった天草四郎は、この総攻撃の中で討ち取られたとされる。その最期については、炎上する城の中で戦死した、あるいは捕らえられて斬首されたなど諸説あるが、いずれにしても16歳という若さでその生涯を閉じた 1。細川忠利が豊後日出藩主木下延俊に宛てた書状(寛永15年3月1日付)には、細川家の家臣が四郎の家を火矢で焼き、出てきたところを討ち取ったと記されている 31。
原城落城後、城内にいた一揆勢は、指導者層だけでなく、女性や子供を含む一般の農民たちもほぼ皆殺しにされたと伝えられている 20。幕府軍は、捕らえた者の首を刎ね、その数は1万人を超えたとも記録されている 32。天草四郎の首は、長崎に送られ、民衆への見せしめとして晒された 33。
この原城における徹底的な殲滅は、キリシタン及び幕府に反抗する勢力に対する徳川幕府の断固たる姿勢を示すものであり、他の潜在的な不満分子やキリシタン残党に対する見せしめとしての意味合いも強かったと考えられる。天草四郎の最期に関する記録の曖昧さは、彼の神格化されたイメージと相まって、後世における様々な伝説化を促す一因となった。若くして悲劇的な死を遂げたカリスマ的指導者の最期は、しばしば神秘的な物語によって彩られる傾向があるが、天草四郎もその例に漏れなかったと言えよう。
- 第五章:一揆の歴史的意義と評価
-
農民一揆としての側面と宗教一揆としての側面
島原・天草一揆の性格については、歴史学研究において長らく議論の対象となってきた。その原因として、松倉氏・寺沢氏による領民からの過酷な年貢取り立てや残虐な仕打ちといった「農民一揆」としての要素と、幕府によるキリスト教禁教政策とそれに対する信仰を守るための抵抗という「宗教一揆」としての要素が複雑に絡み合っている点が指摘されている 5。
研究史を概観すると、かつてはキリシタン宗門一揆説が主流であったが、戦後の歴史学においては、領主の苛政に対する農民の階級闘争として捉える農民一揆説が有力となり、その後、両者の要素を考慮する融合論も提唱されてきた 12。近年の研究では、一揆に参加した人々の内面における信仰の重要性や、「立ち帰りキリシタン」の現象などを踏まえ、宗教的な側面を再評価する動きも見られる 1。
島原・天草一揆を単一の要因に帰結させることは困難であり、経済的搾取と宗教的抑圧が相互に作用し、民衆を蜂起に至らしめた複合的な事件と捉えるのが最も妥当であろう。領主の苛政に苦しむ農民の多くがキリシタンであり、彼らにとって信仰は生活の一部であり、苦難を乗り越えるための精神的な支えであった。したがって、経済的搾取への抵抗と信仰の自由を求める戦いが分かちがたく結びついていたと理解すべきである。そのどちらの側面を重視するかによって、一揆の歴史的評価も異なってくる。 -
近世日本における最大規模の一揆としての位置づけ
島原・天草一揆は、参加した一揆勢の数(約3万7千人)と、それを鎮圧するために幕府が動員した軍勢の規模(12万人以上)から見ても、江戸時代を通じて最大規模の武力闘争であったと言える 1。
この一揆は、確立しつつあった徳川幕府の支配体制に対して大きな衝撃を与え、その後の幕政、特に宗教政策や対外政策に多大な影響を及ぼした点で、近世史における重要な転換点の一つとして評価することができる 5。
一揆の規模の大きさとその鎮圧の困難さは、幕府に対して地方統治のあり方、宗教政策の徹底、さらには対外関係の管理について再考を迫るものであった。幕府は、この一揆の背景にキリスト教信仰があったことを重く見て、キリスト教の潜在的な危険性を再認識し、禁教政策のさらなる強化と徹底(宗門改、寺請制度の確立など)へと舵を切った。また、一揆勢がポルトガルからの援助を期待していたという情報 5 や、鎮圧に際してオランダの協力を得たという経験は、幕府の対外政策にも影響を与え、ポルトガル船の来航を禁止し、いわゆる「鎖国」体制を完成させる一因となった可能性が指摘されている。このように、島原・天草一揆は、幕府の国内統治と対外政策の両面において、より厳格で統制的な体制へとシフトする画期となったと言えるだろう。
第三部:島原・天草一揆後の影響と天草四郎像の変遷
- 第六章:幕府政策への影響
-
鎖国体制の完成とキリスト教禁教の徹底
島原・天草一揆は、江戸幕府の国内統治および対外政策に深刻な影響を及ぼした。幕府は、この大規模な反乱の背景にキリスト教の存在があったことを重く受け止め、キリスト教に対する警戒感を一層強めた。その結果、従来から進められていた禁教政策はさらに徹底され、強化されることとなった 5。
具体的には、寛永16年(1639年)、幕府はポルトガル船の来航を全面的に禁止した。これは、ポルトガルがカトリック教国の中心であり、キリスト教布教と貿易が一体化していたため、その影響力を排除する狙いがあった。このポルトガル船の来航禁止をもって、日本のいわゆる「鎖国」体制が完成したと一般的に理解されている 5。これにより、海外との交流は、幕府が公認したオランダと中国(明、後の清)との長崎出島における貿易に限定されることになった 6。
島原の乱は、幕府が既存の禁教・貿易制限政策を最終的に完成させ、鎖国へと舵を切る決定的な後押しとなったと言える。国内の安定と支配体制の維持を最優先課題とする幕府にとって、キリスト教およびそれと結びつく可能性のある海外勢力は、体制を脅かす潜在的な危険因子と見なされ、徹底的に排除すべき対象とされたのである。 -
寺請制度と宗門改
キリスト教禁教を徹底するため、幕府は国内の民衆に対する宗教統制を強化した。その具体的な手段として導入・強化されたのが寺請制度(檀家制度)と宗門改である 5。
寺請制度とは、民衆がいずれかの仏教寺院の檀家となり、その寺院からキリシタンではないことの証明(寺請証文)を受けることを義務付ける制度である。これにより、幕府は仏教寺院を末端の行政機関として利用し、民衆の宗教的帰属を把握しようとした。宗門改は、この寺請制度に基づいて定期的に行われる宗教調査であり、隠れキリシタンの摘発を目的としていた。
これらの制度は、キリシタンの発見という直接的な目的だけでなく、より広範な民衆支配の手段としても機能した。民衆を寺院組織に緊密に結びつけることで、戸籍管理に類似した人口把握、領民の移動制限、さらには寺院を通じた思想・教育の統制をも可能にした。寺院は、葬祭儀礼を独占的に執り行うだけでなく、幕府の民衆統制の一翼を担うことになり、その社会的影響力は非常に大きなものとなった 35。 -
島原・天草地方の復興と移民政策
島原・天草一揆によって、一揆の主戦場となった島原半島南部と天草諸島の人口は著しく減少し、田畑は荒廃した 5。幕府は、これらの地域の生産力を回復させ、治安を安定させるため、大規模な復興政策を実施した。
その中心となったのが、他藩からの農民の強制移住である。幕府は、九州諸藩を中心に、四国などからも農民を募り、あるいは強制的に島原・天草地方へ移住させた 5。これにより、荒廃した農地の再開発と人口の回復が図られた。天草では、初代代官として赴任した鈴木重成らが、検地、新田開発、寺社復興、殖産興業など、多岐にわたる復興事業を精力的に推進した 7。
この大規模な強制移住は、単に人口を補充し経済を復興させるだけでなく、地域の社会構造や文化にも新たな変容をもたらした可能性がある。多様な文化的背景を持つ人々が新たに地域社会を形成する過程で、移住者と地元に残ったわずかな人々(もし存在すれば)との関係、異なる地域の慣習や方言、信仰(仏教の宗派など)の融合や衝突などが起こったかもしれない。また、この移民政策には、地域のキリシタン的色彩を薄め、幕府の支配体制に順応的な社会を再構築するという、政治的な意図も含まれていた可能性が考えられる。
- 第七章:天草四郎像の形成と文化表象
-
史実と伝説の交錯:「美少年」「奇跡の人」イメージの形成
天草四郎の人物像、特にその容姿や能力については、史実と後世の伝説・創作が複雑に交錯している。後世の創作物においては、しばしば「美少年」として描かれることが多いが、実際の記録によれば、四郎は天然痘を患った痕が顔にあったとも伝えられている 3。作家の坂口安吾も、天草四郎の美少年説に言及しつつ、その史料的根拠の曖昧さを指摘している 48。
また、四郎が数々の奇跡を行ったという伝説(盲目の少女の治癒、海上歩行、鳩の卵からの経文出現など)も広く知られているが 3、これらは彼のカリスマ性を高め、神格化するために後世に付加された要素が大きいと考えられている。
江戸時代に成立した「島原実録物」と呼ばれる一連の軍記物語においては、天草四郎の姿が、同じく若くして悲劇的な最期を遂げた源義経のような英雄のイメージと重ね合わされ、理想化された「美少年」としての像が形成されていったという説もある 17。
このように、天草四郎の「美少年」「奇跡の人」といったイメージは、歴史的事実そのものよりも、むしろ民衆の願望や後世の創作者の意図が強く反映された結果であると言える。これは、悲劇的な英雄が時代を経て理想化され、神格化されていくという、歴史上の人物のイメージ形成における典型的なプロセスの一つと見なすことができる。 -
文学、映画、ゲーム等における天草四郎
天草四郎とその指導した島原・天草一揆は、その劇的な展開と悲劇的な結末、そして指導者のカリスマ性から、後世の多くの創作物の題材となってきた。
山田風太郎の伝奇小説『魔界転生』(初出時の題名は『おぼろ忍法帖』)では、島原の乱で無念の死を遂げた天草四郎が、森宗意軒らとともに魔界の力で蘇り、徳川幕府への復讐を企てるという大胆な設定で描かれている 8。この作品は幾度も映画化・舞台化され、妖術を操る美青年としての天草四郎像を広く浸透させた。
映画監督の大島渚は、1962年に映画『天草四郎時貞』を制作した。この作品は、1960年の安保闘争敗北後の日本社会の状況や民衆の心情を、島原の乱におけるキリシタン農民の姿に重ね合わせて描いたとされ、歴史劇の枠を超えた社会批評的な作品として評価されている 53。
ゲームの世界においても、天草四郎は人気の高いキャラクターである。特に、対戦型格闘ゲーム『サムライスピリッツ』シリーズでは、初代作品の最終ボスとして登場して以来、シリーズを通して重要な役割を担っている。ゲーム内では、暗黒神の力によって復活した存在として描かれ、時には善、時には悪の側面を見せるなど、独自のキャラクター設定がなされている 8。
これらの他にも、芥川龍之介の短編小説『おぎん』は、キリシタン殉教をテーマとし、島原の乱の時代背景を色濃く反映している 55。また、吉村昭の歴史小説『海の史劇』は、島原の乱を詳細な時代考証に基づいて描いた作品として知られている 55。
天草四郎は、その生涯に多くの謎を残し、伝説的な要素も多分に含んでいるため、後世の創作者にとって想像力を刺激する格好の題材であり続けている。彼の悲劇性、若さ、カリスマ性、そして体制への反逆者という側面は、時代ごとの社会状況や作者の思想を反映する鏡のような存在として、多様な形で表象され、様々な解釈を生み出し続けていると言えよう。 -
関連史跡と顕彰施設
天草四郎と島原・天草一揆に関連する史跡や顕彰施設は、主に一揆の舞台となった長崎県島原地方と熊本県天草地方に数多く存在する。これらの施設は、歴史を伝え、犠牲者を慰霊し、また地域の観光資源としても重要な役割を果たしている。
長崎県南島原市に位置する原城跡は、一揆の最後の拠点であり、激戦地となった場所である。現在は国の史跡に指定されており、発掘調査によって当時の遺構や遺物(十字架、メダイ、人骨など)が多数発見されている 25。城跡には、天草四郎の像や、彼の母が建立したと伝えられる墓石(後に民家の石垣から発見され移設されたもの)などが設置されている 16。
熊本県上天草市大矢野町には、天草四郎メモリアルホール(天草四郎ミュージアムとも呼ばれる)があり、天草四郎の生涯や島原・天草一揆の歴史的背景、南蛮文化の影響などをテーマとした展示が行われている 4。同市内には天草四郎公園も整備されており、そこにも天草四郎の像や石碑が建てられている 16。
また、熊本県天草市にある天草市立天草キリシタン館には、国指定重要文化財である「天草四郎陣中旗」が所蔵・展示されている 5。この旗は、聖体と聖杯、そして二人の天使が描かれ、ラテン語の銘文が記されたもので、一揆軍が宗教的結束を象徴する旗印として用いたものと考えられている。
これらの史跡や施設の存在は、天草四郎と島原・天草一揆が地域史において重要な出来事として記憶され、後世に語り継がれていることを示している。ただし、これらの施設における展示内容が、歴史的事実と後世に形成された伝説やイメージをどのように区別し、あるいは融合させて提示しているかについては、注意深い検討が必要である。特に「天草四郎陣中旗」のような実物資料は、一揆の宗教的側面を具体的に示す貴重な遺物であり、その保存と学術的な研究・解説は極めて重要である。
結論
-
天草四郎と島原・天草一揆の再評価
天草四郎時貞は、江戸時代初期という激動の時代が生んだ、若く悲劇的な指導者であった。彼の生涯と島原・天草一揆における役割は、歴史的史料の制約や後世の多様な解釈・創作によって、未だ多くの謎と議論を残している。しかし、彼が苛政と宗教弾圧に苦しむ民衆の希望の象徴となり、大規模な蜂起の精神的支柱となったことは疑いようがない。その実像に迫るためには、現存する史料を丹念に読み解くとともに、彼をめぐる伝説や創作物がどのように形成され、受容されてきたのかを多角的に検証する必要がある。
島原・天草一揆は、徳川幕府の支配体制に対する近世日本における最大級の武力抵抗であり、その後の日本の歴史に大きな影響を与えた事件として再評価されるべきである。単なる農民反乱や宗教戦争といった一面的な捉え方ではなく、当時の社会経済状況、宗教思想、政治権力の動向などが複雑に絡み合って発生した複合的な歴史事象として理解することが重要である。 -
歴史研究における意義と今後の課題
天草四郎と島原・天草一揆の研究は、近世日本の民衆史、宗教史、政治史を理解する上で重要な意義を持つ。今後の研究においては、以下のような課題が挙げられる。
第一に、一次史料のさらなる発掘と分析である。特に、幕府側の記録だけでなく、一揆に参加した民衆側の視点や、当時の国際関係を示すオランダ商館長日記やイエズス会報告書などの海外史料との比較検討を通じて、一揆の実態をより詳細に解明する必要がある。また、原城跡をはじめとする関連遺跡の考古学的調査成果との照合も、当時の生活や戦闘の様子を具体的に復元する上で不可欠である。
第二に、天草四郎像の形成と変遷に関する学際的な研究の推進である。歴史学のみならず、文学、民俗学、宗教学、美術史、表象文化論といった多様な分野からのアプローチによって、天草四郎という人物が時代や社会背景に応じてどのように解釈され、表象されてきたのかを明らかにすることができる。これは、日本の英雄像や宗教観、あるいは「反逆者」のイメージがどのように形成され、消費されてきたのかを理解する上でも重要な示唆を与えるだろう。
第三に、現代社会における天草四郎の多様な表象が、歴史認識にどのような影響を与えているかについての考察である。小説、映画、漫画、ゲームなど、大衆文化の中で繰り返し描かれる天草四郎像は、人々の歴史に対する関心を喚起する一方で、史実とは異なるイメージを植え付ける可能性も否定できない。歴史教育や博物館展示などにおいて、史実と創作を区別し、多角的な視点を提供することの重要性が増している。
天草四郎と島原・天草一揆は、日本史における悲劇的な出来事であると同時に、人間の尊厳や信仰の自由、社会正義といった普遍的なテーマを現代に問い続ける存在でもある。今後の研究によって、その歴史的意義がさらに深く明らかにされることが期待される。
引用文献
- 島原の乱 - 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/5389/files/KU-1100SS-20090731-04.pdf
- カリスマ・天草四郎が散った地…… 自然に恵まれた半島、長崎県 ... https://shingakunet.com/journal/column/20160829170000/
- 総大将は16歳の少年キリシタン。悲しき運命に翻弄された「天草 ... https://mag.japaaan.com/archives/225638
- 天草四郎の歴史 https://kami-amakusa.jp/history
- 島原の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1
- www.city.nagasaki.lg.jp https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/5/index.html#:~:text=%E8%BF%91%E4%B8%96%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%8F%86%E3%83%BB%E5%86%85%E4%B9%B1,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
- 歴史叙述における島原の乱 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/228675243.pdf
- 天草四郎- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%9B%9B%E9%83%8E
- 『魔界転生』1981 | 塵人えむ俗記帳 https://ameblo.jp/zinzinemu/entry-12881133657.html
- 天草四郎時貞 (サムライスピリッツ) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%9B%9B%E9%83%8E%E6%99%82%E8%B2%9E_(%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84)
- 【名作発掘】「アケアカNEOGEO サムライスピリッツ 天草降臨」レビュー - GAME Watch https://game.watch.impress.co.jp/docs/review/1119507.html
- 島原の乱に関する史料から - 北翔大学学術リポジトリ https://hokusho.repo.nii.ac.jp/record/2000051/files/10_085-090.pdf
- www.city.nagasaki.lg.jp https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/5/index.html#:~:text=%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%80%81%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%85%B1%E3%81%AB%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99,%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 島原の乱 - 「ナガジン」 https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/5/index.html
- 上天草市 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/library/h30/07/assets-manual/pdf/h3007.pdf
- 天草四郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%9B%9B%E9%83%8E
- 第5章 島原実録物から見る 「天草四郎」 美少年像の成立 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2252/files/03_1Suu.pdf
- 島原・天草一揆(島原天草の乱) / 南島原市教育委員会 / 長崎県南 ... https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kyouiku/kiji0034735/index.html
- 総大将は16歳の少年キリシタン。悲しき運命に翻弄された「天草 ... https://mag.japaaan.com/archives/225638/2
- 天草四郎の最期の言葉 戦国百人一首⑦|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/ndd98d53d4387
- 【感想】NHK 歴史探偵「天草四郎と島原の乱」を視聴しました|hayahi_taro - note https://note.com/hayahi_taro/n/ned11943b8472
- 島原の乱(島原・天草一揆)|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=802
- 島原・天草一揆の舞台 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_column/ikki-butai
- No.047 「 天草、富岡城物語 」 - 熊本県観光サイト https://kumamoto.guide/look/terakoya/047.html
- 原城跡 ガイドマップ - 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 https://kirishitan.jp/cms/wp-content/uploads/2018/02/001_hara.pdf
- 湯島/談合島 - 上天草市 - オールクマモト https://allkumamoto.com/spot/yushima-dangoujima
- 島原の乱と佐賀藩 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7179486/024_p057.pdf
- 明治維新以前に日本に入国した欧米人の一覧 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AB%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E5%85%A5%E5%9B%BD%E3%81%97%E3%81%9F%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
- 日本関係海外史料「オランダ商館長日記訳文編之三(下)」 - 東京 ... https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/13/pub_kaigai-oranda-yaku-03-ge/
- 日本関係海外史料「オランダ商館長日記」原文編之四 - 東京大学史料 ... https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/17/pub_kaigai-oranda-genbun-04/
- https://crd.ndl.go.jp/refapi/servlet/refapi.RSearchAPI?query=02_crd%20ndl%20go%20jp - レファレンス協同データベース - 国立国会図書館 https://crd.ndl.go.jp/refapi/servlet/refapi.RSearchAPI?query=02_crd%20ndl%20go%20jp
- 45 「天草・島原一揆」 2013年8月14日放送 - 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒~宿命の対決が歴史を動かした!~|BS-TBS https://bs.tbs.co.jp/rival/bknm/45.html
- 原城 [2/4] 本丸 池尻口門跡には天草四郎時貞の祈る石像が建つ。 - 城めぐりチャンネル https://akiou.wordpress.com/2015/03/20/harajo-p2/
- 島原の乱の日(10月25日 記念日) | 今日は何の日 - 雑学ネタ帳 https://zatsuneta.com/archives/110255.html
- 寺請制度:葬儀供養の独占化 - エンディングスマート https://sakozo.com/blog/temple-petition-system/
- 寺請制度とは?その目的と制度の由来を解説 | 家系図作成の家樹 https://ka-ju.co.jp/column/terauke
- 庶民の一生を浮き彫りにする“歴史人口学” | 関西大学ニューズレター『Reed』 https://www.kansai-u.ac.jp/reed_rfl/archive/08_1.php
- キリシタン弾圧と初代宗門改役・井上政重 - 世界日報DIGITAL https://www.worldtimes.co.jp/culture/20250104-189162/
- 「島原の乱」はなぜ起きたのか? 10代の総大将・天草四郎と、壮絶な闘いの結末まで【親子で歴史を学ぶ】 | HugKum(はぐくむ) https://hugkum.sho.jp/447759
- The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/91494/mre_055_001.pdf
- 細川家も出陣!「島原の乱」とは - Readyfor https://readyfor.jp/projects/eiseibunko_02/announcements/233728
- 後、佐賀藩家老多久茂辰、鍋島茂綱が江戸の藩邸にだした報告書の一節にも - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34628_20130514092122.pdf
- 近代日本における海外移民送出地域の 歴史地理学研究 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/47164/files/DB02857.pdf
- 境界を超える女性たちと近代 ——海外日本人娼婦の表象を中心として—— - 機関リポジトリ HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/26725/lan020201300703.pdf
- 明清交替期の東アジア海域と華人海商 : 『華夷変 態』を中心として - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1485055/lit0184.pdf
- 佐賀近代史年表 http://www.chiikigaku.saga-u.ac.jp/pdf/kindaishinenpyout4.pdf
- 日中民間交流における「岡まさはる記念長崎平和 資料館」の役割 https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/28176/files/Ka_Dissertation_rev.pdf
- 坂口安吾 安吾史譚 天草四郎 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/56837_63907.html
- 日本近世文学会大会研究発表一覧 http://www.kinseibungakukai.com/doc/ichiran.html
- 島原実録物から見る「天草四郎」美少年像の成立 | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1050001202914899968
- 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/
- 魔界転生にも登場「森宗意軒神社」とは | 天草観光&グルメ&レジャー情報 https://tenku-f.hmup.jp/blog/53
- 天草四郎時貞の動画配信サービス・視聴方法・サブスクまとめ|Filmarks映画 https://filmarks.com/movies/14716/vod
- 天草四郎時貞 : 作品情報・キャスト・あらすじ - 映画.com https://eiga.com/movie/3713/
- HUREC AFTERHOURS 人事コンサルタントの読書・映画備忘録: 人文社会・自然科学 Archives http://hurec.bz/book-movie/archives/02_/
- 20200101 https://miraionlibrary.jp/HeadlinesNP/HeadlinesNP20200101-20200630.xlsx
- WORD GINI (日本語) - ソーシャル・コンピューティング研究室 http://sociocom.jp/~data/2018-wordgini/data/GINI_ja.csv
- CiNii Books 内容検索 - 芥川龍之介 https://ci.nii.ac.jp/books/contents?p=3&contents=%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B&count=200&sortorder=6
- CiNii Books 内容検索 - 芥川龍之介 https://ci.nii.ac.jp/books/contents?p=7&contents=%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B&count=200&sortorder=3
- https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/74_14635.html
- 『暗い夜、星を数えて―3・11被災鉄道からの脱出―』 彩瀬まる ... https://www.shinchosha.co.jp/book/120052/
- 長崎の世界遺産 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産を一挙紹介 - たびらい https://www.tabirai.net/sightseeing/article/feature26/
- 国指定文化財 / 南島原市教育委員会 / 長崎県南島原市公式ホームページ https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kyouiku/kiji0034730/index.html
- 世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」って? | 観光特集 https://www.at-nagasaki.jp/feature/christian
- 過去の展覧会 | 西南学院大学博物館 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/special-exhibition/past-special-ex/index.html
- 天草四郎時貞とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%9B%9B%E9%83%8E%E6%99%82%E8%B2%9E
- 天草四郎ミュージアム | 天草四郎観光協会 https://kami-amakusa.jp/archives/study/4850
- 天草四郎ミュージアム | 観光スポット | 【公式】熊本県観光サイト ... https://kumamoto.guide/spots/detail/11504
- 天草四郎の墓 - 天草四郎出生地の島に立つ墓碑 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/kumamoto/siroukouen.html
- 天草キリシタン資料館 整備活用計画 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039798/3_9798_51684_up_nquc7q4p.pdf
- 天草キリシタン館 - 熊本県天草観光ガイド https://www.t-island.jp/spot/3
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/ach/org/shisetsu/kirishitan.html