奥平貞能
奥平貞能は三河の国人領主。今川・徳川・武田の間で主家を変え、一族の存続を最優先。長篠の戦いでは酒井忠次隊に加わり、鳶ヶ巣山砦奇襲を成功させ、奥平家を譜代大名へと導いた。
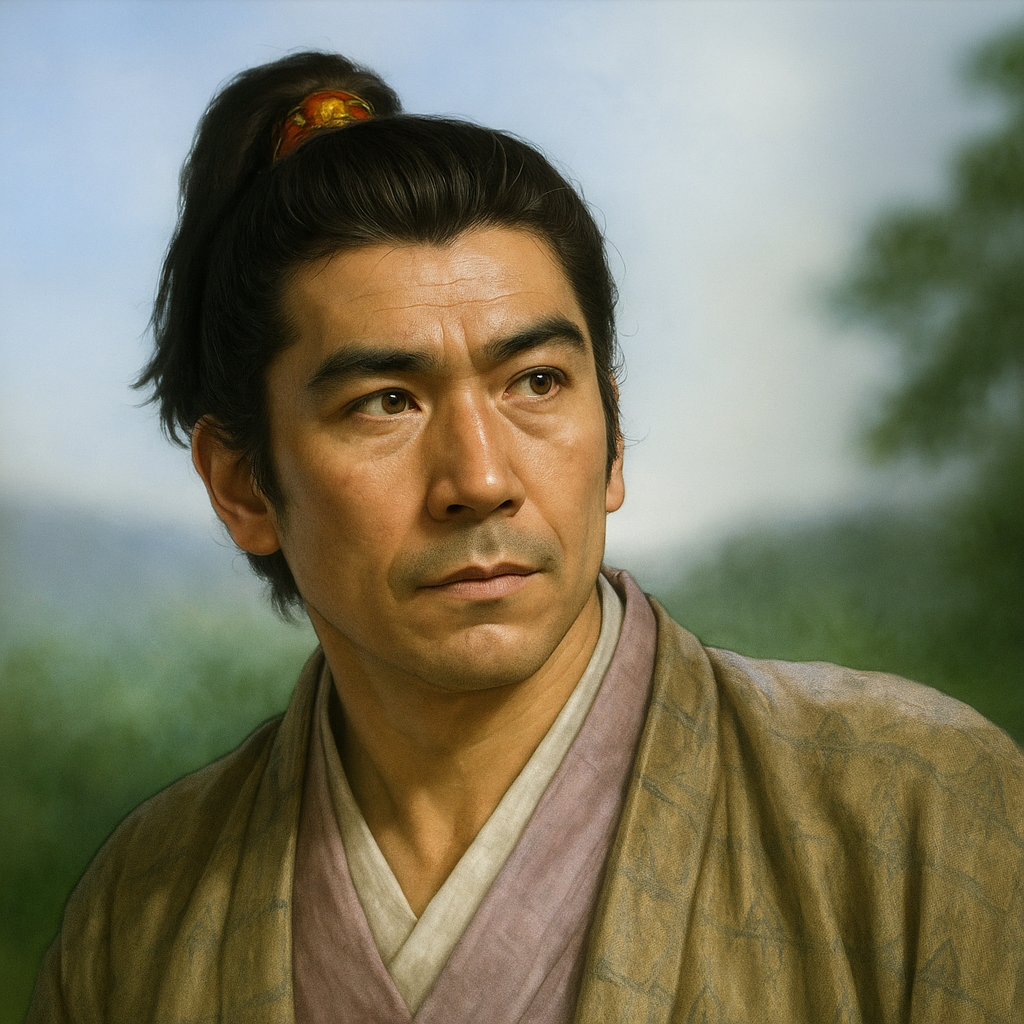
報告書:奥平貞能 ― 激動の戦国を生き抜き、一族を大名へと導いた国衆の生涯
序章:奥平貞能という武将
はじめに:三河の国衆・奥平貞能の位置づけ
奥平貞能(おくだいら さだよし)は、戦国時代を代表する徳川家康や武田信玄といった天下人ではなく、彼ら大国の狭間で一族の存亡を賭けて戦い抜いた「国衆(くにしゅう)」と呼ばれる地方豪族の典型的な人物である。彼の生涯は、戦国乱世における小勢力が直面した苦悩、駆使した戦略、そして下した決断の軌跡を凝縮しており、この時代を理解する上で極めて重要な事例と言える。本報告書では、近世の家譜類で広く用いられる「貞能」という表記 1 に加え、同時代の文書で確認される諱(いみな)である「定能」 4 を主として用い、その実像に迫る。
本報告書の目的:基礎知識を超えた多角的・深層的分析の提示
本報告書は、「今川家臣から徳川家臣となり、一時的に武田家に属した後、長篠の戦いで活躍した」という一般的な人物像の骨子を、史料の断片を丹念に繋ぎ合わせることで肉付けし、その行動原理、人間関係、そして歴史的意義を深く掘り下げることを目的とする。単なる事実の羅列に留まらず、彼の幾度にもわたる主家の変更という決断が、なぜ、どのようにして下されたのかを、当時の地政学的状況や一族内の力学といった多角的な視点から解き明かす。これにより、戦国という時代を生きた一人の国衆のリアルな姿を浮き彫りにする。
第一章:奥三河の国衆・奥平氏の出自と地政学的環境
奥平氏のルーツと三河国作手(つくで)での台頭
奥平氏の家伝によれば、その発祥は上野国奥平郷(現在の群馬県)とされ、村上源氏赤松氏の流れを汲むと称している 6 。その後、室町時代に三河国設楽郡作手(現在の愛知県新城市)へと移住し、亀山城を本拠として勢力を拡大した 6 。三河の山間部という地理的条件の中で、彼らは着実にその地盤を固めていった。
「山家三方衆(やまがさんぽうしゅう)」としての一翼
作手を本拠とする奥平氏は、近隣の田峰城(だみねじょう)を領する菅沼氏、長篠城を領する菅沼氏と緊密な婚姻関係を結び、「山家三方衆」と称される奥三河の有力な国衆連合を形成していた 9 。これは、単独では大国の圧力に対抗することが困難な山間部の小勢力が、互いに連携し、時には共同で軍事行動を起こすことで、その自立性を保とうとするための生存戦略であった。
三大勢力に挟まれた国衆の苦悩と生存戦略
奥平氏が本拠とした奥三河は、東に駿河の今川氏、西に尾張の織田氏(後に三河の徳川氏)、そして北に甲斐の武田氏という、当代屈指の三大勢力がぶつかり合う緩衝地帯に位置していた 12 。この極めて厳しい地政学的条件が、奥平氏の運命を絶えず左右し続けた。彼らは常にいずれかの大国の圧力に晒され、一族の存続という至上命題のために、臣従する相手をめまぐるしく変えざるを得ない状況に置かれていたのである 13 。
奥平氏の行動を理解する上で重要なのは、彼らが「境界領主(きょうかいりょうしゅ)」であったという点である。彼らの行動原理は、特定の主君への忠誠心や信義といった観念よりも、「家を存続させる」という極めて現実的な目標によって貫かれている。主君を頻繁に変えた行為は、現代的な価値観で見れば「裏切り」と映るかもしれないが、戦国時代の力学の中では、変化し続けるパワーバランスを冷静に分析し、一族が生き残るための最適解を模索し続けた結果であった 9 。定能の生涯は、まさにこの境界領主の生存戦略を体現したものであり、彼の全ての決断はこの文脈の中で理解されるべきである。
第二章:今川家臣時代と徳川家康への帰属
史料に見る若き日の定能:人質経験と今川氏への反逆
奥平定能が歴史の表舞台に初めてその名を見せるのは、天文16年(1547年)、今川義元から医王山砦攻略の恩賞として所領を与えられた記録である。この時、彼はまだ幼名の仙千代を称していた 4 。しかし、その平穏は長くは続かず、翌年には父・貞勝によって今川氏への忠誠の証として人質として吉田(現在の豊橋市)に送られるという経験をしている 4 。この出来事は、大勢力に翻弄される国衆の脆弱な立場を、彼に肌で感じさせたに違いない。
注目すべきは、弘治2年(1556年)の動向である。父・貞勝が今川氏への臣従を続ける一方で、定能は一族の一部と共に今川氏への反逆を企て、結果として親今川派の親類衆によって高野山へ追放されている 4 。この事件は、彼が若くして現状を是としない強い独立心と、父とは異なる独自の政治的判断力を持っていたことを示す重要な逸話である。
桶狭間の戦いと三河の動乱:今川からの離反と徳川への帰属決断
永禄3年(1560年)、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると、三河における今川氏の支配力は劇的に失墜する 10 。この歴史的転換点を捉え、松平元康(後の徳川家康)が岡崎城で独立を果たすと、三河の国衆は次々と今川氏を見限り、家康の下へと馳せ参じた。奥平氏もこの大きな流れに乗り、永禄7年(1564年)頃までには今川氏から離反し、徳川家康に属することを決断した 4 。
徳川家臣としての初期の戦歴:掛川城攻めと姉川の戦い
家康の麾下に入った定能は、その能力を早速発揮する。家康の遠江侵攻においては、今川氏真が籠城する掛川城攻めに従軍 21 。永禄12年(1569年)、定能は掛川城の西に位置する仁藤山砦(笠町砦)に布陣し、単に武力で攻めるだけでなく、家康に対して「掛川城の力攻めを中止し、兵糧攻めによって氏真を追い詰め、北条氏への退去を交渉で認めさせる」という、外交と軍事を組み合わせた高度な戦略を献策している 23 。
さらに、元亀元年(1570年)には、織田・徳川連合軍が浅井・朝倉連合軍と激突した姉川の戦いにも参陣している 24 。この戦いは、定能の嫡男である貞昌(後の信昌)にとって初陣であり、彼が敵将の首を挙げた際、家康がその武勇を称賛した逸話も残っている 26 。これらの戦功を通じて、奥平家と家康との主従関係はより強固なものとなっていった。
定能の徳川への帰属は、単に時流に乗った受動的な行動ではなかった。若き日の反逆経験や掛川城攻めでの戦略的な献策は、彼が単なる一武将ではなく、大局を見据えて自らの判断で行動し、主君に戦略を提言できるほどの知見と主体性を備えた人物であったことを示している。家康もまた、彼を単なる兵力供給源としてではなく、奥三河という戦略的要衝を抑えるための重要なパートナーとして高く評価し、3,500貫文という破格の知行と美作守の受領名を与えて厚遇した 24 。この相互の信頼関係が、後の定能のより大胆な決断の土台となったのである。
第三章:苦渋の選択 ― 武田信玄への従属
武田氏の三河侵攻と「山家三方衆」の動揺
元亀2年(1571年)頃から、甲斐の武田信玄による三河・遠江への侵攻(西上作戦)が本格化すると、奥平氏を取り巻く情勢は一変する 20 。信玄は巧みな調略を駆使して奥三河の国衆の切り崩しを図り、山家三方衆を構成していた田峰菅沼氏、長篠菅沼氏が次々と武田方になびいた 14 。これにより奥平氏は徳川方として完全に孤立し、周囲を武田の勢力圏に囲まれ、自領を維持することすら極めて困難な状況に追い込まれた 10 。
一族内の対立:徳川残留を望む定能と、武田従属を主張する父・貞勝
この未曾有の危機に際し、奥平一族の内部で深刻な意見対立が生じた。当主である定能は、家康との関係を重視し、徳川への忠誠を維持しようと試みた。しかし、すでに隠居の身であった父・貞勝(道文入道)が、目前に迫る武田の圧倒的な軍事力を前に、武田への従属を強く主張したのである 18 。
貞勝の判断は、周辺国衆が次々と武田に降る中で、徳川に与し続けても援軍は期待できず、一族が滅亡するだけだという現実的な見通しに基づいていた 32 。一方、定能は家康との関係に一族の将来性を見出していたが、ここで一族が分裂すれば共倒れになることを避けられなかった。最終的に、定能は父の意見を容れ、本意ならずも武田氏に一時的に従属するという苦渋の選択を下した 10 。
武田軍の一員として:三方ヶ原の戦いへの参陣
武田方に属することになった奥平氏は、武田軍の重臣である山県昌景の与力(配下)に編入され、皮肉にも武田軍の先鋒として、かつての仲間であった徳川方の城を攻めることになった 14 。そして元亀3年(1572年)12月、家康の生涯最大の敗戦として知られる三方ヶ原の戦いにおいて、奥平氏は武田軍の一員として参陣し、本来の主君である家康の軍勢を敗走させる側に加担することになった 18 。この屈辱的な経験は、定能の中に徳川へ帰参する機会をうかがう強い動機を植え付けたに違いない。
この定能と父・貞勝の対立は、単なる親子の確執として片付けられるべきではない。それは、目前の脅威を回避することを最優先する短期的な生存戦略(貞勝)と、将来の発展を見据えてリスクを取る長期的な投資戦略(定能)との衝突であった。貞勝は「武田の現在の力」という現実を直視し、定能は「徳川との未来の関係」という可能性に賭けようとした。当主でありながら父の意向に逆らえなかったという事実は、戦国国衆の意思決定が当主一人のものではなく、一族内の複雑な力学の中で行われることを示している。定能の武田への一時的従属は、戦略的敗北ではなく、一族の崩壊を防ぎ、再起の機会を待つための「苦渋の妥協」であり、計算された戦略的後退であったと評価できる。
第四章:一族の命運を賭した徳川への再帰参
武田信玄の死と、徳川家康からの調略
元亀4年(天正元年、1573年)、武田軍が野田城を攻略したにもかかわらず、突如として西上作戦を中止し甲斐へ引き返すという不可解な動きを見せた。この情報に接した定能は、武田信玄の死を確信する 9 。この千載一遇の好機を、徳川家康は見逃さなかった。家康は直ちに奥平氏に接触し、徳川方への再度の帰参を働きかける。その際、家康が提示した切り札こそ、自身の長女である亀姫と、定能の嫡男・貞昌(後の信昌)との婚約という、破格の条件であった 9 。
決断の決め手:嫡男・信昌と家康の長女・亀姫との婚約
この縁組の提案は、奥平氏を単なる家臣としてではなく、徳川家の親族(御連枝)として迎えることを意味した 6 。奥三河の一国衆に過ぎなかった奥平家にとって、これは将来の安泰と一族の地位の飛躍的な向上を約束する、何物にも代えがたい魅力的な提案であった。この条件が、人質の犠牲という大きなリスクを冒してでも、定能に武田からの離反を決意させた最大の要因であったことは間違いない。
亀山城からの脱出劇とその周到な計画
定能は、武田方の監視の目を欺き、一族を徳川方へ導くために、極めて周到な計画を実行に移す。武田方の将・武田信豊に内通の疑いをかけられ詰問された際には、巧みな弁舌でその場を凌ぎ、平然と囲碁に興じるなどして相手を完全に油断させた 38 。作手城に戻ってからも、武田方の目付を酒肴で饗応して警戒心を解き、万全の準備を整えた上で、天正元年(1573年)8月21日の夜、一族郎党の大部分を率いて本拠・亀山城を脱出。徳川方へと走ったのである 10 。
裏切りの代償:人質となった次男・仙千代らの悲劇的な処刑
定能・信昌親子の離反という報に激怒した武田勝頼は、即座に報復措置を取った。人質として甲斐に送られていた定能の次男・仙千代(当時13歳)、そして信昌の妻であったおふうの方(当時16歳)ら、奥平家の人質たちを無慈悲に処刑したのである 1 。一説には、彼らの亡骸は鳳来寺の参道に晒されたとされ、この悲劇は、定能の決断が文字通り一族の血を代償とする、非情なものであったことを物語っている 38 。この時亡くなった仙千代の墓は、現在も新城市の華蔵寺に祀られている 42 。
帰参直後の戦い:滝山合戦と田原坂の戦い
徳川方に帰参した定能らは、悲しみに暮れる間もなく、武田方との戦いに身を投じる。帰参からわずか1ヶ月後の9月21日、武田勢が定能らの新たな拠点である滝山城に攻撃を仕掛けてきた。定能らは、まだ防御施設も不十分な城でこれをよく防ぎ、さらに退却する敵を追撃して田原坂で戦い、勝利を収めた 38 。この迅速な戦功は、彼らの徳川方への帰参が本物であることを、疑いの余地なく証明するものであった。
定能の徳川への再帰参は、単なる鞍替えではなく、一族の未来を賭けた壮大な「賭け」であった。彼は、信玄の死という情勢の変化を的確に捉え、家康が提示した「亀姫との婚約」という最大の好機を逃さなかった。人質の見殺しという非情な決断は、この賭けに勝利するためには避けられないコストであると冷静に判断した結果であろう。彼の行動は、戦国国衆の生存戦略が、時に冷徹なコスト計算と、未来への投資という観点を伴うことを如実に示している。
第五章:長篠の戦いにおける奥平一族の功績
長篠の戦いにおける奥平氏の功績は、しばしば嫡男・信昌の籠城戦に集約して語られるが、実際には父・定能も城外で決定的に重要な役割を果たしていた。父子が内外から連携して武田軍を挟撃した「父子による共同作戦」という構図を理解することが、彼らの貢献の全体像を把握する鍵となる。
【表】長篠の戦いにおける奥平一族の役割分担
|
人物 |
場所 |
役割 |
具体的な行動 |
戦いへの貢献 |
|
奥平信昌(貞昌) |
長篠城内 |
籠城軍総大将 |
わずか500の兵で武田軍1万5千の猛攻を約2週間にわたり耐え抜く 44 。鳥居強右衛門を使者として派遣し、援軍要請と情報連絡を成功させる 45 。 |
織田・徳川連合軍の到着まで時間を稼ぎ、設楽原での決戦の舞台を整えた最大の功労者。 |
|
奥平定能(貞能) |
長篠城外(設楽原) |
鳶ノ巣山砦奇襲部隊(別動隊)の一員 |
酒井忠次率いる別動隊に加わり、武田軍の背後にある鳶ノ巣山砦を奇襲・陥落させる 1 。 |
武田軍の退路を断ち、兵站を破壊。これにより武田本隊に深刻な動揺を与え、無謀な正面攻撃へと誘導する決定的な一撃となった。 |
前哨戦としての長篠城籠城戦:信昌による寡兵での奮戦
天正3年(1575年)5月、武田勝頼は裏切った奥平氏を討伐し、徳川方の重要拠点を奪うべく、1万5千と号する大軍で長篠城を包囲した 12 。この時、城主であった信昌は、父・定能から家督を譲られ、家康からこの城を預かっていた。彼はわずか500という寡兵ながら、配備されていた鉄砲を効果的に用いて徹底抗戦し、織田・徳川連合軍の本隊が到着するまで城を死守した 44 。この籠城戦の成功なくして、長篠の戦い全体の勝利はあり得なかった 49 。
城外での定能の役割:酒井忠次率いる鳶ノ巣山砦奇襲部隊への参加
一方、設楽原に布陣した織田・徳川連合軍の軍議において、徳川の重臣・酒井忠次が、長篠城を包囲する武田軍の背後に位置する鳶ノ巣山砦への奇襲攻撃を献策した 47 。織田信長はこの策を即座に採用し、酒井忠次を大将とする約4,000の別動隊が編成された 47 。奥平定能はこの別動隊に加わり、地元・奥三河の地理に明るいことを活かして奇襲を成功に導いたと伝えられている 1 。この奇襲により鳶ノ巣山砦をはじめとする武田軍の背後の砦は次々と陥落・炎上した。これにより武田軍は退路と補給線を断たれ、心理的に極度に追い詰められたことが、設楽原での決戦を強行する大きな一因となったのである 47 。
一族の奮闘が織田・徳川連合軍の勝利に与えた決定的影響
信昌の籠城が「時間」を稼ぎ、定能の奇襲が「空間(退路)」を断った。この父子の活躍がなければ、織田・徳川連合軍の鉄砲三段撃ちという有名な戦術がその効果を最大限に発揮する舞台そのものが成立しなかった可能性が高い 42 。信昌の「守り」が武田軍主力を一点に拘束し、定能の「攻め」がその拘束された敵の弱点を突いた。この二つの行動は、結果として互いの効果を増幅させる関係にあり、奥平一族の功績は、長篠の戦いの勝利に不可欠な、決定的な要素であったと結論付けられる。
第六章:戦後の論功行賞と晩年
長篠の戦いにおける功績への恩賞
長篠の戦いが織田・徳川連合軍の圧勝に終わると、奥平一族、特に長篠城を死守した信昌の功績は、織田信長と徳川家康から絶賛された 37 。論功行賞として、信昌は信長から偏諱(へんき)、すなわち「信」の一字を与えられ、名を「貞昌」から「信昌」へと改めた 20 。さらに家康からは、かねてからの約束通り長女・亀姫を正室として迎え、新たな居城として新城(しんしろ)城を築くことを許された 35 。これにより、奥平家は単なる国衆から、徳川一門に連なる譜代大名としての確固たる地位を確立するに至ったのである 37 。
嫡男・信昌への家督継承と定能の隠居
定能は、徳川への帰参を果たした天正元年(1573年)の時点で、すでに嫡男の信昌に家督を譲り、自身は隠居の身となっていた 18 。長篠の戦いの後、彼は表舞台から一歩退き、輝かしい功績を挙げた息子・信昌の活躍を後見する立場に徹した 4 。これは、一族の未来を若き新当主である信昌に完全に託すという、経験豊富な老将の賢明な判断であったと言えるだろう。
豊臣秀吉との謁見と長篠の戦功物語
定能の武名は、天下人の耳にも達していた。天正18年(1590年)、豊臣秀吉が小田原征伐の途上で三河に立ち寄った際、定能は秀吉に直々に招かれ、長篠の戦いでの武功について語る機会を得ている 4 。天下統一を成し遂げた秀吉が、かつての一国衆に過ぎなかった定能の戦功話に熱心に耳を傾けたという事実は、長篠の戦いにおける彼の役割が当時からいかに高く評価されていたかを示している。この時、定能は秀吉から褒美として呉服を拝領し、都に住むことを勧められたという逸話も伝わっている 4 。
最期の地・伏見と墓所
晩年は秀吉の勧めに従い、政治の中心地であった伏見で過ごした 1 。そして慶長3年12月11日(西暦1599年1月7日)、伏見の屋敷にて病没した。享年62であった 1 。彼の墓所は、愛知県岡崎市にある広祥院に、父・貞勝や息子・信昌らの墓と共に、五輪塔が並んで建てられている 59 。また、埼玉県行田市の大蔵寺には、江戸時代前期の狩野派の絵師によるものとされる、気品と威厳に満ちた定能の肖像画が今に伝来している 37 。
終章:奥平貞能の歴史的評価
人物像の再評価:状況に応じて主君を変えた「裏切り者」か、一族を存続させた「稀代の戦略家」か
奥平定能の生涯を振り返ると、今川、徳川、武田、そして再び徳川と、主君を何度も変えたその経歴から、表面的には「不忠」や「裏切り者」という評価を受けがちである。しかし、本報告書で詳述してきたように、彼の行動は常に「一族の存続と発展」という、国衆にとっての至上命題に貫かれている 9 。彼の決断の一つ一つは、激しく変動する情勢を的確に読み、リスクを恐れずに一族にとっての最善の選択肢を追求した結果であった。人質となった実子の犠牲という非情な決断さえも、より大きな目的、すなわち一族全体の未来を確保するための戦略的判断であった。したがって、定能は単なる「裏切り者」ではなく、戦国乱世という極限状況を生き抜いた「稀代の戦略家」として再評価されるべきである 39 。
国衆としての生存戦略:定能の決断が、戦国乱世を生き抜く小勢力の典型例として持つ意味
定能の人生は、強大な勢力に囲まれた国衆が、いかにして生き残りを図ったかを示す、絶好のケーススタディと言える 13 。彼は、卓越した情報収集能力、冷静な状況分析力、そして好機を逃さない大胆な決断力を兼ね備えていた。時には一族内の対立や個人的な悲劇をも乗り越え、家を未来へと繋いだ。彼の生き様は、綺麗事では済まされない戦国時代という時代の本質と、その中で生きる地方領主のリアルな姿を我々に教えてくれる。
後世への遺産:奥平家を譜代大名へと押し上げた最大の功労者としての位置づけ
奥平定能の最も偉大な功績は、その生涯を賭した戦略的な決断によって、奥三河の一国衆に過ぎなかった奥平家を、江戸時代を通じて10万石を領する譜代大名(最終的には豊前中津藩主)という名門の地位へと押し上げたことである 6 。彼の息子・信昌が長篠の英雄として歴史に名を刻み、徳川家康の婿として破格の厚遇を受けたのも、すべては父・定能が、一族の命運を賭けて徳川への再帰参という「賭け」に勝利したからに他ならない。奥平家の近世大名としての繁栄の礎は、まさしく父・奥平定能によって築かれたのであり、彼は奥平家中興の祖として、その歴史的評価を確立している。
引用文献
- おくだいら - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/okudaira.html
- 歴史の目的をめぐって 奥平定能 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-05-okudaira-sadayoshi.html
- 奥平貞能(おくだいら さだよし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E8%B2%9E%E8%83%BD-1062757
- 奥平定能とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E5%AE%9A%E8%83%BD
- 奥平貞能(オクダイラサダヨシ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=2239
- 奥平氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E6%B0%8F
- 奥平氏発祥の地 | 三河の住人の庵 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/mikawanoiori/13001/
- 奥平氏(おくだいらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E6%B0%8F-40004
- 【戦国時代の境界大名】奥平氏――家運が開いた運命的な活躍の場とは? https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/16/180000
- 亀山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/mikawa/shiseki/higashi/kameyama.j/kameyama.j.html
- 山家三方衆 - 設楽原ボランティアガイド https://s-vg.com/vg/person/%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E4%B8%89%E6%96%B9%E8%A1%86/
- 05 戦国時代の荒波に翻弄されながらも必死に生きた奥三河の人たちのお話し(鳥居強右衛門) - 今日は、とよがわ日和。 - 愛知県 https://www.pref.aichi.jp/site/toyogawabiyori/suneemon.html
- 山家三方衆(やまがさんぽうしゅう) - 愛知エースネット https://apec.aichi-c.ed.jp/kyouka/shakai/kyouzai/2018/syakai/tousan/tou069.htm
- 山家三方衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%AE%B6%E4%B8%89%E6%96%B9%E8%A1%86
- 新城市観光協会 − 歴史 https://shinshirokankou.com/history.html
- 歴史を辿る - 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/promotion/history/rekishi.html
- 長篠の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 奥平信昌~武田軍の猛攻に屈せず長篠城を死守 | WEB歴史街道 ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4920
- 徳川家康による掛川城攻めについて 掛川城 家康 読本 公式WEB https://www.bt-r.jp/kakegawajo/chapter1/
- 長篠城主奥平信昌〈長篠の戦い⑶〉(徳川家康ゆかりの地19) https://wheatbaku.exblog.jp/32828599/
- 奥平信昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E4%BF%A1%E6%98%8C
- 長篠城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/mikawa/shiseki/higashi/nagashino.j/nagashino.j.html
- 仁藤山砦 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/totoumi/shiseki/chuen/nitouyama.sj/nitouyama.sj.html
- 奥平定能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E5%AE%9A%E8%83%BD
- 姉川の戦|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2375
- 短編時代小説『剣豪・奥山休賀斎公重』|城田涼子 - note https://note.com/ryouko/n/n6d3a3b02fa5b
- 奥平家と貞治、家康のつながり その7 - 関ケ原笹尾山交流館スタッフブログ http://sekigahara2013.blog.fc2.com/blog-entry-161.html?sp
- 奥平信昌、父貞能とともに武田家から離反(「どうする家康」71) https://wheatbaku.exblog.jp/32994329/
- 長篠合戦のぼりまつりの旅【その2・長篠の戦いに至るまでの前振りについて年表化・永生2年~元亀3年】 - 暁の空 https://ieyasu1543.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
- Ⅱ 遠江侵攻と武田氏 #3 信玄と三方ヶ原の合戦(2)|だい - note https://note.com/daaai_2023/n/nc5e2da60b9ec
- "侵攻ルート"はまさに風林火山!:「三方ヶ原の戦い」を地形・地質的観点で見るpart1【合戦場の地形&地質vol.5-1】|ゆるく楽しむ - note https://note.com/yurukutanosimu/n/nbf5e41e4063c
- 怒る武田信玄が猛攻、家康の窮地救った忠臣の正体 「3年間のうっぷんを晴らす」信玄が怒った根本原因 | なぜ天下人になれた?「人間・徳川家康」の実像 | 東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/669272?display=b
- 徳川家康が生き延びたのは奇跡に等しい…「三方ヶ原の戦い」で武田信玄が描いた完璧すぎる家康殲滅プラン 信玄があと1年長生きしたら歴史は変わっていた - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/69385?page=1
- 亀山城 (愛知県新城市作手) - らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-488.html?sp
- 家康の長女・亀姫が辿った生涯|本多正純を失脚させた「宇都宮釣り天井事件」の真相【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1128788
- 小田原市立足柄小学校 | 学校日記 | 家康没後400年に際して その3 亀姫 1 https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/ashigara_s/weblog/3324332
- 奥平貞能画像 - 行田市 https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/shougaigakusyubu/bunkazaihogo/gyomu/rekishi_bunkazai/1/2295.html
- 長篠の戦に至るまでの動向【元亀4年/天正元年】主に ... - 暁の空 https://ieyasu1543.blog.fc2.com/blog-entry-20.html
- 奥平 貞能 | 歴史 | みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/okuhirasadayoshi.html
- 【R-SZ024】奥平信昌邸跡 https://www.his-trip.info/siseki/entry2310.html
- 戦国時代の悲劇〜家康 平和への願い〜 | 岡崎いいとこ風景ブログ https://okazakikeikan.boo-log.com/e217080.html
- 長篠の戦|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2376
- 奥平仙千代の墓 - 新城市 - キラッと奥三河観光ナビ https://www.okuminavi.jp/search/detail.php?id=511
- 長篠城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/chubu-castle/chubu-nagashino-castle/
- 鳥居強右衛門 - 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kanko/hito/torisuneemon.html
- 鳥居強右衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85%E5%BC%B7%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80
- 鳶ヶ巣山砦 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/mikawa/shiseki/higashi/tobigasuyama.sj/tobigasuyama.sj.html
- 【会期終了】収蔵品展「ナガシノノキオク~中津藩士のルーツは長篠にあり~」 https://nakahaku.jp/2023/06/17/%E5%8F%8E%E8%94%B5%E5%93%81%E5%B1%95%E3%80%8C%E3%83%8A%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%8E%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%82%AA%E3%82%AF%EF%BD%9E%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E8%97%A9%E5%A3%AB%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84/
- とんでもない奇襲ルート:「長篠の戦い」を地形・地質的観点で見るpart3【合戦場の地形&地質vol.6-3】|ゆるく楽しむ - note https://note.com/yurukutanosimu/n/nd5e3234810d0
- 長篠・設楽原古戦場 http://shanehsmt.html.xdomain.jp/Travel/Japan/Chubu0/Shitaragahara.html
- 「大量の鉄砲が武田の騎馬隊を蹴散らした」はウソである…最新の研究でわかった長篠の戦いの本当の姿 武田軍の主力は騎馬隊ではなく長槍隊だった (3ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/66303?page=3
- 鳶ヶ巣山砦〈長篠の戦い⑻〉(徳川家康ゆかりの地24) - 気ままに江戸 散歩・味・読書の記録 https://wheatbaku.exblog.jp/32840310/
- 其の八 酒井忠次の大作戦「鳶ヶ巣山(とびがすやま)」 - 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kanko/taiga/shinshiro/tobigasuyama.html
- 登場人物インデックス - 新城市商工会 http://www.shinshiro.or.jp/battle/jinbutu-index.htm
- 奥平信昌 - 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kanko/hito/okudairanobumasa.html
- 奥平信昌(おくだいら・のぶまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E5%B9%B3%E4%BF%A1%E6%98%8C-40005
- 奥平 https://www.okuminavi.jp/_upfiles/pamphlet/file/0c0f81bb36cbc741cdf75983e23f8db3.pdf
- KD13 奥平貞俊 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/kd13.html
- 【K-AC112】奥平一族墓所〔広祥院〕 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/siseki/entry768.html
- 織田・徳川vs武田、境界国衆の戦い「長篠・設楽原の戦いはどんな戦いだったのか」を聞いてきた! https://journal.kojodan.jp/archives/1866
- 江戸時代の大名家一覧 - 攻城団 https://kojodan.jp/family/