屋代政国
屋代政国は信濃の国衆。村上義清の重臣だったが、武田信玄に降伏し、川中島の戦いの引き金となる。子孫は徳川家で大名となるも、万石騒動で改易され旗本として存続。
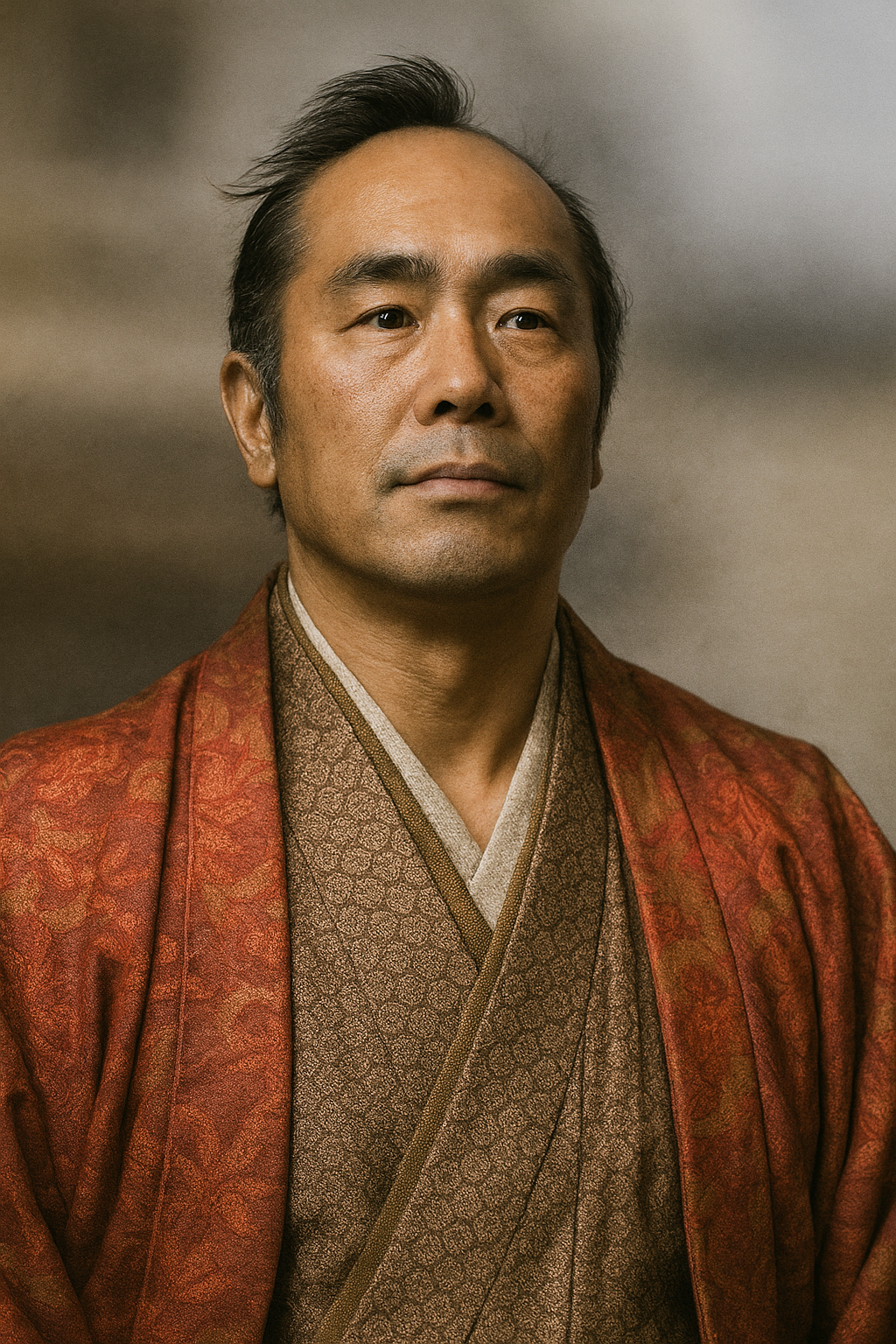
信濃国衆・屋代政国の生涯と一族の興亡 ―激動の戦国を生き抜いた在地領主の実像―
本報告書は、信濃国の戦国武将、屋代政国(やしろ まさくに)の生涯と、彼が率いた屋代一族の歴史的変遷を、現存する古文書や城郭調査などの実証的史料に基づき、詳細かつ多角的に分析・考察するものである。
屋代一族関連年表
|
年代(西暦) |
元号 |
主な出来事 |
出典 |
|
1520年 |
永正17年 |
屋代政国、屋代正重の子として誕生。 |
1 |
|
1548年 |
天文17年 |
上田原の戦い。政国の嫡男・屋代基綱が村上方として戦死。 |
1 |
|
1553年 |
天文22年 |
4月5日、政国が塩崎氏と共に武田信玄に降伏。4月9日、主君・村上義清が本拠・葛尾城を放棄し越後へ敗走。川中島の戦いが勃発する。 |
1 |
|
1559年 |
永禄2年 |
政国、本拠を荒砥城へ移す。屋代城は廃城となる。信玄より隠居料を与えられたとの記録もある。 |
4 |
|
1561年 |
永禄4年 |
第四次川中島の戦い。政国がこの戦いで戦死したとする異説が存在する。 |
1 |
|
1567年 |
永禄10年 |
武田家臣団が忠誠を誓った「下之郷起請文」に、政国が名を連ねる。 |
1 |
|
1575年 |
天正3年 |
長篠の戦い。政国の養子・屋代正長(清綱)が武田方として参陣し戦死。 |
7 |
|
1576年 |
天正4年 |
政国、弟・室賀満正の四男・秀正を新たに養子に迎え、家督を継がせる。 |
7 |
|
1582年 |
天正10年 |
武田氏滅亡。天正壬午の乱が勃発。政国の没年とする説が有力。秀正は織田家臣・森長可、次いで上杉景勝に従う。 |
1 |
|
1584年 |
天正12年 |
秀正、徳川家康と内通し上杉方から離反。荒砥城、次いで虚空蔵山城に籠城し、上杉・真田軍の攻撃を撃退する。 |
3 |
|
1600年代初頭 |
慶長年間 |
秀正の子・屋代忠正が、徳川幕府より安房国北条に一万石を与えられ、近世大名となる。 |
4 |
|
1711年 |
正徳元年 |
三代藩主・屋代忠位の代に「万石騒動」が発生。失政を咎められ改易となるが、祖先の勲功により旗本3,000石として家名は存続。 |
8 |
|
1982年 |
昭和57年 |
静岡県在住の子孫のもとで、武田信玄・上杉景勝・徳川家康らの朱印状を含む「屋代家文書」が発見される。 |
3 |
序章:戦国史における屋代政国の位置づけ
戦国時代の信濃国、特に北信濃から東信濃にかけての地域は、甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信という二大巨頭が覇を競った最前線であった。この激動の地において、一人の在地領主(国衆)の決断が、地域の、ひいては日本戦国史全体の流れを大きく変えることがある。屋代政国は、まさにそのような歴史の転換点を演出した人物であった。
彼が本拠とした屋代郷(現在の長野県千曲市屋代)は、善光寺平の南端に位置し、千曲川の東岸を押さえることで北信濃と東信濃の交通を扼する地政学上の要衝であった 7 。この地を支配する屋代氏の動向は、単に一族の盛衰に留まらず、北信濃全体の勢力図を左右するほどの重みを持っていたのである。
当初、屋代政国は北信濃に覇を唱えた村上義清配下の有力な重臣であった 3 。しかし、天文22年(1553年)、彼の武田信玄への降伏という一つの決断が、ドミノ倒しのように歴史を動かす。この離反によって主君・村上義清の防衛線は崩壊し、その没落を決定づけた 3 。そして、越後へ逃れた義清の救援要請に応える形で上杉謙信が信濃へ出兵し、十数年に及ぶ「川中島の戦い」の直接的な引き金となったのである 3 。この一点において、彼は単なる一地方領主ではなく、戦国史の大きな転換点における紛れもないキーパーソンであったと言える。
本報告書では、政国を単に「主家を裏切った武将」という一面的な評価で断じることを避ける。彼の降伏は、塩崎氏など周辺国衆と連携した上での地域的な動きであり 4 、武田信玄による巧みな調略が村上氏の支配体制の脆弱性を突いた結果であった。本報告書は、屋代政国と彼の一族が、いかにして激動の時代を読み、生き残りを図り、そして時には飛躍の機会を掴んだのかを、近年発見された「屋代家文書」などの一次史料や、彼らが拠点とした城郭の構造といった具体的な物証に基づいて多角的に解明することを目的とする。
第一章:屋代氏の出自と北信濃における勢力基盤
屋代氏の歴史は古く、清和源氏の一流で信濃に勢力を張った村上氏の支流を称する、由緒ある武家であった 8 。その名は鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』にも見え、承久3年(1221年)の承久の乱において「屋代兵衛尉」なる人物が負傷した記録が残るなど、古くからこの地に根を張っていたことが確認できる 8 。この由緒ある出自は、彼らが戦国期に突如現れた新興勢力ではなく、地域社会において正統性を有する領主として認識されていたことを示している。
戦国期における屋代氏の本拠地は、現在の千曲市屋代、しなの鉄道屋代駅の東にそびえる一重山(ひとえやま、標高458m)に築かれた屋代城であった 4 。この城は、山頂の主郭から北へ伸びる尾根上に、記録によれば12もの郭(くるわ、曲輪)を直線的に配置し、それらを幾重もの堀切や竪堀で厳重に防衛する「連郭式」と呼ばれる典型的な山城の縄張り(設計)を持つ 15 。主郭部には、防御というよりは斜面の崩落を防ぐ土留めの目的と見られる石垣も部分的に用いられており 17 、その堅固で大規模な構造は、屋代氏が相応の経済力、動員力、そして高度な築城技術を有していたことの証左である。
この屋代城の戦略的価値は極めて高い。千曲川と善光寺平南部を一望し、北信濃と東信濃を結ぶ街道(後の北国街道)を押さえる位置にある。さらに、千曲川対岸の塩崎城と連携することで、この地域の交通結節点を完全に支配下に置くことが可能であった 8 。屋代氏が村上氏の「庶流」あるいは「代官」とされながらも 8 、これほど強力な軍事拠点を有していた事実は、彼らが単なる従属的な存在ではなく、高い独立性を持った在地領主であったことを物語っている。主家である村上氏に従いつつも、自らの領地と権益を守るための強力な物理的基盤を築いていたのである。この「国衆」としての強い自立意識こそが、後の武田氏への降伏という、主家から見れば裏切り、自らの家から見れば生き残りのための合理的な選択へとつながる精神的土壌であったと分析できる。
第二章:村上義清の重臣として ―武田信玄の信濃侵攻への抵抗―
武田信玄による信濃侵攻が本格化する中、屋代政国は北信濃の雄・村上義清の重臣として、その侵攻に抵抗する最前線に立っていた。彼の妻が主君・村上義清の養女であったという事実は、両家の関係が単なる主従関係に留まらず、婚姻による血縁関係で固く結ばれていたことを示している 1 。この政略結婚は、義清が屋代氏をいかに重要なパートナーと見なし、その結束を強固にしようと図っていたかの現れである。
その忠誠は、具体的な行動と犠牲によって示された。天文17年(1548年)、村上義清が武田信玄に生涯初の大敗を喫させたとされる「上田原の戦い」において、政国は村上軍の中核として参陣した。この激戦で、屋代家は嫡男であった屋代基綱を失うという、計り知れない痛手を被ったのである 1 。嫡男の死という最大の犠牲を払ってでも武田氏と戦ったこの事実は、当時の政国が村上氏の一員として、武田の侵略を断固として食い止めようとする強い意志を持っていたことを明確に物語っている。
しかし、上田原の戦いで一時的に武田軍を退けたものの、戦局は村上氏にとって次第に不利となっていった。体勢を立て直した信玄は、力攻めだけでなく、真田幸隆らを駆使した巧みな調略によって村上方の国衆を切り崩していく。これにより、村上義清は同盟者であった小笠原長時も信濃を追われるなど、徐々にその勢力を削がれ、孤立を深めていった 18 。
嫡男を失ってまで守ろうとした村上方の劣勢が、もはや覆い隠せないほど決定的になったこと、これが政国の心を動かした最大の要因であったと考えられる。彼が個人的に抱いていたであろう武田氏への深い遺恨よりも、このまま村上方に与し続ければ一族郎党が共倒れになるという冷徹な現実認識が上回った。滅びゆく主君と運命を共にすることよりも、一族全体の存続という国衆領主としてのリアリズム(現実主義)が、彼に重大な決断を迫ったのである。この苦渋の選択は、戦国時代の国衆が常に直面していた究極の問い、すなわち「主家への忠義か、自家の存続か」を象徴している。
第三章:天文22年(1553年)の決断 ―武田氏への降伏とその波紋―
天文22年(1553年)4月5日、屋代政国は歴史的な決断を下す。千曲川を挟んで対岸に位置する塩崎城主・塩崎氏と歩調を合わせ、武田信玄の軍門に降ったのである 4 。この行動は、武田方の執拗な調略に応じたものであったと記録されており 13 、政国個人の単独行動ではなく、地域の国衆が連携して行った計画的なものであったことが窺える。
この降伏がもたらした影響は、即時かつ決定的であった。屋代城と塩崎城は、村上氏の本拠・葛尾城の南方を固める最後の防衛線であり、いわば玄関の扉であった。この両拠点を同時に、しかも内部からの寝返りという形で失ったことで、村上義清の防衛体制は完全に崩壊した。政国らの降伏からわずか4日後の4月9日、義清はもはや抵抗は不可能と判断し、父祖伝来の本拠である葛尾城を自ら捨てて、北の越後国へと敗走した 1 。
越後へ逃れた義清は、同地の領主である長尾景虎(後の上杉謙信)に救援を懇願する。信濃の秩序を守るという大義名分と、武田の勢力が国境に迫るという現実的脅威を前に、景虎はこの要請を受諾し、信濃への出兵を決意した。これが、以降5度、12年間にわたって繰り広げられる、戦国史に名高い「川中島の戦い」の直接的な原因となったのである 3 。屋代政国の降伏という一国衆の去就が、信濃一国を巡る地域紛争を、甲越二大勢力が国運を賭けて激突する巨大な戦争へとエスカレートさせる、歴史の引き金となった瞬間であった。
この一連の出来事は、戦国期における「忠義」の概念を考察する上で極めて示唆に富む。政国が、妻の養父でもある主君・村上義清を裏切ったことは紛れもない事実である。しかし、戦国時代の国衆にとっての最優先事項は、主家への滅私奉公ではなく、自らの「家」と「領地」の存続(家名存続)であった。滅びゆく主君と運命を共にするという道徳的な選択肢よりも、新たな強者に従うことで家の血脈を未来へ繋ぐという、極めて現実的な生存戦略を選択したのである。この視点に立つとき、政国は単なる「裏切り者」ではなく、激動の時代を生き抜くための冷徹な判断を下した「現実主義的な経営者」としての側面が、より強く浮かび上がってくる。
第四章:武田家臣「信濃先方衆」としての活動
武田信玄に降伏した屋代政国は、武田家の家臣団に「信濃先方衆」の一員として組み込まれた 7 。これは、信濃の旧領主たちの支配権をある程度認めつつ、武田家の軍事指揮下に編入するという、信玄の巧みな支配政策の現れである。彼らは、武田軍が信濃やそれ以北へ進出する際の先兵としての役割を期待された。
降伏に伴い、政国の所領にも変化が生じた。武田氏からは当初、恩賞として雨宮(現在の千曲市雨宮)の地を与えられたが、同年8月にはその替地として新砥(あらと、現在の千曲市上山田温泉周辺)などを与えられた 1 。これにより、屋代氏は本拠地を長年拠点とした屋代城から、新たに荒砥城へと移すことになった 4 。旧来の屋代城は、この移転に伴い永禄2年(1559年)頃に廃城になったとみられている 5 。
武田家臣として、政国は忠誠を形として示すことを求められた。永禄10年(1567年)、武田家の家臣団が信玄への忠誠を改めて誓約した「下之郷起請文」が信濃国の上田市にある生島足島神社に奉納されており、その中に屋代政国(当時は義綱を名乗っていた可能性もある)の起請文も含まれている 1 。これは、彼が武田家臣団の一員として正式に認められ、その秩序の中で行動していたことを示す貴重な一次史料である。興味深いことに、同神社に残る別の起請文では、屋代氏と領地を接する国衆・麻績氏が「特に隣接の屋代氏やその支族室賀氏、大日方氏とは私信を交わさない」と誓わされている 8 。この一文は、信玄が信濃先方衆同士の過度な連携を巧みに牽制し、相互に監視させることで支配の安定を図っていたことを示唆しており、屋代氏が武田家中において信頼される一方で、常に警戒下にも置かれるという複雑な立場にあったことを物語っている。
政国の没年については諸説あり、明確な結論は出ていない。武田家が滅亡した天正10年(1582年)に亡くなったとする説が一般的であるが 1 、永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦いで戦死したとする説も存在する 1 。また、永禄2年(1559年)に信玄から隠居料として所領を与えられたという記録もあり 6 、これを基にすれば、早々に家督を後継者に譲り、自身は隠居の身として天正年間まで存命した可能性も考えられる。永禄10年の起請文の存在を考慮すると、永禄4年戦死説の信憑性は低いと言わざるを得ない。本報告書では、少なくとも長篠の戦いで養子・正長が戦死し、その翌年に秀正が家督を継ぐという一連の出来事が、政国の存命中に行われたという蓋然性の高い見解に基づき、以降の議論を進める。
第五章:激動の家督相続 ―後継者・屋代秀正の登場―
屋代政国の後半生は、後継者問題に深く悩まされる苦難の連続であった。一族の存続を賭けて武田氏に降った彼であったが、その武田家のために後継者を次々と失うという皮肉な運命に見舞われる。
まず、本来の跡継ぎであった嫡男・基綱は、天文17年(1548年)の上田原の戦いで、武田氏と敵対していた時期に戦死した 1 。嫡男を失った政国は、一族の将来を託すため、実の弟である室賀満正の次男・正長(清綱とも)を養子として迎えた 1 。しかし、その正長もまた、天正3年(1575年)、今度は武田方として参陣した長篠の戦いで、織田・徳川連合軍の前に壮絶な討死を遂げてしまう 7 。
この一連の出来事は、屋代家が信濃の動乱にいかに深く巻き込まれ、翻弄されたかを象徴している。嫡男を「反武田」の戦で、養子を「親武田」の戦で失ったという事実は、時代の荒波の中で国衆が生き抜くことの過酷さを物語っている。
屋代氏 主要人物系図
Mermaidによる関係図
二度にわたって後継者を失った政国は、天正4年(1576年)頃、再び実弟の室賀満正に頼り、その四男である秀正(勝永、忠照とも呼ばれる)を新たな養子として迎え、屋代家の家督を継がせた 1 。
この秀正への家督相続は、屋代家の歴史における大きな転換点であった。父祖伝来の地で村上氏に仕え、苦渋の決断の末に武田氏に降った政国の世代から、武田家臣として生まれ育ち、さらにその後の主家なき動乱期を自らの才覚で乗り切っていく秀正の世代へと、歴史のバトンが渡されたのである。秀正は、旧主への葛藤を持つ政国や、武田家と運命を共にした正長とは異なる、全く新しい時代の価値観を持つ武将であった。この世代感覚の違いこそが、後の彼の、主家を次々と乗り換える大胆な行動を可能にした重要な背景であったと分析できる。
第六章:「天正壬午の乱」を駆ける ―屋代秀正の活躍―
天正10年(1582年)、織田信長の甲州征伐によって巨大な武田帝国はあっけなく滅亡した。信濃国は織田家臣の森長可らの支配下に入るが、その直後に本能寺の変で信長が横死すると、信濃は一気に権力の空白地帯と化した。この機を逃さず、北からは上杉景勝、東からは北条氏直、そして南からは徳川家康が、武田の遺領を巡って雪崩を打って侵攻を開始する。世に言う「天正壬午の乱」の勃発である 4 。
この未曾有の混乱期に、屋代家の家督を継いだ秀正は、父・政国とはまた異なる、卓越した戦略眼と行動力を発揮する。
まず、武田氏滅亡後、北信濃に進駐してきた上杉景勝の配下に入り、川中島の拠点である海津城の副将に任じられた 3。これは地理的に最も近い大勢力に従うという、国衆として極めて現実的な初期行動であった。
しかし、秀正の真価はここから発揮される。彼は上杉配下という安定した地位に安住することなく、水面下で徳川家康と密かに連絡を取り、内通していた。天正12年(1584年)、この密通が上杉方に露見すると、秀正は即座に行動を起こす。海津城を脱出して旧領の荒砥城に立てこもり、公然と上杉氏に反旗を翻したのである 3 。
上杉軍の攻撃を受けて荒砥城を追われた後も、秀正の抵抗は終わらなかった。彼はさらに要害堅固な虚空蔵山城(現在の坂城町)を占拠し、徹底抗戦の構えを見せる。この城には、上杉方の村上国清(かつての主君・義清の子)や、当時上杉配下にあった真田昌幸らの軍勢が幾度となく押し寄せた。秀正はこの猛攻を、実に18回にもわたって撃退したと伝えられており、徳川方にとって北信濃における極めて重要な橋頭堡を確保し続けたのである 3 。
この秀正の獅子奮迅の働きは、遠く三河・遠江にいた徳川家康のもとにも届いた。家康は秀正の功績を手放しで賞賛し、「比類無き働き」と記した感状(感謝状)を送っている 3 。秀正の行動は、単なる寝返りではない。天正壬午の乱という千載一遇の機会を捉え、将来の覇者となりうる主君(家康)を自ら見抜き、一族の命運を賭けて行った戦略的投資であった。当時、家康は真田昌幸の離反(第一次上田合戦)などで北信濃の経営に苦慮していた 22 。その中で、秀正が上杉・真田勢力の真っ只中で拠点を確保し続けたことは、敵の勢力を分断し、家康方の他の国衆を勇気づける計り知れない戦略的価値を持っていた。秀正は、自らの手で屋代家の存在価値を最大限に高め、来るべき徳川の世における一族の安泰を、その武功によって確実なものとしたのである。
第七章:近世大名から旗本へ ―屋代家のその後
天正壬午の乱における屋代秀正の「比類無き働き」は、徳川家康の記憶に深く刻まれた。この功績が礎となり、屋代家は戦国の動乱を乗り越え、江戸時代に新たな発展期を迎える。秀正の子・屋代忠正は、江戸幕府が開かれると、父の勲功によって安房国北条(現在の千葉県館山市北条)に一万石の所領を与えられ、屋代家はついに近世大名としての地位を確立した 4 。信濃の一国衆から大名へと至る、まさに戦国乱世の成功物語であった。
しかし、その栄華は長くは続かなかった。三代藩主・屋代忠位の時代、正徳元年(1711年)、藩の財政再建のために登用された家老・川井藤左衛門による性急な年貢増徴策が領民の激しい反発を招き、領内27ヶ村の農民が一体となった大規模な一揆「万石騒動」が勃発した 27 。領民は藩への嘆願に留まらず、江戸に出て幕府へ直訴する事態にまで発展。この結果、藩主・忠位は領内を統治できない失政を咎められ、北条藩は改易、すなわち領地没収の厳しい処分を受けることになった 8 。
屋代家の興亡は、武士社会の価値基準が、戦場で功を立てる「武功」から、領地を安定して治める「統治能力」へと移行した江戸時代の社会変化を象徴している。秀正の武功によって大名の地位を得た一族が、その孫の代に経済政策の失敗で改易されるという皮肉な結末は、時代の変化に対応することの難しさを物語っている。
だが、屋代家の血脈はここで途絶えなかった。幕府は、藩主の失政を断罪する一方で、屋代秀正が天正壬午の乱で徳川家のために立てた「比類無き」功績を高く評価していた。この祖先の勲功に免じ、大名の地位は剥奪するものの、蔵米三千俵(3,000石格の待遇)を与えるという温情ある措置が取られた。これにより、屋代一族は旗本として家名を保つことを許され、江戸幕府の家臣として明治維新を迎えることになったのである 3 。戦国末期の「創業期」の功績が、安定した江戸時代においても家の格を保証する「無形の資産」として機能し続けたことを示す好例と言えよう。
終章:現代に蘇る記憶 ―「屋代家文書」の発見とその歴史的価値―
屋代一族の波乱に満ちた物語は、明治維新後、歴史の表舞台から姿を消したかに見えた。しかし、昭和57年(1982年)、歴史を揺るがす大発見がなされる。明治維新後に静岡県に移り住んでいた屋代氏の子孫のもとで、戦国時代から代々伝えられてきた古文書群が、大切に保管されていることが判明したのである 3 。
この「屋代家文書」と名付けられた史料群は、後に一族の故郷である千曲市に寄贈され、現在、同市の文化財センターで調査・保管されている 3 。その内容は驚くべきものであった。文書群の中には、屋代政国・秀正親子が、武田信玄、上杉景勝、そして徳川家康といった戦国時代の主役たちと直接やり取りしたことを示す、彼らの朱印が押された書状などの一次史料が多数含まれていたのである 3 。
これらの古文書の発見は、信濃の戦国史研究に計り知れない貢献をもたらした。これまで『甲陽軍鑑』などの軍記物語や後世の編纂史料に頼ることが多かったこの地域の歴史を、当事者である屋代氏の視点から、生々しい一次史料に基づいて再検証することを可能にしたからである。まさに「信濃の戦国史を塗り替える一級の資料」と評価される所以である 3 。
この発見により、屋代政国という人物像もまた、新たな光のもとで捉え直すことができるようになった。彼は、滅びゆく主家を見限り、新たな覇者である武田信玄に降るという、国衆として生き残るための冷徹な現実主義に徹した人物であった。彼の決断は、北信濃の勢力図を一変させ、甲越対決の時代を招来した。そして、彼が守り抜いた「屋代」の家名は、後継者・秀正の代に再び時代の奔流に乗り、その卓越した武功によって徳川の世で大名へと駆け上がった。
一族の栄光、統治の失敗による没落、そして祖先の功績による存続という劇的な物語は、彼らが奇跡的に現代まで伝え残した古文書によって、今、私たちの前に鮮やかに蘇ったのである。屋代政国の生涯は、戦国という時代に翻弄されながらも、自らの情報収集と判断力で一族の未来を切り拓こうとした、一地方領主の力強い生き様を、現代の我々に雄弁に語りかけている。
引用文献
- 屋代正国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%AD%A3%E5%9B%BD
- G506 屋代満照 - 清和源氏 https://www.his-trip.info/keizu/entry346.html
- 屋代一族について - 一重山みらい会議 https://yashiro-1eyama.link/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- 信濃 屋代城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shinano/yashiro-jyo/
- 屋代城の見所と写真・100人城主の評価(長野県千曲市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1198/
- 砥石城 とは - Japanese dictionary, Japanese Japanese dictionary https://mazii.net/my-MM/search/japanese/jaja/%E7%A0%A5%E7%9F%B3%E5%9F%8E
- 屋代城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/entry/000682.php.html
- 屋代氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E6%B0%8F
- 山浦景国 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%B1%B1%E6%B5%A6%E6%99%AF%E5%9B%BD
- 武家家伝_屋代氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yasiro_k.html
- 万石騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E7%9F%B3%E9%A8%92%E5%8B%95
- 屋代政国(やしろまさくに)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=E701
- 屋代城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%BB%A3%E5%9F%8E
- 塩崎城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/siseki/entry/000199.html
- 屋代城 ~数多の曲輪と堀切が本丸を守る~ | 城なび https://www.shiro-nav.com/castles/yashirojou
- 文化財・遺産・史跡 アーカイブ - ちくま検定 https://chikuma-kentei.com/encyclopediacat/history/
- 屋代城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/nagano/tikumasi02.htm
- 村上義清 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/murakami-yoshikiyo/
- 上田原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 屋代城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1276
- 須田信正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E7%94%B0%E4%BF%A1%E6%AD%A3
- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/
- 天正壬午の乱【増補改訂版】 本能寺の変と東国戦国史 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/258/
- 海津城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/TokaiKoshin/Nagano/Kaidu/index.htm
- G507 室賀宗国 - 清和源氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry347.html
- 信濃に発祥した屋代一族、徳川家康に仕えた武田の遺臣・屋代秀正 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784903991825
- 万石騒動(マンゴクソウドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%87%E7%9F%B3%E9%A8%92%E5%8B%95-636597
- 万石騒動-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/5561
- 『「屋代家 文書 」ほか一括 』 - 千曲市 https://www.city.chikuma.lg.jp/material/files/group/35/city80.pdf
- 初の古文書博物館 千曲市武水別神社神官松田邸 開館/千曲市 https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/rekishibunkazaicenter/7722.html