市義直
市義直(市三郎兵衛)は宇喜多直家の家臣。美作国境の要衝・宮山城主として、織田・毛利の激戦地で防衛を担った。伝説と異なり、主君の命で開城した忠実な将。その一族は「宮山城主」の名誉を継承した。
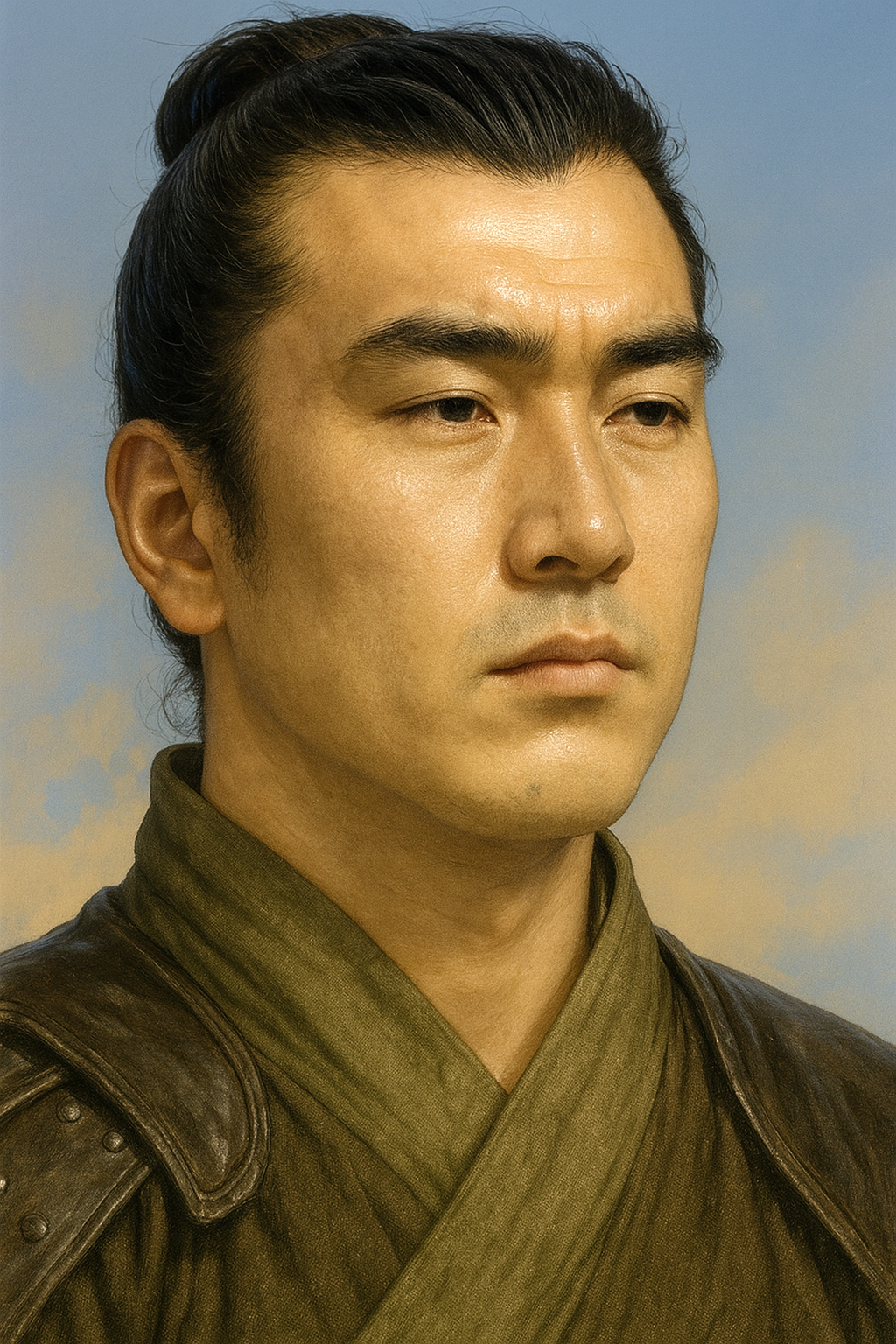
戦国武将「市義直」に関する詳細調査報告
序論:謎多き武将「市義直」を追う
主題の提示と問題提起
日本の戦国時代、数多の武将が歴史の舞台で活躍したが、その多くは詳細な記録を残さぬまま姿を消した。本報告書が対象とする宇喜多家臣「市義直」もまた、そうした歴史の狭間に埋もれた人物の一人である。利用者が提示した「市義直」という諱(いみな、実名)を持つ人物は、しかしながら、天正年間の美作国(現在の岡山県北部)における動向を記した一次史料や、信頼性の高い二次史料群においてはその名を確認することができない。
代わりに、同時代・同地域で活躍した宇喜多氏の将として、複数の史料に「市三郎兵衛(いち さぶろうびょうえ)」という名が一貫して記録されている 1 。諱ではなく、官途名風の通称(兵衛府の役職に由来する通称)で記録されている事実は、彼の出自や宇喜多家中での地位を考察する上で重要な手がかりとなる。譜代の重臣や国人領主層であれば諱が記録に残りやすいのに対し、通称で呼ばれることが多いのは、実力で登用された叩き上げの武将である可能性を示唆している。
本報告書では、利用者が探求する「市義直」と、史料上で確認できる「市三郎兵衛」を同一人物とみなし、その実像に迫ることを目的とする。彼の生涯を追うことは、単に一人の武将の経歴を明らかにするだけでなく、戦国大名・宇喜多直家の支配戦略や、織田氏と毛利氏という二大勢力の狭間で揺れ動いた「境目(さかいめ)」地域のリアルな実情を解明する一助となるであろう。
調査の対象範囲と地理的設定
本報告の主たる舞台は、備前国と美作国の国境地帯、特に現在の岡山県真庭市上市瀬に位置した山城「宮山城」である。この城は、天正年間の宇喜多・毛利両氏の角逐において、最前線の拠点として極めて重要な役割を担った。
なお、岡山県内には「宮山城」と称される城跡が複数存在し、混同を避ける必要がある。以下に主要な城を整理し、本報告の対象を明確にする。
|
城名 |
所在地(現市町村) |
主な城主・関連人物 |
時代・背景・備考 |
|
|
宮山城(高屋城) |
真庭市上市瀬 |
市三郎兵衛、小瀬修理(宇喜多家臣) |
本報告書の主題。天正年間の宇喜多・毛利の係争地 1 。 |
|
|
両宮山城 |
赤磐市穂崎 |
和田伊織(松田氏家臣) |
両宮山古墳を転用した平城。宇喜多氏に攻められ落城したが、本件とは別の城である 4 。 |
|
|
宮山城(植月城) |
勝央町植月 |
植月氏、岡豊前守 |
美作の有力国人・菅家七流の一つである植月氏の本城。本件とは別の城である 6 。 |
この表が示す通り、本報告が論じるのは真庭市に存在した宮山城と、その城主であった市三郎兵衛の動向である。
第一章:天正年間における美作国の情勢:宇喜多氏と毛利氏の角逐
「梟雄」宇喜多直家の戦略と外交転換
市三郎兵衛の活躍を理解するためには、まず彼が仕えた主君・宇喜多直家(1529-1582)の戦略を把握する必要がある。直家は、尼子経久、毛利元就と並び「中国地方の三大謀将」の一人に数えられる人物である 7 。流浪の身から身を起こし、知謀と時に非情な手段を駆使して、主君であった浦上宗景を天正3年(1575年)に追放。備前国と美作国南部、播磨国西部を支配下に収め、一代で戦国大名へと成り上がった 8 。
当初、直家は西国の雄・毛利氏に従属することで勢力を安定させていた。しかし、天正5年(1577年)に織田信長の命を受けた羽柴秀吉の中国攻めが始まると、状況は一変する。直家は、織田と毛利という二大勢力の間で、自家の存続を賭けた絶妙な立ち回りを要求された。
そして天正7年(1579年)、直家は重大な決断を下す。毛利輝元が上洛を断念するなど、毛利方の勢いに陰りが見え始めたことを見透かし、それまでの従属関係を破棄して織田信長に与することを決意したのである 10 。この外交方針の転換は、宇喜多領の運命を大きく左右するものであった。
美作国境の最前線化
直家の織田方への寝返りにより、それまで毛利氏の勢力圏との緩衝地帯であった美作国は、一夜にして織田方(宇喜多)と毛利方が直接対峙する、極めて危険な最前線へと変貌した。特に、備中・美作国境は、毛利軍の侵攻ルートの真正面に位置し、地政学的に極めて重要な防衛線となった。
この緊迫した状況下で、国境地帯の防衛を誰に任せるかは、直家の支配体制の根幹に関わる問題であった。美作の在地国人領主たちは、長年の慣習から毛利氏との繋がりも深く、忠誠心が完全に信頼できるとは限らない。下手に彼らを最前線に置けば、毛利方に寝返る危険性も否定できなかった。
このような背景を考慮すると、直家が国境防衛の要である宮山城に、市三郎兵衛という人物を配置した意味が浮かび上がってくる。市氏が美作の在地領主の系譜に見られないことから 11 、彼は直家が備前時代から抱えていた腹心か、あるいはその能力を高く評価して抜擢した「直属の将」であった可能性が高い。つまり、市三郎兵衛の宮山城への配置は、旧来の在地勢力に依存せず、自らの息のかかった信頼できる武将によって国境を防衛するという、直家の中央集権的な支配体制を象徴する人事であったと解釈できる。市三郎兵衛は、まさに宇喜多家の命運を背負い、国境の守りを託された武将だったのである。
第二章:美作の要衝・宮山城
城の地理的・戦略的価値
市三郎兵衛が守備した宮山城は、現在の岡山県真庭市上市瀬と高屋にまたがる、標高450メートル、比高320メートルの峻険な山上に築かれた要塞である 1 。別名を高屋城ともいう 13 。城の東麓には、美作を南北に貫く大河・旭川が流れ、天然の堀を形成している。眼下には、古代からの交通の要衝である出雲街道が通過する久世盆地を一望でき、地域の軍事・経済動向を完全に掌握できる絶好の立地であった 3 。
この城の戦略的価値を決定づけていたのは、旭川を挟んだ北東約2キロメートルの地点に、毛利方の拠点である篠向城(ささむきじょう)が存在したことである 3 。両城は互いを監視し、牽制しあう一触即発の状況にあり、宮山城は宇喜多方にとって対毛利防衛線の最前線基地そのものであった。
城郭の構造(縄張り)と防御思想
宮山城は、単なる見張り台や物見の砦ではなかった。現存する遺構は、この城が大軍による攻撃を想定して築かれた、極めて堅固な戦闘要塞であったことを物語っている 1 。
- 曲輪群 : 城は東西に長く伸びる尾根筋に沿って、複数の曲輪を直線的に配置した「連郭式」の縄張りを持つ。最高所に位置する西端の曲輪Iが主郭(本丸)と推定され、そこから東に向かって曲輪II、曲輪IIIと連なっている 1 。この構造は、敵に一つの曲輪を奪われても、次の曲輪で防戦を継続できる、縦深防御を意図したものである。
- 堀切と土塁 : 尾根筋を断ち切るように設けられた堀切は、深く明瞭に残存しており、特に西尾根の二条の堀切や、北側斜面の二重堀切は、敵兵の直線的な突撃を阻む強力な障害物として機能した 1 。また、曲輪の縁辺には土塁が巡らされ、城兵が身を隠しながら応戦するための防御壁となっていた。
- 畝状竪堀群(うねじょうたてぼりぐん) : 宮山城の防御思想を最もよく示す遺構が、主郭の西から南にかけての斜面に設けられた畝状竪堀群である 1 。これは、山の斜面に複数の竪堀を並行して掘り、畝のような土塁を間に残す防御施設である。この構造は、斜面をよじ登ってくる敵兵の横移動を著しく困難にし、兵力を分散させる効果がある。城兵は上方の曲輪から、動きの鈍った敵兵に対して一方的に矢や鉄砲を射かけることができ、極めて効率的な防御が可能となる。
畝状竪堀群は、戦国時代後期に発達した先進的な築城技術であり、その存在は宮山城が毛利軍による大規模な力攻めを具体的に想定し、それに対抗するために最新の軍事技術を投じて改修されたことを示している。宇喜多直家がこの城に寄せた期待の大きさと、城主である市三郎兵衛が、こうした高度な城郭を理解し、運用する能力を持った優れた指揮官であったことが窺える。
第三章:宮山城主・市三郎兵衛の実像
宇喜多家中における立場と役割
市三郎兵衛に関する直接的な記述は、江戸時代の地誌である『作陽誌』や『美作鏡』に見られる。これらの史料によると、彼は同僚の小瀬中務(史料によっては小瀬修理とも 1 )と共に、宇喜多家の将として宮山城を守っていたと記されている 2 。二人の将が配置されていたことから、宮山城が単独の城主ではなく、複数の指揮官が共同で管理する重要な軍事拠点であったことがわかる。
彼の出自については、依然として謎に包まれている。美作の有力な在地領主であった三浦氏や菅家党などの系譜に「市」姓は見当たらず 11 、彼が美作土着の国人領主ではなかった可能性は極めて高い。この事実は、彼が備前出身の宇喜多氏譜代の家臣か、あるいは直家がその武勇や才覚を見出して身分に関わらず抜擢した人物であったことを強く示唆している。いずれにせよ、彼は主君・直家からの個人的な信頼に基づいて、国境の要衝を任された腹心の一人であったと考えられる。
同僚・小瀬修理(中務)との関係
宮山城を共に守った小瀬修理(中務)は、市三郎兵衛の動向を考える上で重要な人物である。江戸時代に成立した軍記物『備前軍記』では、この宇喜多家臣・小瀬中務が、後に『太閤記』や『信長記』を著したことで知られる儒学者の小瀬甫庵と同一人物であるかのように記述されている 14 。甫庵は宇喜多家に仕えた後、諸国を流浪し、最終的に加賀前田家に仕えたとされている 15 。
しかし、近年の研究では、甫庵は尾張国の出身であることが定説となっており、宇喜多家臣の小瀬中務とは別人であるという見解が有力である 14 。『備前軍記』の著者が、物語性を高めるために、経歴の異なる二人の「小瀬」という人物を接合してしまった可能性が高い。この事例は、江戸時代の軍記物を扱う際の史料批判の重要性を示す好例であり、市三郎兵衛に関しても、後世の創作が加わっている可能性を常に念頭に置く必要がある。
軍事活動の具体像
天正7年(1579年)に宇喜多氏が毛利氏から離反して以降、市三郎兵衛は宮山城を拠点として、毛利方に対する活発な軍事活動を展開したと考えられる。利用者が事前に把握していた「高田城・松山城を分断」という働きは、この時期の具体的な活動内容を指していると推測される。高田城(現在の真庭市)は美作における毛利方の重要拠点であり、市三郎兵衛は宮山城から出撃し、これらの毛利方諸城間の連携を妨害し、補給路を遮断するなどのゲリラ的な作戦を遂行していたのであろう。
また、彼が連携したとされる伊賀久隆は、備前と備中の国境に位置する虎倉城(現在の岡山市北区)の城主であった 16 。久隆もまた、宇喜多直家に従い毛利勢と激しく戦った武将であり、天正7年に宇喜多氏が織田方へ転じた後は、毛利氏の侵攻に備える最前線に立たされた 16 。市三郎兵衛や伊賀久隆といった国境地帯の城主たちが、互いに連絡を取り合い、広域的な防衛線を形成して、西から迫る毛利の大軍を食い止めていたのである。
第四章:作州攻防戦の激化と宮山城の開城
毛利方の猛攻と周辺拠点の陥落
天正8年(1580年)に入ると、毛利方の美作侵攻は熾烈を極めた。毛利輝元は、猛将・杉原盛重らを美作に派遣し、宇喜多方の諸城に対して猛攻を開始した。この攻勢により、同年2月には小寺畑城、続いて大寺畑城が相次いで陥落し、宇喜多方の将兵は篠向城へと退却を余儀なくされた 3 。
戦況は宇喜多方にとって日に日に不利となり、天正9年(1581年)6月には、美作における宇喜多方の最重要拠点の一つであった岩屋城が、毛利軍の前に遂に攻略される 1 。そして同月29日、宮山城と旭川を挟んで対峙していた篠向城も、抗戦を断念して毛利方に降伏した 3 。この篠向城の降伏は、宮山城にとって致命的であった。連携すべき友軍を失い、周囲を完全に毛利方の勢力下に置かれた宮山城は、完全に孤立無援の状態に陥ったのである。
落城伝説と史実としての「開城」
宮山城の最期については、地元に悲劇的な伝説が残されている。それは、「天正某年の3月3日、節句の酒宴に興じている最中、毛利勢四万余騎の不意打ちに遭い、城は陥落した」というものである。この伝説に基づき、現在でも旧暦3月3日にはこの山に登るべきではないという言い伝えが残っている 3 。
しかし、この伝説は、城の最期を劇的に語り伝えようとする後世の人々の心情が生んだものであろう。より信頼性の高い史料や戦況の推移を分析すると、宮山城は戦闘によって陥落(落城)したのではなく、主君・宇喜多直家の命令を受けて、城兵の命と引き換えに城を明け渡した「開城」であったことが明らかになっている 3 。
篠向城が降伏し、宮山城が完全に孤立した状況下で、これ以上の籠城は無駄な兵力の損耗を招くだけである。奇しくもこの頃、主君の直家自身も病に倒れ、宇喜多家の将来は極めて不透明な状況にあった 10 。こうした戦略的な判断から、直家は市三郎兵衛に対して開城を命じたと考えられる。開城の時期は、篠向城が降伏した天正9年6月29日の直後、同年7月初旬頃と推定される 3 。
この「落城」と「開城」の違いは、市三郎兵衛という武将を評価する上で決定的に重要である。戦闘の末に城を奪われることは将の敗北を意味するが、主君の命令に従って城を明け渡すことは、戦略的判断を理解し、忠実に実行する指揮官の行動である。したがって、市三郎兵衛の最期は、伝説にあるような油断による悲劇的な敗北ではなく、宇喜多家の忠実な将として、与えられた任務を最後まで全うした結果であったと結論付けられる。
第五章:市一族のその後と考察
開城後の市三郎兵衛
宮山城を開城した後の市三郎兵衛の具体的な動向については、残念ながら現存する史料からその足跡を追うことは困難である。宇喜多家の家臣として、他の戦線に転じたか、あるいは一時的に逼塞していたか、その後の消息は不明となっている。
市氏存続の証左「市虎熊丸」
しかし、市三郎兵衛の一族がその後も存続していたことを示す、極めて重要な記録が存在する。それは、宮山城の麓にある天津神社の旧記に見られる、「天正二十年九月、宮山城主市虎熊丸、獅子頭一頭寄進の事」という一文である 3 。
この短い記述は、いくつかの重要な事実を示唆している。
- 市氏の存続と地域との関わり : 開城から11年後の天正20年(1592年)においても、市一族が存続し、地域の神社に寄進を行うだけの経済的・社会的基盤を保持していたことがわかる。
- 「虎熊丸」の存在 : 「虎熊丸」という名は、明らかに元服前の幼名である。これは市三郎兵衛の子息、すなわち後継者であった可能性が極めて高い。このことから、市氏は家名を絶やすことなく、次代へと継承されていたことが裏付けられる。
- 「宮山城主」という称号の意味 : 天正20年当時、宮山城は既に廃城となっていた可能性が高いにもかかわらず、「宮山城主」という肩書が記されている点は興味深い。これは、実際の役職としてではなく、かつて国境の要衝を守った功績を称える一種の「名誉称号」として、市氏の家格を示すために用いられていたと解釈できる。この事実は、天正9年の開城が宇喜多家中で不名誉なこととは見なされていなかったことを、間接的に証明している。
宮山城の終焉
宮山城そのものは、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による天下統一後、その軍事的役割を終えた。宇喜多領内では、天正17年(1589年)頃に、豊臣政権の意向を受けた城破り(一国一城令の先駆けとなる支城の破却政策)が行われており、宮山城もこの時に廃城となった可能性が高い 19 。堅固な山城は、平時の統治には不要な存在となり、歴史の舞台から静かに姿を消したのである。
残された謎:市氏のルーツ
本報告を通じて、市三郎兵衛が天正年間の美作国境において果たした重要な役割は明らかになった。しかし、彼の出自や一族の系譜、そして「義直」という諱の真偽については、依然として謎に包まれたままである。美作の在地史料にその名が見られないことから、宇喜多氏の本拠地である備前国の出身で、直家に見出されて重用された人物であったという推測が、現時点での最も有力な説と言えよう。今後の史料発見や、宇喜多家臣団に関する研究の深化が待たれるところである。
結論:歴史の狭間に生きた国境の将
本調査を通じて、戦国武将「市義直」こと市三郎兵衛の人物像は、当初の断片的な情報から大きくその輪郭を現した。彼は、地元の伝説が語るような酒宴での油断によって城を失った悲劇の将ではない。むしろ、戦国屈指の謀将・宇喜多直家から深い信頼を寄せられ、織田・毛利という二大勢力が激突する国家の最前線を任された、有能かつ忠実な指揮官であった。
彼が守った宮山城の堅固な縄張りは、宇喜多氏がこの防衛線にいかに大きな期待を寄せていたかを物語っている。そして、戦略的判断に基づく主君の命令を忠実に実行し、無駄な犠牲を払うことなく開城した彼の行動は、武将としての分別と忠誠心の証左である。開城後も、その一族が「宮山城主」という名誉ある称号と共に地域に存続していた事実は、彼の功績が宇喜多家中で正当に評価されていたことを示している。
市三郎兵衛の生涯は、巨大勢力の狭間で翻弄されながらも、自らの職務を全うした無数の「境目の武将」たちの典型例と言える。彼の名は、天下人のように歴史の表舞台に大きく刻まれることはなかった。しかし、彼のような武将たちの献身的な働きこそが、戦国大名の勢力圏を支える揺るぎない礎であったことは間違いない。
断片的な史料をつなぎ合わせ、伝説と史実を切り分け、記録の行間を読むことで、歴史に埋もれた人物像をここまで復元することができた。市三郎兵衛の生涯の探求は、一人の無名武将の物語に留まらず、戦国という時代のリアリティ、そして歴史研究そのものの意義と可能性を我々に示してくれるのである。
引用文献
- 美作 宮山城(高屋)[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mimasaka/miyayama-jyo/
- 宮山城 旧真庭郡落合町 | 山城攻略日記 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-12397159388.html
- 最後まで頑張った宇喜多の城 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2022/01/%E5%AE%AE%E5%B1%B1.html
- 備前両宮山城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/ryouguzan.htm
- 備前 両宮山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bizen/ryoguzan-jyo/
- 植月城跡(小山城)(宮山城)勝央町 - 津山瓦版 https://www.e-tsuyama.com/report/2018/08/post-1638.html
- 「宇喜多直家」稀代の梟雄と評される武将は実はかなりの苦労人!? - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/516
- 宇喜多直家・宇喜多秀家をはじめとする 「戦国 宇喜多家」を主人公とした大河ドラマ実現に向 - 岡山市 https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000058/58389/05sankou.pdf
- 宇喜多直家と城 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622717.html
- 宇喜多直家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6
- 美作三浦氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F
- 美作菅氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E8%8F%85%E6%B0%8F
- 宮山城 岡山県真庭市上市瀬・髙屋・上市瀬 - 小花と春の古城巡り https://kohanatoharu.hatenablog.com/entry/%E5%AE%AE%E5%B1%B1%E5%9F%8E
- 歴史を創作した男の創作 - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2020/04/%E7%94%AB%E5%BA%B5.html
- 小瀬甫庵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%80%AC%E7%94%AB%E5%BA%B5
- 伊賀久隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E4%B9%85%E9%9A%86
- 虎倉城 - - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-792.html
- 宇喜多秀家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%A7%80%E5%AE%B6
- 真庭市教委「宮山城」を市重要文化財(史跡)に指定したと発表 - 津山朝日新聞社 https://tsuyamaasahi.co.jp/%E7%9C%9F%E5%BA%AD%E5%B8%82%E6%95%99%E5%A7%94%E3%80%8C%E5%AE%AE%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%80%8D%E3%82%92%E5%B8%82%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%EF%BC%88%E5%8F%B2%E8%B7%A1%EF%BC%89%E3%81%AB/