庄元資
庄元資は細川政元の内衆。備中守護細川勝久と対立し「備中大合戦」を引き起こす。京兆家被官の権威を背景に守護に反抗し、備中守護家の権威を失墜させ戦国乱世への扉を開いた。二人の同名武将が存在する。
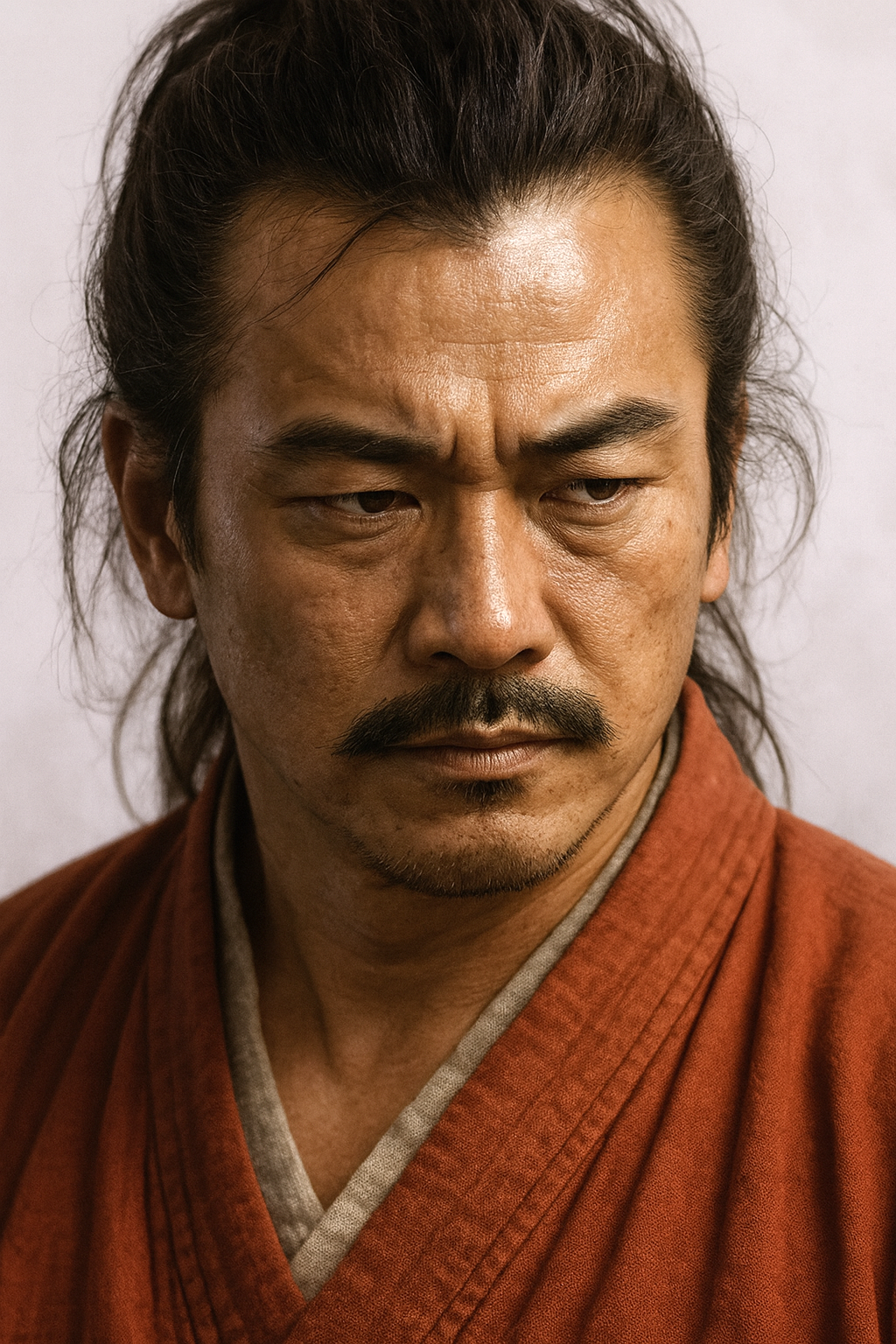
備中の動乱を駆け抜けた武将、庄元資の実像 — 中央と地方の狭間で生きた生涯
序章:二人の「庄元資」と戦国初期の政治情勢
日本の戦国時代史において、「庄元資(しょう もとすけ)」という名は、しばしば研究者や歴史愛好家の間で混乱を引き起こす。なぜなら、この名を名乗った重要な武将が、異なる時代に二人存在するためである。本報告書は、この二人の人物を明確に区別し、特に15世紀後半に室町幕府の中枢で活動し、備中国に大きな動乱を巻き起こした人物、すなわち初代の庄元資の生涯と、その歴史的意義を徹底的に解明することを目的とする。
研究対象の明確化
本報告書が主題とするのは、室町幕府の管領であった細川京兆家の内衆(ないしゅう、直属の家臣)として、主君・細川政元に仕えた15世紀の庄元資である 1 。彼は備中国の国人・庄氏の一族でありながら、その活動の主舞台は京都の中央政界にあった。しかし、その政治的立場が故郷である備中の利害と衝突した時、彼は守護・細川勝久と干戈を交える大規模な内乱、「備中大合戦」の主役となった。
一方で、約一世紀後の16世紀後半に活躍したもう一人の庄元資は、もともと備中の有力国人・三村家親の長男であり、名を穂井田元祐(ほいだ もとすけ)といった 2 。彼は毛利氏の仲介により、当時衰退しつつあった庄氏の養子に入り、その名跡を継いで「庄元資」と改名した人物である 3 。彼は毛利氏麾下の武将として各地を転戦し、その生涯は初代の元資とは全く異なる文脈の中に位置づけられる。
この二人の人物の混同を避けるため、以下にその主要な相違点をまとめた比較表を提示する。
|
項目 |
庄元資(本報告書の対象) |
庄元資(穂井田元祐) |
|
活動時代 |
15世紀後半(室町時代中期~後期) |
16世紀後半(戦国時代後期) |
|
出自 |
備中庄氏(駿河守の子) |
備中三村氏(三村家親の長男) |
|
主な主君 |
細川政元(室町幕府管領) |
毛利元就・輝元 |
|
主な活動 |
細川京兆家の内衆として中央で活動、備中守護・細川勝久と抗争 |
庄為資の養子となり庄氏を継承、毛利氏麾下として各地を転戦 |
|
生没年 |
不詳~文亀2年(1502年)頃 |
不詳~元亀2年(1571年) |
この明確な区別の上に立ち、本報告書は15世紀の庄元資の生涯を追っていく。
時代背景:応仁の乱後の権力構造
庄元資が生きた15世紀後半は、日本史における大きな転換期であった。十年以上にわたる応仁の乱(1467-1477)は、室町幕府の権威を決定的に失墜させた 4 。将軍の権力は形骸化し、幕府の実権は管領職を世襲する有力守護大名、とりわけ細川京兆家(宗家)の当主の手に集中していた 6 。
細川氏は、京兆家を頂点として、阿波、淡路、讃岐、備中などの守護職を分家が務めるという、一種の同族連合体を形成することでその権力を維持していた 7 。この体制は、一族の結束を固め、将軍による干渉を排除する上で有効であったが、一方で構造的な矛盾も内包していた。京兆家が中央集権を志向するのに対し、各分国の守護家はそれぞれの領国において自立的な支配を確立しようとする。この中央と地方の利害対立は、常に潜在的な紛争の火種となっていた 8 。庄元資の生涯は、まさにこの細川一族の構造的矛盾が、備中という一つの舞台で顕在化した悲劇であり、また戦国乱世の到来を告げる序曲でもあったのである。
第一部:備中庄氏の系譜 — 鎌倉御家人から戦国国人へ
庄元資の行動原理と、彼が引き起こした動乱の根源を理解するためには、まず彼が属した備中庄氏の成り立ちと、その特異な家系構造を把握する必要がある。庄氏は、単なる地方の土豪ではなく、鎌倉時代以来の名門としての矜持と、中央政界との深い繋がりを持つ一族であった。
一族の出自と備中への土着
庄氏の起源は、遠く関東の地に遡る。彼らは平安時代末期から鎌倉時代にかけて武蔵国で勢力を誇った武士団、武蔵七党の一つである児玉党の嫡流を汲む、由緒ある一族であった 9 。その出自は中臣鎌足を祖とする藤原氏を称しており、後年、庄元資自身も菩提寺である洞松寺への寄進状に「藤原元資」と署名していることから、その意識が強く受け継がれていたことがわかる 9 。
この関東の武士団が、西国の備中に根を下ろすきっかけとなったのは、源平合戦における一ノ谷の合戦(1184年)である。当時の児玉党惣領であった庄太郎家長は、この戦いで平家の大将・平重衡を生け捕りにするという大功を立てた 12 。その恩賞として、鎌倉幕府より備中国小田郡草壁庄の地頭職を与えられ、一族を率いて西遷したのが、備中庄氏の始まりである 6 。
家長らは、備中南部の要衝、小田川を見下ろす丘陵に猿掛城を築き、その麓に居館を構えた 6 。眼下には山陽道が東西に走り、備中南部の平野部を抑える絶好の立地であったこの城を拠点として、庄氏は次第にその勢力を蓄え、備中を代表する有力な国人領主へと成長していったのである。
室町時代の庄氏と二つの家系
時代が下り室町時代に入ると、庄氏の政治的地位はさらに向上する。彼らは備中守護に任じられた細川氏のもとで、同じく有力国人であった石川氏と共に、守護の代官である守護代の職を務めるようになった 6 。これは、庄氏が単なる在地領主から、守護の領国支配体制に組み込まれた重要な家臣へと変貌を遂げたことを意味する。
しかし、この時期の庄氏を理解する上で極めて重要なのは、一族が大きく二つの系統に分かれて活動していたという事実である。
一つは、引き続き備中に本拠を置き、守護代として地方行政を担った惣領家。
もう一つは、京に在住し、守護家の上位者である管領・細川京兆家の直属の被官、すなわち「内衆」として中央政界に仕えた庶流家である 1。
本報告書の主題である庄元資は、この後者の 庶流家 の出身であった。文安6年(1449年)付の『洞松寺文書』には、父である庄駿河守(法名・慧稠)と共に、元資の幼名である「鶴若丸」の名が記されており、彼の出自を明確に物語っている 1 。
この一族の二元的な構造は、一見するとリスク分散と機会最大化を狙った巧みな生存戦略に見える。地方に確固たる地盤を維持しつつ、中央の権力中枢にも直接的なパイプラインを確保することで、一族の安泰を図ろうとしたのであろう。しかし、この戦略こそが、皮肉にも庄元資の代に深刻な構造的矛盾を生み出すことになる。
元資の立場は、極めて「ねじれ」たものであった。彼は備中の国人として、備中守護・細川勝久の支配下にある。しかし同時に、彼は細川京兆家の内衆として、勝久の主筋にあたる管領・細川政元の直臣でもある。つまり、地方においては被官でありながら、中央の序列においては主君の主君に仕えるという、二重の主従関係の中に身を置いていたのである。この複雑で曖昧な立場こそが、彼に特異な政治行動を可能にさせ、やがて主家であるはずの備中守護家との全面対決へと彼を駆り立てる根本原因となった。庄氏が自ら作り出した家系の構造そのものが、後の「下剋上」にも似た紛争の火種を内包していたと言えるだろう。
第二部:細川京兆家内衆としての庄元資 — 中央政界での暗躍
庄元資のキャリアは、備中の在地領主としてではなく、京都の中央政界における管領・細川政元の側近として始まった。彼の前半生は、応仁の乱後の混沌とした政治状況の中で、主君の権力基盤を固めるための様々な謀略と軍事行動に彩られている。そして、この中央での活動が、後の備中での動乱に直接的な影響を及ぼしていくことになる。
管領・細川政元の側近として
元資は、若くして家督を継いだ管領・細川政元の側近集団である「内衆」の一員として、重要な役割を担っていた 1 。内衆は、単なる家臣ではなく、政元の政務を補佐し、時にはその代理として軍事・政治の最前線に立つ、まさしく政権の中枢を担う存在であった。
特に元資は、その出自から中国地方の国人との繋がりが深く、彼らとの交渉や取次を行う「申次(もうしつぎ)」の役割を果たしていたと考えられる。文明7年(1475年)には、応仁の乱が公式に終結した後も続いていた安芸・備後国境の高山城をめぐる紛争を鎮静化させるなど、細川政権の地方政策において早くからその手腕を発揮していた 1 。
丹波国出兵(文明11-12年 / 1479-1480年):主君救出と確執の始まり
元資の名を中央政界で一躍高めたのが、文明11年(1479年)に発生した「細川政元拉致事件」である。この前代未聞の事件は、政元の被官であった一宮宮内大輔が、主君である政元を丹波国に拉致・監禁したものであった 1 。事件の背景には、細川氏の分国であった丹波の守護代の地位を巡る、内藤氏と一宮氏の深刻な対立があった 14 。自らの訴えが聞き入れられないことに不満を募らせた一宮氏が、実力行使に及んだのである。
主君の危機に際し、元資は同じく京兆家内衆の安富元家(やすとみ もといえ)らと共に、政元奪回のための軍を率いて丹波へ出陣した 1 。そして翌文明12年(1480年)3月、一宮氏を討ち滅ぼし、無事に政元を救出することに成功する 1 。この功績は、元資の京兆家内における地位を不動のものにしたかに見えた。
しかし、この成功が新たな火種を生む。元資は、この丹波出兵における軍功の第一人者の座を巡って、共に出陣した安富元家と激しく対立(相論)したのである 1 。この出来事は、二人の間に終生にわたる根深い確執を刻み込んだ。個人的なライバル意識は、やがて京兆家家臣団内部の派閥争いへと発展し、その対立の構図は、遠く備中の地における大規模な内乱へと飛び火していくことになる。中央での最大の功績が、結果として地方での紛争の遠因となるという、歴史の皮肉がここに見られる。
京兆家被官としてのその他の活動
丹波での一件以降も、元資は政元の忠実な家臣として活動を続ける。
- 備前国福岡合戦(文明15年 / 1483年): 備前で起こった合戦に松田元成方として参陣。この戦いで松田方は勝利を収めたものの、元資は息子の右衛門四郎を失うという痛手を被っている 1 。
- 摂津国兵庫中荘の押領(文明16年 / 1484年): 青源寺の僧であった兄と共に、幕府の有力な財源であった相国寺の寺領を押領(不法占拠)している。幕府から停止命令が出されたにもかかわらず、これに従わなかったことから、主君・政元の内意を得た上での行動であったと推測される 1 。これは、彼が主君の利益のためには、幕府の権威さえも無視する非合法な手段を辞さない、典型的な戦国期の武将の側面を持っていたことを示している。
- 鈎の陣への不参加(長享元年 / 1487年): 9代将軍・足利義尚による六角氏征伐(鈎の陣)に際しては、元資自身は従軍せず、子の春資を代理として政元に随行させている 1 。この頃から、彼の関心が再び自らの本拠地である備中に向かい始めていたことが窺える。
これらの活動は、庄元資が単なる地方の国人ではなく、中央政界の力学の中で生きる、高度に政治的な武将であったことを物語っている。彼の忠誠は、あくまで直属の主君である細川政元に向けられており、その利益のためには幕府の法秩序や、同じ細川一門である備中守護家の権威さえも相対化しうるものであった。この思考様式こそが、次の時代を画する「備中大合戦」へと彼を導いていくのである。
第三部:備中大合戦 — 守護・細川勝久との抗争
庄元資の生涯におけるクライマックスは、延徳3年(1491年)に始まる備中守護・細川勝久との全面的な軍事衝突、いわゆる「備中大合戦」である。この戦いは、単なる一国人の反乱ではなく、応仁の乱を経て変質した室町幕府の権力構造の矛盾が、備中という一国で噴出した象徴的な事件であった。
対立の構造:京兆家被官 vs 備中守護
応仁の乱は、全国の守護の権威を揺るがし、備中もその例外ではなかった。守護・細川氏の領国支配力は次第に衰え、それに乗じて庄氏や石川氏といった在地国人が自立化の動きを強めていた 6 。
この対立の根本原因は、庄元資の特異な立場にあった。彼は、管領・細川政元の直臣であるという中央の権威を背景に、備中国内での自らの権益を拡大しようとした。一方、備中守護である細川勝久にとって、元資の動きは自らの領国支配権を脅かす、看過できない挑戦であった 7 。元資の行動は、勝久の目には「下剋上」と映ったであろうが、元資自身の論理からすれば、それは自らの主君(政元)から与えられた特権を守るための正当な闘争であった 8 。この両者の埋めがたい認識の齟齬が、武力衝突を不可避なものとした。
延徳3年(1491年)の蜂起と合戦の推移
直接の引き金は、延徳2年(1490年)頃に備中国河辺郷の代官職を巡って、庄元資と、彼の政敵である安富元家との間で始まった抗争であった 1 。安富元家が守護・細川勝久と結んだことで、この対立は「庄元資 vs 備中守護家」という構図へと発展する。
延徳3年(1491年)10月、庄元資はついに決起する。彼は同じく京兆家被官であった上野玄蕃頭元氏や、隣国讃岐の有力国人・香西五郎左衛門尉らと連携し、細川勝久に対して公然と反旗を翻したのである 1 。
当時の記録である『蔭凉軒日録』によれば、合戦の序盤は庄氏方が優勢であった。彼らは守護方の軍勢を打ち破り、その倉を襲撃・略奪するなど、大きな戦果を挙げた 9 。しかし、この報に接した在京中の守護・細川勝久が自ら備中に下向し、さらに備前の実力者であった浦上則宗が2400の兵を率いて守護方に加勢したことで、戦況は一変する 1 。
延徳4年(1492年)3月、庄氏方は大敗を喫し、元資は本拠地である猿掛城からの逃亡を余儀なくされた 1 。この時、元資の盟友であった香西氏の一党は、城の北方に位置する「寺丸」と呼ばれる曲輪で最後まで奮戦し、討死したと伝えられている 19 。敗れた元資は、同年6月頃に勝久と和議を結び、一旦は降伏した 1 。
再蜂起と晩年
しかし、この和議は束の間のものに過ぎなかった。翌明応2年(1493年)、中央で細川政元が将軍・足利義材を追放するクーデター(明応の政変)を敢行し、政局は再び混乱する。この混乱に乗じてか、備中守護職も勝久から細川駿河守(人名不詳)へと交代した 1 。
この新守護家が、庄元資ら京兆家被官の所領を押領し始めたことが、新たな火種となった。自らの権益を侵害された元資は、これに強く反発し、明応3年(1494年)までには再び蜂起する 1 。この二度目の内乱は、その後も長く続き、文亀2年(1502年)頃まで続いたと見られている。そして、庄元資自身も、この長く続いた戦乱の最中、同年頃にその波乱の生涯を閉じたと推測されている 1 。
庄元資の反乱は、一見すると守護に対する国人の「下剋上」に見える。しかし、その内実はより複雑な構造を持っていた。彼は、幕府の公式な階級秩序を単に無視したのではなく、むしろ巧みに「利用」したのである。すなわち、備中守護(地方の最高権力者)の上位に位置する管領(中央の最高権力者)の権威を盾に、守護に反抗した。これは、より大きな権威による、地方権威の切り崩しという側面を持つ、新たな時代の下剋上の形態であった。
結果として、彼の行動は備中守護家の権威を決定的に失墜させ、備中国内に権力の真空状態を生み出した。そして、その真空地帯に、もはや中央の権威に頼ることなく、純粋な実力のみで覇を競う、庄為資や三村家親といった、真の意味での戦国領主が台頭する土壌を整えることになった。庄元資は、自らがよじ登ろうとした古い秩序の梯子を、意図せずして自らの手で破壊し、本格的な戦国乱世への扉を開ける役割を演じたのである。彼の戦いは、古い秩序が内側から崩壊していく、時代の過渡期を象徴する出来事であった。
第四部:元資の死後と庄氏の変遷 — 栄華、没落、そして再生
庄元資の死は、備中における一つの時代の終わりを告げたが、それは庄一族の物語の終焉ではなかった。元資が破壊した古い秩序の廃墟の中から、庄氏は新たな戦略で再び立ち上がり、一族の栄華と、それに続く没落、そして再生という、戦国乱世を生き抜いた地方豪族の典型的な軌跡を辿ることになる。
元資の子孫と一族の動向
元資の死後、彼の子である春資が京都における京兆家被官としての地位を引き継いだ形跡がある 1 。しかし、元資が備中で起こした長年の戦乱は、庄一族の内部にも亀裂を生んでいた。元資の子の一人である兵庫助が、父とは逆に備中守護家と結びつき、他の京兆家被官の所領を押領するなど、一族内で対立があったことを示唆する記録も存在する 10 。中央との繋がりを維持しようとする系統と、在地での生き残りを模索する系統とで、一族の進むべき道は分かれ始めていた。
庄為資の台頭と「庄氏の黄金時代」
元資の死から約30年後、庄氏の中から新たな時代の覇者が登場する。庄為資(しょう ためすけ)である 11 。彼は元資とは対照的に、中央政界との繋がりよりも、備中国内での実力行使によって勢力を拡大する道を選んだ。
天文2年(1533年)、為資は山陰の雄・尼子氏の支援を背景に、備中松山城(現在の高梁市)の城主であった上野頼氏を攻め滅ぼした 11 。そして、鎌倉時代以来の本拠地であった猿掛城から、より広大な平野部を支配するのに適した備中松山城へと本拠を移したのである 9 。
これにより、庄氏は備中半国、一万貫を領有する備中最大の戦国領主へと飛躍し、一族の歴史におけるまさに黄金時代を築き上げた 11 。この時、旧本拠の猿掛城には、一族の穂田(穂井田)実近を城代として配置している 9 。
戦国大名の荒波と庄氏の没落
しかし、庄氏の栄華は長くは続かなかった。為資の死後、家督を継いだ子・高資の時代になると、周辺の政治情勢は激変する。安芸の毛利氏が中国地方の覇者として急速に台頭し、その支援を受けた備中の国人・三村氏が庄氏の強力なライバルとして立ちはだかった 25 。
両者の抗争は激化し、やがて毛利氏の圧力を受けた庄氏は、三村家親の長男・元祐(後の二代目庄元資)を養子として迎え入れるという、事実上の屈服を意味する屈辱的な和睦を結ばざるを得なくなった 3 。これにより、備中における庄氏の主導権は失われ、事実上三村氏に乗っ取られる形となった。
その後、庄高資は備前の宇喜多直家と結んで三村氏への抵抗を試みるが、元亀2年(1571年)、毛利・三村連合軍との戦いにおいて討死 9 。高資の子・勝資も尼子氏を頼って落ち延びた後、天正4年(1576年)に戦死し、ここに戦国領主としての庄氏本流は事実上滅亡した 9 。
帰農と再生
武士としての道を絶たれた庄氏であったが、その血脈は途絶えなかった。高資の弟・資直らが一族を継ぎ、彼らはかつての栄華を捨て、一族発祥の地である英賀郡津々村(現在の岡山県井原市)などに帰農した 9 。そして、江戸時代を通じて代々庄屋(村役人)を務めることで、地域の有力者としてその家名を後世に伝えたのである 11 。これは、戦国の荒波に敗れた多くの地方豪族が辿った、一つの典型的な結末であった。
庄一族の歴史は、時代の変化に対応した戦略の転換の歴史でもあった。庄元資の「中央志向」戦略は、まだ中央の権威が地方に影響を及ぼせた15世紀末という時代には有効であった。一方、庄為資の「地方割拠」戦略は、中央が形骸化し、地方での純粋な軍事力が全てを決する16世紀前半の時代変化を的確に捉えたものであった。しかし、その戦略も、毛利氏というさらに強大な戦国大名の登場によって限界を迎える。最終的に庄氏が選んだ「帰農」という道は、武士としての矜持を捨て、地域社会に深く根ざすことで一族の血脈を未来に繋ぐという、最も現実的な最終戦略であったと言えるだろう。庄元資の生涯は、このダイナミックな興亡史の、決定的な転換点となる重要な一章を形成しているのである。
結論:庄元資の歴史的評価
備中庄氏の一族、庄元資の生涯を詳細に追うことで、室町時代から戦国時代へと移行する、日本史の大きな転換期の力学が、一人の武将の生き様を通して鮮明に浮かび上がってくる。
第一に、庄元資は、室町幕府の権力構造が末期的な矛盾を露呈する中で、その「ねじれ」を巧みに利用して自己の勢力拡大を図った、過渡期の典型的な武将として位置づけられる。彼は、管領・細川京兆家の内衆という中央の権威と、備中の有力国人という地方の自立性という、二つの異なる要素を一身に体現していた。そして、その二重性を武器として、自らの上位者であるはずの備中守護・細川勝久に戦いを挑んだ。これは、旧来の秩序の内側から、その秩序そのものを破壊していく行動であった。
第二に、彼の行動が、備中を本格的な「戦国」の時代へと突入させる直接的な引き金となった点は、歴史的に極めて重要である。彼が引き起こした「備中大合戦」は、備中守護家の権威を決定的に失墜させ、この地域に権力の真空を生み出した。その結果、庄為資や三村家親に代表される、中央の権威ではなく自らの実力のみを頼みとする新たなタイプの領主が台頭する舞台を整えた。その意味で、庄元資は旧秩序の破壊者ではあったが、新秩序の建設者ではなかった。彼は、意図せずして、自らが生きる時代の幕を自らの手で下ろしたのである。
第三に、彼の生涯は、個人的な野心やライバルとの確執といった人間的な要因が、いかに大きな歴史の転換点において重要な触媒となりうるかを示す好例である。特に、丹波での主君救出という功績を巡る安富元家との対立は、単なる個人的な反目にとどまらず、京兆家家臣団の派閥争いと連動し、最終的には備中における大規模な内乱の一因となった。これは、戦国時代の紛争が、しばしば公的な利害と私的な感情が複雑に絡み合って発生したことを如実に物語っている。
総じて、庄元資という一人の武将の生涯を徹底的に調査することは、単に一個人の伝記をなぞることに留まらない。それは、応仁の乱後から本格的な戦国時代へと至る、約半世紀にわたる日本の政治・社会構造の地殻変動を、備中という一つの地域を通して、より深く、より具体的に理解するための貴重な鍵を提供するものである。彼は、中央と地方の狭間で、古い秩序と新しい時代の波に翻弄されながらも果敢に戦い、そして歴史の次なる段階への扉を開けた、まさしく時代の転換点を象徴する人物であったと言えよう。
引用文献
- 庄元資 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SyouMotosuke~izu.html
- 莊元祐- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BA%84%E5%85%83%E7%A5%90
- 荘元祐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%85%83%E7%A5%90
- 【より道‐13】随筆_『新見太平記』(長谷部さかな)|LittleVaaader/ファミリーヒストリー - note https://note.com/vaaader/n/nd9f89e5e17a2
- 知られざる戦国前夜の激動 - 細川高国VS三好之長の運命を分けた1520年5月の闘い - note https://note.com/yaandyu0423/n/n073f09f2bb3c
- 備中猿掛城主 庄氏 http://okayamaken.fc2web.com/mabi/shousi.htm
- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F
- 吉野貢著 : 『中世後期細川氏の権力構造』 : (吉川弘文館08年12月刊) https://ocu-omu.repo.nii.ac.jp/record/2003378/files/111E0000017-12-5.pdf
- 武家家伝_庄(荘)氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mim_syou.html
- 庄氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%84%E6%B0%8F
- 荘(庄)家上房郡津々村 https://gos.but.jp/shotz.htm
- 旧山陽道を眼下に望む備中猿掛城跡 | 史跡散策 https://ameblo.jp/chikuzen1831/entry-12362334127.html
- 武家家伝_備中細川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hosoka_bit.html
- なぜ主君は家臣にさらわれたのか…戦国時代幕開けのきっかけと ... https://president.jp/articles/-/95327?page=3
- オカルト武将 細川政元の戦略!|細川政元スペシャル【オールナイト幕府 176】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IAnHkqswUhQ
- 安富元家 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YasutomiMotoie.html
- 1491年―延徳三年― - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/tizu/ezu_1491.htm
- 庄氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BA%84%E6%B0%8F
- 備中 猿掛城(庄氏、毛利(穂井田)元清の居城。毛利輝元の本陣) | 筑後守の航海日誌 https://tikugo.com/blog/okayama/bichu_sarukakejo/
- 大堀切で守られた要衝の城 - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2024/07/%E7%8C%BF%E6%8E%9B%E5%9F%8E.html
- 庄為資 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%84%E7%82%BA%E8%B3%87
- 猿掛城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%BF%E6%8E%9B%E5%9F%8E
- 備中松山藩 幕末前史 - 山田方谷マニアックス https://yamadahoukoku.com/%E5%82%99%E4%B8%AD%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E8%97%A9%E3%80%80%E5%B9%95%E6%9C%AB%E5%89%8D%E5%8F%B2/
- 武家家伝_三村氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mimura_k.html
- 三村家親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%91%E5%AE%B6%E8%A6%AA
- 毛利の失墜② 備中兵乱 - 六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋〜(嶋森航) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054897753837/episodes/16816452219057483459
- 猿掛城と庄氏(岡山県矢掛町) | どこいっきょん? - FC2 http://jaimelamusique.blog.fc2.com/blog-entry-118.html
- 猿掛城主庄為資の子孫になると思われる若林次郎右衛門について - デジタル岡山大百科 https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2008022711044764992
- 前回までの『荘直温伝』を巡って https://matsuyamashoke.com/wp/hobotsuki/%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%80%8E%E8%8D%98%E7%9B%B4%E6%B8%A9%E4%BC%9D%E3%80%8F%E3%82%92%E5%B7%A1%E3%81%A3%E3%81%A6/