志道広良
志道広良は毛利元就を支えた重臣。執権として家督相続を主導し、外交手腕で毛利家を中国の覇者へ導く。91歳で没するまで毛利家を支えた。
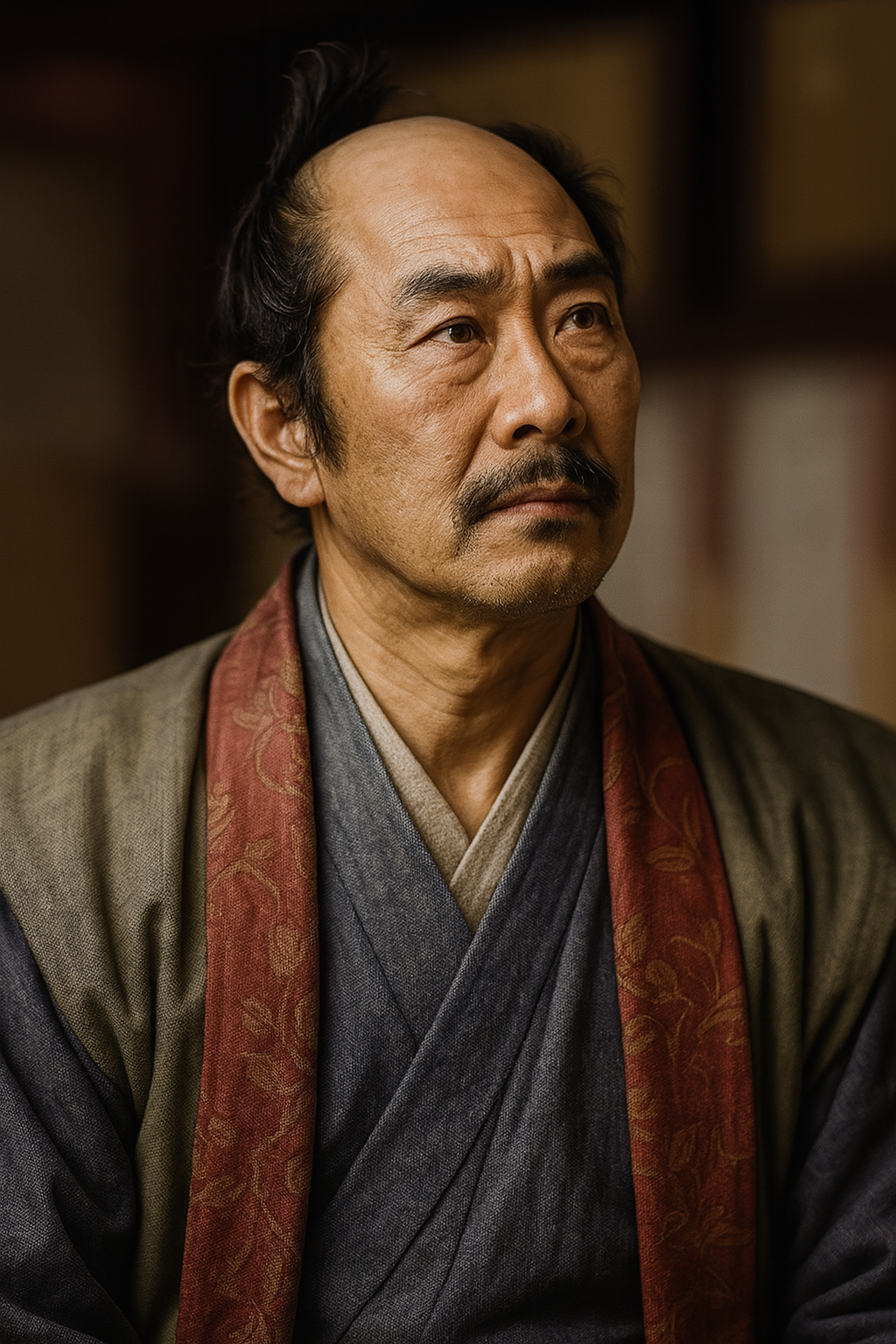
毛利家を支えた巨星、志道広良の生涯と功績
序章:毛利家を支えた巨星、志道広良
戦国時代の中国地方に覇を唱えた毛利元就。その輝かしい功績の影には、常に一人の老臣の存在があった。志道広良(しじ ひろよし)、応仁元年(1467年)に生を受け、弘治3年(1557年)に91歳で没するまで、毛利弘元、興元、幸松丸、そして元就という四代の当主に仕え、安芸国の一国人に過ぎなかった毛利氏を中国地方の覇者へと押し上げる原動力となった人物である。
彼の名は、元就の家督相続を主導し、嫡男・隆元に「君は船、臣は水」と君主のあり方を説いた忠臣として知られている。しかし、その評価は彼の功績の一端を捉えたに過ぎない。広良の91年という驚異的な長寿は、毛利家が存亡の危機を乗り越え、飛躍を遂げる激動の時代と完全に重なる。彼はその歴史の単なる証人ではなく、卓越した政治手腕と先見性をもって家中の舵を取り、時には冷徹な決断を下すことで毛利家の未来を設計した、まさしく「宰相」と呼ぶにふさわしい存在であった。
本報告書は、志道広良という人物を、単なる元就の忠臣という一面的な評価から解き放ち、その出自、元就登場以前の「執権」としてのキャリア、毛利家の命運を分けた家督相続における決定的役割、そして次代への継承という多岐にわたる功績を史料に基づき徹底的に分析する。これにより、彼の多面的な人物像と、毛利家飛躍の歴史における真の意義を再構築することを目的とする。
第一章:出自と家系 ― 毛利一門としての志道氏
志道広良の政治的影響力の源泉を理解するためには、まず彼が属した志道氏の出自と、毛利一門内におけるその特異な地位を把握する必要がある。
1.1 毛利氏庶流、坂氏からの分立
志道氏の源流は、鎌倉時代以来の毛利氏の庶流である坂氏に遡る 1 。坂氏は、毛利豊元・弘元の代には毛利家の「執権」として家政を掌握し、庶家の中でも屈指の権勢を誇った名門であった 3 。
志道広良の父は、この坂氏の当主・坂広秋の四男であった元良(もとよし)である 1 。元良は安芸国高田郡志道村(現在の広島市安佐北区白木町志路)に居住したことから、その地名を取って「志道」の姓を称するようになった 1 。これにより、志道氏は坂氏の分家として、毛利一門の中に新たな地位を築くこととなった。この事実は、広良が単なる譜代家臣ではなく、毛利本家と血縁を共有する一門衆、それもかつて家中を牛耳った坂氏の血を引くエリートであったことを示している。
1.2 志道広良の生誕と家族
志道広良は、応仁元年(1467年)、志道元良の嫡男として生を受けた 1 。父・元良が明応9年(1500年)に死去すると、広良は34歳で家督を相続し、毛利家の歴史の表舞台に登場する 5 。
彼の家族構成は、毛利家中における彼の影響力を示す上で極めて示唆に富んでいる。嫡男であった大蔵少輔は、天文8年(1539年)に広良に先立って死去したため、家督は嫡孫の志道元保が継承した 3 。
広良には他にも多くの子女がいた。特筆すべきは、後に毛利輝元を支える「御四人」の一人として毛利家の中枢を担うことになる口羽通良(くちば みちよし)である 1 。また、後述する相合元綱の変で没落した本家筋の坂氏の名跡を、息子の一人である坂元貞に継がせている 6 。これは、かつての名門・坂氏を自らの血統の下に再興させるという、高度な政治的意図が見て取れる。
さらに、娘たちを毛利家の重臣である桂元澄や福原氏、秋山氏といった有力な一族に嫁がせており、広良が婚姻政策を巧みに利用して、家中に広範な人脈と影響力ネットワークを構築していたことがうかがえる 6 。
一連の事実は、広良が単に主君に忠誠を尽くすだけでなく、自らの一族の地位を盤石にし、毛利家臣団の中核に据えようとする、極めて戦略的な思考の持ち主であったことを物語っている。
表1:志道広良 略年譜・系譜
|
西暦(和暦) |
年齢 |
主要な出来事 |
関連する毛利氏当主 |
|
1467年(応仁元) |
0歳 |
安芸国志道にて、志道元良の嫡男として生誕 1 。 |
毛利豊元 |
|
1500年(明応9) |
34歳 |
父・元良の死去に伴い家督を相続。毛利興元に仕え、執権(執政)を務める 6 。 |
毛利興元 |
|
1513年(永正10) |
47歳 |
17歳の毛利元就から、興元への忠誠と相互協力を誓う起請文を受け取る 6 。 |
毛利興元 |
|
1516年(永正13) |
50歳 |
毛利興元が死去。嫡男・幸松丸が家督を継ぐ。 |
毛利幸松丸 |
|
1523年(大永3) |
57歳 |
9歳の幸松丸が夭折。宿老会議を主導し、毛利元就の家督相続に尽力する 6 。 |
毛利元就 |
|
1524年(大永4) |
58歳 |
相合元綱の変が発生。元就を支持し、坂広秀らの反乱鎮圧に関与する 3 。 |
毛利元就 |
|
1525年(大永5) |
59歳 |
大内氏の重臣・陶興房を説得し、毛利氏の大内氏への帰属を実現させる 6 。 |
毛利元就 |
|
1537年(天文6) |
71歳 |
元就の嫡男・毛利隆元が大内氏への人質として山口へ赴く際、後見役として随行する 1 。 |
毛利元就 |
|
1539年(天文8) |
73歳 |
嫡男・大蔵少輔が死去。嫡孫の元保が後継者となる 6 。 |
毛利元就 |
|
1557年(弘治3) |
91歳 |
7月1日、防長経略が一段落した時期に死去。法名は瑞卜道亀 1 。 |
毛利元就 |
【志道氏直系略譜】
坂広秋 ― 志道元良(広良の父) ― 志道広良 ― 志道大蔵少輔(広良の嫡男、早世) ― 志道元保(広良の嫡孫、家督継承者)
第二章:毛利家執権としての初期のキャリア
毛利元就が歴史の表舞台に登場する以前から、志道広良は毛利家の中枢で絶大な影響力を行使していた。その地位を示す言葉が「執権」である。
2.1 弘元・興元・幸松丸の三代に仕えて
毛利元就が後年に記した自筆書状によれば、広良は毛利興元の代から、その子・幸松丸、そして元就自身の代に至るまで、長きにわたり「執権仕来事候」(執権を務めてきた)とされている 4 。この「執権」という呼称は、単なる家老筆頭を意味するものではない。それは鎌倉幕府の実権を握った北条氏を想起させ、名目上の当主を補佐し、事実上の最高権力者として家中の万事を差配する存在であったことを強く示唆している 4 。
しかし、この「執権」という言葉が史料上で確認できるのは、現在のところ元就の自筆書状のみであるという点は重要である 4 。これは、「執権」が毛利家における公式な職制の名称であったというよりも、むしろ元就が広良の果たした役割と絶大な影響力を、最大級の敬意と信頼を込めて表現した、個人的な評価であった可能性を示唆している。自らが苦境にあった時代から支え続け、ついには自分を当主の座に押し上げた広良の功績を、元就は鎌倉幕府の実質的支配者であった「執権」になぞらえたのである。この呼称自体が、二人の間の極めて固く、そして特殊な信頼関係を物語る証左と言えよう。
2.2 若き元就との邂逅
広良が元就の器量を早くから見抜いていたことを示す、決定的な史料が存在する。永正10年(1513年)、当時まだ多治比の猿掛城にあって分家の当主に過ぎなかった17歳の元就が、47歳で毛利家の執権として権勢を誇っていた広良に対し、起請文(誓約書)を差し出しているのである 6 。
この起請文の中で、元就は「広良とよく協力し、主君である兄・興元に忠節を尽くすこと」を神仏に誓っている。主君の弟が、筆頭家老に対して忠誠と協力を誓うという構図は、当時の武家の常識から見れば極めて異例である。これは、広良が単なる家臣ではなく、元就にとって政治的な後見人であり、その承認なくしては家中での活動がままならないほどの権威を持っていたことを示している。
同時に、この事実は広良の非凡な先見性を浮き彫りにする。彼は、まだ若く不遇であった元就を単なる主君の弟としてではなく、並々ならぬ器量を秘めた将来の逸材と見抜き、家督相続が現実のものとなる10年も前から特別な関係を築き、次代の指導者として育成していた可能性が極めて高い。二人の運命的な出会いは、この時にすでに始まっていたのである。
第三章:元就の家督相続 ― 存亡の危機における決断
大永3年(1523年)、毛利家の歴史を揺るがす一大事件が発生する。当主・幸松丸の夭折である。この未曾有の危機において、志道広良の政治手腕が遺憾なく発揮されることとなる。
3.1 幸松丸の夭折と後継者問題
当主であった毛利幸松丸が、わずか9歳で病没した 14 。指導者を失った毛利家は、北の尼子氏、西の大内氏という二大勢力の狭間で、まさに存亡の危機に立たされた。
特に、当時毛利氏が従属していた出雲の尼子経久は、この機に乗じて自らの孫を幸松丸の養子として送り込み、毛利家を完全に傀儡化しようと画策した 7 。家臣団の内部でも、元就の異母弟である相合元綱を擁立しようとする動きが起こり、毛利家中は分裂の危機に瀕した 3 。
3.2 元就擁立の立役者
この絶体絶命の状況を打開し、毛利家の未来を切り拓いたのが、執権・志道広良であった。彼は、家中が動揺する中でいち早く元就の擁立を決断し、その実現のために迅速かつ周到な政治工作を展開した 3 。
広良はまず、宿老たちによる合議を主導し、元就を後継者とすることで家中の意思統一を図った。そして、福原広俊や桂元澄ら14名の宿老と共に連署起請文を作成させ、元就に家督相続を要請した 6 。この連署状には、当時家中で大きな勢力を誇っていた井上氏の一族が5名も名を連ねており、広良が対立や軋轢を生むことなく、巧みに家中をまとめ上げた卓越した調整能力を物語っている 12 。
3.3 相合元綱の変と坂氏の反乱
しかし、全ての家臣が元就の家督相続に同意したわけではなかった。広良の本家筋にあたる坂氏の当主・坂広秀や渡辺勝らは、この決定に不満を抱き、尼子氏と結んで相合元綱を擁立し、謀反を企てたのである 3 。
これに対し、広良は断固として元就を支持し、この反乱を速やかに鎮圧。元綱と坂広秀らを粛清することで、元就の新たな権力基盤を盤石なものにした 3 。この一連の動きは、広良にとって、自らの出自である坂氏本家を排除し、分家である志道家の影響力を家中において決定的なものにするという、極めて重要な意味を持っていた。
3.4 幕府の公認と外交手腕
広良の戦略は、国内の平定に留まらなかった。彼は、内部の合意形成と反対派の粛清を推し進めると同時に、家臣の粟屋元秀を密かに京都へ派遣していた。そして、室町幕府第12代将軍・足利義晴から、元就の家督相続を正式に認める御内書(公的な承認文書)を得ることに成功したのである 6 。
これは、尼子経久が毛利家の家督問題に介入するための口実を完全に封じ込める、決定的な一打であった。幕府という最高の権威からのお墨付きを得たことで、元就の当主としての正統性は内外に証明され、もはや誰も異を唱えることはできなくなった。
広良が展開した一連の行動は、単なる忠誠心の発露ではない。それは、「家中の合意形成」「反対派の物理的排除」「外部権威による正統性の担保」という三つの戦略を、同時並行かつ迅速に実行する、極めて高度な政治的立ち回りであった。彼の先見性と卓越した戦略がなければ、毛利家はこの危機を乗り越えることはできなかったであろう。
第四章:元就の智謀の源泉 ― 軍師・外交官としての広良
毛利元就は「謀神」と称されるほどの策略家として知られるが、その智謀が現実の力として結実する背景には、常に志道広良の外交手腕と実行力があった。彼は元就の戦略を支える、いわば「影の外交部長」であった。
4.1 大内氏への鞍替えと外交戦略
元就の家督相続後、毛利家はそれまで従属していた尼子氏との関係を断ち切り、大永5年(1525年)、西の強国である大内氏に再び従属するという、重大な外交方針の転換を行った 7 。この方針転換が成功した最大の要因は、志道広良と大内氏の重臣であった陶興房(すえ おきふさ、後の陶晴賢の父)との間に、個人的な信頼関係に基づく強固なパイプが存在したことであった 6 。
広良は興房を説得し、一度は離反した毛利氏の帰参を認めさせた。これにより、毛利氏は強大な大内氏の庇護下に入ることで尼子氏の脅威から逃れ、安芸国内で勢力を着実に蓄えるための貴重な時間を得ることができた。彼の外交手腕は高く評価され、享禄3年(1530年)に尼子氏の内部で塩冶興久の乱が起こった際には、陶興房が広良に意見を求めるほど、その存在は重きをなしていた 6 。元就が描く壮大な戦略図を、現実の外交交渉によって形にしていたのが広良だったのである。
4.2 吉田郡山城の戦いと井上氏粛清
毛利家の命運を左右した二つの大事件においても、広良の存在は不可欠であった。天文9年(1540年)、尼子晴久率いる3万の大軍が毛利家の本拠地・吉田郡山城を包囲した「吉田郡山城の戦い」では、元就の幕僚として籠城戦の指揮に関わったとされる 7 。伝承によれば、城の改修や兵糧管理を担当し、絶望的な状況下で大内氏への援軍要請を成功させる上で重要な役割を果たしたという 20 。
さらに、天文19年(1550年)、元就は長年にわたり家中で増長し、当主の権力を脅かす存在となっていた井上一族の粛清という、血を伴う大改革を断行する 7 。この極めて困難な政治工作において、中心的な役割を担ったのも広良であったと伝えられている 20 。周到な準備の末に井上氏を排除したことで、元就の独裁的な権力が確立され、国人領主の連合体に過ぎなかった毛利家は、当主の強力なリーダーシップの下で統制された真の戦国大名へと脱皮を遂げたのである。
第五章:次代への継承 ― 毛利隆元の後見役
自らの手で元就を当主の座に据え、その覇業を支え続けた広良に、晩年、最後の重要な任務が与えられる。それは、毛利家の未来そのものである次代の当主・隆元の育成であった。
5.1 嫡男・隆元の傅役として
元就は、自らの後継者である嫡男・毛利隆元の教育と後見という大役を、最も信頼する広良に託した 1 。天文6年(1537年)、隆元が大内義隆への人質として、その本拠地である周防国山口へ赴くことになった際、当時すでに71歳という高齢であった広良が傅役(ふやく、後見人兼教育係)として随行した 1 。これは、元就が広良の知見と人格に全幅の信頼を寄せていたことの何よりの証拠である。
5.2 諫言「君は船、臣は水」の真意
広良が隆元を諭した言葉として、後世に最もよく知られているのが「君は船、臣は水」の逸話である。彼は隆元に対し、次のように説いたと伝えられる。
「君は船、臣は水にて候。水よく船を浮かべ候ことにて候。船候も水なく候へば、相叶はず候か」
(主君は船、家臣は水のようなものです。水はよく船を浮かべるものですが、船があっても水がなければ、どうにもならないでしょう)6。
この言葉は、単に家臣の重要性を説くだけではない。そこには、「水は船を浮かべることもできるが、荒れ狂えば簡単に船を覆すこともできる」という、より深く、そして厳しい君臣関係の本質を突いた含意があった 6 。すなわち、家臣の支持と信頼なくして君主の地位は成り立たず、彼らの心を失えば、いかに強大な権力を持つ君主であろうと、その地位は危うくなるという戒めである。
この有名な逸話の直接的な出典は、江戸時代に成立した軍記物語である『陰徳太平記』などであり、言葉そのものが史実であったかについては慎重な検討を要する 7 。しかし、この逸話がなぜ生まれ、語り継がれたのかを考えることこそが重要である。それは、毛利家が国人領主の連合体から強力な戦国大名へと移行する中で、家臣団の統合がいかに死活的な課題であったかを象徴している。父・元就が権謀術数と恐怖によって家臣を統制したのに対し、温厚な人柄であった隆元には、徳と信頼による統治が求められた。広良の諫言とされるこの言葉は、まさにそうした毛利家の統治理念の変化と、次代の君主が心すべき要諦を体現する「教訓物語」として、後世に形作られ、受容されたのである。
第六章:晩年と後世への影響
志道広良の生涯は、毛利家の覇権確立を見届けたかのように、静かに幕を閉じる。しかし、彼が遺した影響は、その死後も長く毛利家を支え続けた。
6.1 九十一歳の長寿と死
毛利氏が厳島の戦いで陶晴賢を破り、続く防長経略によって大内氏の旧領をほぼ手中に収め、中国地方における覇権を確立した直後の弘治3年(1557年)7月1日、志道広良は91歳でその長大な生涯を終えた 1 。彼の死は、元就と共に歩んだ毛利家飛躍の一つの時代の終わりを象徴する出来事であった。
6.2 志道一族の繁栄と毛利家への貢献
広良の最大の功績は、個々の戦功や外交交渉に留まらない。彼の真の遺産は、毛利家を永続的に支える「人」と「システム」を構築したことにあった。
彼の死後も、彼が築いた基盤は揺るがなかった。家督を継いだ嫡孫の志道元保は、厳島の戦いや防長経略で武功を挙げ、毛利家の主要な家臣として活躍を続けた 8 。そして、息子の口羽通良は、元就死後の輝元体制において、吉川元春、小早川隆景、福原貞俊と並ぶ「御四人」と称される最高幹部の一人として、毛利家の中枢で重責を担った 10 。
志道氏とその分家である口羽氏は、江戸時代に入って長州藩となってからも、寄組(上級家臣)という高い家格を維持し続けた 3 。これは、広良が一代で築き上げた功績と影響力が、数世代にわたって一族の繁栄を保証するほどの大きなものであったことを示している。
6.3 史跡を訪ねて:志道氏の墓所と居城跡
志道広良の功績を偲ぶ史跡は、現代にも残されている。彼の本拠地であった志道城は、現在の広島県安芸高田市向原町有留にあったとされ、その周辺は志道氏ゆかりの地として知られている 5 。
また、広良の菩提寺であった龍福寺の跡地(広島市安佐北区白木町)には、現在も志道氏一族の墓所が残されており、毛利家の礎を築いた老宰相の眠る地として、その歴史を今に伝えている 30 。
結論:戦国最高の宰相の一人としての評価
本報告書を通じて明らかになった志道広良の実像は、単なる「忠臣」や「元就の補佐役」という言葉では到底捉えきれない。彼は、主君・元就の影に隠れがちであるが、その実態は、卓越した政治力、家中をまとめ上げる調整能力、そして次代を見据える非凡な先見性を兼ね備えた、戦国時代屈指の「宰相」であった。
彼の91年の生涯は、安芸の一国人に過ぎなかった毛利家が、存亡の危機を幾度も乗り越え、中国地方の覇者へと駆け上がる激動の時代そのものであった。そして、家督相続、外交方針の転換、家中の内紛鎮圧、次代の育成といった、その全ての重要な局面において、彼は常に中心的な役割を果たし、最善の道筋を描き出した。
毛利元就という英雄の類稀なる智謀と決断力が、志道広良という稀代の宰相による盤石な基盤と実行力なくしては、決して歴史を動かすほどの力とはなり得なかったであろう。志道広良は、戦国時代が生んだ最高の補佐役の一人として、その功績を再評価されるべき人物である。
引用文献
- 志道広良(しじ・ひろよし) 1467~1557 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ShijiHiroyoshi.html
- 毛利氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%8F
- 志道氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E9%81%93%E6%B0%8F
- 毛利氏執権制の再検討 https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2023077/files/SigakuKenkyu_307_27.pdf
- 志道元良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%85%83%E8%89%AF
- 志道広良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%BA%83%E8%89%AF
- 【安芸毛利家】毛利元就と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/mori/
- 志道元保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%85%83%E4%BF%9D
- 志道広良とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%BA%83%E8%89%AF
- 口羽通良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A3%E7%BE%BD%E9%80%9A%E8%89%AF
- 桂元澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%85%83%E6%BE%84
- 毛利氏とその家中 https://lab.kuas.ac.jp/~jinbungakkai/pdf/2021/h2021_08.pdf
- 毛利家・家臣団 - 日记 - 豆瓣 https://m.douban.com/note/349353684/
- 毛利元就の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8100/
- 第37話 「三本の矢」で知られる毛利元就と小倉城との関係 https://kokuracastle-story.com/2021/03/story37/
- 戦国時代に策略家として名を馳せた毛利元就はどんな人生を歩んだのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28255
- 元就。とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%83%E5%B0%B1%E3%80%82
- 公開講座録「毛利元就と井上元兼」 - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-350.html
- 久しぶりに『毛利元就』を見る | せめて窓辺の月 http://nandothers.blog.fc2.com/?no=211
- 志道広良(しどう ひろよし) 拙者の履歴書 Vol.312~毛利元就を支えた忠臣の生涯 - note https://note.com/digitaljokers/n/n1752d89d2afb
- 新宮党の一矢 - 登場人物紹介 https://ncode.syosetu.com/n4186gd/1/
- 新カード武将の役に立たない解説の話 | 英傑大戦のコミュニティ https://taisengumi.jp/posts/161552
- 日本史の中に生きた人物の歴史を紹介しその生きざまを考証する私設サイトです。 http://www.web-nihonshi.jp/death-2.html
- 11月2022 - 日本史專欄 http://sengokujapan.blogspot.com/2022/11/
- 福原貞俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%8E%9F%E8%B2%9E%E4%BF%8A
- 萩藩諸家系譜 http://www.e-furuhon.com/~matuno/bookimages/11960.htm
- 志道元保とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%85%83%E4%BF%9D
- 英賀城 松尾城 高橋城 古吹城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/hirosima/akitakadamidori.htm
- 文化 安芸高田歴史紀行 - マイ広報紙 https://mykoho.jp/article/342149/9252436/9397442
- 安芸の戦国再発見 https://www.mogurin.or.jp/museum/library/event/h22_akinosengoku.pdf