松前盛広
松前盛広は松前藩初代藩主慶広の子。若くして病没したが、京都で文化を学び、徳川家康に拝謁。松前藩成立期の重要な橋渡し役を担った。
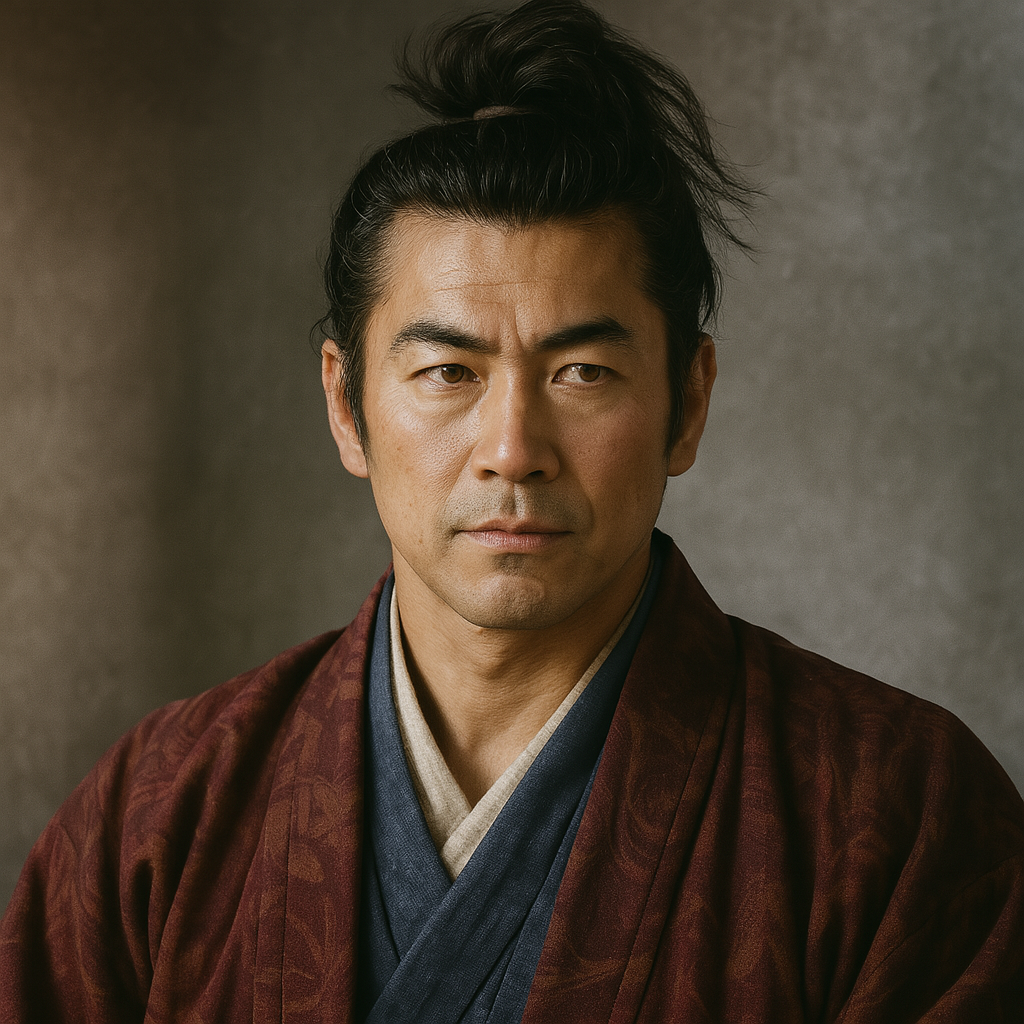
歴史の狭間に生きた世子 ― 松前盛広の生涯と松前藩成立期における役割
序章:継承されるべき未来 ― 松前盛広という存在
日本の歴史が安土桃山時代の終焉から江戸幕府による泰平の世へと大きく舵を切る、まさにその転換期において、北の辺境・蝦夷地(現在の北海道)に、特異な運命を背負った一人の武将がいた。その名を松前盛広(まつまえ もりひろ)という。彼は、松前藩の始祖として絶大な権威を誇った父・慶広(よしひろ)と、その孫にして藩政の基礎を固めた二代藩主・公広(きんひろ)という、二人の偉大な当主の間に存在する人物である。公式な記録上、彼は藩主の座に就くことなく、父に先立って病没した「早世の世子」として記憶されている 1 。
しかし、盛広の生涯を単なる悲運の一言で片付けることは、松前藩成立期の複雑な力学を見誤ることになる。中央の動乱から物理的に隔絶されながらも、天下の趨勢と決して無縁ではいられなかった松前氏(旧姓・蠣崎氏)は、豊臣政権から徳川幕府へと移り変わる権力の奔流の中で、生き残りを賭けた巧みな外交戦略を展開していた 3 。その戦略の一翼を担い、父と共に次代の覇者・徳川家康に拝謁し、藩の未来を託されたのが、まさしく世子・盛広であった 2 。
本報告書は、この松前盛広という人物を、「幻の藩主」あるいは「継承の架け橋」として再評価することを目的とする。断片的に伝わる彼の生涯の記録を、家族関係、中央政権との交渉、文化的活動、そして死後の扱いといった多角的な視点から統合し、分析する。それにより、彼が松前藩の黎明期において果たした、目立たずとも不可欠であった役割を立体的に再構築し、その歴史的意義を明らかにしたい。盛広の短い生涯を丹念に追うことは、北の王国・松前藩がいかにして二百数十年続く礎を築いたのか、その深層を理解するための重要な鍵となるであろう。
第一章:北の辺境に生まれて ― 誕生と血脈、そして宿命
松前盛広の生涯を理解するためには、まず彼がどのような時代背景と家族環境の中に生を受けたのかを深く掘り下げる必要がある。彼の出自と血脈、そして家中に渦巻いていた後継者を巡る緊張関係は、彼の運命を大きく左右する要因となった。
誕生と時代背景
松前盛広は、元亀二年(1571年)に生を受けた 1 。この年、中央では織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちにするなど、天下統一に向けた苛烈な戦いが繰り広げられていた。しかし、遠く離れた蝦夷地において、盛広の父・慶広はまだ家督を継いでおらず、蠣崎氏の一族として、宗家である出羽国の安東氏の支配下で蝦夷地の和人社会を束ねる一領主に過ぎなかった 3 。盛広の誕生は、蠣崎氏がまだ独立した大名ではなく、やがて訪れる大きな変化の予兆をはらんだ静かな時代の中での出来事であった。
父・慶広は、盛広が十二歳となった天正十年(1582年)に家督を相続する 3 。この頃から慶広は、安東氏からの独立と、天下人との直接的な関係構築を視野に入れた、野心的な戦略を展開し始める。盛広は、そのような父の背中を見ながら、蠣崎家の世子として成長していくこととなる。
血筋の意義と複雑な家族関係
盛広の父は、後に松前藩の初代藩主となる松前慶広。そして母は、蠣崎家の家臣であった村上季儀(すえよし)の娘である 1 。この婚姻は、単なる家臣との結びつきに留まらず、蝦夷地における在地勢力との連携を強化し、蠣崎家が在地領主としての支配基盤を固めていく上での重要な政略的意味合いを持っていたと考えられる。盛広は、この蠣崎家の嫡男として、一族の期待を一身に背負う存在であった。
しかし、その立場は必ずしも安泰ではなかった。慶広には盛広の他にも数多くの男子がおり、家中の権力構造は複雑な様相を呈していた 1 。特に盛広の人生に影を落としたのが、四男・由広(よしひろ)の存在である。盛広には長らく嗣子となる男子が生まれなかったため、弟である由広が一時的に盛広の養子となり、後継者候補とされた時期があった 6 。ところが、慶長三年(1598年)に盛広に待望の嫡男・公広(後の二代藩主)が誕生すると、この養子縁組は白紙に戻される 7 。
一度は世子の養子という次期当主にもっとも近い立場にありながら、その地位を追われた由広は、父・慶広や兄・盛広、そして甥にあたる公広に対して深い確執を抱くようになったと伝えられる 7 。彼の行動は次第に「粗暴」になり、慶長十七年(1612年)には紀伊国高野山に母の供養で赴いたついでに、幕府が警戒する豊臣秀頼に謁見するという、松前家の存亡を揺るがしかねない行動に出る 6 。この一件は、藩祖・慶広の逆鱗に触れ、最終的に由広は父の命によって誅殺されるという悲劇的な末路を辿った 6 。
この一連の出来事は、単なる家族内の不和として片付けられる問題ではない。それは、藩主家の後継者問題が、いかにその支配体制の根幹を揺るがす脆弱なものであったかを示している。同時に、実子である由広の殺害という父・慶広の冷徹な決断は、徳川の世において少しでも幕府に疑念を抱かせる要素を徹底的に排除し、藩の存続を最優先しようとする、藩祖としての強烈な意志と絶対的な権力の現れであった。この非情な決断は、盛広からその子・公広へと続く嫡流の継承ラインを盤石にするための、血塗られた地ならしであったとも解釈できる。盛広は、このような緊迫した家中の力学の中で、世子としての重責を担い続けていたのである。
表1:松前盛広 関連略年表
|
西暦 |
元号 |
松前盛広の動向 |
松前家(蠣崎家)の動向 |
日本中央の動向 |
|
1571年 |
元亀2年 |
誕生 1 |
|
織田信長、比叡山延暦寺を焼き討ち |
|
1582年 |
天正10年 |
(12歳) |
父・慶広が家督を相続 3 |
本能寺の変 |
|
1587年 |
天正15年 |
(17歳) 京都に滞在し、観世流の太鼓を習う 10 |
|
豊臣秀吉、九州を平定 |
|
1590年 |
天正18年 |
(20歳) |
父・慶広、秀吉に謁見し所領安堵 3 |
豊臣秀吉、天下統一 |
|
1596年 |
慶長元年 |
(26歳) 父・慶広と共に徳川家康に拝謁 2 |
|
|
|
1598年 |
慶長3年 |
(28歳)長男・公広が誕生 8 |
|
豊臣秀吉、死去 |
|
1599年 |
慶長4年 |
(29歳) |
蠣崎から「松前」へ改姓 11 |
|
|
1600年 |
慶長5年 |
(30歳) 内々に家督を相続したとされる 12 |
福山館の築城を開始 12 |
関ヶ原の戦い |
|
1604年 |
慶長9年 |
(34歳) |
徳川家康より黒印状を拝領 13 |
徳川家康、江戸幕府を開く(前年) |
|
1608年 |
慶長13年 |
(38歳) 病により死去 1 |
|
|
表2:松前家 主要関係者系図(盛広周辺)
蠣崎季広(4代)
┃
松前慶広(初代藩主)
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
(正室:村上季儀の娘) (側室)
┃ ┃
┏━━━┻━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━╋━━━(他多数)
松前盛広(本稿の主題) 喜庭直信室 松前忠広 松前由広 松前景広
┃
(妻:下国直季の娘)
┃
松前公広(2代藩主)
注:本系図は本報告書の議論に関わる主要人物に絞って簡略化している。
第二章:世子としての器量 ― 中央への眼差しと文化的素養
辺境の地に生まれ育った盛広であったが、彼の視野は蝦夷地の内に留まるものではなかった。若き日の彼の足跡は、彼が松前家の将来を担う世子として、いかに中央の政治・文化の動向を意識し、その中で自らの、そして一族の価値を高めようとしていたかを物語っている。特に、京都での文化修練と徳川家康への拝謁は、彼の器量と松前家のしたたかな生存戦略を象ucちょうする重要な出来事であった。
京での文化修練とその政治的意味
松前藩の公式な記録である『新羅之記録』には、注目すべき一節がある。それによれば、盛広は家督を継ぐ前の天正十五年(1587年)、十七歳の若さで京都に滞在し、当代一流の能楽流派である観世流の太鼓打ち、観世与左衛門尉の子・与十郎に弟子入りし、その技を習得して名手となったと記されている 10 。
この記録は、単に若き世子の個人的な趣味や教養の習得として読み過ごすべきではない。ここには、高度な政治的意図が隠されていると見るべきである。天正十五年という時期、父・慶広は主家である安東氏からの完全な独立と、天下人となった豊臣秀吉との直接的な関係構築を悲願としていた 3 。しかし、蝦夷地の領主は中央の権力者から見れば、文化的に洗練されていない「狄(えびす)の酋長」と見なされ、政治的にも格下として扱われる危険性が常にあった。
このような状況下で、跡継ぎである盛広を政治の中心地・京都に送り込み、武芸ではなく、当時の最高級の文化であった能楽、それも観世流の太鼓を学ばせるという行為は、「我々は北の粗野な武人ではない。中央の洗練された文化を理解し、その一員となる資格と教養を十分に備えている」という強力なメッセージを発信するものであった。これは、武力や経済力だけでなく、文化的な権威、いわゆる「文化的資本」をも駆使して、一族の地位向上を図ろうとする、松前家の長期的かつ巧みなイメージ戦略の一環であった。この文化的な下地作りが、後に慶広が前田利家といった中央の実力者に取り入り 3 、天正十八年(1590年)の秀吉への謁見という快挙を成し遂げる上で、少なからぬ潤滑油となった可能性は十分に考えられる。盛広の京での活動は、松前家が中央政界へ進出するための、重要な布石だったのである。
徳川家康への拝謁と次代への布石
盛広の世子としての重要な役割を示すもう一つの出来事が、慶長元年(1596年)に行われた徳川家康への拝謁である 2 。この時、盛広は父・慶広に帯同し、当時内大臣であった家康に謁見している。
この時期の政治情勢は極めて流動的であった。天下人・豊臣秀吉はまだ健在であったものの、朝鮮出兵の失敗や後継者問題などでその権勢には明らかに陰りが見え始めていた。一方で、徳川家康は着実にその影響力を増大させており、次代の天下を担う最有力候補として台頭しつつあった。このような天下の分水嶺ともいえるタイミングで、父・慶広が世子である盛広を伴って家康に接近したという事実は、慶広が秀吉後の政局を見据え、次代の覇者として家康を明確に認識していたことの何よりの証左である。
この拝謁は、単なる挨拶以上の意味を持っていた。世子・盛広を同席させることで、松前家が親子二代にわたって徳川家に忠誠を誓うという強固な意思表示となり、将来にわたる松前家の安泰を確保するための、極めて重要な外交活動であった。慶長四年(1599年)に慶広が家康に蝦夷の地図などを献上して臣従の意を示し 15 、蠣崎から松平の「松」と前田の「前」を取ったとされる「松前」へと改姓したのも 4 、この拝謁に始まる一連の対徳川外交の延長線上にあった。盛広は、松前家が激動の時代を乗り切り、新たな支配者の下でその地位を確立していくという、歴史的な転換点の証人であり、当事者だったのである。
第三章:松前藩の成立と盛広の曖昧な立場
関ヶ原の戦いを経て徳川の覇権が確立すると、松前家もまた新たな時代への対応を迫られる。この時期、松前藩が公式に成立していく過程において、盛広は極めて曖昧かつ複雑な立場に置かれることとなった。彼は「藩主」であったのか、それとも単なる「世子」であったのか。その実態は、松前家が置かれた過渡期特有の事情を色濃く反映している。
「内々の家督相続」という謎
松前家の歴史を語る上で、一つの謎とされるのが盛広の家督相続である。一部の記録によれば、関ヶ原の戦いがあった慶長五年(1600年)、盛広は「内々」に家督を相続したとされている 12 。しかし、これは江戸幕府による公式な代替わりの承認を得たものではなく、対外的には依然として父・慶広が当主として振る舞い続けていた。この非公式な家督相続は、一体何を意味するのだろうか。
この「内々の家督相続」は、当時の松前家が直面していた内外の課題に対応するための、戦略的な統治体制であったと解釈するのが最も妥当であろう。すなわち、内外での役割分担である。慶長五年は、徳川家康が天下統一を成し遂げた決定的な年であり、松前家にとって新政権との関係をいかに構築するかは、一族の存亡をかけた最重要課題であった 9 。一方で、領内ではこの年から居城となる福山館の築城が開始されるなど 12 、大規模な事業が進められていた。
このような状況下で、老練な外交手腕と中央に豊富な人脈を持つ父・慶広が、江戸や京都での困難な政治交渉に専念する。その間、領内の統治や家臣団の掌握、そして城普請の監督といった内政を、信頼できる後継者である盛広に委ねる。これは極めて合理的な分業体制である。藩内的に「家督相続」という形式を取ることで、盛広の権威を高め、家臣団に対する指揮命令系統を明確にする狙いがあったと考えられる。この巧みな権力委譲により、慶広は後顧の憂いなく対外活動に邁進することができ、それが後の黒印状獲得という大きな成果に繋がったのである。この非公式な相続は、松前家が藩として自立していく過渡期における、巧みな統治の試みであった。
松前藩の確立と黒印状
慶長の世が安定すると、慶広の長年にわたる外交努力はついに実を結ぶ。慶長九年(1604年)一月、将軍・徳川家康は松前慶広(当時の官位から松前志摩守)に対し、蝦夷地におけるアイヌとの交易独占権を公式に認める黒印状(制書)を発給した 13 。この黒印状は、稲作が不可能で石高を持たない松前藩が、幕藩体制の中で大名格として存続するための経済的基盤を確立した、歴史的に極めて重要な文書である。これにより、他の者が松前氏の許可なく蝦夷地で交易を行うことは禁じられ、松前藩は北方の交易利権を独占する特異な藩として成立した。
この歴史的な黒印状の獲得は、表向きには父・慶広の功績として記録されている。しかし、その偉業の背後には、父が安心して領地を留守にできるよう、領内の統治を安定させていたであろう盛広の「内治」の貢献があったことは想像に難くない。盛広は、公式の歴史には名を残さずとも、松前藩成立の土台を支える重要な役割を果たしていたのである。
この時期の盛広の立場は、その呼称の混乱にも現れている。彼は、蠣崎氏の祖先からの通算で「六世当主」と呼ばれることがある一方 10 、藩内では実質的な「二代藩主」と見なされることもあった。しかし、幕府の公式な記録上、松前藩の藩主は初代・慶広の次は、盛広の子である公広が二代藩主とされている 8 。この複雑な位置づけこそ、盛広の生涯を象徴している。彼は公式な藩主ではなかったが、実質的な統治者として行動した期間を持つ、「過渡期の統治者」だったのである。
第四章:志半ばの死と遺されたもの
藩の黎明期にあって、内政を担い将来を嘱望されていた盛広であったが、その運命はあまりにも早く暗転する。彼の志半ばでの死は、松前家の権力継承に大きな影響を与え、その存在は死後、複雑な形で歴史に刻まれることとなった。
三十八歳の早世と権力継承の変転
慶長十三年(1608年)一月、松前盛広は病に倒れ、父・慶広に先立ってこの世を去った。享年三十八という若さであった 1 。父・慶広が描いていたであろう、経験を積ませながら徐々に権力を移譲していくという計画は、この早すぎる死によって頓挫した。
盛広の死により、松前家の後継者問題は新たな局面を迎える。世子を失った慶広は、盛広の長男であり、自らにとっては嫡孫にあたる公広を新たな世子として指名した 1 。当時、公広はまだ十一歳の少年であった。そして八年後の元和二年(1616年)、藩祖・慶広が六十九歳で没すると、公広がその跡を継ぎ、幕府に公認された松前藩二代藩主となったのである 5 。この祖父から孫へと直接的に家督が継承されるという異例の事態は、盛広の早世がもたらした特異な結果であった。
二代藩主となった公広は、若くしてその才覚を発揮する。金山奉行を設置して藩の財源確保に努め、また、上級家臣に交易権を知行として分与する「商場知行制」を確立するなど、初期藩政の安定に多大な功績を残した 8 。これらの政策は、もし盛広が生きていれば彼自身が担ったであろうものであり、公広は父の遺志を継ぎ、あるいは父が敷いた路線を発展させる形で、松前藩の未来を築いたと評価できる。
墓所の配置が語る歴史的評価
盛広の死後、彼の存在が松前家の歴史の中でどのように位置づけられていったのか。その問いに対する一つの答えは、松前家の菩提寺である法幢寺(ほうどうじ)の墓所に静かに示されている。国指定史跡でもあるこの墓所には、松前藩の始祖から歴代藩主、そしてその一族が眠っている 22 。
墓所は大きく二つの区画に分かれている。本堂に近い主たる区画には、藩祖・慶広や二代藩主・公広、そしてそれ以降の歴代藩主たちの墓が、藩の権威と正統性を示すかのように整然と並んでいる 22 。しかし、盛広の墓は、この主区画から外れた東側の別の区画に、他のいくつかの墓と共に置かれているのである 16 。
この物理的な配置が持つ意味は大きい。藩の権威と歴史を象徴する空間である墓所において、誰の墓をどこに配置するかは、極めて政治的な意味合いを帯びる。盛広の墓が歴代藩主の列から外されているという事実は、彼の死後、松前家の公式な歴史(正史)が「初代・慶広から二代・公広へ」という、幕府に公認された系譜で固定化されていく過程で、「公式な藩主ではなかった」盛広の存在が意図的に周縁化されたことを示す、動かぬ証拠である。文化庁の調査記録においても、盛広の墓石は「後世移されたものであろう」と推測されており 22 、その扱いが特別であったことを物語っている。
彼はあくまで「藩主の父」であり、「藩祖の子」であって、彼自身は正統な支配者の系譜の連鎖から外れた存在として、後世に記憶されることとなった。この墓所の物理的な隔絶は、彼の生涯が持った「過渡的」「非公式」という性質を、死後も永続的に示すための、後世の意図的な采配であった可能性が極めて高い。盛広の墓は、松前藩の歴史がどのように編纂され、記憶されていったかを物語る、静かなる語り部なのである。
結論:継承の架け橋としての松前盛広
松前盛広の三十八年の生涯を振り返る時、城を築き、法を定め、戦に勝利するといった、歴史の教科書に名を刻むような華々しい「功績」を見出すことは難しい。彼は偉大な父の影に隠れ、有能な息子がその跡を継ぐ前に、志半ばで世を去った。彼の人生は、一見すると未完に終わった悲劇として映るかもしれない。
しかし、本報告書で詳述してきたように、彼の真の歴史的価値は、具体的な功績の有無で測られるべきではない。その重要性は、彼の「存在」そのものにあった。松前盛広は、蠣崎氏という一地方領主が、松前藩という幕藩体制下の大名へと脱皮する、最も困難で重要な過渡期を生きた人物である。彼は、絶対的な権力で藩の礎を築いた藩祖・慶広の時代と、その基盤の上に具体的な統治システムを構築した二代藩主・公広の時代とを繋ぐ、不可欠な「結節点」であり、「継承の架け橋」であった。
若き日には、政治の中心地・京都で当代一流の文化を身につけることで、辺境の武家と見られがちであった一族のイメージ向上に貢献した。壮年期には、「内々の家督相続」という形で内政を担い、父・慶広が徳川幕府との困難な外交交渉に専念できる環境を整え、間接的に藩の成立を支えた。そして彼の早すぎる死は、皮肉にも祖父から孫への強固で揺るぎない権力継承を促し、結果として藩の基盤固めへと繋がった。
松前盛広は、自らが栄光のゴールテープを切ることはなかった。しかし彼は、次代の走者である息子・公広へと、藩の未来というバトンを確実に渡すという、最も重要な歴史的役割を果たしたのである。歴史の表舞台に長く立つことはなく、その墓所が示すように公式の系譜からさえも外された存在ではあるが、北の王国・松前藩が二百数十年にわたって存続するための礎の一つを築いた人物として、彼は静かなる功労者として再評価されるべきである。
引用文献
- 松前盛広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E7%9B%9B%E5%BA%83
- 松前盛広(まつまえ もりひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E7%9B%9B%E5%BA%83-1111205
- 松前慶廣とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E6%85%B6%E5%BB%A3
- 松前藩(まつまえはん)[北海道] /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/matsumae/
- 松前慶広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E6%85%B6%E5%BA%83
- 松前由広の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/matumae/b-matumae-yosi.html
- 松前由広とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E7%94%B1%E5%BA%83
- 松前公廣とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%BB%A3
- 【歴史の話をしよう】「関ヶ原の戦い・大名一覧」松前慶広 http://naraku.or-hell.com/Entry/1608/
- 第三編第四章第四節 | - 福島町 https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/kyouiku/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%94%BA%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%94%BA%E5%8F%B2%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%B7%BB%E9%80%9A%E8%AA%AC%E7%B7%A8%E4%B8%8A/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%B7%A8%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AF%80/
- 蠣崎氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F
- 『べらぼう』石高なし?異例ずくめの松前藩の実態、12歳で藩主になった8代・松前道廣はどんな人物だったのか 蔦重とゆかりの人々(21) | JBpress (ジェイビープレス) https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/88780
- 北海道ゆかりの人たち 松前 慶広 - note https://note.com/hokkaido_view/n/ndacc841549b3
- 4.和人とのかかわり https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/pamphlet/tabi/pdf/03-04-wajin_kakawari-p136-143.pdf
- 1599年 家康が権力を強化 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1599/
- 松前家墓所訪問記 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/siseki/html/matumaekebosho.htm
- ② 松前藩の交易支配と 「場所」 https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/pamphlet/tabi/ctll1r00000045zc-att/ctll1r000000cz1r.pdf
- 松前藩の誕生!アイヌを支配する体制の確立とロシアとのにらみあい - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/2260/
- [ID:6915] 徳川家康黒印状 : 資料情報 | 収蔵資料検索システム | 北海道博物館 https://jmapps.ne.jp/hmcollection1/det.html?data_id=6915
- 松前公広(まつまえ きんひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%BA%83-1111190
- 松前 慶広まつまえ よしひろ - 北海道ビューポイント https://hokkaido-viewpoint.com/peuple/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E3%80%80%E6%85%B6%E5%BA%83%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%88%E3%80%80%E3%82%88%E3%81%97%E3%81%B2%E3%82%8D/
- 地域から見る 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/region/1/1331
- 松前藩主松前家墓所 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/189982
- 松前藩主松前家墓所 | 函館・道南の観光スポット - 遊ぶべ!道南探検隊 https://donan.org/kankou/matumaebosyo.html