森山季定
森山季定は陸奥の戦国武将。安東氏の家臣で森山館主。天文15年(1546年)に主君に反乱を起こし、蠣崎季広の活躍により落城、滅亡した。
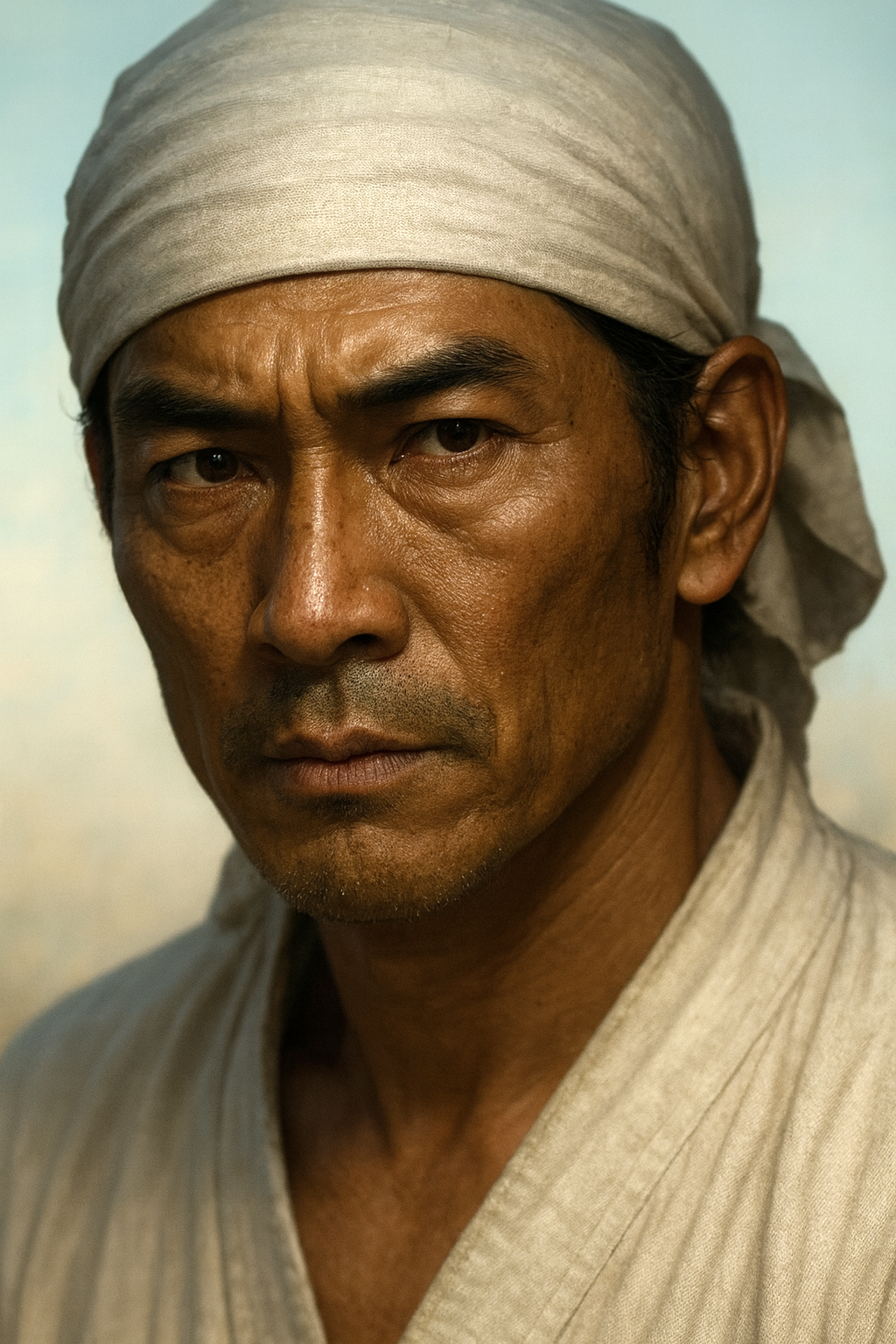
陸奥の戦国武将・森山季定の実像 —『新羅之記録』の逸話と北奥羽の動乱—
序論:陸奥の海に生きた武将、森山季定
戦国時代の陸奥国、日本海沿岸の歴史の片隅に、森山季定という一人の武将の名が刻まれている。彼の生涯に関する情報は断片的であり、活躍した期間は天文15年(1546年)の出来事にほぼ集約されている 1 。これは、一般に想定されがちな「1507年から1600年頃まで活躍した」という広範な期間とは異なり、彼の歴史上の役割が特定の重要な事件に凝縮されていたことを示唆している。
また、彼を「水軍衆の頭領」と捉える見方は、その本質を的確に捉えつつも、正確な位置づけには補足が必要である。季定が仕えた檜山安東氏は、日本海交易を掌握し「安東水軍」とも称されるほどの海上勢力であった 3 。その海上交通の要衝である森山館を本拠とした季定は 5 、安東氏の水軍力の一翼を担う重要な指揮官であったと推察される。しかし、瀬戸内海の村上海賊のように独立した勢力ではなく、あくまで陸奥の戦国大名である安東氏の家臣という立場であった 1 。
本報告書は、この森山季定という人物の実像に迫ることを目的とする。彼の生涯は、単なる一地方武将の物語に留まらない。それは、16世紀半ばの北奥羽における勢力均衡の変動、すなわち主家・安東氏が抱える内部の脆弱性と、周辺勢力との緊張関係を映し出す鏡である。本報告書では、以下の問いを軸に論を進める。
第一に、森山季定はなぜ主君に反旗を翻したのか。第二に、彼の反乱と滅亡を唯一詳細に記す史料『新羅之記録』の記述は、どこまで信頼できるのか。そして第三に、一武将の滅亡が、北奥羽の政治情勢、特に安東氏と、その被官でありながら台頭しつつあった蠣崎氏との関係に、いかなる影響を及ぼしたのか。これらの問いを解き明かすことで、歴史の波間に消えた一武将の生涯を再評価し、彼が生きた時代の力学を明らかにする。
第一章:森山季定の時代背景 —動乱の北奥羽—
森山季定という人物を理解するためには、彼が生きた16世紀半ばの北奥羽(陸奥国・出羽国)が、複雑な政治情勢下にあったことを把握する必要がある。彼の主家である安東氏の内部事情、宿敵・南部氏との対立、そして被官であった蠣崎氏の台頭という三つの要素が絡み合い、季定の行動を規定する力学を形成していた。
第一節:北奥羽の覇者・安東氏の動向
森山季定が仕えた安東氏は、単一で安定した勢力ではなかった。内部に分裂と抗争の火種を抱えながらも、日本海交易によって強大な経済力を維持するという二面性を持っていた。
安東氏は古くから、出羽国檜山(現在の秋田県能代市)を本拠とする「檜山安東氏」と、土崎湊(現在の秋田市)を拠点とする「湊安東氏」に分裂し、長きにわたり対立と和解を繰り返してきた 6 。森山季定が家臣として属していたのは、このうち檜山安東氏(下国安東氏とも呼ばれる)である 1 。この根深い内部対立は、家臣団にも派閥争いを生じさせ、忠誠心のあり方を複雑にしていた可能性が高い。季定が後に起こす謀反も、こうした内部の不安定さという土壌と無関係ではなかったと考えられる。
一方で安東氏は、鎌倉時代より蝦夷管領として北方交易に深く関与し 4 、津軽の十三湊などを拠点として莫大な富を築き上げていた 9 。この経済力こそが、彼らが「日之本将軍」を称するほどの勢力を北奥羽に維持する基盤であった 4 。森山季定が守る森山館は、まさにこの日本海交易ルート上に位置する重要な拠点であり、彼の地位の重要性を示唆している 5 。
第二節:安東氏と周辺勢力—南部氏・蠣崎氏との関係
安東氏を取り巻く外部環境もまた、緊張に満ちていた。特に、東の南部氏との敵対関係と、北の蠣崎氏との主従関係の変質は、森山季定の乱を理解する上で欠かせない要素である。
安東氏と南部氏は、津軽地方の支配権を巡って長年にわたり激しい抗争を繰り広げていた 9 。安東氏にとって、日本海側の拠点を固め、南部氏の西進を阻止することは、勢力維持のための至上命題であった。季定の森山館は、まさに対南部氏防衛線の西端を担う要衝であり、その軍事的価値は極めて高かった 5 。
一方、蝦夷地(現在の北海道南部)の和人勢力を束ねる蠣崎氏は、形式的には安東氏の被官、すなわち家臣であった。しかし、その実態は半ば独立した領主であり、徐々に安東氏の支配からの完全な自立を強めていた 13 。主家である安東氏の内部抗争(湊騒動など)は、蠣崎氏の自立を促す格好の機会となった 16 。天文15年(1546年)の森山季定の乱に、被官であるはずの蠣崎季広が援軍の大将として参陣したという事実は、この両者の微妙で複雑な主従関係を象徴する出来事であった。
これらの状況を総合すると、森山季定の「謀反」は、孤立した突発的な事件とは考え難い。それは、安東氏が抱える内部の脆弱性と、南部氏からの外部圧力が交差する地点で発生した、ある種の必然的な帰結であった可能性が浮かび上がる。安東氏の支配体制に綻びが生じれば、季定のような重要拠点の指揮官が、敵対勢力への内通や自立といった、自らの生き残りを賭けた政治的行動に出る動機は十分に考えられる。
さらに、蠣崎氏の視点に立てば、この主家の内乱は、単なる主君への奉公の機会に留まらなかった。むしろ、鎮圧軍の主力として活躍することで自らの軍事力を内外に誇示し、安東氏に対する政治的地位を向上させる戦略的な好機であった。季定の反乱鎮圧に貢献することで、蠣崎氏は安東氏に対して大きな「貸し」を作り、その後の自立への道をさらに確かなものにしたのである。結果として、森山季定の滅亡は、蠣崎氏台頭の踏み台となった側面は否定できない。
表1:天文十五年(1546年)森山季定の乱 主要関係者一覧
|
人物名 |
所属・役職 |
森山季定との関係 |
乱における役割・動機(推定) |
|
森山 季定 |
檜山安東氏家臣、陸奥国森山館主、飛騨守 |
本人 |
謀反の首謀者。動機は不明だが、安東氏内部の対立や南部氏との連携などが考えられる。 |
|
安東 尋季 |
檜山安東氏当主 |
主君 |
討伐軍の総大将。家中の反乱を鎮圧し、支配体制を維持することが目的。 |
|
安東 舜季 |
尋季の子(後の当主) |
主君の子 |
討伐軍の主将の一人。父と共に反乱鎮圧にあたる。 |
|
蠣崎 季広 |
安東氏被官、蝦夷地(渡島半島)の領主 |
主家の同僚(形式上) |
討伐軍の搦手大将。主家への忠誠を示すと同時に、自らの武功と政治的地位を高める好機と捉えていた可能性。 |
|
南部 晴政 |
南部氏当主 |
敵対勢力の長 |
直接の関与は不明だが、安東氏の内乱は勢力拡大の好機であり、季定の謀反を裏で画策していた可能性も否定できない。 |
第二章:森山季定と森山館
物語の主役である森山季定という人物と、彼の本拠地であった森山館に焦点を当てる。限られた史料から彼の人物像を推測し、拠点の地理的・戦略的な価値を分析することで、彼が安東氏の支配体制の中で果たしていた役割の重要性を浮き彫りにする。
第一節:人物像の考察—安東氏家臣としての季定
森山季定に関する直接的な記録は乏しいが、その呼称や役職から、安東家臣団における彼の地位をある程度推し量ることができる。
季定は「森山飛騨守季定」と称されている 1 。戦国時代において官位はしばしば自称されるものであったが、有力な武将がその家格や勢威を示すために用いるのが通例であった。このことから、季定が単なる一兵卒ではなく、安東家臣団の中でも一定の格式を持つ重要な人物であったことが窺える。
彼が「水軍衆の頭領」であったという評価も、この文脈で再検証できる。前述の通り、彼は独立した海賊大名ではなかったが、その居城・森山館が日本海に面した天然の要害であったことを踏まえると、彼の役割は極めて海事的なものであったと推測される 5 。安東氏の権力基盤が日本海交易にあった以上、その交易路を扼する森山館の主である季定は、安東氏の命を受けて、交易船の保護、敵対勢力(南部氏方の水軍など)の海上活動の妨害、さらには兵員の海上輸送といった任務を統括する、地域艦隊の司令官に等しい役割を担っていたと考えるのが最も妥当であろう。
第二節:拠点・森山館の地理的・戦略的重要性
森山季定の謀反が安東氏にとって重大な脅威と見なされた背景には、彼が掌握していた森山館という拠点の、他に代えがたい戦略的価値があった。
森山館は、現在の青森県西津軽郡深浦町森山に位置し、日本海に突き出した丘陵の先端に築かれた山城であった 2 。海側は断崖絶壁、陸側も急峻な地形で守りを固めた、まさに天然の要害であったと伝わる 5 。現在も堀切などの遺構が確認されており、その堅固さが偲ばれる 18 。
この城の価値は、その防御力だけではない。立地そのものが戦略的に重要であった。森山館は、安東氏の本拠地である出羽国檜山(能代)方面と、抗争の最前線である津軽地方とを結ぶ沿岸交通路「大間越街道」を直接的に支配できる位置にあった 5 。つまり、陸路と海路の両方を監視し、掌握できる交通の結節点だったのである。
この拠点が敵対勢力の手に渡る、あるいは独立勢力化することは、安東氏にとって致命的な事態を意味した。第一に、経済の生命線である日本海交易ルートが寸断される危険性がある。第二に、津軽方面への軍事的な連絡線が絶たれ、対南部氏戦線が崩壊しかねない。そして第三に、北の被官・蠣崎氏との連携が分断される恐れもあった。したがって、安東尋季・舜季父子が謀反の報に接するや即座に大軍を派遣し、さらには蠣崎季広にまで援軍を要請するという迅速かつ大規模な対応をとったのは、この戦略的脅威を何としても排除するためであった。森山季定の乱は、単なる家臣の反乱ではなく、安東氏の支配体制そのものを根幹から揺るがす「国家的危機」として認識されたのである。
なお、調査の過程で、青森県三戸郡階上町 19 や秋田県山本郡三種町 21 にも同名の「森山館」が存在することが確認されたが、これらは森山季定が拠った城とは異なる。本報告書で扱うのは、深浦町の森山館(後に「茶右衛門館」とも呼ばれる)である 2 。
第三章:天文十五年の謀反と落城
本章では、森山季定の運命を決定づけた天文15年(1546年)の謀反とその結末を、現存する唯一の詳細な記録である『新羅之記録』の記述に沿って再現する。同時に、この史料が持つバイアスを批判的に検討し、劇的な逸話の裏に隠された歴史の真実に迫る。
第一節:謀反に至る背景の分析
史料は、森山季定がなぜ主君に背いたのか、その動機を明確には語らない。『新羅之記録』をはじめとする諸資料は、彼が「謀反を起こした」という事実を記すのみである 5 。しかし、第一章で詳述した時代背景から、その動機についていくつかの学術的な推論を立てることは可能である。
第一に、「安東氏内部の派閥抗争説」が考えられる。当時くすぶっていた檜山安東氏と湊安東氏の対立構造の中で、季定が何らかの形で敵対派閥と見なされ、粛清の対象となった可能性である。追い詰められた季定が、やむなく兵を挙げたという筋書きである。
第二に、「南部氏への内通説」である。宿敵である南部氏の調略に応じ、安東氏を裏切って寝返りを図ったという可能性も十分に考えられる。季定が守る森山館の戦略的重要性を鑑みれば、南部氏が彼に破格の条件を提示して内応を誘う価値は極めて高い。
第三に、「個人的な野心・待遇への不満説」も挙げられる。自らが守る拠点の重要性や自身の功績に見合った待遇を主家から得られないことへの不満が募り、これを機に自立を画策したという可能性である。
いずれの説が真実であったにせよ、彼の行動が、当時の北奥羽の複雑な政治力学の中で下された、極めて危険な賭けであったことは間違いない。
第二節:『新羅之記録』に見る落城の顛末
松前藩の公式史書である『新羅之記録』は、森山館の落城を劇的に描いている 1 。
天文15年(1546年)春、森山季定謀反の報は、主君である檜山城の安東尋季・舜季父子のもとに届いた。父子は直ちに討伐軍を編成して出陣する一方、蝦夷地の被官である蠣崎季広にも飛脚を送り、搦手(からめて、城の裏手)の大将として参陣するよう要請した 1 。
要請を受けた季広は、速やかに兵を整え、海路で津軽半島の小泊に上陸。3月5日には森山に到着し、城の包囲網に加わった 1 。籠城戦はしばらく続いたが、3月15日、戦況を動かす出来事が起こる。城内から水桶を担いで出入りする者を見た蠣崎季広は、城の麓から遥かにその人物を狙って弓を放った。矢は見事に命中し、その者の背中を射抜き、胸板を貫通したという 1 。
この一射の後、森山館の士気は崩壊し、城はほどなくして落城した。そして、捕らえられた城兵の口から、驚くべき事実が明らかになる。実は城内では水が完全に枯渇しており、敵にそれを悟られまいと、水を汲みに行く「振り」をしていたというのである。季広の一矢は、その決死の偽装工作を打ち破り、籠城側の最後の望みを絶った。これにより、万策尽きた森山季定は自害して果てたと、『新羅之記録』は伝えている 1 。
第三節:一矢が招いた落城—逸話の歴史的信憑性と意義
この劇的な落城の逸話は、歴史的事実としてどこまで受け入れるべきだろうか。ここで史料批判の視点が重要となる。『新羅之記録』は、客観的な記録ではなく、蠣崎氏の後身である松前藩の正史として、藩祖・蠣崎季広の功績を称揚し、その支配の正当性を後世に伝えるという明確な政治的意図をもって編纂された書物である 23 。
この点を踏まえて逸話を再検討すると、強い作為の存在が浮かび上がる。蠣崎季広の神がかった弓の腕前と、敵の計略を見抜く洞察力によって、難攻不落の城が落ちたという物語は、英雄譚としてあまりにも完成されすぎている。籠城戦において水の手の確保が死活問題であることは常識であり、水不足が落城の直接的な原因であった可能性は高い。しかし、その発覚の経緯が、主君である安東氏の軍功ではなく、被官である蠣崎季広ただ一人の手柄として描かれている点に、この史料の性格が最もよく表れている。
この逸話は、実際に起きた出来事をありのままに伝えているというよりは、「松前藩の始祖である蠣崎季広は、これほど武勇と知略に優れた英雄であった」という強力なメッセージを発信するための、政治的な物語(ナラティブ)として解釈するのが妥当である。この物語の中で、森山季定の死は、蠣崎氏の英雄性を際立たせるための、いわば「舞台装置」として利用された側面が強い。我々はこの記述を通して、「実際に何が起こったか」と同時に、「松前藩が自らの歴史を後世にどう記憶されたかったか」という、二つの層を読み解く必要がある。
結論:森山季定が歴史に遺したもの
森山季定の生涯は、主家への反逆と、それに続く悲劇的な滅亡という形で幕を閉じた。彼は安東氏の重要な拠点を任された有力な武将でありながら、戦国という時代の荒波の中で、主家への忠誠と自家の存続という二律背反の狭間で苦しい選択を迫られ、結果として敗者となった。
しかし、彼の行動が北奥羽の歴史に与えた影響は決して小さくはなかった。主家である安東氏にとっては、有力家臣の反乱を自らの力だけで完全に鎮圧できず、被官である蠣崎氏の力を借りなければならなかったという事実は、その権威に少なからず陰りを落としたであろう。一方で蠣崎氏にとっては、この鎮圧への貢献は、安東家中での発言力を飛躍的に高め、その後の完全な自立に向けた大きな布石となった。森山季定は、図らずも蠣崎氏台頭の触媒としての役割を果たしたのである。
季定の死後、彼が拠った森山館もまた、奇妙な運命をたどる。時代が下り、この地が津軽氏の領土となると、津軽氏の家臣・小野茶右衛門が城代として入った。これにより、城は「茶右衛門館」とも呼ばれるようになる 2 。しかし、この小野茶右衛門もまた、藩主の家督争いに巻き込まれた、あるいは海賊行為を理由とされたなど諸説あるが、最終的には主家によって誅伐され、森山館は廃城となった 5 。二代にわたる城主が、いずれも主家との対立の末に非業の死を遂げたこの城は、北奥羽の戦国末期から近世初期にかけての過酷な時代の記憶を留める、悲劇の舞台として歴史に名を刻んでいる。
最終的に、森山季定の物語は、戦国時代の歴史叙述がしばしば勝者の視点から描かれるという、厳然たる事実を我々に突きつける。彼の謀反の動機や人間性の詳細は、彼を討伐した側の、それも自らの正当性を主張する必要があった蠣崎氏(松前氏)の記録の中にしか残されていない。彼の生涯は、中央の有名大名たちの華々しい活躍の陰で、巨大な勢力の狭間に翻弄されながらも熾烈な生存競争を繰り広げた、無数の地方武将たちの運命を象徴していると言えるだろう。
引用文献
- 森山季定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E5%AD%A3%E5%AE%9A
- 陸奥 森山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/fukaura-moriyama-jyo/
- 安東水軍(尾崎酒造)|グルメ・お土産 - 青森県観光情報サイト Amazing AOMORI https://aomori-tourism.com/gourmet/detail_4825.html
- 三春物語207番 「三春五万石日ノ本将軍安倍ノ称安東秋田氏」 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?e=56
- 深浦町 森山城の歴史と史跡をご紹介! - KABUOのぶらり旅日記 https://www.yamagatakabuo.online/entry/Moriyama_Castle
- 安東氏(あんどううじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F-29435
- ”日ノ本将軍”と謳われた安東氏が築いた「檜山城」【秋田県能代市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22439
- 戦国時代に秋田を支配し能代を本拠地とした檜山安東氏【秋田県】 https://jp.neft.asia/archives/39005
- 十三湊を制して栄えた安藤氏と室町期に台頭した南部氏の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20726/?pg=2
- 「北のまほろば」と「安東氏」という謎|中村隆一郎 - note https://note.com/modern_snail5349/n/nf158ece5f14f
- 僕のルーツ・中世への旅No13 - 無明舎出版 http://www.mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval09.html
- 安藤氏の通説と議論 下国安東氏ノート~安東氏500年の歴史 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page11
- 安東氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%B0%8F
- 小稿では、いよいよ豊臣・徳川政権と向き合わなくてはならなくなる、 天正十八年以降の夷島での蠣崎氏による地域大名権力の形成について考 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1518/files/HirodaiKokushi_135_1.pdf
- 蠣崎氏(かきざきうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F-824363
- 武家家伝_蠣崎(松前)氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/matuma_k.html
- 森山城 もりやまじょう - 奥羽古城散策 https://www.ne.jp/asahi/saso/sai/castle/aomori/moriyamajo/moriyamajo.html
- 森山館 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/aomori/moriyama/moriyama.html
- 森の交流館 - 階上町 Offical Web Site https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/10,0,58,html
- 山館前公園 - 階上町 Offical Web Site https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/10,16609,98,html
- ホテル森山館 - 三種町観光協会 https://mitanekanko.com/enjoy/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E9%A4%A8/
- 上巻・〔四代蠣崎季広〕 | khirin C https://khirin-ld.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E9472
- 新羅之記録 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/184140
- 森山館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%B1%B1%E9%A4%A8
- 新羅之記録 上 - 函館市中央図書館デジタル資料館 https://archives.c.fun.ac.jp/documents/1810651800/0010