海部友光
海部友光は阿波の国人領主。長宗我部元親の弟を討ち、阿波侵攻の口実を与え海部城は落城。友光は消息不明だが、城はその後も重要拠点として利用された。
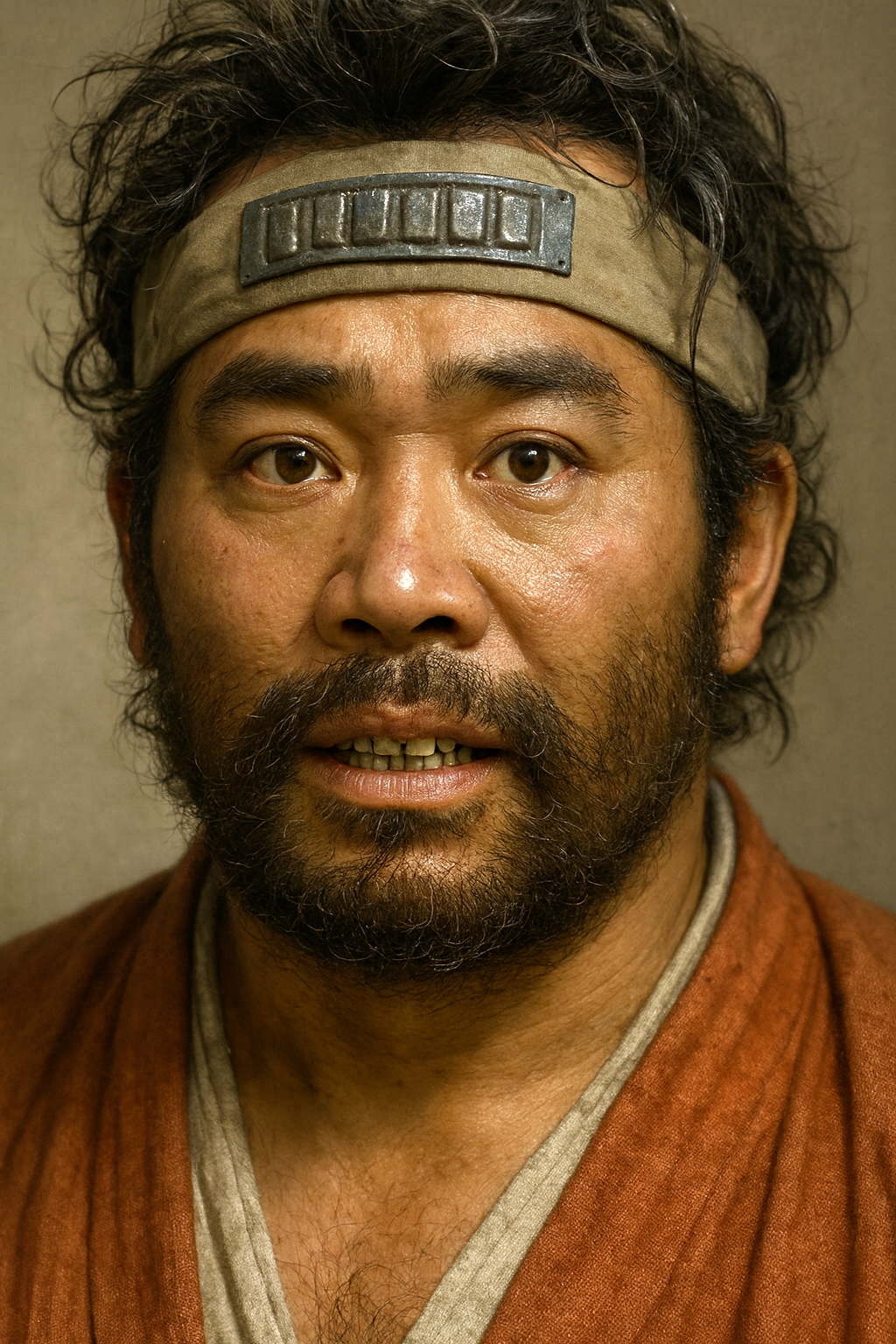
戦国史の奔流に消えた阿波の国人、海部友光 ― その生涯と時代の徹底考察
序論:歴史の奔流に消えた阿波の国人、海部友光
本報告書は、戦国時代の阿波国(現在の徳島県)にその名を刻んだ国人領主、海部友光(かいふ ともみつ)の生涯を、現存する史料と伝承に基づき、多角的かつ詳細に解明することを目的とする。一般に「長宗我部元親の弟を誤って討ち、その報復によって没落した悲劇の武将」という一面的な評価で語られがちな友光の人物像を、より深く、時代の文脈の中に正確に位置づけることを試みる。
彼の行動は、単なる「誤認」や個人的な「不運」に帰結するものであったのだろうか。本報告では、友光の決断の背景にあった三好氏の衰退と長宗我部氏の台頭という、四国史の大きな転換点を分析する。これにより、彼が一地方領主として直面した過酷な現実と、その中での選択の重みを浮き彫りにする。海部友光の生涯は、戦国乱世の統一過程で淘汰されていった数多の国人領主たちの運命を象徴する事例として、深く考察する価値を持つものである。
(参考資料) 海部友光と周辺情勢年表
報告書本編で詳述する出来事、特に複数の説が存在する事件の年代を時系列で整理し、読者の理解を助けるための参照資料として以下に示す。三好氏、長宗我部氏、そして海部氏の動向を一覧化することで、各勢力の相関関係と時代の大きな流れを直感的に把握することが可能となる。これは、特に海部城落城の時期に関する複雑な議論を理解する上での重要な土台となる。
|
年代(西暦) |
元号 |
主要な出来事 |
関連史料・根拠 |
|
1564年頃 |
永禄7年 |
三好長慶が死去。三好氏の畿内における権勢に陰りが見え始める。 |
1 |
|
1569年 |
永禄12年 |
長宗我部元親が安芸国虎を滅ぼし、土佐東部を平定。阿波への脅威が増す。 |
3 |
|
1570年頃 |
元亀元年 |
海部友光、長宗我部氏の脅威に備え、海部城を築城または大改修したとされる。 |
4 |
|
1571年 |
元亀2年 |
**島弥九郎事件発生。**海部友光が那佐湾に停泊中の島弥九郎親益を討つ。 |
5 |
|
1575年 |
天正3年 |
長宗我部元親、四万十川の戦いで一条兼定を破り、土佐をほぼ統一。 |
7 |
|
|
|
**海部城落城(天正3年説)。**元親が阿波南部沿岸へ侵攻。 |
9 |
|
1576年 |
天正4年 |
阿波守護・細川真之が三好長治に反旗を翻し、元親に援軍を要請。阿波国内の混乱が激化。 |
10 |
|
1577年 |
天正5年 |
**海部城落城(天正5年説/再攻撃説)。**元親が阿波への影響力をさらに強める。 |
11 |
|
1582年 |
天正10年 |
中富川の戦い。元親が三好(十河)軍に決定的勝利を収め、阿波の支配権を確立。 |
1 |
|
1585年 |
天正13年 |
豊臣秀吉による四国征伐。長宗我部氏が降伏。蜂須賀家政が阿波に入国し、海部城は阿波九城の一つとなる。 |
3 |
|
1638年 |
寛永15年 |
一国一城令により海部城が廃城となる。 |
4 |
第一章:阿波海部氏の出自と戦国期の動向
古代からの系譜
阿波国海部郡を拠点とした海部氏の起源は、複数の説が伝えられている。一説には古代豪族である宍昨別(しさくわけ)の子孫、また一説には藤原氏の子孫ともいわれ、代々海部郡司を継承してきた家柄とされる 16 。その氏名が示す通り、海部氏のルーツは古代の海洋民と深く関わっていた可能性が高い。「海部(あまべ)」とは、漁撈や航海、製塩などに従事した部民のことであり、彼らを統率したのが海部直(あまのあたい)などの伴造であった。
実際に、阿波国那賀郡(後の海部郡を含む)には、古代において海人集団を統率した阿曇氏が存在したことが、平城京二条大路から出土した天平七年(735年)の年紀を持つ木簡によって確認されている 17 。また、丹波国においても、彦火明命を祖神とする海部氏が古くから存続しており、国宝「海部氏系図」を伝えている 16 。これらの事実から、阿波の海部氏もまた、単なる土着の武士ではなく、古くから海運を掌握し、海洋に関わる専門技術集団としての側面を持っていた一族であったと推察される。彼らの歴史は、古代の海人族の統率から、戦国期の水運・港湾利権の掌握、そして海からの脅威への対応へと、一貫して「海」と密接に関わっていたのである。
室町・戦国期の海部氏
室町時代に入ると、海部氏は阿波守護であった細川氏に仕える国人領主としてその地位を確立した 16 。その後、戦国期に細川氏に代わって阿波の実権を握った三好氏とも婚姻関係を結び、その支配体制に組み込まれていった 16 。この時代の海部氏の本拠地は、当初、海部川上流の内陸部に位置する吉野城であった 4 。
しかし、戦国時代末期、土佐国で長宗我部元親が勢力を拡大し始めると、海部氏の戦略は大きな転換点を迎える。彼らは本拠地を内陸の吉野城から、海部川河口の要衝であり、港湾都市でもあった鞆浦(ともうら)へと移し、新たに海部城を築いた 4 。この拠点移動は、単なる居城の変更ではない。それは、長宗我部氏による海洋からの侵攻という新たな脅威を明確に認識し、沿岸防衛と水運の掌握こそが自らの存亡を左右するという、地政学的判断に基づいた戦略的決断であった。この海部城の主こそが、官途名を「左近将監」と称した海部友光だったのである 3 。
第二章:天正期阿波国の政治情勢 ― 巨大勢力の狭間で
衰退する旧主・三好氏
海部友光が歴史の表舞台に登場した天正年間(1573年-1592年)、彼が主家として仕えていた三好氏は、かつての栄光を失い、急速に衰退の一途をたどっていた。三好氏は、三好長慶の時代に畿内一円を支配下に置き、室町幕府を凌ぐ権勢を誇ったが、その長慶が永禄7年(1564年)に死去すると、権力基盤は大きく揺らぎ始めた 1 。
本国である阿波においても、三好氏の統制力は著しく低下していた。長慶の死後、家督を継いだ三好長治と、彼が名目上の守護として擁立していた細川真之(三好実休の妻と細川持隆の間に生まれた子で、長治の異父兄にあたる)との間に対立が生じ、阿波国内は事実上の内乱状態に陥っていた 10 。この内部抗争は、三好氏が国人領主たちをまとめ上げる力を失っていることを如実に示しており、国境地帯の防衛体制に深刻な綻びを生じさせていた。
伸長する新興勢力・長宗我部氏
三好氏が内憂に苦しむ一方、隣国・土佐では長宗我部元親が飛躍的な勢力拡大を遂げていた。天正3年(1575年)の四万十川の戦いで土佐一条氏を破り、悲願の土佐統一を成し遂げた元親は、その矛先を四国全土の制覇へと向け、次なる標的として阿波国を定めていた 7 。
元親の阿波侵攻は、単なる軍事行動にとどまらなかった。彼は巧みな外交戦略を展開し、三好氏の支配に不満を持つ阿波国内の国人領主たちと連携を深めていた。特に、一宮城主の一宮成助などは、細川真之の反乱に呼応する形で元親に援軍を要請しており、長宗我部氏は阿波の内部から三好体制を切り崩す足がかりを築きつつあった 10 。
海部氏の地政学的立場
この衰退する旧主・三好氏と、伸長する新興勢力・長宗我部氏という二大勢力が激突する、まさにその最前線に、海部友光と彼の海部城は位置していた。海部城は土佐との国境に最も近い阿波南部の玄関口であり、長宗我部氏が侵攻する際には、真っ先にその攻撃に晒される運命にあった 3 。
友光が置かれた状況は、極めて過酷であった。彼の悲劇は、個人的な資質の問題というよりも、三好氏の統制力低下によって生じた「権力の真空」と、長宗我部氏の膨張がもたらす「地政学的圧力」という、二つの抗いがたい要因が重なった必然の結果であったと言える。弱体化したとはいえ旧主である三好氏への忠誠を維持すれば、長宗我部氏の猛攻を単独で受け止めなければならない。一方で、勢いを増す長宗我部氏に与すれば、三好方から裏切り者として討伐される危険を冒すことになる。友光は、いずれの道を選んでも破滅が待ち受ける、選択の余地のない板挟み状態に追い込まれていた。彼の行動は、この構造的な圧力に対する、一地方領主の必死の反応として理解する必要がある。
第三章:運命の岐路 ― 島弥九郎事件の真相
第一節:事件の勃発と経緯(元亀2年/1571年)
元亀2年(1571年)、海部友光の運命を決定づける事件が発生する。長宗我部元親の末弟であり、武勇に優れた武将として知られていた島弥九郎親益(しま やくろう ちかます、諱は親房とも)が、病の療養のため、海路で摂津国の有馬温泉へ向かっていた 6 。その途上、彼の乗る船団は紀伊水道で嵐に遭遇し、風雨を避けるために海部城下の那佐湾(現在の徳島県海陽町那佐)に停泊した 4 。
この知らせは、直ちに海部城の友光のもとへ届けられた。友光はこれを長宗我部氏による侵攻の兆候と判断し、手勢を率いて那佐湾に停泊中の弥九郎の船を襲撃、弥九郎とその家臣団をことごとく討ち取ったのである 4 。この「島弥九郎事件」は、長宗我部元親による本格的な阿波侵攻の直接的な引き金となった。
第二節:友光の決断とその背景 ― 「誤認」説の再検討
この友光の決断は、長年にわたり「敵襲との誤認」であったと説明されてきた 21 。当時、土佐を平定しつつあった元親の脅威は阿波南部の国人領主にとって現実のものであり、国境の港に長宗我部氏の船団が現れれば、それを偵察部隊や先遣隊と見なすのは、当時の緊張状態を考えれば不自然なことではなかった。
しかし、この決断の背景には、単なる誤認では片付けられない、より複雑な政治的計算が存在した可能性を考慮すべきである。第二章で述べたように、友光は旧主・三好氏と新興勢力・長宗我部氏の板挟みという絶望的な状況にあった。この状況下で、あえて長宗我部方の重要人物である弥九郎を討ち取るという行動は、弱体化する三好氏に対して自らの忠誠を明確に示し、支援を引き出すための「示威行動」であった可能性が考えられる。あるいは、周辺の国人たちから長宗我部方への内通を疑われないようにするための、苦渋に満ちた政治的決断だったのかもしれない。彼の行動は、無能な誤断ではなく、限られた選択肢の中で自らの勢力を維持しようとした、計算された賭けであったとも解釈できるのである。
第三節:事件の異説と歴史的評価 ― 「挑発」説の検証
この事件には、もう一つの側面が存在する。それは、長宗我部元親が、病弱な弟・弥九郎を意図的に危険な海域へ送り込み、阿波侵攻の口実を自ら作り出したとする「挑発説」である 22 。この説によれば、弥九郎の死は元親の計算のうちであり、友光はその策略にはまったに過ぎないということになる。
この説の信憑性を補強するのが、長宗我部側の史書である『土佐物語』などに描かれる弥九郎のあまりにも英雄的な最期である。「我、弓馬の家に生まれ、病床にて死するは無念なり。戦場にて命を落とすは本懐なり」と叫び、壮絶な討死を遂げたとされるこの逸話は 21 、元親の弔い合戦を正当化し、その大義名分を内外に知らしめるための、後世の創作、あるいはプロパガンダとしての性格が強いと考えられる。
結局のところ、事件の真相が友光の「政治的決断」であったのか、元親の「戦略的挑発」であったのかを断定する史料は存在しない。しかし、この一件が、単純な軍事衝突ではなく、情報戦とプロパガンダが複雑に絡み合った政治事件であったことは確かである。そして、その結果として長宗我部元親に「弟の仇を討つ」という、誰もが納得する絶好の侵攻理由を与えてしまったことこそが、歴史的な事実なのである 22 。
第四章:海部城の攻防と落城
第一節:落城時期に関する諸説の検討
島弥九郎事件によって、長宗我部元親の怒りを買った海部友光と海部城の運命は、風前の灯火となった。しかし、その落城時期については、史料によって記述が異なり、複数の説が存在する。天正3年(1575年)とする説 4 と、天正5年(1577年)とする説 11 がその代表的なものである。
この年代のズレは、単なる記録の誤りとして片付けるべきではない。むしろ、それは長宗我部元親の阿波侵攻が、一度の決戦によって雌雄を決したのではなく、数年にわたる段階的なプロセスであったことを示唆している。歴史は「点」ではなく「線」で捉える必要があり、この日付の矛盾こそが、その侵攻作戦の実態を解き明かす鍵となる。
天正3年説は、元親が四万十川の戦いで土佐をほぼ統一した直後、その勢いを駆って阿波南部沿岸へ最初の侵攻を行い、海部城を一時的に攻略、あるいは従属させた段階を示していると考えられる。その後、天正4年(1576年)に阿波国内で細川真之が三好長治に反旗を翻すなど、反三好勢力との連携が本格化する 10 。そして、天正5年説は、これらの国内情勢の変化を踏まえ、元親が阿波における支配をより確固たるものにするために再度軍事行動を起こし、海部城を最終的に制圧した段階を示すものと解釈できる。海部城の陥落は、一度きりの出来事ではなく、数年がかりの戦略的な「浸透・制圧作戦」の開始を告げる象徴的な出来事であり、その完了を示す画期でもあったのである。
第二節:合戦の実態と異説
海部城の攻防戦の具体的な様子についても、異なる伝承が残されている。一つの有名な伝承によれば、海部方には栗原伊賀右衛門(くりはら いがうえもん)という鉄砲の名手がおり、城壁から次々と長宗我部方の兵を撃ち倒して奮戦した。しかし、長宗我部方の槍の名手として知られた黒岩治左衛門が、巧みに身を隠しながら城に迫り、ついに栗原を討ち取った。これにより海部方の士気は崩壊し、城は落城に至ったという 3 。
一方で、これとは全く異なる説も存在する。それによれば、長宗我部軍が押し寄せた際、海部方の主力部隊は主家である三好氏からの要請に応じ、讃岐方面などへ出兵しており、城内は極めて手薄な状態であった。そのため、大規模な籠城戦が行われることなく、ほとんど抵抗せずに開城した、というものである 4 。
これらの説の真偽を現代において確かめることは困難である。しかし、弥九郎事件から数年の時を経て、長宗我部氏の圧倒的な軍事力の前に友光がその拠点を失ったことは、疑いようのない事実である。
第五章:落城後の友光と海部氏の行方
友光の逃亡とその後
海部城を追われた海部友光のその後の人生は、歴史の闇の中に深く閉ざされている。いくつかの伝承によれば、彼は紀伊国(現在の和歌山県)に縁者を頼って落ち延びたとされている 3 。海部氏が古くから海洋民としての性格を持っていたことを考えれば、海を越えて紀伊半島へ逃れることは十分に可能であっただろう。
しかし、紀伊へ渡った後の友光の具体的な足跡、活動、そして没年に関する確かな記録は一切見つかっていない。彼は歴史の表舞台から完全に姿を消し、その消息は不明のままである。彼の没落は、戦国乱世の統一過程において、時代の変化に対応できずに淘汰されていった数多の地方領主が辿った、典型的な末路の一つであった。
海部城のその後
海部友光という個人の物語は落城と共に「断絶」するが、彼が築いた「海部城」という物理的な拠点は、その戦略的価値ゆえに、支配者を変えながらも歴史の「連続性」を示していく。
友光なき後の海部城は、皮肉にも、彼を滅ぼした長宗我部氏の阿波侵攻における最重要拠点となった。城主には元親の弟である香宗我部親泰が置かれ、ここを足がかりとして阿波全域の平定が進められた 3 。
その後、天正13年(1585年)に豊臣秀吉による四国征伐が行われ、長宗我部氏が降伏すると、阿波国には蜂須賀家政が入国する。蜂須賀氏は、海部城が持つ土佐に対する国境防衛の要衝としての価値を高く評価し、城を改修。「阿波九城」の一つに位置づけ、重臣を城代として配置した 3 。
しかし、江戸幕府による治世が安定し、元和元年(1615年)に一国一城令が発布されると、海部城もその役割を終える時が来た。寛永15年(1638年)、海部城は正式に廃城となり、その歴史に幕を下ろした 4 。友光個人の運命は早々に尽きたが、彼が築いた城は、その地が持つ地政学的な重要性ゆえに、支配体制が三度変わる中で生き続けた。この事実は、個人の運命と、土地が持つ戦略的価値とは時に切り離されて進行するという、歴史の非情な側面を浮き彫りにしている。
結論:海部友光が現代に問いかけるもの
海部友光の生涯は、三好氏から長宗我部氏へ、そして豊臣政権へと至る四国の権力構造が激変する時代において、一人の国人領主がいかにして翻弄され、歴史の奔流の中に消えていったかを示す、鮮烈な事例である。
彼の運命を決定づけた島弥九郎事件における決断は、限られた情報と選択肢の中で下された、一族の生き残りを賭けた必死の選択であったと見るべきである。その結果としての悲劇は、彼を単なる「判断を誤った敗者」として切り捨てるのではなく、時代の巨大なうねりの中で、旧来の秩序と新興勢力の狭間に立たされた数多の地方領主の苦悩を体現する存在として捉え直すことを我々に求める。
海部友光の物語は、大きな時代の転換期において、個人や中小組織がいかに脆弱であるか、そして一つの決断が時にいかに予測不可能な結果を招きうるかという、現代にも通じる普遍的な教訓を示している。彼の生涯の探求は、歴史の勝者の視点からだけでは見えてこない、時代の多層的な真実を理解するためには、敗者の視点から歴史を読み解くことの重要性を教えてくれるのである。
引用文献
- 阿波国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E5%9B%BD
- 【三好氏の台頭】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d100010/ht010180
- 海部城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/shikoku/kaifu.j/kaifu.j.html
- 阿波 海部城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/awa/kaifu-jyo/
- 海部城の見所と写真・100人城主の評価(徳島県海陽町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1622/
- 岛亲益- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B3%B6%E8%A6%AA%E7%9B%8A
- 「四万十川(渡川)の戦い(1575年)」長宗我部の土佐統一戦 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/60
- 長宗我部元親簡史: WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/13178726/
- 島弥九郎の悲劇 - 高知市歴史散歩 https://www.city.kochi.kochi.jp/akarui/rekishi/re9906.htm
- 長宗我部元親の四国進出はどのように展開されていったのか(1575 ... https://sengoku-his.com/39
- 海部城:長宗我部元親の弟島親益を殺害した海部友光の居城 海部城 【お城特集 日本の歴史】 https://www.jp-history.info/castle/5334.html
- 海部友光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%83%A8%E5%8F%8B%E5%85%89
- 中富川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AF%8C%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 海部城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2492
- 海部城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%83%A8%E5%9F%8E
- 海部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%83%A8%E6%B0%8F
- 倭王権と淡路の密接な関係を指摘し https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/wp-content/uploads/2021/03/kiyo02_09.pdf
- 海陽町おすすめみどころマップ - NPOあったかいよう https://attakaiyo.org/midokoro/
- 三好長治の自刃 - 徳島県立図書館 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/37/3719.html
- 中富川の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Nakatomigawa.html
- 阿波海部城番外編 島弥九郎事件 | 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-426.html
- 土佐の長宗我部元親、他國侵攻の契機となった事件 < 島弥九郎事件 / 徳島県海陽町 > https://www.kotobus-express.jp/column/2019/07/post-113.html
- 非業の死から復姓へ!長曾我部家の隆盛と再興、双方のきっかけを作った「島弥九郎事件」とは? https://mag.japaaan.com/archives/166394
- 海部城落城 - スペイン太平洋航路 http://kouro1565.html.xdomain.jp/kaifujourakujou.html
- 室戸紀行⑧ DAY2-3 徳島県海陽町 「海部城(かいふじょう)」はどこだ? - note https://note.com/tadanomorita/n/n30a362195504
- 海部城 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/sikoku/tokusima/kaifu.html