清野長範
清野長範は蘆名家臣の子から上杉景勝の側近となる。会津移封後は伊南城代を務め、米沢藩の奉行として藩政を主導。上杉家の危機を支えた能吏。
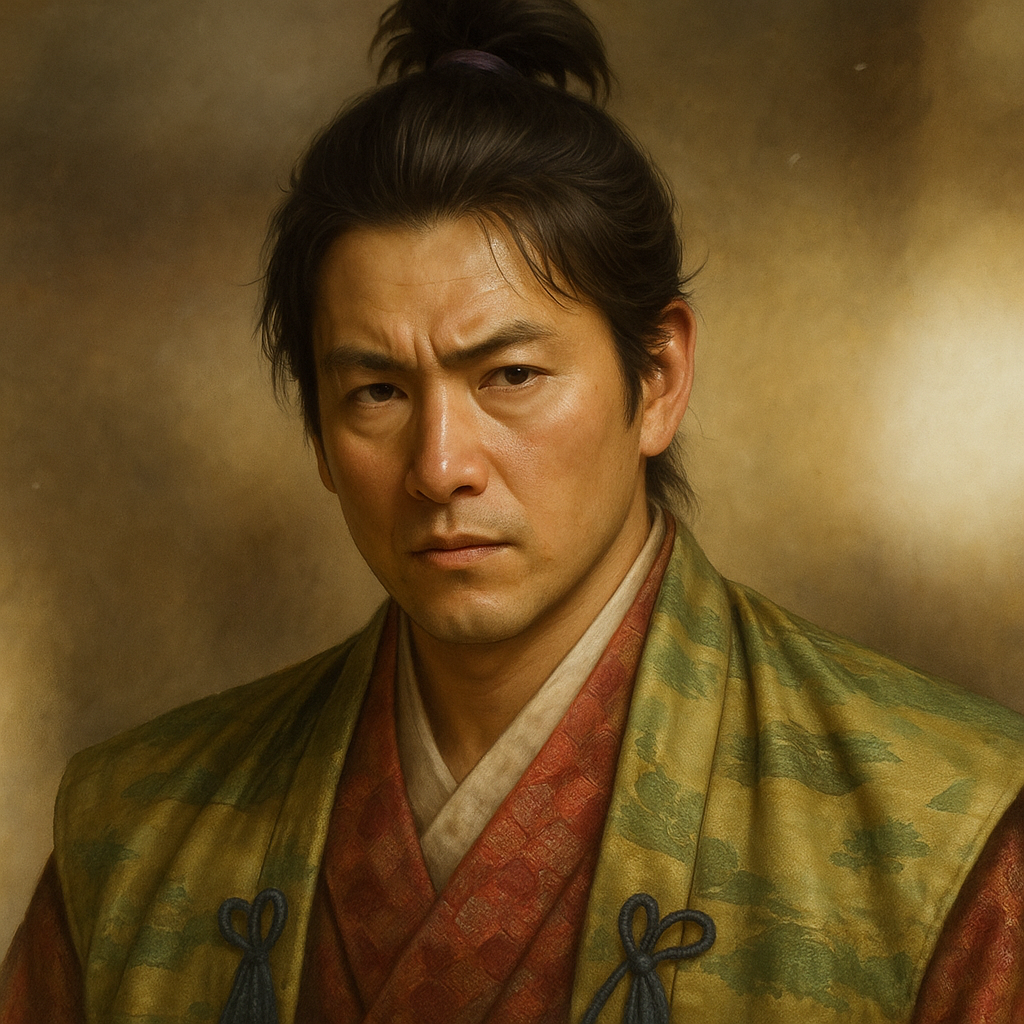
上杉家宿老・清野長範の生涯と功績:史料に基づく徹底的考察
序論
清野長範という人物の再評価、その歴史的実像に迫るにあたり、ご依頼者が提示された「蘆名家臣の子から上杉景勝の近侍となり米沢奉行に至った」という概要は、彼の生涯の骨子を的確に捉えている。しかし、その簡潔な経歴の背後には、敵方からの人質という特異な出自、主君の絶対的な信頼を勝ち得た非凡な才覚、そして上杉家が戦国大名から近世大名へと変容を遂げる激動の時代にあって、行政官僚として果たした極めて重要な役割が秘められている。本報告書は、諸史料に残された断片的な情報を統合し、多角的な分析を通じて、清野長範という一人の武将の歴史的実像を徹底的に解明することを目的とする。
長範がその生涯を捧げた主君・上杉景勝の治世は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人が次々と現れる、日本史上でも屈指の変革期であった。上杉家は、越後を中心に120万石を領する大大名から、関ヶ原の戦いを経て出羽米沢30万石へと減封されるという、まさに存亡の危機に直面した。この苦難の時代を、長範は景勝の最も信頼する側近として、そして藩の重臣として支え続けたのである。彼の生涯は、この時代の武士の生き様、特に戦場での武功のみならず、卓越した実務能力によって立身する「能吏」の典型として、極めて興味深い研究対象である。
第一章:出自と上杉家仕官の謎
1.1. 蘆名四天王・平田氏の子として
清野長範の出自は、その後の彼の人生を理解する上で不可欠な要素である。彼は陸奥国会津を本拠とした戦国大名・蘆名氏の重臣、平田舜範の子として生を受けたとされる 1 。父・舜範は、通称を左京亮、周防守といい、「蘆名四天の宿老」の一人に数えられるほどの重要人物であった 2 。史料によれば、天文9年(1540年)に会津で執り行われた諏訪神社の落成式に際し、他の重臣たちと共に連署しており、古くから蘆名家中枢にいたことが確認できる 2 。また、天正6年(1578年)には、上杉謙信に呼応して蘆名氏に叛旗を翻した大槻政通らを鎮圧するために出陣し、これを成功させるなど、軍事面でも高い能力を有していた 2 。
長範が人質として上杉家へ送られた背景には、当時の蘆名氏と上杉氏の複雑な国際関係があった。両家は奥羽と越後の隣国として、時には不戦同盟を結ぶなど協調関係にあったが 3 、天正6年(1578年)に上杉謙信が没し、その後継を巡って上杉景勝と上杉景虎が争った「御館の乱」では、蘆名盛氏が景虎方に与して越後へ出兵するなど、激しく対立した歴史も持つ 4 。このような緊張と協力が交錯する外交関係の中で、長範は両家の友好、あるいは牽制の証として上杉家へ送られたのである。
彼の出自が単なる一武将の子ではなく、隣国の大大名である蘆名家の最高幹部の子であったという事実は、極めて重要である。この「名門」の出自は、彼が人質として上杉家に渡った際に、単なる保証品以上の価値を持つ存在として扱われた可能性を強く示唆する。後に彼の非凡な才覚が景勝に見出されたことは事実であろうが、その前提として、多くの家臣や小姓の中から景勝の注意を引くに足るだけの高い身分があったことは、彼の立身の第一歩を理解する上で見過ごすことのできない要素である。
1.2. 仕官時期をめぐる諸説
長範が上杉家に仕え始めた時期については、複数の説が存在し、そのキャリアの出発点を巡る謎となっている。
通説として広く知られているのは、少年時代に蘆名氏からの人質として上杉家に入り、その類稀なる才気を主君・上杉景勝に見出されて小姓として取り立てられ、そのまま家臣となった、というものである 1 。この説は、景勝の人物眼と長範の才能を劇的に描き出すものであり、彼の立身出世物語の根幹をなしている。
しかし、この通説に再考を促す史料が存在する。米沢藩の公式記録である『上杉文書』所収の「古代士籍」という家臣名簿の中に、「謙信様衆」、すなわち上杉謙信直属の家臣団の中に「平田助次郎」という名が確認できるのである 1 。長範の通称は助次郎であり、もしこれが同一人物であるならば、彼の仕官は景勝の代ではなく、既に謙信の治世にまで遡ることになる。
さらに、この謙信期仕官説を補強するのが、彼の生年に関する検討である。長範の生年は一般に元亀4年(1573年)頃とされているが 1 、『上越市史』には天正10年(1582年)以前のものと推定される、直江兼続が「清野助次郎」に宛てた書状が二通収録されている 1 。そのうちの一通で、兼続は長範に対して御用材の調達という実務を命じている。もし1573年生まれであれば、この時点で長範はわずか9歳であり、このような実務を一人で担当することは現実的ではない。この書状が正しく長範宛のものであるとすれば、彼はこの時点で既に成人に達し、奉行的な役割を担っていたと考えるのが自然であり、生年は通説よりも大幅に遡り、兼続(1560年生まれ)とほぼ同世代である可能性さえ浮上する。
これらの史料的検討から導き出されるのは、「景勝に見出された少年人質」という通説は、後世に彼の劇的な生涯を分かりやすく伝えるために形成された、ある種簡略化された物語である可能性が高いということである。実際には、父・舜範を通じて謙信の時代から上杉家と何らかの繋がりを持ち、比較的早い段階から上杉家中で活動していたと考える方が、史料との整合性が高い。彼のキャリアの始点は、景勝との個人的な関係性のみに帰結するのではなく、蘆名・上杉両家の複雑な外交関係の中にこそ求められるべきであろう。
第二章:上杉景勝の側近としての台頭
2.1. 名跡継承と知行の拡大
上杉家臣として正式に認められた長範は、景勝の厚い信任を背景に、着実にその地位を高めていく。その象徴的な出来事が、名跡の継承とそれに伴う知行の拡大であった。
文禄元年(1592年)、長範は景勝の命により、信濃の名門である清和源氏村上氏の支流・清野氏の名跡を継承した 1 。これは、出自が敵方であった蘆名氏である長範に対し、上杉家の譜代家臣団に連なる正式な「家」と「家格」を与えるための、景勝による極めて政治的な配慮であった。これにより長範は、単なる個人としての能力だけでなく、信濃に由来を持つ「清野助次郎長範」として、上杉家臣団の中に確固たる地位を築くことになった。この時、彼は信濃猿ヶ馬場城主として4177石の知行を与えられている 1 。
長範のキャリアにおける最大の転機は、慶長3年(1598年)の上杉家の会津120万石への移封であった。この大規模な国替えに伴い、長範は南会津の伊南城代に任じられ、その知行は1万1000石、さらに与力として配下に置かれる同心分として3200石が与えられた 1 。伊南城は、会津若松から越後や関東方面へと通じる街道上に位置する軍事・交通の要衝であり 9 、そのような重要拠点の城代を任されたことは、景勝の長範に対する信頼がいかに厚いものであったかを如実に物語っている。
会津移封時における他の重臣たちの知行と比較しても、長範の破格の待遇は明らかである。例えば、信濃の名族であった須田満親の子・長義が梁川城主として2万石、島津忠直が長沼城代として7000石、芋川正親が白河城代として6000石を与えられた中で、長範の1万1000石は上級家臣の中でも突出した高禄であった 7 。以下の表は、この時期の主要家臣の知行高を示したものである。
表1:上杉家会津移封時における主要家臣の知行高比較表
|
家臣名 |
移封後の居城 |
知行高(本領) |
同心分 |
典拠史料 |
|
須田長義 |
陸奥 梁川城 |
20,000石 |
3,300石 |
7 |
|
清野長範 |
陸奥 伊南城 |
11,000石 |
3,200石 |
1 |
|
栗田国時 |
陸奥 大森城 |
8,500石 |
3,200石 |
7 |
|
島津忠直 |
陸奥 長沼城 |
7,000石 |
3,200石 |
7 |
|
岩井信能 |
陸奥 宮代城 |
6,000石 |
2,480石 |
7 |
|
芋川正親 |
陸奥 小峰城 |
6,000石 |
2,400石 |
7 |
この表が示すように、長範は外様出身でありながら、上杉家譜代の重臣たちと肩を並べる、あるいはそれを凌ぐほどの待遇を受けていた。これは彼の能力と忠誠心が高く評価されていたことの証左に他ならない。
2.2. 景勝との関係性
長範は景勝の小姓からキャリアをスタートさせ、やがて「御側勤」として常にその側に仕える存在となった 1 。主君との物理的な近さは、他の家臣とは一線を画す強固な信頼関係を築く上で、極めて重要な土台となった。
一部の二次史料や俗説では、景勝と長範の間に衆道(男色)の関係があった可能性が指摘されている 11 。しかし、この関係を直接的に証明する一次史料は現存しておらず、あくまでも長範が受けた並々ならぬ寵愛の深さを示す逸話として、慎重に扱うべきである。史実として断定することはできないものの、彼が景勝にとって個人的にも極めて近しい、特別な存在であったことは疑いようがない。
第三章:慶長期の動乱と長範の役割
3.1. 関ヶ原前夜の情報参謀
豊臣秀吉の死後、徳川家康が台頭し、天下が再び大きく揺れ動いた関ヶ原前夜の緊迫した情勢において、清野長範は上杉家の中枢で極めて重要な役割を果たしていた。彼は単なる城代や武将ではなく、主君・景勝と執政・直江兼続とを結ぶ、情報伝達の要、いわば情報参謀として機能していたのである。
その具体的な活動は、慶長5年(1600年)8月から9月にかけての書状群から鮮明に浮かび上がる。この時期、上杉家は家康との対決姿勢を鮮明にしており、周辺大名との外交交渉や軍事情報の収集が急務であった。この重要な局面で、兼続は関東の佐竹氏との交渉内容や、徳川方の動向といった機密情報を、景勝に直接ではなく、まず伊南城にいる長範に宛てて報告しているのである 8 。例えば、9月8日付の書状では、兼続が佐竹家への返書を見たことや、関東方面に大きな異変がないことを長範に伝えている 13 。
この一見すると迂遠な報告形式は、当時の武家の権力構造における「取次」役の重要性を物語っている。主君への情報の取次役は、現代の首席秘書官にもなぞらえられる役職であり、絶大な影響力を持った。上杉家の最高実力者である兼続でさえ、主君への公式な報告ルートを、景勝側近である長範に依存していたという事実は、上杉家の意思決定過程における長範の枢要な立場を明確に示している。彼は単なる伝令役ではなく、日々刻々と変化する膨大な情報を整理し、その重要度を判断し、主君である景勝へ適切な形で言上するという、高度な政治的判断を担っていた可能性が極めて高い。彼の価値は、一万石を超える城代としての軍事力以上に、この主君の側近くにあって情報管理を一手に担う能力にあったのである。
3.2. 慶長出羽合戦
関ヶ原の戦いの東国における主戦場となった慶長出羽合戦においても、長範の役割は一貫していた。上杉軍の主力が最上義光の領内に侵攻し、長谷堂城を巡る激しい攻防戦を繰り広げる中、長範は景勝の許にあって後方からの支援と情報伝達に専念していた。
米沢藩の公式史書である『上杉家御年譜』には、慶長5年9月29日、長谷堂城攻めの最前線にいた兼続が、その日の戦況報告を景勝側近の長範に宛てて送ったことが記録されている 16 。戦況が膠着し、最上軍の急襲を受けるなど予断を許さない状況下においても、兼続から景勝への報告が長範を経由して行われていたという事実は、戦時下においても彼が情報の中枢を担い続けていたことを示す動かぬ証拠である。
第四章:米沢藩初期における重鎮
4.1. 主君の最期と二代藩主・定勝の信頼
関ヶ原の戦いで西軍が敗北した結果、上杉家は徳川家康から会津120万石から出羽米沢30万石への大減封という厳しい処分を受けた 17 。これに伴い、長範の知行も会津時代の1万1000石から3300石へと大幅に減少した 1 。上杉家は120万石時代の大身の家臣団を解雇することなくそのまま米沢へ移住させたため、藩の財政は発足当初から極度の困難に直面した。
このような苦境の中にあっても、長範の忠誠心は揺らぐことなく、景勝の側近として仕え続けた。その忠勤ぶりを最も象徴するのが、景勝の最期における献身的な姿である。『上杉家御年譜』に収録されている二代藩主・上杉定勝の書状によれば、元和9年(1623年)に景勝が薨去した際、長範は昼夜を問わずその側に付き添い、手厚い看病を行ったと記されている 1 。父の最期を看取った長範のこの忠義は、跡を継いだ若き藩主・定勝の心に深く刻まれ、絶対的な信頼関係を築く礎となったことは想像に難くない。
4.2. 米沢奉行への就任とその意義
景勝の死後、米沢藩の藩政はしばらくの間、直江兼続の旧領である与板(新潟県長岡市)出身者で構成される「与板衆」が中枢を占めていた 1 。これは兼続の執政時代からの権力構造が、彼の死後も色濃く残っていたことを示している。
しかし、この状況は寛永10年(1633年)に大きく転換する。二代藩主・定勝は、清野長範と島津利忠の二人を米沢奉行に任命したのである 1 。米沢奉行は、他藩における国家老に相当する藩政の最高責任者であり、この人事は極めて画期的な意味を持っていた。なぜなら、与板衆以外の者から奉行が登用されたのは、これが初めてのことであったからだ。
この人事は、単に長範個人の能力が評価されたという側面に留まらない、より大きな政治的意図を含んでいた。すなわち、藩主・定勝が、父・景勝と執政・兼続の時代から脱却し、自らの親政体制を確立しようとする明確な意思表示であったと解釈できる。兼続の死(元和5年・1619年)から14年を経て、定勝は旧来の兼続派(与板衆)に代わり、父の代からの忠臣であり、かつ自身が直接その忠誠心と実務能力を信頼する長範らを藩政の中枢に据えることで、名実ともに米沢藩の最高統治者としての地位を確立しようとしたのである。長範の奉行就任は、この米沢藩初期における権力構造の移行を象徴する、歴史的な出来事であった。
奉行としての長範の活動は、その死の直前まで続いており、亡くなる年である寛永11年(1634年)4月22日付で、藩主・定勝が長範と島津利忠の両奉行に宛てて指示を与えた書状が現存している 20 。
第五章:『上杉将士書上』作者説の考証
5.1. 作者伝承と史料の性格
清野長範の名は、武将や奉行としてだけでなく、文筆の分野でも後世に伝えられている。彼は、同じく上杉家臣であった井上隼人正と共に、軍記物『上杉将士書上』の作者として知られているのである 1 。
この史料は、上杉謙信・景勝の二代にわたる家臣たちの伝記や、上杉家に関わる様々な事績をまとめたものである。その奥書によれば、江戸幕府からの尋ねに応じて、慶長20年(1615年)と、その後の寛文9年(1669年)に提出された記録を基にして編纂されたと記されている 23 。
5.2. 史料批判的検討
長範を作者とするこの伝承には、史料批判的な観点からいくつかの疑問点が指摘されている。
第一に、成立時期の矛盾である。長範は寛永11年(1634年)に死去しているため 1 、寛文9年(1669年)に最終的に提出された書状の編纂に、彼が直接関与することは物理的に不可能である。さらに、慶長20年(1615年)の成立とされる部分に関しても、内容を精査すると、主君・景勝の死(元和9年・1623年)以降でなければ知り得ないはずの記述が含まれていることが指摘されており、成立年そのものに後年の加筆や再編纂があったことが強く示唆される 25 。
第二に、史料の内容的な性格である。『上杉将士書上』は、客観的な事実を淡々と記録した一次史料というよりは、上杉家の武威や家臣の忠節を後世に伝えることを目的とした、英雄譚や軍記物語としての色彩が非常に強い 26 。これは、幕府への公式な報告書として、自家の由緒や正当性を強調する意図があったためと考えられる。
これらの点を総合的に考察すると、長範を『上杉将士書上』の「著者」と見なすのは適切ではない可能性が高い。しかし、彼が作者として名を連ねていることには、別の理由が考えられる。景勝の側近中の側近であった長範は、その立場上、日々の政務や軍事に関する数多くの一次情報に接し、それらを覚書や日記として記録・整理していた可能性が極めて高い。彼が残したであろうこれらの膨大な一次記録が、後年、米沢藩が幕府へ提出するための公式な史書を編纂する際に、最も信頼性の高い原史料として活用されたと考えるのが妥当であろう。そして、編纂者たちはその記録の信頼性と権威を保証するため、原記録者である長範の名を「作者」として冠したと推測される。つまり彼は、執筆者というよりも、上杉家の歴史を記録した「原史料の提供者」として、その編纂に大きく貢献した人物と評価すべきである。
第六章:死、そして後世への影響
6.1. 最期と清野家のその後
米沢藩の藩政を担う最高職・奉行に就任した翌年の寛永11年(1634年)、清野長範はその波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。
彼の死後も、清野家は上杉家中でその家格を保ち続けた。長範の子・秀範、孫・重範、そして長尾家から養子に入った範佑へと家督は継承され、米沢藩の上級家臣である「侍組分領家」として幕末まで存続した 29 。米沢藩の家臣団の席次を定めた記録によれば、清野家の席次は第19位、禄高は1416石であり、藩内で非常に高い地位を維持し続けたことがわかる 29 。これは、長範一代の功績がいかに大きなものであったかを物語っている。
6.2. 米沢の地に残る足跡
長範が生きた証は、文書記録だけでなく、現在の米沢市の地名にも深く刻まれている。彼の官途名である「周防守」にちなんだ地名が、今なお市民に親しまれているのである。特に、直江兼続が創建した法泉寺の近く、城下の堀立川に作られた「周防殿堰(すおうどのぜき)」や「周防殿橋」は有名である 22 。これらの名称は、かつてこの近辺に長範の下屋敷があり、彼が生活用水の確保や治水事業に関わったことを示す貴重な痕跡と言える。
6.3. 墓所と菩提寺の探求
清野長範個人の墓所の具体的な場所を直接的に示す史料は、今回の調査範囲では確認することができなかった。しかし、その特定に繋がる極めて重要な史料の存在が明らかになっている。
それは、市立米沢図書館がデジタルアーカイブで公開している『侍組順席』という記録である 31 。この史料は天保2年(1831年)に書写されたもので、米沢藩の最上級家臣団である侍組96家の席次、石高、屋敷の所在地、家紋といった情報と共に、各家の「菩提寺」が明記されている 31 。
清野家は前述の通り、侍組分領家として高い席次を誇る家柄であったため、この『侍組順席』にその菩提寺が記載されていることは確実である。したがって、長範とその一族が眠る墓所を特定するには、この『侍組順席』の原本、あるいはその翻刻を調査し、清野家の菩提寺を突き止めることが最も確実かつ直接的な研究方法となる。本報告書では、現時点で直接的な答えを提示することはできないものの、その答えにたどり着くための最も確実な研究アプローチを提示するものである。
結論
清野長範の生涯は、戦国の動乱から近世の安定へと向かう時代の大きな転換期を、為政者の中枢で生き抜いた一人の能吏の姿を鮮やかに映し出している。彼は、敵方である蘆名家の人質という逆境から出発しながらも、その卓越した才覚によって主君・上杉景勝の絶対的な信頼を勝ち取り、情報と実務を司る側近として頭角を現した。彼のキャリアは、戦場での武功のみに依存する従来の武士の立身出世とは一線を画すものであった。
天下分け目の関ヶ原の戦いにおいては、景勝と執政・兼続を結ぶ情報の中枢として機能し、上杉家の意思決定に深く関与した。そして、米沢藩成立後は、二代藩主・定勝の下で旧来の派閥を越えて藩の最高職である奉行に抜擢され、新たな統治体制の礎を築くという重責を担った。その生涯は、主君への個人的な忠誠心と、それを支える卓越した実務能力が、激動の時代を生き抜く上でいかに重要であったかを雄弁に物語っている。
また、『上杉将士書上』の編纂に関わったとされる伝承は、彼が武人や行政官としてだけでなく、上杉家の歴史とアイデンティティを形成する上で、記録という側面からも重要な役割を担っていたことを強く示唆している。清野長範は、上杉家が存亡の危機を乗り越え、近世大名として新たな時代を歩み始めるために不可欠であった、稀有な才覚を持つ忠臣であったと結論付けることができる。
引用文献
- 清野長範 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E7%AF%84
- 平田舜範 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%94%B0%E8%88%9C%E7%AF%84
- 小助官兵衛の戦国史攻略 http://koskan.nobody.jp/sengokukouryaku.html
- 蘆名盛氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F
- 御館の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1
- 上杉家 会津御在城分限帳 https://shiryobeya.com/shokuho/uesugibungen_keicho.html
- 長野市誌 第三巻 歴史編 近世1 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100030/ct00000003/ht000060
- 北信濃戦国武将ゆかりの史跡を訪ねる http://takai.la.coocan.jp/siryoukitasinano.pdf
- 福島県文化財センター 白河館 - 研究紀 要2016 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/38/38739/86296_1_%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%99%BD%E6%B2%B3%E9%A4%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81.pdf
- 福島県文化財センター 白河館 - 研究紀要2017 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/38/38736/86293_1_%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%99%BD%E6%B2%B3%E9%A4%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81.pdf
- ノート:直江兼続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E7%9B%B4%E6%B1%9F%E5%85%BC%E7%B6%9A
- 耳嚢 根岸鎭衞 巻之三 附やぶちゃん訳注 - 鬼火 http://yab.o.oo7.jp/mimi3.html
- 第十三章 佐竹氏の秋田移封 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10830.pdf
- 身柄を預けられた。十二月十七日、義光は志村光安に https://www.kinokuniya.co.jp/banner/9784490109214_contents.pdf
- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-20.html
- (4ページ目)上杉軍の猛攻も虚しく撤退…最上・伊達軍の“粘り勝ち”ではなかった「北の関ケ原」とは https://dot.asahi.com/articles/-/200306?page=4
- 上杉景勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%99%AF%E5%8B%9D
- 上杉景勝は何をした人?「家康を倒す絶好の機会だったのに痛恨の判断ミスをした」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/kagekatsu-uesugi
- 廟所・菩提寺:上杉時代館の「直江兼続公」講座(別館) - 山形県米沢市 - samidare http://samidare.jp/u_jidaikan/note.php?p=list&c=379692&off=6&lo=2&kw=
- 米沢市上杉博物館 コレクション展「米沢藩 武士のお仕事」 展示資料目録 会期 2020年 https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/image/114shigoto/kouki.pdf
- 令和元年度 VOL. 32 - 米沢市上杉博物館 https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/pdf/nenpo/nenpo32.pdf
- 法泉寺|直江兼続・米沢 .com http://www.naoe-kanetugu.com/trip_yonezawa/housenji.html
- 上杉将士書上 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%B0%86%E5%A3%AB%E6%9B%B8%E4%B8%8A
- 越後史集 天 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E5%8F%B2%E9%9B%86_%E5%A4%A9
- 東国太平記 - 甲南女子大学 https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/33/kikuchi1986.pdf
- 上杉景勝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%99%AF%E5%8B%9D
- 関ヶ原の戦いの布陣図に関する考察 - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=10386
- 石垣原合戦を題材とし た軍記・伝記史料 (上) - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4493116/026_pa001.pdf
- 米沢藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E6%B2%A2%E8%97%A9
- 第1節 米沢城の構成と堀周辺のこと|文夫の窓 - note https://note.com/fumionomado/n/n165bfbb0445c
- 侍組順席 - 市立米沢図書館 https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/GA005.html
- コレクション別 市立米沢図書館デジタルライブラリー https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/index_2.html