渋川義長
渋川義長は九州探題として名門の家格を背負うも、戦国時代の実力主義に翻弄され滅亡。大内氏の傀儡から脱却を図り少弐氏と連携するも、大内義隆の猛攻を受け朝日山城で自害。中世的権威の終焉を象徴。
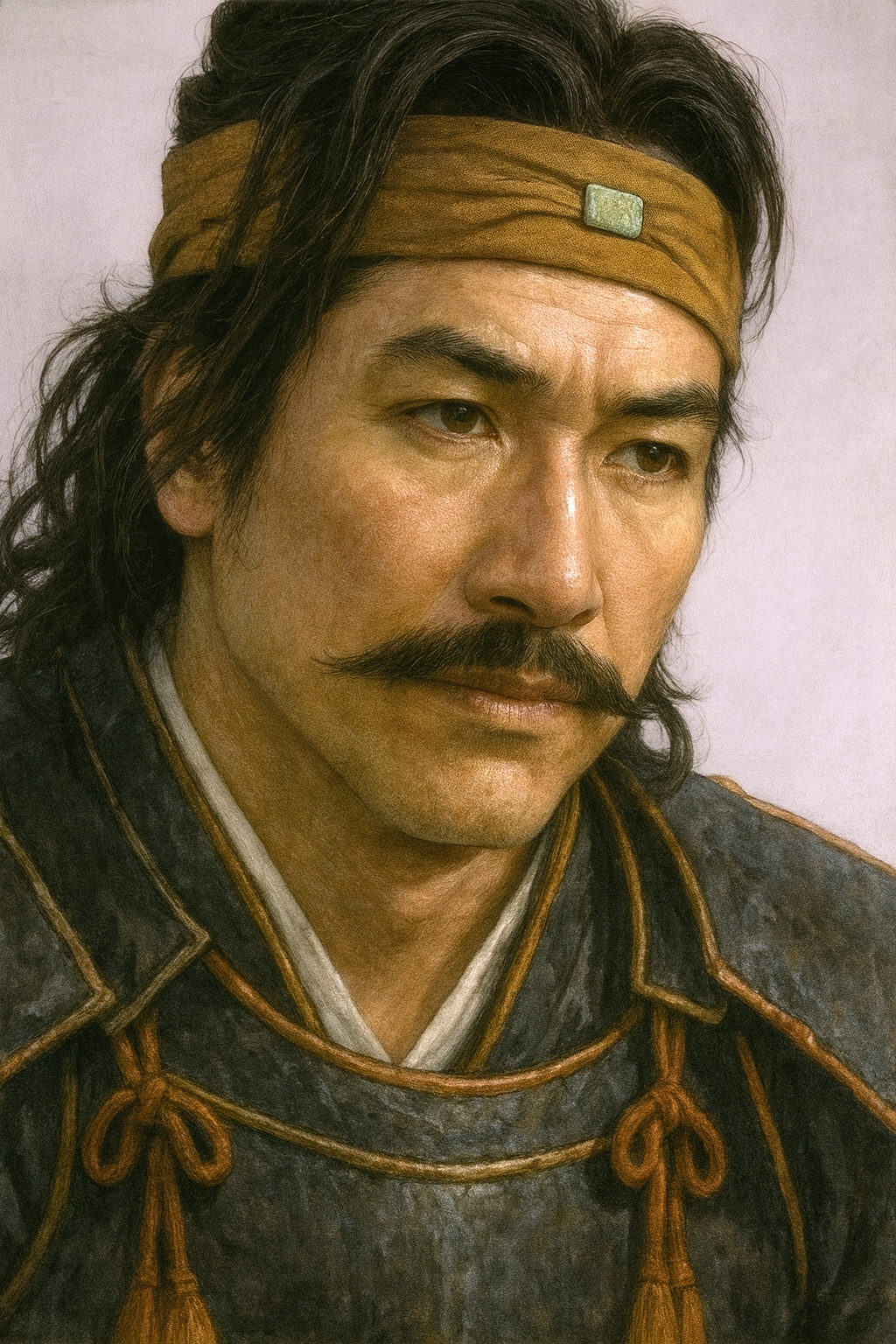
渋川義長 ―滅びゆく権威と戦国九州の動乱―
序論:滅びゆく権威の最後の担い手
戦国時代の九州にその名を刻む武将、渋川義長(しぶかわ よしなが)。彼の生涯は、室町幕府が全国に張り巡らせた権威の象徴である「九州探題」という職位と、足利一門という名門の「家格」を背負いながら、実力主義が全てを支配する時代の荒波に翻弄され、ついには滅亡へと追いやられた悲劇の物語です。彼の人生は、旧来の「権威」と新たな「実力」が激しく衝突した、戦国という時代の転換点を映し出す縮図であったと言えるでしょう 1 。
本報告書が対象とする渋川義長が生きた16世紀前半、九州探題職はすでにかつての権勢を失い、周防の大内氏や豊後の大友氏といった巨大戦国大名の狭間で、その実権をほとんど奪われた「名ばかりの存在」と化していました 2 。本報告書は、この九州探題・渋川義長の生涯を徹底的に追跡し、彼がなぜ滅びなければならなかったのかを、個人的な資質の問題としてではなく、時代の構造的な変化の中に位置づけて分析することを目的とします。彼の悲劇的な結末は、一個人の物語にとどまらず、中世的権威が戦国という時代にいかにして無力化していったかを示す、重要な歴史的ケーススタディとなるからです。
なお、読者の混乱を避けるため、冒頭で一点明確にしておく必要があります。同時期、関東地方においても古河公方・足利義氏に仕えた同名の「渋川義長(義勝)」という武将が存在しますが、本報告書で扱う九州探題・渋川義長とは全くの別人です 5 。この事実は、かつて足利一門として栄華を誇った渋川氏が、本家の衰退と共に日本各地へ拡散し、それぞれの地で在地領主として生き残りを図っていた、戦国時代の武家社会の一側面を象徴しています 4 。九州探題という最高位の職を持つ本家が滅亡の淵に立たされる一方で、分家が各地で新たな道を模索する。この対照的な姿は、渋川氏という一族全体の盛衰という、より大きな歴史的文脈の中で捉えるべきでしょう。
第一章:名門渋川氏の栄光と九州探題職の形骸化
渋川義長の悲劇を理解するためには、まず彼が背負っていた「渋川氏」という家門の栄光と、その権威の源泉であった「九州探題」職が、いかにして力を失っていったのかを把握する必要があります。
1-1. 足利一門「御一家」としての出自
渋川氏は、清和源氏の名門・足利氏の嫡流から分かれた庶流にあたります。その祖は、鎌倉時代の足利宗家4代当主・足利泰氏の子である義顕(よしあき)とされ、彼が上野国渋川荘(現在の群馬県渋川市)を領したことから渋川氏を名乗りました 4 。
足利氏が室町幕府を開くと、渋川氏は将軍家の一族、特に将軍家の家族に準ずる家として扱われる「御一家(ごいっけ)」という極めて高い家格を与えられました 4 。これは、斯波氏や吉良氏など、足利一門の中でも特に格式の高い家にのみ許された待遇でした。2代将軍・足利義詮の正室が渋川幸子であったことも、その地位を一層高める要因となりました 4 。この「御一家」という家格こそが、後に渋川氏が軍事的な実力を失ってもなお、九州における幕府の最高職位である九州探題職を世襲し続けるための、最大の権威的根拠となったのです。
1-2. 九州探題職世襲の経緯
九州探題は、もともと足利尊氏が建武政権から離反し九州へ落ち延びた際、再起をかけて東上するにあたり、九州の統治と南朝勢力の抑圧のために一族の一色範氏を置いたことに始まります 3 。当初は鎮西管領とも呼ばれ、一色氏や斯波氏といった幕府の有力者が任命されました。
特に3代将軍・足利義満の時代に任命された今川了俊(貞世)は、九州に根強く残っていた南朝勢力を一掃し、在地武士団を幕府の支配下に組み込むなど目覚ましい活躍を見せ、九州探題の権威を確立しました 3 。しかし、その功績と九州における強大な権力基盤は、かえって幕府中央の警戒を招くことになります。九州に独立勢力が生まれることを恐れた幕府は、応永2年(1395年)に了俊を解任しました 3 。
そして、その後任として白羽の矢が立ったのが、かつて九州入りすらできずに探題職を更迭された渋川義行の子、渋川満頼でした 3 。幕府からすれば、強大すぎる今川氏よりも、力の弱い渋川氏の方が「御しやすい」と考えたのかもしれません。この満頼の就任以降、九州探題職は渋川氏によって世襲されることとなったのです 3 。
1-3. 権威の失墜 ― 宿敵・少弐氏と新興・大内氏
しかし、この幕府の権力バランスを意図した人事は、結果的に九州探題の権威を著しく低下させる要因となりました。力の弱い渋川氏は、九州の伝統的な名族であり、鎌倉時代以来の勢力圏を持つ少弐氏を抑えきることができませんでした。探題職を世襲した渋川氏は、肥前や筑前の覇権をめぐって少弐氏と絶え間ない抗争を繰り広げることになり、その力は著しく消耗していきました。この少弐氏との宿命的な対立こそが、渋川氏衰退の最大の要因であったと言えます 1 。
さらに、渋川氏の権威に追い打ちをかけたのが、中国地方から関門海峡を越えて北九州へと進出してきた新興勢力・大内氏の存在でした。周防国(現在の山口県東部)を本拠とする大内氏は、幕府の代官として、また日明貿易や日朝貿易の主導権を握ることで、国際貿易港である博多を事実上支配下に置きます 15 。これにより、九州探題が本来持っていたはずの経済的・軍事的基盤は、大内氏によって根こそぎ奪われていきました。
結果として、渋川氏は大内氏の後援がなければ存続すらおぼつかない傀儡のような存在となり、九州全土を統括するはずの九州探題は、肥前国の一部を支配する一地方勢力へと転落してしまったのです 4 。渋川義長が歴史の表舞台に登場した時、彼が継承した「九州探題」という職は、すでにこのような形骸化した権威でしかありませんでした。
第二章:渋川義長の出自と分裂する探題家
権威が失墜し、大国の思惑に翻弄される中で歴史の舞台に登場した渋川義長。彼の出自や名前、そして彼を取り巻く探題家の状況は、渋川氏が置かれていた苦境を如実に物語っています。
2-1. 謎に包まれた出自
渋川義長の出自には、二つの異なる説が存在し、その正確な系譜は謎に包まれています。軍記物である『歴代鎮西志』や『北肥戦誌』は、義長を先代の九州探題・渋川尹繁(ただしげ)の子としています 18 。一方で、渋川家に伝わる「渋川系図」では、尹繁の弟にあたる和是(かずゆき)の子であると記されています 4 。
どちらの説が正しいかを現代において断定することは困難です。しかし、重要なのは、このような系図上の混乱が生じているという事実そのものです。これは、当時の渋川家の家督相続が極めて不安定であり、一族内部の記録すら錯綜するほどの混乱状態にあったことを示唆しています。すでに自立した権力基盤を失っていた渋川家は、外部勢力の介入を受けやすい状況にありました。その結果、家督争いや権威の分裂が常態化し、誰が正統な後継者であるかさえ曖昧になっていったのです。この出自の不確かさは、渋川家が弱体化していたことの「原因」ではなく、すでに弱体化しきっていたことの「症状」と捉えるべきでしょう。
2-2. 名前に秘められた政治的立場 ―「稙直」から「義長」へ
義長の生涯を追う上で興味深いのは、彼が初めは「稙直(たねなお)」と名乗っていたという事実です 19 。この「稙」の一字は、当時、中国地方の雄・大内義興によって擁立され、将軍職に返り咲いた室町幕府第10代将軍・足利義稙(よしたね、初名は義材)から与えられた偏諱(へんき)である可能性が極めて高いと考えられます。
偏諱とは、主君が家臣に自らの名前の一字を与えることで主従関係を確認する、当時としては極めて重要な儀式でした。義長が「稙直」と名乗っていたことは、彼がそのキャリアの初期において、大内氏の強力な影響下にある人物として、大内氏が主導する政治秩序の中に組み込まれていたことを明確に物語っています。
後に彼が「義長」へと改名した正確な経緯は史料からは不明です。しかし、足利将軍家の通字(とおりじ、代々受け継がれる名の一字)である「義」を名前に冠したことは、大内氏の傀儡という立場から脱却し、足利一門としての自らの血筋と、幕府との直接的な繋がりを内外に誇示しようとする、政治的な意図があった可能性が推察されます。それは、彼のその後の行動を予兆する、ささやかな独立への意思表示だったのかもしれません。
2-3. 権力闘争の駒となる探題家
義長が生きた時代、九州探題の権威は地に落ち、もはや九州を統べる力はありませんでした。それどころか、探題職そのものが、北九州の覇権を争う大内氏と大友氏の政争の道具と化していました。両者はそれぞれ、自らにとって都合の良い渋川一族の人間を「九州探題」として擁立し、自らの九州における軍事行動を正当化するための権威として利用したのです 18 。
具体的には、大内義興は渋川稙直(後の義長)を探題として後援する一方で、対立する豊後の大友氏は別の「渋川右衛門佐」なる人物を擁立し、一時期、九州には二人の「九州探題」が並び立つという異常事態が生じていました 18 。渋川義長は、このような大国の思惑に翻弄される、極めて脆弱で不安定な立場で、名ばかりの探題職を継承したのです。彼が自らの意思で行動を起こす余地は、当初からほとんど残されていませんでした。
第三章:北九州の動乱と義長の乾坤一擲
大内氏の傀儡として、かろうじてその地位を保っていた渋川義長。しかし、北九州の勢力図を揺るがす一つの戦いが、彼に生涯一度きりの勝機、そして破滅へと繋がる決断を促すことになります。
この時代の複雑な情勢を理解するため、まず主要な動向を時系列で整理します。
表1:渋川義長の時代における北九州の主要動向
|
年代(西暦/和暦) |
出来事 |
主要関連人物・勢力 |
典拠 |
|
享禄元年 (1528) |
大内義興、朝日山城を攻略。城主・朝日頼貫が敗死。 |
大内義興、朝日氏 |
29 |
|
享禄3年 (1530) |
田手畷の戦い 。少弐資元軍が、龍造寺家兼らの活躍で大内軍に大勝。 |
少弐資元、龍造寺家兼、大内義隆、杉興運 |
24 |
|
天文元年 (1532) |
大内義隆の命を受けた陶興房、大軍を率いて九州に侵攻。 |
陶興房、大内義隆、大友義鑑、少弐資元 |
23 |
|
天文2-3年 (1533-34) |
渋川義長、大内氏から離反し、少弐氏と連携。 |
渋川義長 、少弐資元 |
24 |
|
天文3年 (1534) |
陶興房の攻撃により朝日山城落城。 渋川義長、自害。 |
渋川義長 、陶興房 |
1 |
|
天文5年 (1536) |
大内軍、少弐資元を多久城で自刃に追い込む。 |
少弐資元、陶興房 |
23 |
3-1. 三大勢力の角逐と探題の苦境
16世紀前半の北九州は、三つの巨大勢力が角逐する、まさに戦国の様相を呈していました。一つは、父・義興の死後、家督を継いでさらなる九州経略を推し進める周防の大内義隆。二つ目は、大内氏の侵攻に激しく抵抗し、肥前・筑前における伝統的な権益を守ろうとする名族・少弐資元。そして三つ目は、豊後を拠点に両者の争いを静観しつつ、虎視眈々と勢力拡大の機会を窺う大友義鑑です 21 。
この巨大な勢力争いの渦中で、大内氏の傀儡であった渋川義長の立場は、極めて息の詰まるものでした。自らの意思で軍を動かすことも、領地を安堵することもできず、ただ大内氏の九州支配の道具として存在するだけの、無力な探題。その心中には、名門としての誇りと現実の無力感との間で、絶え間ない葛藤があったことでしょう。
3-2. 決断の背景 ― 田手畷の衝撃
そんな義長の運命を大きく揺るがしたのが、享禄3年(1530年)に起こった「田手畷(たでなわて)の戦い」でした 24 。この戦いで、少弐資元は、家臣である龍造寺家兼らの目覚ましい活躍によって、肥前へ侵攻してきた大内軍を撃破するという劇的な勝利を収めます。
この一戦は、北九州のパワーバランスに衝撃を与えました。当時、向かうところ敵なしと見られていた大内軍の敗北は、その無敵神話を揺るがすのに十分でした。そして、この知らせは、大内氏の圧政に喘いでいた渋川義長にとって、一条の光に見えたはずです。「もしかしたら、大内氏の支配から自立できるかもしれない」。田手畷の勝利は、彼にそうした希望を抱かせた最大の要因であったと推察されます。
3-3. 宿敵との同盟 ― 生き残りを賭けた一手
田手畷の戦いから数年後、渋川義長は生涯で最も重大な決断を下します。長年にわたる後援者であった大内氏を裏切り、本来であれば探題家の宿敵であったはずの少弐資元と手を結んだのです 26 。
この行動は、単なる気まぐれや短慮によるものではありません。滅亡寸前にあった探題家が、千載一遇の好機と見て打って出た、まさに乾坤一擲の賭けでした。彼の行動は、傀儡状態から脱し、九州探題としての権威を取り戻そうとする「自立」への渇望の表れと見ることもできます。しかし同時に、より現実的な視点に立てば、衰退の兆しを見せた大内氏という古いパトロンを見限り、田手畷の勝利で勢いを増した少弐氏という新たなパトロンに「乗り換える」ことで、自らの生き残りを図ろうとした、とも解釈できます。
いずれにせよ、この決断は、彼が独立した権力者としてではなく、より強力な勢力に依存することでしか生き残れないという、当時の九州探題職が抱える構造的な限界を浮き彫りにしています。そして、この賭けは結果的に、西国最強の大名・大内氏の虎の尾を踏む行為であり、自らの破滅を決定づける致命的な一手となったのです。
第四章:朝日山城の攻防と渋川探題家の終焉
少弐氏との連携という最後の賭けに出た渋川義長。しかし、彼の決断は西国の覇者・大内義隆の逆鱗に触れ、名門渋川探題家は、その歴史に終止符を打つことになります。その最後の舞台となったのが、肥前の朝日山城でした。
4-1. 最後の拠点・朝日山城
義長が最後の抵抗の拠点として選んだ朝日山城は、現在の佐賀県鳥栖市に位置し、筑前国と肥前国を結ぶ交通の要衝にありました 28 。この地を押さえることは、北九州の物流と軍事の動脈を掌握することを意味し、戦略的に極めて重要な拠点でした。
しかし、この城は義長にとって因縁の地でもありました。もともとは少弐氏の一族である朝日氏の居城でしたが、義長が籠城するわずか数年前の享禄元年(1528年)、大内義興の攻撃によって陥落し、城主の朝日頼貫が討ち取られていたのです 29 。義長がこの城に拠点を移したことは、大内氏に対する明確な敵対の意思表示であり、もはや後戻りはできないという覚悟の表れでした。
4-2. 大内最強の矛・陶興房の侵攻
主筋であるはずの九州探題の裏切りに対し、大内義隆が派遣したのは、単なる討伐軍ではありませんでした。総大将に任じられたのは、大内家臣団の中でも随一の武功を誇り、義隆の父・義興の代から家を支えてきた重臣中の重臣、陶興房(すえ おきふさ)でした 23 。
陶興房は、大内義興の上洛に従って畿内で戦い、また山陰地方では尼子氏との激戦をくぐり抜けてきた歴戦の猛将です 23 。彼が率いる軍は、大内軍の中でも最強の精鋭部隊でした。義長の反乱を鎮圧するために、大内氏がその全力をもって臨んだことが窺えます。義長が対峙しなければならなかった相手は、あまりにも強大であり、戦いの帰趨は、始まる前からすでに決していたと言っても過言ではありませんでした。
4-3. 籠城戦と義長の最期
天文元年(1532年)、陶興房率いる大内軍の主力は九州に上陸し、少弐・大友連合軍との間で激しい戦いを繰り広げます 23 。当初は筑紫氏らの頑強な抵抗に遭い苦戦するものの、興房は巧みな戦術で戦局を有利に進め、徐々に少弐方の城を攻略していきました。
そして天文3年(1534年)、ついに大内軍の矛先は、渋川義長が籠る朝日山城に向けられます。義長は城に立てこもり必死の抵抗を試みますが、大軍の猛攻の前になすすべもなく、城は陥落。進退窮まった渋川義長は、城中にて自害して果てました 1 。これにより、鎌倉時代から続いた足利一門の名家、九州探題渋川氏は事実上滅亡したのです。
この義長の死は、単なる一個人の敗北ではありませんでした。それは、彼がどれほど有能であったとしても、あるいはどのような判断を下したとしても、もはや抗うことのできなかった、歴史の大きな構造的変化の帰結でした。関門海峡を越えて強大な経済力と軍事力を投射できる大内氏のような戦国大名の前では、幕府の権威を背景とするだけの「探題」という中世的な統治システムは、もはや有効に機能し得なかったのです。義長の死は、個人の能力や判断ミスによる敗北という側面以上に、中世的権威の象徴であった「探題」というシステムが、戦国的な実力支配のシステムに完全に敗北し、取って代わられた歴史的瞬間として捉えるべきでしょう。
4-4. 九州探題職の事実上の滅亡
渋川義長の死は、一個人の死であると同時に、室町幕府が九州統治のために設置した出先機関としての「九州探題」が、その歴史的役割を完全に終えた瞬間でもありました 9 。これ以降、九州探題職は、九州の覇者が自らの権威を装飾するための、名目上の称号へとその意味合いを完全に変えていくことになります。
結論:名門の落日と戦国という時代
渋川義長の生涯は、足利一門という「家格」と九州探題という「職位」に代表される中世的な権威が、武力や経済力といった「実力」によって容赦なく駆逐されていく「下剋上」の時代を、まさに体現した悲劇でした。彼は、滅びゆく権威の最後の担い手として、時代の大きな転換点に立ち会い、そしてその濁流に飲み込まれていったのです。
興味深いことに、義長の死後も「九州探題」という職位そのものは、しばらくの間存続しました。義長を滅ぼした大内義隆は、今度は渋川一族の別の人物である渋川義基を新たな傀儡探題として擁立します 20 。さらに、その大内氏が家臣の謀反(大寧寺の変)によって滅亡すると、今度は豊後の大友宗麟(義鎮)が室町幕府から正式に九州探題に任命されました 9 。しかし、これらはもはや幕府の権威を代行する統治者ではなく、九州における実力者が、自らの支配を正当化するためにまとうアクセサリーへと、その本質を完全に変質させていました。渋川義長の死と共に、本来の意味での九州探題は終焉を迎えたのです。
渋川探題家の滅亡は、北九州における大内氏の支配を一時的に決定的なものにしました。しかし、歴史の歯車は止まりません。その大内氏も、わずか17年後には内部崩壊し、九州は、大友、龍造寺、島津という三大勢力が覇を競う、より熾烈な戦国時代へと突入していきます 35 。渋川義長の死は、九州の歴史が新たな動乱のステージへと移行する、一つの幕開けであったとも言えるでしょう。
最後に、九州探題家という家は滅びましたが、渋川一族の血脈そのものが完全に途絶えたわけではありません。九州に残った一族の一部は、後に肥前の戦国大名となった龍造寺氏や、その跡を継いだ鍋島氏、あるいは大村氏の家臣として仕え、近世までその名を伝えています 1 。名門の落日は、戦国という時代の非情さを示すと同時に、形を変えながらもたくましく生き抜いていく武士たちの姿をも我々に伝えているのです。
引用文献
- 渋川氏(しぶかわうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E6%B0%8F-74873
- 室町幕府の機構 管領、鎌倉府・探題、守護など - 戦国未満 https://sengokumiman.com/family/muromachibakufu.html
- 九州探題(キュウシュウタンダイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%8E%A2%E9%A1%8C-52057
- 渋川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E6%B0%8F
- 渋川義勝(しぶかわ よしかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E5%8B%9D-1080673
- 渋川義陸とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E9%99%B8
- 武家家伝_渋川氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/sibuka_k.html
- 足利氏一門系図 分家の鎌倉・古河・堀越公方等 - 戦国未満 https://sengokumiman.com/family/ashikagaclan.html
- 九州探題 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%8E%A2%E9%A1%8C
- 南北朝の動乱と南九州の武士たち - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab24/nanbokucyou.html
- 渋川義行 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E8%A1%8C
- 渋川(しぶかわ)氏 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/si2.html
- 武家家伝_渋川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sibuka_k.html
- 九州探題の衰滅過程 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7179478/23_p081.pdf
- 大内氏の博多支配機構 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2230665/p001.pdf
- Untitled http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-3-3-2.pdf
- 大内義弘 http://clayon.sakura.ne.jp/sblo_files/y-densho/image/rekidai02.pdf
- 渋川尹繁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E5%B0%B9%E7%B9%81
- 渋川義長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E9%95%B7
- 渋川義基 (九州探題) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E5%9F%BA_(%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%8E%A2%E9%A1%8C)
- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86
- 武家家伝_鍋島氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nabesima.html
- 陶興房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E8%88%88%E6%88%BF
- 九州戦国年表/福岡の歴史 https://www.2810w.com/txtsengokunenp.html
- 田手畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%89%8B%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 九州南北朝(年表) - 福岡史伝 https://www.2810w.com/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%EF%BC%88%E5%B9%B4%E8%A1%A8%EF%BC%89
- 北部九州戦国(年表) - 福岡史伝 https://www.2810w.com/%E5%8C%97%E9%83%A8%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%88%A6%E5%9B%BD%EF%BC%88%E5%B9%B4%E8%A1%A8%EF%BC%89
- 綾部城 (肥前国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%BE%E9%83%A8%E5%9F%8E_(%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%9B%BD)
- 朝日山城の見所と写真・100人城主の評価(佐賀県鳥栖市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1679/
- 肥前 朝日山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/asahiyama-jyo/
- 陶氏(すえうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%99%B6%E6%B0%8F-1177383
- 陶興房 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sue-castle/sue-okifusa/
- 朝日山城 (肥前国)とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E+%28%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%9B%BD%29
- (大友宗麟と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/20/
- 【毛利元就(もとなり)と大友宗麟(そうりん)の戦い 豊前国盗り】 - ADEAC https://adeac.jp/tagawa-lib/text-list/d300010/ht000730