照蓮寺明誓
照蓮寺明誓は飛騨の動乱期に生きた僧。息子たちが武力で内ヶ島氏と衝突、和睦後は共同統治体制を築き、煙硝生産で繁栄。天正大地震で内ヶ島氏滅亡後、照蓮寺は高山へ移転し近世大名に組み込まれた。
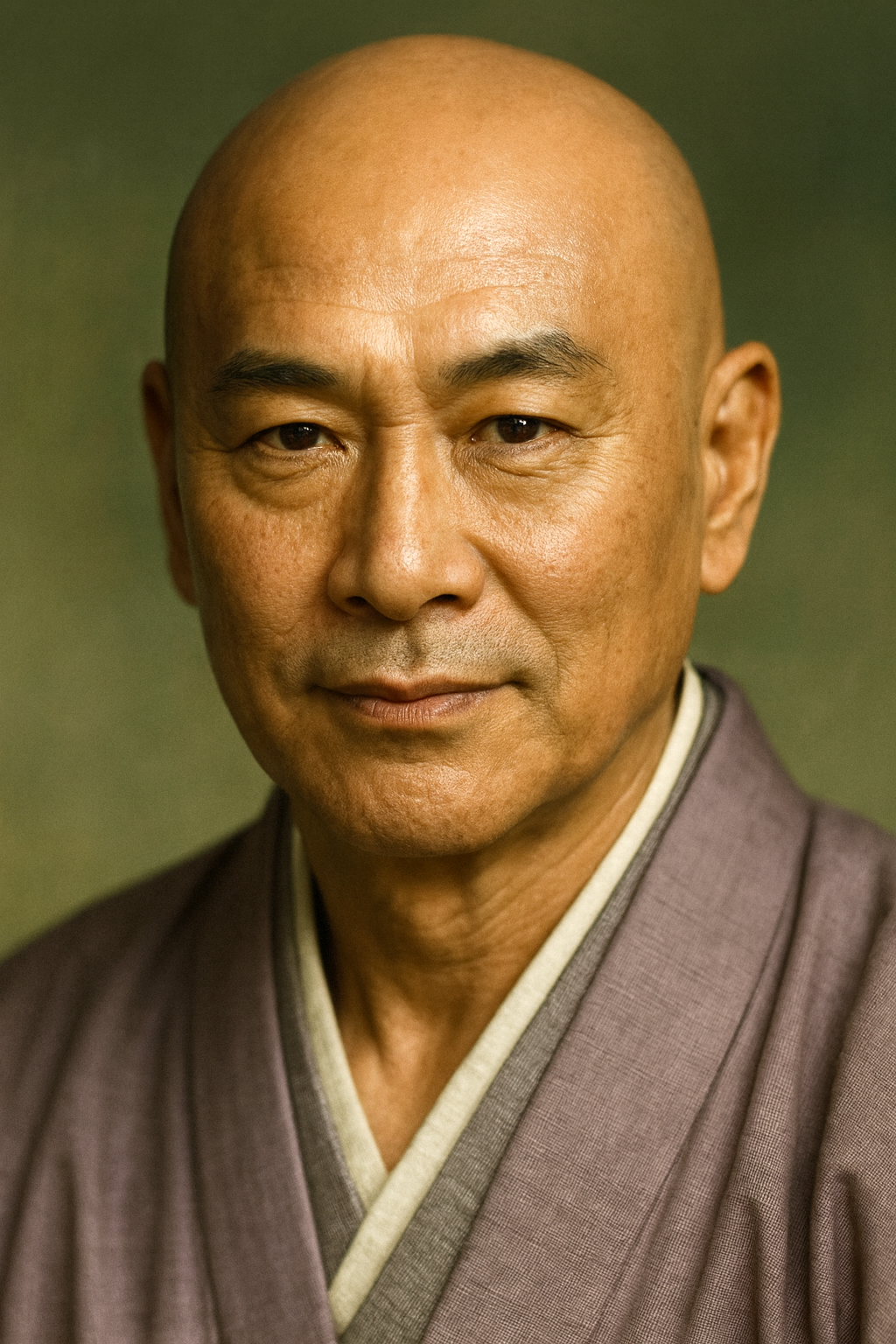
戦国期飛騨の動乱と宗教勢力:照蓮寺明誓とその時代
序章:戦国期飛騨の動乱と照蓮寺明誓 ―激動の転換点に立った僧侶―
本報告は、戦国時代の美濃・飛騨地方にその名を刻む浄土真宗寺院・照蓮寺の八世住職、明誓という一人の人物に焦点を当てる。しかし、明誓個人の具体的な行動を記した史料は極めて乏しい 1 。したがって、本稿では明誓を、彼の息子たちが引き起こす大規模な動乱と、その後の新たな秩序形成という、飛騨白川郷の歴史的転換点を象徴する「家父長」として位置づける。彼の生涯と、彼が生きた時代を、寺院の内部事情、在地領主との関係、そして地域の経済構造という三つの側面から重層的に解明することを目的とする。
飛騨国白川郷は、美濃、越中、加賀という戦略的に重要な地域を結ぶ交通の要衝にありながら、四方を険しい山々に囲まれた閉鎖的な地理的条件を持つ特異な地域であった 3 。この地理的条件は、厳しい自然環境に適応するための合掌造りの家屋や「結」と呼ばれる共同労働の慣習といった独自の文化を育んだ 4 。同時に、この隔絶された土地は、戦国時代の趨勢を左右する二つの重要な経済的資源、すなわち金銀鉱山と火薬の原料である煙硝の生産地としての役割を担うこととなる 4 。本報告で詳述する照蓮寺と在地領主・内ヶ島氏の物語は、この特異な地理的・経済的背景の上で繰り広げられた、信仰と武力、そして富を巡る壮大な歴史劇であった。
第一章:照蓮寺の黎明と明誓の時代 ―武力と信仰の狭間で―
一. 嘉念坊善俊による開基から正蓮寺の成立まで
照蓮寺の起源は、鎌倉時代の1253年(建長5年)に遡る。親鸞聖人の直弟子であった嘉念坊善俊が、美濃国長滝から飛騨国白川郷の鳩ヶ谷に入り、「正蓮寺」を建立したのがその始まりとされる 3 。善俊は後鳥羽上皇の子、あるいは孫であるという高貴な出自の伝説をまとっており、この伝説は後世、寺院の権威を高める上で重要な役割を果たしたと考えられる 3 。この正蓮寺を中心に、飛騨における浄土真宗の教えは深く根を張り、やがて地域社会に絶大な影響力を持つ一大勢力へと発展していった 7 。
二. 八世住職・明誓の登場とその時代背景
15世紀後半、応仁の乱(1467-1477年)を経て室町幕府の権威が失墜し、日本各地で在地領主が実力で領国を支配する「下剋上」の時代が到来した。この激動の時代に、正蓮寺の八世住職として寺を率いたのが明誓である 8 。この時期、寺社勢力もまた、自らの所領や権益を戦乱から守り、さらには勢力を拡大するために、武装化の道を歩むのが全国的な潮流であった 9 。寺院は単なる信仰の場に留まらず、僧兵を擁する軍事拠点、そして金融業や手工業を営む経済主体としての顔を持つようになっていた 12 。明誓が住職を務めた正蓮寺も、この時代の荒波と無縁ではいられなかった。
明誓自身が歴史の表舞台で大きな行動を起こしたという記録は見当たらない。しかし、彼の存在が歴史的に重要であるのは、彼が二人の息子の父であったという点に起因する。この二人の息子の対照的な生き様は、当時の寺社勢力が直面していた「信仰の道」と「武力の道」という二者択一のジレンマを、まさに一身に体現するものであった。兄の教信は武家の道を志向し、弟の明教は法灯を継承した。このことは、明誓の時代が、正蓮寺が純粋な宗教施設から、武装した政治・経済主体へとその性格を大きく変貌させていく、まさにその過渡期にあったことを象徴している。明誓は旧来の宗教的権威を背負う最後の世代であり、彼の息子たちは武力と政治が支配する新しい時代の担い手であった。明誓という一人の僧侶の家庭内に、新旧の価値観が激しく交錯し、寺院のあり方が根本から問われた時代の緊張感が凝縮されていたのである。
三. 明誓の二子:武を好む教信と法を継ぐ明教
明誓には二人の息子がいた 1 。長男の教信は、僧侶として寺に生まれながらも、その心は仏道よりも武芸に向いていた。「弓馬の道を好み合戦計略の事にのみ没頭す」と記録されるように、彼は時代の風潮に憧れ、武士として生きることを渇望した 1 。やがて教信は還俗(僧侶が俗人に戻ること)し、「三島将監」と名乗り、自ら武装勢力を組織して、戦国の世に身を投じていくことになる 6 。
一方、次男の明教は、兄とは対照的に寺に残り、父・明誓の跡を継いで正蓮寺第九世住職となった 6 。この兄弟の明確な役割分担は、単なる個人の資質の違いに留まらない、寺院としての生存戦略であった可能性が考えられる。すなわち、兄の教信が「俗(武力・政治)」の世界で寺の外的安全保障と勢力拡大を担い、弟の明教が「聖(信仰・法灯)」の世界で寺の宗教的権威と門徒組織の結束を維持するという、両面作戦であったと解釈できる。こうして正蓮寺は、信仰と武力を両輪として、飛騨の山中にその勢力を確固たるものにしていったのである。
第二章:在地領主・内ヶ島氏との相克 ―飛騨一向一揆の再解釈―
明誓の息子たちが正蓮寺を率いた時代は、飛騨白川郷に新たな在地領主として内ヶ島氏が登場し、両者の関係が緊張から衝突、そして和睦へと劇的に変化した時期であった。この一連の出来事は、単なる地域紛争ではなく、本願寺教団全体の動向とも深く関わる複雑な様相を呈していた。
表1:照蓮寺と内ヶ島氏に関わる主要年表
|
西暦(和暦) |
主要な出来事 |
関係人物・勢力 |
意義と背景 |
|
1462年頃(寛正年間) |
内ヶ島為氏、帰雲城を築城。飛騨白川郷の領主となる。 |
内ヶ島為氏 |
足利義政の命で入部したとされる在地領主の台頭 14 。 |
|
1475年頃(文明7年) |
内ヶ島為氏、正蓮寺を攻撃するも撃退される。 |
内ヶ島為氏、三島将監(教信)、明教 |
『岷江記』によれば、正蓮寺側の抵抗が激しかったことが示唆される 8 。 |
|
1488年(長享2年) |
内ヶ島為氏による正蓮寺焼き討ち。三島将監戦死、明教自害。 |
内ヶ島為氏、三島将監(教信)、明教 |
正蓮寺は一時壊滅。従来の解釈では内ヶ島氏による宗教弾圧とされた 7 。 |
|
1498年(明応7年) |
「六月二日付蓮如書状」発給。 |
蓮如、善俊門徒、内ヶ島氏 |
善俊門徒(三島将監ら)が本願寺の意に反して内ヶ島氏と交戦したことを蓮如が叱責し、破門。内ヶ島氏が本願寺中央と連携していた可能性が浮上し、歴史解釈が大きく転換した 16 。 |
|
1504年(永正元年) |
明心、内ヶ島氏と和睦し、白川郷中野に寺を再興。「光曜山照蓮寺」と改称。 |
明心(明教の子)、内ヶ島為氏、実如 |
本願寺の仲介による和睦。照蓮寺は内ヶ島氏の庇護下に入ることで再興を果たす 7 。 |
|
1585年(天正13年) |
金森長近の飛騨侵攻。内ヶ島氏理は降伏。 |
金森長近、内ヶ島氏理、豊臣秀吉 |
豊臣政権による天下統一事業の一環。飛騨の支配体制が大きく変わる契機となる 18 。 |
|
1586年1月(天正13年11月) |
天正大地震により帰雲城が埋没。内ヶ島氏一族が滅亡。 |
内ヶ島氏理 |
天災による権力の空白が発生。金森氏による飛騨支配が確定的となる 14 。 |
|
1588年(天正16年) |
金森長近の命により、照蓮寺が高山城下へ移転。 |
金森長近、照蓮寺(明心) |
近世的な城下町政策の一環。照蓮寺は金森藩の統治機構に組み込まれる 7 。 |
一. 武士僧・三島将監(教信)の勢力拡大と内ヶ島氏の台頭
還俗した三島将監(教信)は、弟の明教が率いる正蓮寺の門徒組織を背景に、強力な武装集団を形成した。彼らは飛騨国内に留まらず、加賀一向一揆など、北陸地方で繰り広げられていた本願寺門徒の戦乱にも積極的に兵を派遣し、その武名を轟かせた 7 。
時を同じくして、飛騨の政治地図に新たなプレイヤーが登場する。室町幕府八代将軍・足利義政の命を受け、信濃国から飛騨に入部したとされる内ヶ島為氏である 15 。為氏は白川郷の南口にあたる牧戸に城を築き、やがて北進して帰雲城を本拠と定め、白川郷一帯の支配者としての地位を確立していった 8 。こうして、飛騨の山中を舞台に、新興の武家領主・内ヶ島氏と、武装化した宗教勢力・正蓮寺という二つの権力が対峙する構図が生まれたのである。
二. 文明・長享年間の対立と正蓮寺焼き討ち
両者の勢力圏が接する中で、対立は避けられなかった。照蓮寺側の史料である『岷江記』によれば、両者の緊張は次第に高まり、ついに武力衝突へと発展する 8 。そして1488年(長享2年)、内ヶ島為氏は正蓮寺に大規模な攻撃を仕掛け、堂宇をことごとく焼き払ったとされる 7 。この焼き討ちによって、武装蜂起を主導した三島将監は討死し、弟の住職・明教も辛うじて逃げ延びたものの、後に自害に追い込まれた 7 。これにより、明誓の子らが築き上げた正蓮寺の勢力は、一度完全に滅び去ることとなった 24 。
三. 対立の深層 ―「在地領主 vs 宗教勢力」から「本願寺中央 vs 地方分派」へ―
この一連の抗争は、長らく『岷江記』の記述に基づき、「圧政を敷く在地領主・内ヶ島氏」と「それに抵抗する宗教勢力・正蓮寺」という単純な二項対立の構図で理解されてきた。しかし、近年の研究、特に「六月二日付蓮如書状」という同時代史料の発見によって、この歴史像は根本的な見直しを迫られている 16 。
この書状は、本願寺八世宗主である蓮如が、北陸方面の教団を統括する蓮誓に宛てたものである。その中で蓮如は、白川の善俊(正蓮寺の開祖)の後継者たちが、在地地頭である内ヶ島氏に対して「弓箭を取った(=武力で反抗した)」ことについて、「言語道断の次第である」と極めて厳しい言葉で断罪している 16 。さらに、彼らが本願寺からの命令であると偽って越中や加賀の門徒を動員しようとしたことを非難し、関係者を破門するよう命じているのである 16 。
この書状が明らかにした事実は、歴史の解釈を180度転換させるものであった。第一に、この抗争は内ヶ島氏からの一方的な弾圧ではなく、正蓮寺側が先に仕掛けた、あるいは少なくとも本願寺の意向を無視して引き起こしたものであったこと。第二に、本願寺の最高指導者である蓮如が、内ヶ島氏の立場を事実上、是認していたことである。
これにより、抗争の深層にあった真の構図が浮かび上がってくる。それは、飛騨における真宗門徒が、本願寺中央の統制を受け入れようとする「正蓮寺門徒」と、古くからの土着的な信仰を守ろうとする独立志向の強い「善俊門徒」という二つの派閥に分裂していたという事実である 16 。三島将監(教信)が率いたのは後者の勢力であり、彼らは本願寺中央から見れば、教団の統制を乱すコントロール不能な「異端分子」であった。一方で内ヶ島氏は、本願寺中央と連携し、この「異端」を討伐・平定するための協力者という役割を担っていたと考えられる。つまり、この事件は単なる「領主による宗教弾圧」ではなく、「中央教団が、在地領主と手を組み、地方の独立性の強い分派を粛清・吸収していく過程」であったと再解釈できるのである。
四. 蓮如の仲裁と和睦:明心の照蓮寺再興と新たな関係
三島将監らの勢力が一掃された後、事態の収拾に乗り出したのは、他ならぬ本願寺であった。蓮如とその子・実如の仲介により、自害した明教の遺児・亀寿丸と、内ヶ島氏との間で和睦が成立する 6 。亀寿丸は本願寺で得度して「明心」と名を改め、正蓮寺の再興を許された 8 。
この和睦には明確な条件があった。それは、再興される寺が、内ヶ島氏の支配下(配下)に入ることであった 17 。1504年(永正元年)、明心は白川郷中野の地に寺院を再建し、その名を「正蓮寺」から「光曜山照蓮寺」へと改めた 7 。これは、過去の対立との決別と、内ヶ島氏との新たな協力関係の始まりを象徴する出来事であった。一説には、この和睦の証として、明心は内ヶ島為氏の娘を正室に迎えたとも伝えられており、両者は血縁によっても固く結ばれることになった 25 。こうして、かつての敵対関係は、新たな主従・協力関係へと昇華されたのである。
第三章:白川郷の共同統治体制と経済基盤 ―富と権力の源泉―
一. 領主・内ヶ島氏と宗教権威・照蓮寺による「二元統治体制」の確立
内ヶ島氏との和睦を経て、白川郷の統治体制は新たな段階へと移行した。それは、内ヶ島氏が持つ「武家権力」と、照蓮寺が持つ「宗教的・経済的権威」が相互に補完し合いながら地域を支配する、一種の二元的な共同統治体制であった 24 。この体制において、内ヶ島氏は領主として軍事・外交・徴税といった公的な支配権を掌握し、地域の政治的安定を担った 15 。一方、照蓮寺は広範な門徒ネットワークを通じて民衆の信仰と日常生活を掌握し、後述する地域の基幹産業を組織化するという、内政と経済における重要な役割を担った 7 。
この「両国経営」とも称される統治形態 27 は、両者にとって利益のあるものであった。内ヶ島氏は、照蓮寺の宗教的権威を利用することで、深く真宗信仰が根付いた民衆を円滑に支配することができた。照蓮寺は、内ヶ島氏の軍事力を後ろ盾とすることで、寺領の安全を確保し、安定した環境下で経済活動に専念することができた。かつて血で血を洗う争いを繰り広げた両者は、互いの強みを活かして地域を分業統治するという、極めて合理的で安定した関係を築き上げたのである。
二. 白川郷の富の源泉:金銀鉱山と煙硝生産
この共同統治体制を経済的に支えたのが、白川郷が産出する二つの重要な資源であった。一つは、金銀に代表される鉱物資源である 6 。内ヶ島氏の勢力基盤は、領内に点在する鉱山の経営に大きく依存していた 5 。その産出量は相当なものであったと見られ、一説には、内ヶ島氏が幕府に上納した富が、足利義政による銀閣の建立費用の一部になったとも言われている 17 。
そして、もう一つが、戦国時代の帰趨を左右する戦略物資、すなわち火薬の主原料である「煙硝(塩硝)」の生産である 4 。湿潤な日本の気候風土では生産が困難であった硝石を、白川郷の人々は独自の技術で生み出していた。それは、合掌造りの広大な床下空間を利用し、ヨモギなどの草、蚕の糞、そして人尿などを混ぜ合わせた土(培養土)を数年かけて発酵させ、硝化バクテリアの働きによって硝酸塩を生成させるというものであった 4 。この家内工業的な生産は、照蓮寺の門徒組織によって系統的に管理・運営されていたと考えられ、白川郷の富の大きな源泉となっていた。
三. 戦略物資「煙硝」が規定した白川郷の地政学的価値
鉄砲が戦の主役となった戦国時代において、その弾丸を飛ばすための火薬、そしてその原料である硝石は、現代の石油や半導体にも匹敵する最重要の戦略物資であった 30 。国内での生産が極めて困難であったため、多くの大名はポルトガル商人などがもたらす輸入品に頼らざるを得なかった 30 。
このような状況下で、国内有数の生産地であった白川郷や隣接する越中五箇山は、極めて高い地政学的な価値を有していた 4 。照蓮寺と内ヶ島氏による共同統治体制は、単なる地方の統治機構に留まらず、この「軍需産業」を管理・独占するための経済共同体としての性格を色濃く持っていた。織田信長との10年にわたる石山合戦において、本願寺勢が数千挺ともいわれる鉄砲を駆使して互角に渡り合えた背景には、雑賀衆のような鉄砲傭兵集団の存在に加え、白川郷や五箇山からの安定した火薬供給があったことは想像に難くない 28 。照蓮寺・内ヶ島氏連合は、本願寺教団全体の軍事戦略において、兵站を担う死活的に重要な構成要素だったのである。彼らの力は、門徒の信仰心だけでなく、この戦略物資の生産・供給能力によって強力に裏打ちされていた。
第四章:時代の終焉 ―内ヶ島氏の滅亡と照蓮寺の移転―
一. 織田・豊臣政権の飛騨侵攻と金森長近の台頭
約80年間にわたり続いた照蓮寺と内ヶ島氏による共同統治の時代は、織田信長、そして豊臣秀吉による天下統一事業の進展とともに、大きな転換点を迎える。石山合戦において、照蓮寺・内ヶ島氏連合は本願寺方に与して信長と敵対した 18 。本能寺の変の後、天下統一の覇権を握った秀吉は、天正13年(1585年)、配下の武将・金森長近に飛騨の平定を命じた 18 。越前大野から飛騨へ侵攻した金森軍に対し、当時の内ヶ島氏当主・氏理は抵抗の後に降伏し、秀吉の軍門に下ることで所領の安堵を認められた 15 。これにより、飛騨は中央政権の強力な影響下に置かれることとなった。
二. 天正大地震と帰雲城の埋没:権力構造の劇的な崩壊
内ヶ島氏が金森氏の支配下に入り、新たな秩序が形成されようとしていた矢先、誰も予測し得なかった未曾有の悲劇がこの地を襲う。天正13年11月29日(グレゴリオ暦1586年1月18日)の夜、マグニチュード8クラスと推定される巨大地震、いわゆる天正大地震が発生したのである 6 。この地震により、帰雲城の背後にそびえていた帰雲山が大規模な山体崩壊を起こし、おびただしい量の土石流が、麓にあった帰雲城と300戸以上の家々が軒を連ねる城下町を一瞬にして飲み込んだ 5 。
この時、城では所領安堵を祝う宴が開かれていたとされ、城主・内ヶ島氏理をはじめ、一族郎党、家臣、そして城下町の住民500人以上が、牛馬に至るまで土砂の下に生き埋めとなった 6 。この天災により、120年間にわたって白川郷を支配した内ヶ島氏は、文字通り一夜にして歴史からその姿を消した。この悲劇は、飛騨における権力構造に巨大な空白を生み出し、金森長近による完全な掌握を決定づけることになった。
三. 金森長近の合理的統治と「城下の論理」による照蓮寺の再配置
内ヶ島氏の滅亡によって飛騨全域の支配権を確立した金森長近は、新たな国主として、近世的な論理に基づいた国づくりに着手した。彼が導入したのは、宗教勢力を巧みに統治機構に組み込み、城下町を中心とした集権的な支配体制を構築する手法であった。照蓮寺の高山移転は、この長近の合理的かつ計算された統治政策を象徴する出来事であった。
長近は、飛騨入国の前に越前大野の領主を務めており、そこで大規模な城下町建設を経験していた。彼の都市計画の特徴は、城下町の防衛ラインとして、また有事の際の拠点として、寺院を戦略的に配置することにあった 35 。高山においても、彼はこの手法を踏襲し、碁盤目状の町割りを整備する中で、寺町を計画的に配置した 34 。
照蓮寺の移転は、単なる優遇や懐柔策ではなかった。長近は、照蓮寺が持つ広範な門徒組織の掌握力と、その経済力に注目した。彼は照蓮寺と起請文を交わして協力関係を確約させると、天正16年(1588年)、白川郷中野にあった寺を、自身の居城である高山城の城下へと移転させたのである 7 。この移転には二重の目的があった。第一に、絶大な影響力を持つ照蓮寺を城下に置くことで、領民支配を円滑に進めること。第二に、堅固な寺院建築を城下の防御拠点の一つとして活用することであった。これにより、照蓮寺は白川郷という「国人領主と寺院が共存する中世的空間」から、高山という「大名権力の下に寺社が整然と組み込まれた近世的空間」へと、その立ち位置を大きく変えることになった。それは、一個の寺院の移転に留まらず、飛騨という地域が中世から近世へと移行したことを示す、画期的な出来事であった。
結論:照蓮寺明誓とその一族が残した歴史的遺産
照蓮寺八世住職・明誓。彼自身の行動に関する記録は少ないが、彼の時代とその子孫の動向は、戦国期飛騨の歴史に決定的な影響を与えた。明誓の時代に胚胎した「武」への傾斜は、長男・教信の代に在地領主・内ヶ島氏との全面衝突を引き起こし、旧来の正蓮寺を一度は灰燼に帰せしめた。しかし、その瓦礫の中から、次男・明教の子である明心が成し遂げた和睦と「照蓮寺」としての再興は、在地領主と宗教勢力が相互補完的に地域を支配するという、戦国期としては稀有な共同統治体制を白川郷に生み出した。この体制の下で約80年間の安定期が築かれ、その間に育まれた煙硝生産という独自の経済基盤は、白川郷の地政学的な特異性を決定づけた。
この80年間の歴史は、天正大地震という天災、すなわち歴史の「偶然」によって、余りにも劇的な終焉を迎える。内ヶ島氏の滅亡という権力の空白は、金森長近による近世的な支配体制への移行を加速させた。照蓮寺は、この歴史の大きな転換の波に乗り、白川郷の一地域寺院から、高山藩の城下で重要な位置を占める大寺院へとその姿を変貌させていったのである。
本報告の出発点であった照蓮寺明誓は、結果として、自らが意図することなく、飛騨の宗教勢力が中世的な独立性を失い、近世的な大名権力に組み込まれていく大きな歴史の分水嶺に立った人物として記憶されるべきである。彼の物語は、一人の僧侶とその一族の運命を通して、戦国乱世から天下統一、そして近世社会の到来へと至る、日本の社会構造のダイナミックな変革を鮮やかに映し出している。
引用文献
- 勝蓮寺_(上越市)とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8B%9D%E8%93%AE%E5%AF%BA_%28%E4%B8%8A%E8%B6%8A%E5%B8%82%29
- 眞蓮寺 - 高山市/岐阜県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/106157
- 照蓮寺 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/information/%E7%85%A7%E8%93%AE%E5%AF%BA/
- 白川郷の歴史 https://panoramahida.iza-yoi.net/shirakawagorekishi.html
- 幻の帰雲城/白川郷 - 白川村役場 https://www.vill.shirakawa.lg.jp/1228.htm
- 帰雲城と内ケ嶋氏 - 浄土真宗 正信寺 https://shoshinji.jp/kobore/kobore6.php
- 照蓮寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A7%E8%93%AE%E5%AF%BA
- 高山別院照蓮寺(たかやまべついんしようれんじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%88%A5%E9%99%A2%E7%85%A7%E8%93%AE%E5%AF%BA-3061875
- 白布をかぶって長刀で武装…「僧兵」とは何者だったのか?その由来と役割を探る - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/186139
- 権力に抗した武装僧侶 僧兵 - 実はぜんぶ三重人(みえびと)なんです https://www.miebito.jp/sohei.php
- 延暦寺の焼き打ち http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%94%E3%80%8F.pdf
- 強大な経済力・文化力を持つ寺社 中世の主役は「寺社」だ! - 京都府教育委員会 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_18.pdf
- 信長史上最凶事件!比叡山延暦寺焼き討ちに大義はあったのか? https://kyotolove.kyoto/I0000184/
- 帰雲城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B0%E9%9B%B2%E5%9F%8E
- 帰雲城埋没地 - 大地震で消滅した城と一族の奇談 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/gifu/kiun.html
- 飛騨一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86
- 内ヶ島氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E3%83%B6%E5%B3%B6%E6%B0%8F
- 内ヶ島氏理 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UchigashimaUjisato.html
- 飛騨高山の基礎を築いた金森長近公 https://www.hidatakayama.or.jp/kanamori_nagachika500
- 真宗大谷派高山別院照蓮寺の地域文化史的存在意義 - 一般財団法人 飛騨高山大学連携センター https://www.renkei-center.jp/pdf/society/slidedata/20221210-06.pdf
- 飛騨 帰雲城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hida/kaerikumo-jyo/
- 武家家伝_内島(内ケ嶋)氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/utizima.html
- 物語飛騨の歴史(上) https://panoramahida.iza-yoi.net/monogatarihidarekishimukashi.html
- 内ヶ嶋氏と照蓮寺 https://kaerigumo.jimdofree.com/%E5%86%85%E3%83%B6%E5%B6%8B%E6%B0%8F%E3%82%92%E6%96%AC%E3%82%8B/%E5%86%85%E3%83%B6%E5%B6%8B%E6%B0%8F%E3%81%A8%E7%85%A7%E8%93%AE%E5%AF%BA/
- 内ヶ島氏理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E3%83%B6%E5%B3%B6%E6%B0%8F%E7%90%86
- 3/10放送分 「飛騨の小さな豪族達2 内ケ島氏と三島将監」 https://hidasaihakken.hida-ch.com/e41733.html
- 【大河ドラマ連動企画 第34話】どうする氏理(内ヶ島氏理)|さちうす - note https://note.com/satius1073/n/n2eb8f06e7524
- 五箇山の塩硝史 - 最高品質・最高生産量・最長期生産 - https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/62372/files/SC-PR-ITAGAKI-E-54.pdf
- 加賀藩の火薬 1.塩硝及び硫黄の生産 https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/29583/files/AA11430153-33-itagaki.pdf
- 韓国への輸出管理を厳正化すべき歴史的な事実 この状況は「鎖国」の本質と似ている (2ページ目) https://president.jp/articles/-/29758?page=2
- 六芒星が頂に~星天に掲げよ! 二つ剣ノ銀杏紋~ - 三国同盟と硝石 https://ncode.syosetu.com/n8249fb/18/
- 浄土真宗と硝煙 - 正信寺 https://shoshinji.jp/kobore/kobore7.php
- 本願寺側から見た信長と鉄砲 https://bishogai.com/msand/miwa/kayakumino.html
- 飛騨高山の歴史 https://panoramahida.iza-yoi.net/takayamarekishi.html
- 四、金森長近大野支配 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/ono-ayumi.files/04kanamorinagachika.pdf
- 金森長近公2️⃣ -史跡めぐり- 恩林寺のブログ https://onrinji.com/kanamori_nagachika-historical/
- 金森可重(かなもり あるしげ) 拙者の履歴書 Vol.257~飛騨に城を築きし生涯 - note https://note.com/digitaljokers/n/n7b8a21dc7886