稗貫稙重
稗貫稙重は陸奥の豪族・稗貫氏の当主。将軍足利義稙から偏諱を受け、葛西・伊達氏との戦略的養子縁組で一族の再興を図ったが、その死後、稗貫氏は求心力を失い、豊臣秀吉の奥州仕置で滅亡した。
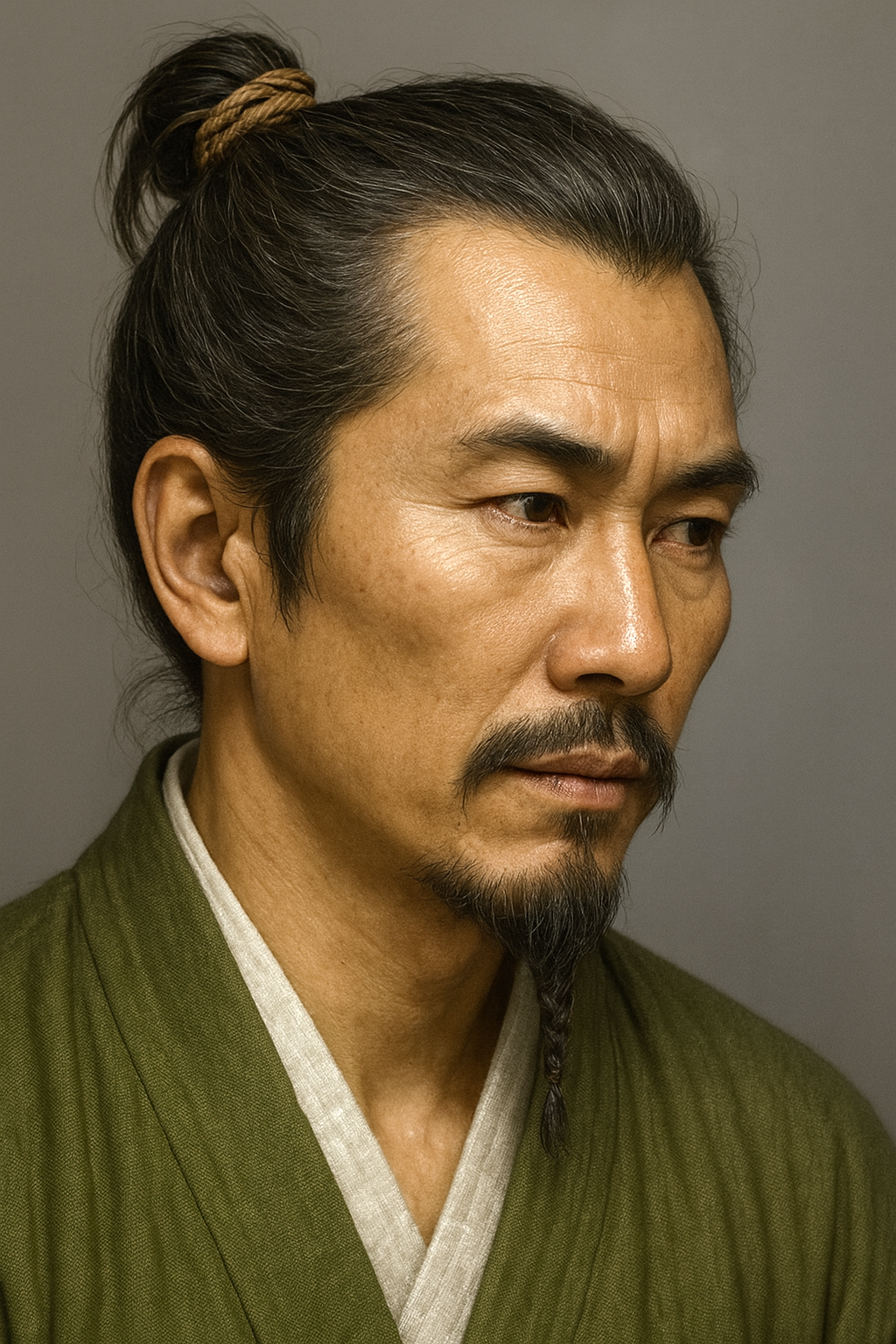
陸奥の豪族・稗貫稙重の実像と稗貫氏の盛衰
序章:歴史の狭間に埋もれた陸奥の将、稗貫稙重
陸奥国の中央、現在の岩手県花巻市一帯にその名を刻んだ豪族、稗貫(ひえぬき)氏。鎌倉時代にその礎を築き、戦国の世を駆け抜け、そして豊臣秀吉による天下統一の奔流の中に消えていった一族である。その歴史の中で、稗貫稙重(ひえぬきたねしげ)という人物は、断片的な記録の中にのみその名をとどめる、いわば「歴史の狭間」に埋もれた存在と言える。しかし、限られた史料を丹念に読み解くとき、彼の生涯は一族の存亡を賭けた壮大な戦略と、その後の凋落を予感させる悲劇性を内包していることが浮かび上がってくる。
本報告書は、この稗貫稙重という一人の武将を基点として、稗貫氏が歩んだ勃興から滅亡に至るまでの軌跡を詳細にたどるものである。稗貫氏に関する史料は、天正十九年(1591年)に本拠地である鳥谷ヶ崎(とやがさき)城が落城した際、その多くが焼失したと伝えられている 1 。敗者として歴史の舞台を去ったがゆえに、その記録は断片的かつ錯綜しており、後世に編纂された系図においても異同が見られるのが実情である 2 。本報告書では、この「記録の不確かさ」そのものを、稗貫氏が辿った過酷な運命の証左として捉え、慎重な史料批判のもと、稙重の実像と一族の盛衰を立体的に再構築することを試みたい。
第一章:稙重以前の稗貫氏 ― 栄光と挫折の軌跡
稗貫稙重という人物を理解するためには、まず彼が背負っていた一族の歴史、特にその栄光と、その後の深刻な挫折について知る必要がある。彼の時代の行動原理は、過去の歴史的経験によって深く規定されていたからである。
1-1. 稗貫氏の出自と確立
稗貫氏の起源は、鎌倉幕府創設期にまで遡る。通説では、源頼朝に仕えた有力御家人・中条氏の一族がその祖とされている 2 。文治五年(1189年)、頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした奥州合戦において戦功を挙げた中条氏の一族が、その恩賞として稗貫郡の地頭職を給され、この地に土着したことが稗貫氏の始まりとされる 2 。この事実は、稗貫氏が鎌倉幕府という中央権力によってその支配の正統性を公的に認められた、由緒ある家柄であったことを示している。彼らは在地領主として着実に力を蓄え、稗貫郡における支配体制を盤石なものにしていった。
1-2. 南北朝の動乱と勢力拡大
十四世紀、日本全土を巻き込んだ南北朝の動乱において、稗貫氏はその存在感を一層高める。当初は、奥州に下向した北畠顕家を擁する南朝方として活動した記録が残る 2 。しかし、戦局が北朝優位に傾き、足利幕府が奥州探題として斯波氏を派遣すると、稗貫氏は時流を読み、北朝方へと巧みに転身した 4 。この政治的転換は、南朝方の拠点であった北の南部氏との間に深刻な対立を生むことになったが、結果として奥州探題斯波氏の権威を背景に、周辺豪族との抗争を繰り広げながら自らの勢力基盤を固めていくことに成功した。この時代の変転に柔軟に対応した経験が、稗貫氏の武門としての名声を高め、その後の発展の礎となったのである。
1-3. 永享の乱と決定的敗北 ― 凋落の序曲
しかし、室町時代中期に発生したある事件が、稗貫氏の運命に暗い影を落とすことになる。永享七年(1435年)、隣接する和賀郡の有力豪族・和賀氏において内乱が勃発した。この機に乗じ、稗貫氏は和賀氏の分家である須々孫(煤孫)氏に与し、惣領家の居城である飯豊城を攻撃したのである 4 。これは勢力拡大を狙った軍事介入であったが、致命的な誤算があった。
和賀惣領家は、当時、北奥羽に強大な勢力を誇っていた三戸南部氏の当主・南部守行に救援を要請した。守行はこれに応じ、三万と号する大軍を率いて和賀・稗貫の地に介入した 2 。南部氏という巨大勢力の出現により、戦況は一変する。稗貫氏は果敢に抗戦したものの、圧倒的な兵力差の前になすすべもなく、翌永享八年(1436年)には本拠地に近い寺林城や台城といった重要拠点を次々と攻略された 2 。万策尽きた稗貫氏は、南部氏の軍門に降るという屈辱的な形で和議を結ばざるを得なかった。
この「永享の敗北」は、稗貫氏の歴史における重大な転換点であった。単なる一戦の敗北ではなく、軍事的に南部氏への従属を強いられたことを意味する。これにより、稗貫氏は自立した領主としての威信と実力を大きく損ない、常に北からの南部氏の圧力を意識せざるを得ない、脆弱な立場に追い込まれた。この過去のトラウマこそが、後代の当主である稗貫稙重の時代の行動を理解する上で、不可欠な前提条件となるのである。
第二章:稗貫稙重の時代 ― 将軍家との結びつきと存続への模索
永享の敗北から数十年後、一族が凋落の淵に沈む中で当主となったのが稗貫稙重である。彼は、失われた権威と実力を回復すべく、地方の力学に留まらない、高度な政治戦略を展開した。
2-1. 稗貫稙重の登場と活動年代の特定
稗貫稙重は、史料において「大和守」を称し、父は稗貫為隆とされる人物である 7 。彼の生没年は不明であるが、その活動時期は彼の名前に秘められた政治的背景から、極めて高い精度で特定することができる。
彼の諱(いみな)である「稙」の字は、当時の武将の名前として一般的なものではない。この一字は、室町幕府第十代将軍・足利義稙(よし たね )に由来するものである可能性が極めて高い。足利義稙は、二度にわたる在職期間(一度目:1490年~1493年、二度目:1508年~1521年)において、自らの権威を示すため、全国の多くの大名や国人に自身の諱の一字である「稙」の字を与える「偏諱(へんき)」を授与している 7 。偏諱は、主君と家臣の間の強固な結びつきを可視化する重要な政治儀礼であった。
この事実から、稗貫稙重は、陸奥の片田舎にありながらも、京都の室町幕府、特に将軍・義稙と直接的な関係を構築し、その権威を借り受けることに成功した人物であったと推測される。これは、永享の敗北以降に低下した稗貫氏の権威を補強し、南部氏をはじめとする周辺の強敵に対抗するための、卓越した外交戦略であった。彼は、地域的な力関係の劣勢を、中央の最高権威という「飛び道具」を用いることで覆そうとしたのである。これにより、稗貫稙重の主要な活動時期は、十五世紀末から十六世紀前半にかけての、足利義稙の治世と重なる時代であったと明確に位置づけることができる。
2-2. 後継者問題と戦略的養子縁組
中央との結びつきによって権威の回復を図った稙重であったが、彼には一族の存続を揺るがす深刻な問題があった。彼には実子がいなかったのである 7 。跡継ぎの不在は、一族の断絶、ひいては滅亡に直結する。この危機に際し、稙重が下した決断は、彼の戦略家としての一面を如実に物語っている。
彼は、後継者として、南方に一大勢力を築いていた葛西氏の第十三代当主・葛西宗清の次男・晴家を養子として迎え入れた 1 。この養子縁組は、単なる血筋の維持を目的としたものではなく、幾重にも張り巡らされた戦略的な意図を持っていた。
第一に、南の大勢力である葛西氏との間に、極めて強固な軍事同盟を構築する意味があった。これにより、北の南部氏からの圧力を直接的に牽制することが可能となる。
第二に、この養子縁組は、さらに大きな勢力との連携をもたらした。養子・晴家の実父である葛西宗清は、もともと伊達氏の第十三代当主・伊達成宗の次男であり、葛西氏へ養子に入った人物であった 13 。つまり、稗貫氏の後継者となった晴家は、奥州で最も勢力を伸張しつつあった伊達家の血を引く人物でもあったのだ。これにより、稗貫氏は葛西氏のみならず、その背後にいる伊達氏とも間接的な同盟関係を結ぶことになり、北の南部氏、西の斯波(大崎)氏に対し、「南の葛西・伊達連合」という強力な防波堤を築くことに成功した。
将軍家からの偏諱という「権威」と、葛西・伊達という「実力」とを結びつける。この二重の戦略こそ、稗貫稙重が描いた一族再興の青写真であった。彼は、権威と実利の両面から、永享の敗北によって失われた一族の威勢を回復しようと試みた、稀代の戦略家であったと言えよう。
第三章:稙重以降の混迷 ― 相次ぐ養子と失われる求心力
稗貫稙重の巧みな戦略は、一時的に稗貫氏に安定をもたらしたかに見えた。しかし、彼の死後、その戦略は形骸化し、逆に一族の結束を蝕む深刻な問題へと変質していく。その根源は、常態化した「外部からの養子」にあった。
【表:稗貫氏の継承と血縁関係(稙重以降)】
|
当主名 |
続柄 |
出自(実家) |
典拠史料 |
備考 |
|
稗貫為隆 |
稙重の父 |
稗貫氏 |
7 |
|
|
稗貫稙重 |
- |
稗貫氏 |
- |
将軍・足利義稙より偏諱。葛西氏から晴家を養子に迎える。 |
|
稗貫晴家 |
稙重の養子 |
葛西氏 |
7 |
実父は葛西宗清。伊達氏の血を引く。 |
|
稗貫輝時 |
晴家の養子 |
斯波氏 |
2 |
高水寺斯波氏か。将軍・足利義輝より偏諱。 |
|
稗貫広忠 |
輝時の養子 |
和賀氏 |
4 |
最後の当主。奥州仕置により改易。 |
3-1. 権威の継承と実態 ― 稗貫輝時の時代
稙重の養子となった葛西氏出身の晴家であったが、彼にもまた実子はいなかった。そのため、晴家の後継者として、今度は紫波郡を拠点とする高水寺斯波氏から輝時が養子として迎えられた 11 。
この輝時は、天文二十四年(1555年)に上洛して将軍・足利義輝に謁見し、黄金十両を献上した上で、その諱から「輝」の一字を賜っている 2 。これは明らかに、養祖父にあたる稙重が用いた「中央権威の活用」という成功体験を踏襲しようとした動きである。将軍の権威を借りることで、当主としての正統性を内外に示し、一族をまとめようとしたのであろう。
しかし、この頃の稗貫氏は、南下政策を推し進める三戸南部氏との衝突を繰り返す斯波氏を支援するなど、絶え間ない軍事的緊張状態に置かれていた 2 。将軍の権威はもはや名目的なものとなりつつあり、それだけで地域の力関係を覆すことは困難になっていた。輝時の努力もむなしく、稗貫氏は周辺大名の草刈り場と化し、郡内を支配する一国人領主の地位から脱却することはできなかった。
3-2. 混迷の極み ― 稗貫広忠の登場
輝時の後、稗貫氏の家督はさらに混迷を深める。輝時にも世継ぎがなく、今度は隣接する和賀氏から広忠が養子として当主の座に就いたのである 4 。
稙重の代に始まった戦略的養子縁組は、彼の死後、もはや戦略としての意味を失い、単に血筋を繋ぐためだけの場当たり的な手段と化してしまった。葛西氏、斯波氏、そして和賀氏と、二代、三代にわたって当主の血筋が外部から供給され続けるという異常事態は、稗貫一族と家臣団の間に深刻な亀裂を生じさせた。
当主はもはや稗貫一族の利益を代表する存在ではなく、その出身母体である葛西氏、斯波氏、和賀氏の意向を汲まざるを得ない、傀儡に近い存在と見なされた可能性が高い。これにより、一族の結束力と求心力は致命的に低下した。後世の記録である『稗貫家之次第』の中に、最後の当主・広忠を評して「性闇弱むにして諸臣へ愛なかりかし故、臣下不服」(性格が優柔不断で家臣への恩愛がなかったため、家臣たちは従わなかった)という記述が見られる 5 。これは、広忠個人の資質の問題というよりも、度重なる外部からの当主就任によって引き起こされた、構造的な君臣関係の崩壊、家臣団の離反と不信の表れと解釈すべきであろう。稗貫氏は、天下統一の嵐が吹き荒れる直前、すでに内部から崩壊しつつあったのである。
第四章:終焉の刻 ― 奥州仕置と稗貫氏の滅亡
内部に深刻な問題を抱えながら、稗貫氏は戦国時代の最終局面を迎える。それは、地方の論理が一切通用しない、中央集権化という巨大な時代のうねりであった。
4-1. 運命の決断 ― 小田原不参陣
天正十八年(1590年)、関白豊臣秀吉は天下統一の総仕上げとして、関東の雄・小田原北条氏への征伐軍を起こした。これに際し、秀吉は全国の大名・領主に対し、小田原への参陣を厳命した。これは単なる軍事動員ではなく、秀吉政権への服従を誓う「臣従儀礼」としての意味を持っていた。
しかし、稗貫氏当主・広忠は、南隣の葛西晴信や大崎義隆らと共に、この小田原へ参陣しなかった 14 。その理由は定かではないが、中央の情勢への疎さか、あるいは周辺豪族との牽制関係から領地を離れられなかったのか、いずれにせよこの決断が稗貫氏の運命を決定づけた。秀吉は、参陣しなかった大名を「反逆者」とみなし、容赦のない処分を下した。奥州へ進駐した「奥州仕置軍」によって、稗貫広忠は所領没収・城地追放という最も厳しい処分を受けることになったのである 14 。
4-2. 最後の抵抗 ― 和賀・稗貫一揆
拠点を失い、路頭に迷った稗貫広忠は、同じく改易処分を受けた和賀義忠らと結び、最後の抵抗を試みる。奥州仕置軍が引き上げた隙を突いて、旧領回復を目指す大規模な一揆を蜂起したのである 14 。これは「和賀・稗貫一揆」として知られる。
一揆勢は、旧家臣や新領主の検地に不満を持つ農民らを糾合し、瞬く間に勢力を拡大。和賀氏の旧居城であった二子城を攻略して奪回すると、その勢いのまま、稗貫氏の本拠であった鳥谷ヶ崎城を二千余の兵で包囲した 14 。城内には、仕置軍が残した浅野長政の代官・浅野重吉らがわずかな兵で守るのみであったが、城が天然の要害であったため、一揆勢は攻めあぐねた。
この報を受けた南部信直は、秀吉への忠誠を示す好機と捉え、自ら兵を率いて鳥谷ヶ崎城の救援に駆け付け、一揆勢の包囲を破った。しかし、季節はすでに冬に差し掛かっており、積雪期に城を維持することは困難と判断した南部・浅野勢は、城を放棄して北の三戸城へと撤退した。その結果、鳥谷ヶ崎城も一揆勢の手に落ち、和賀・稗貫の両氏は一時的に旧領の回復に成功した 14 。
4-3. 鎮圧と完全なる滅亡
旧領主たちによる大規模な反乱の報は、天下人・秀吉を激怒させた。翌天正十九年(1591年)、秀吉は甥の豊臣秀次を総大将とし、徳川家康、上杉景勝、前田利家ら日本中の大名を動員した、数十万ともいわれる「奥州再仕置軍」を編成し、奥州へと派遣した 14 。
地方豪族の一揆に対し、国家規模の討伐軍が差し向けられたのである。圧倒的な兵力の前に、和賀・稗貫一揆勢はなすすべもなく鎮圧され、和賀義忠は逃走中に土民に殺害されたと伝わる 14 。稗貫広忠の最期は定かではないが、ここに大名としての稗貫氏は完全に滅亡した。
戦後、一揆の舞台となった和賀・稗貫の両郡は、一揆鎮圧に功のあった南部信直に加増領として与えられた 4 。稗貫氏の本拠であった鳥谷ヶ崎城は「花巻城」と改称され、以降、南部氏の南の拠点として、仙台伊達藩との境界を守る重要な城となったのである 4 。
稗貫氏の滅亡は、小田原不参陣という直接的な原因だけでなく、より構造的な問題を内包していた。彼らは戦国時代を通じて、周辺豪族との水平的な同盟や抗争という、旧来の「国人領主」の論理で行動し続けた。しかし、秀吉の天下統一事業は、そうした地方の論理を一切許容せず、中央の権力者に対する絶対的な服従を求める、全く新しい近世的な政治秩序の到来を意味していた。内部的には求心力を失い、外部的には時代の巨大な地殻変動を読み違えた。この二重の要因が、稗貫氏の滅亡を必然的なものとしたのであった。
終章:稗貫氏のその後と歴史的意義
稗貫一族の流転
天正十九年(1591年)の奥州再仕置をもって、大名としての稗貫氏は歴史の表舞台から完全に姿を消した。しかし、一族が根絶やしにされたわけではない。没落後、一部の一族は、かつて稙重の戦略によって縁を結んだ伊達氏を頼り、仙台藩士として召し抱えられ、その家名を後世に伝えたとされる 2 。江戸時代に編纂された『稗貫家譜』といった記録は、この仙台藩士となった稗貫氏の子孫によって、一族の由緒を後世に残すためにまとめられたものである 1 。
しかし、それらの系図や事跡は曖昧な点が多く、一族の記憶が断絶と混乱の中にあることを物語っている 2 。それは、敗者として歴史を終えた一族が辿る、宿命的な姿でもあった。
総括 ― 稗貫稙重と稗貫氏が物語るもの
本報告書で焦点を当てた稗貫稙重は、一族が凋落の危機に瀕していた時代にあって、将軍家という中央の権威と、葛西・伊達という周辺の実力者との同盟という二つのカードを巧みに駆使し、一族の再興を試みた有能な戦略家であった。彼の構想は、地方の力学に埋没することなく、より広い視野で自らの置かれた状況を打開しようとする、非凡な政治感覚を示している。
しかし、彼の死後、その戦略は後継者たちに正しく理解・継承されなかった。血筋を繋ぐためだけに繰り返された養子縁組は、戦略的意味を失い、逆に一族の結束を内側から蝕む結果を招いた。
最終的に、稗貫氏は戦国時代から近世へと移行する巨大な地殻変動に対応できず、歴史の波に飲み込まれた。その興亡の物語は、中央の政変に翻弄され、強大な隣人に脅かされながらも、必死に一族の存続を模索した数多の地方豪族が辿った運命の典型例と言える。稗貫稙重という、歴史の狭間に埋もれた一人の武将の生涯を深く掘り下げることは、戦国という時代の本質的な厳しさと、そこに生きた人々の苦闘を理解する上で、我々に極めて重要な示唆を与えてくれるのである。
引用文献
- 総じて奥羽仕置研究は、戦国期の領主が豊臣権力を「てこ」に https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1534/files/HirodaiKokushi_137_51.pdf
- 稗貫氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%97%E8%B2%AB%E6%B0%8F
- 稗貫氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A8%97%E8%B2%AB%E6%B0%8F
- 武家家伝_稗貫氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hienuki.html
- 稗貫家之事 - 近世こもんじょ館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/kirokukan/kirokukan_view.cgi?mode=details&code_no=57220
- 領として下向させ、北朝方の勢力拡大を図ったことに始ま るといわれる。奥州斯波氏は足利泰 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/34/34367/63039_3_%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E5%88%86%E5%B8%83%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
- 稗貫種重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%97%E8%B2%AB%E7%A8%AE%E9%87%8D
- 足利義稙(アシカガヨシタネ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99-14301
- 足利義稙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99
- 足利義稙とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99
- F824 伊達為家 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F824.html
- 稗貫晴家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%97%E8%B2%AB%E6%99%B4%E5%AE%B6
- 葛西宗清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E5%AE%97%E6%B8%85
- 和賀・稗貫一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%B3%80%E3%83%BB%E7%A8%97%E8%B2%AB%E4%B8%80%E6%8F%86
- 大條実頼(着座大條家第一世)【中】|(伊達)大條家 - note https://note.com/oeda_date/n/n1b9ae068f593
- 花巻城 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/094/1369353001034.pdf
- 奥州仕置(2/2)豊臣秀吉が東北平定、波紋を呼んだ - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/322/2/
- 花巻城跡 | 観る【花巻観光協会公式サイト】 https://www.kanko-hanamaki.ne.jp/spot/article.php?p=159