簗田藤左衛門
簗田藤左衛門は戦国から江戸初期の会津で活躍した豪商。支配者交代を乗り越え、経済を掌握。塩の輸入と特産品輸出の物流網を築き、その地位は子孫に継承された。
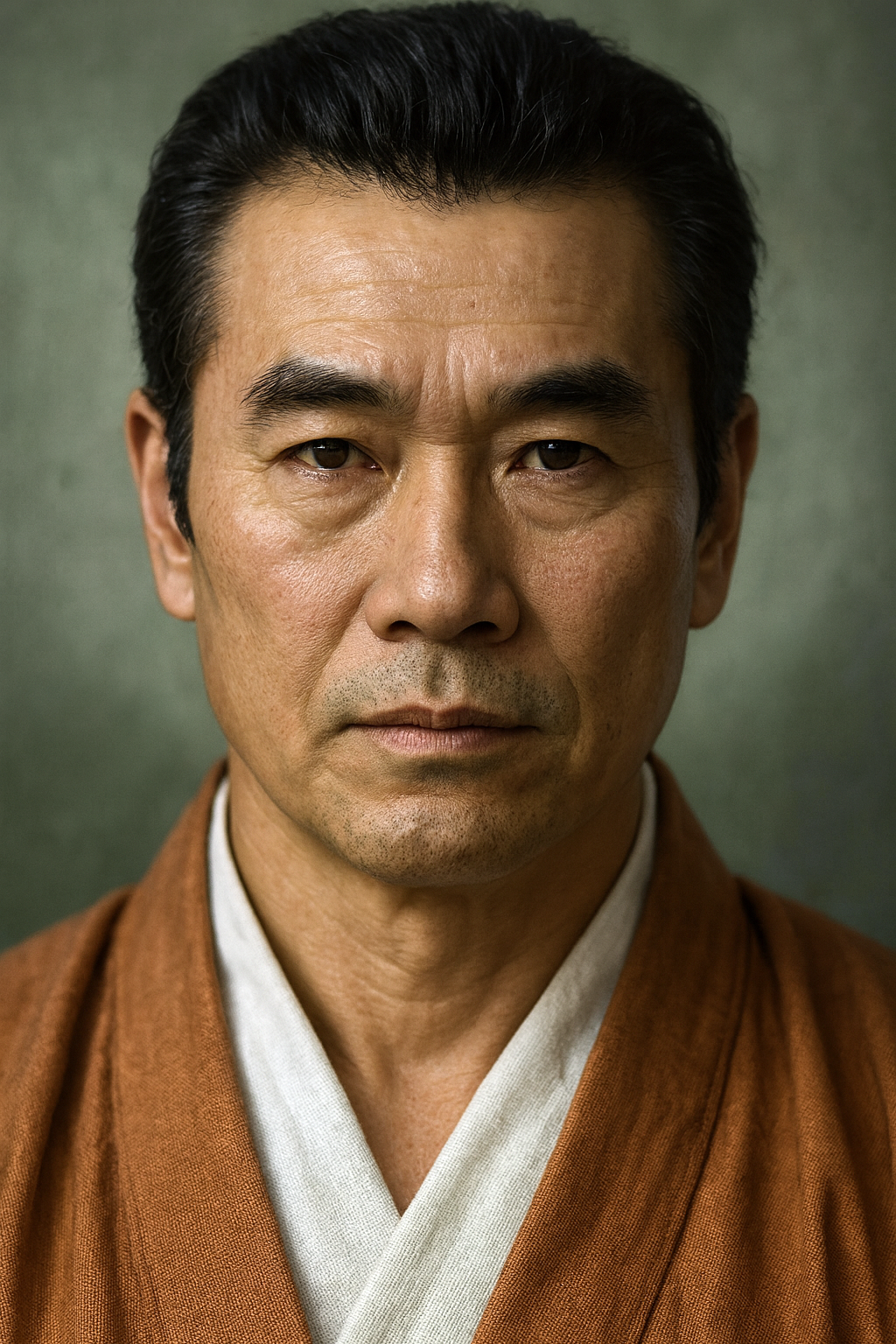
乱世会津の経済を掌握した男:簗田藤左衛門の実像
序論:乱世の会津に屹立した経済的巨星
本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて、会津の地で絶大な影響力を誇った商人、簗田藤左衛門(やなだ とうざえもん、生年不詳 - 元和6年/1620年)の生涯と、その歴史的役割を徹底的に解明することを目的とする 1 。彼は単に富を蓄積した一介の豪商ではない。戦国大名蘆名氏の経済政策を体現する代理人として台頭し、伊達政宗、蒲生氏郷といった時の権力者が次々と会津を支配する激動の時代を乗り越え、その特権的地位を維持、発展させた稀有な人物である。彼の生涯は、戦国から近世へと移行する社会のダイナミズムを、経済という側面から鮮やかに映し出している。
利用者より提示された「塩釜の商人」という伝承は、藤左衛門を理解する上で極めて示唆に富む謎である 2 。史料が明確に示す彼の本拠地は会津であり、蘆名家の御用商人として活動していたことは疑いようがない 1 。この「会津」と「塩釜」という二つの地名の間に横たわる乖離は、単なる情報の錯綜や誤伝として片付けるべきではない。むしろ、この謎を解き明かすことこそが、藤左衛門が構築した広大かつ複眼的な商業ネットワークの全貌を理解するための鍵となる。
本報告書では、簗田藤左衛門の実像に迫るため、以下の四つの視点から多角的な分析を行う。第一に、彼が歴史の表舞台に登場する背景となった蘆名氏の領国経営と、彼が「商人司」としていかにして特権的地位を築いたかを検証する。第二に、蘆名氏滅亡後の支配者交代の荒波の中、彼がいかなる生存戦略をもって自らの地位を維持したのかを追跡する。第三に、「塩釜の商人」の謎を解くべく、彼が掌握した具体的な商業ネットワークを物流の観点から再構築する。そして最後に、藤左衛門個人に留まらず、彼が築いた遺産が後世の会津藩にいかに継承され、どのような歴史的意義を持ったのかを考察する。これらの分析を通じて、一地方商人の枠を超えた「政商」簗田藤左衛門の姿を立体的に浮かび上がらせることを目指す。
第一章:蘆名王国と商人司・簗田藤左衛門の誕生
簗田藤左衛門が歴史の表舞台に登場し、その権勢の礎を築いた背景には、戦国大名蘆名氏、特にその最盛期を現出した蘆名盛氏による先進的な領国経営が存在した。藤左衛門の台頭は個人の商才のみによるものではなく、会津という土地の特性を最大限に活用しようとした領主の国家構想と密接に結びついた、必然的な帰結であった。
1-1. 会津の地政学的・経済的環境
会津盆地は、四方を山々に囲まれた内陸の地でありながら、古来より交通の要衝としての役割を担ってきた。西は越後(新潟県)を経て日本海へ、南は下野国(栃木県)を経て関東平野へ、そして東は仙道(中通り)や海道(浜通り)へと通じる街道が交差し、人、物資、情報が絶えず行き交う結節点であった 4 。この地理的条件は、会津を軍事戦略上の要地であると同時に、商業的にも大きな可能性を秘めた土地たらしめていた。
また、会津は豊かな自然資源に恵まれていた。特に、蘆名氏の時代から特産品として知られていたのが漆である 5 。会津漆器の原料となる良質な漆は、領外へ移出される重要な商品であった。さらに、漆の木の実から採取される蝋も、灯火や武具の手入れ、工芸品の材料として需要が高く、政宗の時代には既に重要な交易品として認識されていた 6 。これらに加え、盆地で生産される豊富な米は、会津の経済を支える根幹をなしていた。これらの産品は、他国との交易において会津の富の源泉となり、その流通を掌握することは、領国経済を支配することと同義であった。
1-2. 蘆名盛氏の領国経営と経済の掌握
簗田藤左衛門を抜擢した蘆名盛氏(1521-1580)は、会津蘆名氏第16代当主であり、その治世に一族の勢力を最大にまで伸張させた英主である 4 。彼は伊達氏からの自立を果たし、周辺の諸豪族を次々と従え、南奥州に一大勢力圏を築き上げた 7 。盛氏の卓越性は、その軍事的手腕に留まらない。彼は領国の富国強兵を実現するため、内政、特に経済基盤の強化に並々ならぬ情熱を注いだ。
盛氏の経済政策の柱は、領国経済を大名が直接的にコントロールし、その利益を確実に吸い上げる体制を構築することにあった。その具体的な施策として、領内における金山の開発に力を入れると同時に、流通体制の整備に着手した 4 。当時の戦国大名の多くが、領内の経済活動を円滑化し、財源を確保するために、特定の商人を「御用商人」として取り立て、様々な特権を与えることで経済政策を代行させていた。例えば、武田信玄にとっての酒田氏、上杉謙信にとっての蔵田氏などがその代表例である 8 。盛氏もまた、この手法を会津で実践し、その実行者として簗田藤左衛門に白羽の矢を立てたのである。
1-3. 「商人司」への抜擢とその権能
蘆名盛氏は、簗田藤左衛門を単なる御用商人の一人としてではなく、「商人司(しょうにんつかさ)」、すなわち商人全体の頭領に任命した 1 。これは、領内の商業活動全般を統括する、半ば官僚的な性格を帯びた極めて重要な役職であった。先祖代々蘆名家の庇護を受けてきたとされる藤左衛門は、この抜擢により、会津の経済界に君臨する特権的な地位を確立したのである 1 。
「商人司」としての藤左衛門に与えられた権能は、多岐にわたり、かつ絶大なものであった。
第一に、特産品の独占販売権である。前述の漆や蝋といった会津の主要産品の領外への販売を一手に行う権利を認められていた 1。これは、領国の最も重要な収入源を直接管理することを意味した。
第二に、他国商人の統制権である。会津の市場に出入りする他領の商人たちを管理し、その商業活動を監督する権限を有していた 1。これにより、領内の市場価格の安定や、不公正な取引の防止を図ることができた。
第三に、徴税の請負である。領内を往来する商人から課される諸税の徴収を、蘆名氏に代わって行う権利を持っていた 1。これは、領主の財政に直接関与する、極めて信頼された立場であったことを示している。
さらに、伊達政宗の時代には明文化される関所通行手形の発行権も、この頃から実質的に有していた可能性が高い 3。これは、領内の物流そのものを管理・統制する権限であり、彼の支配が会津経済の隅々にまで及んでいたことを物語っている。
藤左衛門の台頭は、単に彼個人の商才や蘆名氏との旧来の関係性だけでは説明できない。それは、会津という領国を一つの独立した経済圏として確立し、その富を中央集権的に掌握しようとした蘆名盛氏の壮大な「国家」構想の産物であった。盛氏は、複雑化する商業・流通ネットワークを効率的に管理し、安定した税収を確保するための専門家を必要としていた。武士階級にはないその能力を、最も有能な商人に絶大な権限を与えることで補い、自らの経済政策の「代理人」としたのである。簗田藤左衛門は、この盛氏の構想を実現するための最適な「装置」として選ばれた存在であった。彼の権力は盛氏の権力と表裏一体であり、個人的な寵愛を超えた、極めて合理的な政治判断の結果であった。したがって、藤左衛門の初期の活動を理解するには、彼を蘆名氏の経済政策を体現する「生きたインフラ」として捉える視点が不可欠なのである。
第二章:権力の奔流を乗りこなす生存戦略
蘆名氏の庇護の下で絶対的な地位を築いた簗田藤左衛門であったが、その権勢の真価が問われたのは、蘆名氏が滅亡し、会津の支配者が目まぐるしく交代する激動の時代においてであった。彼は、各時代の権力者の性格や政策を的確に見極め、自らの役割を巧みに変質させることで、その地位を維持するだけでなく、むしろより強固なものへと変えていった。
2-1. 伊達政宗の支配と特権の安堵
天正17年(1589年)、摺上原の戦いで蘆名義広は伊達政宗に大敗し、ここに会津の名門蘆名氏は事実上滅亡する 9 。勝利した政宗は黒川城(後の会津若松城)に入り、会津は新たな支配者を迎えることとなった。この政権交代は、旧体制の重鎮であった藤左衛門にとって、その地位と財産を失いかねない最大の危機であったはずである。
しかし、驚くべきことに、新支配者である政宗は藤左衛門の特権を剥奪するどころか、その支配権をそのまま承認したのである 1 。さらに、新たに関所の通行手形の発行権を与えるなど、その地位を公式に追認した 3 。この政宗の判断は、単なる温情によるものではなく、極めて現実的な計算に基づいていた。
第一に、 経済的合理性 である。政宗自身、自らの領国である米沢や仙台において、塩や米の産業振興、運河の整備など、経済基盤の強化に熱心な大名であった 11 。彼にとって、征服したばかりの会津の経済を混乱させることは得策ではなかった。既に確立され、円滑に機能している簗田藤左衛門の流通・徴税システムをそのまま活用することこそ、会津の富を最も効率的に掌握する道であった。藤左衛門は、会津経済という複雑な機械を動かすための、代替不可能な「管理者」だったのである 6 。
第二に、財政的必要性である。伊達家は、度重なる軍事行動や京都での交際費などにより、常に財政難に苦しんでいた実情がある 12。会津からの安定した税収は、政宗にとって旱天の慈雨にも等しいものであった。藤左衛門が構築した徴税システムは、政宗にとって即座に利用可能な財源確保の仕組みであり、これを手放す理由はなかった。
2-2. 蒲生氏郷の改革と「検断」への移行
政宗による会津支配は、わずか1年あまりで終わりを告げる。天正18年(1590年)、豊臣秀吉による奥州仕置の結果、政宗は会津を召し上げられ、代わって蒲生氏郷が42万石(後に加増され92万石)の領主として入府した 10 。氏郷は、織田信長や豊臣秀吉の下で近代的な領国経営を学んだ先進的な武将であり、彼の統治は会津に抜本的な変革をもたらした。
氏郷は、黒川を「若松」と改名し、七層の天守閣を持つ壮麗な城郭を築くとともに、城下町の大規模な改造に着手した。武家屋敷と町人地を明確に分離し、碁盤の目状の町割りを行い、要所に寺社を配置するなど、防御機能と経済機能を両立させた近世的な城下町を設計した 14 。さらに、旧領の近江日野や伊勢松坂から自らの息のかかった商人や職人を多数呼び寄せ、楽市楽座を導入して商業の活性化を図った 15 。
この氏郷による「上からの改革」は、旧来の土着勢力である藤左衛門にとって、政宗の支配以上に深刻な危機であった可能性が高い。氏郷が自派の商人を重用し、既存の商業秩序を刷新しようとした場合、商人司としての藤左衛門の地位は根本から覆されかねなかったからである。しかし、藤左衛門はここでも驚くべき適応能力を発揮する。
氏郷は、藤左衛門を排除する道を選ばなかった。むしろ、彼が築き上げた町方支配の仕組みを温存し、自らの新しい都市計画の中に正式な役職として組み込んだのである 14 。それが「検断(けんだん)」であった。検断とは、城下町の町人地における行政、警察、そして軽微な裁判権を統括する町役人の筆頭であり、領主によって任命される公式な役職であった 17 。藤左衛門は、蘆名時代のような領主との個人的な繋がりを基盤とする特権商人「商人司」から、近世的な都市行政の一翼を担う公式な「町役人」へと、その役割と立場を変質させることで、新たな支配体制の中に自らの場所を確保したのである。
2-3. 支配者交代の荒波を越えて
氏郷が文禄4年(1595年)に40歳の若さで急逝した後も、会津の支配者は上杉景勝、そして関ヶ原の戦い後には再び蒲生氏(秀行)と、目まぐるしく交代した。しかし、簗田藤左衛門(および彼の一族)は、この権力の奔流の中にあっても、検断としての地位を揺るがせることなく維持し続けた。藤左衛門自身は、蒲生秀行の治世下である元和6年(1620年)にその生涯を終えるが、彼が築いた盤石な地位は一族に継承されていくことになる 1 。
彼の生涯は、支配者が交代するたびに、その統治方針に適応し、自らの価値を証明し続けた稀有な生存の記録である。以下の表は、会津の支配者の変遷と、それに対応する簗田藤左衛門の地位の変化をまとめたものである。
【表1:会津支配者の変遷と簗田藤左衛門の地位】
|
時代区分 |
時期(西暦) |
会津支配者 |
主要な出来事・政策 |
簗田藤左衛門の地位・役割の変化 |
典拠 |
|
戦国時代 |
16世紀中頃 |
蘆名盛氏 |
領国経済の掌握、金山開発 |
商人司 に任命され、特権的地位を確立 |
1 |
|
〃 |
~1589年 |
蘆名義広 |
蘆名氏の衰退・滅亡 |
既存の特権を維持 |
9 |
|
安土桃山時代 |
1589~1590年 |
伊達政宗 |
会津征服、経済基盤の維持 |
支配権を安堵され、 関所手形発行権 などを追認される |
1 |
|
〃 |
1590~1595年 |
蒲生氏郷 |
城下町の大改革、楽市楽座 |
検断 として新都市行政に組み込まれ、地位を制度化 |
10 |
|
〃 |
1598~1601年 |
上杉景勝 |
関ヶ原の戦い |
地位を維持 |
- |
|
江戸時代初期 |
1601~1620年 |
蒲生秀行 |
藩体制の確立 |
検断としての地位を維持し、1620年に死去 |
1 |
この表が示すように、藤左衛門は単に幸運に恵まれたわけではない。彼は、各政権の性格を冷静に分析し、蘆名氏の下では「特権商人」として、伊達氏の下では「経済システムの管理者」として、そして蒲生氏の下では「近世的町役人」として、自らの役割を巧みに変化させていった。この卓越した政治感覚と適応能力こそが、彼が激動の時代を乗り越え、その地位を不動のものとした最大の要因であった。
第三章:「二つの川」が拓いた商業ネットワーク
簗田藤左衛門の権勢の源泉は、彼が構築し、支配した広大な商業ネットワークにあった。その実態を解明する鍵は、冒頭で提示した「塩釜の商人」という謎めいた伝承にある。この伝承は、単なる地名の混同ではなく、藤左衛門が会津盆地を起点として、西の日本海と東の太平洋、双方に繋がる二つの大河川を駆使した、壮大な物流システムを掌握していたことの証左と解釈することができる。
3-1. 内陸の富:会津の主要交易品
藤左衛門が取り扱った会津の産品は、領国の富そのものであった。彼の商業活動の根幹をなしたのは、会津漆器の原料となる高品質な漆であり、その漆の木の実から採れる蝋であった 5 。これらは軽量でありながら付加価値が高く、遠隔地への輸送に適した商品であった。また、会津藩の財政基盤であり、年貢として集められる膨大な量の米も、彼の流通網を通じて領外へ販売され、莫大な利益を生み出していたと考えられる。これらの商品をいかに効率よく、かつ広範囲に販売するか。それが藤左衛門の商業戦略の核心であった。
3-2. 西へ:阿賀川舟運と日本海ルート
会津と外部世界を結ぶ最も重要な物流路は、西流して日本海に注ぐ阿賀川(下流では阿賀野川)を利用した舟運であった 19 。江戸時代には、陸運に比べて舟運の輸送コストは4分の1から5分の1程度と格段に安く、大量輸送には不可欠な手段であった 19 。この阿賀川舟運の最大の目的は、日本海側から
塩 を会津へ輸入することにあった 20 。四方を山に囲まれた会津にとって、塩は人間の生命維持に不可欠であるだけでなく、食料保存などにも用いられる戦略物資であった。この「西入塩」と呼ばれる塩の安定供給ルートを掌握することは、会津の経済、ひいては領民の生活の生命線を握ることに等しかった。
この舟運の会津側の拠点となったのが、その名の通り「塩川」という町であった 22 。越後の新潟湊から阿賀川を遡ってきた塩は、ここで荷揚げされ、会津各地へと陸送された 21 。商人司として会津の物流を統括していた藤左衛門が、この塩の流通に深く関与していたことは想像に難くない。彼の活動拠点である会津若松と塩川は近接しており、彼がこの日本海ルートを完全に掌握していたことは確実視される。
3-3. 東へ:阿武隈川水系と太平洋ルート
一方で、これまであまり注目されてこなかったのが、太平洋側へと通じる東のルートである。会津盆地から東へ山を越えると、阿武隈川の上流域に達する。阿武隈川は、福島県中通りを北上し、宮城県で太平洋に注ぐ東北第二の大河であり、古くから舟運が盛んであった 24 。江戸時代前期には、米沢藩が領地であった信達地方(福島盆地)の余剰米を江戸へ輸送するため、阿武隈川の舟運開発に多額の投資を行った記録が残っている 26 。
この事実は、会津の産品、特に米や漆、蝋といった商品を、阿武隈川水系を通じて太平洋岸へ輸送するルートが存在した可能性を強く示唆する。会津から奥州街道などを通じて阿武隈川の河岸まで陸送し、そこから舟に積み替えて河口の荒浜(宮城県亘理町)まで下る。荒浜からは、伊達政宗が整備した貞山運河などを利用して、奥州一の宮・塩竈神社の門前町であり、古くからの良港であった塩釜湊へ物資を運ぶことは十分に可能であった 27 。このルートは、人口が密集し、大消費地である仙道地方や、さらには江戸市場へと会津の産物を直接結びつける、極めて重要な輸出路となり得た。
「塩釜の商人」伝説の再解釈
ここで、「塩釜の商人」という伝承が持つ意味が、新たな光を帯びてくる。この言葉は、単に藤左衛門の出身地や、塩川と塩釜という地名の混同から生じたものではない。それは、簗田藤左衛門が構築した商業ネットワークの広大さと、その戦略性を象徴する言葉として捉えるべきである。
すなわち、藤左衛門は、西の阿賀川舟運を掌握して生活必需品である**「塩を内に入れる(輸入)」 ことで領内の経済基盤を固め、同時に、東の阿武隈川水系を利用して会津の特産品を 「外に売り出す(輸出)」**ことで莫大な利益を上げるという、複眼的な物流戦略を展開していたのではないだろうか。西のルートが会津の生命線を守る「守り」の交易であるとすれば、東のルートは積極的に利益を追求する「攻め」の交易であった。
この壮大な物流システムの管理者であった藤左衛門の活動は、当然、太平洋側の拠点であった塩釜の商人たちにも広く知られていたはずである。彼らにとって、会津の富を一手に握る藤左衛門は、「会津の商人」であると同時に、自分たちの取引相手として最も重要な「塩釜(の市場を動かす)商人」でもあった。この太平洋側からの視点が、「簗田藤左衛門は塩釜の商人」という伝承となって、断片的に後世に伝えられた。このように解釈することで、史実と伝承の間の矛盾は解消され、藤左衛門の商人としての真のスケールが明らかになるのである。
第四章:簗田家の遺産と近世会津への継承
簗田藤左衛門の歴史的意義は、彼一代の成功に留まらない。彼が築き上げた経済的・社会的な地位は、一族によって継承され、会津の近世社会に深く根付いていく。藤左衛門の真の功績は、富の蓄積以上に、戦国時代の領主との個人的な繋がりを基盤とする不安定な特権を、近世社会の制度に組み込まれた世襲の役職へと昇華させた点にある。
4-1. 一族の出自に関する考察
会津の商人・簗田氏のルーツを直接的に示す史料は現存しない。しかし、「簗田」という姓は、関東において室町時代に古河公方の筆頭宿老として絶大な権勢を誇った名門武家・簗田氏を想起させる 28 。この関東簗田氏は、下総国関宿城を本拠とし、関東の政治史に大きな足跡を残した一族である 30 。
会津の簗田藤左衛門と、この関東の名門一族との間に直接的な系譜関係があったかを証明することはできない。しかし、全く無関係と断じるのも早計である。簗田氏のルーツを巡る一説には、足利氏の庶流である斯波氏の譜代家臣となり、奥州斯波氏に仕えて東北地方に下った流れが存在した可能性が指摘されている 28 。この奥州に土着した簗田氏の一派が、何らかの経緯で会津に移り住み、武士から商人へと転身した可能性は十分に考えられる。あるいは、名門の威光を借りて簗田姓を名乗った可能性も否定はできないが、蘆名氏から「商人司」という破格の地位を与えられたことを鑑みれば、一族が何らかの由緒ある家柄であったと考える方が自然であろう。この出自の問題は、今後の研究が待たれる興味深いテーマである。
4-2. 「検断筆頭」としての簗田家
藤左衛門の死後、会津の領主は蒲生氏から加藤氏、そして寛永20年(1643年)には徳川家光の異母弟である保科正之へと代わり、以後、会津松平家による統治が幕末まで続く。驚くべきことに、簗田家は、この支配者の交代を経てもなお、会津若松の町方支配の最高責任者である「検断筆頭」の地位を世襲し続けたのである 17 。
特に、江戸時代初期屈指の名君と謳われる保科正之が、旧体制から続く簗田家をそのまま重用したという事実は重要である 14 。正之は、藩内の身分制度を再編し、中央集権的な藩政改革を断行した人物であり、旧来の勢力を刷新することも可能であったはずだ 14 。それでも彼が簗田家を温存したのは、簗田家が単なる特権商人の家系ではなく、会津の複雑な商業機構と町政を円滑に運営するために不可欠なノウハウ、経験、そして権威を蓄積した「専門家集団」として、既に藩の統治システムに欠かせない存在となっていたからに他ならない。藤左衛門が蒲生氏郷の改革の中で手に入れた「検断」という公的な役職は、個人の才覚に依存する「商人司」の地位とは異なり、制度化された権威であった。この制度への転換こそが、一族の永続を可能にしたのである。
4-3. 現代に続く歴史の残響
簗田家が「検断筆頭」として会津の町人社会を統括する役割は、実に明治の廃藩置県に至るまで、約250年もの長きにわたって続いた 17 。これは、簗田藤左衛門が一代で築き上げた社会的基盤がいかに強固で、後継者たちもその役割を的確に果たし続けたかを物語っている。
その歴史の残響は、現代にまで及んでいる。近年の会津若松市において、地域の歴史や文化を伝える講座の講師として、簗田姓を持つ人物が活動している記録が確認できる 31 。これは、藤左衛門から始まる簗田一族が、会津の地に深く根を下ろし、その歴史と文化の担い手として、今なお地域社会の中で重要な役割を果たし続けていることを示す、象徴的なエピソードと言えよう。藤左衛門の遺産は、単なる過去の記録ではなく、現代にまで続く生きた歴史として会津の地に息づいているのである。
結論:歴史の転換点を生きた「政商」の実像
本報告書で詳述してきた通り、簗田藤左衛門の生涯は、「会津の豪商」あるいは「蘆名家の御用商人」といった単純な言葉で要約できるものではない。彼は、戦国乱世から近世社会へと日本史が大きく転換する時代を、経済という武器を手に、類稀なる政治感覚で生き抜いた、極めて複合的な人物であった。
彼の人物像は、複数の側面から再定義されなければならない。
第一に、彼は蘆名氏の経済的代理人であった。領主・蘆名盛氏の富国強兵策を実務レベルで支え、領国の富を管理・増大させる「生きたインフラ」として機能した。
第二に、彼は支配者交代期を乗り切る交渉人であった。蘆名氏滅亡後、伊達政宗、蒲生氏郷という全く性質の異なる支配者に対し、自らの価値を的確に提示し、地位を安堵させるだけでなく、新たな統治体制の中に自らを組み込ませることに成功した。
第三に、彼は二つの川を制する物流の覇者であった。西の阿賀川で塩の輸入ルートを、東の阿武隈川で特産品の輸出ルートを掌握し、日本海と太平洋を結ぶ広大な商業ネットワークを支配した。「塩釜の商人」という伝承は、彼の事業の壮大さを物語るものであった。
そして最後に、彼は一族を近世の名家へと押し上げた創業者であった。一代で築いた権勢を、個人的な特権から制度化された世襲の役職「検断」へと昇華させ、幕末まで続く一族の繁栄の礎を築いた。
簗田藤左衛門は、武力ではなく、経済力、情報力、そして卓越した状況判断能力を駆使して乱世を生き抜いた「政商」の典型であった。彼の生涯は、戦国大名の領国経営における商人の決定的な役割を浮き彫りにすると同時に、戦国から近世へと社会の支配構造が再編されていくダイナミズムを、一人の人物の視点から鮮やかに映し出している。簗田藤左衛門の物語は、会津という一地方の歴史に留まるものではない。それは、日本の近世社会がいかにして形成されたのか、その過程における経済の役割を理解するための、極めて貴重なケーススタディなのである。
引用文献
- 簗田藤左衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%97%E7%94%B0%E8%97%A4%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80
- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys13=54
- 簗田藤左衛門(やなだ とうざえもん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B0%97%E7%94%B0%E8%97%A4%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-1116847
- 「蘆名盛氏」地方の大名でありながら将軍直属の家臣! 会津蘆名家の最盛期を築いた大名 https://sengoku-his.com/817
- 藩が支え酒どころとなった会津若松市/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44017/
- 漆器商人と株仲間 https://www.shirokiyashikkiten.com/museum/historical-study/shikki-syounin.html
- 蘆名盛氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F
- 「財閥」のルーツは戦国時代の”御用商人”にあった!彼らはどのように財をなしていったのか? https://mag.japaaan.com/archives/239791
- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599
- 伊達政宗の挑戦、 蒲生氏郷の理想 - JR東日本 https://www.jreast.co.jp/tohokurekishi/tohoku-pdf/tohoku_2019-07.pdf
- 伊達政宗が拓いた杜の都 仙台市/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44021/
- 経営者としても一流 だった伊達政宗 - 仙台経済同友会 http://www.sendai-doyukai.org/publish/download/report/387.pdf
- 蒲生氏郷(がもう うじさと) 拙者の履歴書 Vol.36〜織田・豊臣二代に仕えし会津の名将 - note https://note.com/digitaljokers/n/nf1e67e17acd8
- 【商人旅】〜会津商人篇②〜 蒲生氏郷と保科正之、そして藤樹学 ... https://rekishikuidaorediary.hatenablog.com/entry/2020/11/08/233057
- 会津若松城|城のストラテジー リターンズ|シリーズ記事 - 未来へのアクション https://future.hitachi-solutions.co.jp/series/fea_shiro_returns/01/
- 蒲生氏郷公/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/gamouujisato.html
- 七日町通りの歴史 https://www.nanukamachi.com/shop/nanukamachi_history.html
- 第4回「戊辰戦争における会津藩の情報収集」(前期) - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2023/2023-4.html
- 阿賀野川の流域紹介 https://www.hrr.mlit.go.jp/agano/aganogawa/ryuiki/ryuuiki0204.html
- 相互交流宣言(新潟市) - 会津若松市 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2011113000038/
- 講演録:阿賀川と舟運 - 北陸地方整備局 https://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/river/history_gijyutsu04.html
- 塩川駅の船 - 福島盆地から山越えて http://happyisland.blog.shinobi.jp/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E5%91%A8%E8%BE%BA/%E5%A1%A9%E5%B7%9D%E9%A7%85%E3%81%AE%E8%88%B9
- 食の風土記 13 舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ https://www.mizu.gr.jp/img/kikanshi/no61/mizu61p.pdf
- 阿武隈川 ~四季折々の風景と舟運の歴史~ https://marumori-net.tourbooking-japan.com/A/ja-JP
- 阿武隈川舟運 - わたりっ子ニュース http://mizube8.web.fc2.com/shuun.html
- 近世阿武隈川の舟運 - みちのく伊達の香り http://datenokaori.web.fc2.com/sub155.html
- 阿武隈川の歴史 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0207_abukuma/0207_abukuma_01.html
- 簗田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%97%E7%94%B0%E6%B0%8F
- 武家家伝_簗田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yanada_k.html
- 簗田氏の動向 - 野田市 https://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/779/3-3a.pdf
- 会津の歴史シリーズ 「商家の歴史 1」 講師: 簗田 直幸 氏 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Md2ikQeVmKo