荒木元清
荒木元清は荒木村重の従兄弟で花隈城主。村重の謀反に同調し、後に豊臣秀吉に仕える。秀次事件で流罪となるも赦免され、荒木流馬術を創始した。
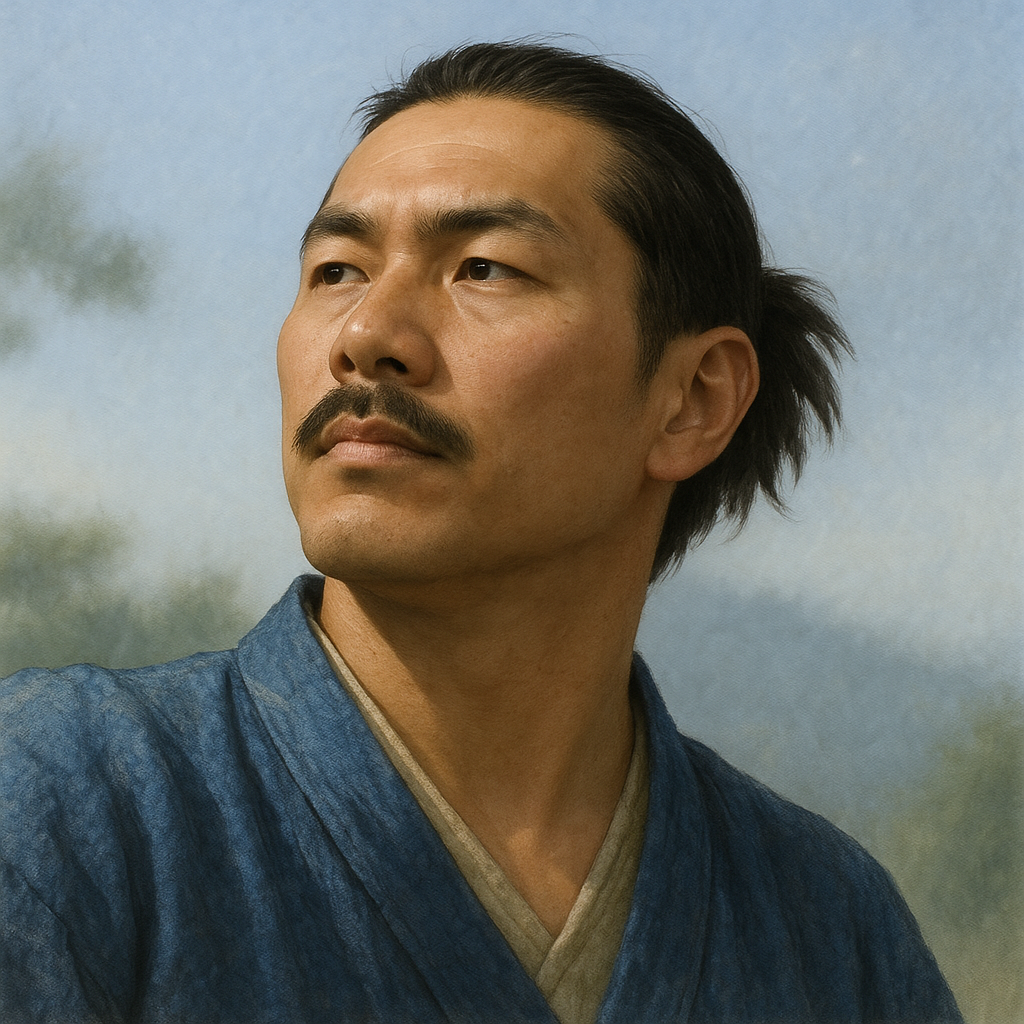
荒木元清:戦国を駆け抜けた武将、馬術の道を拓く
1. はじめに
本報告は、戦国時代から江戸時代初期にかけて生きた武将であり、また馬術家としても名を残した荒木元清(あらき もときよ)の生涯と業績について、現存する史料に基づいて多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。荒木元清は、織田信長、豊臣秀吉といった天下人が相次いで台頭する激動の時代に、摂津国(現在の大阪府北部と兵庫県南東部)を拠点とした荒木村重の一族として歴史の表舞台に登場した。彼は武将としての道を歩みつつ、独自の馬術流派「荒木流」を創始するという、戦国武将の中でも特異な経歴を持つ人物である。
本報告では、元清の出自に関する謎、主君であり縁戚でもあった荒木村重の謀反への関与、花隈城(はなくまじょう)主としての籠城戦、豊臣秀次事件における連座と赦免、そして荒木流馬術の創始と継承といった、彼の生涯における重要な出来事を詳細に追う。これらの出来事が彼に与えた影響を考察し、戦国という時代を生きた一人の武将の実像を明らかにすることを目指す。
表1:荒木元清 略年譜
|
西暦 (和暦) |
年齢 (数え) |
主要な出来事 |
主な関連史料 |
|
1535年 (天文4年)頃 |
1歳 |
生誕(天文5年説もあり) |
1 |
|
不明 |
不明 |
荒木村重に仕え、摂津国花隈城主となる |
1 |
|
1578年 (天正6年) |
44歳頃 |
荒木村重の織田信長への謀反に同調。有岡城の戦いに関連し花隈城を守備 |
3 |
|
1579年 (天正7年) |
45歳頃 |
村重父子を花隈城に迎え入れる。長男・渡辺四郎、次男・荒木新之丞が京都で処刑される |
2 |
|
1580年 (天正8年) |
46歳頃 |
花隈城落城。備後国鞆へ逃れる |
2 |
|
1582年 (天正10年) 以降 |
48歳頃以降 |
本能寺の変後、豊臣秀吉に仕える |
1 |
|
不明 |
不明 |
大坪流斎藤好玄より馬術を学び、荒木流馬術を創始 |
1 |
|
1595年 (文禄4年) |
61歳頃 |
豊臣秀次事件に連座し遠流となる |
1 |
|
1598年 (慶長3年) 以降 |
64歳頃以降 |
豊臣秀吉の死後、赦免され京都に隠棲 |
1 |
|
1610年 (慶長15年) |
75歳 |
5月23日、京都にて死去 |
1 |
2. 出自と一族
生没年と出自に関する諸説
荒木元清の生年は、天文4年(1535年)とする説 1 と、翌天文5年(1536年)とする説 1 が存在する。没年は慶長15年5月23日(1610年7月13日)で、享年75歳であったとされることから逆算すると天文4年生まれが有力と考えられる 1 。
元清の父については、『朝日日本歴史人物事典』などでは重元の子とされ 1 、また荒木村正(美作守) 7 、あるいは美作守氏元 7 といった名も伝えられており、確定していない。通常、主要な歴史上の人物であれば父の名は比較的明確に記録されるものであるが、元清に関しては複数の説が存在する。これは、元清自身の記録が断片的であったか、あるいは彼の家系が複雑であった可能性を示唆しており、荒木一族内での彼の正確な系統が必ずしも明確でなかったことを物語っているのかもしれない。いずれの説をとっても、系図上では荒木村重の従兄弟に位置付けられていることは共通している 7 。
荒木村重との血縁と主従関係
荒木元清は、摂津の戦国大名である荒木村重の従兄弟にあたる 1 。具体的には、元清の父が村重の父・荒木義村の弟であったとされている 7 。この近しい血縁関係にありながら、元清は当初、村重の家臣として仕えていた 1 。これは戦国時代の武家社会における一族内の序列や力関係を反映したものであり、村重の信頼を得ていたことが、後に花隈城主という要職に就く背景にあったと考えられる。
村重は摂津における有力な大名であり、元清はその一族かつ家臣という立場にあった。天正6年(1578年)に村重が主君織田信長に対して反旗を翻すという重大な決断を下した際 3 、元清が異なる道を選ぶことは、当時の武家社会の構造や一族の結束を考えると極めて困難であったと言えよう。主君であり血縁者でもある村重と運命を共にすることは、元清にとって避けられない選択であった可能性が高い。
妻と子女、そしてその運命
荒木元清の妻は、細川晴元の奉行人を務めた田井源介長次の娘であった 7 。興味深いことに、彼女は荒木村重の妻・だしの母とは姉妹であり、したがって、だしは元清にとって義理の姪にあたる関係であった 7 。
村重の謀反は、元清自身の運命だけでなく、その子供たちの人生にも大きな影響を及ぼした。
長男の渡辺四郎(1559年~1579年)は、渡辺勘大夫の婿養子となっていたが、有岡城の戦いの最中である天正7年(1579年)12月16日、京都において21歳で処刑された 5。『信長公記』には「廿一(歳) 渡辺四郎 荒木志摩守(元清)兄むすこなり」との記述があり 5、これは元清の兄の子(つまり甥)で、元清の養子になった可能性も示唆されるが、他の史料では元清の長男として扱われている 7。
次男の荒木新之丞(1561年~1579年)も、兄と同じく天正7年(1579年)に京都で処刑されている 7。これらの処刑は、信長の荒木一族に対する厳しい処断の現れであった。
一方で、三男以降の子息は生き延び、それぞれ異なる道を歩んだ。
三男の石尾治一(いしお はるかず、石尾越後守、156?年~1631年)は、豊臣秀吉の命により石尾姓に改め、秀吉の親衛隊である黄母衣衆の一員となった。その後、徳川家康にも仕え、その家系はしばらく続いた 7。
四男の荒木元満(あらき もとみつ、十左衛門、1565年~1632年)は、諱を「元治」(もとはる)とする史料もある 7。父・元清と共に豊臣秀次事件に連座して流罪となったが、秀吉の死後は黒田長政のもとに寄食した。大坂の陣に際して幕府に召し出され、徳川忠長に仕えた。元満の子・荒木元政(もとまさ)も忠長に仕えたが、忠長が改易されると一時松平直政のもとに預けられた後、三代将軍徳川家光に許されて幕臣(旗本)となり、上総国武射郡に1,500石を賜った。この元政の孫には、後に若年寄などを務めた荒木政羽がいる。そしてこの元満こそが、父・元清が創始した荒木流馬術を継承した人物である 1。
五男の荒木平大夫(実名不詳)は、日向国延岡藩主内藤忠興に仕え、その家系はしばらく続いたとされている 7。
有岡城の戦いにおける敗北とそれに続く一族の処刑は、荒木家にとって壊滅的な打撃であった。元清の長男・次男もこの粛清の犠牲となったが、三男以降の子息がそれぞれ異なる主君に仕え家名を繋いだ事実は、戦国末期から江戸初期にかけての武家の流転と再興の様相を映し出している。特に四男・元満が父の創始した馬術を継承し、その技能が後の仕官や家名維持に繋がった可能性は、混乱期において専門技能が個人の価値を高め、新たな道を開く手段となり得たことを示唆している。
表2:荒木元清 関係系図(概要)
|
続柄 |
氏名 |
生没年・備考 |
|
父 |
荒木重元、村正(美作守)、氏元など諸説あり |
不明 |
|
妻 |
田井源介長次の娘 |
荒木村重の妻だしの母と姉妹 |
|
長男 |
渡辺四郎 |
1559年~1579年。渡辺勘大夫の婿養子。京都にて処刑。 |
|
次男 |
荒木新之丞 |
1561年~1579年。京都にて処刑。 |
|
三男 |
石尾治一(越後守) |
156?年~1631年。豊臣秀吉・徳川家康に仕える。黄母衣衆。 |
|
四男 |
荒木元満(十左衛門、元治) |
1565年~1632年。秀次事件で流罪。黒田長政に寄食後、徳川忠長に仕える。荒木流馬術を継承。子は旗本。 |
|
五男 |
荒木平大夫 |
実名不詳。内藤忠興に仕える。 |
3. 武将としての道程
花隈城主としての元清
荒木元清は、摂津国花隈(現在の兵庫県神戸市中央区花隈町)の城主であった 1 。石高は18,000石を領有していたと伝えられている 7 。花隈城は、有岡城(伊丹城)の重要な支城であり、西国街道を見下ろし、大坂湾にも面した戦略的要衝であった 12 。この地は、毛利氏の水軍との連携や、石山本願寺への補給路を監視する上でも重要な拠点であり、元清がこの城を任されたことは、主君・村重からの信頼の厚さを示すと同時に、彼の軍事的能力がある程度評価されていたことを示唆する。
織田信長への反旗:有岡城の戦いと花隈城の攻防
天正6年(1578年)10月、主君である荒木村重が突如として織田信長に反旗を翻した(有岡城の戦い) 3 。これに対し、元清も村重に同調し、織田方と敵対することになる 7 。『信長公記』巻十一には、この時期、滝川一益や丹羽長秀といった織田軍の部隊が「荒木志摩守(元清)が籠る花隈城を攻める」と記されており 4 、元清が花隈城の守将として織田軍と対峙したことがわかる。
天正7年(1579年)9月、戦況が不利となり有岡城から荒木村重・村次父子が逃れてくると、元清は彼らを花隈城に迎え入れた 2 。これにより花隈城は、荒木氏にとって最後の抵抗拠点の一つとなった。
翌天正8年(1580年)閏3月2日から、池田恒興・輝政親子を中心とする織田軍による花隈城への本格的な攻撃が開始された(花隈城の戦い) 14 。池田輝政はこの戦いで武功を挙げ、信長から感状を授けられたと記録されている 15 。有岡城が天正7年11月に落城した後 11 、村重は妻子を見捨てて尼崎城、そして元清が城主を務める花隈城へと逃れた。花隈城が荒木村重にとって最後の抵抗拠点となったことは、元清が主君を見捨てず最後まで運命を共にしようとした忠誠心の表れとも解釈できる。しかし、織田信長から見ればこれは許しがたい反逆行為の継続であり、花隈城での抵抗が長引いたことが、結果として荒木一族に対するより厳しい処罰に繋がった可能性も否定できない。
落城と雌伏、そして豊臣秀吉への臣従
数ヶ月にわたる攻防の末、天正8年(1580年)7月2日、花隈城はついに開城(落城)した 2 。元清は城を脱出し、備後国鞆(現在の広島県福山市鞆町)へと逃れたとされている 7 。
しかし、天正10年(1582年)に本能寺の変で織田信長が横死し、その後、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が台頭すると、元清の運命は再び転機を迎える。秀吉は、かつて信長に敵対した元清の罪を許し、家臣として迎え入れたのである 1 。信長に徹底的に反抗した荒木一族の元清が、信長の死後、その後継者レースを勝ち抜いた秀吉に許され登用された背景には、秀吉の現実的な人材登用策と、旧敵対勢力であっても有能であれば取り込むという戦略があったと考えられる。元清が花隈城主として籠城戦を指揮した経験は一定の武将としての評価に繋がり、また荒木一族の旧臣である元清を取り込むことは、秀吉の摂津支配を円滑にする上で有利に働いた可能性がある。
4. 豊臣秀次事件の波紋
事件への連座と処罰
豊臣秀吉に仕えることになった荒木元清であったが、平穏な日々は長くは続かなかった。文禄4年(1595年)、関白豊臣秀次が秀吉から謀反の疑いをかけられて失脚し、自刃に追い込まれるという「豊臣秀次事件」が発生する。この事件は多くの大名や武士を巻き込み、元清もまた連座し、追放の上、流罪に処せられた 1 。
史料によれば、豊臣秀次は吉田重氏から日置流弓術を、そして荒木元清(当時は安志と号していた)からは荒木流馬術を学んでいたとされている 9 。この秀次の師という立場が、連座の直接的な理由となったと考えられる。秀次事件の連座者リストには、「荒木安志(元清)」の名が記され、「遠流」と処罰されたことが確認できる 9 。
豊臣秀次事件は、秀吉による大規模な粛清であり、秀次に関わる多くの人物が厳しい処罰を受けた。元清が秀次の馬術の師範であったことは、彼が秀次と個人的に近しい関係にあったことを意味し、これが連座の直接的な理由となったと考えられる。しかし、秀次の家老格の人物が切腹や斬首に処されたのに対し、元清の処罰が「遠流」であったことは、彼の役割が政治的なものではなく、あくまで技術指導者であったため謀反への直接的関与は薄いと判断されたか、あるいは彼の馬術の技能が惜しまれた等の事情があった可能性を示唆している。
流罪から赦免へ
流罪となった元清であったが、後に赦免されている 1 。具体的な流罪先やその期間、赦免に至る正確な時期や経緯についての詳細な史料は乏しい。しかし、慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去した後、元清は京都に隠棲したと記録されていることから 7 、赦免は秀吉の死が大きな契機となった可能性が高い。
元清が秀次事件で遠流となった後、慶長3年(1598年)の秀吉の死後に赦免され京都に隠棲したという記録は、この事件が秀吉個人の強い意志によって推進された粛清であり、彼の死によってその政治的圧力が緩和されたことを示している。秀吉の死後、豊臣政権内部では権力闘争が激化し徳川家康が台頭するが、家康は旧豊臣系大名や武将の懐柔策もとっており、秀次事件の連座者に対する恩赦もその一環として行われた可能性がある。元清の赦免も、こうした大きな政治的変動の中で実現したと考えられる。
5. 馬術家・荒木元清と荒木流の創始
荒木元清の生涯において特筆すべきは、武将としての側面と並び称される馬術家としての一面である。
大坪流斎藤好玄に学ぶ
元清は、当時代表的な馬術流派の一つであった大坪流の斎藤安芸守好玄(さいとう あきのかみ よしはる)より、弓術を伴わない馬術を学んだとされている 1 。史料には「のち純粋に馬術を修練することを志したと思われ」 1 とあり、彼が単なる武芸の一環としてではなく、専門的な技術としての馬術に深く傾倒していった様子が窺える。この「弓術を伴わない純粋な馬術」という志向が、後の荒木流の独自の特色へと繋がっていった可能性がある。
新流派「荒木流」の確立とその特徴
斎藤好玄のもとで大坪流を修めた元清は、それに自身の新しい工夫を加え、自らの名を冠した新流派「荒木流」(または荒木流馬術)を創始した 1 。既存の流派を学び、それに独自の創意を加えて新たな流派を立てることは、日本の武芸の歴史においてしばしば見られる発展の形態であり、元清が自身の名を流派名としたことは、彼の馬術における深い理解と自信、そして独創性を示すものである。
元清は花隈城落城や秀次事件による流罪など、武将としてのキャリアにおいて度重なる蹉跌を経験した。こうした状況下で、彼が「のち純粋に馬術を修練することを志したと思われ」るという記述は、武将としての立身が困難になった時期に、専門技能である馬術を磨き、新たな道を切り開こうとしたことを示唆している。結果として、この馬術への情熱と才能が、彼の名を後世に伝え、さらには子孫の繁栄にも繋がる重要な要素となった。『武術流祖録』といった江戸時代の武芸流派の系譜を記した書物にも、「荒木流」は馬術の流派としてその名が記載されている 16 。
後代への継承
荒木元清によって創始された荒木流馬術の道統は、彼の四男である荒木十左衛門元満によって継承された 1 。元満は父と同様に秀次事件に連座し流罪となったが、後に赦され、大坂の陣では幕府方として召し出され、徳川忠長に仕えた。さらに元満の子・元政は旗本として徳川幕府に仕え、1,500石の知行を得るに至っている 7 。流派の存続には後継者の育成が不可欠であり、元満が父の流儀を忠実に継承し、さらにその子孫が幕臣として家名を繋いだことは、荒木流馬術が一定の評価を得ていたことの証左と言えよう。
6. 晩年と最期
京都での隠棲
慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去し、豊臣秀次事件による流罪から赦免された後、荒木元清は京都に隠棲した 1 。法名を「安志」(あんし)と称し、「志摩入道安志」とも呼ばれた 1 。晩年は京都に住み、引き続き馬術の研究や指導に専念し、一派を開いたと記す史料もある 1 。
秀吉の死後、赦免された元清が文化の中心地であった京都に居を定めたことは、彼が馬術家としての名声を確立し、それを次世代に伝える上で重要な意味を持った。当時、京都は多くの公家や武士、文化人が集う場所であり、元清もそうした人々と交流があったことが示唆されている。例えば、当代一流の文化人であった近衛信尹(このえ のぶただ)とも知己の関係にあり、また塩川長満の孫にあたる池田元信に馬術を指導したとも伝えられている 18 。このような交流を通じて荒木流馬術が広まり、評価される機会が増え、結果として息子の元満による流派の継承や、さらにその子孫が幕臣として取り立てられる道筋にも好影響を与えた可能性がある。
死没
幾多の戦乱と政治的変転を乗り越えた荒木元清は、慶長15年5月23日(1610年7月13日)、京都において75年の生涯を閉じた 1 。戦国乱世を生き抜き、江戸時代初期まで長寿を保ったことは、彼の強靭な生命力と、時代の変化に適応する柔軟性を示しているのかもしれない。
7. 史料に見る荒木元清
荒木元清に関する記述は、いくつかの同時代の史料や後世の編纂物に見られるが、断片的なものが多い。
太田牛一が著した『信長公記』巻十一「荒木摂津守逆心を企て並びに伴天連の事」には、天正6年(1578年)の有岡城の戦いに際し、織田方の滝川一益・丹羽長秀が「荒木志摩守(元清)が籠る花隈城を攻める」との記述が見える 4 。これは、元清が花隈城の守将として歴史の表舞台に登場したことを示す重要な記録である。また、同じく『信長公記』には、天正7年(1579年)12月16日、京都の六条河原で行われた荒木一族の処刑の際に、「廿一(歳) 渡辺四郎 荒木志摩守(元清)兄むすこなり 渡辺勘大夫娘に仕合せ(めあわせ) 即養子するなり」との記述がある 5 。これは元清の長男(または養子となった甥)である渡辺四郎の最期を伝えるもので、元清の一族が受けた過酷な運命を物語っている。
江戸時代中期に成立したとされる前野家文書『武功夜話』には、荒木村重について「村重は実直にして風雅の心ある人」「荒木は実心あり」「実直にして巧偽をつくらず」といった評価が記されている 12 。これは元清自身への直接的な評価ではないものの、彼が属した荒木一族の気風を窺い知る上で参考になるかもしれない。また、江戸時代初期に成立した小瀬甫庵によるとされる『信長記』(太田牛一の『信長公記』とは別史料の可能性が高い)では、有岡城、尼崎城が落城した後も、元清は花隈城を守り抜き、天正8年(1580年)7月の落城まで持ちこたえたと記されている 19 。
史料における元清の記述は、主に荒木村重の謀反という大事件の関連人物として登場する場合が多い。これは、彼の武将としての生涯が村重の動向に大きく規定されていたことを改めて示している。一方で、馬術家としての側面は、『武術流祖録』 16 や日夏繁高の『本朝武芸小伝』 1 といった武芸史関連の史料に色濃く記録されており、元清が歴史に二つの異なる足跡を残したことを物語っている。彼の人となりを直接示す逸話は乏しいものの、一族の危機に際して最後まで抵抗し、また失脚後も新たな分野で道を切り開いた点からは、不屈の精神と専門技能への深い情熱を抱いた人物像が浮かび上がる。
8. おわりに
荒木元清の生涯は、戦国時代から江戸時代初期という激動の時代を背景に、武将としての栄光と挫折、そして馬術家としての独自の道を切り開いた点で、極めて興味深い軌跡を描いている。主君であり血縁者でもあった荒木村重の織田信長への謀反は、元清の運命を大きく揺るがし、花隈城での籠城戦、そしてその後の雌伏と豊臣秀吉への臣従、さらには豊臣秀次事件への連座と流罪という波乱に満ちたものであった。
しかし、元清は単に時代の波に翻弄されただけではなかった。彼は武将としての道を閉ざされかけた後も、大坪流の馬術を基礎としながら独自の工夫を凝らし、「荒木流」という新たな馬術流派を創始した。この業績は、彼の武芸に対する深い造詣と情熱、そして不屈の精神を示すものであり、四男・元満へと受け継がれ、その子孫は旗本として江戸幕府に仕えるに至った。
荒木元清の生涯は、戦国武士の多様な生き方の一例として、また、武芸の伝承という文化史的な側面からも評価されるべきであろう。彼の人生は、主家の盛衰や政治的陰謀に翻弄されながらも、個人の持つ技能と不屈の精神によって新たな道を切り開き、後世に名を残す可能性を示唆している。断片的な史料の中から彼の足跡を辿ることは、戦国という時代の複雑さと、そこに生きた人々の力強さを改めて認識させてくれる。
引用文献
- 荒木元清(あらきもときよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%92%E6%9C%A8%E5%85%83%E6%B8%85-1051197
- 摂津 花隈城 巨大模擬石垣の内部は立体駐車場 - 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-400.html
- 有岡城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 歴史の目的をめぐって 伊丹城(摂津国) https://rekimoku.xsrv.jp/3-zyoukaku-02-itamizyou.html
- シリーズ:「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」 第二十回 | 東谷ズム https://higashitanism.net/shiokawa-s-misunderstanding20/
- (荒木村重と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/29/
- 荒木元清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%92%E6%9C%A8%E5%85%83%E6%B8%85
- 大坪流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%AA%E6%B5%81
- 豊臣秀次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E6%AC%A1
- 荒木又右衛門 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/araki.html
- 第2回有岡城で織田信長と戦った?! - 伊丹市 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/bunnkazai/KEIHATU_ZIGYO/ouchideariokajyou/1588049228013.html
- 荒木村重 https://itami-bunbora.main.jp/jinbutu/jinbutu_photo/arakimurashige.pdf
- 花隈城攻め - FC2WEB http://tenkafubu.fc2web.com/murashige/html/hanakuma.htm
- 花隈城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E9%9A%88%E5%9F%8E
- 池田輝政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E8%BC%9D%E6%94%BF
- Union Catalogue Database of Japanese Texts https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100240826?ln=en
- 武術流祖録 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100240826
- 「摂津国衆・塩川氏の誤解を解く」 第27回「塩川長満・娘慈光院は ... https://note.com/tohbee_/n/n8648c4b58ccd
- シリーズ・「摂津国衆、塩川氏の誤解を解く」 第三回 - 東谷ズム https://higashitanism.net/shiokawa-s-misunderstanding3/