赤沢朝経
戦国初期の武将・赤沢朝経は、細川政元の腹心として畿内を席巻し、比叡山や興福寺を破壊。大和支配を試みるも、主君の死で後ろ盾を失い丹後で自刃。旧秩序破壊を体現した。
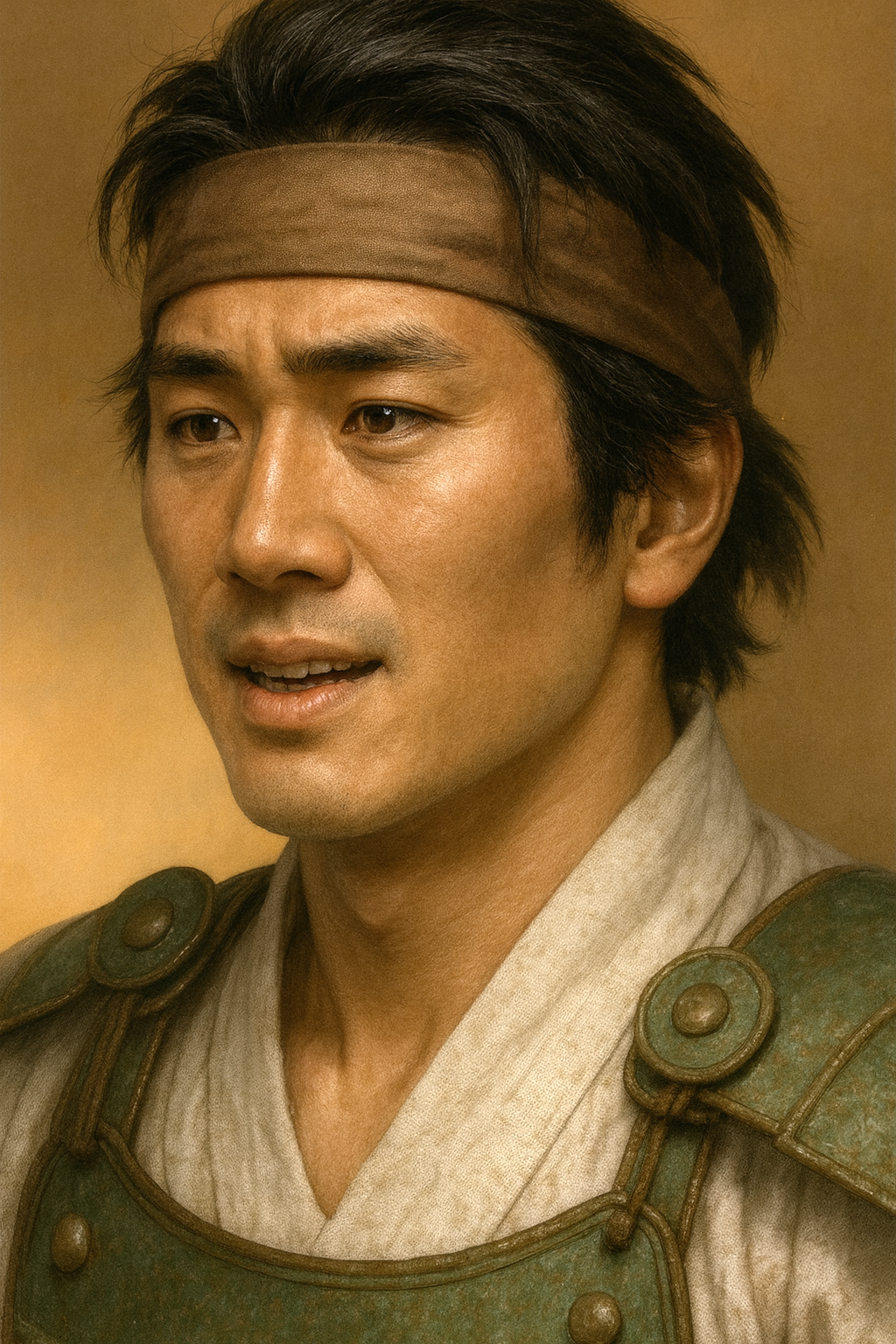
戦国初期の破壊と創造 ― 武将・赤沢朝経の実像
序章:戦国初期の畿内と赤沢朝経という存在
応仁・文明の乱(1467-1477年)が終結して以降の日本、とりわけ畿内は、旧来の権威が失墜し、新たな権力秩序が模索される混沌の時代にあった。守護大名の権威は揺らぎ、幕府の権力は衰退の一途をたどる中で、実力主義が社会の隅々にまで浸透し始めていた。この時代の転換期に、管領として中央政界に君臨したのが細川政元である。彼の存在なくして、赤沢朝経という武将の特異な活躍を語ることはできない。
細川政元は、従来の武家の棟梁像とは大きくかけ離れた人物であった。修験道に深く帰依し、飯綱の法などの呪術的修行に没頭、生涯独身を貫き女人を近づけなかったとされる 1 。その奇行はしばしば周囲を困惑させたが、同時に修験者や山伏のネットワークを情報網として活用するなど、合理的な統治術も持ち合わせていた 2 。このような異端の指導者の下では、細川氏に代々仕えてきた譜代の家臣団との間に、価値観の齟齬や政治的対立が生じることは避けられなかった。事実、政元は最終的にその譜代家臣である薬師寺長忠らによって暗殺される運命をたどる 3 。
こうした背景の中、政元が自身の権力を維持・強化するために重用したのが、「内衆」と呼ばれる側近集団であった。特に赤沢朝経は、信濃小笠原氏の庶流という、細川氏の伝統的な権力基盤とは無縁の「外様」の出身であった 4 。彼は、家柄ではなく、弓馬術や軍事指揮官としての卓越した個人的技能によって政元に見出され、その腹心となった「外様の内衆」なのである 4 。この立場は、朝経が畿内の伝統的な利害関係やしがらみに囚われることなく、純粋に政元の意向を遂行する「爪牙」としての役割を担うことを可能にした。赤沢朝経の台頭は、単なる一個人の立身出世物語ではなく、細川政元という特異な権力者の政治的要請と、実力主義という時代の潮流が交差した点に生まれた、歴史の必然であったと言える。彼の生涯は、後の戦国大名が国衆や地侍を直接支配下に組み込んでいく権力構造の先駆的な事例として、重要な意味を持つのである。
第一章:出自と上洛 ― 信濃小笠原庶流から京の武人へ
赤沢朝経の武名を理解するためには、まず彼が属した赤沢氏の出自と、彼が中央政界に進出するに至った経緯を明らかにする必要がある。彼のキャリアの出発点は、単なる武勇ではなく、高度な文化的背景に裏打ちされたものであった。
赤沢氏の系譜と本拠地
赤沢氏は、清和源氏の流れを汲む甲斐源氏・小笠原氏の庶流に位置づけられる 5 。その祖は、小笠原長経の次男とされる清経が、伊豆国赤沢郷(現在の静岡県伊東市赤沢)を領して赤沢氏を称したことに始まると伝えられている 7 。このため、赤沢氏の当主は伊豆守を称することが多かった 5 。家紋は「下太松皮菱の内十文字」や「五七桐」などが知られている 5 。その後、一族は信濃国へと拠点を移し、朝経の時代には塩崎城(現在の長野市篠ノ井塩崎)などがその本拠地であったと考えられている 6 。
上洛と細川政元への仕官
赤沢朝経は、宝徳3年(1451年)に生まれたとされ、通称を源次郎、後に入道して沢蔵軒宗益(たくぞうけんそうえき)と号した 4 。彼は家督を嫡子である政経に譲ると、父の経隆らと共に上洛を果たす 4 。その目的は、武芸の腕試しや立身出世だけではなかった。彼が携えていたのは、小笠原家に伝わる弓馬術礼法、すなわち「糾法的伝(きゅうほうてきでん)」であった 4 。これは単なる戦闘技術ではなく、武家の故実や礼法全般を含む、武士の棟梁たる者に必須の高度な文化的教養であった。
朝経の戦略は、この「文化的資本」を最大限に活用することにあった。彼はまず、その卓越した弓馬の術をもって8代将軍・足利義政の弓道師範、さらには武者所の役職に就くことに成功する 4 。将軍家へのアクセスを果たした彼は、次いで当代随一の実力者であった管領・細川政元に「糾法的伝」を伝授する機会を得る 4 。これが、彼の運命を決定づける出会いであった。さらに延徳3年(1491年)、10代将軍・足利義稙(後の義尹)が行った六角高頼征伐(長享・延徳の乱)に従軍した際には、鷹狩の技能も政元に高く評価され、政元個人の被官、すなわち「内衆」としての確固たる地位を築き上げるに至った 6 。
信濃の一地方武士が、畿内の中央政界で最高権力者の側近となるまでの道程は、彼が武力と文化的教養という二つの価値を巧みに使い分けた結果であった。戦国初期という時代は、まだ武力のみが全てを決定する時代ではなく、室町時代から続く伝統的な文化的価値が依然として大きな力を持っていた過渡期であった。赤沢朝経は、その両方を体現し、戦略的に利用することで、自らの道を切り開いたのである。
第二章:政元の爪牙 ― 畿内を席巻した軍事活動
細川政元の内衆となった赤沢朝経は、その類稀なる軍事的才能を遺憾なく発揮し、政元の政権安定と勢力拡大に不可欠な存在となっていく。彼の軍事行動は、政敵にとっては恐怖の象徴であり、その苛烈さは政元の政治的意思を色濃く反映したものであった。
畿内各地での転戦
朝経の軍事司令官としての活動は、明応5年(1496年)頃から本格化する。彼は政元の命を受け、南山城に侵攻していた畠山義豊の家臣・遊佐氏らを撃退 4 。この功績により、山城国の南三郡(久世郡・綴喜郡・相楽郡)の守護代に任じられ、畿内における自身の拠点を築いた 4 。明応8年(1499年)には、山城南部の御牧城、水主城、槇島城を次々と攻略。公家・近衛政家の日記『後法興院政家記』には、御牧城攻めにおいて「首9つ討ち取ると云々」との記述があり、その勇猛さが同時代人によって記録されている 6 。
彼の活動範囲は山城にとどまらなかった。河内国では、政元に反旗を翻した畠山尚順や畠山義英を再三にわたって攻撃し、彼らの拠点である高屋城などを占領した 13 。また、近江国では守護・六角高頼と対立した守護代・伊庭貞隆を支援するために出兵し、音羽城を攻撃している 6 。その影響力は畿内を越え、遠江国で今川氏親から圧迫を受けていた尾張守護・斯波義寛を救うため、本家である信濃の小笠原氏に援軍の派遣を要請するなど、広域にわたる軍事・外交活動を展開した 6 。
伝統的権威への挑戦
朝経の軍事行動の中でも特に際立っているのは、伝統的権威に対する容赦のない攻撃である。明応8年(1499年)7月、前将軍・足利義稙に与する動きを見せた比叡山延暦寺に対し、政元は焼き討ちを命令。朝経は波々伯部宗量と共にこれを実行し、天台宗の総本山である延暦寺の根本中堂、大講堂をはじめとする山上の主要伽藍をことごとく焼き払った 6 。これは、長年にわたり聖域として不可侵とされてきた宗教的権威への正面からの挑戦であり、政元政権のラディカルな性格を天下に示す象徴的な事件であった。
この比叡山焼き討ちに見られるような苛烈な行動は、朝経個人の資質のみに帰せられるものではない。主君である政元自身が、既存の仏教宗派や伝統的権威に対して懐疑的、あるいは対抗的な思想を持っていたことが、その背景にあると考えられる 1 。譜代の家臣であれば、旧来の寺社勢力との関係から躊躇したであろう徹底的な破壊も、「外様の内衆」である朝経は、政元の命令を最も忠実に、かつ躊躇なく実行することができた。彼の武力は、まさに政元の政治思想を代行するための装置として機能していたのである。朝経の戦いの軌跡は、主君・政元の野心と、それを実現するための非情なまでの合理性を映し出している。
第三章:大和侵攻 ―「先代未聞」の破壊と支配
赤沢朝経の名を戦国史に深く刻み込んだのは、彼の軍事キャリアの頂点ともいえる大和国への侵攻であった。この一連の軍事行動は、単なる戦闘や略奪にとどまらず、中世的な支配構造そのものを武力で解体し、新たな支配体制を構築しようとする、戦国時代の萌芽ともいえる画期的な試みであった。
第一次侵攻と「先代未聞」の破壊
明応8年(1499年)、細川政元は、政敵である畠山尚順に呼応する動きを見せた筒井順賢ら大和国人衆を制圧するため、赤沢朝経を大和へ派遣した 6 。朝経は、かねてより大和国人衆の内部対立を利用し、古市澄胤を手引きとして奈良盆地へと侵攻した 14 。緒戦となった超昇寺城の戦いで筒井党をやすやすと撃破すると 18 、その矛先は近隣の寺社へと向けられた。
朝経軍は、法華寺、西大寺、海龍王寺を打ち壊し、特に喜光寺には火を放ち、鎌倉時代に再興された本堂をはじめとする伽藍のほぼ全てを焼き尽くした 6 。さらに奈良市中に乱入し、大和国の支配者であった興福寺の僧房から春日大社に至るまで、乱暴狼藉の限りを尽くした 18 。この惨状を目の当たりにした興福寺の学僧・尋尊は、自身の日記『大乗院寺社雑事記』に「先代未聞沙汰也(前代未聞の出来事である)」と、その衝撃と悲嘆を記している 18 。比叡山に続き、南都・奈良という鎮護国家の象徴を徹底的に破壊した朝経の行動は、旧時代の価値観を根底から揺るがすものであった。
支配の試みと権威への挑戦
朝経の目的は、破壊そのものではなかった。彼は占領地において、敵対した国人の所領を没収して自らの配下に再配分し(闕所処分)、興福寺の荘園に段銭(軍事税)を課すなど、直接的な支配体制の構築を試みた 18 。これは、荘園領主や寺社、国人といった多様な権力が重層的に存在する中世的な土地支配のあり方を否定し、単一の軍事権力による一元的な支配を目指すものであった。
この強権的な支配に対し、興福寺は伝統的な対抗手段である神木動座(春日大社の神木を担ぎ出して強訴すること)をもって朝廷に朝経の撤兵を訴えた。しかし、朝経は朝廷の命令すらも公然と無視し、軍事行動を継続した 18 。神仏や朝廷の権威が、剥き出しの武力の前にもはや無力化しつつあることを示す、時代の大きな転換点であった。
しかし、その朝経も永正元年(1504年)、細川家の内紛である薬師寺元一の乱に加担したことで一時失脚し、捕縛される 2 。だが、その武勇を惜しんだ政元によって助命され、再び表舞台へと復帰することになる 6 。
第二次侵攻と大和平定
朝経が一時的に大和を離れた隙に、彼の脅威に直面した大和の国人たちは、長年の敵対関係を超えて結集した。筒井氏、越智氏をはじめ、朝経に与した古市氏を除くほぼ全ての大和国人が団結し、「大和国人一揆」を結成して他国からの侵略者に対抗しようとしたのである 14 。
永正3年(1506年)、赦免された朝経は、三好之長らと共に再び大和へ侵攻する 6 。彼は菩提山正暦寺や多武峰妙楽寺といった寺社勢力をも焼き払い、抵抗する大和国人一揆を圧倒的な軍事力で粉砕した 6 。これにより、奈良盆地一帯は完全に赤沢朝経の支配下に置かれることとなった 17 。
赤沢朝経の大和侵攻は、後の織田信長や豊臣秀吉が行う寺社勢力の制圧や検地による領域支配の原型ともいえる。彼の行動は、中世的秩序を破壊し、近世的な「領域支配」を志向する、戦国時代の到来を告げる画期的なモデルケースであったと評価できる。
表1:赤沢朝経による大和国および周辺寺社への主要な攻撃一覧
|
年月日 |
対象寺社 |
行為 |
被害状況 |
典拠史料(例) |
|
明応8年(1499)7月 |
比叡山延暦寺 |
焼き討ち |
根本中堂など主要伽藍全焼 |
『後法興院政家記』等 6 |
|
明応8年(1499)12月 |
喜光寺 |
焼き討ち |
鎌倉再興の本堂など、ほぼ全焼 |
『大乗院寺社雑事記』等 18 |
|
明応8年(1499)12月 |
法華寺、西大寺、海龍王寺 |
打ち壊し |
堂舎の破壊 |
『大乗院寺社雑事記』等 18 |
|
明応8年(1499)12月 |
興福寺、春日大社 |
乱入、狼藉 |
院家・僧房での略奪・乱暴 |
『大乗院寺社雑事記』等 18 |
|
永正3年(1506)7月以降 |
菩提山正暦寺、多武峰妙楽寺、龍門寺 |
焼き討ち |
堂舎の焼失 |
『多聞院日記』等 6 |
第四章:永正の錯乱と非業の最期
大和国を平定し、その武威が絶頂に達したかに見えた赤沢朝経であったが、その栄華は突如として終焉を迎える。中央政界で起きた激震は、遠く離れた戦場の将の運命をも一瞬にして暗転させた。彼の最期は、個人の武勇がいかに優れていようとも、それを支える政治的基盤が崩壊すれば、たちまち無力化するという戦国初期の権力構造の脆弱性を如実に物語っている。
丹後出兵と主君の暗殺
永正4年(1507年)、朝経は主君・細川政元の命令を受け、新たな戦線へと向かった。若狭国守護・武田元信を支援し、それに敵対する丹後国守護・一色義有を攻撃するため、丹後国へ出兵したのである 3 。この軍勢には、若狭の粟屋親栄や、大和で朝経に協力した古市澄胤の子・胤盛らも加わっていた 6 。
朝経が一色勢と丹後で対陣している最中の同年6月23日、京都で天下を揺るがす大事件が発生する。主君・細川政元が、自らの邸宅において、養子の一人である細川澄之を擁立しようと画策した家臣の香西元長、薬師寺長忠らによって暗殺されたのである 3 。この「永正の錯乱」と呼ばれる政変により、朝経は自身の権力の源泉であった最大の後ろ盾を、あまりにも突然に失うことになった。
丹後九世戸での自刃
主君暗殺の衝撃的な報せは、丹後の陣中にいる朝経のもとにも届いた。軍事行動の正当性と目的を失った彼は、軍を京都へ撤退させることを決断する 3 。しかし、この好機を敵が見逃すはずはなかった。これまで朝経軍の攻撃に耐えていた一色義有と、丹後の有力国人であった石川直経が、即座に反撃に転じたのである 3 。
朝経の強大さは、彼自身の軍事力と、「管領・細川政元」という巨大な権威の組み合わせによって成り立っていた。政元の死によってその後ろ盾が消滅した瞬間、彼は管領の代官から単なる「丹後への侵略者」へとその立場を変えられてしまった。大和で国人一揆をいとも簡単に鎮圧した彼が、丹後では国人の反撃の前に窮地に陥ったのは、この立場の変化が決定的な要因であった。
退路を断たれ、一色・石川連合軍の猛追を受けた朝経軍は壊乱。永正4年6月26日、朝経は丹後九世戸(現在の京都府宮津市)の文殊堂(智恩寺)において進退窮まり、自刃を遂げた 3 。享年57であったとされる 6 。この時、従軍していた粟屋親栄、古市胤盛も共に討ち死にした 6 。一個人の武将の死は、中央の政治構造の変動に翻弄された結果であり、戦国時代における武将の栄光と没落が、常に中央政局と不可分であったことを示す典型的な事例と言える。
表2:永正の錯乱における主要人物の動向(永正4年6月23日-26日)
|
日付 |
場所:京都 |
場所:丹後 |
影響と連関 |
|
6月23日 |
細川政元、香西元長・薬師寺長忠らにより暗殺される 3 。 |
赤沢朝経、一色義有と対陣中。 |
朝経の権力の源泉が消滅。 |
|
6月24日 |
京では澄之派が一時的に権力を掌握。混乱が始まる。 |
朝経、主君暗殺の報を受け、軍の撤退を決断 3 。 |
軍事行動の目的と大義名分を喪失。 |
|
6月25日 |
- |
一色義有・石川直経ら丹後国人衆が、撤退する朝経軍への追撃を開始 3 。 |
敵対勢力が、朝経の孤立という好機を捉えて反撃。 |
|
6月26日 |
- |
朝経、九世戸・文殊堂で包囲され、進退窮まり自刃 3 。 |
政元の死が、わずか3日で前線の司令官の死に直結。 |
第五章:その後の赤沢氏と後世への影響
赤沢朝経の死は、彼の一族の運命にも大きな転換をもたらした。朝経が切り開いた「武」の路線を継承しようとした者と、一族の原点である「芸」に活路を見出した者。その対照的な二つの道は、戦国乱世から泰平の江戸時代へと移行する中で、武家がいかにして生き残りを図ったかを象徴する事例となっている。
「武」の継承と挫折 ― 養子・長経の戦い
朝経が丹後で自刃した際、その陣中から辛くも生還したのが、彼の養子(一説には弟)・赤沢長経であった 3 。長経は、政元のもう一人の養子であった細川澄元の配下となり、養父・朝経の路線を継承して軍事活動を継続する 3 。彼は大和の古市澄胤らと連携し、澄元方として大和・河内を転戦。細川高国や畠山尚順の軍勢と激しく戦った 17 。
しかし、長経は朝経のような強力な政治的後ろ盾に恵まれなかった。朝経の強さが政元という絶対的な権力者との個人的な結びつきに依存していたのに対し、長経は細川家の内紛という、より不安定な状況下で戦わねばならなかった。永正5年(1508年)7月、長経は河内国での戦いに敗れて逃走。大和国の初瀬で捕縛され、河内において斬首された 21 。朝経の死からわずか1年余り、彼が築き上げた武威と大和支配の野望は、長経の死によって完全に潰えることとなった。
「芸」による再興 ― 弓馬術礼法の宗家へ
一方、朝経の嫡子であり、早くに家督を譲られていた赤沢政経は、異なる道を歩んだ。彼は一時期、河内国の城を守っていたが、落城後に本拠地である信濃へ帰還したと伝えられる 7 。その後の赤沢一族は、信濃で小笠原宗家に従い、武田信玄との抗争にも加わったが、戦国大名としての勢力を回復することはできず、次第に没落していった 7 。
しかし、赤沢氏には武力とは別の、もう一つの資産があった。それは、一族の源流であり、朝経が上洛するきっかけともなった「小笠原流弓馬術礼法」という「家芸」である。戦国乱世を生き抜いた一族の赤沢貞経は、天下人となった徳川家康に召し出される機会を得る。家康は彼の武功ではなく、その卓越した弓馬術の技能を高く評価した 7 。
貞経は赤沢から小笠原姓に復することを許され、江戸幕府の御家人として五百俵を与えられ、騎射の師範役という名誉ある地位に就いた 7 。戦乱の世が終わり、平和な江戸時代が到来すると、戦闘技術としての武術よりも、儀礼や教養としての「武芸」の価値が相対的に高まった。赤沢(小笠原)氏は、この時代の価値観の変化に巧みに適応し、一族のアイデンティティを「武功」から「家芸」へと再定義することで、家名を後世に伝えることに成功したのである。この系統は、現代にまで続く「小笠原流弓馬術礼法宗家」として、その伝統を継承している 5 。赤沢一族の盛衰は、時代が求める価値の変化を読み解き、自らの強みを再発見して生き残った武家の、優れた適応戦略の物語として捉えることができる。
結論:赤沢朝経が体現した戦国初期という時代
赤沢朝経の生涯を総括する時、彼は単なる「細川政元に仕えた猛将」という評価にとどまらない、より深い歴史的意義を持つ人物として浮かび上がる。彼の存在そのものが、室町時代が終焉を迎え、戦国時代が本格的に幕を開ける、まさにその過渡期の破壊と創造のダイナミズムを体現していた。
第一に、朝経は 実力主義と下剋上の体現者 であった。信濃の小笠原庶流という、中央政界から見れば傍流の出身でありながら、弓馬術礼法という専門技能と卓越した軍事の才覚のみを武器に、一代で畿内を席巻する軍事司令官へと成り上がった。彼の立身出世は、家格や伝統よりも個人の能力が重視される新時代の到来を告げるものであった。
第二に、彼は 伝統的権威の解体者 であった。比叡山延暦寺や南都・興福寺といった、長年にわたり聖域とされてきた宗教的権威を武力で蹂躙し、さらには朝廷の命令すら無視した彼の行動は、中世的な秩序と価値観の崩壊を加速させた。神仏の権威よりも、剥き出しの武力が全てを決定するという戦国乱世の非情な現実を、誰よりも早く、そして徹底的に示したのである。
第三に、朝経は 戦国大名の先駆者 としての側面を持つ。特に大和国で見せた、敵対国人の所領没収と再配分(闕所処分)、領域内からの直接的な軍事費徴収(段銭)といった一連の政策は、荘園制に代表される重層的な中世の支配構造を否定し、単一の権力による領域一元支配を目指すものであった。これは、後の戦国大名が推し進める「領国経営」の先駆的なモデルケースであり、彼の試みは、意図せずとも新時代の統治システムを実験する役割を果たした。
しかし、その栄光は、細川政元という特異な権力者の死と共にあまりにもあっけなく潰え去った。彼の悲劇的な最期は、個人の能力がいかに高くとも、それを支える政治的基盤がいかに脆弱であったか、そして中央政局の動乱が地方の戦線に即座に、かつ致命的な影響を及ぼす、戦国初期の権力構造の不安定性を象徴している。
したがって、赤沢朝経は単なる「破壊者」として記憶されるべきではない。彼は、旧時代の秩序を破壊し、新時代の統治原理を萌芽的に示した、歴史の転換期における重要なアククターであった。彼の鮮烈な栄光と非業の死は、戦国初期という時代の混沌と可能性、その光と影を映し出す、類稀な鏡であると言えるだろう。
引用文献
- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/
- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83
- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1
- 赤沢朝経(あかざわ・ともつね) ?~1507 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AkazawaTomotsune.html
- 赤沢氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E6%B0%8F
- 赤沢朝経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E6%9C%9D%E7%B5%8C
- 武家家伝_赤澤氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/og_akaza.html
- 赤澤氏とは - 備中赤澤家と玉島古戦記 https://akazawa-shi.jimdofree.com/%E8%B5%A4%E6%BE%A4%E6%B0%8F%E3%81%A8%E3%81%AF/
- akazawa - 名字の由来 http://www.myouji.org/MFDocuments2/akazawa.htm
- 塩崎城跡 - 長野市文化財データベース http://bunkazai-nagano.jp/modules/dbsearch/page0463.html
- 歴史の目的をめぐって 赤沢朝経 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-akazawa-tomotsune.html
- 宗瑞を圧迫した立役者、赤沢朝経~家永遵嗣氏 講演 http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/post-c31160.html
- 赤沢朝経(あかざわともつね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E6%9C%9D%E7%B5%8C-1048774
- 戦国!室町時代・国巡り(10)大和編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n2d6f2aae417d
- 畠山尚順 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%B0%9A%E9%A0%86
- 高屋城の歴史 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/613/memo/4293.html
- 細川京兆家の分裂と大和国人一揆の終焉~大和武士の興亡(9) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi09
- 大和国人一揆・赤沢朝経の猛威~大和武士の興亡(8) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi08_kokujinikki
- 一色義有 http://dayzi.com/zisyo/i-nyoshiari.html
- 戦国!室町時代・国巡り(23)丹後編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n541e2765b853
- 赤沢長経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E9%95%B7%E7%B5%8C
- 赤沢朝経父子の侵入 - M-NETWORK http://www.m-network.com/tsutsui/t01_04.html
- 【二代 小笠原長経】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht053220