足利政氏
足利政氏は第2代古河公方。長享の乱では扇谷上杉氏、後に山内上杉氏を支持し、関東の覇権を巡る争いに介入。嫡男高基との対立「永正の乱」で古河を追われ、隠棲。文化人としての一面も持つ。
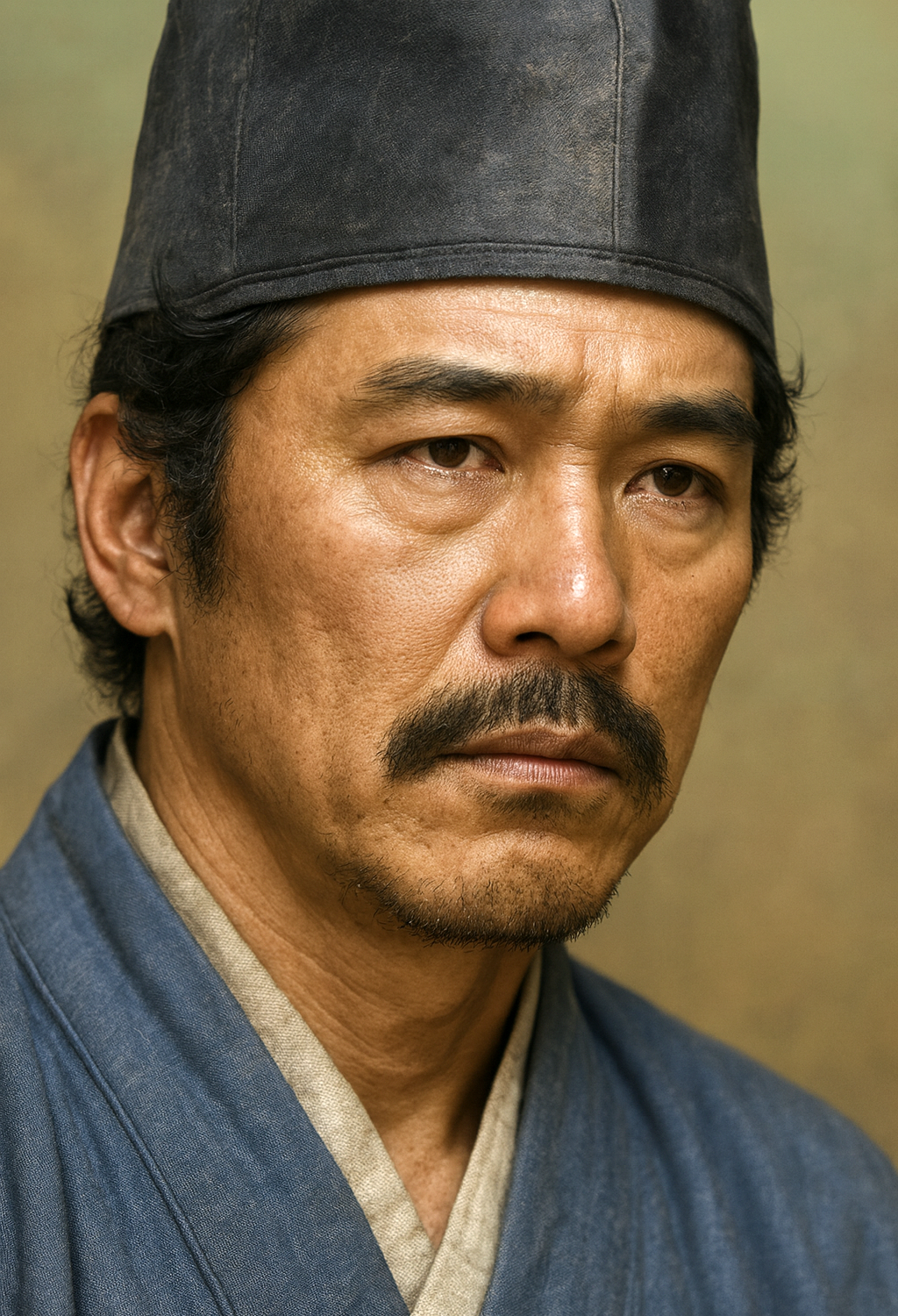
日本の戦国時代の武将、足利政氏に関する包括的調査報告
序章:戦国関東の黎明と古河公方家の成立
足利政氏の生涯を理解するためには、まず彼がその半生を送る舞台となった戦国時代初期の関東地方における特異な政治状況を把握する必要がある。政氏の父、足利成氏は、室町幕府およびその関東における出先機関である関東管領上杉氏との間で約30年にも及ぶ大乱「享徳の乱」を戦い抜いた 1 。この乱の結果、成氏は伝統的な本拠地である鎌倉を追われ、下総国古河に新たな拠点を構えることを余儀なくされた。これにより、彼は「古河公方(こがくぼう)」と称されるようになり、関東は利根川を境として、古河公方の勢力圏と上杉氏の勢力圏に事実上二分される状況が生まれた 2 。
幕府は、この事態に対抗すべく、8代将軍足利義政の弟である政知を新たな鎌倉公方として関東へ派遣したが、彼は関東の混乱を前にして鎌倉に入ることさえできず、伊豆国堀越に留まり「堀越公方」と称されるに留まった 2 。この結果、関東には二人の公方が並立し、政治的権威の分裂は決定的となった。
このような状況下で、古河公方足利成氏は、結城氏、里見氏、小田氏、千葉氏といった、伝統的に反上杉氏の気風が強い在地武士団の支持を権力基盤とした 3 。特に、公方家の重臣である簗田(やなだ)氏や野田氏は、古河周辺の下河辺荘に拠点を持ち、公方家の軍事的・経済的基盤を支える中核的存在であった 6 。中でも簗田氏は、成氏と姻戚関係を結ぶことで公方家臣団の筆頭としての地位を確立し、その後の古河公方家の政治に深く関与していくことになる 7 。
長期にわたる戦乱の末、文明11年(1479年)、ついに幕府と成氏の間で和睦(都鄙和睦)が成立し、享徳の乱は公式に終結した 2 。この和睦成立後、成氏の嫡男は元服し、将軍義政から「政」の一字を賜り「政氏」と名乗った 10 。これは、古河公方が再び幕府の権威体系に形式上組み込まれたことを象徴する出来事であった。
しかし、政氏が父から継承したのは、単に「古河公方」という地位だけではなかった。それは、父・成氏が享徳の乱を通じて作り上げた、「対上杉氏」という明確な対立軸を前提とした権力構造そのものであった。彼の支持基盤は反上杉の国人衆であり、彼の存在意義は関東における上杉氏への対抗勢力の盟主であることにあった。したがって、政氏の政治的選択肢は、当初からこの「対立の構造」に強く規定されていたのである。父の路線を継承することは、必然的に上杉氏との緊張関係を維持することを意味した。この構造的制約こそが、後の彼の政策決定、特に長享の乱への介入や、自らの息子である高基との対立の根源的な要因となっていく。政氏の生涯の悲劇は、この継承した構造から最後まで脱却できなかった点に求められるのである。
足利政氏 略年表
|
和暦 (西暦) |
年齢 (数え) |
出来事 |
典拠 |
|
寛正3年 (1462) |
1歳 |
足利成氏の嫡男として誕生(文正元年・1466年説もあり) |
11 |
|
文明11年 (1479) |
18歳 |
都鄙和睦が成立。将軍義政より偏諱を受け「政氏」と名乗る |
9 |
|
延徳元年 (1489) |
28歳 |
父・成氏より家督を継承し、第2代古河公方となる |
12 |
|
長享元年 (1487) |
26歳 |
長享の乱が勃発。扇谷上杉定正を支持 |
9 |
|
明応3年 (1494) |
33歳 |
上杉定正の死後、山内上杉顕定支持に転換 |
9 |
|
永正元年 (1504) |
43歳 |
立河原の戦いで、山内方として扇谷方・伊勢宗瑞らと戦う |
13 |
|
永正3年 (1506) |
45歳 |
嫡男・高基との対立が表面化(永正の乱の始まり) |
13 |
|
永正9年 (1512) |
51歳 |
高基方に敗れ、古河城を退去。小山氏を頼る |
9 |
|
永正13年 (1516) |
55歳 |
小山氏の離反により、岩付城の上杉朝良を頼る |
9 |
|
永正15年 (1518) |
57歳 |
上杉朝良の死後、武蔵国久喜に隠棲。出家し道長と号す |
9 |
|
永正17年 (1520) |
59歳 |
古河城にて高基と面会(形式的な和解) |
13 |
|
享禄4年 (1531) |
70歳 |
7月18日、久喜の甘棠院にて死去 |
9 |
第一章:家督相続と長享の乱 — 関東の覇権を巡る介入
家督相続と関東の新たな火種
足利政氏は、寛正3年(1462年)あるいは文正元年(1466年)に、初代古河公方・足利成氏の嫡男として生を受けた 11 。母は、公方家の筆頭重臣であった簗田直助の娘、伝心院である 10 。延徳元年(1489年)、父・成氏が病、あるいは隠居によって政務を執れなくなると、政氏は家督を継承し、第2代古河公方となった 10 。ただし、父・成氏が明応6年(1497年)に死去するまでは、その影響下にあり、名実ともに古河公方として関東に君臨するのは父の死後であったとも考えられる 9 。
政氏が家督を継承した時期の関東は、享徳の乱の終結によって得られた束の間の平穏が破られ、新たな戦乱の時代に突入しようとしていた。関東管領を世襲する山内上杉家と、その分家である扇谷上杉家の間で対立が先鋭化し、長享元年(1487年)、ついに両家は武力衝突に至る。これが、その後約20年にわたり関東を二分する内乱「長享の乱」である 14 。この新たな火種に対し、関東の武家の棟梁たる古河公方がいかなる立場を取るのか、その動向は関東の全勢力から注視されていた。
長享の乱への介入と支持勢力の転換
長享の乱が勃発すると、政氏は扇谷上杉家の当主・上杉定正に擁立される形で乱に介入し、関東管領である山内上杉顕定と敵対する道を選んだ 13 。この選択は、父・成氏以来の伝統的な反山内上杉(関東管領家)路線を継承するものであり、扇谷上杉家と連携することで、関東における古河公方家の影響力をさらに拡大しようとする戦略的意図があったものと分析される 19 。
しかし、政氏の立場は固定的なものではなかった。明応3年(1494年)、扇谷上杉家の当主であり、勇将として知られた上杉定正が急死すると、勢力均衡は大きく揺らぐ 9 。扇谷上杉家が弱体化したこの好機を、政氏は見逃さなかった。彼は従来の扇谷上杉家支持の方針を180度転換し、それまで敵対していた山内上杉顕定との連携へと舵を切ったのである 10 。この転換は、単なる裏切りや気まぐれと見るべきではない。それは、古河公方の「関東の盟主」としての権威を最大化するための、極めて計算された機会主義的戦略であった。両上杉氏を争わせ、常に優勢な側に付くことで、自らを関東情勢のキャスティング・ボートを握る存在として位置づけようとしたのである。
この方針転換後、政氏は山内上杉軍の中核として積極的に軍事行動を展開する。明応5年(1496年)の武蔵柏原合戦や、永正元年(1504年)の武蔵立河原の戦いでは、山内上杉顕定と共に、かつての同盟相手であった扇谷上杉朝良と干戈を交えた 10 。特に立河原の戦いでは、扇谷方に加勢した駿河の今川氏親と、その客将であった伊勢宗瑞(後の北条早雲)の軍勢とも戦っており、政氏が関東の覇権を巡る争いの中心人物であったことを示している 13 。
乱の終結と新たな体制の構築
永正2年(1505年)、長期にわたった長享の乱は、扇谷上杉家の降伏という形でついに終結する 13 。政氏は、この和睦後の新体制構築を主導した。その象徴的な行動が、実弟の義綱(ぎこう)を、子のいなかった山内上杉顕定の養子として送り込んだことであった 10 。義綱は名を上杉顕実(あきざね)と改め、関東管領家の後継者となった。これにより、古河公方家と関東管領家は緊密な姻戚関係で結ばれ、政氏は両上杉家を自らの影響下に置くことに成功したかのように見えた。
この一連の政氏の動きは、短期的には成功を収めたと言える。彼は関東の二大勢力である両上杉氏の争いを巧みに利用し、最終的には両家の上に立つ存在としての地位を確立しようとした。しかし、その機会主義的な立ち回りは、関東の諸勢力に「古河公方は信頼に足らず」という不信感を植え付けた可能性は否定できない。そして何よりも、自らの権威を外部の勢力争いに依存させるという構造的な脆弱性を内包していた。この脆弱性こそが、後に勃発する自らの家を二分する内乱「永正の乱」において、息子・高基に足元を掬われる遠因となるのである。
第二章:永正の乱 — 親子相克と古河公方家の分裂
対立の勃発と根本原因
長享の乱を乗り切り、関東における権威を固めたかに見えた足利政氏であったが、彼の治世における最大の悲劇は、外部の敵ではなく、自らの家庭内から生じた。永正3年(1506年)、政氏と嫡男・高基(たかもと)の対立が表面化し、古河公方家の分裂と衰退を決定づける「永正の乱」が勃発したのである 9 。
この親子相克の根源には、外交方針を巡る深刻な不一致があった。政氏は、長享の乱を通じて構築した山内上杉氏との連携を外交の基軸とし、伊豆から相模へと勢力を急拡大させていた新興勢力・伊勢宗瑞(北条早雲)を明確に敵視していた 9 。これは、父祖以来の伝統的な権力構造を維持しようとする保守的な路線であった。
これに対し、嫡男の高基は、旧来の権力構造に固執する父の方針に強く反発した。彼は、もはや家格や伝統だけでは通用しない戦国の世の到来を敏感に感じ取り、旧弊な上杉氏よりも、実力で頭角を現しつつあった伊勢宗瑞(後北条氏)との連携に活路を見出そうとしたのである 11 。この路線対立は修復不可能なレベルに達し、ついに高基は父と袂を分かち、古河を離れて舅である下野国の有力大名・宇都宮成綱のもとへと身を寄せた 13 。
関東全域を巻き込む内乱へ
古河公方家の内紛は、単なる一家庭内の問題に留まらなかった。それは、関東の諸大名を二分する大規模な内乱へと即座に発展した。政氏と高基は、それぞれが自派の正当性を主張し、関東の国人領主たちに味方になるよう働きかけた。これにより、関東の勢力図は、以下の表のように明確に二分されることとなる。
永正の乱 主要勢力図
|
足利政氏方 (Masauji Faction) |
足利高基方 (Takamoto Faction) |
|
公方一族 |
上杉顕実(政氏実弟・山内上杉家) |
|
関東管領家 |
(上杉顕実を通じて)山内上杉氏の一部 |
|
有力大名・国人 |
佐竹義舜、岩城由隆、小山成長(当初) 24 |
|
公方家臣団 |
簗田政助、野田政保 7 |
|
その他 |
扇谷上杉朝良(政氏の庇護者として) 9 |
|
公方一族 |
足利義明(政氏次男・後に離反し小弓公方へ) 13 |
|
関東管領家 |
上杉憲房(顕定養子・後に山内上杉家継承) 9 |
|
有力大名・国人 |
宇都宮成綱(高基舅)、結城政朝、上那須氏、小田氏 24 |
|
公方家臣団 |
簗田高助(政助の子) 7 |
|
その他 |
伊勢宗瑞(北条早雲)(間接的に連携) 11 |
この対立構造で特に注目すべきは、家臣団の分裂である。古河公方家の筆頭重臣であった簗田氏も、この内乱で分裂した。当主の簗田政助は長年の主君である政氏を支持したが、その子である簗田高助は次代の公方である高基を支持し、一族内で骨肉の争いを演じた 7 。最終的に、簗田氏の主流派は高基を支持し、これが戦局を大きく左右した。高基は簗田高助を宿老筆頭として重用し、公方家の実権を着実に掌握していく 8 。
権威の空洞化と関連する内紛
永正の乱は、単なる親子の争いではなかった。それは、古河公方という「権威」が、もはや自律的な権力ではなく、有力な国人領主たちが自らの勢力拡大のために利用する「旗印」へと変質してしまったことを示す象徴的な事件であった。宇都宮氏や簗田氏のような有力家臣は、もはや一方的に公方に従う存在ではなく、政氏と高基のどちらを「主君」として担ぐかを選択する立場にあった。簗田高助が高基を支持したことは、単なる忠誠心の移動ではなく、次代の関東の覇権を見据えた戦略的投資であったと言える。公方自身が内紛を起こしたことで、家臣たちは「どちらの主君が自分たちの利益になるか」を天秤にかけることが可能になった。これは、主従関係の逆転、すなわち権威の「空洞化」を意味する。
この混乱は、さらなる混乱を呼んだ。永正9年(1512年)、高基の最大の支援者であった宇都宮成綱は、政氏方であった重臣・芳賀高勝を殺害。これをきっかけに宇都宮氏の家中も大規模な内紛、いわゆる「宇都宮錯乱」に陥った 22 。
さらに、政氏の次男であった義明は、父とも兄とも袂を分かち、上総国の真里谷武田氏の支援を受けて下総小弓城に入り、「小弓公方」を自称して独立勢力を築いた 13 。これにより、関東には古河、堀越、小弓と三人の公方が並立する異常事態となり、公方の権威は地に堕ちた。政氏が守ろうとした権威の器は、彼自身の行動によって中身(実権)を家臣たちに奪われ、粉々に砕け散ってしまったのである。
第三章:落日 — 流転、隠棲、そして終焉
古河からの追放と流浪の日々
永正の乱は、嫡男・高基方の優勢のうちに進んだ。永正9年(1512年)頃、高基とその支持勢力の攻勢により、足利政氏はついに本拠地である古河城を追われることとなった 9 。関東の盟主としての座を失った政氏の、長く苦しい流転の生活が始まった。
古河を追われた政氏がまず頼ったのは、下野国の有力国人である小山氏であった。彼は小山城(祇園城)に身を寄せ、再起の機会をうかがった 4 。しかし、戦局は非情であった。高基方の勢力が関東の大部分を制圧する中、永正13年(1516年)、政氏を庇護していた小山氏までもが高基方に寝返ってしまう 9 。これにより、政氏は小山城からも退去を余儀なくされ、次なる庇護者を求めて扇谷上杉朝良のもとへ赴き、武蔵国の岩付城(現在の岩槻城)へと移った 9 。
出家、隠棲、そして政治生命の終焉
権力闘争に完全に敗北した政氏は、岩付城で出家し、「道長(どうちょう)」と号した 9 。これは、世俗の権力への執着を断ち切る象徴的な行為であった。そして永正15年(1518年)、最後の庇護者であった扇谷上杉朝良が死去すると、政氏はついに全ての政治的基盤を失う 9 。彼は岩付城を去り、武蔵国太田荘久喜(現在の埼玉県久喜市)に用意された館に隠棲した 4 。この政氏の完全な政治的引退をもって、十数年にわたって関東を揺るがした永正の乱は、事実上の終結を迎えたのである 9 。
政氏は久喜の居館を寺院とし、「永安山甘棠院(えいあんざんかんとういん)」と名付けた 32 。そして、自身の子(一説には弟)とされる貞岩昌永を開山として招いた 10 。現在も甘棠院の敷地には土塁や空堀の跡が残り、単なる隠居所ではなく、有事に備えた城館としての性格を備えていたことが窺える 18 。これは、政氏自身、あるいは彼を担ごうとする勢力が、再起の可能性を完全には捨てていなかったことを示唆している。彼の晩年は、単なる敗者の隠遁生活ではなく、完全に無力化されたわけではない「権威の残滓」を保持し続けた、静かなる政治的営為であったとも解釈できる。
永正17年(1520年)、政氏は古河城を訪れ、公方の座を奪った息子・高基と面会したと伝えられている 13 。これは形式上の「和解」であったが、その実態は、高基の古河公方としての地位を追認させられるという、敗者としての最後の儀礼であった可能性が高い。高基側からすれば、父という対抗勢力の象徴を完全に無力化し、自らの正統性を確立するための最終的な政治的措置であり、政氏の存在そのものが、高基にとっては最後まで潜在的な脅威であり続けたのである。
終焉の地、久喜
享禄4年7月18日(1531年8月30日)、足利政氏は、波乱に満ちた生涯を久喜の甘棠院にて閉じた 9 。享年は66歳、あるいは70歳であったとされる 11 。彼の墓所は甘棠院の境内に五輪塔として現存し、「甘棠院殿吉山長公大禅定門」という法名が刻まれ、埼玉県の史跡に指定されている 31 。父から受け継いだ権威を守ろうと戦い続け、結果としてその権威を自ら失墜させた悲劇の公方は、関東の片隅で静かにその生涯を終えたのである。
第四章:文化人としての足利政氏 — 乱世に咲いた教養
武将としての足利政氏の生涯は、対立と敗北に彩られたものであったが、その一方で、彼は文化の庇護者として、関東の文化史に特筆すべき足跡を残している。政氏の治世は、歴代古河公方の中でも文化活動が最も充実していた時期と評価されている 13 。これは、応仁の乱以降、戦乱の続く京都を逃れた公家や僧侶、文化人たちが、安定と庇護を求めて地方の有力大名のもとへ下向するという、当時の大きな文化的潮流を反映したものであった。
政氏の文化活動を象徴するのが、連歌の第一人者として天下にその名を知られた猪苗代兼載(いなわしろけんさい)との深い交流である 13 。兼載は晩年、公方の侍医であった田代三喜の治療を受けるために古河を訪れ、永正7年(1510年)にこの地で亡くなるまで、政氏の厚い庇護を受けた 13 。
二人の交流の深さは、残された資料からも明らかである。兼載の句集『園塵(えんじん)』には政氏を詠んだ歌が収録されており、その内容から兼載が政氏の「殿中」に直接伺候し、親密な関係を築いていたことがわかる 13 。さらに兼載は、政氏に対して『景感道』や『連歌四十四条書』といった連歌の秘伝や理論に関する書物、そして『古川(古河)公方様江進上連歌』と題された小句集を献上している 13 。これは、二人が単なる庇護者と文化人という関係に留まらず、連歌における師弟に近い関係にあったことを強く示唆している。
政氏のこうした文化後援は、単なる個人的な趣味や教養の表れとしてのみ捉えるべきではない。それは、失われつつある政治的・軍事的な実権を、文化的な権威、すなわち「文化資本」によって補強・正当化しようとする、高度な政治戦略であったと分析できる。戦国時代において、武力だけでなく、家格や教養といった文化的な権威もまた、大名の正統性を支える重要な要素であった。政氏は、関東の覇権を巡る争いや息子との内紛によって、その政治的実権を徐々に失いつつあった。このような状況下で、当代最高の文化人である猪苗代兼載を自らの宮廷に招き、庇護することは、「自分こそが関東における正統な支配者であり、文化の中心である」と内外に宣言する強力なメッセージとなった。
政治的な権力が不安定化するほど、それを補う文化的な権威の重要性は増す。政氏の文化活動は、彼の政治的苦境と表裏一体の関係にあり、失墜していく権威を維持するための必死の試みであったと解釈することができる。乱世の敗者として歴史に名を残す一方で、彼が庇護した文化は、古河の地に関東文化の一つの黄金期をもたらしたのである。
終章:歴史的評価 — 伝統的権威の終焉と次代への遺産
足利政氏の生涯は、中世的な権威が戦国的な実力主義に取って代わられる、日本の歴史における大きな転換点を象徴している。彼は、父・成氏が享徳の乱という激しい戦いの中で築き上げた「古河公方」という関東における伝統的権威の守護者たらんとした。上杉氏との連携を重視し、新興勢力を敵視した彼の外交方針は、全てこの文脈で理解することができる 13 。
しかし、時代は既に、家格や伝統よりも実力が支配する戦国乱世へと大きく舵を切っていた。伊豆・相模から急速に勢力を伸張する後北条氏(伊勢氏)の台頭という時代の大きな変化に対応できず、むしろ旧来の秩序を乱す者として敵視したことが、彼の最大の政治的失敗であったと言わざるを得ない 13 。
そして、その失敗を決定的なものにしたのが、嫡男・高基との対立、すなわち永正の乱であった。この内紛は、古河公方家の権威を内部から崩壊させ、その権威の「空洞化」を招いた 11 。公方家は、宇都宮氏や簗田氏といった有力な国人領主たちの勢力争いの道具へと転落し、関東の政治的中心としての地位を完全に失ったのである 17 。
皮肉なことに、政氏が引き起こした関東の混乱は、結果として後北条氏という新たな覇者が登場するための「揺り籠」の役割を果たしてしまった。古河公方家と両上杉氏が、長享の乱と永正の乱という二つの長期にわたる内紛で互いに消耗している間に、後北条氏は着実に関東へ進出する基盤を固めていったのである 13 。
総括すれば、足利政氏は、旧時代の価値観に生きた悲劇の武将であった。彼の政治的判断は、常に「古河公方」という伝統的権威の維持を目的としていたが、その行動こそが権威の失墜を早めるという自己矛盾に満ちていた。彼は、室町時代的な権威秩序が崩壊し、戦国大名による新たな支配体制が確立される過渡期に生きた。そして、意図せずして旧時代の幕引き役となり、次代の扉を開ける役割を担った人物として、歴史に記憶されるべきである。彼の敗北と流転の生涯は、一個人の悲劇に留まらず、一つの時代そのものの終焉を物語っている。
引用文献
- 享徳の乱~関東でひと足早く始まった戦国時代! - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9876/
- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/
- 享徳の乱(房顕の時代) - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%EF%BC%88%E6%88%BF%E9%A1%95%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%EF%BC%89
- 武蔵久喜 嫡男高基との権力争いに敗れ隠居を余儀なくされた古河第二代公方『足利政氏居館』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11105862
- 永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2min.html
- 古河公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9
- 簗田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%97%E7%94%B0%E6%B0%8F
- 武家家伝_簗田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yanada_k.html
- 足利政氏 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AshikagaMasauji.html
- 足利政氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E6%B0%8F
- 足利政氏(あしかがまさうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E6%B0%8F-25218
- 足利政氏- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E6%B0%8F
- 足利政氏 - 箕輪城と上州戦国史 http://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E6%B0%8F
- 武家家伝_山内上杉氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/y_uesugi.html
- 立河原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 古河公方足利氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%B0%8F
- 【永正の乱】 https://higashiyamatoarchive.net/ajimalibrary/00%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E3%80%90%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%91.html
- 足利政氏館 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/011saitama/214masauji/masauji.html
- 本家と分家がつぶし合い、上杉家の抗争「長享の乱」 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50856?page=3
- 長享の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/CyoukyouNoRan.html
- 10分で読める歴史と観光の繋がり 東国に誕生した日本初の戦国大名・北条早雲、京では足利将軍が追い落とされる明応の政変/ゆかりの天下の険箱根山と箱根湯本温泉、難攻不落の小田原城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/02/15/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%B9%95%E9%96%8B/
- 永正の内訌 (下野宇都宮氏) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%8C_(%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F)
- 「宇都宮氏一族の群像」宇都宮の錯乱。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403310014/
- 「宇都宮氏一族の群像」佐竹義峰との覇権争い。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403310015/
- 竹林の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/tosyu-yanada.html
- 足利政氏のとき。 古河公方政氏の時代 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/3shou/3shou_1/3shou_1.html
- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
- 宇都宮錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1
- 令和4年度特別展 「我、関東の将軍にならん-小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏-」 https://www.city.chiba.jp/kyodo/tenji/kikakutenji/tokubetsu_2022_01.html
- 久喜館(足利政氏館跡) ※現在の甘棠院 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/saitama/asikaga-masauji-kantouin.html
- 甘棠院 | 春日部・越谷・久喜の観光スポット | AVA Travel(アバトラベル) https://travel.ava-intel.com/jp/kanto/saitama/kasukabe/spot/5493755/
- 県指定 足利政氏館跡及び墓 - 久喜市 https://www.city.kuki.lg.jp/miryoku/rekishi_bunkazai/bunkazai/1002311/1006129.html