足利義稙
足利義稙は二度将軍となり、二度追放された不屈の将軍。明応の政変で失脚後、大内義興の支援で復帰するも、阿波で病没。将軍親政を目指した。
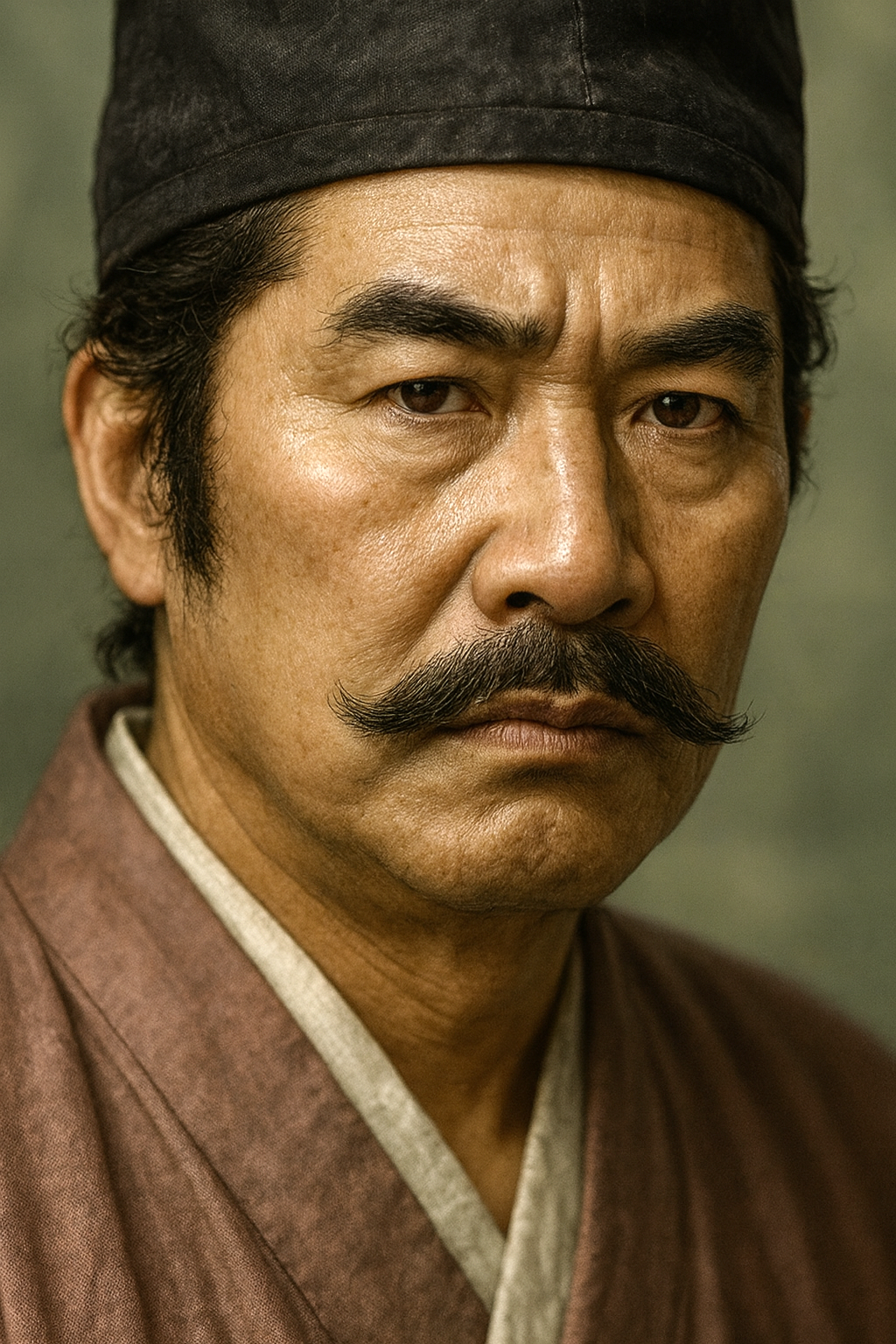
足利義稙:戦国に生きた不屈の将軍、その流転と闘争の生涯
序章:戦国乱世に翻弄された「不屈の将軍」
1. はじめに:二度、将軍になった男
室町幕府第10代将軍、足利義稙(あしかが よしたね)。彼の名を歴史に深く刻むのは、史上唯一、二度にわたり征夷大将軍の座に就き、そして二度ともその座を追われたという、他に類を見ない特異な経歴である 1 。その生涯は、京都を追われ各地を流浪したことから「流れ公方(ながれくぼう)」、あるいは淡路や阿波に拠ったことから「島公方(しまくぼう)」といった、流転と苦難を象徴する異名で長らく語られてきた 2 。
しかし、彼を単なる「無力な傀儡」として片付けることは、その実像を見誤ることになる。本報告書は、こうした従来の評価に留まらず、近年の研究成果を踏まえ、失墜した将軍権威の回復という一貫した目標のために生涯を捧げた、不屈の意志を持つ政治家としての足利義稙の実像に、多角的な視点から迫ることを目的とする 4 。彼の人生は、時代の激流に翻弄されながらも、それに抗い続けた一人の人間の壮絶な闘争の記録なのである。
2. 足利義稙 略年表
義稙の波乱に満ちた生涯を理解するため、まずその主要な出来事を年表形式で概観する。彼の頻繁な移動、改名、そして目まぐるしく変わる政治的状況は、この時代の混沌を象徴している。
|
西暦 (和暦) |
年齢 |
主な出来事 |
関連人物 |
官位 |
|
1466 (文正元) |
1歳 |
足利義視の子として美濃で誕生。初名は義材(よしき) 6 。 |
足利義視, 日野良子 |
- |
|
1467 (応仁元) |
2歳 |
応仁の乱が勃発。父・義視は西軍の盟主となる 7 。 |
足利義政, 日野富子 |
- |
|
1487 (長享元) |
22歳 |
元服。従五位下・左馬頭に叙任される 3 。 |
- |
従五位下・左馬頭 |
|
1489 (延徳元) |
24歳 |
9代将軍・足利義尚が死去。後継者候補となる 7 。 |
足利義尚 |
- |
|
1490 (延徳2) |
25歳 |
8代将軍・足利義政の死後、第10代征夷大将軍に就任 2 。 |
日野富子, 細川政元 |
従四位下・参議・右近衛中将 |
|
1491 (延徳3) |
26歳 |
父・足利義視が死去。近江の六角高頼を討伐(第二次六角征伐) 7 。 |
六角高頼 |
- |
|
1493 (明応2) |
28歳 |
河内へ出陣中、細川政元らのクーデター(明応の政変)で将軍職を解任される。幽閉後、越中へ脱出 7 。 |
細川政元, 足利義澄, 畠山政長 |
- |
|
1498 (明応7) |
33歳 |
越中から越前へ移る。名を義尹(よしただ)と改める 7 。 |
朝倉貞景 |
- |
|
1499 (明応8) |
34歳 |
上洛に失敗し、周防の大内義興を頼る 7 。 |
大内義興, 畠山尚順 |
- |
|
1508 (永正5) |
43歳 |
大内義興に奉じられ上洛。15年ぶりに将軍職に復帰 7 。 |
細川高国, 細川澄元 |
従三位・権大納言 |
|
1511 (永正8) |
46歳 |
船岡山の戦いで、足利義澄・細川澄元軍に勝利 10 。 |
大内義興, 細川高国 |
- |
|
1513 (永正10) |
48歳 |
名を義稙(よしたね)と改める 2 。 |
- |
- |
|
1521 (大永元) |
56歳 |
管領・細川高国と対立し、京都を出奔。淡路へ逃れる 2 。 |
細川高国, 足利義晴 |
- |
|
1523 (大永3) |
58歳 |
阿波国撫養にて病没 1 。 |
足利義維 |
権大納言 |
|
1535 (天文4) |
- |
死後、従一位・太政大臣を追贈される 13 。 |
- |
贈従一位・太政大臣 |
第一部:将軍への道程 ― 応仁の乱の遺産と名門の血筋
第1章:誕生と血統 ― 足利義視の子として
足利義稙の生涯を理解する上で、その出自と彼が生まれた時代背景は決定的に重要である。文正元年(1466年)、義稙(初名:義材)は、室町幕府8代将軍・足利義政の弟である足利義視(よしみ)と、義政の正室・日野富子の実妹である日野良子(よしこ)との間に生を受けた 1 。この血筋は、彼を将軍家の直系に極めて近い、高貴な存在として位置づけた。9代将軍となる足利義尚とは従兄弟であり、将軍夫妻の甥という、幕府の中枢に最も近い血縁関係にあったのである 11 。
しかし、この高貴な血統は、彼に安寧をもたらすどころか、生後間もなく始まった応仁・文明の乱(1467-1477)の渦中へと彼を投げ込んだ。乱の直接的な原因の一つは、将軍家の後継者問題であった。子に恵まれなかった義政は、弟である義視を還俗させて養子とし、次期将軍に定めた。ところがその直後、義政と富子の間に義尚が誕生し、後継者問題が紛糾する 8 。この対立構造の中で、義視は山名宗全率いる西軍の盟主として、兄・義政や細川勝元率いる東軍と骨肉の争いを繰り広げることとなった。
義稙は、物心つく前から父と共に西軍の象徴として、戦乱の京都で過ごした。応仁の乱が終結した後も、父・義視は幕府内で孤立し、義稙を連れて美濃守護・土岐成頼を頼って下向するなど、安定とは程遠い幼少期・青年期を送った 7 。この経験は、義稙の精神に深く刻み込まれた。彼は、将軍という地位がいかに脆弱であり、有力な家臣の動向によって容易に覆されうるものであるかを、父・義視の苦悩を通じて痛感していた。父が果たせなかった権力の確立、そして有力守護大名に左右されない将軍親政の実現は、義稙にとって生涯をかけた悲願となったのである。
第2章:将軍就任の経緯
長享3年(1489年)、9代将軍・足利義尚が近江の六角征伐の陣中にて、わずか25歳で病没した 7 。この突然の死は、室町幕府を再び深刻な後継者問題に直面させた。
後継候補として有力視されたのは二人の人物であった。一人は、応仁の乱以来、父と共に雌伏の時を過ごしていた足利義視の嫡男・義材(後の義稙)。もう一人は、関東を統治する堀越公方・足利政知の子で、当時は僧籍にあった清晃(せいこう、後の11代将軍・義澄)である 8 。
ここで政治の舞台で決定的な役割を果たしたのが、義尚の母であり、義材の伯母にあたる日野富子であった。驚くべきことに、かつて夫・義政と対立し、義材の父・義視を西軍の盟主にまで追い込んだ富子が、今度は甥である義材を次期将軍として強力に後援したのである 2 。一方で、大御所としてなおも権力を保持していた義政や、管領・細川政元は、清晃を推していたとされる 8 。富子の選択の裏には、複雑な政治的計算があった。直接的な血縁者であり、若く政治基盤の弱い義材の方が、幕府の実権を自らが握り続ける上で、より御しやすい存在だと判断した可能性が高い。
延徳2年(1490年)、最大の障壁であった大御所・義政が死去すると、富子の意向が最終的に通り、義材は25歳で第10代征夷大将軍に就任した 2 。父・義視の無念を晴らすかのように将軍の座に就いた義材であったが、その選定過程で生じた管領・細川政元との深刻な軋轢は、彼の未来に暗い影を落とす、避けられない対立の火種として燻り続けることになったのである。
第二部:権力確立の試みと挫折 ― 明応の政変
第3章:将軍親政への野心
将軍に就任した義稙(当時は義材)は、歴代将軍が直面した権威の形骸化という問題に、正面から立ち向かう決意を固めていた。彼は、管領や有力守護大名の意のままに動く「お飾り将軍」の立場を断固として拒否し、将軍自らが政治と軍事の最高権力者として君臨する「将軍親政」の実現に強い意欲を燃やした 1 。
その野心を具体的な行動で示したのが、積極的な軍事行動であった。就任翌年の延徳3年(1491年)、最大の政治的後ろ盾であった父・義視が死去すると、義稙は自らの権威を幕府内外に誇示する必要に迫られた。彼は、従兄弟の義尚が生涯をかけても成し得なかった近江守護・六角高頼の討伐(第二次六角征伐)を自ら主導する 8 。多くの守護大名を動員した「雲の如し、霞の如し」と評される大軍勢を前に、六角氏は戦わずして敗走。義稙は京都に凱旋し、将軍の武威を天下に示した。これは、将軍こそが幕府軍の最高指揮官であることを再確認させる、計算された政治的パフォーマンスであった。
勢いに乗る義稙は、明応2年(1493年)、さらに権威を示すべく、幕府に忠実であった管領・畠山政長を支援し、その宿敵である畠山基家(義就の子)を討伐するため、自ら軍を率いて河内国へと出陣した 8 。しかし、この一連の行動は、将軍の権力基盤を強化する一方で、幕府の伝統的な権力構造を根底から揺るがすものであった。将軍が「征夷大将軍」という称号の文字通り、軍事の最高指導者として振る舞うことは、幕府の軍事・政治機構を掌握することで権力を維持してきた管領・細川政元の存在意義を直接的に脅かすものであった。義稙の積極的な親政への動きは、政元との破滅的な対立を不可避なものとしていたのである。
第4章:明応の政変 ― クーデターによる将軍追放
義稙の河内出陣は、彼の親政志向に強い危機感を抱いていた管領・細川政元にとって、千載一遇の好機となった。政元は、将軍が幕府全体の意向を無視し、畠山氏の内紛という「私闘」に介入したと見なし、これを将軍廃立の正当な理由とした 8 。
明応2年(1493年)4月、政元は、かつて義稙を後援した日野富子や政所執事・伊勢貞宗らと密かに連携し、義稙が京都を留守にしている隙を突いて電撃的にクーデターを決行した。彼は、かねてより擁立を画策していた足利義澄を新たな将軍として擁立し、京都を完全に制圧したのである 8 。
この「明応の政変」は、日本史上、画期的な事件であった。家臣である管領が、主君である現職の将軍を武力で追放し、新たな将軍を擁立するという前代未聞の事態は、「下剋上」の風潮を決定的なものとし、室町幕府がこれまでかろうじて維持してきた権威を根底から覆した 9 。戦国時代の本格的な扉を開いた政変として、歴史に深く刻まれている。
河内の陣中で味方に次々と離反され孤立無援となった義稙は、なすすべもなく捕縛され、京都の龍安寺に幽閉された。日野富子による毒殺の危機にも瀕したが、側近らの決死の手引きによって辛くも京を脱出することに成功する 1 。ここから、彼の長く過酷な流浪の人生が始まったのである。
明応の政変 主要人物関係図
このクーデターの複雑な人間関係を理解するために、主要人物の関係性を以下に示す。
|
人物 |
立場・役割 |
義稙との関係 |
備考 |
|
足利義稙 |
第10代将軍 |
本人 |
河内出陣中に追放される |
|
細川政元 |
管領 |
対立 |
クーデター首謀者。義稙の親政志向を危険視 |
|
足利義澄 |
堀越公方の子 |
対立 |
政元に擁立され、第11代将軍となる |
|
日野富子 |
義稙の伯母 |
支持 → 裏切り |
当初は義稙を後援したが、政変では政元に同調 |
|
伊勢貞宗 |
政所執事 |
対立 |
幕府官僚として政元に協力 |
|
畠山政長 |
管領 |
忠臣 |
義稙派。河内で敗れ自刃 |
|
畠山基家 |
畠山義就の子 |
討伐対象 |
義稙の河内出兵の標的 |
|
畠山尚順 |
政長の子 |
忠臣 |
父の死後も義稙を支持し続ける |
第三部:流浪と再起 ―「流れ公方」から「不死鳥」へ
第5章:越中公方府の樹立
京都を脱出した義稙が目指したのは、北陸の地であった。彼は、明応の政変で自刃した忠臣・畠山政長の重臣であった神保長誠を頼り、越中国射水郡放生津(ほうじょうづ、現在の富山県射水市)へと下向した 17 。ここで義稙は、単なる亡命者として身を潜めるのではなく、驚くべき政治行動に出る。彼は現地の正光寺を仮の御所とし、京都の幕府に対抗する亡命政権、通称「越中公方府(えっちゅうくぼうふ)」、あるいは「越中幕府」を樹立したのである 18 。
これにより、京都の義澄政権と越中の義稙政権という、二つの幕府(公権)が同時に並立する、日本の歴史上極めて異例の事態が発生した 17 。義稙は、越中から「我こそが正統な将軍である」として、クーデターの首謀者・細川政元を討伐せよとの御教書(命令書)を全国の守護大名に発した。これに対し、能登の畠山氏、越前の朝倉氏、加賀の富樫氏といった北陸の諸大名が参集して忠誠を誓い、遠く九州の大友氏までもが協力の意思を示した 17 。
この「越中公方府」の樹立は、義稙が不屈の政治家であったことを如実に物語っている。彼は、追放された後も将軍としての自らの正統性を決して疑わず、幕府の公的文書を発給し続けることで、その権威を維持しようと試みた。この行動は、全国の大名に京都方か越中方かの選択を迫るものであり、畿内の一政変に過ぎなかったはずの明応の政変を、全国規模の争乱へと拡大させる結果を招いた。それは、戦国時代の分裂と混沌を加速させる、重要な一歩であった。
第6章:西国への活路 ― 大内義興との連携
越中で再起の基盤を築いた義稙であったが、上洛への道は遠かった。明応7年(1498年)、彼は京都への距離がより近い越前へと拠点を移し、守護・朝倉貞景を頼った。この際、過去の不運を断ち切り、再起にかける強い決意を示すため、名を「義材」から「義尹(よしただ)」へと改めている 7 。しかし、朝倉氏の支援は限定的であり、翌年には忠臣・畠山尚順(政長の子)と共に京を目指すも、細川政元軍に阻まれ失敗に終わる。
再び行き場を失った義尹は、起死回生の一手として、西国へと活路を求めた。明応8年(1499年)、彼は中国地方から九州北部にまで勢力を広げる西国随一の太守・大内義興を頼り、その本拠地である周防国山口へと下向した 7 。
この亡命は、双方の利害が一致した高度な政治的判断であった。大内義興にとって、追放されたとはいえ正統な血筋の将軍を庇護することは、宿敵である管領・細川氏の中央政界における権威を揺るがし、自らが幕政の主導権を握るための絶好の切り札であった。義興は義尹を丁重に迎え入れ、その強大な軍事力と、日明貿易などで蓄積した豊かな経済力を背景に、彼の将軍復帰を全面的に支援することを約束した 11 。
義尹は、「西の京」と称されるほどの繁栄を誇った文化都市・山口の大内館に身を寄せ、約10年近くにわたり、京都の政情が変化するのを待つことになる。この長い雌伏の期間は、彼の不屈の精神をさらに鍛え上げ、再起への執念を燃やし続けるための重要な時間となった 7 。
第7章:二度目の将軍宣下
長く続いた流浪の日々に、ついに転機が訪れる。永正4年(1507年)、義尹を追放した張本人であり、幕府の実権を20年近く握り続けた管領・細川政元が、後継者を巡る家中の内紛(細川澄之、澄元、高国の三者間の争い)の末に、家臣によって暗殺されるという事件が起きた(永正の錯乱) 1 。絶対的な権力者の突然の死により、細川京兆家は深刻な内紛状態に陥り、京都の政治権力に巨大な空白が生まれたのである。
この千載一遇の好機を、義尹と大内義興が見逃すはずはなかった。永正5年(1508年)、義尹は大内義興に奉じられ、数万と号する大軍を率いて、悲願の上洛を果たすべく山口を出発した 1 。大内軍の圧倒的な軍事力を前に、京都を守る11代将軍・足利義澄と管領・細川澄元は戦わずして近江へと逃亡した。
こうして義尹は、明応の政変から15年ぶりに京都への帰還を果たした。そして朝廷から再び征夷大将軍に任命され、将軍職への復帰を成し遂げたのである 7 。一度追放された将軍が、自らの政治力と有力大名の支援によって実力で返り咲くという、まさに不死鳥のごとき前代未聞の快挙であった。この成功は、彼の執念と、将軍という地位が依然として持つ政治的価値を雄弁に物語っている。
第四部:再度の権力闘争と終焉
第8章:第二次政権の権力構造と限界
15年ぶりに将軍職に復帰した義稙(永正10年(1513年)に義尹から改名)であったが、その政権は盤石なものではなかった。それは、将軍・義稙を頂点としつつも、実質的な軍事権力を掌握する管領代・大内義興と、幕府の公的な管領職にある細川高国(政元の養子の一人で、澄元と対立する派閥)という、三者の協力関係の上に成り立つ、極めて危うい均衡の連合政権であった 21 。義稙の権威は、大内義興の強大な軍事力に大きく依存しており、彼の悲願である将軍親政の実現には、依然として大きな制約が伴っていた。
この連合政権の結束を試すかのように、永正8年(1511年)、近江へ逃れていた前将軍・義澄と細川澄元が京都奪還を目指して侵攻してきた。義稙・義興・高国連合軍は、これを京都北部の船岡山で迎え撃ち、決定的な勝利を収めた(船岡山の戦い) 12 。この戦いの直前に義澄が病死したこともあり 24 、敵対勢力は一時的に後退を余儀なくされ、義稙政権は数年間の比較的安定した時期を迎えることになった。
第二次義稙政権 権力構造図
この時期の政権の脆弱な構造は、以下の図で示すことができる。三者が互いに協力しつつも、潜在的な対立要因を内包していた。
|
権力層 |
人物 |
役割・権力基盤 |
|
頂点 |
将軍 足利義稙 |
正統性の源泉 。幕府の公式な首長としての権威。 |
|
二大支柱 |
管領代 大内義興 |
実質的な軍事力の源泉 。西国の大軍を率いる最高軍事権力者。 |
|
|
管領 細川高国 |
幕府内での公的地位 。細川京兆家の家督として管領職を保持。 |
この構造は、共通の敵である義澄・澄元派が存在する間は機能したが、その脅威が薄れると、義興と高国の間、そして将軍親政を目指す義稙とそれを支える二人の実力者との間の緊張関係が表面化する危険性を常に孕んでいた。
第9章:細川高国との対立と最後の都落ち
第二次政権の危うい均衡は、永正15年(1518年)に崩壊の時を迎える。政権の最大の軍事的支柱であった大内義興が、領国である出雲・安芸方面で勢力を急拡大する尼子経久への対処を迫られ、10年以上に及んだ在京生活を終えて周防へと帰国したのである 21 。
義興という巨大な重石が取れたことで、京都の権力バランスは一変した。残された細川高国は、幕府内における唯一の有力な軍事権力者となり、その権力を独占しようと動き始めた(専横) 1 。あくまで将軍親政の実現を目指す義稙が、一介の管領に過ぎない高国の専横を許容するはずはなかった。両者の対立は日増しに先鋭化し、政権は内部から崩壊の危機に瀕した 27 。
決裂は永正17年(1520年)に訪れた。細川澄元・三好之長軍が摂津に侵攻し、高国がこれに敗れて近江へ逃亡すると、義稙は高国を完全に排除する好機と捉えた。彼は、敵であるはずの澄元と連携するという、常識を覆す驚くべき奇策に打って出た 10 。これは、自らの手で幕政の実権を取り戻すための、最後の大きな賭けであった。
しかし、この賭けは無惨な失敗に終わる。近江で六角定頼の支援を得て勢力を回復した高国は、ただちに反撃に転じ、京都近郊の等持院の戦いで三好之長を討ち取った。指導者を失った澄元も、失意のうちに阿波へ逃れた後に病死した 10 。高国との関係が修復不可能なまでに悪化し、完全に孤立無援となった義稙は、大永元年(1521年)、ついに高国によって京都を追われることとなった。これが、彼の二度目にして最後の都落ちであった。彼は和泉の堺を経て、淡路へと逃れた 7 。高国は、かつての将軍・義澄の遺児である亀王丸を擁立し、第12代将軍・足利義晴として幕府を掌握した。
第10章:阿波での終焉と「阿波公方」の源流
二度目の追放後、義稙は淡路から海を渡り、皮肉にもかつての宿敵・細川澄元の本拠地であった阿波国(現在の徳島県)へと身を寄せた。阿波の細川氏の庇護のもと、彼はなおも再起の機会をうかがった 1 。この時期、義稙は自らの血統が途絶えることを見越し、一つの重要な政治的布石を打つ。前将軍・義澄の子であり、現将軍・義晴の兄にあたる足利義維(よしつな)を養子に迎えたのである 29 。これは、自らが体現してきた「正統な将軍家」の血脈と、京都の幕府に対抗する立場を、次代に継承させようとする最後の意志表示であった。
しかし、その望みが叶うことはなかった。大永3年(1523年)4月9日、義稙は阿波国撫養(むや)の地にて、58年の波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。その終焉の地は、後に「将軍塚」として今に伝えられている 29 。
義稙の死は、彼の闘争の終わりではなかった。彼が残した政治的遺産は、その後も半世紀にわたって畿内の政治を揺るがし続ける。彼の養子となった義維は、阿波の地で「阿波公方」として反高国勢力の象徴として擁立された 29 。後に細川晴元(澄元の子)や三好元長に担がれて和泉国堺に拠点を移し、「堺公方」として京都の義晴政権と激しく対立する 32 。義稙個人の復権闘争は、彼の死後、「阿波公方家」という制度化された反主流派として継承され、足利将軍家の分裂を決定的なものとした。彼の不屈の生涯が、戦国時代の政治力学に与えた影響は、計り知れないほど大きかったのである。
終章:足利義稙の歴史的再評価
1. 従来の評価 ―「流れ公方」のレッテル
足利義稙に対する歴史的評価は、長らく否定的なものであった。二度にわたり将軍職を追われ、生涯の多くを流浪の身で過ごしたことから、「流れ公方」の異名が象徴するように、「無力で無能」「有力大名に翻弄された傀儡将軍」というイメージが定着していた 4 。彼の行動は、時代の大きな流れに抗うことができなかった敗者のそれと見なされ、戦国時代の将軍権威失墜の典型例として語られてきたのである。
2. 近年の研究動向と新たな義稙像
しかし近年、山田康弘氏の著作『戦国に生きた不屈の大将軍 足利義稙』をはじめとする研究の進展により、史料を丹念に読み解くことで、こうした旧来の評価は大きく見直されつつある 4 。
新たな研究が描き出す義稙像は、単なる傀儡ではない。彼は、応仁の乱以降、地に堕ちた将軍権威の回復と、将軍親政の実現という明確な政治目標を一貫して持ち続けた、極めて強い意志と行動力を備えた「不屈の大将軍」として再評価されている 4 。彼の生涯における全ての行動、すなわち自ら軍を率いた六角征伐や河内出兵、越中公方府の樹立、大内義興との連携、そして細川高国との最後の対決に至るまで、その全てがこの一貫した目的意識によって説明可能である。
彼の生涯は、室町幕府が内包していた構造的欠陥、すなわち形骸化する将軍の公的権威と、実力を持つ管領・守護大名との権力闘争という根源的な矛盾に、一身をもって立ち向かった悲劇として捉え直されている 35 。彼は、時代の流れにただ翻弄されたのではなく、その流れを自らの手で変えようと、最後まで戦い抜いたのである。
3. 結論:戦国乱世に刻んだ不屈の足跡
足利義稙は、最終的に自らの悲願を達成することはできなかった。彼の目指した将軍親政は夢と消え、幕府の権威は彼の死後も回復することなく、戦国乱世はさらに深まっていった。
しかし、彼の存在と30年にわたる不屈の闘争が、歴史に与えた影響は決して小さくない。彼が起こした行動は、明応の政変を単なる一時的なクーデターで終わらせず、将軍家の分裂という政治構造を半世紀以上にわたって固定化させ、戦国時代の政治力学そのものを大きく規定する要因となった。
彼は、滅びゆく権威にただ流されたのではなく、その権威を自らの手で再興しようと、執念ともいえる意志で戦い抜いた人物である。その極めてドラマチックで波乱に満ちた生涯は、歴代足利将軍の中でも際立った個性を放ち、近年の歴史ファンの人気投票では、初代将軍・足利尊氏に次ぐ第2位にランクされるなど、現代の我々にも強い感銘を与えている 36 。足利義稙の人生は、既存の権威が崩壊し、個人の意志と実力が時代の行方を左右する「戦国」という時代の本質を、誰よりも早く、そして誰よりも痛切に体現したものであったと言えるだろう。彼の不屈の足跡は、敗者としてではなく、時代の変革期に抗い続けた一人の政治家の壮絶な記録として、記憶されるべきである。
引用文献
- 室町幕府10代将軍/足利義材|ホームメイト https://www.meihaku.jp/muromachi-shogun-15th/shogun-ashikagayoshiki/
- 足利義稙(アシカガヨシタネ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99-14301
- 「足利義稙」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99
- 『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』 | 奈良県立図書情報館 https://www.library.pref.nara.jp/reference/kininaru/2222
- 【楽天市場】足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍 (中世武士選書) [ 山田康弘 ](楽天ブックス) https://review.rakuten.co.jp/item/1/213310_18031733/1.1/?l2-id=pdt_review_list_1
- 足利義政|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1166
- 足利義材の家系図・年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89133/
- 明応の政変 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/meio-no-seihen/
- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/meio-no-seihen/#:~:text=%E3%80%8C%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89%E3%80%8D%EF%BC%88,%E3%81%B8%E3%81%A8%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 足利氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/asikaga.html
- 足利義稙(義材) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/ashikaga-yoshitane/
- 「船岡山合戦(1511年)」細川高国VS細川澄元の決戦?足利義澄の急死で高国勝利 https://sengoku-his.com/419
- 足利義稙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99
- 明応の政変〜戦国時代の幕開けとなったクーデターをわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/643/
- 【歴代征夷大将軍総覧】室町幕府10代・足利義材――幕府崩壊劇の主役となった「流れ公方」 1466年~1523年 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2021/05/28/180000
- 明応の政変~クーデター勃発で将軍家が分裂! - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9899/
- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89
- 足利義稙 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn18590
- 足利将軍がやってきた(1) | コラム - 射水市新湊博物館 https://shinminato-museum.jp/docs/column/14490/
- [合戦解説] 10分でわかる船岡山の戦い 「足利将軍家・管領細川家が二派に分かれて激突」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tubNU2MEyHM
- 「大内義興」乱世の北九州・中国の覇権を確立。管領代として幕政にもかかわった西国最大の大名 https://sengoku-his.com/811
- 細川高国(ホソカワタカクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD-133261
- 船岡山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6
- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175
- 大内義興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E8%88%88
- 大内氏遺跡|義興が築いた庭園と城塞。なぜ戦国時代西国の覇者になれた? - 史跡ナビ https://shisekinavi.com/oouchishiiseki/
- 第10代将軍/足利義材|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/72420/
- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74
- 阿波平島公方 ~征夷大将軍になりたかった男達 https://akahigetei.weblike.jp/rekitan/r3.html
- 堺公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%85%AC%E6%96%B9
- 「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(後編)澄元方の上洛戦敗退と将軍義稙の淡路出奔事件の顛末 - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/entry/2018/01/19/120901
- 「足利義稙」島公方・流れ公方と呼ばれた室町幕府第10代将軍 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/214
- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%85%AC%E6%96%B9#:~:text=%E7%BE%A9%E7%B6%AD%E3%83%BB%E6%99%B4%E5%85%83%E3%81%AE,%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AD%AB%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
- 山田康弘『足利義輝・義昭 天下諸侍、御主に候』(ミネルヴァ書房)の感想 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/ashikagayoshiteruyoshiaki-m
- 『足利義稙-戦国に生きた不屈の大将軍-』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/b/4864031916
- 〝足利将軍総選挙〟結果発表|戎光祥出版 - note https://note.com/ebisukosyo/n/ndef56f869a83