長野稙藤
長野稙藤は伊勢の国人領主。北畠氏と争い、将軍家と結び一族の独立を保つも、北畠氏の圧力で養子を迎え従属。最期は暗殺説がある。
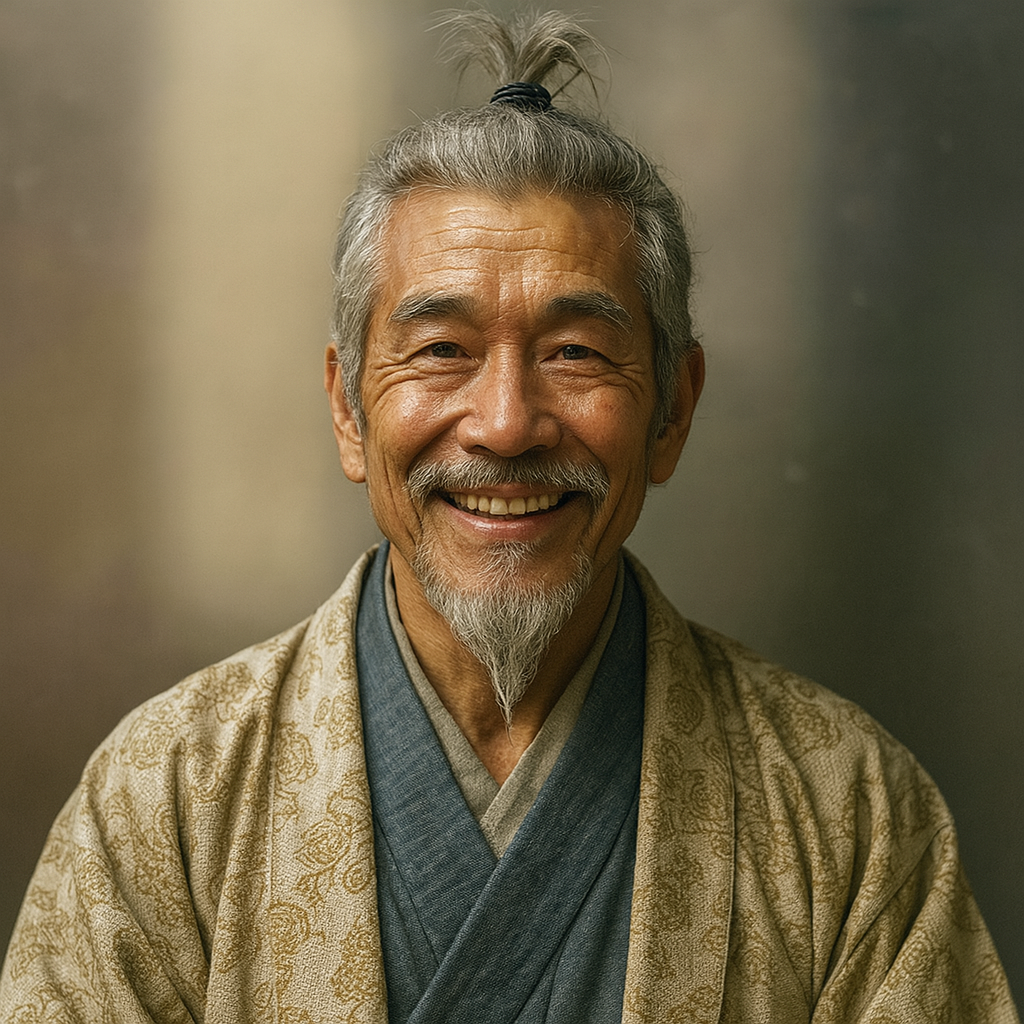
伊勢国人 長野稙藤 ― 北畠氏との相克と一族の行方
序章:中伊勢の雄、長野稙藤
戦国時代の伊勢国は、守護の権威が及ばず、数多の国人領主が群雄割拠する動乱の地であった。その中にあって、伊勢国の中央部、安濃郡・奄芸郡に強固な地盤を築き、伊勢国司を称する南伊勢の雄・北畠氏と長年にわたり熾烈な覇権争いを繰り広げた一族がいた。長野工藤氏である。本報告書は、この長野工藤氏の第14代当主として、一族の最盛期から衰亡への転換点という激動の時代を生きた武将、長野稙藤(ながの たねふじ)の生涯を、その出自から謎に満ちた最期、そして一族のその後に至るまで、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。
長野稙藤の生涯は、単なる一地方武将の興亡史に留まるものではない。彼の人生は、室町幕府の権威が失墜し、実力主義が支配する世の中にあって、伝統的な領主がいかにして生き残りを図ったかという、戦国時代の縮図を映し出している。隣接する大大名・北畠氏との絶え間ない抗争、家中の統制、そして尾張から現れた織田信長という新たな天下人による既存秩序の破壊。これらの荒波に、稙藤は如何に対峙し、どのような決断を下したのか。彼の生涯と、その背景にある長野工藤氏一族の歴史を丹念に追うことは、戦国期伊勢国の複雑な政治情勢と、その中で翻弄された国人領主の実像を理解するための重要な鍵となるであろう。
第一章:長野工藤氏の出自と伊勢国における勢力基盤
長野稙藤の人物像を理解するためには、まず彼が率いた長野工藤氏が、伊勢国においていかなる存在であったかを把握する必要がある。その出自は鎌倉時代に遡り、中伊勢に確固たる勢力圏を築き上げていた。
第一節:工藤氏の伊勢入部と長野氏の成立
長野工藤氏の祖は、藤原南家乙麿流を称する工藤氏の一族である 1 。具体的には、鎌倉初期の御家人で、『曽我物語』における曾我兄弟の仇討ちの相手として知られる工藤祐経の三男、工藤祐長がその初代とされる 1 。祐長は、伊勢国内に残存していた伊勢平氏の残党討伐の功により、鎌倉幕府から伊勢国安濃郡・奄芸郡の地頭職に補任された 1 。これが、一族の伊勢における歴史の始まりである。
その後、祐長の子である祐政が父の所領に来住し、その地の名を取って「長野氏」を名乗った 1 。これにより、伊勢における国人領主・長野氏が誕生した。他の同名の氏族と区別するため、後世の史料では、その出自である工藤の名を冠して「長野工藤氏」と呼称されることが多い 1 。
この出自は、長野工藤氏の性格を規定する上で極めて重要である。彼らは単なる在地土豪ではなく、鎌倉幕府という中央の公権力によって公式に所領の支配を認められた「地頭」を起源とする武家領主であった。この点は、同じく伊勢に勢力を張った北畠氏が、南朝方の公家として「国司」の権威を背景にしていたことと対照的である 6 。両者の権力の源泉にあるこの根本的な違いが、後に数世紀にわたって続く根深い対立の一因となったと考えられる。
第二節:中伊勢の支配体制
長野工藤氏は、安濃郡・奄芸郡(現在の三重県津市から鈴鹿市にかけての一帯)を中心に、巧みな領域支配体制を構築していた。その中核を成したのが、一族代々の居城である長野城であった。
長野城は、二代当主・長野祐藤によって文永11年(1274年)に築城されたと伝わる山城である 4 。標高540m、比高360mの峻険な山上に築かれ、伊勢と伊賀を結ぶ交通の要衝を抑える戦略的拠点であった 9 。この城は単一の城郭ではなく、山頂の本郭に加え、山腹の尾根筋に「東の城」「中の城」「西の城」と呼ばれる複数の郭群を備えた複合的な城郭であり、極めて堅固な防御施設であったことが窺える 8 。
さらに長野工藤氏の支配は、この本城だけでなく、安濃郡内に張り巡らされた庶家・家臣団の城砦ネットワークによって支えられていた 14 。一族の中でも特に有力であったのが、分部氏、細野氏、そして雲林院氏といった分家である 1 。彼らはそれぞれが居城を持ち、長野宗家を中心とする一種の連合体を形成して中伊勢を支配していた。特に雲林院氏は、『勢州軍記』などの記述から「工藤の両家督」と称されるほど宗家と並び立つ格式を持っていたとされ、単なる主従関係を超えた強固な一族結合が存在したことを示唆している 17 。
この本城と支城、そして庶家を巧みに配置した重層的な支配ネットワークこそが、長野工藤氏が南伊勢の雄・北畠氏と長年にわたり互角に渡り合うことを可能にした力の源泉であった。しかし、この一族連合体という構造は、裏を返せば、一度内部に亀裂が生じれば体制そのものが崩壊しかねない脆弱性を内包しており、この弱点が後の織田信長の侵攻時に露呈することになる。
戦国期伊勢国の主要勢力図(長野稙藤の時代)
|
勢力名 |
主要拠点 |
支配地域 |
備考 |
|
長野工藤氏 |
長野城 |
中伊勢(安濃郡・奄芸郡など) |
本報告書の主題。北朝方。 |
|
北畠氏 |
多気御所、大河内城 |
南伊勢(一志郡、飯高郡など) |
伊勢国司。南朝方。長野氏の宿敵。 |
|
関氏 |
亀山城 |
北伊勢(鈴鹿郡など) |
勢州四家の一つ。 |
|
神戸氏 |
神戸城 |
北伊勢(河曲郡など) |
関氏の庶流。後に北畠氏から養子を迎える。 |
|
伊勢神宮 |
宇治・山田 |
神宮領(度会郡など) |
寺社勢力。国人たちの侵攻に苦しむ。 |
|
六角氏 |
(観音寺城) |
(近江国) |
北伊勢の国人に影響力を行使。 |
出典: 6 を基に作成。
第三節:南北朝以来の宿敵・北畠氏
長野工藤氏の歴史を語る上で、伊勢国司・北畠氏の存在は不可分である。両家の対立は南北朝時代にまで遡り、戦国時代に至るまで伊勢国の政治情勢を大きく左右し続けた。
南北朝の動乱期において、南朝方の公家である北畠氏が伊勢国司として進出してくると、鎌倉幕府以来の地頭であった長野工藤氏は、一貫して北朝方、すなわち室町幕府方に与してこれに対抗した 1 。この政治的立場の違いが、両家の間に決定的な対立構造を生み出した。当時の軍記物である『梅松論』にも「長野工藤三郎左衛門尉」の名が見えることから、長野氏がこの時代から中央にも知られた有力な国人であったことがわかる 1 。
この対立関係は、室町時代を通じて継続した。特に応仁の乱(1467年-1477年)では、長野氏が西軍の山名方に、北畠氏が東軍の細川方にそれぞれ属し、伊勢国内で激しく争った 3 。戦国時代に入っても、両家の抗争は伊勢の覇権を巡る中心的な対立軸であり続けた。その勢力は、関氏や神戸氏と並び、「伊勢三家」あるいは「勢州四家」と称されるほど、伊勢国を代表する大身であった 16 。
第二章:長野稙藤の時代 ― 抗争と苦渋の決断
長野工藤氏が北畠氏との長きにわたる抗争の最終局面を迎えた時代、その当主の座にあったのが長野稙藤である。彼の治世は、一族の独立を賭けた激しい戦いと、その末の苦渋に満ちた決断によって特徴づけられる。
長野工藤氏略系図(稙藤周辺)
Mermaidによる関係図
長野氏祖); B --> C(...); C --> D(13代 長野通藤); D --> E( 14代 長野稙藤 ); E --> F(15代 長野藤定); E --> G(雲林院祐基
雲林院氏へ養子); H(北畠具教) --> I(長野具藤
北畠氏次男); F -.-> I; style E fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width: 4.0px;
出典: 1 を基に作成。
第一節:家督相続と将軍家との関係
長野稙藤は、永正元年(1504年)、長野工藤氏第13代当主・長野通藤の子として生を受けた 3 。幼名は金吾と伝わる 23 。
彼の名である「稙藤」は、その出自と政治的立場を雄弁に物語っている。元服に際し、当時京を追われ流浪していた室町幕府第10代将軍・足利義稙(よしたね)から「稙」の一字を、そして父・通藤から長野氏の通字である「藤」の一字をそれぞれ拝領(偏諱)し、「稙藤」と名乗ったのである 23 。戦国武将にとって、将軍から名前の一字を賜ることは極めて大きな名誉であり、中央政権との強固な結びつきを示す政治的行為であった。これは、長野氏が自らを、南朝の系譜を引く北畠氏とは異なる「幕府方」の正統な領主として位置づけ、その権威を内外に示すための重要な戦略であったことを示唆している。
享禄3年(1530年)、父・通藤の死去に伴い、稙藤は家督を相続し、長野工藤氏第14代当主となった 23 。
第二節:中伊勢の覇権を巡る攻防
稙藤が当主となった時代、南伊勢では北畠晴具、そしてその子で「剣豪国司」としても知られる北畠具教が勢力を拡大しており、両家の衝突は避けられない状況にあった 3 。稙藤は、中伊勢の支配権を巡って北畠氏との全面対決に臨むこととなる。
軍記物である『勢州軍記』などによれば、天文年間には両家の間で激しい合戦が繰り返された。天文12年(1543年)の「垂水鷺山の戦い」では、南伊勢に侵攻してきた長野藤定(稙藤の子)の軍を北畠晴具が迎え撃ち 28 、その後も天文14年(1545年)から16年(1547年)にかけて「葉野の戦い」などで一進一退の攻防が続いた 28 。
この時期、稙藤は嫡男の藤定に家督を譲って隠居したと見られるが、実権は依然として保持し、藤定と共に政務や軍事指揮を執る共同統治体制を敷いていた可能性が高い 3 。これは、強力な外敵である北畠氏に対抗するため、一族の総力を結集する必要があったことの表れであろう。また、稙藤は実子の一人である祐基を、有力な分家である雲林院氏の養子に送り込んでいる 17 。これは、嫡男に宗家を継がせつつ、重要な庶家を実子に率いさせることで一族の結束を固め、北畠氏に対抗しようとする統治者としての深謀遠慮が窺える。
第三節:勢力衰退と北畠氏への従属
長年にわたる抗争の末、両家の力関係は次第に北畠氏優位へと傾いていく。天文16年(1545年)頃からの北畠晴具による執拗な侵攻により、長野方は徐々に劣勢に立たされた 23 。さらに、智勇兼備の将であった北畠具教が家督を継ぐと、その攻勢は一層激しさを増し、長野氏は防戦一方に追い込まれていった 5 。
そして永禄元年(1558年)、稙藤はついに苦渋の決断を下す。北畠氏との和睦である。しかし、その条件は長野氏にとって極めて屈辱的なものであった。北畠具教の次男・亀松(後の長野具藤)を、稙藤の嫡孫、すなわち藤定の養嗣子として迎え入れ、長野家の家督を強制的に譲らされることになったのである 5 。
この養子縁組は、単なる和睦の証ではなく、実質的な乗っ取りであった。軍事力による制圧が行き詰まった北畠氏が、婚姻・養子政策によって長野氏を内部から解体し、完全に自らの支配下に置こうとする周到な戦略であった。これにより、鎌倉時代以来、中伊勢に君臨してきた独立領主・長野工藤氏の歴史は事実上終焉を迎え、北畠氏の支配下に組み込まれることとなった 5 。
第四節:謎に包まれた最期
北畠氏への従属後、稙藤の晩年は謎に包まれている。その死に関しても、二つの説が存在し、穏やかなものではなかったことを示唆している。
稙藤の没年には、永禄5年(1562年)5月5日説 23 と、それより1年早い永禄4年(1561年)1月8日説 26 がある。どちらが正しいか断定はできないが、永禄5年説を採る場合、極めて重大な事実が浮かび上がる。それは、稙藤の嫡男であり、共に長野氏を率いてきた長野藤定も、全く同じ日に死去しているという記録である 3 。
父子が同日に、しかも自然死や病死で亡くなるというのは、常識的に考えて極めて不自然である。このことから、この父子の死は、北畠氏による暗殺であった可能性が非常に高いと指摘されている 23 。北畠氏から送り込まれた養子・具藤の支配を盤石なものにするためには、旧主である稙藤と、その血を引く正統な後継者である藤定の存在は、大きな障害であった。彼らを同時に排除することは、北畠氏にとって支配を確立するための冷徹かつ合理的な最終手段であったと考えられる。この一件は、戦国時代の権力闘争の非情さを如実に物語る事例と言えよう。
第三章:稙藤亡き後の長野工藤氏と織田信長の伊勢侵攻
稙藤と藤定の死によって、長野工藤氏は新たな時代を迎える。しかしそれは、北畠氏、そして尾張から急速に台頭してきた織田信長という、さらに巨大な権力に翻弄される時代の幕開けであった。
第一節:養子当主・長野具藤と家中の動揺
稙藤父子の死後、北畠具教の次男である長野具藤が、名実ともに長野工藤氏の当主となった 3 。しかし、長年の宿敵であった北畠家の血を引く若き当主に対する、長野譜代の家臣団の視線は冷ややかであった。
特に、剛勇で知られた重臣・細野藤敦らは具藤と不仲であったと伝えられ、家中は具藤に従う派閥と、それに反発する旧臣派閥とで分裂し、常に不安定な状態にあった 3 。稙藤が守ろうとした一族の結束は、皮肉にも彼が屈した相手から送り込まれた養子の代に、内部から崩壊の危機に瀕していたのである。
第二節:織田信長の侵攻と一族の分裂
永禄11年(1568年)、織田信長による本格的な伊勢侵攻が開始された。信長はまず、北伊勢の有力国人である神戸氏を攻め、和睦の条件として三男の信孝を養子に送り込み、これを屈服させる 6 。
次いで信長の矛先が中伊勢の長野氏に向けられると、家中の対立は決定的となった。当主・具藤や細野藤敦ら一部が抗戦を主張する一方で、長野氏の分家である分部光嘉・光高兄弟らは、北畠支配下での将来に見切りをつけ、新たな支配者である織田方への内応を決意する 3 。これは単なる裏切りというよりも、激動の時代を生き抜くための、戦国国人としての現実的な生き残り戦略であった。
分部氏らの手引きと、織田軍の圧倒的な軍事力を背景に、当主・具藤は居城から追放され、長野家中の主導権は完全に親織田派が掌握することとなった 31 。
第三節:長野氏の終焉
具藤を追放した長野氏は、信長と和睦を結ぶ。その条件は、かつて北畠氏が用いた手法と全く同じであった。信長の弟である織田信包(のぶかね)が長野氏の新たな養子となり、家督を継承することになったのである 7 。信長は、北畠氏が長野氏に対して用いた「養子による乗っ取り戦略」を模倣し、それを神戸氏、長野氏、そして最終的には南伊勢の北畠氏本体(次男・信雄を養子に入れる)にまで適用することで、伊勢国全体をシステマティックに、そして迅速に自らの支配下に組み込んでいった。
新たな当主となった信包は、元亀元年(1570年)に上野城を新たな居城と定めた。これに伴い、長野工藤氏が鎌倉時代から三百数十年間にわたって本拠としてきた長野城は廃城となり、その歴史に幕を下ろした 7 。
こうして長野工藤氏という名門国人の家名は、事実上、織田家に乗っ取られる形で終焉を迎えた。その後の関係者の運命は様々である。追放された旧当主・長野具藤は、天正4年(1576年)、織田信雄(北畠信雄)が北畠一族を粛清した「三瀬の変」において、実父・具教らと共に殺害された 3 。一方で、いち早く織田方に付いた分部光嘉は、その功を認められ、信包の家臣となった後、豊臣秀吉、徳川家康にも仕え、最終的には伊勢上野藩2万石の大名として家名を後世に残すことに成功した 1 。また、稙藤の子であった雲林院祐基も、信長の直臣として召し抱えられ、一族の存続を果たしている 24 。長野工藤氏の滅亡は、外部からの圧力だけでなく、稙藤の代から続いた北畠氏との長年の抗争がもたらした「家中の疲弊と分裂」という内部要因によって決定づけられたと言えるだろう。
結論:長野稙藤の歴史的評価
長野稙藤の生涯は、伊勢国の中央部という地政学的に重要な地で、鎌倉以来の伝統を持つ武家領主として一族の独立を保とうと奮闘した、一人の戦国武将の苦闘の記録である。彼は、将軍家との繋がりを権威の拠り所とし、一族の結束を固めながら、南から圧迫する強大な戦国大名・北畠氏に生涯をかけて対峙した。しかし、時代の大きな流れは彼に味方せず、最終的にはその圧力の前に屈し、一族が独立性を失う道を開かざるを得なかった。
彼の直面した課題―強大な隣国との軍事・外交、不安定な家中の統制、そして後継者問題―は、中央の権威が揺らぎ、実力が全てを決定する戦国時代において、多くの地方国人領主が共有した普遍的なものであった。その意味で、稙藤は戦国期における地方領主の典型的な姿を体現していると言える。
歴史の皮肉は、彼が一族の命脈を保つために下したであろう最善の策、すなわち北畠氏への従属という決断が、結果として家中に深刻な亀裂を生み、織田信長による伊勢平定を容易にし、長野工藤氏という名門の歴史に事実上の終止符を打つ遠因となった点にある。彼は自らの手で一族の独立を守り抜くことはできなかった。しかし、その苦悩に満ちた生涯は、戦国という時代の権力移行のダイナミズムと、その巨大なうねりの中で翻弄された地方領主の悲哀を、後世に生々しく物語る貴重な歴史事例として評価されよう。
付録:長野稙藤関連年表
|
西暦 |
元号 |
長野氏の動向 |
伊勢国内および中央の動向 |
出典 |
|
1504年 |
永正元年 |
長野稙藤、生まれる。 |
|
23 |
|
1511-21年 |
永正8-大永元年 |
稙藤、元服。将軍・足利義稙より偏諱を受ける。 |
|
23 |
|
1530年 |
享禄3年 |
父・通藤の死去に伴い、 稙藤が家督を相続。 |
|
23 |
|
1543年 |
天文12年 |
垂水鷺山の戦い。長野藤定軍が北畠晴具軍と交戦。 |
|
28 |
|
1545年 |
天文14年 |
葉野の戦い。北畠氏との抗争が激化。 |
北畠晴具による長野領への侵攻が本格化。 |
23 |
|
1558年 |
永禄元年 |
北畠氏と和睦。具教の次男・具藤を藤定の養子に迎える。 事実上の従属。 |
北畠具教、志摩・大和へも勢力を拡大。 |
23 |
|
1561年 |
永禄4年 |
1月8日、稙藤死去説あり。 |
|
26 |
|
1562年 |
永禄5年 |
5月5日、 稙藤と嫡男・藤定が同日に死去。 (暗殺説が有力) |
|
23 |
|
1568年 |
永禄11年 |
織田信長の伊勢侵攻開始。分部氏らが織田方に内応。 |
信長、神戸氏を降し三男・信孝を養子に入れる。 |
24 |
|
1569年 |
永禄12年 |
長野氏は信長の弟・信包を養子に迎え、織田氏に降伏。 |
信長、大河内城の戦いで北畠氏を降す。 |
7 |
|
1570年 |
元亀元年 |
信包が上野城へ移り、 長野城は廃城となる。 |
|
8 |
|
1576年 |
天正4年 |
三瀬の変。長野具藤、北畠一族と共に織田信雄に殺害される。 |
北畠氏、事実上滅亡。 |
3 |
引用文献
- 長野工藤氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B7%A5%E8%97%A4%E6%B0%8F
- 工藤氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E8%97%A4%E6%B0%8F
- F051 工藤祐長 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F051.html
- 長野城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/nagano.j/nagano.j.html
- 伊勢國 長野氏城(東の城) - FC2 https://oshiromeguri.web.fc2.com/ise-kuni/naganoshi/higashishiro/higashishiro.html
- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6
- 長野城の見所と写真・100人城主の評価(三重県津市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/662/
- 長野城 (伊勢国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD)
- 伊勢の豪族・工藤長野 - 三重ふるさと新聞 | 三重県 津市 http://furusato-shinbun.jp/2013/01/31-114.html
- 長野城(ながのじょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9F%8E-180181
- 東側から見た雲林院城跡の遠景 (鉄塔手前の山頂付近が主郭) - 津市 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000012677/simple/rekishisanpo100.pdf
- 長野氏城跡 - 津の時間。(津市観光協会) https://tsukanko.jp/spot/s88/
- 「賢吉は行く」長野氏城跡 - 白山道しるべの会 ニュース https://hakusan0guide0blog.localinfo.jp/posts/33507830/
- 三重県の長野氏城に行ってきました。|ぐこ - note https://note.com/good5_/n/n6a01132a9024
- 安濃津 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/28/28571/20682_1_%E5%AE%89%E6%BF%83%E6%B4%A5.pdf
- 北勢四十八家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%8B%A2%E5%9B%9B%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%AE%B6
- 雲林院城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.ujii.htm
- 織田信長の伊勢侵攻(伊勢平定戦) | 城めぐりん https://ameblo.jp/hiibon33/entry-11207446306.html
- 神戸城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/kanbe.j/kanbe.j.html
- 三重歴史紀行(2):北畠氏館跡庭園|東雲旭 - note https://note.com/shinonome55asahi/n/n5374258ce74b
- 六角定頼 - UTokyo BiblioPlaza - 東京大学 https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/F_00231.html
- 北畠家とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6
- 長野稙藤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%A8%99%E8%97%A4
- 雲林院祐基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E9%99%A2%E7%A5%90%E5%9F%BA
- 長野具藤とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%85%B7%E8%97%A4
- 长野稙藤- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%A8%99%E8%97%A4
- 北畠具教-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73543/
- 戦国!室町時代・国巡り(3)伊勢・志摩編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n0d30d0b9bc2a
- 长野藤定- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%95%B7%E9%87%8E%E8%97%A4%E5%AE%9A
- 長野藤定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E8%97%A4%E5%AE%9A
- 大坂の幻〜豊臣秀重伝〜 - 第72話 羽柴の嫁取り騒動(前編) - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n8196hx/73/
- 3織田政権時代 - 戦国勢力図 解説 https://sengoku-seiryokuzu.jimdofree.com/%EF%BC%93%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%94%BF%E6%A8%A9%E6%99%82%E4%BB%A3/
- H143 関 盛政 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H143.html
- 北畠満雅ゆかりの地蔵堂/桜郷土史研究会 https://www.sakuracom.jp/~kyoudoshi/8-jizoudou/jizoudou.html
- 伊勢國 長野氏城(城の台) (三重県津市 https://oshiromeguri.web.fc2.com/ise-kuni/naganoshi/shironodai/shironodai.html
- 伊勢上野初代藩主 分部光嘉 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/shijyo/detail.asp?record=605
- 雲林院城(津市芸濃町雲林院城山)(林光寺背後) https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-siro/setumei/24-mie/ujii-jou.pdf