関種盛
伊勢関氏は亀山城主として戦国乱世を生き抜き、織田・豊臣に従属。関ヶ原で東軍に寝返り大名となるも、家中騒動で改易。旗本として存続した。
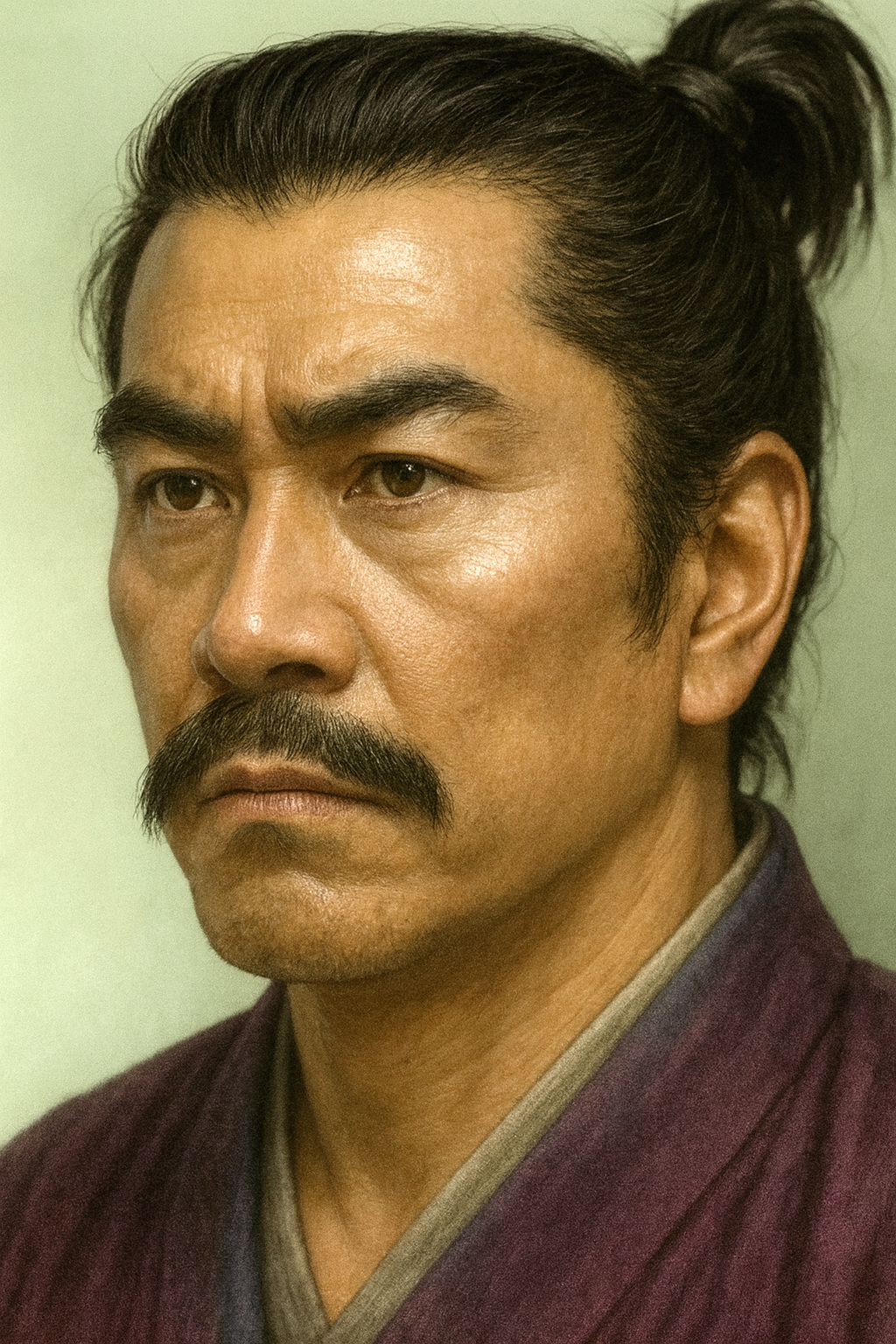
伊勢国人・関氏の興亡史 ― 戦国期亀山城主・関盛信を中心に ―
序論:伊勢国人・関氏研究の視座 ―「関種盛」を手がかりとして―
本報告書の主題設定について
本報告書は、日本の戦国時代における伊勢国の豪族、「関種盛」という人物に関する詳細な調査依頼に応えるものである。しかしながら、初期調査の段階で、依頼者が照会した「関種盛(せき たねもり)」という名の人物は、戦国期の伊勢国亀山城主の系譜上、主要な史料からはその名を確認することができなかった。同姓同名の人物は存在するものの、時代も地域も異なるため(明治から昭和期の愛媛県出身の人物など 1 )、本件の主題とは直接的な関連性を持たない。
一方で、依頼者が提示した「伊勢の豪族。亀山城主。関家は…平実忠が…地名を姓としたのに始まる」という概要は、まさしく伊勢国鈴鹿郡を本拠とした国人領主・ 関氏 の歴史的特徴と完全に一致する 2 。この事実から、本報告書の主題は、「関種盛」という特定の個人名に限定されるものではなく、戦国時代に亀山城を拠点として活躍した関一族、とりわけその動乱の時代を象徴する当主・**関盛信(せき もりのぶ)**を中心とした一族の興亡史そのものであると解釈するのが最も妥当である。本報告書は、この視座に基づき、関氏の歴史を徹底的に掘り下げ、その実像に迫ることを目的とする。
伊勢国における関氏の歴史的位置づけ
関氏は、鎌倉時代にその起源を持ち、伊勢国北部に深く根を張った在地領主である。彼らの歴史は、一地方豪族が、南北朝の動乱、戦国時代の群雄割拠、そして織豊政権による天下統一、江戸幕藩体制の確立という激動の時代をいかにして生き抜こうとしたかを示す、極めて貴重な事例と言える。その軌跡は、単なる地方史に留まらず、中世から近世へと移行する日本の社会構造の変容を映し出す鏡でもある。
本報告書では、まず関氏の出自と北伊勢における勢力基盤の確立過程を明らかにする。次いで、戦国期の当主・関盛信の時代に焦点を当て、織田信長、豊臣秀吉という巨大権力と対峙し、従属する中で見せた巧みな生存戦略を分析する。さらに、その子・一政の代における関ヶ原の戦いでの決断と、近世大名への変貌、そして最終的な改易に至るまでの全貌を、多角的な史料分析を通じて詳述する。最後に、関氏が地域社会に残した文化的・経済的遺産を考察し、その歴史的評価を試みる。
第一章:関氏の起源と伊勢国における勢力基盤の確立
第一節:出自と系譜の諸説 ― 権威の源泉をめぐって
伊勢関氏の出自については、複数の説が存在し、その系譜は一様ではないが、最も広く知られているのは桓武平氏の流れを汲むというものである 5 。具体的には、平清盛の孫にあたる平資盛(たいらのすけもり)を祖とする説が有力視されている 7 。『勢州軍記』や『勢州四家記』などの軍記物によれば、資盛が伊勢国鈴鹿郡久我荘に配流された際に生まれた子が盛国であり、その子こそが関氏の初代とされる関実忠(せき さねただ)であると伝えられている 2 。この系譜は、かつて伊勢国に絶大な影響力を誇った伊勢平氏の後裔であることを示し、戦国時代において一族の権威を高める上で極めて重要な意味を持っていた。
一方で、史料上、より確実な祖として登場するのが関実忠である。『吾妻鏡』などの記録によれば、実忠は鎌倉幕府の有力な御家人であり、第三代執権・北条泰時の側近として承久の乱(1221年)などで武功を挙げたとされる 2 。その戦功により、源頼朝から伊勢国鈴鹿郡関谷二十四郷の地頭職を賜り、その地名を姓としたことが関氏の始まりとされている 2 。この伝承は、関氏が単なる在地土豪ではなく、中央の鎌倉幕府と直接的な繋がりを持つ由緒ある家柄であったことを示唆している。
しかし、これらの系譜には検討すべき点も多い。例えば、資盛と盛国の生没年から見ると年代的な矛盾が生じる可能性が指摘されているほか 2 、藤原姓伊藤氏の一族であるとする異説も存在する 7 。こうした複数の説が並立し、特に権威ある伊勢平氏の血脈が強調される背景には、戦国時代の国人領主が自らの支配の正当性を確立するための政治的な意図があったと考えられる。血統は支配の正当性や社会的地位を保証する重要な要素であり、特に伊勢国において「伊勢平氏」は特別な権威を持っていた。関氏が北伊勢で勢力を拡大する過程で、この権威あるブランドを積極的に利用し、後世に系譜を整えた可能性は高い。これは単なる事実の誤りとしてではなく、当時の武家社会における権威構築戦略の一環として理解すべきであろう。
第二節:亀山城の築城と本拠地の形成
関氏の勢力の中核を成したのが、伊勢亀山城である。この城は、文永2年(1265年)、初代・関実忠によって築かれたと伝えられている 4 。当初は若山(現在の亀山市若山町)の地に築かれ、「亀山古城」または「若山城」と呼ばれたが、後に現在の丘陵地に移された 9 。
以後、戦国時代に至るまで約300年、16代にわたって関氏累代の居城となり、一族の支配の象徴として機能した 4 。城は別名を「粉蝶城(こちょうじょう)」とも呼ばれたが、これは関氏の家紋である揚羽蝶に由来すると考えられている 2 。
第三節:「関五家」の成立と北伊勢支配
室町時代に入ると、関氏はその支配体制をより強固なものにするため、一族を周辺の要地に配置する戦略をとった。南北朝時代の当主・関盛政が五人の子を分家させ、本家の 亀山城 に加え、 神戸(かんべ)城 、 国府(こう)城 、 峯(みね)城 、 鹿伏兎(かぶと)城 にそれぞれを配した 3 。これが「関五家」と呼ばれる強力な一族連合の始まりである。
この同族連合体制により、関氏は鈴鹿郡および河曲郡にまたがる広大な地域を面的に支配し、「関一党」として北伊勢における最大の勢力へと成長した 7 。この体制は、一族による軍事的な連携と領土の共同防衛を可能にし、外部勢力に対する抵抗力を飛躍的に高める上で極めて有効な戦略であった。しかし、この分家体制は、諸刃の剣でもあった。特に、分家筆頭の神戸氏は、伊勢国司・北畠氏との関係を強化するなどして独自の勢力を拡大し、やがて本家である関氏と並び称されるほどの力を持つに至った 16 。この神戸氏の独立性の高まりは、関一党の結束に亀裂を生じさせ、後に織田信長による介入を許す遠因となった。したがって、「関五家」の成立は、関氏の繁栄の礎であると同時に、その後の衰退の伏線でもあったと評価できる。
表1:伊勢関氏 主要人物系譜図
平資盛(伝)
┃
(盛国)
┃
関実忠(初代)
┇
関盛政(関五家の祖)
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┏━━━┻━━━┓ ┃
神戸盛澄 国府為頼 峯盛重
(神戸氏祖) (国府氏祖) (峯氏祖)
┃ ┃
┏━━━┻━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
鹿伏兎頼盛 (本家) ┃
(鹿伏兎氏祖) 関盛光 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
関盛信 ================= 蒲生定秀の娘 ┃
(万鉄) ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
関一政 ================= 蒲生氏郷の妹 ┃
┃(養子) ┃
関氏盛(旗本初代) ┃
┃
【関連人物】 ┃
北畠具盛 ━━ 神戸具盛(友盛) ┃
(養子) ┃ ┃
┗━(養子)織田信孝 ┃
注:系図は諸説あり、主要な関係性を基に簡略化して示している。
第二章:戦国期の動乱と関盛信の台頭
第一節:関盛信の登場と家督相続
戦国時代の伊勢国は、北勢、中勢、南勢に分かれ、特に北勢地域は「北勢四十八家」と呼ばれる小規模な国人領主が乱立する、群雄割拠の状態にあった 18 。このような混乱期に、関氏の当主として歴史の表舞台に登場するのが関盛信である。
盛信は、父・関盛光の子として生まれた 19 。父・盛光自身の具体的な事績に関する史料は乏しいが 20 、盛信の代に関氏は戦国乱世の荒波に本格的に向き合うことになる。盛信の家督相続の正確な時期は明らかではないが、16世紀中頃には当主として活動を開始したとみられる。彼は安芸守を称し、後年には出家して「万鉄(ばんてつ)」と号した 7 。
第二節:周辺勢力との外交戦略
盛信が当主となった当時、関氏の領国は、東に他の北勢諸家、南に中勢の長野氏、そして西には近江国の戦国大名・六角氏という強大な勢力と境を接していた。このような地政学的状況下で、盛信は巧みな外交戦略を展開し、家の存続と勢力の安定を図った。
その中核となったのが、南近江の戦国大名・六角氏への従属である 19 。当時、北伊勢に強い影響力を持っていた六角氏の庇護下に入ることで、国内の競合勢力に対して優位に立とうとした。この関係をさらに強固なものにするため、盛信は六角氏の重臣であった日野城主・蒲生定秀の娘を正室として迎えた 14 。この婚姻は、単なる縁組ではなく、強大な隣国勢力を後ろ盾とすることで自領の安全を保障するという、極めて計算された生存戦略であった。この同盟は、六角氏にとっても伊勢への影響力を確保する足がかりとなり、双方に利益をもたらすものであった。しかし、この強固な結びつきは、後に六角氏が織田信長に攻められた際、関氏が信長と敵対せざるを得なくなるという「しがらみ」にも繋がり、戦国国人が置かれた宿命的な立場を浮き彫りにしている 14 。
また、南伊勢に君臨した国司・北畠氏との関係も重要であった。関氏は、南北朝時代には北畠氏と協力して幕府軍と戦うなど、歴史的に深い繋がりを持っていた 22 。戦国期においても、北伊勢の関氏と南伊勢の北畠氏は、伊勢国を二分する大勢力として、時に緊張し、時に協調する複雑な関係にあったと推測される。
第三節:文化人としての側面
関氏は武辺一辺倒の国人領主ではなく、文化的な活動にも深い関心を示していた。これは、領主としての権威を高め、中央の文化人との交流を通じて情報収集や人脈形成を行う上で、重要な役割を果たした。
盛信の父の代にあたる関盛貞は、何似斎(かじさい)と号し、連歌師の宗長や公家の飛鳥井雅康といった一流の文化人と親交を結び、永正2年(1505年)には正法寺を建立して歌会を催している 3 。また、盛信の時代にも、著名な連歌師である里村紹巴が永禄10年(1567年)に関氏の領地を訪れ、その様子を紀行文に記している 23 。これらの事実は、関氏が京の文化と通じた洗練された一面を持つ、文化的な領主であったことを物語っている。
第三章:織田信長の伊勢侵攻と関氏の選択
第一節:抵抗、そして降伏へ
永禄11年(1568年)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛を果たすと、長年の主君であった近江の六角義賢は信長の前に敗れ、観音寺城を捨てて甲賀へと逃亡した 14 。これにより、関盛信は強力な後ろ盾を失い、信長の次なる標的が自らの領国・伊勢であることは火を見るより明らかであった。
信長の伊勢侵攻が開始されると、分家の神戸氏をはじめとする北勢四十八家の国人たちが次々とその軍門に降る中、関盛信は叔父の盛重ら一族と共に最後まで抵抗を試みた 14 。しかし、織田軍の圧倒的な兵力の前に抗しきれず、盛信はついに信長に降伏し、その支配下に入ることとなった 14 。降伏後は、信長が伊勢国司・北畠具教を攻めた大河内城の戦いに、織田方として従軍している 25 。
第二節:信長の支配体制と関氏の苦境
信長は、関氏を完全に支配下に置くため、武力だけでなく、巧みな謀略を用いた。その核心にあったのが、関一族の最有力分家であった神戸氏の乗っ取りである。信長は、神戸城主・神戸具盛(友盛)が当初、関盛信の子である勝蔵(後の関一政)を養子に迎えるとしていた約束を反故にさせ、代わりに自身の三男・信孝を具盛の養子として送り込んだ 2 。
この信孝の養子縁組は、単なる人質や縁組ではなかった。それは、関氏の権力基盤であった「関五家」という同族連合を内部から無力化するための、極めて効果的な分断統治策であった。関氏の力の源泉であった一族連合 3 、その中でも本家に匹敵する力を持っていた神戸氏を直接支配下に置くことで 16 、信長は関一党の結束を根底から破壊した。これにより、関盛信は最強の味方を失い、織田家の一員となった信孝に領地を隣接される形となり、政治的・軍事的に完全に封じ込められたのである。これは、武力だけでなく、婚姻や養子縁組といった伝統的な制度を逆用して敵を弱体化させる、信長ならではの合理的かつ冷徹な支配戦略を示す典型例と言える。
第三節:亀山城からの追放と復帰
元亀4年(1573年)、関盛信は突如、信長によって本拠地である亀山城から追放されるという憂き目に遭う 3 。その明確な理由は史料には記されていないが、神戸氏の当主となった信孝との根深い不和が原因であったと推測されている 30 。名門・関氏本家の当主としての誇りが、織田家の威光を笠に着る若年の信孝への完全な服従を潔しとしなかった可能性は高い。
しかし、盛信はただ雌伏していたわけではなかった。本能寺の変の直前である天正10年(1582年)、彼は信長に許され、約9年ぶりに亀山城への復帰を果たしている 3 。この追放と復帰という劇的な経験は、その後の盛信の政治的判断に大きな影響を与え、より現実的で慎重な生存戦略を模索させる契機となったと考えられる。
第四章:豊臣政権下における関氏の動向
第一節:本能寺の変後の選択
天正10年(1582年)6月、本能寺の変によって織田信長が横死すると、織田家の後継者をめぐる激しい権力闘争が始まった。この時、関盛信は迅速かつ的確な判断を下す。かつての対立相手であり、信長の三男として後継者候補の一人であった織田信孝から離れ、中国大返しによって明智光秀を討ち、一躍その名を高めた羽柴秀吉(豊臣秀吉)に接近したのである 19 。これは、先の追放経験から信孝の器量に見切りをつけ、織田家中の実権を掌握しつつあった秀吉に与することで、激動の時代における家の存続を図った、極めて現実的な政治判断であった。
第二節:賤ヶ岳の戦いと亀山城争奪戦
天正11年(1583年)、秀吉と柴田勝家・織田信孝が雌雄を決した賤ヶ岳の戦いが勃発すると、その前哨戦として伊勢国が再び戦場となった。信孝方に与した織田家宿老・滝川一益が北伊勢で蜂起し、関氏の本拠・亀山城を占拠したのである 19 。
この城の失陥については、複数の説が伝えられている。一つは、盛信が秀吉への年賀のために城を不在にしていた隙を突き、家臣の岩間氏ら反秀吉派が城を乗っ取り、一益に明け渡したというものである 32 。また、盛信の弟・盛清がかつて柴田勝家に仕えていた縁から、滝川方に内通したという説もある 34 。これらの伝承は、中央の巨大権力の対立が、関氏という地方領主の家中にまで波及し、親秀吉派と反秀吉派(親柴田派)の内部対立を誘発・顕在化させたことを示唆している。滝川一益という外部からの働きかけが、家中に潜んでいた不満分子に蜂起の機会を与えたのであろう。これは、戦国末期の地方領主が、自家の統制を維持しつつ、上位権力への従属という二重の課題に直面していたことを示す好例である。
秀吉は、この事態に迅速に対応し、蒲生氏郷らを先鋒とする大軍を伊勢に派遣した。秀吉軍は滝川方が守る亀山城を包囲し、激しい攻防戦の末にこれを奪還した 9 。この戦いにおいて、関盛信・一政親子も秀吉方として戦功を挙げ、亀山城主としての地位を再び確保することに成功した 19 。
第三節:蒲生氏郷の与力大名として
賤ヶ岳の戦いの後、関氏は亀山城主としての地位は安堵されたものの、その立場は大きく変化した。秀吉の命により、蒲生氏郷の「与力大名」とされたのである 19 。与力とは、独立した大名ではなく、方面軍の司令官ともいえる有力大名の指揮下に入ることを意味する。かつて蒲生氏とは婚姻を通じて対等な同盟関係を結んでいたことを考えれば、これは関氏の地位が相対的に低下したことを示している。
この頃、盛信は家督を子の関一政に譲り、「万鉄」と号して隠居生活に入ったとされる 19 。当主となった一政は、蒲生氏郷の麾下として、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いや、その後の九州征伐、小田原征伐といった豊臣政権の主要な合戦に従軍し、武功を重ねた 9 。
天正18年(1590年)、小田原征伐後の論功行賞で蒲生氏郷が会津42万石(後に92万石)へ大大名として移封されると、与力であった関一政もそれに従い、陸奥国白河に5万石の所領を与えられた 3 。父・盛信も一政と共に白河へ移り、文禄2年(1593年)6月28日、その地で波乱の生涯を終えた 7 。
第五章:関ヶ原の戦いと関氏の近世大名への道、そして改易
第一節:関一政の決断 ― 関ヶ原での寝返り
豊臣秀吉の死後、天下の情勢は徳川家康と石田三成の対立を軸に、再び大きく動き始めた。慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、当時、美濃国多羅城主であった関一政は、極めて重要な岐路に立たされた。
一政は当初、石田三成が率いる西軍に属していた 2 。しかし、合戦の直前、あるいは合戦の最中に突如として東軍に寝返るという大胆な行動に出る。この決断の背景には、家康側からの執拗な調略があったと考えられている。東軍に与する見返りとして、先祖伝来の地である伊勢亀山城への復帰が約束されていた可能性が高い。一政は、豊臣家の将来性よりも、徳川家康の下で旧領を回復し、家名を存続させる道を選んだのである。
第二節:旧領復帰と伊勢亀山藩の立藩
関ヶ原の戦いは東軍の圧勝に終わり、一政の決断は功を奏した。戦後、その功績を認められた一政は、約束通り、念願の旧領・伊勢亀山に3万石で復帰を果たした 10 。ここに、譜代ではない外様大名として、近世大名・伊勢亀山藩が立藩されたのである。
藩主となった一政は、荒廃した城郭の修築や、城下町であり東海道の重要な宿場町でもある亀山宿の整備に尽力し、藩政の基礎を築いた 39 。鎌倉時代から続く関氏の歴史は、ここに一つの頂点を迎えた。
第三節:改易と関氏のその後
伊勢亀山への復帰から10年後の慶長15年(1610年)、一政は伯耆国黒坂(現在の鳥取県日野町)へ5万石で加増移封された 2 。これは石高の上では栄転であったが、一族が400年近くにわたって支配してきた先祖伝来の地を離れることを意味した。
そして、そのわずか8年後の元和4年(1618年)、関氏は突如として幕府から改易(領地没収)を命じられる。その理由は「家中騒動(お家騒動)」であった 2 。戦国の荒波を巧みな政治判断で乗り越え、ついに近世大名となった関氏が、最終的に内部の統制問題を理由にその地位を失ったことは、時代の大きな転換を象徴している。戦国時代の実力主義や流動的な主従関係といった気風を残す武家が、徳川幕府が求める厳格な支配体制と秩序に適応することの困難さを示している。江戸時代に入ると、家中の混乱は藩主の統治能力の欠如と見なされ、厳罰の対象となった。関氏の改易は、多くの戦国上がりの大名が直面した「泰平の世を治める術」への転換に失敗した典型例として位置づけることができる。
大名としての関氏はここに終焉を迎えたが、家名が完全に途絶えたわけではなかった。一政の養子であった氏盛(一政の弟・盛吉の子)が、近江国蒲生郡に5,000石の所領を与えられ、旗本として家名を存続させることが許された 2 。その子孫は代々、中山陣屋(現在の滋賀県日野町)を拠点とし、明治維新まで旗本として続いたのである 2 。
第六章:関氏の文化的・経済的影響
第一節:関宿の発展と経済基盤
関氏が数百年にわたり本拠とした「関」の地は、古代から交通の要衝であった。壬申の乱(672年)の頃に設置された古代三関の一つ「鈴鹿関」がその名の由来であり 40 、常に人々の往来が絶えない場所であった。
関氏は、この地理的優位性を活かし、領内のインフラ整備に力を注いだ。特に戦国期の当主・関盛信は、現在の関宿の町並みの基礎となる新所城を築き、宿場町の整備を本格的に進めたと伝えられている 3 。江戸時代に入り、関宿が東海道五十三次の47番目の宿場町として大いに繁栄した背景には、関氏の時代から築かれてきたこの基盤があった。参勤交代の大名行列や伊勢神宮への参詣者で賑わい、大名御用達の火縄生産 43 や商業が盛んになるなど、地域経済の中心地として発展した。
第二節:「関の山」の語源と地域文化
関氏がこの地に残した最も有名な無形の遺産の一つが、「関の山」という言葉である。この言葉の語源は、関宿で毎年夏に行われる祇園祭で曳き出された山車(だし)にあるとされる 42 。
この祭りの山車は、江戸時代には関西五大祭の一つに数えられるほど豪華絢爛であり、その壮麗さから「これ以上立派なものはない」「これが精一杯の極致である」という意味で、「関の山」という言葉が生まれたと伝えられている 44 。また、狭い街道を巨大な山車が屋根すれすりで進む様子から、「これが限界」という意味になったという説もある 42 。いずれにせよ、この言葉は、関氏の治世下で育まれた地域の経済力と文化的な豊かさが、後世にまで語り継がれる形で残った証左と言える。
結論:伊勢国人・関氏の歴史的評価
伊勢関氏は、鎌倉時代の御家人にその端を発し、江戸時代初期に至るまで、約400年にわたって伊勢国北部に深く根を張った名族であった。彼らの歴史は、一地方領主が中央の権力構造の激しい変動にいかに対応し、家の存続を図ったかを示す貴重な縮図である。
戦国期の当主・関盛信の時代、彼らは六角氏、織田氏、豊臣氏という巨大勢力の間で、婚姻、抵抗、従属、そして離反といったあらゆる政治的選択を駆使して乱世を渡り抜いた。その過程では、かつて勢力拡大の礎であった「関五家」という一族連合の分家が、織田信長の介入によって逆に仇となるなど、国人領主が抱える構造的な脆弱性も露呈した。
その子・関一政は、関ヶ原の戦いにおける絶妙な政治判断によって、ついに近世大名への道を切り開いた。しかし、その栄華は長くは続かず、家中騒動という内部要因によって瓦解する。これは、戦国から近世へと移行する時代の厳しさ、そして武家の統治能力が新たな基準で厳しく問われるようになったことを象徴する出来事であった。
最終的に大名の地位は失ったものの、旗本として家名を後世に伝え、また「関宿」の町並みや「関の山」という言葉の中にその名を刻んだ関氏の歴史は、戦国乱世を駆け抜けた一地方豪族の、栄光と挫折、そして地域社会に与えた深い影響を今に物語る、重要な歴史の一頁と言えるだろう。
付録:関氏関連略年表
表2:関氏関連略年表
|
西暦(和暦) |
関氏の動向 |
関連する中央・周辺の動向 |
|
1265年(文永2) |
関実忠、亀山城を築城する 4 。 |
鎌倉幕府、元寇に備える。 |
|
1428年(正長元) |
正長の乱で、関氏が北畠満雅に味方し幕府軍と戦う 22 。 |
室町幕府6代将軍・足利義教が就任。 |
|
1568年(永禄11) |
織田信長の伊勢侵攻に対し、関盛信は抵抗の後に降伏 14 。神戸氏に信長の三男・信孝が養子として入る 2 。 |
織田信長、足利義昭を奉じて上洛。六角氏が滅亡。 |
|
1573年(元亀4) |
関盛信、信長により亀山城を追放される 3 。 |
信長、将軍・足利義昭を京から追放し、室町幕府が事実上滅亡。 |
|
1582年(天正10) |
関盛信、亀山城に復帰を許される 3 。本能寺の変後、羽柴秀吉に接近。 |
本能寺の変で織田信長が死去。山崎の戦い。清洲会議。 |
|
1583年(天正11) |
賤ヶ岳の戦いの前哨戦で、亀山城が滝川一益に奪われるが、秀吉軍が奪還 19 。 |
賤ヶ岳の戦いで羽柴秀吉が柴田勝家を破る。 |
|
1590年(天正18) |
関一政、蒲生氏郷の会津移封に従い、陸奥国白河5万石へ移る 3 。 |
豊臣秀吉、小田原征伐により天下を統一。 |
|
1593年(文禄2) |
関盛信、白河にて死去 19 。 |
文禄の役。 |
|
1600年(慶長5) |
関ヶ原の戦いで、関一政は当初西軍に属すも東軍に寝返る 2 。 |
関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍が勝利。 |
|
1600年(慶長5) |
戦後、功により伊勢亀山3万石に復帰し、伊勢亀山藩を立藩 10 。 |
|
|
1610年(慶長15) |
伯耆国黒坂5万石へ加増移封される 2 。 |
|
|
1618年(元和4) |
関一政、家中騒動を理由に改易(領地没収)される 2 。 |
大坂夏の陣(1615年)を経て、徳川幕府の支配体制が盤石となる。 |
引用文献
- 愛媛県史 人 物(平成元年2月28日発行) - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/57/view/7507
- 関氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%B0%8F
- 亀山市 - (かめやまし) - の歴史 - (れきし) - 亀山人物伝|日本の歴史の中の亀山|亀山こども歴史館 https://kameyamarekihaku.jp/kodomo/w_e_b/rekishi/jinbutu/page002.html
- 亀山城の歴史/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-castle/kameyama-castle/
- 武家家伝_関 氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/seki_k.html
- 武家家伝_関 氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/seki_k.html
- 関氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E9%96%A2%E6%B0%8F
- 平氏(へいし)と関氏(せきし) - 亀山市歴史博物館 https://kameyamarekihaku.jp/kodomo/w_e_b/rekishi/chusei/taitou/heishi/index.html
- 古城の歴史 亀山城 http://takayama.tonosama.jp/html/kameyama.html
- 亀山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/kameyama.j/kameyama.j.html
- 亀山城 (伊勢国)~三重県亀山市~ - 裏辺研究所「日本の城」 https://www.uraken.net/museum/castle/shiro83.html
- 亀山城 (伊勢国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%80%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD)
- 亀山城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1740
- 東海道の昔の話(45) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido45.htm
- 鹿伏兎城 関氏一族の鹿伏兎盛宗が築いた鹿伏兎氏代々の居城 | 小太郎の野望 https://seagullese.jugem.jp/?eid=684
- 神戸城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/kanbe.j/kanbe.j.html
- 「織田信孝(神戸信孝)」信長の三男。兄との差別を糧にのし上がる!? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/492
- 【大河ドラマ連動企画 第42話】どうする直昌(田丸直昌) - note https://note.com/satius1073/n/n7ca4f1958a72
- 関盛信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E7%9B%9B%E4%BF%A1
- 尾張の城館を調べる - 名古屋市図書館 https://www.library.city.nagoya.jp/img/reference/0103_1.pdf
- 盛光(もりみつ)/ホームメイト - 著名刀工・刀匠名鑑 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/sword-artisan-directory/morimitsu/
- 北畠満雅ゆかりの地蔵堂/桜郷土史研究会 https://www.sakuracom.jp/~kyoudoshi/8-jizoudou/jizoudou.html
- 室町時代(むろまちじだい)の旅人(たびびと) - 亀山市歴史博物館 https://kameyamarekihaku.jp/kodomo/w_e_b/koten/tabi/page003.html
- 武家家伝_神戸氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kanbe_k.html
- 織田信長の伊勢侵攻と支配… 伊勢を呑み込んだ非情な養子戦略の全貌 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2894
- 謀略戦で勢力拡大:「織田信長の伊勢侵攻」を地形・地質的観点で見るpart10【合戦場の地形&地質vol.7-10】 - note https://note.com/yurukutanosimu/n/ne648d61f5602
- 東海道の昔の話(133) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido134.htm
- 織田信孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%AD%9D
- 織田信孝(オダノブタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%AD%9D-40520
- 神戸信孝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E4%BF%A1%E5%AD%9D
- 秀吉VS.家康 小牧・長久手の戦いを知る 第3回 織田・徳川連合軍の城・砦②(長島城と伊勢の城を中心に) - 城びと https://shirobito.jp/article/1504
- 4.秀吉、滝川一益を攻める http://www.ibukiyama1377.sakura.ne.jp/shizugatake/3-4.html
- 伊勢 新所城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/ise/shinjo-jyo/
- 東海道の昔の話(141) http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido141.htm
- 関一政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E4%B8%80%E6%94%BF
- 蒲生氏郷 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7
- 関一政の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/daimyo/b-seki.html
- 伊勢亀山藩(1/2)多くの大名家が治める - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/147/
- 亀山 城下町 6万石 with 関宿 - ポンタックのブログ at DESIGN OFFICE TAK https://www.pontak.jp/urban-history-japan-castle-town-kameyama-with-sekijyuku/
- 関宿 - あいち歴史観光 https://rekishi-kanko.pref.aichi.jp/place/seki.html
- 東海道関宿 - 亀山市観光協会 http://kameyama-kanko.com/wp-content/uploads/2017/03/2062d7cfd6de597f1a3afa51d486610a.pdf
- 関宿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%AE%BF
- 関宿の歴史と文化 - 亀山市 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112311914/
- 関宿祇園夏まつりが開催されます。 - 亀山市観光協会 http://kameyama-kanko.com/info/%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%93%EF%BC%90%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%96%A2%E5%AE%BF%E7%A5%87%E5%9C%92%E5%A4%8F%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82/