隈部親永
隈部親永は肥後の国衆。菊池三家老の一人で、龍造寺・島津氏に仕える。豊臣秀吉の検地に抵抗し肥後国人一揆を主導。敗れて立花宗茂に「放し討ち」で処刑された。
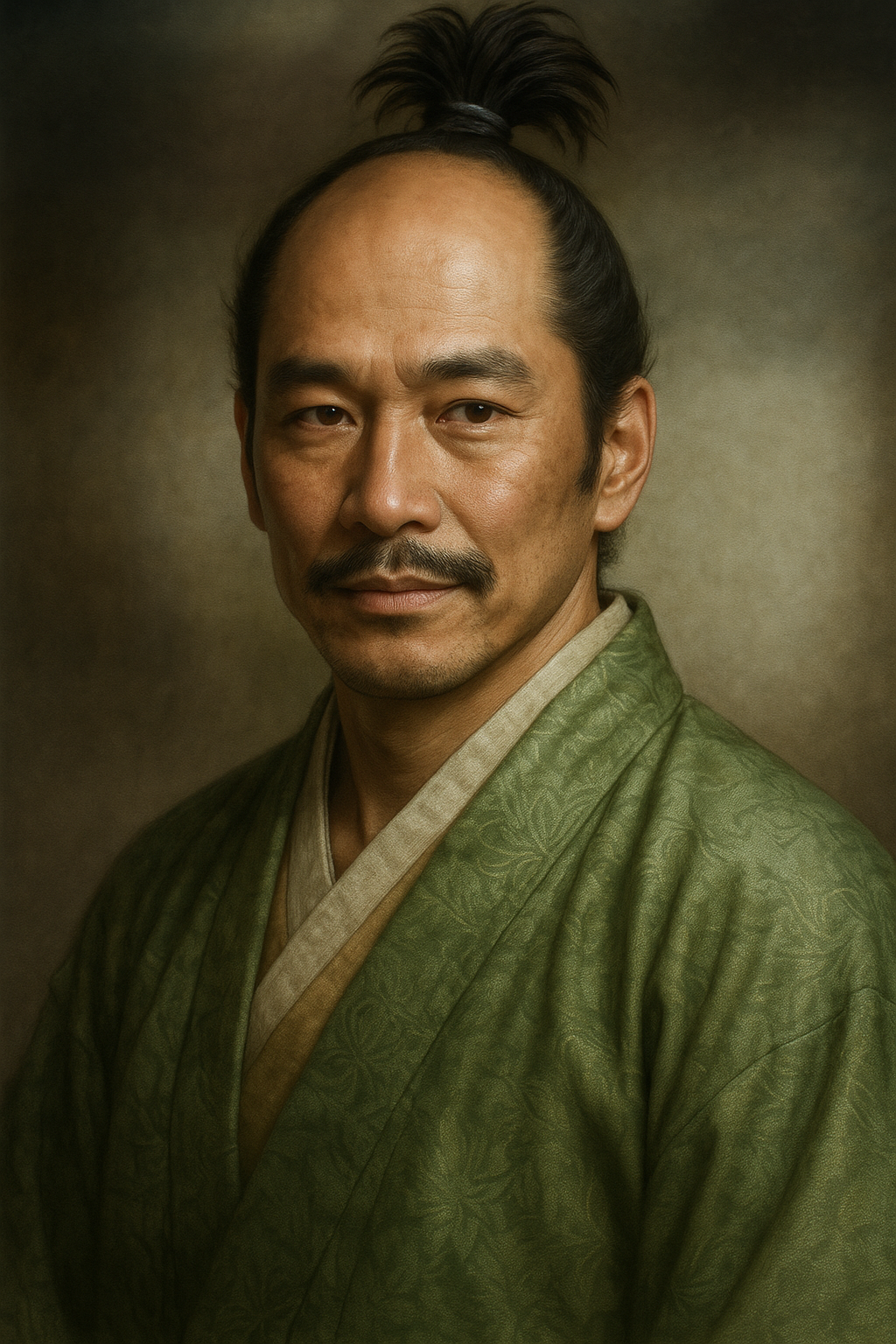
肥後国衆・隈部親永の実像:中世の終焉と武士の意地
序章:戦国肥後、最後の国衆・隈部親永
本報告書は、日本の戦国時代末期から安土桃山時代にかけて、肥後国(現在の熊本県)にその名を刻んだ武将、隈部親永(くまべ ちかなが)の生涯を、あらゆる角度から徹底的に調査し、その実像に迫るものである。一般に親永は、主家であった菊池氏の没落後、龍造寺氏、島津氏と主君を替え、最終的に豊臣秀吉に降伏するも、新領主・佐々成政の検地に抵抗して「肥後国人一揆」を主導し、敗れて死に至った人物として知られている 1 。しかし、この概要だけでは、彼の行動の根源にある動機や、彼が生きた時代の激しい変化の本質を捉えることはできない。
本報告書が解き明かす中心的な問いは、以下の点にある。「なぜ親永は、天下人・豊臣秀吉の圧倒的な権力の前に、破滅を予期しながらも肥後国人一揆という大規模な抵抗を主導したのか。その行動原理はどこにあったのか」。この問いに答えるため、本報告書では親永個人の伝記に留まらず、彼が属した隈部一族の出自と誇り、主家滅亡後の肥後における権力闘争、そして豊臣政権による中央集権化という、より大きな歴史的文脈の中に彼を位置づける。
隈部親永は、単なる一地方の反乱者ではない。彼は、中世以来の在地領主としての誇りと自立性を持ち、新しい時代の画一的な支配体制に抗った、旧時代の最後の象徴ともいえる人物である。彼の生涯を丹念に追うことは、戦国という時代がいかにして終わりを告げ、近世という新しい社会がいかにして産声を上げたのか、その激しい移行期のダイナミズムを解明する上で、極めて重要な鍵となるであろう 3 。
第一章:隈部氏の出自と台頭
隈部親永の行動原理を理解するためには、まず彼が背負っていた一族の歴史と、肥後国におけるその地位を把握する必要がある。隈部氏は、単なる土着の豪族ではなく、由緒ある家系と、主家を支えたという強い自負心を持つ一族であった。
第一節:清和源氏の流れを汲む名門
隈部氏の出自は、清和源氏の一流で、大和国(現在の奈良県)を本拠とした大和源氏の宇野氏に遡ると伝えられている 4 。伝承によれば、一族の祖である宇野親治は、保元の乱(1156年)で敗れた後、肥後国に下り、当時この地で勢力を誇っていた名門・菊池氏の庇護を受けたという 7 。このことは、隈部氏がその発祥から中央の政争と無縁ではなく、また肥後の有力者である菊池氏との間に古くからの主従関係を築いていたことを示唆している。この由緒ある出自は、隈部一族が代々高い家格意識を持ち続けていたことの根拠であり、後の親永が自身の家門の誇りをかけて抵抗に至る精神的な土壌となった。
第二節:菊池三家老としての地位
肥後国に根を下ろした宇野一族は、菊池氏の家臣として忠勤に励み、やがてその家臣団の中で最高位の地位を占めるに至る。16代当主・隈部持直の代には、その功績を主君・菊池武房に賞され、菊池氏の本拠地である隈府城(わいふじょう)の別名「隈部城」に因んで、「隈部」の姓を賜ったとされる 7 。これは、隈部氏が菊池氏から絶大な信頼を得ていたことの証左であり、以後、赤星氏・城氏と共に「菊池三家老」と称される筆頭家老の家柄として、肥後国政に重きをなした 4 。
菊池三家老という地位は、隈部氏にとって最高の栄誉であった。しかし、この栄光は、主家である菊池氏の権威が揺らぎ始めると、一転して宿命的な対立の火種へと変質する。絶対的な権威である菊池氏が存在する間は、三家老は互いに競いつつも主家を支える存在として機能した。だが、16世紀に入り、菊池氏が度重なる内紛や、豊後の大友氏をはじめとする外部勢力の介入によって弱体化し、事実上滅亡すると 9 、肥後国に権力の空白が生じる。その空白を埋めるべく、残された最高位の家臣である三家老が、旧菊池領の覇権を巡って争うのは、いわば必然であった。特に、同じく三家老の家柄である赤星氏との対立は、この構造的な要因から生まれたものであり、親永の代にその対立は頂点に達することになる。
第三節:父・親家から親永へ:乱世の家督相続
隈部親永が父・親家から家督を継いだとされる天正元年(1573年)頃、肥後北部は豊後の大友氏の強い影響下に置かれていた 11 。隈部氏も、大友氏が菊池氏の家督に介入して菊池義武を擁立した際にはこれに協力しており、以来、大友氏の傘下にあった 11 。
このような複雑な情勢の中で当主となった親永は、大友氏に従属するという立場をとりながらも、旧菊池家臣団の中で巧みに立ち回り、その中心人物としての地位を固めていく 11 。主家が滅び、外部の強大な勢力が支配する乱世の中で家督を継いだこの時期の経験は、彼の現実主義的な外交感覚と、自家の存続と勢力拡大にかける執念を磨き上げたに違いない。
第二章:肥後国衆の覇権争い
主家・菊池氏が歴史の舞台から姿を消した後、肥後国は群雄割拠の時代に突入した。北の龍造寺氏、東の大友氏、南の島津氏という三大勢力がこの地を草刈り場とし、隈部親永ら肥後の国人領主(国衆)は、その狭間で生き残りをかけた熾烈な権力闘争を繰り広げた。
第一節:主家菊池氏の没落と三大勢力の狭間で
菊池氏滅亡後の肥後は、九州の三大戦国大名である豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、薩摩の島津氏が、それぞれ勢力圏の拡大を目指して介入する、まさに力の交差点であった 12 。このような状況下で、肥後の国衆は単独で自立を保つことは極めて困難であり、三大勢力のいずれかに従属することで自家の存続を図ることを余儀なくされた。
隈部親永もまた、この冷徹な国際情勢を的確に読み、自家の利益を最大化するために従属先を巧みに変えていった。
- 大友氏への従属 :当初は父の代からの関係を引き継ぎ、大友氏の傘下にあった 11 。
- 龍造寺氏との連携 :後述する赤星氏との対立が深まると、大友氏と敵対関係にあった龍造寺氏と手を結ぶ 1 。
- 島津氏への降伏 :龍造寺氏が沖田畷の戦いで敗れ勢力を失うと、南から圧力を強める島津氏に人質を出し、その軍門に降った 1 。
この一連の動きは、単なる変節や裏切りと見るべきではない。それは、強大な勢力に囲まれた中小領主である国衆が、激動の時代を生き抜くために選択せざるを得なかった、極めて現実的な生存戦略であった。
第二節:宿敵・赤星氏との抗争
親永の生涯において、最も激しい敵対関係にあったのが、同じく菊池三家老の家柄である赤星氏であった。この対立の根源は、菊池氏滅亡後の肥後北部における覇権、すなわち旧菊池領の実質的な継承者を巡る争いにあった 10 。
両者の対立が決定的となったのが、永禄2年(1559年)の合勢川(あわせがわ)の戦いである 17 。この戦いで親永は、自領に侵攻してきた赤星親家(道雲)の軍勢を寡兵ながらも夜襲によって打ち破り、軍事的な名声を高めた 10 。この勝利は、親永が肥後北部の実力者として台頭する大きな契機となった。
しかし、敗れた赤星氏が宗主である大友氏に支援を求めたことで、事態はより複雑化する。大友氏の介入を警戒した親永は、これに対抗するため、当時「肥前の熊」と恐れられ、大友氏と激しく対立していた肥前の龍造寺隆信との連携へと舵を切る 10 。これは、肥後国内の地域紛争が、九州全土を巻き込む大名間の代理戦争の様相を呈し始めたことを意味していた。
第三節:龍造寺氏への臣従と隈府城入手
親永の外交戦略が大きな転機を迎えたのは、天正6年(1578年)の耳川の戦いであった。この戦いで大友氏が島津氏に歴史的な大敗を喫し、その権威が失墜すると、親永はこれを好機と捉え、龍造寺氏の肥後侵攻に全面的に協力する 1 。彼は龍造寺軍の先兵として、赤星氏方の長坂城などを次々と攻略し、その勢力拡大に大きく貢献した 11 。
そして天正9年(1581年)、ついに龍造寺政家(隆信の子)が赤星氏の本拠地であった隈府城を攻略すると、親永はその功績を認められ、同城の支配を任されることとなった 1 。この時、親永は本拠地を古来の永野城(隈部館)から隈府城へと移し、子の親泰を城村城に配して守りを固めた 11 。その所領は菊池・山鹿・山本の三郡に及び、約5,000町(石高換算で3万石から6万石に相当)に達したとされ、名実ともに肥後北部最強の国人領主として、その生涯の頂点を迎えたのである 8 。
この隈府城への本拠移転は、単なる軍事・政治的な判断を超えた、極めて象徴的な意味を持つ行為であった。隈府城は、かつて肥後一国を支配した守護・菊池氏の本拠地であり、肥後北部の政治的中心地そのものであった 19 。親永がこの地に移ったことは、彼が単に龍造寺氏の代官として満足するのではなく、自らが菊池氏の正統な後継者としてこの地を支配するという、強烈な意志の表明に他ならなかった。この「一国一城の主」としての自負と、先祖代々の土地を自らの手で治めるという中世的領主としての誇りが、後の豊臣政権による中央集権的な支配体制と根本的に相容れないものであり、肥後国人一揆という悲劇的な結末へと至る精神的な伏線となったのである。
第三章:天下統一の波と肥後国人一揆
隈部親永が肥後北部で覇を唱えていた頃、中央では織田信長の後を継いだ豊臣秀吉が天下統一事業を急速に進めていた。その巨大な権力の波は、やがて九州にも及び、親永ら国衆の運命を根底から揺るがすことになる。
第一節:豊臣秀吉の九州平定と「国分」への不満
天正12年(1584年)、親永が頼みとしていた龍造寺隆信が沖田畷の戦いで島津・有馬連合軍に敗れ戦死すると、肥後における龍造寺氏の勢力は急速に衰退した 11 。この機を逃さず南から侵攻してきた島津氏の圧力の前に、親永は人質を差し出して降伏し、その傘下に入った 1 。
しかし、その島津氏も長くは続かなかった。天正15年(1587年)、秀吉が20万ともいわれる大軍を率いて九州征伐を開始すると、親永は時勢を的確に読み、いち早く秀吉に降伏してその軍門に下った 8 。彼は、秀吉に従うことで自らの所領が安堵されることを期待していた。
ところが、九州平定後に行われた「九州国分(領地再配分)」は、親永ら肥後国衆の期待を大きく裏切るものであった。親永の所領は、最大期の約5,000町から大幅に削減され、約1,900町のみが安堵されるに留まったのである 8 。
この処遇への不満が、肥後国人一揆の根本的な原因であったとする見方が近年有力視されている。通説では、後任の領主・佐々成政の検地強行が一揆の原因とされてきた 22 。しかし、より深く分析すると、隈部氏のように島津氏に最後まで抵抗し、秀吉に味方した旧大友方の国衆たちは、島津氏に奪われた旧領の回復を強く期待していた 25 。それにもかかわらず、秀吉の国分は、敵対してきた旧島津方の国人の多くも所領を安堵するなど、彼らの「論功行賞」への期待を裏切る内容であった 25 。この秀吉の裁定に対する構造的な不満と失望が、豊臣政権への潜在的な不信感となり、新領主・佐々成政の政策は、その不満を爆発させる単なる引き金に過ぎなかったのである。
第二節:佐々成政の検地強行:一揆の導火線
九州国分の結果、肥後一国(球磨郡を除く)は、織田信長旧臣の佐々成政に与えられた 27 。秀吉は成政に対し、「3年間は検地を行ってはならない」など、国衆を刺激しないよう慎重な統治を命じたとされる「五ヶ条の定書」を与えたと伝えられている 24 。
しかし、成政はこの命令を無視し、入国後間もない同年7月、性急に検地の実施を布告した 23 。この「太閤検地」は、単なる田畑の測量ではなかった。それは、荘園制以来続く複雑な土地所有関係や中間的な支配層をすべて否定し、すべての土地を「石高」という統一された基準で把握し、土地を直接耕作する農民を直接の納税義務者とする、中世的な支配体制を根底から覆す革命的な政策であった 31 。国人領主にとって、これは自らの領主権、すなわち土地と人民に対する支配権そのものの否定に他ならなかった。
隈部親永は、国衆の筆頭として成政に呼び出されると、「我々は秀吉公から直接に本領を安堵された」という朱印状を盾に、成政の検地指出(検地のための土地台帳提出)命令を断固として拒否した 3 。この親永の抵抗が、肥後国人一揆の直接的な導火線となった。
この一連の経緯には、秀吉の冷徹な政治戦略が隠されているとする説もある。秀吉は、かつて敵対し、武勇には優れるものの政治的に扱いにくい成政を、あえて国人勢力が強く「難治の国」とされた肥後に配置した 23 。成政に強引な統治を強いることで国人の反発を招くことは、秀吉にとって予見可能であったはずである。結果として、秀吉は一揆の責任をすべて成政一人に負わせて切腹させ 3 、同時に抵抗した国人衆を「天下人への反逆者」として武力で殲滅した 3 。これにより、厄介な元敵将と、中央集権化の障害となる在地勢力という二つの問題を一挙に片付けることに成功したのである。この見方に立てば、肥後国人一揆は秀吉によって巧妙に誘発された事件であったとも解釈できる 23 。
第三節:城村城籠城戦:肥後国衆、最後の抵抗
親永の抵抗に対し、佐々成政は直ちに約7,000の兵を率いて親永の居城・隈府城を攻撃した。衆寡敵せず、親永は城を脱出し、子の隈部親泰が守る山鹿の城村城へと合流、籠城戦を開始した 29 。
この城村城には、隈部一族の兵だけでなく、彼らの支配を慕う百姓、町人、僧侶らも次々と馳せ参じ、その数は総勢1万5千人(一説には1万8千人)にも膨れ上がったという 3 。これは、隈部氏が単なる武力支配者ではなく、領民から強い求心力を持つ存在であったことを物語っている 7 。
親永の蜂起は、肥後各地で燻っていた不満に火をつけた。玉名の和仁氏、益城の甲斐氏など、肥後の有力国衆が次々とこれに呼応して蜂起し、一揆は肥後全土に拡大した 8 。一揆勢は、成政が城村城攻めで手薄になった居城・隈本城を包囲するなど、一時は成政軍を窮地に追い込んだ 8 。
事態を重く見た秀吉は激怒し、九州・四国の諸大名を総動員した数万の鎮圧軍の派遣を決定した。総大将には小早川秀包、軍監には安国寺恵瓊が任じられ、立花宗茂、鍋島直茂といった九州の猛将たちが次々と肥後へ投入された 27 。秀吉は「国が荒れ果てても、ことごとく成敗(皆殺しに)せよ」と檄を飛ばし、徹底的な弾圧を命じた 3 。
圧倒的な兵力差の前に、一揆勢は次第に追い詰められていく。最後まで頑強に抵抗した和仁氏の田中城も、約40日にわたる壮絶な籠城戦の末に落城 39 。天正15年(1587年)12月、四面楚歌となった城村城の隈部親子も、安国寺恵瓊による降伏勧告を受け入れ、ついに開城した 3 。
第四節:一揆の構造と全国的な文脈
肥後国人一揆は、単なる一地方の反乱ではなかった。それは、豊臣秀吉による天下統一事業の最終段階において、太閤検地や惣無事令に象徴される近世的な支配秩序の強制に対し、中世以来の在地領主層が組織的に行った最後の、そして最大級の抵抗であった。
この一揆は、天正18年(1590年)に奥州で発生した葛西大崎一揆と、その構造において驚くほど類似している 41 。両者を比較すると、以下の共通点が見出せる。
- 新領主(肥後の佐々成政/奥州の木村吉清)の強引な統治手法が直接的な引き金となったこと 42 。
- 旧来の支配体制を覆す検地の強行が、国衆・領民の強い反発を招いたこと 42 。
- 改易された旧領主を慕う家臣団と、新たな支配に不安を抱く領民が一体となって蜂起したこと 44 。
- 豊臣政権が大規模な鎮圧軍を派遣し、徹底的な掃討作戦を展開したこと。
- 一揆鎮圧後、抵抗した在地勢力が一掃され、豊臣政権と密接な関係にある大名(肥後の加藤清正・小西行長/奥州の伊達政宗・蒲生氏郷)による新たな支配体制が確立されたこと。
この比較分析から、肥後国人一揆が秀吉の全国統一政策における一つの典型的なパターンであったことが浮かび上がる。秀吉は、中央の統制が及びにくい遠隔地の在地勢力を排除するため、意図的に対立を煽り、それを口実に武力で一掃するという手法を各地で用いていた可能性が高い。隈部親永の悲劇は、この全国的な歴史の潮流の中で捉え直されるべきなのである。
第四章:隈部一族の最期とその後
城村城の開城により、肥後国人一揆は事実上終結した。しかし、それは隈部親永とその一族にとって、壮絶な最期への序章に過ぎなかった。
第一節:降伏と立花宗茂への預託
降伏した隈部親子であったが、秀吉は彼らを許さなかった。一揆の首謀者として、その影響力を根絶する必要があったからである。秀吉は、残党による再蜂起を恐れ、親永と子の親泰を別々の場所で処断することを決定した 21 。
子の隈部親泰は、家老の有働兼元らと共に豊前国小倉城主・毛利勝信に預けられ、間もなく同地で処刑された 21 。一方、父である親永は、二男の親房ら側近12名と共に、筑後国柳川城主・立花宗茂のもとへ預けられることとなった 45 。
第二節:柳川黒門前の「放し討ち」:武士としての最期
天正16年(1588年)5月27日、ついに秀吉からの処刑命令が柳川の立花宗茂のもとに届いた 46 。この時、検使として浅野長政が柳川に来着していたという 46 。
命令を受けた宗茂は、苦しい立場に立たされた。親永は、秀吉からの本領安堵を信じて降伏した身である。それを一方的に斬罪に処すことは、武士の信義にもとる「騙し討ち」に等しい。実父・高橋紹運と養父・立花道雪という二人の名将から武門の誉れを叩き込まれた宗茂にとって、それは断じて受け入れがたいことであった 46 。
しかし、天下人である秀吉の命令に背くこともできない。苦慮の末、宗茂は一つの決断を下す。それは、肥後の勇将である隈部一党の面目を立て、かつ自らの武門の名誉を守るため、前代未聞の処刑方法を検使の浅野長政に願い出ることだった。それが「放し討ち」である 46 。
「放し討ち」とは、罪人に武器を持たせ、同数の討手と一対一で決闘させる処刑方法である。これは、単なる処刑ではなく、罪人に対して武士としての名誉ある死を与える、最大限の敬意を表すものであった 47 。討手側にも死傷のリスクがあるこの申し出に長政は驚いたが、宗茂の信義を貫こうとする決意に心動かされ、ついにこれを許可したという 46 。
かくして、柳川城の黒門前の広場にて、世にも稀な決闘が行われた。隈部親永ら12名は、十時伝右衛門をはじめとする立花家選りすぐりの家臣12名と対峙した 46 。老齢で、先の戦で足に傷を負っていた親永であったが、臆することなく太刀を構えた。凄惨な戦いの末、親永は十時伝右衛門に討ち取られ、他の者たちも激しい刃合わせの末に全員が討ち死にした 46 。この逸話は、親永が敵将である宗茂からも一目置かれ、武士としての最期を飾るにふさわしい器量と武威を備えた人物であったことを雄弁に物語っている。
この「放し討ち」は、立花宗茂個人の信義の発露であると同時に、旧時代の価値観(武士の名誉)と新時代の命令(天下人の絶対的権力)とが衝突した末に生まれた、妥協の産物であった。宗茂は、秀吉の冷徹な命令を履行しつつも、滅びゆく者への手向けとして、武士の作法を貫いた。このエピソードは、時代の大きな転換期に生きた武将たちの、複雑な心境を象徴している。
第三節:隈部氏傍流の存続
隈部親永の死により、肥後国人としての隈部氏正統は滅亡した。しかし、その血脈が完全に途絶えたわけではない 8 。
一族の傍流は、親永に敬意を払った立花宗茂によって取り立てられ、祖先の姓である「宇野氏」に復して柳川藩士として存続した 8 。また、肥後に残った一族もおり、後に細川藩の御小姓を輩出した「仲光氏」や、山鹿郡の惣庄屋を務めた後に隈部への復姓を許され細川藩士となった「中富氏」などが、その子孫として伝えられている 8 。彼らの存在は、隈部氏という一族が、その本拠地であった肥後の地に深く根を下ろしていたことの証しといえるだろう。
第五章:人物像と領国経営の実態
隈部親永とは、一体どのような人物だったのか。彼は単なる反逆者だったのか、それとも領民を思う英雄だったのか。残された史跡や伝承、そして彼を取り巻く状況から、その多面的な人物像と、国人領主としての実力に迫る。
第一節:英雄か、不忠の臣か:多様な人物評価
隈部親永に対する評価は、今日に至るまで二つに大きく分かれている。
一つは、**「英雄」**としての評価である。特に、彼の本拠地であった熊本県山鹿市周辺では、中央の強大な権力に屈することなく、領地と領民を守るために敢然と立ち上がった地元の英雄として、今なお深く敬愛されている 48 。その象徴が、旧居館跡である隈部館跡に建立された隈部神社であり 18 、また、近くの観光施設「あんずの丘」に建てられた、熊本県内最大級とされる巨大な銅像である 53 。地元では、親永は「勇武」(武勇に優れる)、「知政」(統治能力に長ける)、「仁侠」(弱きを助け強きを挫く)の三徳を兼ね備えた人物であったと伝えられている 52 。
もう一つは、**「不忠の臣」**としての評価である。熊本県の無形文化財である伝統芸能「肥後琵琶」には、『菊池崩れ』という演目がある。この物語の中で親永は、主家である菊池氏を裏切り、自らの野心のために赤星氏を追い落とし、結果として菊池家を滅亡に導いた不忠不義の臣として描かれている 11 。
この両極端な評価は、親永の行動をどの立場から見るかによって生じたものである。『菊池崩れ』は、滅び去った名門・菊池氏の視点に立ち、その没落の原因を家臣の裏切りに求める物語構造を持つ。この中では、主家を見限り龍造寺氏と結んだ親永は、格好の「悪役」として描かれる。一方で、山鹿・菊池の領民にとっては、菊池氏はもはや過去の存在であり、自分たちの生活を直接的に保障し、守ってくれるのは領主である隈部氏であった。彼らにとって、親永の抵抗は、新領主・佐々成政による過酷な収奪から自分たちの生活を守るための正義の戦いと映ったのである。この評価の分裂は、中世から近世へと移行する時代の中で、人々の忠誠の対象が「旧来の名門」から「現実の支配者」へと変化していく過程を如実に示している。
第二節:本拠・隈部館の構造と機能
親永が隈府城に移るまで本拠としていた隈部館(永野城)の跡地は、現在、国の史跡に指定され、その遺構が良好な状態で保存されている 56 。この城館の構造は、親永の実像を解き明かす上で多くの示唆を与えてくれる。
隈部館は、標高345メートルの山腹に築かれ、背後には詰城である猿返城が控える、典型的な戦国時代の山城の構造を持つ 18 。発掘調査では、石垣で固められた堅固な枡形虎口(城門の一種)や、敵の侵入を阻む複数の堀切といった、高い防御能力を示す遺構が確認されている 6 。
しかし、特筆すべきは、これらの軍事施設に加え、立石や池泉を備えた本格的な庭園跡が発見されたことである 54 。戦国時代の城館における庭園は、単なる癒やしの空間ではない。それは、領主の権威と文化的素養を内外に示すための重要な政治的装置であった。隈部館の洗練された庭園は、親永が他国の使者や近隣の国衆を饗応し、政治交渉を行うための社交空間として機能していたと考えられる。このことは、彼が単なる一介の武辺者ではなく、肥後北部の有力者たちの中で中心的な役割を担う、政治力と文化資本を兼ね備えた自立した地域権力者であったことを物理的に証明している。武骨な山城のイメージとは裏腹に、隈部氏が高い文化レベルを維持できるだけの経済力と、安定した領国経営を行っていたことが窺える。
第三節:菊池・山鹿郡の経済基盤と信仰
隈部氏の権勢を支えた経済的基盤は、その領国が肥後国有数の穀倉地帯である菊池川流域に位置していたことにあった 60 。安定した農業生産力は、家臣団を養い、軍事力を維持するための根幹であった。
さらに、菊池川は内陸部と有明海を結ぶ物資輸送の大動脈であり、その流域に位置する山鹿は、宿場町・在町(商業が許可された町)として栄えていた 60 。河口の高瀬港は、年貢米などを大坂へ積み出す重要な港であり、この水運を掌握することは、隈部氏の経済力に大きく寄与していた可能性が高い 63 。
信仰面では、主家であった菊池氏以来の伝統を受け継ぎ、領内の寺社を篤く保護していた。特に、山鹿市菊鹿町にある天台宗の古刹・相良寺(あいらじ)は、菊池氏没落後、隈部氏の信仰を受けていたことが記録されている 66 。また、一族の先祖である隈部忠直が光久寺に土地を寄進した記録も残っており 68 、寺社への寄進を通じて領内の安寧を図るとともに、自らの支配の正当性を権威づけていたと考えられる。
結論:時代の転換点に生きた武将
隈部親永の生涯は、中世的な価値観と近世的な支配体制が激しく衝突した、時代の断層そのものであった。彼は、清和源氏の末裔、そして肥後の名門・菊池氏の筆頭家老という誇りを胸に、自らの才覚と武力で激動の戦国時代を生き抜き、肥後北部に一大勢力を築き上げた、戦国国人領主の典型であった。
彼の豊臣政権に対する抵抗は、単なる私利私欲や目前の損得勘定によるものではない。それは、先祖代々受け継いできた土地と、そこに根差した領主としての自立性を守ろうとする、中世武士としての根源的な「意地」に根差していた。太閤検地や惣無事令に象徴される豊臣政権の画一的で中央集権的な支配体制は、彼が守ろうとした世界そのものの否定であり、両者の衝突は歴史の必然であったといえる。
肥後国人一揆の敗北と、それに続く親永の壮絶な最期は、肥後において国人領主の時代が完全に終焉し、加藤清正や小西行長といった豊臣大名による近世的な領国支配が始まる画期的な出来事であった。隈部親永は、歴史の大きな転換点において、旧時代の代表として新しい時代の巨大な波に抗い、そして散っていった。彼の生き様は、戦国という時代の終焉を象徴する、悲劇的でありながらも強烈な光を放つ存在として、後世に記憶されている。
添付資料
表1:隈部親永 関連略年表
|
西暦(和暦) |
隈部親永・隈部氏の動向 |
肥後・九州の情勢 |
中央の情勢 |
|
1559年(永禄2年) |
合勢川の戦いで赤星親家を破る。龍造寺氏と連携を開始 10 。 |
大友氏と龍造寺氏が肥後北部で影響力を争う。 |
織田信長が上洛。 |
|
1573年(天正元年) |
父・親家の隠居により家督を継承か。大友氏傘下の国人として活動 11 。 |
大友氏が肥後北部に強い影響力を持つ。 |
室町幕府滅亡。 |
|
1578年(天正6年) |
大友氏を見限り、龍造寺氏の肥後侵攻に加担 1 。 |
耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗。龍造寺氏が肥後へ侵攻。 |
織田信長、毛利氏との戦い(中国攻め)を本格化。 |
|
1581年(天正9年) |
龍造寺政家の支援で赤星氏の本拠・隈府城を入手し、本拠を移す 1 。 |
龍造寺氏が肥後北部を制圧。 |
織田信長、京都で馬揃えを行う。 |
|
1582年(天正10年) |
- |
- |
本能寺の変。織田信長死去。 |
|
1584年(天正12年) |
龍造寺氏の勢力後退に伴い、肥後へ侵攻してきた島津氏に降伏 1 。 |
沖田畷の戦いで龍造寺隆信が戦死。島津氏が九州の覇権を握る。 |
小牧・長久手の戦い。 |
|
1587年(天正15年) |
豊臣秀吉に降伏。所領を大幅に削減される。佐々成政の検地に抵抗し、肥後国人一揆を主導。城村城に籠城 8 。 |
豊臣秀吉の九州平定。島津氏降伏。佐々成政が肥後国主となる。 |
豊臣秀吉、聚楽第行幸、北野大茶湯開催。 |
|
1588年(天正16年) |
降伏後、立花宗茂に預けられる。5月27日、柳川城黒門前にて「放し討ち」により死没 1 。 |
肥後国人一揆鎮圧。佐々成政が責任を問われ切腹。肥後は加藤清正と小西行長に分割される 3 。 |
豊臣秀吉、刀狩令を発布。 |
引用文献
- 隈部親永(くまべ・ちかなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B0%B8-1072316
- 【信長の野望 覇道】隈部親永の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/377370
- No.043 「 肥後国衆一揆(ひごくにしゅういっき) 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/043.html
- 34-35 くまもとの文化財(PDFファイル:346KB) - 熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/28475.pdf
- 福岡以外の城-隈部館 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/219kumabe-yakata/kumabe-yakata0.htm
- 肥後 隈部館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/higo/kumabe-yakata/
- 平成24年10月4日 https://ja6blv.sakura.ne.jp/roots.htm
- 隈部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E6%B0%8F
- 09他氏の介入|菊池一族公式ウェブサイト https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9292.html
- 福岡以外の城-隈府城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/215kikuchi01/kikuchi001.htm
- 隈部親永 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B0%B8
- 戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について : 起請文の分析を中心に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2000999/files/2024000400.pdf
- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1
- 肥後国衆一揆で豊臣秀吉の九州統一の功労者 佐々成政を切腹に追い込んだ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/21193/
- 古墳巡りシリーズ:隈部親永像、国指定史跡・隈部館跡と朱塚古墳(熊本県山鹿市) https://ameblo.jp/rx7fd3s917/entry-12584575675.html
- 赤星氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%98%9F%E6%B0%8F
- 合勢川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%8B%A2%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 隈部館(熊本県山鹿市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/9611
- 菊池城の見所と写真・100人城主の評価(熊本県菊池市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/817/
- 隈府(わいふ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9A%88%E5%BA%9C-879780
- 隈部親泰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B3%B0
- adeac.jp https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht050260#:~:text=%E4%BD%90%E3%80%85%E6%88%90%E6%94%BF%E3%81%B8%E8%82%A5%E5%BE%8C%E4%B8%80,%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
- 肥後国衆一揆 | オールクマモト https://allkumamoto.com/history/higo_uprising_1587
- 加 藤 清 正 実 像 - 熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032846/Bun_89199_21_0044e_09_201201.pdf
- 肥後国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86
- 肥後国人一揆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86
- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/
- 安土桃山時代|宇土市公式ウェブサイト https://www.city.uto.lg.jp/museum/article/view/8/377.html
- 2017「隈部親永一族・鞠智城を訪ねて」資料・千寿の楽しい歴史 https://kusennjyu.exblog.jp/23774303/
- 隈部氏館跡リーフレット表(PDF文書)(PDF:735.8キロバイト) - 山鹿市 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji003206/3_206_3_kumabe01.pdf
- 第6章 郷土の三英傑に学ぶ資金調達 - 秀吉、太閤検地で構造改革を推進 https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-23.html
- 「太閤検地」とはどのようなもの? 目的や、当時の社会に与えた影響とは【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/269995
- 太閤検地(タイコウケンチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AA%E9%96%A4%E6%A4%9C%E5%9C%B0-91096
- 特別寄稿佐々成政と肥後国衆一揆 ~中世から近世への歴史的転換点 https://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/magazine/narimasa/sasa0205.html
- 肥後田中城 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/314/314shiro.pdf
- 〜中世肥後の終焉〜 肥後国衆一揆最後の砦⚔️田中城跡|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/nfcdcc25d3007
- 城村城跡 | 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト https://kumamoto-museum.net/blog/archives/chiiki/1215
- No.080 「 肥後の国衆(くにしゅう)一揆 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/080.html
- 田中城 (肥後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%9F%8E_(%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD)
- 田中城跡(国史跡) / 観光情報TOP / 和水町 https://www.town.nagomi.lg.jp/kankou/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=624&class_set_id=6&class_id=590
- 葛西大崎一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E5%A4%A7%E5%B4%8E%E4%B8%80%E6%8F%86
- 九州平定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B9%B3%E5%AE%9A
- 葛西大崎一揆(かさいおおさきいっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E5%A4%A7%E5%B4%8E%E4%B8%80%E6%8F%86-1153956
- 大條実頼(着座大條家第一世)【中】 - note https://note.com/oeda_date/n/n1b9ae068f593
- 2017『黒門前の決闘(放し討ち)について』の紹介5・千寿の楽しい歴史 - エキサイトブログ https://kusennjyu.exblog.jp/23880218/
- 2017『黒門前の決闘(放し討ち)について』の紹介2・千寿の楽しい歴史 - エキサイトブログ https://kusennjyu.exblog.jp/23861025/
- 無双と呼ばれた男~立花宗茂 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/musou-muneshigetachibana/
- 隈部氏館跡 - 菊鹿町観光協会 https://yamaga-kikuka.com/wp-content/uploads/2021/02/0abab1b1e304cf4ca6d08897dc30b78c.pdf
- 立花宗茂の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/32514/
- 新・肥後細川藩侍帳【な】の部 http://www.shinshindoh.com/samurai/20-na.htm
- 新・肥後細川藩侍帳【と】の部 http://www.shinshindoh.com/samurai/19-to.htm
- 隈部神社の祀りの由来 https://ja6blv.sakura.ne.jp/kumabehokora.htm
- 県内最大級の武士像が完成しました(隈部親永公像) - 山鹿市 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji003149/index.html
- 隈部氏館跡を訪ねて・千寿の楽しい歴史 https://kusennjyu.exblog.jp/16521638/
- 菊池くずれ短縮版|琵琶語りのコタロウ - note https://note.com/biwagatarinokota/n/n0c89201f094d
- 隈部氏館跡 (戦国時代 肥後の有力国人の居館跡) - 山鹿市 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji003206/index.html
- 隈部館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E9%A4%A8
- 隈部館の見所と写真・100人城主の評価(熊本県山鹿市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/810/
- 隈部館跡 - 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト https://kumamoto-museum.net/blog/archives/chiiki/1213
- 山鹿の歴史 https://www.ne.jp/asahi/yamaga/mydm/yinfo/ya_his01.html
- 熊本県の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
- 山鹿市歴史的風致維持向上計画(第2期) https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji003618/3_618_1_up_6IBPM137.pdf
- 菊池川流域の歴史と鞠智城 - 熊本県立装飾古墳館 https://kofunkan.pref.kumamoto.jp/kikuchijo/kikuchi-river/
- 熊本藩高瀬米蔵跡と菊池川の港まち「高瀬」|玉名の自然、景観 - note https://note.com/tamananto/n/n338a5cd51b99
- 菊池川下流域の船着場と港町 (高瀬大浜晒) https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/58/58234/138870_1_%E7%86%8A%E6%9C%AC%E8%97%A9%E9%AB%98%E7%80%AC%E7%B1%B3%E8%94%B5%E8%B7%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
- 相良寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E5%AF%BA
- 【相良寺】山鹿市の安産祈願に相良観音様へご参拝 - 熊本のパワースポット旅 https://kumamoto-powerspot.com/temple/aira-temple/
- 光九寺跡(こうきゆうじあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E4%B9%9D%E5%AF%BA%E8%B7%A1-3101886
- 第2節 隈府地区の調査 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/51/51597/130992_2_%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%B0%8F%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf