万葉集
『万葉集』は日本最古の和歌集で、戦国時代に再評価された。万葉仮名が読解の障壁となるも、中世には解読が進む。多様な歌風と編纂の謎を持ち、時代を超えた普遍的価値を持つ。
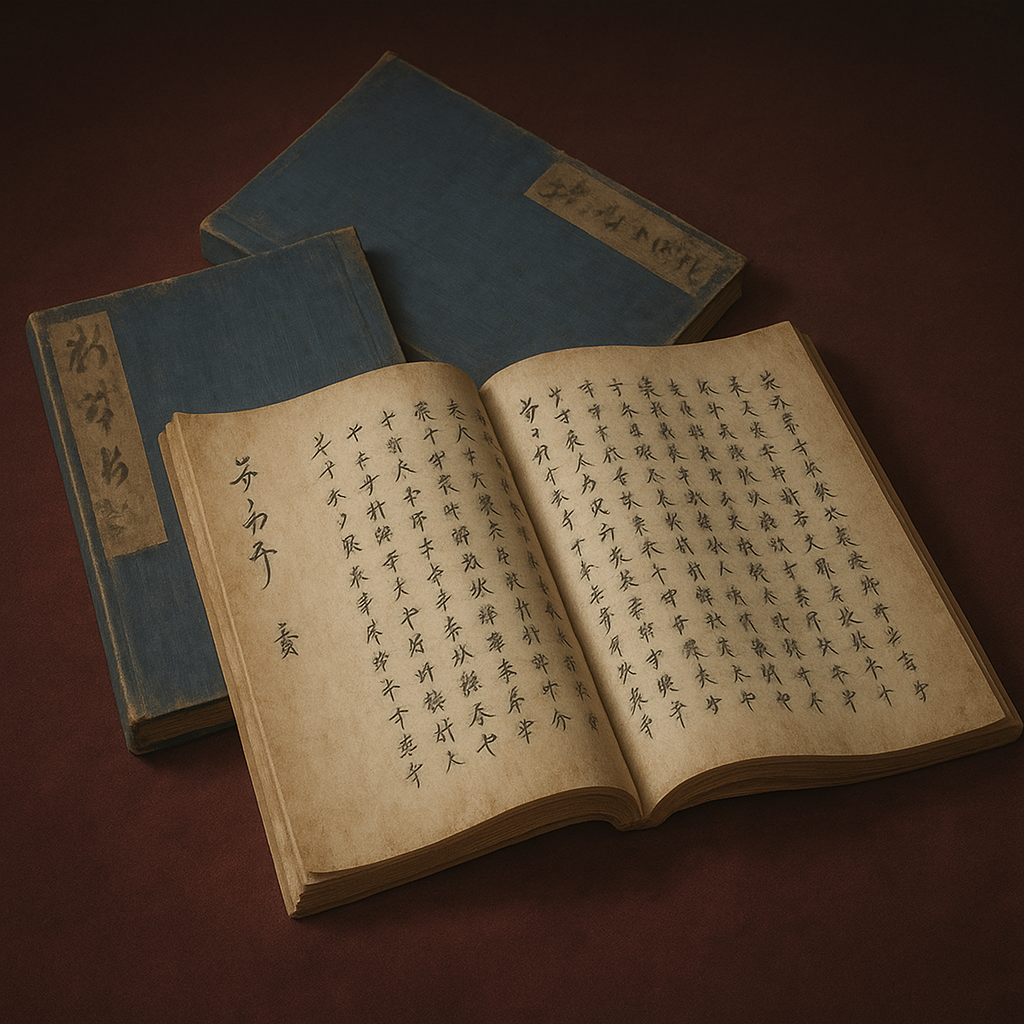
『万葉集』に関する専門調査報告書:戦国時代の視座から
序論:時代を超克する「言の葉」— 戦国武将は『万葉集』をどう読んだか
本報告書は、現存する日本最古の和歌集である『万葉集』を、その成立から約800年の時を経た「戦国時代」という特異な時代的文脈の中に位置づけ、その受容の実態を多角的に解明することを目的とする。奈良時代に編纂されたこの巨大な歌集が、なぜ下剋上の乱世に生きた武将たちの関心を惹きつけたのか。それは単なる風雅な教養趣味に留まるものであったのか、あるいは彼らの精神性や文化的戦略と分かち難く結びついていたのか。この根源的な問いの探求を通じて、『万葉集』が持つ時代を超えた普遍性と、特定の時代状況に応じて変容する多面的な価値を明らかにする。
分析にあたり、本報告書は三部構成を採る。第一部では、『万葉集』自体の構造的・歴史的特質を専門的に詳解する。第二部では、上代から中世にかけての受容史、特に「解読」をめぐる知的挑戦の歴史を辿り、戦国時代に至るまでの『万葉集』のテクストとしての地位を明らかにする。そして第三部において、戦国時代の文化的状況、特に和歌や連歌の流行と武将たちの動向の中に、『万葉集』が果たした具体的な役割を位置づけ、その影響を考察する。
本報告書の分析を通じて、戦国時代における『万葉集』の受容が、公家の伝統的権威であった『古今和歌集』とは異なる、武家社会の気風や新興文芸の要請に応える「もう一つの古典」としての貌(かたち)を帯びていたことを論証する。それは、乱世の覇者が文化の覇者でもあることを示すための、高度な知的営為であった。
第一部:『万葉集』の基礎構造 — 歌、歌人、そして編纂の謎
戦国時代の視点から『万葉集』を分析するためには、まずその前提知識として、歌集そのものの成り立ちと構造を学術的な深度をもって理解することが不可欠である。本第一部では、その重層的な構造、編纂の謎、歌風の変遷、そして古代人の世界観を反映した分類法について詳述する。
1.1. 歌集の概要と構成:一巻から二十巻までの重層的構造
『万葉集』は、全20巻、収録歌数約4500首(正確には4516首)を数える、日本に現存する最古にして最大の歌集である 1 。収録された歌の制作年代は、仁徳天皇の皇后・磐之媛や雄略天皇の作と伝承される歌から、淳仁天皇治世下の天平宝字三年(759年)に詠まれた大伴家持の歌まで、約130年間の長大な期間を包括している 1 。
この歌集の顕著な特徴は、作者層の驚くべき多様性にある。天皇や皇族、貴族、高級官人といった支配者層の歌はもちろんのこと、彼らに仕えた下級官人、さらには東国農民の素朴な歌である「東歌(あずまうた)」や、九州の防衛に赴いた兵士たちの望郷の念が込められた「防人歌(さきもりうた)」まで、極めて幅広い階層の人々の声が記録されている 4 。この点は、後の勅撰和歌集が主に貴族社会の歌に限定されたことと対照的であり、『万葉集』の持つ国民的文学としての性格を基礎づけている。
全20巻の構成は、単純な年代順にはなっていない。各巻がそれぞれ独自の編集方針や特徴を有しており、全体として重層的かつ複雑な構造をなしている 7 。
- 巻一・二: 『万葉集』全体の構成原理を提示する巻と見なされる。巻一は天皇の行幸や宮廷儀礼など公的な場での歌「雑歌(ぞうか)」を、巻二は天皇や皇族間の恋愛や死を悼む私的な歌「相聞(そうもん)」「挽歌(ばんか)」を、それぞれ天皇の御代ごとに配列する 8 。この二巻は早い段階で成立し、後に続く巻々の原型となった「原万葉集」とも考えられている 2 。
- 巻三〜十六: 巻一・二を増補し、展開させた部分と位置づけられる。雑歌・相聞・挽歌の三大部立(さんだいぶだて)が見られる巻(巻三、七、九、十三、十四など)のほか、春夏秋冬の季節に沿って歌を並べた巻(巻八、十)、旅や伝説を主題とする巻(巻九)、特定の地域(東歌、防人歌)や特定の歌人(柿本人麻呂、山上憶良など)に焦点を当てた巻など、多種多様な編集意図が混在している 2 。
- 巻十七〜二十: 最終編纂者と目される大伴家持の私的な歌日記、あるいは彼の家集としての性格が極めて濃厚な部分である 2 。特に、彼が越中国守として赴任していた5年間に詠んだ歌が突出して多く収録されており 7 、家持個人の創作活動の軌跡を色濃く反映している。歌集の最後を飾る4516番歌は、天平宝字三年正月一日に、家持が因幡国庁で詠んだ新年を祝う歌である 14 。
このように、『万葉集』は単一の意図によって貫かれた書物ではなく、複数の歌集や資料が段階的に編み合わされて成立した、巨大なアンソロジーとしての性格を持っている。
1.2. 編纂者をめぐる諸説:混沌の向こう側に見える人影
『万葉集』には、編纂者の名が記されておらず、その特定は長年にわたる学術的な論争の的となってきた 17 。いくつかの説が提唱されてきたが、現在では大伴家持を中心とする編纂過程が最も有力視されている。
- 大伴家持中心編纂説: この説を支える論拠は複数ある。第一に、家持の歌が473首と群を抜いて多く、かつ歌集全体の最終歌の作者であること 7 。第二に、家持の手記によると考えられる資料が、他のどの資料よりも時代的に新しく、かつ豊富に用いられていること 18 。第三に、家持の作品には柿本人麻呂や山上憶良といった先行歌人からの影響が顕著に見られ、彼が過去の膨大な和歌作品を熟知し、それらを編纂素材として自在に扱える立場にあったことがうかがえる点である 18 。これらの状況証拠から、複数の私家集や古歌集を核とし、父・旅人や山上憶良ら大伴氏ゆかりの歌人の作品群を加え、最終的に家持が自身の歌日記を統合して現行の20巻の形にまとめた、という段階的な編纂過程が想定されている 2 。
- その他の編纂者説: かつては有力な政治家であった橘諸兄(たちばなのもろえ)を編纂者とする説も存在した。しかし、諸兄自身にとって極めて重要な、橘姓を賜った際の記念碑的な歌の作者が「未詳」とされている点などから、彼が編者である可能性は低いと現在では考えられている 18 。また、特定の個人ではなく、複数の編者が長い年月をかけて関与したとする「段階的編纂説」も根強い。これは、巻ごとに編集方針が統一されていないという『万葉集』の「乱雑な構成」を説明するものである 17 。
編纂の背景には、家持個人の政治的運命が影を落としている。彼は武門の名家・大伴氏の嫡流として順調な官途を歩んだが、晩年には藤原氏との政争に巻き込まれ、長岡京遷都を主導した藤原種継の暗殺事件に連座したとして、死後に官位を剥奪され、その財産も没収された 22 。この家持の悲劇的な失脚が、『万葉集』が完成後しばらくの間、歴史の表舞台から姿を消し、平安時代中期まで文献にその名が登場しない一因になったとする説は極めて有力である 22 。歌集の成立は、単なる文学的営為に留まらず、奈良時代末期の激しい政治闘争と深く結びついていたのである。
1.3. 主要歌人と四つの時代区分:歌風の変遷
『万葉集』に収められた約130年間の歌は、その作風の変遷から、大きく四つの時期に区分して理解されるのが一般的である 3 。この時代区分は、歌集のダイナミックな展開を把握する上で有効な視点を提供する。
- 第一期(舒明朝〜壬申の乱、7世紀中頃):
- 代表歌人: 額田王(ぬかたのおおきみ)、有間皇子(ありまのみこ)など、皇族が中心 6 。
- 歌風: 宮廷儀礼や行幸といった公的な場面で詠まれる歌が多く、個人の内面的な感情よりも、共同体の意志や感情を代弁する叙事詩的な性格が強い 19 。歌は個人の表現である以前に、政治的・社会的な機能を持つものであった。
- 第二期(壬申の乱後〜平城遷都、7世紀末〜8世紀初頭):
- 代表歌人: 柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)。身分は六位以下の下級官人であったと推定される 6 。
- 歌風: 「歌聖」と称される人麻呂の登場により、和歌は飛躍的な発展を遂げる。長歌とそれに添えられる短歌(反歌)という形式を駆使し、天皇や皇族を賛美する壮大な歌や、人の死を悼む荘重な挽歌など、公的な題材を扱いながらも、卓越した表現力と普遍的な人間感情を盛り込み、和歌を個人の芸術表現として確立させた 5 。
- 第三期(平城京時代前半、8世紀前半):
- 代表歌人: 山部赤人(やまべのあかひと)、山上憶良(やまのうえのおくら)、大伴旅人(おおとものたびと)など、個性豊かな歌人が輩出した 19 。
- 歌風: 多様化の時代。山部赤人は、自然の風景を客観的かつ絵画的に描写する「自然詩人」として、叙景歌の伝統を確立した 19 。一方、遣唐使としての経験を持つ山上憶良は、儒教や仏教の思想を背景に、貧者の苦しみ(貧窮問答歌)や子への愛情といった、社会性・思想性の強い独自の歌世界を切り開いた 19 。また、大伴家持の父である大伴旅人は、大宰府の長官として赴任中、文化サロンを主宰し(梅花の宴など)、中国文学の影響を受けた知的で洒脱な歌を残した 19 。
- 第四期(平城京時代後半〜天平宝字年間、8世紀中頃):
- 代表歌人: 大伴家持。貴族であり、最終編纂者と目される 6 。
- 歌風: これまでの時代の歌人たちの影響を色濃く受けながら、それを自らの内で昇華させ、繊細で主観的な叙情性を深めた。宮廷での公的な歌から、個人的な憂愁や喜びを吐露する私的な歌まで、その作風は多岐にわたる。彼の歌は、奈良時代の集大成であると同時に、平安和歌へと続く優美で内省的な流れを準備したと言える 19 。
【表1:『万葉集』四期分類と代表歌人・歌風の比較】
|
期 |
時代 |
代表歌人 |
身分(推定) |
歌風の特徴 |
|
第一期 |
舒明朝〜壬申の乱 |
額田王、有間皇子 |
皇族 |
公的・儀礼的・集団的。共同体の感情を代弁する叙事詩的性格。 |
|
第二期 |
壬申の乱後〜平城遷都 |
柿本人麻呂 |
下級官人 |
荘重・雄大。長歌を駆使し、公的な題材に普遍的人間感情を詠み込む。和歌の芸術的確立。 |
|
第三期 |
平城京時代前半 |
山部赤人、山上憶良、大伴旅人 |
下級官人、貴族 |
多様化の時代。自然を詠む叙景歌(赤人)、社会性・思想性の強い歌(憶良)、知的・洒脱な漢詩文趣味の歌(旅人)が並立。 |
|
第四期 |
平城京時代後半 |
大伴家持 |
貴族 |
先行歌人の影響を統合し、繊細で主観的な叙情性を深める。公私の両面にわたり、平安和歌への橋渡しとなる。 |
1.4. 歌の三大部立「雑歌・相聞・挽歌」:古代人の世界観の反映
『万葉集』の歌は、内容によって大きく三つのカテゴリー、すなわち「三大部立」に分類される。この分類法は、古代日本人の世界観や、歌が担っていた役割を理解する上で重要な手がかりとなる。
- 部立の定義:
- 雑歌(ぞうか): 文字通り「雑多な歌」という意味ではなく、相聞・挽歌以外の公的な歌全般を指す。宮廷儀礼、天皇の行幸、宴席での歌、旅の歌など、主に共同体の「ハレ」の場面で詠まれた歌がここに分類される 3 。
- 相聞(そうもん): 本来は「互いに消息を通わせる」という意味で、親子、兄弟、友人など親しい間柄での贈答歌も含まれるが、その圧倒的多数は男女間の恋愛を詠んだ歌である 4 。個人の私的な情愛の世界を扱う。
- 挽歌(ばんか): 人の死を悼み、哀悼の意を表す歌。元々は、葬送の際に棺を挽く人々が歌った歌に由来するとされる 26 。死という人間存在の根源的な出来事に向き合う。
この三大部立は、巻一に「雑歌」、巻二に「相聞」「挽歌」が配されることで、歌集の冒頭で明確に提示されており、『万葉集』全体の分類の基本骨格をなしている 11 。この分類法の起源については、中国文学からの影響が指摘されている。特に、六朝時代の詩文集『文選』に「雑歌」「挽歌」という分類名が見られることから、編纂者がこれを参考にした可能性が高い 11 。一方で、「相聞」という部立名は『文選』にはなく、『万葉集』独自の分類と考えられる 27 。
さらに、中国最古の詩集である『詩経』の三分類「風(ふう)・雅(が)・頌(しょう)」との内容的な類似性も注目される。「風」が民間の恋歌、「雅」が宮廷の公的な歌、「頌」が宗廟祭祀の歌であることから、「相聞」が「風」に、「雑歌」が「雅」に、「挽歌」が「頌」にそれぞれ対応するという見方である 27 。しかし、『万葉集』の分類は必ずしも厳密ではなく、例えば雑歌の部に相聞的な歌が混入するなど、後から既存の歌群の傾向を考慮して大まかに部立を冠した可能性も示唆されている 27 。この分類は、神と関わる公的な世界(雑歌)、人と人との愛(相聞)、そして人の死(挽歌)という、古代人の人間理解の根幹をなす三つの領域を歌によって表現しようとしたものと解釈できる 11 。
第二部:解読への挑戦 — 万葉仮名と中世における『万葉集』の受容
奈良時代に編纂された『万葉集』が、後の時代、特に武家社会に受容される上で最大の障壁となったのが、その特殊な表記法「万葉仮名」であった。本第二部では、この万葉仮名の複雑な特質と、その解読をめぐる中世の学問的営為を詳述する。これにより、戦国武将が『万葉集』に触れる際の知的背景を明らかにする。
2.1. 万葉仮名の複雑な世界:音と意味の遊戯
万葉仮名とは、漢字が本来持つ意味(表意性)とは関わりなく、その音や訓を借りて日本語の音節を表記するために用いられた漢字のことである 29 。後に生まれる平仮名や片仮名の母体となった、日本独自の文字文化の原点と言える 31 。
その用法は多岐にわたるが、大きく二つに大別される。一つは漢字の音読みを利用する**音仮名(おんがな)で、「花」を「波奈(はな)」、「秋」を「安吉(あき)」と表記する類である 29 。もう一つは漢字の訓読みを利用する
訓仮名(くんがな)**で、「夏樫(なつかし)」や、魚の「鱸」を「為酢寸(すずき)」と表記するような例がこれにあたる 31 。
江戸時代の学僧・春登(しゅんとう)は、その著書『万葉用字格』の中で、この複雑な用法をさらに精密に8種類に分類した 29 。正音・略音(音仮名の細分化)、正訓・義訓・略訓・約訓・借訓(訓仮名の多様なバリエーション)、そして「十六(しし)」や「山上復有山(出づ)」のような、字謎や言葉遊びに近い高度な**戯書(ぎしょ)**である 29 。特に「恋」を「孤悲(こひ)」と表記するように、音を借りながらも漢字の意味を巧みに重ね合わせる用法は、万葉仮名の表現の豊かさを示している 31 。
しかし、『万葉集』の読解を最も困難にした要因は、 上代特殊仮名遣い 、通称「甲乙(こうおつ)の別」の存在であった。これは、奈良時代以前の日本語には、現代では区別されない母音の発音が存在したことを示す証拠である。具体的には、キ、ヒ、ミ、ケ、ヘ、メ、コ、ソ、ト、ノ、ヨ、ロなどの音節において、それぞれ2種類の発音(甲類・乙類)があり、『万葉集』ではこれらを異なる漢字を用いて厳密に書き分けていた 32 。例えば、同じ「こ」の音でも、「心(こころ)」の「こ」は「許」や「己」といった乙類の文字で書かれるのに対し、「子(こ)」は「古」や「故」といった甲類の文字で書かれ、両者が混用されることはなかった 33 。この書き分けは、当時の人々がこれらの音を明確に発音し分けていたことを物語る、言語史上の極めて貴重な資料である。
【表2:上代特殊仮名遣い(甲乙の別)の具体例】
|
音 |
甲類(Type A) |
乙類(Type B) |
|
|
万葉仮名例 |
使用語例 |
|
キ |
支、吉、岐、来 |
秋、君、時、聞く |
|
コ |
古、故、固、姑 |
子、衣、此処 |
|
ヒ |
比、必、卑、賓 |
日、干、氷、光 |
|
メ |
売、馬、米、迷 |
目、芽、女 |
|
ヨ |
用、容、欲、夜 |
夜、四、吉野 |
この発音上の区別は平安時代に入ると次第に失われ、一つの音に統合されていった 35 。その結果、後世の人々にとっては、なぜ同じ音に対して複数の異なる漢字が意図的に使い分けられているのか、その理由が全く理解できなくなり、『万葉集』は専門的な知識なしには解読不能な「古人の暗号」と化してしまったのである。
2.2. 平安時代の「忘却」と鎌倉時代の「再発見」:仙覚の功績
上代特殊仮名遣いに代表される言語的障壁のため、平安時代中期には『万葉集』は一部の専門家を除いてほとんど読まれなくなり、「忘却」の時代を迎えた 36 。宮廷和歌の世界では、より洗練され、理解しやすい『古今和歌集』が絶対的な規範となり、『万葉集』は歴史の奥深くへと沈んでいった。
この状況に決定的な転機をもたらしたのが、鎌倉時代である。武家政権が確立し、公家文化とは異なる新たな価値観が模索される中で、『万葉集』の持つ力強さや素朴さへの関心が再び高まり始めた。この「再発見」の動きの中心にいたのが、学僧・**仙覚(せんがく)**であった 38 。
建仁三年(1203年)に生まれた仙覚は、13歳で『万葉集』研究を志し、生涯をその解読と注釈に捧げた 38 。彼の最大の功績は、当時諸本に散在していた『万葉集』を校合し、それまで誰も訓(よみ)を付けることができずにいた難解な152首の歌に、新たに訓点を施したことである。これを「新点(しんてん)」と呼び、これによりついに『万葉集』の全歌約4500首が読解可能となった 38 。この画期的な事業は、鎌倉幕府第四代将軍・藤原頼経の命を受けて行われたものであり、武家政権による文化事業としての一面も持っていた 38 。
さらに仙覚は、訓点事業に留まらず、詳細な注釈書である**『万葉集註釈』(通称『仙覚抄』)**を著し、書名や撰者、用字法などに関する考証的研究も行った 40 。彼の業績は、それまで暗号のようであった『万葉集』を、後世の研究者が学問的にアプローチできる対象へと変貌させ、近世の国学に至るまでの万葉研究の揺るぎない基礎を築いたのである。
2.3. 武士の心性と「ますらおぶり」:もう一つの和歌観
鎌倉時代以降、武家社会が台頭する中で、『万葉集』は新たな価値基準によって評価されるようになる。その中心的な概念が「 ますらおぶり 」である。
この言葉を定着させたのは、江戸時代の国学者・賀茂真淵(かものまぶち)である。彼は、『万葉集』の歌風を、飾り気がなく、おおらかで力強い男性的な風格、すなわち「ますらおぶり(益荒男振り)」と評した 42 。これは、平安時代の『古今和歌集』に代表される、繊細で優美、知的な技巧を凝らした「たおやめぶり(手弱女振り)」と明確に対比される概念であった 44 。
この「ますらおぶり」という価値観は、特に鎌倉時代の武士たちの気風と強く共鳴したと考えられる 44 。質実剛健を理想とし、実生活における素朴な感動や強い実感を重んじる武士の精神性にとって、『古今和歌集』の洗練された美意識よりも、『万葉集』の直接的で力強い表現の方が、より親和性が高かったのである。将軍家で『万葉集』が愛読され、関東で実証的な研究が進められた背景には、こうした武家社会独自の美意識があった 44 。
戦国武将もまた、この鎌倉武士の精神的後継者であり、彼らが『万葉集』に関心を寄せた根底には、公家文化の規範とは異なる、自らのアイデンティティに合致した「もう一つの古典」を求める意識があったと見ることができる。なお、この「ますらおぶり」という評価は、近代に至って、防人歌などにみられる自己犠牲の精神が強調され、軍国主義的な思想を鼓舞するために利用されるという側面も持つことになった 46 。
第三部:戦国乱世のなかの『万葉集』— 武将たちの教養と創作
本報告書の中核となる本第三部では、これまでの分析を踏まえ、戦国時代の具体的な文化的コンテクストの中に『万葉集』を位置づける。そして、武将たちがこの難解な古典をいかに受容し、自らの文化活動や精神世界に反映させていったのかを、人物や作品を例に挙げて詳述する。
3.1. 戦国武将と和歌・連歌:必須の教養と外交ツール
戦乱に明け暮れた戦国時代であるが、武将たちにとって和歌や連歌は、単なる慰みや風流な趣味ではなかった。それは、彼らの社会を生き抜く上で不可欠な教養であり、実用的なツールでもあった。
和歌は、荒んだ心を慰める精神的な支えであったと同時に 47 、その人の教養の深さを示すバロメーターであった 48 。武田信玄が京都から公家を招いて頻繁に歌会を催したように 49 、和歌に通じていることは一流の武将たる証とされた。また、手紙や贈答の際に和歌を詠み交わすことは、外交交渉や人間関係を円滑に進めるための重要なコミュニケーション手段として機能した 50 。
特に戦国時代に大流行したのが、和歌から派生した**連歌(れんが)**である 52 。これは、五・七・五の長句と七・七の短句を、複数の参加者(連衆)が交互に詠み繋いでいく集団創作詩である 54 。連歌会は、単なる文芸の会に留まらず、情報交換や同盟関係の確認、政治的駆け引きの場といった、高度に社会的な機能を帯びていた 52 。織田信長への謀反を決意した明智光秀が、その直前に愛宕山で催した連歌会「愛宕百韻」は、連歌が歴史の重要な局面に深く関わっていたことを示す象徴的な出来事である 52 。この流行を背景に、里村紹巴(さとむらじょうは)のような専門の連歌師が登場し、各地の大名に指南役として仕え、連歌文化の普及と深化に大きな役割を果たした 52 。
3.2. 連歌における『万葉集』の位置づけ:新たなインスピレーションの源泉
連歌というジャンルの発展は、『万葉集』が再評価される上で重要な契機となった。なぜなら、連歌はその創作の典拠(寄り所)として、『万葉集』を積極的に活用したからである。
伝統的な和歌の世界では、平安時代に編纂された『古今和歌集』が絶対的な規範(手本)とされ、その歌を元に新たな歌を詠む「本歌取り」という技法が重視された。これに対し、次々と句を詠み繋いでいく連歌では、より自由で多様な発想が求められた。そのため、連歌師たちは『古今和歌集』の典雅な世界に留まらず、より古い時代の『古事記』や『日本書紀』、そして『万葉集』に新たなインスピレーションの源泉を求めた 57 。
連歌が『万葉集』を重視した理由はいくつか考えられる。第一に、 語彙の豊富さ である。『万葉集』に見られる素朴で力強い言葉、動植物や各地の地名といった多様な題材は、ともすればマンネリに陥りがちな連歌の世界に、新鮮な言葉とイメージを供給する宝庫であった。第二に、 権威の相対化 という側面である。『古今和歌集』の確立された美意識から意図的に距離を置き、より古層の『万葉集』を参照することは、連歌というジャンル独自の芸術性を追求する上で有効な戦略であった 57 。そして第三に、
難解さそのものが持つ価値 である。『万葉集』は仙覚以降、読解可能になったとはいえ、依然として高度な学識を要する難解な古典であった。そのため、連歌の座において『万葉集』から巧みに句を引用することは、作者の学識の深さを一座の連衆に示すことになり、その文化的権威を高める効果があった 57 。
3.3. 文化人武将・細川幽斎の万葉観:二つの古典を統べる者
戦国時代における『万葉集』の受容を最も象徴する人物が、**細川幽斎(藤孝)**である。彼は足利義輝に始まり、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、激動の時代を生き抜いた武将であると同時に、和歌、連歌、茶の湯など諸芸に通じた当代随一の文化人であった 51 。
幽斎の文化人としての地位を不動のものとしたのは、彼が和歌の奥義とされる「 古今伝授 」を、その正統な継承者である公家の三条西家から受け継いだことである 59 。これは、彼が公家文化の頂点に立つ和歌の伝統を完全にマスターしたことを意味する。慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いの際、西軍に居城の田辺城を包囲された幽斎を救ったのは、軍勢ではなく、「古今伝授の断絶を恐れた」後陽成天皇の勅命であったという逸話は、彼の文化的権威の絶大さを物語っている 59 。
しかし、幽斎の教養は『古今和歌集』に留まらなかった。彼は『万葉集』にも極めて深い造詣を持っていた 60 。そのことは、彼の著作や和歌から明確に読み取れる。例えば、彼が九州へ下向した際の紀行文『九州道の記』には、『万葉集』の歌枕や古歌を踏まえた作品がいくつも見られる。ある岬で詠んだ歌は、地名の由来を聞いた上で『万葉集』の歌を意図的にもじったものであり、彼の深い知識と知的遊戯の精神を示している 61 。また、彼自身が『万葉集』の歌風を「丈夫(ますらお)の手振り」と評しており、武家の気風と響き合う「ますらおぶり」の価値観を明確に認識していたことがわかる 63 。
幽斎は、公家文化の象徴である『古今和歌集』と、武家文化と親和性の高い『万葉集』という、二つの異なる価値を持つ古典を、一人の人間の中で統合した稀有な存在であった。秀吉から、亡き子・鶴松を悼む悲痛な歌への返歌を求められるという極めて難しい課題に対し、深い人間洞察と古典の教養を背景に見事な歌を返した逸話は 51 、彼にとって和歌が、単なる遊戯ではなく、人間関係の機微を読み解き、天下人の心さえも動かすことのできる、高度な知性の発露であったことを示している。
3.4. 諸大名と古典の関わり:作品世界に見る万葉的感性
細川幽斎ほど体系的ではないものの、他の戦国大名の作品や言動にも、『万葉集』に通じる感性や、古典への関心の高さを見て取ることができる。
- 伊達政宗: 「独眼竜」の勇猛なイメージとは裏腹に、多数の和歌や漢詩を残した教養人であった 64 。彼の和歌には月の歌が多く、特に故郷・松島の月や、歌枕として名高い「さらしなの月」への言及が見られる 66 。これは、主君であった豊臣秀吉が伏見城から見る月を「さらしなや松島の月にも劣らない」と自慢した歌を詠んだことと無関係ではないだろう 66 。直接的な『万葉集』からの引用は確認しにくいが、武蔵野の広大さを詠んだ歌 67 などには、『万葉集』の東歌に描かれた雄大な自然のイメージと響き合う感性が認められる。
- 上杉謙信: 「軍神」と称された謙信は、熱心な仏教徒としても知られ、その辞世の句・歌は仏教的な無常観や悟りの境地を詠んだものが多い 68 。一方で、能登攻略の陣中で詠んだとされる「もののふの鎧の袖をかたしきて枕に近き初雁の声」という歌は、戦を前にした武人の孤独と張り詰めた緊張感を、飾り気のない言葉で率直に表現している 71 。この素朴で力強い情感は、『万葉集』の防人歌の世界と通底するものがある。
- 武田信玄: 信玄もまた和歌に熱心で、京都から公家を招いて歌会を催すほどであった 49 。現存する「武田晴信朝臣百首和歌」は、彼の高い教養レベルを示している 72 。彼の歌も、戦や人生の無常を詠んだものが多く、観念的な遊戯ではなく、武将としての日々の実感が込められている点に特徴がある 49 。
【表3:戦国武将と和歌・古典文学の関わり】
|
武将名 |
主な文化活動 |
代表的な和歌・逸話 |
『万葉集』との関連性 |
|
細川幽斎 |
和歌、連歌、茶の湯、故実 |
古今伝授の継承。秀吉との和歌の贈答。 |
直接的・体系的な研究と引用。『万葉集』の歌を本歌取りした作品や、紀行文での言及が多数。 |
|
伊達政宗 |
和歌、漢詩、能、茶の湯 |
辞世の句「曇りなき心の月を先だてて…」。月の歌を多く詠む。 |
間接的影響。雄大な自然観や、東国のイメージに万葉的感性との類似性が見られる。 |
|
上杉謙信 |
和歌、仏教信仰 |
辞世の句「極楽も地獄も先はありあけの…」。陣中の歌「もののふの鎧の袖を…」。 |
歌風の類似性。陣中で詠んだ歌の素朴で力強い情感が、防人歌と通底する。 |
|
武田信玄 |
和歌、漢詩 |
「武田晴信朝臣百首和歌」。「誰も見よ満つればやがて欠く月の…」。 |
歌風の類似性。実感を込めた無常観の表現に、万葉的な直接性が見られる。 |
3.5. 戦国期の写本と研究の様相:乱世における知の継承
戦国時代、『万葉集』は広く一般に読まれる書物ではなかった。江戸時代に木版印刷による 古活字版 や整版が出版されるまで、その本文はすべて高価な手書きの写本によって伝えられていた 73 。戦国時代は、この長きにわたる写本文化の最終期にあたる。
このような状況下で、『万葉集』の研究と伝承を担ったのは、ごく一部の知的エリート層であった。その中心にいたのが、 三条西家 のような公家の学問家たちである。彼らは古今伝授を家職としながらも、『万葉集』の研究にも取り組み、貴重な写本を所蔵していた 76 。江戸時代の国学者・契沖に影響を与えた下河辺長流が、三条西家の蔵書を見るために青侍として仕官したという逸話は、彼らが戦国期における古典研究の一大センターであったことを示している 76 。
もう一つの担い手が、 里村紹巴 に代表される連歌師たちであった。彼らは、連歌創作の典拠として『万葉集』を実用的な観点から研究し、その知識を交流のあった武将たちに伝える媒介者の役割を果たした 52 。
したがって、戦国時代における『万葉集』の受容は、決して広く浸透したものではなかった。「戦国時代の間、万葉集はまた眠りにつく」という評価 73 は、社会全体を見渡した場合、的を射ている。しかし、それはあくまで大衆レベルでの話であり、その水面下では、公家、一部の文化人武将、そして専門家である連歌師といった、限られた知的エリート層の間で、その価値は深く認識され、研究と享受が脈々と続けられていたのである。その受容は、広がりを欠く一方で、極めて高いレベルの深度を持っていた。
結論:戦国から江戸へ — 『万葉集』評価の変遷と現代への継承
本報告書の分析を通じて、戦国時代における『万葉集』の受容が、単なる古典趣味に留まらない、重層的かつ戦略的な意味合いを持っていたことが明らかになった。
戦国時代において『万葉集』は、和歌の正統的規範であった『古今和歌集』の対抗軸として、あるいはそれを補完する豊かなインスピレーションの源泉として、細川幽斎に代表される一部の文化人武将や連歌師によって再発見された。その「ますらおぶり」と評される素朴で雄大な歌風は、公家文化とは異なる価値観を求める武家の精神性と共鳴し、一方でその万葉仮名の難解さは、読み解く者の知的権威を証明する象徴となった。この受容は、武将が「旧来の権威(公家)」と「新たな実力(武家)」を自らの中に統合し、文化と武力の両面における覇者であることを示すための、高度な知的営為であったと言える。
この戦国期における限定的だが深い関心は、次代への重要な橋渡しとなった。幽斎のような文化人武将や、三条西家、下河辺長流といった学者たちの研究の蓄積は、江戸時代に隆盛する国学の知的土壌を準備した 60 。賀茂真淵による「ますらおぶり」論の確立や、本居宣長が『古事記』研究の階梯として『万葉集』を精読したこと 79 は、戦国期に萌芽した武家的な価値観に基づく古典解釈を、より学問的に体系化し、発展させたものと位置づけられる。
そして、戦国乱世が終わり、泰平の世が訪れると、慶長期(17世紀初頭)に『万葉集』の 古活字版 が刊行される 75 。これは、古典の受容史における画期的な出来事であった。これにより、それまで一部エリート層が写本で独占していた『万葉集』のテクストが、より広い知識人層に開かれる道が拓かれ、その後の大衆的な普及の礎となったのである。
奈良時代に生まれ、平安時代に忘れられ、鎌倉時代に再発見され、戦国武将の教養となり、江戸の国学によって国民的古典として位置づけられた『万葉集』。その重層的な受容の歴史は、時代ごとに人々がこの巨大な歌集に新たな価値を見出し、自らの文化を豊かにしてきた営みの証左である。本報告書で光を当てた「戦国時代」という特異な視座もまた、この長大な歴史の一環として、現代の我々に『万葉集』の尽きせぬ魅力を再認識させる、深い示唆を与えてくれるのである。
引用文献
- 万葉集の魅力・再発見 |國民會館 https://www.kokuminkaikan.jp/chair/lecture/acDOL1fY
- 万葉集(萬葉集) - 古典文学 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=8
- 歌の解説と万葉集 | 大阪府柏原市 https://www.city.kashiwara.lg.jp/docs/2019021900044/
- 万葉集とは https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/about/river-museum/manyo/info.html
- 万葉集を学ぶ - painter shiro hasegawa 画家 長谷川資朗 https://shiro-hasegawa.com/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%B6/
- 日本人なら知っておきたい文学作品!”令和”の典拠となった最古の歌集『万葉集』 - 中学受験ナビ https://chugaku-juken.com/manyoshu/
- 万葉集に収められている歌の表現 様式や種類にはさまざまな形があります。 知ってい ると https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1183520/13.pdf
- 現存する日本最古の歌集【万葉集】成り立ちと特徴を歌と写真を交えてわかりやすく解説 https://mikurunurie.com/manyo-syu-about/
- はじめての万葉集 その一 https://mukei-r.net/waka-1a/1-1-manyou-1.htm
- 【万葉集の基礎知識】内容・構成・成立・代表的な歌人などごく基本的な内容を解説 | 奈良まちジオグラフィック https://narakanko-enjoy.com/?p=33910
- [ID:32076] ぞうか : 資料情報 | 研究資料・収蔵品データベース | 國學院大學デジタル・ミュージアム http://jmapps.ne.jp/kokugakuin/det.html?data_id=32076
- 万葉集 全体の配置と構造 - 古典の改め:Classic Studies https://classicstudies.jimdofree.com/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86/%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AE%E9%85%8D%E7%BD%AE/
- 万葉集セット(全5冊) /佐竹 昭広, 山田 英雄, 工藤 力男, 大谷 雅夫, 山崎 福之 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b457064.html
- 万葉集と明日香について https://www.mlit.go.jp/common/001058306.pdf
- 大伴家持を触発した越中の自然 高岡で『万葉集』ゆかりの風景を巡る - 水と匠 https://mizutotakumi.jp/stories/326/
- 謎解き 万葉集 最後の歌の成立を考える|作業員 - note https://note.com/masachan5/n/nec03f88d02b7
- 『万葉集』巻十六について 「無心所著歌」を中心に https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2000201/files/sce27010.pdf
- 万葉集の編纂と大伴家持 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/2006412/files/nagujj_100_1.pdf
- 主要万葉歌人について http://www.cims.jp/star/kororin/kajin.html
- ﹃万葉集の編纂と形成﹄ 原 田 貞 義 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/5345/files/Kokubungakukenkyu_153-154_HaradaS.pdf
- 万葉集の編纂原理 https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/japanese/pdf/sbun-05-04.pdf
- 万葉集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86
- 大伴家持の生涯と万葉集 - 高岡市万葉歴史館 https://www.manreki.com/arekore/yaka-manyou/yaka-manyou.htm
- 万葉歌人・大伴家持と多賀城 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/manyo-digital-museum/culture/poet.html
- 万葉集なりきり大冒険 ~なぞとき!最古の歌の世界~|なら記紀・万葉 https://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/manabu/online/2020_narikiri/
- 万葉集: 歌の分類 https://art-tags.net/manyo/terms/poem_kind.html
- 万葉集の三大部立の設立について https://soai.repo.nii.ac.jp/record/1111/files/AN1011857X_19951200_1216.pdf
- 歌(大御葬歌)によって悲劇的に語られている。 記紀にはこの他にも、登場人物の死を語る場面にしばしば歌謡 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/41400/files/da002004.pdf
- 万葉仮名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E4%BB%AE%E5%90%8D
- 万葉仮名|国史大辞典・日本国語大辞典・世界大百科事典 ... https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=375
- 万葉仮名とは?平仮名と片仮名との関係性は? - 旅する応用言語学 https://www.nihongo-appliedlinguistics.net/wp/archives/9638
- 万葉仮名(マンヨウガナ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%87%E8%91%89%E4%BB%AE%E5%90%8D-636777
- 万葉集巻5に見る万葉文字の考察 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~mkawa/manyou5.html
- 上代特殊仮名遣い - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=843
- 上代特殊仮名遣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D%E9%81%A3
- 藤原清輔と藤原俊成の歌論の分析からみた中世における『万葉集』の受容について https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/4026/files/I4203.pdf
- 万葉受容の通史的研究 https://research.kosen-k.go.jp/index.php/file/2844
- 鎌倉と源氏物語〈第29回〉 『万葉集』の仙覚と北条実時 - タウンニュース https://www.townnews.co.jp/0602/2018/08/24/445434.html
- 【コラム】鎌倉殿の13人 比企の乱の年に生まれ、4500首の万葉集注釈を完成させた比企一族の一人、仙覚(せんがく) - 松堀不動産 https://www.matsubori.co.jp/news/archive/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%91%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%AE%BF%E3%81%AE13%E4%BA%BA-%E6%AF%94%E4%BC%81%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%AE%E5%B9%B4%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%80%814500/
- 仙覚(センガク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%99%E8%A6%9A-88040
- 全体を簡易な体にするために、原本であるハードカバーにある、「万葉集」の原文を省略して、現在私どもが読んでいる形態の読み下し文だけが収められていることです。しかしながら漢点字版の製作に当たっては、それでも歌の https://www.ukanokai-web.jp/Sanpo/sanpo_62.html
- 時間切れ!倫理 131 賀茂真淵|金岡新 - note https://note.com/kanaokasinn/n/nb605845f8f6e
- 国学者賀茂真淵翁並びに翁の師と門流及び遠江の国学者に関する資料を展示【静岡県浜松市】賀茂真淵記念館 https://mabuchi-kinenkan.jp/waka/043.html
- 万葉集巻14・3384 - 東京大学附属図書館 https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/html/tenjikai/josetsu/2009_07/page2.html
- 「ますらおぶり」と「たおやめぶり」とは。 | 和のすてき 和の心を感じるメディア https://wanosuteki.jp/archives/13814
- 1 『万葉集』に見られる大正・昭和初期の日本人論 https://www.jpf.go.jp/j/project/intel/exchange/organize/ceeja/report/11_12/pdf/11_12_04.pdf
- 連歌の基礎知識/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/39220/
- 和歌が生まれるとき https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/29337/files/056000760005.pdf
- 戦国武将の内面を「和歌」で垣間見る|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-092.html
- 有名戦国武将の和歌10選 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ldvIss3jPxI
- 細川幽斎の和歌を称賛したい審神者|遠野 - note https://note.com/noted_enya984/n/n47d6d86b74a3
- 連歌師とは何者?連歌会とはどんな場?戦国時代の不思議な職業の秘密とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/63285/
- 連歌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E6%AD%8C
- 夢想之連歌 - 太宰府市文化ふれあい館 学芸だより https://dazaifu-bunka.or.jp/info/letter/detail/71.html
- 連歌(レンガ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%80%A3%E6%AD%8C-152050
- 里村玄陳発句(七首) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/508817
- 連歌と万葉集との関係 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/jl/ronkyuoa/AN0025722X-016_001.pdf
- 血で血を洗う戦国時代。織田信長ら武将たちが、茶の湯にはまった3つの理由 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/73672/
- 古今伝授とは http://www.kokindenju.com/kokindenju.html
- 国学について https://www2.kokugakuin.ac.jp/kada/joho/joho_suzuki_001.html
- 細川幽斎「九州道の記」における地名の詠み方 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/2000364/files/CP4804.pdf
- 細川幽斎 ほそかわゆうさい 天文三~慶長一五(1534~1610) 号:玄旨 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yusai.html
- 古典への招待 【第82回:和学者と和歌惰弱論】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_82.html
- DATE MASAMUNE(伊達政宗)s Chinese Poetry(漢詩) https://mue.repo.nii.ac.jp/record/245/files/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%94%BF%E5%AE%97%E6%BC%A2%E8%A9%A9%E6%A0%A1%E9%87%88.pdf
- 政宗和歌集 https://www.city.sendai.jp/miyagino-kikakuchose/miyaginonooto/documents/miyaginonooto42.pdf
- 更旅229号・伊達政宗が詠んださらしなの歌 https://www.sarashinado.com/2014/06/03/masamune/
- 「むさしの」と言えば「野っ原」 伊達家 月の前立て - daitakuji 大澤寺 墓場放浪記 https://www.daitakuji.jp/2014/10/28/%E3%82%80%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%AE-%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%88%E3%81%B0-%E9%87%8E%E3%81%A3%E5%8E%9F-%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%AE%B6-%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%89%8D%E7%AB%8B%E3%81%A6/
- 辞世の句・歌 その26「極楽も地獄も先はありあけの月ぞこころに懸かる雲なし」(上杉謙信) https://wakadokoro.com/learn/jisei/%E8%BE%9E%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%AD%8C-%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%EF%BC%96%E3%80%8C%E6%A5%B5%E6%A5%BD%E3%82%82%E5%9C%B0%E7%8D%84%E3%82%82%E5%85%88%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%82%E3%81%91%E3%81%AE/
- 語り継がれる辞世の句・歌 一覧 - 令和和歌所 https://wakadokoro.com/category/learn/jisei/
- #1291 極楽も 地獄もさきは 有明の ・・・ 他一首と漢詩 : 万葉歳時記 一日一葉 - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/rh1-manyo/archives/48391116.html
- もののふの よろいのそでを かたしきて まくらにちかき はつかりのこゑ - おいどんブログ https://oidon5.hatenablog.com/entry/2018/03/21/170757
- 武田晴信捐是百首尔歌 - 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/fs/8/1/2/7/5/_/__2018_1__No126___________________12.pdf
- 古典への招待 【第6回:万葉集をよむ】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_06.html
- 『万葉集』の翻訳における テキストと訓義をめぐる問題点 https://www.manyo.jp/ancient/report/pdf/report15_15_texts.pdf
- 萬葉集 20巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007317439
- 林 大樹 (Hayashi Daiki) - マイポータル - researchmap https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/115171/4885cce88456ce1cb6ee277538d1913c?page_id=302874
- 連歌師宗祇の古典研究-『古今集』伝授と注 - Brandeis Library Open Access Journals https://journals.library.brandeis.edu/index.php/PAJLS/article/download/856/303/2828
- 下河辺長流の万葉研究 https://www.manyo.jp/ancient/report/pdf/report4_7_simokoube.pdf
- 解説項目索引【ま~も】 - 本居宣長記念館 https://www.norinagakinenkan.com/pages/201/
- 本居宣長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%B1%85%E5%AE%A3%E9%95%B7
- 古活字版『萬葉集』(活字無訓本) https://lib.ndsu.ac.jp/collection/pdf/collection_36.pdf
- ︎ 万葉集 古活字版(PDF) - 天理図書館 https://www.tcl.gr.jp/wp-content/uploads/meihin151.pdf