家業伝
木下清左衛門の『家業伝』は、戦国期自治精神を継ぎ、河内綿作を軸に高度な農業経営を詳述。知識を形式化し、幕末近世農業の到達点を示した。
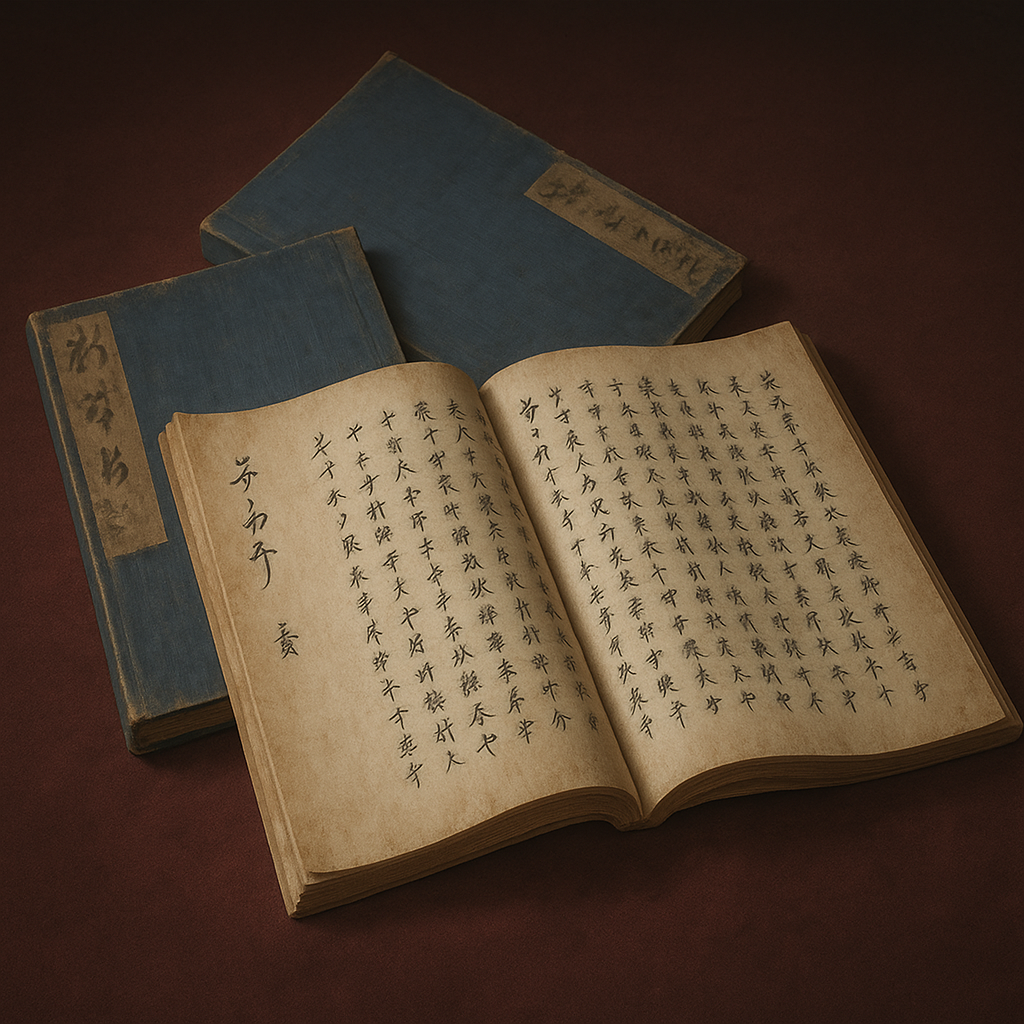
『家業伝』の深層分析:戦国期からの連続性と幕末期における農業経営の到達点
序論:『家業伝』研究の視座—時代的文脈の再設定と課題
本報告書は、木下清左衛門によって著された農書『家業伝』を、その歴史的文脈である江戸時代後期に正確に位置づけ、徹底的に分析することを目的とする。ご依頼の「戦国時代という視点」は、一見すると時代的な齟齬が存在する。なぜなら、『家業伝』の著者・木下清左衛門は文化14年(1817年)から文久3年(1863年)に生きた人物であり、本書の執筆期間も天保13年(1842年)から安政3年(1856年)に及ぶ、まさしく幕末期の史料であるからだ 1 。
しかし、この時代的相違は、歴史研究において断絶ではなく、むしろ連続性と発展の軌跡を探るための貴重な手掛かりとなる。本報告書では、この「戦国時代という視点」を、単なる時代区分としてではなく、『家業伝』に描かれる高度な農業社会の歴史的源流を探るための「分析軸」として再定義する。すなわち、戦国時代に形成された農業基盤や社会構造が、いかにして江戸時代の泰平の世を経て変容し、幕末期における先進的な農業経営の到達点ともいえる『家業伝』の世界へと繋がっていったのか。そのダイナミックな歴史的変遷を解明することで、ご依頼の趣旨に対して、より深く、より広範な視野からの回答を提示する。
本報告書は、まず『家業伝』が生まれた幕末期河内国の社会経済的背景を明らかにし、次にその源流を戦国時代にまで遡る。そして、『家業伝』の具体的な農業技術と経営哲学を詳細に分析し、最後にその歴史的意義と現代への示唆を考察するという構成をとる。これにより、一点の史料を多角的に読み解き、日本農業史における壮大な物語を浮かび上がらせることを目指す。
第一部:『家業伝』が生まれた世界—幕末期河内国の社会と経済
『家業伝』という一冊の農書を理解するためには、まずそれが書かれた時代と場所、そして著者自身の姿を正確に捉える必要がある。本書は、幕末という激動の時代を目前にした、日本の農業先進地帯であった河内国(現在の大阪府東部)から生まれた。その背景には、一人の篤農家の情熱と、地域史を塗り替えた巨大な土木事業の存在があった。
第一章:著者・木下清左衛門の実像—篤農家にして経営者
『家業伝』の著者、木下清左衛門(きのした せいざえもん)は、文化14年(1817年)に生まれ、文久3年(1863年)に没した、河内国若江郡八尾木村(現・大阪府八尾市)の実在の農民である 2 。彼の生家は村の庄屋を務める有力な家柄であり、彼自身も地域の指導者としての役割を担っていた 2 。
ここで、歴史上の人物を扱う上で極めて重要な注意点を指摘せねばならない。「木下」という姓や「清左衛門」という名から、豊臣秀吉の一族である武家の木下氏 3 や、藤沢周平の小説を原作とする時代劇の主人公・三屋清左衛門 4 を想起するかもしれない。しかし、これらの著名な武家や架空の人物と、『家業伝』の著者とは全くの別人である。本書の著者は、歴史の表舞台に立つ武将や剣客ではなく、土地に根差し、土と共に生きた一人の篤農家であり、卓越した経営者であった。この人物像の正確な比定こそが、『家業伝』を正しく理解するための第一歩となる。
清左衛門が本書の執筆を開始したのは天保13年(1842年)、病床にあってのことだった 2 。彼は、自らが実践を通じて築き上げた農業技術の粋を、後世に生きる子孫たちに遺すという強い意志に突き動かされ、実に14年もの歳月をかけてこの大著を完成させた 2 。その内容は、綿作を中心としながらも、稲作、麦作、野菜類に至るまで、自身の経営する田畑一筆ごとの作業内容や注意点を、月別に克明に記したものであった 8 。これは単なる農作業の記録ではない。自らの知識と経験を、家の永続を支える無形の財産、すなわち「家業」として後世に継承しようとする、彼の経営者としての先見性と、子孫への深い愛情の表れに他ならない。
第二章:大変動の時代—大和川付替えが変えた河内平野
木下清左衛門が活躍し、『家業伝』に描かれるような高度な綿作農業が展開された背景には、彼の生きた時代から約150年前に遡る、河内平野の歴史を根底から変えた一大事業が存在する。それが、宝永元年(1704年)に断行された大和川の付替え工事である。
かつて大和川は、奈良盆地から北上して現在の大阪市中心部で淀川と合流し、大阪湾に注いでいた。このため、河内平野の中央部はたびたび氾濫に見舞われる洪水の常襲地帯であった。しかし、この付替え工事によって、川筋は柏原から西へ直流し、堺の北で直接大阪湾に注ぐ現在の流路へと変更された 9 。
この地理的な大変革は、河内地方の農業経済に劇的なインパクトをもたらした。第一に、長年の課題であった治水環境が劇的に改善された。第二に、そしてこれがより重要な点であるが、かつての川床や沼地であった広大な土地が干上がり、新田として開発することが可能になったのである 9 。この新たに生まれた土地は、砂質を多く含み、水はけが良いという特性を持っていた。この土質は、稲作には必ずしも最適ではなかったが、深く根を張り、過湿を嫌う綿花の栽培にはまさに理想的な環境であった 10 。
この結果、18世紀以降、河内地方では綿作が爆発的に普及し、「河内木綿」の名は全国に知られるブランドへと成長していく 10 。木下清左衛門が庄屋を務めた八尾木村も、まさにこの恩恵を直接受けた地域であった。『家業伝』に描かれる先進的な綿作経営は、一個人の才能だけで成立したのではなく、大和川付替えという巨大なインフラ整備によって創出された、新たな経済的機会という土台の上に花開いたものなのである。このマクロな歴史的視点を持つことで、一農書に記されたミクロな農業技術の背後にある、壮大な因果関係を理解することができる。
第二部:戦国から近世へ—農業社会の構造転換
『家業伝』が示す幕末期の高度な農業社会は、突如として出現したわけではない。その根は深く、戦国時代の動乱期にまで遡ることができる。戦乱の時代に生まれた農民たちの自治の精神と、それに続く泰平の世がもたらした社会経済の革命。この二つの大きな歴史のうねりが、近世日本の農業の姿を形作っていった。
第一章:戦国期における農業の原風景
戦国時代、特に畿内やその周辺地域では、絶え間ない戦乱から自らの生命と財産を守るため、農民たちは強固な団結を必要とした。こうして生まれたのが「惣村(そうそん)」と呼ばれる、農民による自治的な村落共同体である 13 。
惣村において、農民たちは寄合を開いて村の意思決定を行い、「惣掟(そうおきて)」と呼ばれる独自の規約を定めて村の秩序を維持した。水利の管理や入会地の共同利用、年貢の村単位での一括納入(地下請)など、その自治の範囲は多岐にわたった 13 。この過程で、契約書や規約の作成といった実務的な必要性から、惣村を主導する乙名(おとな)や沙汰人(さたにん)といった上層農民の間では、識字能力が着実に発達していった 13 。彼らは、単に農耕に従事するだけでなく、村を運営する政治的な主体でもあったのである。
この戦国期の惣村が育んだ自治の能力と経験は、近世社会を理解する上で極めて重要である。織田信長や豊臣秀吉による天下統一の過程で、惣村の武装や過度な自治は「徹底的に弾圧」され、一向一揆の殲滅に象徴されるように、その力は大きく削がれた 14 。一見すると、これは「自治」から「支配」への完全な断絶に見える。
しかし、より深く考察すれば、そこには明確な連続性を見出すことができる。新たな支配者である大名や幕府にとっても、村落の秩序を維持し、安定的に年貢を徴収するためには、村を運営する社会技術は不可欠であった。その結果、かつて惣村の指導者であった上層農民層は、多くが幕藩体制下における村役人、すなわち庄屋や名主といった形で新たな支配構造の末端に組み込まれていった。彼らは領主の支配を受け入れつつも、村落内部における指導者としての役割を継続したのである。『家業伝』の著者・木下清左衛門が庄屋として発揮したリーダーシップや経営能力の源流は、遠くこの戦国期の惣村が育んだ「自治の遺産」にまで遡ることができる。それは、支配の形態は変われども、村落共同体を支える社会関係資本が、時代を超えて受け継がれていったことを示している。
第二章:泰平の世における農業革命
戦国時代の終焉と徳川幕府による泰平の世の到来は、日本の農業社会に構造的な大転換をもたらした。豊臣秀吉が断行した刀狩と太閤検地、そしてそれを引き継いだ江戸幕府の政策は、二つの大きな変化を生んだ。
一つは、「兵農分離」である。武士は城下町に集住し、農業生産から完全に切り離された。これにより、農民は土地に縛り付けられ、耕作に専念する存在として明確に位置づけられた。もう一つは、検地によって全国の土地が米の生産量を基準とする「石高(こくだか)」で評価され、それを基に年貢が徴収される「石高制」が確立されたことである。これにより、領主による農民支配はより安定的かつシステマティックなものとなった。
一方で、二百数十年におよぶ平和な時代は、経済に劇的な変化をもたらした。五街道をはじめとする交通網が整備され、全国的な市場が形成される。大坂や江戸といった大都市の発展は、大量の食料や物資を必要とし、貨幣経済が農村の隅々にまで浸透していった。
こうした社会経済の変化の中で、農民たちの意識も大きく変わっていった。彼らはもはや、自らが食べるための米を作るだけの存在ではない。より高く売れる作物を栽培し、現金収入を得て、より豊かな生活を目指すという、営利的な視点を持つようになった。米はもちろんのこと、木綿の原料となる綿花、灯油の原料となる菜種、染料となる藍などは、収益性の高い「商品作物」として、各地で栽培が奨励された 1 。
この自給自足的な農業から商品作物を生産する営利的農業への転換こそが、「近世農業革命」と呼ぶべき本質的な変化であった。『家業伝』に描かれる、綿作を中心とした高度な農業経営は、まさにこの大きな時代の流れの最先端に位置するものであり、戦国期には考えられなかった、市場経済と深く結びついた新たな農業の姿を象徴しているのである。
第三部:『家業伝』にみる近世農法の神髄
『家業伝』は、単なる一農民の覚え書きではない。それは、幕末期日本の先進農業地帯における、最高水準の技術、経営、そして労働のあり方を凝縮した、生きたマニュアルである。そのページをめくることで、我々は近世農民が到達した驚くべき合理性と緻密さの世界に触れることができる。
第一章:綿作を中核とする複合的農業経営
『家業伝』の経営の中核をなすのは、疑いなく商品作物としての綿作である。しかし、その最大の特徴は、綿作に特化するのではなく、稲、麦、さらには大根などの根菜、豆類、芋類といった多様な作物を巧みに組み合わせた、複合的な経営システムを構築している点にある 8 。
木下清左衛門の記述は、驚くほどに微視的かつ体系的である。彼は、自らが耕作する「田畑一筆ごと」に、土壌の性質や日当たり、水はけといった条件を完全に把握し、それぞれの土地に最も適した作物を割り当てていた 8 。そして、月ごとの作業内容、種まきや施肥の時期と量、栽培上の注意点などを、子孫が誰でも実践できるよう、具体的かつ丁寧に記録している。
このアプローチは、単なる熟練農家の経験と勘の記録を超えている。それは、近代的な意味での「経営者」の思考様式を色濃く反映していると言える。複数の作物を組み合わせることは、特定の作物の不作や市場価格の暴落といったリスクを分散させるための、計算されたポートフォリオ戦略である。また、田畑一筆ごとの詳細な記録は、土地という経営資産の生産性を最大化するための、徹底したデータ収集と分析に他ならない。これは、現代の精密農業(Precision Agriculture)の思想にも通じる、極めて合理的なアプローチである。
木下清左衛門は、土を耕す篤農家であると同時に、土地、労働力、資本といった経営資源をいかに最適に配分し、収益を最大化するかを常に考える、優れたマネージャーであった。農書を単なる技術書としてではなく、「経営マニュアル」として読み解くことで、我々は近世農民が保持していた高度な経営能力と知的水準を再評価することができるのである。
第二章:先進技術の導入と実践
木下清左衛門の卓越した経営を支えていたのは、その緻密な計画性だけではない。彼は、当時の最先端の農業技術を積極的に導入し、自らの圃場で実践していた。その代表例が、河内地方独特の農法である「半田(はんでん)」または「掻揚田(かきあげでん)」と、購入肥料である「金肥(きんぴ)」の戦略的な活用である。
「半田」とは、一つの田んぼの中で、土を高く掻き上げて畝(うね)を作り、その高い部分で綿を栽培し、低くなった溝の部分で稲を栽培するという、独創的な農法である 11 。これにより、排水性の良い乾燥した環境を好む綿と、水を必要とする稲という、全く性質の異なる二つの作物を、同一の圃場で同時に栽培することが可能になった。これは、限られた土地から最大限の収益を上げるための、土地利用効率を極限まで高めた画期的な技術であった。
さらに、近世農業の生産性を飛躍的に向上させたのが、「金肥」と呼ばれる購入肥料の登場である。『家業伝』の時代、農民はもはや村内で得られる草や人糞尿といった自給肥料だけに頼るのではなかった。彼らは現金(金)を投じて、より肥効の高い肥料を購入したのである。その代表が、鰯(いわし)を乾燥させた「干鰯(ほしか)」や、菜種や綿実から油を搾った後の「油粕(あぶらかす)」であった 16 。これらは窒素やリン酸を豊富に含み、特に収益性の高い商品作物である綿の栽培に重点的に投下された 16 。
この金肥の導入は、単なる施肥技術の進歩以上の、革命的な意味を持っていた。それは、村という閉鎖的な物質循環の輪(生態系)を打ち破り、外部から栄養分を「輸入」する開放的な生産システムへの転換を意味したからである。干鰯は海の資源を、油粕は他の地域の畑の資源を、貨幣を介して自らの土地に投入する行為である。これにより、土地本来の生産力の限界を超えた、持続的な高収量が可能となった。『家業伝』に描かれる高い生産性は、この開放的な経済ネットワークの上に成り立っており、木下清左衛門の経営が、遠く房総の漁村や各地の菜種産地と市場を通じて結びついていたことを物語っている。
以下の表は、『家業伝』や同時代の史料から推測される、河内地方における主要作物の年間作業暦を模式的に示したものである。これを見れば、一年を通じていかに労働が連続し、各作業が緻密に計画されていたかが一目瞭然となる。
表1:『家業伝』に見る主要作物(綿・稲・麦)の年間作業暦(模式図)
|
月 |
綿 |
稲 |
麦 |
その他の特記事項 |
|
1月 |
前年収穫綿の繰り・糸紡ぎ |
堆肥・寒肥の準備 |
麦踏み |
根菜類の収穫・貯蔵 |
|
2月 |
〃 |
田の土起こし(荒起こし) |
麦踏み、追肥 |
菜種の開花準備 |
|
3月 |
〃 |
苗代の準備、種籾の選別 |
追肥 |
春野菜の作付け |
|
4月 |
種蒔き準備、畑の準備 |
苗代への種蒔き、水管理 |
出穂期 |
夏野菜の準備 |
|
5月 |
麦の畝間への蒔き付け 20 |
代掻き、田植え準備 |
収穫 、乾燥、脱穀 |
菜種の収穫 |
|
6月 |
間引き、補植 |
田植え 、水管理 |
- |
害虫駆除の準備 |
|
7月 |
中耕、土寄せ、追肥 |
除草(草取り)、水管理 |
- |
夏野菜の収穫 |
|
8月 |
真留め(摘心) 20 、追肥 |
中干し、出穂 |
- |
盆行事、施餓鬼 |
|
9月 |
収穫開始 (下から順次) |
落水、 稲刈り |
畑の準備、耕起 |
秋野菜の作付け |
|
10月 |
収穫最盛期 |
稲の乾燥(はさ掛け)、脱穀 |
種蒔き |
- |
|
11月 |
収穫終盤、綿打ち |
籾摺り、藁の処理 |
麦踏み |
冬野菜の収穫 |
|
12月 |
収穫後処理、道具の手入れ |
年貢米の納入 |
麦踏み |
年末準備 |
この表から、麦の収穫と田植え、稲刈りと麦の種蒔きが連続して行われ、その合間に綿の集約的な管理作業が組み込まれていることがわかる。労働力の配分がいかに重要であったか、そして一年を通じてほとんど休みなく農作業が続いていた当時の農民の勤勉さがうかがえる。
第三章:労働力の編成と共同体
『家業伝』に描かれるような大規模かつ集約的な農業経営は、当然ながら多くの労働力を必要とした。その労働力は、主に三つの要素から構成されていたと考えられる。
第一の基盤は、家長を中心とする「家族労働」である。家業としての農業は、家族という単位で営まれ、家の財産である農地を継承していくことが基本であった 21 。特に経営主やその後継者となる男子の労働力は、経営の根幹をなしていた。
第二に、家族労働だけでは補いきれない部分を、奉公人などの「雇用労働力」が担った。木下清左衛門ほどの経営規模であれば、年間を通じて働く下人や、農繁期に短期的に雇われる日雇い労働者を活用していたことは想像に難くない。彼らは家族の一員に準ずる形で扱われつつも、経営を支える重要な労働力であった。
第三に、そして近世農村の社会関係を特徴づけるのが、「結(ゆい)」や「もやい」と呼ばれる共同労働の慣行である 22 。田植えや稲刈りのように、短期間に集中的な労働力を必要とする作業は、一個人の家族労働力だけでは到底まかなえない。そこで、村の人々がお互いの田畑の作業を手伝い合い、労働力を交換し合うという相互扶助のシステムが機能していた 22 。今日はAの家の田植えを村中が手伝い、明日はBの家の田植えを手伝う。このような協力関係があったからこそ、村全体の農作業を滞りなく終えることができたのである。
この「結」の精神は、農作業だけでなく、家屋の建築や屋根の葺き替えなど、村の生活全般に及んでいた 22 。木下清左衛門のような有力な経営者もまた、この共同体のネットワークの中に深く組み込まれており、その指導力を発揮する一方で、村人たちとの協力関係なしには自らの経営を維持することはできなかった。彼の合理的な経営手腕と、村落共同体の相互扶助の精神は、決して矛盾するものではなく、むしろ車の両輪として機能していたのである。
第四部:「家業」の思想—経営哲学と生活規範
『家業伝』が後世に与える感銘は、その高度な農業技術の記述に留まらない。行間からは、著者が子孫に伝えたかった「家業」をめぐる経営哲学、労働倫理、そして自然と共生する精神が滲み出ている。それは、単なる技術書を超えた、一つの教育思想の書でもある。
第一章:『家業伝』に流れる教育思想
『家業伝』は、その執筆動機から明らかなように、子孫への「家訓書」としての性格を色濃く持っている 7 。これは、同時代の他の農書、例えば広島で書かれた『家業考』が耕作技術と共に葬式の出し方まで記したり、能登の豪農による『村松家訓』が主人の心のもち方や奉公人の使い方まで説いたりしたのと同様に、日本の「家業」思想の系譜に連なるものである 17 。技術の伝承と、それを担うべき人間の倫理教育が、分かちがたく結びついていたのである。
ここで特に注目すべきは、木下清左衛門が「執筆」という手段を選んだことの先進性である。それまでの農業技術の伝承は、多くの場合、親から子へ、日々の労働を通じて直接伝えられる「暗黙知」が中心であった。これは経験に裏打ちされた貴重な知識である一方、伝承者の死や記憶違いによって失われたり、劣化したりする危険性を常にはらんでいた。
病床にあった清左衛門は、自らが直接指導できないという物理的な制約の中で、自身の持つ膨大な知識と経験を、客観的な文字情報、すなわち「形式知」へと転換する作業に着手した 7 。これは、彼の知恵を、彼個人の身体的・時間的制約から解放し、誰でも、そしていつでも参照可能な、永続性を持つ「マニュアル」へと昇華させる行為であった。
この行為の背後には、彼が土地や家屋といった有形の財産以上に、この農業経営に関する「知」こそが、木下家という「家業」を未来永劫にわたって維持・発展させる上で最も重要な資産であると深く認識していたことがうかがえる。これは、自らの知識を体系化し、それを次世代に相続可能な「知的財産」として確立しようとする、極めて意識的かつ近代的な試みであったと言えよう。彼の筆が綴ったのは農法であると同時に、知の継承という普遍的な課題に対する、一人の農民経営者が出した卓越した答えだったのである。
第二章:自然との共生と信仰
『家業伝』全体を貫いているのは、自然に対する鋭敏な観察眼と、その理(ことわり)を深く理解しようとする科学的な精神である。土壌の乾湿、日照の具合、天候の微妙な変化、作物の生育段階に応じた顔つき。それらを冷静かつ精密に観察し、記録し、最適な対応策を導き出す。その姿勢は、自然を力ずくで支配しようとするものではなく、自然の法則に寄り添い、その力を最大限に引き出すことで生産性を高めようとする、共生の思想に基づいている。
一方で、木下清左衛門のような合理主義者が、信仰や習俗と無縁の乾いた世界に生きていたわけではない。当時の農民の生活は、科学的知見と精神文化が渾然一体となった、豊かな世界であった。
日々の労働の区切りとなるのは、五節句などの年中行事や、地域の神社の祭礼であった 22 。これらは「遊び日」と呼ばれ、仕事を休んで神仏や祖霊と共に楽しむ、ハレの機会であった 22 。また、作物の豊穣を祈り、収穫に感謝する様々な農耕儀礼は、厳しい労働に精神的な意味とリズムを与えた。お盆には多くの作物を供えて祖霊を迎え、施餓鬼を行うなど、その信仰は日々の生産活動とも密接に結びついていた 25 。
『家業伝』には、こうした信仰に関する直接的な記述は少ないかもしれない。しかし、本書に底流する勤勉や倹約といった労働倫理、自然への畏敬の念、そして家と子孫の繁栄を願う心性の背景には、こうした村落共同体の精神的基盤が存在したことは間違いない。木下清左衛門の精神世界においては、合理的な経営判断と、目に見えない存在への信仰が、何ら矛盾することなく共存していた。それは、近代化の過程で我々が失ってしまったかもしれない、人間と自然、そして共同体との、より統合された関係性の姿を今に伝えている。
結論:『家業伝』が現代に問いかけるもの
本報告書は、農書『家業伝』を、その正確な歴史的文脈である幕末期に位置づけ、その内容を多角的に分析してきた。そして、その源流を「戦国時代という視点」から遡ることにより、一つの史料が内包する重層的な歴史性を明らかにしてきた。
『家業伝』は、戦国時代の動乱期に生まれた惣村の自治の精神を源流とする、強固な村落共同体の社会技術。そして、江戸時代の泰平と市場経済の発展の中で育まれた商品作物栽培という新たな農業形態。さらに、金肥に代表される技術革新。これら日本の近世社会を特徴づける複数の歴史的要素が、河内国という先進地域において見事に結実した、幕末期農業経営の一つの到達点であったと結論づけることができる。
木下清左衛門という一人の人物像を通して、我々は従来の近世農民に対するイメージを大きく修正する必要がある。彼らは、決して封建的な支配の下でただ搾取されるだけの、無知で受け身な存在ではなかった。むしろ、市場の動向を読み、最新の技術を導入し、緻密なデータに基づいて経営判断を下す、合理的精神と企業家的な能力を備えた主体的な存在であった。『家業伝』の執筆という行為自体が、自らの知識を「知的財産」として未来へ継承しようとする、長期的かつ戦略的な視点を持っていたことの何よりの証左である。
そして、『家業伝』が現代に問いかけるものは決して少なくない。地域環境の特性を最大限に活かし、多様な作物を組み合わせることでリスクを分散させる複合的経営のあり方は、現代の持続可能な農業や生物多様性の問題を考える上で示唆に富む。また、徹底した記録に基づくデータ駆動型の経営判断や、後継者のために知識を形式知化し、事業承継を円滑に進めようとするその思想は、現代の企業経営が直面する課題とも深く共鳴する。
戦国時代から幕末期へ。動乱から泰平へ。自給から市場へ。『家業伝』は、この壮大な歴史的変遷のダイナミズムを一身に体現した、類い稀な史料である。その一頁一頁に刻まれた知恵と情熱は、時代を超えて、我々に農業の、そして経営の本質とは何かを問いかけ続けている。
引用文献
- 農書(ノウショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%9B%B8-111930
- 木下清左衛門(きのした せいざえもん)とは? 意味や使い方 ... https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E6%B8%85%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-1070004
- 木下氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E6%B0%8F
- 北大路欣也主演シリーズ最新第8作『三屋清左衛門残日録 春を待つこころ』 https://www.jidaigeki.com/mitsuya8/
- 三屋清左衛門残日録 あの日の声 - 時代劇専門チャンネル https://www.jidaigeki.com/mitsuya6/
- 三屋清左衛門残日録 あの日の声 - 北大路欣也主演・シリーズ最新第6作【jcom 三屋6】 - J:COMテレビ番組ガイド - MY J:COM https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya6/
- 木下清左衛門 〜 の在庫検索結果 / 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search&search_only_has_stock=1&search_word=%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E6%B8%85%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80
- 『日本農書全集8 家業伝 在庫僅少』木下清左衛門著他 - 田舎の本屋さん https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540780263/
- 大和川つけかえの史跡探訪ガイドブック 柏原・八尾コース http://ycn-2009.ciao.jp/da_he_chuan_shi_minnettowaku/shi_ji_tan_fang_bai_yuanba_wei_biao_zhi_files/%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E6%8E%A2%E8%A8%AA%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%95%E3%82%99%E3%83%83%E3%82%AF_%E8%A6%8B%E9%96%8B2-3.pdf
- 松原歴史ウォーク https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/57/57590/97249_1_%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF.pdf
- 河内木綿と農業の歴史 - JAグリーン大阪 https://www.ja-greenosaka.or.jp/uploads/20c667112de30b970a5992e299d9404b64715ee1.pdf
- 基本構想 - 八尾市 https://www.city.yao.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/063/kousou202402.pdf
- 社会経済史:中世 - かーしゅうの一橋大日本史論述 https://kashu-nihonshi8.com/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8F%B2%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E4%B8%96/
- 【第二章】北国の憂愁 | 常願寺川 農人の記憶―山をも流した河 Jyouganji-River Memory of the Farmers - 水土の礎 https://suido-ishizue.jp/nihon/14/02.html
- 《家業伝》(かぎょうでん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E6%A5%AD%E4%BC%9D-1287941
- 干鰯(ほしか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B2%E9%B0%AF-132968
- 『日本農書全集』 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/digital-zensyu/images/1028395309.pdf
- 【高校日本史B】「農具・肥料の改良」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12757/lessons-12856/
- 干鰯 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%B9%B2%E9%B0%AF
- 【綿作の変遷】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000278
- 農業雇用労働力問題の政策課題化 https://www.grips.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2014/04/fulltextdoc09006.pdf
- 江戸時代の百姓の生活【まとめ】衣食住から仕事の流儀までわかりやすく解説 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rWnK8c21W18&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD
- 分野別農書一覧 - ルーラル電子図書館 https://lib.ruralnet.or.jp/ns/03bunya.html
- 第一章 農民生活の概観 - 滝沢市 https://www.city.takizawa.iwate.jp/about-takizawa/gaiyo/bunkazai-history/sonshi/sonshi-nominseikatsu/p20241125125032
- 第二章 農民生活変遷の各説 - 滝沢市 https://www.city.takizawa.iwate.jp/about-takizawa/gaiyo/bunkazai-history/sonshi/sonshi-nominseikatsu/p20241125135036