平沙落雁図
「平沙落雁図」は、中国「瀟湘八景」の一つ。牧谿・玉澗ら禅僧画家が描き、足利将軍家「東山御物」として日本へ。戦国時代、六角氏や朝倉氏が所蔵し、信長ら天下人が権威の象徴として争奪した。
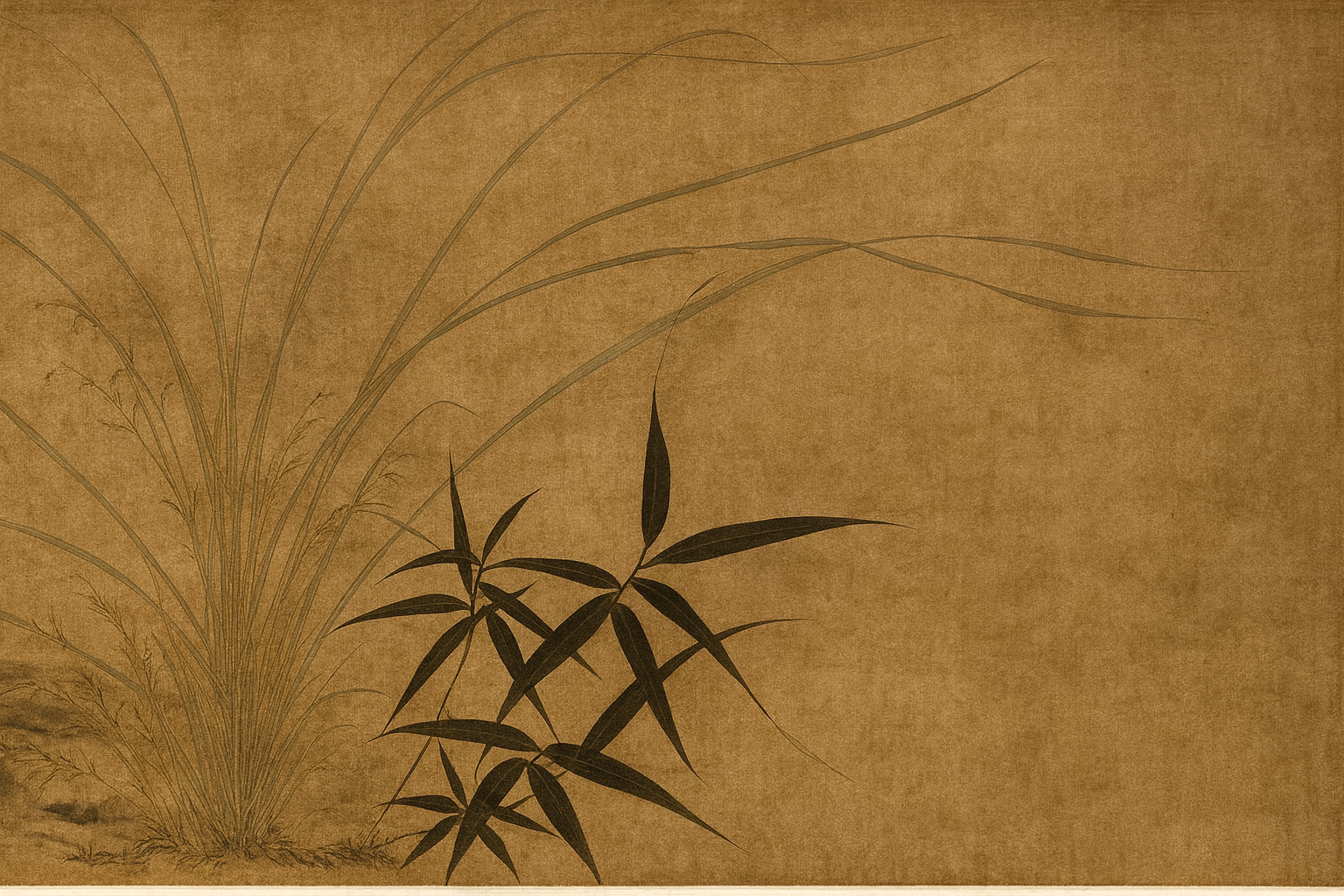
『平沙落雁図』の文化史的研究:戦国武将の審美眼と権力の象徴
序章:一幅の水墨画が映し出す世界
「平沙落雁図」。その名が喚起するのは、広々とした砂洲に雁の群れが静かに舞い降りる、一枚の水墨画の情景である。しかし、この絵画は単に美しい自然の一場面を切り取ったものではない。それは、中国大陸の広大な自然観と深い詩情に源流を発し、日本へと渡って禅宗の精神性と深く結びつき、やがては戦国武将たちの野望と洗練された美意識を映し出す、重層的な文化的記号へと昇華した存在である。本報告書は、この一幅の絵が辿った壮大な文化史的旅路を、特に「日本の戦国時代」という激動の時代をプリズムとして多角的に解明することを目的とする。
なぜ戦国の武将たちは、この画題にこれほどまでに魅了されたのか。なぜ一幅の絵が、時に領地一国にも匹敵するほどの価値を持つと見なされたのか。そして、その所有と継承は、彼らにとっていかなる意味を持っていたのか。これらの問いを丹念に解き明かすことを通じて、我々は武力と策略だけでは語り尽くせない、戦国時代の精神文化の深奥へと迫ることができるだろう。この探求は、「平沙落雁図」という窓を通して、乱世を生きた人々の心の有り様を垣間見る試みに他ならない。
第一部:『瀟湘八景』の誕生と東伝 ― 理想郷の創出と日本への移植
「平沙落雁図」の価値と意味を理解するためには、まずその源流である中国の画題「瀟湘八景」の成立と、それが日本へともたらされた経緯を深く知る必要がある。ここに、後の戦国時代における絶大な価値の源泉が存在する。
第一章:画題の源流 ― 中国・瀟湘の詩情
瀟湘八景の成立
「瀟湘八景」とは、中国湖南省に広がる洞庭湖の南、そこに注ぎ込む瀟水(しょうすい)と湘水(しょうすい)が合流する一帯の、風光明媚な景観を主題とする絵画である 1 。この画題の創始者と伝えられるのは、北宋時代(11世紀)の文人画家、宋迪(そうてき)である 4 。重要なのは、これが単なる実景の写生ではなく、文人たちが理想とする精神的な風景、すなわち心の中の理想郷を描き出すという、極めて知的で詩的な営みから始まった点にある。瀟湘の地は、古来より多くの詩文に詠まれ、屈原をはじめとする文人たちの憂愁や隠逸の思いが重ねられてきた場所であり、その詩情を絵画として視覚化したのが「瀟湘八景図」であった。
八景の構成と象徴性
「瀟湘八景」は、以下の八つの景観から構成される 2 。
- 平沙落雁(へいさらくがん) : 広い砂洲に雁が舞い降りる様。
- 漁村夕照(ぎょそんせきしょう) : 夕日に照らされる漁村の光景。
- 山市晴嵐(さんしせいらん) : 雨上がりの山里にかかる霞。
- 江天暮雪(こうてんぼせつ) : 日暮れの川と空に雪が降る景色。
- 洞庭秋月(どうていしゅうげつ) : 洞庭湖に映る秋の月。
- 瀟湘夜雨(しょうしょうやう) : 瀟湘地方に夜通し降る雨。
- 煙寺晩鐘(えんじばんしょう) : 夕靄に霞む寺から聞こえる鐘の音。
- 遠浦帰帆(えんぽきはん) : 遠くの入り江に帆船が帰っていく様。
これらの八景は、単に八つの名所を並べたものではない。その構成には、晴れと雨、昼と夜、そして秋の月や冬の雪といった季節感が巧みに織り込まれている 6 。鑑賞者は、この対照的な要素の組み合わせによって生まれる「組み合わせの妙」を通じて、時間と空間の移ろいの中に広がる自然の摂理や万物の調和といった、より大きな世界観を一枚の絵の中に感じ取ることができた 6 。それは、絵の中に凝縮された小宇宙を旅するような、知的で豊かな鑑賞体験であった。
南宋の画僧:牧谿と玉澗
この画題を不朽のものとし、特に日本の美術史に決定的な影響を与えたのが、南宋時代(13世紀)に活躍した二人の禅僧画家、牧谿(もっけい)と玉澗(ぎょっかん)である 5 。
牧谿は、墨の濃淡や滲みを自在に操り、湿潤な大気、揺らめく光、そして霧に包まれた空間といった、目には見えない自然の息吹を感覚的に描き出す技法に長けていた 11 。彼の作品は、中国本土においてよりも、むしろ海を渡った日本で絶大な評価を受け、後の日本の水墨画壇における絶対的な規範となった 11 。
一方、玉澗は、極度に簡略化された粗放な筆遣いと、墨を紙に注ぎかけるように用いる「潑墨(はつぼく)」という技法によって、対象の形態よりもその内面に宿る気迫や精神性を劇的に表現した 14 。
彼らの作品が単なる風景画と一線を画すのは、その背景に禅の思想が深く横たわっているからである 16 。描かれた風景は、見る者を悟りの境地へと誘い、あるいは世の無常を観想させるための、いわば禅的な精神世界への入り口として機能した。彼らが禅僧であったという事実は、禅宗文化が花開いた中世日本において、彼らの作品が特別視される極めて重要な要因となった。牧谿や玉澗の絵を理解し、所有することは、単なる美術愛好の域を超え、禅の深い精神性を理解しているという、最高の文化的ステータスを示す行為だったのである。
第二章:日本への伝来と室町文化における受容 ― 唐物から名物へ
禅宗文化と水墨画
鎌倉時代後期から室町時代にかけて、中国との交流を担った禅僧たちによって、水墨画は本格的に日本へともたらされた。禅宗において、絵画は教えを視覚的に伝える方便であり、また「画禅一如」の言葉に示されるように、作画行為そのものが修行の一環と見なされることもあった 17 。こうして、水墨画は禅宗文化と不可分なものとして日本に根付き、独自の発展を遂げていく。
足利将軍家と東山御物
この水墨画の価値を絶対的なものに高めたのが、室町幕府の将軍たち、特に三代将軍・足利義満と八代将軍・義政であった。彼らは、日明貿易などを通じて中国から渡来した最高級の美術品(唐物)を熱心に蒐集し、将軍家代々のコレクションである「東山御物(ひがしやまごもつ)」を形成した 19 。
牧谿や玉澗が描いた「瀟湘八景図」は、この東山御物の中核をなす至宝中の至宝として位置づけられ、最高の権威が付与された 13 。特に、牧谿の作品に押された義満の鑑蔵印「道有」は、その作品が将軍家のコレクションであったことを示す何よりの証拠であり、後世の権力者たちが垂涎の的とする価値の源泉となった 11 。
鑑賞形式の日本的変容
ここで、日本美術史上、極めて重大な意味を持つ一つの出来事が起こる。それは、本来長大な「画巻」であった「瀟湘八景図」を、足利将軍家が景観ごとに「切断」し、独立した「掛物(掛軸)」に仕立て直したことである 11 。この行為は、書院造という日本の建築空間や、茶の湯の会で床の間を飾るという日本独自の文化様式に適応させるためのものであった。
しかし、この「切断」という行為は、単なる物理的な分割にとどまらない、根源的な三つの変革を引き起こした。
第一に、 鑑賞体験の変革 である。連続する時間の流れの中で物語を追うように鑑賞する画巻から、一つの凝縮された情景と静かに対峙し、その余白に禅的な精神世界を観想する掛物へと、鑑賞のあり方が根本的に変わった。
第二に、 価値の変革 である。一体であった作品が、それぞれ独立した価値を持つ八つの「名物」へと姿を変えた。これにより、作品の価値は八倍に増殖したとも言える。
そして第三に、 所有形態の変革 である。一つの作品は一人の所有者にしか属し得ないが、八つの断簡は、八人の異なる所有者への分散を可能にした。
この「断簡」化こそが、足利将軍家の権威の象徴であった「瀟湘八景図」を、後の戦国武将たちによる争奪の対象となる流動的な「文化的財産」へと変貌させる、決定的な画期であった。将軍家による文化的適応策が、皮肉にも、自らの権威の象徴が拡散し、新たな権力者たちの手に渡る道を開いたのである。
第二部:戦国乱世における『平沙落雁図』の価値と流転 ― 権力者の掌を渡る雁
応仁の乱を経て室町幕府の権威が失墜すると、かつて将軍家が独占していた「東山御物」は、次第に各地の守護大名や新興勢力である戦国武将たちの手に渡っていく。この部では、本報告書の核心として、「平沙落雁図」が戦国の世においていかにして特別な価値を持ち、権力者たちの掌を渡り歩いていったのかを、具体的な史料と歴史的背景から徹底的に分析する。
第三章:「名物」としての美術品 ― 戦国の文化的資本
戦国時代において、優れた唐物、とりわけ茶入や天目茶碗、そして水墨画の掛物は「名物(めいぶつ)」と呼ばれ、金銀や領地をもしのぐほどの絶大な価値を持つと見なされた 24 。これらは単なる贅沢品や美術品ではない。所有者の権威、教養、そして経済力を社会に示す、極めて重要な「文化的・政治的資本」であった。
特に、武将たちが主催する茶の湯の会は、単なる喫茶の場ではなく、同盟関係の確認や情報交換、そして自らの権勢と洗練された審美眼を誇示するための、重要な政治的パフォーマンスの舞台であった 20 。その茶会の格式を決定づける最も重要な道具が、茶室の床の間を飾る掛物であった。中でも、足利将軍家旧蔵の「東山御物」に由来する掛物は、最高のステータスシンボルであり、それを所有し、茶会で披露することは、自らが将軍家の文化の正統な継承者であることを天下に示す行為に他ならなかった 19 。
第四章:近江守護・六角氏と牧谿筆『平沙落雁図』
『松屋名物集』の記録
利用者からの指摘にもある通り、室町時代から江戸時代初期にかけての茶会における名物道具を記録した一級史料『松屋名物集』には、近江守護・六角氏が牧谿筆の「平沙落雁図」を所蔵していたという、極めて重要な記述が見られる 4 。この記録は、戦国時代における「平沙落雁図」の具体的な所在を示す、確かな手がかりである。
六角氏の文化的背景と絵画所蔵の意義
近江(現在の滋賀県)を本拠とした守護大名・六角氏は、京に隣接する地理的優位性を活かし、足利将軍家とも密接な関係を築いていた 28 。彼らは中央の洗練された文化を積極的に領国に導入し、居城である観音寺城の城下は、多くの公家や文化人が集う一大文化センターとして繁栄した 29 。
このような文化的背景を持つ六角氏が、東山御物の至宝である牧谿筆「平沙落雁図」を所蔵していたという事実は、彼らが単なる地方の武力勢力ではなく、室町文化の正統な継承者の一人であったことを雄弁に物語っている。この一幅の絵は、六角氏の文化的権威の象徴であった。
観音寺城の陥落と「名物狩り」
しかし、その栄華は長くは続かなかった。永禄11年(1568年)、足利義昭を奉じて上洛を目指す織田信長の軍勢によって観音寺城は陥落し、六角氏は没落する。
ここで重要となるのが、信長の行動様式である。信長は、敵対勢力を軍事的に征服するだけでなく、彼らが所有する「名物」を徹底的に接収したことで知られる。これは後に「名物狩り」と称される、信長の天下布武戦略の重要な一環であった 30 。
この歴史的文脈から、一つの蓋然性の高い推論が導き出される。すなわち、六角氏が所蔵していた牧谿筆「平沙落雁図」は、観音寺城の陥落時に信長の手中に渡った可能性が極めて高いということである。信長にとって、この名画の獲得は、単なる戦利品以上の意味を持っていた。それは、旧勢力である六角氏が保持していた文化的権威を剥奪し、それを自らのものとして吸収する、極めて象徴的な行為であった。絵画の所有権の移動が、すなわち権力の移動そのものを可視化した瞬間であった。
第五章:越前太守・朝倉氏と「筆者不詳」の『平沙落雁図』
一乗谷の栄華と文化
時を同じくして、北陸の越前(現在の福井県)を支配していたのが朝倉氏である。五代当主・朝倉孝景(宗淳)らのもと、本拠地である一乗谷には京を模した壮麗な城下町が築かれ、応仁の乱で荒廃した京から逃れてきた多くの公家や僧侶、文化人を受け入れたことで、北陸の小京都として栄華を極めた 31 。
朝倉家所蔵の『平沙落雁図』
朝倉家もまた、「平沙落雁図」を所蔵していたと伝えられている。しかし、こちらは六角家所蔵のものとは異なり、「筆者不詳」とされている点が注目される 4 。この「筆者不詳」の絵の正体については、いくつかの可能性が考えられる。
- 牧谿画の異伝 : 六角家が所蔵していたものとは別の、伝牧谿筆「瀟湘八景図」の断簡の一つであった可能性。東山御物の名画は、必ずしもその全てが完璧な記録と共に伝わったわけではない。
- 玉澗画の可能性 : 牧谿と並び称される玉澗の「瀟湘八景図」の断簡であったが、伝承の過程で筆者名が失われた可能性。玉澗の作品もまた、東山御物として極めて高く評価されていた 14 。
- 日本製の高精度の写し : 東山御物の名画を手本として、狩野派のような当代一流の日本の絵師が制作した模写であった可能性。当時、原本に肉薄する優れた模写は、原本に準ずる価値を持つことも珍しくなかった 33 。
- 記録の不備 : 実際には牧谿や玉澗の真筆であったが、後世の記録者(例えば『松屋名物集』の編者など)がその情報を確認できなかっただけの可能性も否定できない。
いずれにせよ、朝倉氏が「平沙落雁図」という画題の絵画を珍重し、所蔵していた事実は、この画題が当時の武家社会においていかに高い文化的価値を持つものであったかを物語っている。
一乗谷の滅亡と文化財の行方
朝倉氏の栄華もまた、信長の前に潰え去る。天正元年(1573年)、刀禰坂の戦いで朝倉義景は信長に大敗し、栄華を誇った城下町・一乗谷は信長軍によって三日三晩にわたって焼き払われ、完全に灰燼に帰した 35 。この時、朝倉家が長年にわたって蒐集した膨大な書籍や美術品といった文化財もまた、戦利品として持ち去られたか、あるいは戦火の中で永遠に失われたと考えられる。朝倉家所蔵の「平沙落雁図」のその後の明確な足取りは、歴史の闇の中へと消えている。この喪失の物語もまた、文化財が常に破壊の危機に晒されていた戦国時代の無常を象徴していると言えよう。
第六章:天下人たちの蒐集と継承 ― 権威の集約
六角氏や朝倉氏といった旧勢力を次々と滅ぼした信長のもとには、全国から「名物」が集められた。しかし、その信長も天正10年(1582年)に本能寺で倒れる。信長が集めた名物の多くは、彼の後継者となった豊臣秀吉に引き継がれた。黄金の茶室に象徴されるように、秀吉もまた茶の湯と美術品蒐集に並々ならぬ情熱を注ぎ、自らの絶大な権力を飾るためにそれらを利用した。
そして秀吉の死後、関ヶ原の戦いを経て天下は徳川家康の手に帰し、豊臣家にあった名物の多くもまた、家康のもとへと集約されていった 22 。
この時代の美術品の流転を最も雄弁に物語るのが、玉澗筆と伝えられる「遠浦帰帆図」(現・徳川美術館蔵)の伝来史である。この一幅は、足利義政から連歌師の宗長、そして今川義元、北条氏綱、豊臣秀吉、徳川家康、そして御三家の筆頭である尾張徳川家へと、まさに当代きっての権力者たちの手を渡り歩いてきた 22 。
この事実は、「平沙落雁図」を含む「瀟湘八景図」の断簡を所有することが、戦国武将にとっていかに重要な意味を持っていたかを明確に示している。それは、単なる美術鑑賞という趣味の領域を遥かに超えた、極めて戦略的な行為であった。すなわち、
- 文化的正統性の証明 : 足利将軍家が築いた室町文化の正統な継承者であることの証。
- 政治的威信の誇示 : 強大な敵を滅ぼし、その至宝を奪うほどの圧倒的な力があることの表明。
- 経済的実力の顕示 : 一城、一国にも匹敵する価値のものを所有できる、揺るぎない財力の証明。
これら三つの意味を同時に示す、究極の自己顕示行為であった。したがって、「平沙落雁図」をはじめとする名物の伝来史を追うことは、すなわち戦国時代における権力の変遷そのものを、文化という側面から追跡することに他ならないのである。
第三部:近世以降の展開と現代における意義
戦国乱世を経て、権威の象徴としての地位を確立した「平沙落雁図」とその画題「瀟湘八景」は、泰平の世となった江戸時代以降、どのように継承され、変容していったのだろうか。そして、それは現代の我々に何を伝えているのだろうか。
第七章:画題の継承と日本的展開
狩野派による受容と新たな様式の創出
江戸幕府の成立と共に、絵画の世界で不動の地位を築いたのが御用絵師・狩野派であった。狩野派の絵師たち、特に江戸狩野の祖である狩野探幽は、牧谿や玉澗といった中国宋元の巨匠たちの画風を熱心に学び、それを自らの様式に取り入れた 36 。探幽が描いた「瀟湘八景図」は、古典に深く根差しながらも、余白を大胆に活かした瀟洒で知的な画面構成に特徴があり、古典の学習と独自の解釈を融合させ、新たな時代の美意識を反映した様式を生み出すことに成功した 37 。こうして「瀟湘八景」は、武家社会における最高の画題として、その命脈を保ち続けた。
画題の和様化 ― 「近江八景」の誕生
さらに、「瀟湘八景」という画題のコンセプトそのものが、日本独自の風景美と結びつき、新たな文化を生み出す現象も見られた。その最も代表的な例が、「近江八景」である 19 。琵琶湖周辺の八つの景勝地を、瀟湘八景の八つの画題になぞらえて選定したもので、「平沙落雁」は「堅田の落雁」に、「煙寺晩鐘」は「三井の晩鐘」に対応づけられた。これは、かつて中国の理想郷であった瀟湘のイメージが、日本の身近な風景の中に見出され、完全に日本文化として土着化したことを示す象
徴的な出来事であった。
第八章:離散と再会、そして現代へ
大名家の至宝として
戦国時代に天下人の手を経て、あるいは独自に入手された「瀟湘八景図」の断簡は、江戸時代を通じて各大名家の至宝として秘蔵された。例えば、牧谿筆の「平沙落雁図」は松江藩主・松平家(雲州松平家)に、「漁村夕照図」は淀藩主・稲葉家に伝わるなど、それぞれの絵画が各大名家の格式を象徴する宝物として、大切に守り伝えられていった。
徳川吉宗による世紀の再会
ここで、文化史上の特筆すべき出来事が起こる。享保13年(1728年)、幕政改革を進めていた八代将軍・徳川吉宗が、諸大名家に分蔵されていた伝牧谿筆の「瀟湘八景図」の断簡を江戸城に集めさせ、一時的に「再会」させるという、壮大な観賞会を催したのである 23 。これは、かつて足利将軍家が所有し、戦国の動乱の中で離散した文化的権威の象徴を、徳川将軍家が泰平の世において再び一つに集結させたことを意味する。徳川の権威が、文化的側面においても完全に天下を掌握したことを内外に示す、極めて象徴的な一大イベントであった。
現代への継承
明治維新による武家社会の終焉と共に、多くの大名家は財政的な困窮に陥り、秘蔵してきた宝物を手放さざるを得なくなった。こうして市場に流出した「瀟湘八景図」の断簡は、三井家や岩崎家といった近代の財閥や実業家たちのコレクションに収められた。そして戦後、これらのコレクションが美術館として公開されるに至り、かつては将軍や大名など、限られた権力者しか目にすることができなかった至宝を、我々一般市民も鑑賞できるようになった。
現在、伝牧谿筆「瀟湘八景図」の主要な断簡は、以下の美術館に所蔵され、国宝や重要文化財として大切に保管・公開されている。
|
画題 |
現所蔵先 |
文化財指定 |
|
平沙落雁図 |
出光美術館 |
重要文化財 |
|
漁村夕照図 |
根津美術館 |
国宝 |
|
煙寺晩鐘図 |
畠山記念館 |
国宝 |
|
遠浦帰帆図 |
京都国立博物館 |
重要文化財 |
|
洞庭秋月図 |
徳川美術館 |
重要文化財 |
|
瀟湘夜雨図 |
(個人蔵) |
- |
|
江天暮雪図 |
(個人蔵) |
- |
|
山市晴嵐図 |
(所在不明、模本のみ現存) |
- |
(出典: 11 等の情報を基に作成)
我々が今日、美術館の静かな展示室でこれらの断簡に対面できるのは、偶然の産物ではない。それは、戦国の武将たちがその文化的価値を鋭敏に見抜き、時に命を懸けて争奪し、そして近世の大名たちが家の威信をかけて守り抜いた、数百年にわたる歴史の積み重ねの結果なのである。これらの絵画は、単なる美しい美術品ではない。それは、日本の権力者たちの夢と野望、そして彼らが抱いた美意識が幾重にも刻み込まれた、歴史そのものの証人なのである。
結論:乱世を渡った雁
「平沙落雁図」の物語は、中国の詩的な風景画が、日本の禅的な美意識と出会い、戦国という乱世の坩堝で鍛え上げられ、権力と文化の絶対的な象徴へと昇華していく、壮大な歴史ドラマである。砂洲に舞い降りる一羽の雁が描かれた静謐な情景の裏には、足利将軍の雅、近江六角・越前朝倉の栄華と没落、そして織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人たちの覇業が、墨の濃淡のように幾重にも折り重なっている。
美術品の伝来史を丹念に紐解く作業は、文字による史料だけでは決して見えてこない、時代の精神や人間の息遣いを我々の前に鮮やかに蘇らせてくれる。武将たちは、この絵の中に何を見たのか。それは、故郷を遠く離れ、再び帰ることを願う旅人の心象風景(帰思)であったかもしれないし、あるいは、秩序をもって飛ぶ雁の群れに、自らが目指す理想の組織の姿を重ねたのかもしれない。
確かなことは、「平沙落雁図」が単なる鑑賞の対象ではなく、所有され、継承され、時には争奪の的となることで、歴史を動かす一つの力として機能したという事実である。乱世を生き抜き、数々の権力者の手を渡り、そして今なお我々の前に静かに佇むこの名画は、日本の歴史を深く理解するための、この上なく雄弁な語り部なのである。
引用文献
- fujita-museum.or.jp https://fujita-museum.or.jp/topics/2025/05/12/9710/#:~:text=%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%AF,%E3%81%8C%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
- 瀟湘八景図屏風 - 学芸員おすすめの所蔵品500 | 石川県立歴史博物館 https://www.ishikawa-rekihaku.jp/collection/detail.php?cd=GI00447
- 三重県立美術館 ミニ用語解説:瀟湘八景 東俊郎 友の会だよりno.18, 1988.7.23 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/53339036416.htm
- 瀟湘八景図 | Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/old/jp/theme/floor2_3/f2_3_koremade/cyuse_20170117.html
- 瀟湘八景図(ショウショウハッケイズ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF%E5%9B%B3-79364
- 空想の名所を巡る | 藤田美術館 | FUJITA MUSEUM https://fujita-museum.or.jp/topics/2025/05/12/9710/
- 相阿弥《瀟湘八景図》水墨画のメロディー 「島尾 新」:アート・アーカイブ探求 - artscape https://artscape.jp/study/art-achive/10122354_1982.html
- 瀟湘八景図を楽しむ(しょうしょうはっけいずをたのしむ) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/70shosho/
- 雲谷 等益《瀟湘八景図》 - 山口県立美術館 https://y-pam.jp/collection/highlight/unkoku_3/
- 瀟湘八景 | 豊橋市美術博物館 https://toyohashi-bihaku.jp/bihaku02/%E7%BE%8E%E8%A1%93%E8%B3%87%E6%96%99/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF/
- 漁村夕照図|根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=10390
- 遠浦帰帆図えんぽきはんず - 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/collection/meihin/chuugoku/item07/
- 平沙落雁図 - 出光コレクション https://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/chinese/01.php
- 山市晴嵐図 - 出光コレクション https://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/chinese/02.php
- 玉澗 : 作家情報データ&作品一覧 | 収蔵作品データベース | 岡山県立美術館 http://jmapps.ne.jp/okayamakenbi/sakka_det.html?list_count=10&person_id=111
- 玉澗「瀟湘八景図」の詩画と印章の研究(完成原稿) - SlideShare https://www.slideshare.net/lofen/ss-25875259
- 臨済禅師1150年・白隠禅師250年遠諱記念 特別展「禅―心をかたちに―」 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=4688
- 雪舟と探幽の「瀟湘八景」そして蕪村の「夜色楼台図」(その一~その三) - Press夜半亭 https://yahantei.fc2.page/%E9%9B%AA%E8%88%9F%E3%81%A8%E6%8E%A2%E5%B9%BD%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E8%95%AA%E6%9D%91%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A4%9C%E8%89%B2%E6%A5%BC/
- 絵画|漁村夕照図(伝牧谿筆)[根津美術館/東京] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-00101/
- 油滴天目 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/uploads/r_press/169.pdf
- 遠浦帰帆図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/588199
- 【重要文化財】遠浦帰帆図 - 玉澗 - Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/asset/returning-sailboat-from-a-distant-shore-yujian/uwHQUh6A840dmg?hl=ja
- 茶道具 翔雲堂 岡本 掛軸とは, http://shoundo.jpn.com/tool/jiku.html
- 戦国大名や商人が熱狂した「茶器」|初花肩衝など有名な茶器を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1143333
- 茶碗(唐物)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96835/
- 松屋名物﹁白鷺緑藻図﹂考 https://nara-wu.repo.nii.ac.jp/record/2001995/files/issn09132201v37pp148-137.pdf
- 名物記 めいぶつき - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/11002
- 安土城考古博物館の「戦国時代の近江・京都―六角氏だってすごかった!!―」に行ってきた - note https://note.com/yukinyan14/n/n8d753a3addc9
- 令和4年度春季特別展「戦国時代の近江・京都-六角氏だってすごかった!」図録 https://www.shiga-bunkazai.jp/publication/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%94%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%98%A5%E5%AD%A3%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%B1%95%E3%80%8C%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%BF%91%E6%B1%9F%E3%83%BB%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%80%8D/
- 織田信長 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7
- 戦国武将・朝倉家5代の城下町の栄枯盛衰を伝える名物案内人|福井人 http://communitytravel.jp/fukui/archives/80
- 戦国武将から学ぶVol. 4 「改革者!?中途採用、明智光秀の挑戦」 - d's JOURNAL https://www.dodadsj.com/content/200405_sengoku004/
- 潚湘八景図(模本) しょうしょうはっけいずもほん - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-6745?locale=ja
- 紙本水墨瀟湘八景図〈(伝元信筆)/〉 - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/160475
- 一乗谷朝倉氏遺跡とは?日本のポンペイと呼ばれる貴重な遺跡は、大河ドラマ「麒麟がくる」にも登場しました - 福いろ https://fuku-iro.jp/feature/11
- 瀟湘八景図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/13094
- [ID:1494] 瀟湘八景 : 資料情報 | デジタルアーカイブ | 静岡県立美術館 https://jmapps.ne.jp/spmoa/det.html?data_id=1494
- 狩野探幽《瀟湘八景図屛風》 江戸時代、ミネアポリス美術館 - 「美術史チャンネル」ブログ https://art-history-channel.blogspot.com/2021/05/31663.html
- 牧谿とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%89%A7%E8%B0%BF