徒然草
『徒然草』は吉田兼好の随筆。無常観を基調に人生論、社会批評、美意識、逸話など多様なテーマを和漢混淆文で描く。日本三大随筆の一つ。
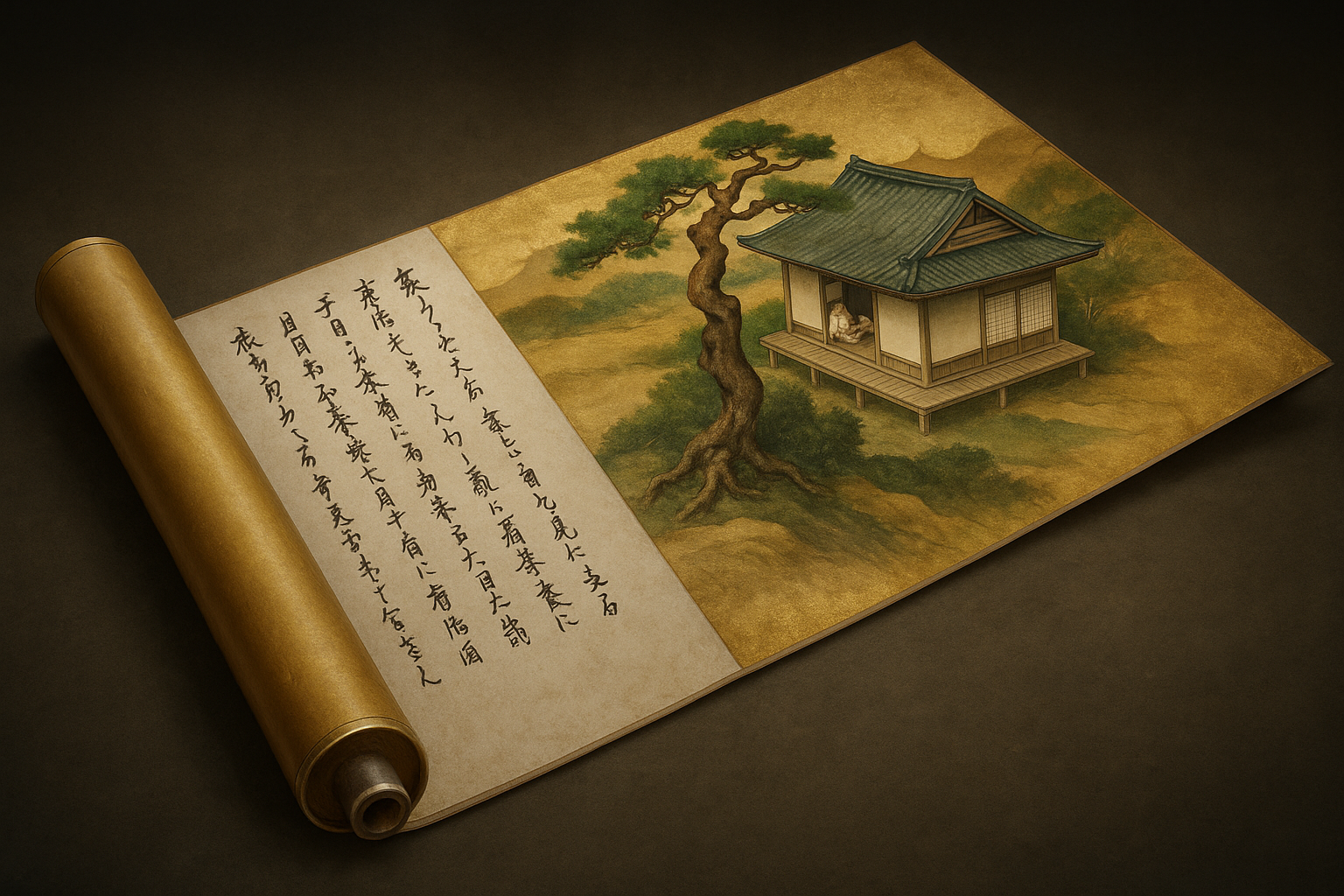
吉田兼好『徒然草』の総合的研究:成立背景から現代的意義まで
はじめに
本報告書は、日本文学史において不朽の名作として位置づけられる吉田兼好作『徒然草』について、その成立背景、作者実像、内容、文学的特徴、後世への影響、そして現代における意義を多角的に調査・分析し、その総合的な価値を明らかにすることを目的とする。『徒然草』は、鎌倉時代末期から南北朝時代という激動の時代に生み出されながら、時代を超えて多くの人々に読み継がれてきた。その魅力の源泉は、無常観を基調としながらも、人間や社会に対する鋭い観察眼、洗練された美意識、そして普遍的な人生訓に富む内容にあると言えよう。本報告書は、これらの要素を詳細に検討することで、『徒然草』の奥深い世界へと読者を誘うことを目指す。
第一部:『徒然草』の成立と吉田兼好
この部では、『徒然草』という作品がどのような人物によって、どのような時代背景のもとに生み出されたのかを深く掘り下げていく。作者の実像と執筆当時の社会・文化的状況を理解することは、作品解釈の不可欠な基盤となる。
第一章:作者・吉田兼好の実像
出自と経歴:伝統的見解と近年の研究動向
『徒然草』の作者、吉田兼好(通称、兼好法師)は、本名を卜部兼好(うらべのかねよし)といい、1283年(弘安6年)頃の生まれとされる 1 。伝統的には、京都の吉田神社の神官を務める卜部氏の家系出身と考えられてきた 1 。しかし、この説は、吉田神道の創始者である吉田兼倶(よしだかねとも)が、自家の権威を高めるために兼好を卜部氏嫡流に結びつける系譜を捏造した可能性が、近年の研究、特に小川剛生氏の研究によって指摘されている 3 。この指摘は、兼好の出自や経歴に関する従来の理解を大きく揺るがし、その実像について再検討を迫るものである。
近年の研究では、兼好は出家前の若年期に、鎌倉幕府の有力者であった金沢北条氏の被官として活動し、鎌倉と京都を往来していたとする説が有力視されている 3 。特に、北条貞顕との関係を通じて朝廷における人脈を形成していったことが、金沢文庫に残された文書の解明などから明らかになってきている 3 。この事実は、兼好が単に京都の文化人であったというだけでなく、東国の武家政権とも深く関わり、当時の政治・社会の中枢にも近い位置にいた可能性を示唆する。このような経験は、『徒然草』に見られる多様な題材や、公家社会と武家社会双方への視線に影響を与えたと考えられる。
兼好は若い頃、後二条天皇に仕えたが、中流貴族であったため出世の道は限られていた 1 。後二条天皇の崩御後、30歳前後で出家し、特定の宗派に深く帰依することなく、京都の修学院や横川などに隠棲しつつ、時には朝廷の歌会に出席するなど、比較的自由な生活を送ったと伝えられる 1 。
和歌の才能にも恵まれ、当代随一の歌人であった二条為世(にじょうためよ)に師事し、頓阿(とんあ)・慶運(けいうん)・浄弁(じょうべん)と共に「和歌四天王」の一人と称されるほどの評価を得ていた 1 。その実力は、天皇や上皇の勅命によって編纂された勅撰和歌集に18首もの歌が採録されていることからも窺える 1 。兼好の歌人としての深い素養は、『徒然草』の洗練された文章表現や、随所にみられる鋭敏な美意識の形成に大きく寄与したと考えられる。
思想形成の背景:仏教、儒教、老荘思想、和歌、平安女流文学からの影響
吉田兼好の思想形成には、多様な要素が複雑に絡み合っている。その根底には、当時の知識人にとって必須の教養であった仏教思想、特に無常観や隠遁思想が深く影響している 6 。『徒然草』全体を貫くこの無常観は、万物が流転し、何一つとして永遠なるものはないという仏教の基本的な教えであり、諸行無常の理として作品の随所に現れる 9 。また、世俗の煩わしさから離れ、静かな環境で精神の自由を求める隠遁の思想も、兼好の生き方や作品に影を落としている。しかし、兼好の隠遁は、必ずしも現実逃避的なものではなく、むしろ世の中を冷静に観察し、思索を深めるための積極的な選択であったとも解釈できる。
仏教思想に加え、儒教や老荘思想からの影響も無視できない。儒教的な道徳観や人間関係に関する洞察は、処世訓的な章段に散見される。一方、老荘思想、特に『老子』や『荘子』は兼好の愛読書であったとされ 10 、その自然観や無為自然の思想は、兼好の美意識や人生観に影響を与えたと考えられる。近年の研究では、兼好がこれらの漢籍を『老子河上公章句』や『論語集解』といった古注釈書を通じて受容していた可能性も指摘されている 12 。
さらに、兼好は優れた歌人であり、和歌の伝統や美意識も彼の文学的基盤を形成している。そして、平安時代の女流文学、とりわけ清少納言の『枕草子』からの影響は顕著である。『徒然草』の序段で用いられる「つれづれ」という言葉自体、平安時代の女性貴族が好んで用いたものであり、愛する人の訪れを待つ間の退屈さや寂しさを表現する言葉であった 1 。兼好が『枕草子』を愛読していたことは知られており 1 、その観察眼の鋭さや、日常の些細な事柄に美を見出す感性は、『徒然草』の随筆としての性格や内容に大きな影響を与えたと言えるだろう 6 。
兼好の思想的重層性と『徒然草』の多面性
吉田兼好の思想は、仏教(特に無常観、禅宗的要素)、儒教(現実的な処世術や人間関係の洞察)、老荘思想(隠逸志向、自然観)、そして和歌や平安女流文学に代表される国風文化の伝統という、複数の要素が複雑に絡み合って形成されている。これらは単に並存するだけでなく、時に緊張関係を保ちつつ、兼好の中で独自の調和を見出していたと考えられる。
兼好は仏教の無常観を深く内面化しているが 6 、それは単なる厭世や逃避ではなく、むしろ変化する現実を直視し、その中でいかに生きるかという問いに繋がっている。一方で、儒教的な知恵や人間関係の機微、社会への鋭い観察眼も持ち合わせており 12 、これは現実社会との関わりを完全に断ち切ってはいないことを示す。さらに、老荘思想に見られるような自然への愛着や、世俗的な価値観からの自由を求める精神も顕著である 10 。
これらの異なる思想的源泉が、兼好の中で衝突・融合することで、『徒然草』の各段に見られる多様な主題(人生論、社会批評、美意識、逸話など)と、時にシニカルでありながらも人間味あふれる多面的な筆致を生み出したと言える。例えば、第137段「花は盛りに」に見られる美意識は、完成された美だけでなく、移ろいゆくもののうちにも美を見出すという点で、無常観と深く結びつきつつ、老荘的な自然観とも共鳴する。また、仁和寺の法師(第52段)のような逸話では、人間の愚かさや滑稽さを描きつつも、そこには温かい眼差しがあり、儒教的な人間理解と仏教的な慈悲が混ざり合っていると解釈できる。
このように、兼好の思想的背景の重層性は、『徒然草』が一面的に解釈されることを拒み、時代を超えて多様な読まれ方(教訓書、趣味論、人生論など 6 )をされてきた根源的な理由であると言える。この多面性こそが、作品の普遍性と永続的な魅力の源泉なのである。
第二章:成立の時代背景
鎌倉末期~南北朝初期の政治・社会状況
『徒然草』が執筆されたと推定される1331年頃は、日本史における大きな転換期であった。鎌倉幕府の権威が揺らぎ、やがて滅亡へと向かい、後醍醐天皇による建武の新政も短期間で瓦解するなど、政治的混乱と社会変動が激しい時代であった 5 。『太平記』などの軍記物語には、当時の社会の不穏な空気、武士たちの台頭と抗争、そしてそれに伴う人々の苦難が描かれている。
具体的には、政治的な不満や陰謀が渦巻き、各地で争乱が頻発した。武士による焼き討ちや、戦闘による死者の首が河原に晒されるといった凄惨な光景も珍しくなく、人心は荒廃し、社会秩序は大きく乱れていた 5 。このような激動の時代背景は、『徒然草』の中では直接的に生々しく描かれることは少ない。しかし、作品全体を覆う無常観や、世事を一歩引いた地点から冷静に観察しようとする兼好の態度は、こうした時代の空気と無縁ではないだろう。むしろ、混乱した世相であればこそ、変わらない人間の本質や、束の間の美、そして避けられない死といったテーマが、より切実なものとして兼好の心に迫ってきたのかもしれない。
この時代の混乱の一因として、鎌倉時代を通じて続いてきた二元的な政治体制の矛盾が指摘される。京都には天皇を中心とする伝統的な公家政権が存在し続けた一方で、鎌倉には武家による幕府が実権を握っていた。この二つの権力が、荘園の支配や各種の許認可権を巡って複雑に関係し、時には対立することで、社会全体の不安定さを増幅させていた側面がある 5 。
文化的動向と『徒然草』執筆の契機
政治的・社会的な変動は、文化のあり方にも影響を与えた。鎌倉時代を通じて武士階級が台頭し、その質実剛健な気風が文化にも反映される一方で、公家社会では伝統的な王朝文化が継承されていた。和歌の世界では、藤原俊成・定家親子によって「幽玄」「有心」といった新しい歌風が確立され、歌壇に大きな影響力を持っていた 5 。兼好自身もこの流れを汲む優れた歌人であり、その美的感覚は『徒然草』にも反映されている。
兼好が『徒然草』をいつ頃から、どのような明確な動機で執筆し始めたのかについては、確かな記録がなく、今日においても不明な点が多い 1 。作品の成立時期についても諸説あり、20代で起筆し最晩年まで書き継がれた可能性や、複数の段階を経て編集された可能性などが議論されている 6 。
しかし、作品の冒頭である序段には、その執筆の姿勢が象徴的に記されている。「つれづれなるままに、日暮らし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」 1 。これは、手持ち無沙汰な時間に任せて、心に浮かんでは消えるとりとめのない事柄を、あてもなく書きつけていると、不思議と熱中して狂おしい気持ちになる、といった意味である。この一文は、『徒然草』という作品の、特定の主題や構成に縛られない自由な形式と、日常の雑感から深い思索に至るまでの多様な内容をよく表していると言えよう。
激動の時代と「書かれなかったこと」の重要性
『徒然草』は、鎌倉幕府滅亡前夜から南北朝の動乱期という、日本史上でも稀に見る激動の時代に書かれた 5 。しかしながら、作品中にはその政治的混乱や社会不安を直接的に描いた箇所は極めて少ない。この「書かれなかったこと」こそが、『徒然草』の深層を理解する鍵であり、兼好の文学的スタンスや処世術、さらには作品が持つ普遍的な価値を示唆している。
当時の社会は『太平記』に描かれるように、政争、戦乱、裏切りが日常茶飯事で、人々の生活は極度に不安定であった 5 。兼好自身も、そのような現実から完全に隔絶していたわけではなく、むしろその渦中で人間関係を巧みに渡り歩いていた形跡がある。例えば、幕府か朝廷か許認可権者も定まらない中で不動産物件の売買や寄進を仲介していたという記録も存在する 5 。
にもかかわらず、『徒然草』の多くの段は、日常の些事、趣味、人間観察、美意識、仏教的思索といった、一見すると時代状況から遊離したかのような内容に満ちている。これは、兼好が意図的に「時事的なもの」「政治的なもの」を排除し、より普遍的で永続的なテーマを選び取った結果ではないだろうか。激動の現実を直接描くのではなく、その中で見出される人間の本質や美、あるいは無常の理といったものを描くことで、時代を超えた価値を持つ作品を目指した可能性が考えられる。
また、激しい対立や混乱を直接描くことを避けるのは、兼好の処世術の一環であったとも考えられる。特定の立場に与するような記述は、自身の身を危うくする可能性があったため、より中立的で普遍的な語り口を選んだのかもしれない。この「書かれなかったこと」の背景を理解することで、例えば無常観の記述は、単なる仏教的諦念ではなく、目の前の激しい変化に対する兼好なりの応答として、より切実なものとして読解できる。また、美意識に関する段は、混乱した世の中だからこそ求められる精神的な安らぎや、変わらない価値への希求の表れと捉えることも可能である。
『徒然草』が直接的に時代を描かないことは、作品の価値を減じるものではなく、むしろその普遍性を高める要因となっている。兼好は、激動の時代状況を背景としつつも、それを超越する人間の普遍的な営みや思索に焦点を当てることで、後世の読者にも共感と示唆を与え続ける作品を創造したと言える。この「書かれなかったこと」を意識することが、現代における『徒然草』の意義を再発見する上で不可欠である。
第二部:『徒然草』の内容と文学世界
この部では、『徒然草』が具体的にどのような内容を持ち、どのような思想や世界観を提示しているのかを詳細に分析する。構成の妙、主題の多様性、そして代表的な章段の読解を通じて、兼好の文学的達成を明らかにする。
第一章:構成と主題の多様性
全243(または244)段の構成的特徴
『徒然草』は、序段とそれに続く多数の章段から構成されている。章段の総数については、243段とする説 2 と244段とする説 6 があり、現在も議論が続いている。江戸時代の国学者、北村季吟が著した注釈書『徒然草文段抄』以降、序段に続く本文を243段に区分する形式が一般的に用いられるようになった 15 。
『徒然草』の構成上の大きな特徴は、各章段が基本的に独立した内容を持ち、全体として明確な起承転結や一貫した物語性を持たない点である 6 。作者である兼好法師が、心に浮かぶまま、連想の赴くままに様々な事柄を書き綴ったものであり、その配列も論理的な順序というよりは、むしろ「連歌的」と評されるような、自由で飛躍のある連なりを見せている 15 。この構成の自由さが、読者に対して多様な解釈の可能性を開き、時代を超えて読み継がれる魅力の一つとなっている。章段の長さもまちまちで、短いものは数行、長いものは数ページに及ぶものもある。
主題の分類(人生論、無常観、美意識、社会批評、逸話など)
『徒然草』の内容は極めて多岐にわたり、作者兼好の広範な知識と深い洞察力を反映している。主題を大まかに分類すると、人生論・処世訓、無常観・死生観、美意識・趣味、社会批評・世相、逸話・説話、有職故実・知識、仏教思想などが挙げられる 2 。
評論的な調子で人生のあり方や処世の知恵を説く章段もあれば、歴史上の人物や市井の人々の興味深い逸話を語る説話的な章段もある。また、作者自身が見聞した雑事や、心に抱いた感慨を断片的に記したもの、あるいは朝廷の儀式や故実に関する知識を書き留めたものなど、その内訳はまさに雑多であり、一言でその全体像を捉えることは難しい 6 。
以下に、『徒然草』の主要なテーマを分類し、その概要を示す表を提示する。これは、 13 で言及されている橘純一、鈴木一彦、鬼頭清明らの分類案を参考にしつつ、本報告書の視点を加えて再構成したものである。
表1: 『徒然草』主要テーマ分類表
|
分類項目 |
内容例 |
関連する学説・資料 |
|
1. 人生論・処世訓 |
生き方、人間関係の心得、専門分野での心構え、日常の言動に関する教訓、質素倹約の推奨、慈悲や思いやりの大切さ |
13 (橘分類「処世訓」全般)、 19 、 19 |
|
2. 無常観・死生観 |
諸行無常の理、死の必然性、人生のはかなさへの眼差し、変化することの意義 |
6 、 7 、 9 、 23 、 6 、 24 |
|
3. 美意識・趣味 |
自然美(花、月、四季の移ろい)、芸術(和歌、音楽)、調度品、住居のあり方、もののあはれ、不完全なものの美 |
19 、 21 (第137段など)、 26 、 21 、 6 |
|
4. 社会批評・世相 |
当時の風俗や流行に対する批判的視点、人間模様の観察、政治や社会のあり方への言及 |
5 、 19 、 5 、 6 |
|
5. 逸話・説話 |
歴史上の人物(天皇、貴族、武士など)の逸話、僧侶や名人のエピソード、滑稽談、奇聞 |
2 、 21 、 21 、 13 (鬼頭分類 II)、 25 |
|
6. 有職故実・知識 |
朝廷の儀式や制度、官職、言語や文字に関する記述、故事来歴 |
2 、 6 、 13 (橘分類「広義の学問資料提供」、鬼頭分類 III) |
|
7. 仏教思想 |
仏教の教えに関する考察、信仰のあり方、因果応報 |
76 、 77 、 7 、 9 、 12 、 8 |
|
8. その他 |
作者の個人的な感想、断片的な思索、自己言及 |
6 、 13 (橘分類「其の他」) |
この表は、『徒然草』がいかに多様なテーマを扱っているかを一覧で示すことで、作品の懐の深さを具体的に理解する一助となる。どの主題に多くの段が割かれているかを見ることで、兼好の関心の中心や、彼が読者に伝えたかったメッセージの傾向を推測する手がかりとなる。また、特定の主題に分類された段々をまとめて読むことで、その主題に対する兼好の多角的な視点や思想の深まりを追うことができる。例えば、「無常観」という主題でも、単なる諦念から積極的な肯定まで、様々なニュアンスがあることがわかるであろう。
第二章:主要な段の読解と分析
代表的な章段の読解
『徒然草』には数多くの印象的な章段が存在するが、ここでは特に広く知られ、作品の思想や特徴をよく表しているいくつかの段を取り上げ、その内容を概観する。
- 序段: 「つれづれなるままに、日暮らし、硯に向かひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」という有名な一文で始まるこの段は、作者兼好が本作を執筆する際の心境と姿勢を示している 1 。手持ち無沙汰な時間に任せ、心に浮かぶとりとめのない事柄を書き連ねることへのある種の興奮が語られており、作品全体の自由な精神を象徴している。
- 第25段「飛鳥川」: 絶えず流れを変える飛鳥川の淵瀬の無常さを引き合いに出し、人の世もまた常に変化し、何一つとして永遠ではないという真理を説く 20 。かつての繁華街が荒野となり、住人も移り変わっていく様を描写し、栄枯盛衰の儚さを印象づける。
- 第52段「仁和寺にある法師」: 仁和寺の老僧が、長年念願だった石清水八幡宮へ参詣するものの、山上の本社を知らずに麓の極楽寺や高良社だけを拝んで満足して帰ってきたという逸話 21 。この話を通して、物事をよく知らないまま早合点することの愚かさや、何事につけても先達(案内者・指導者)の重要性を説いている。
- 第91段「吉凶は人によりて、日によらず」: 世間で言われる日の吉凶(例えば赤舌日)に惑わされることなく、物事の成否は結局その人の心がけや行いによるのだという考えを示す 21 。迷信にとらわれることを批判し、主体的な生き方を促す。
- 第109段「高名の木登り」: 木登りの名人が、弟子が高い木から降りてくる際、危険な高所では何も言わず、軒先ほどの安全に見える高さになった時に初めて「あやまちすな。心して降りよ」と注意したという話 21 。本当に危険なのは、油断が生じやすい状況であるという、人間の心理の機微を鋭く突いている。
- 第137段「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」: 満開の花や満月といった完璧な状態だけが美しいのではなく、咲き始めの蕾や散り際の桜、雨に隠れた月、欠けた月など、不完全なものや移ろいゆくもののうちにも深い趣があるという、兼好独自の美意識を表明した代表的な段 19 。
- 第155段「死期は序を待たず」: 四季の巡りには順序があるが、人の死はいつ訪れるか分からず、順番を待ってはくれないという、死の突然性と無常の理を説く 6 。人々は死を遠いものと考えがちだが、実際には常に身近に迫っていることを警告する。
- 第243段「八つになりし年」: 兼好が8歳の頃、父に「仏とは何か」と問い、父が答えに窮したという微笑ましい幼少期の逸話 22 。子供の純粋な疑問と、それに対する大人のユーモラスな対応が描かれ、兼好の人間観察の鋭さがうかがえる。
各段に込められた兼好の思想とメッセージ
これらの代表的な章段は、それぞれが独立した読み物として楽しめるだけでなく、兼好の多様な思想や人間観、社会観、そして彼が読者に伝えようとしたメッセージを色濃く反映している。
例えば、第137段「花は盛りに」は、単に自然美の鑑賞法を述べているだけでなく、物事の価値は一面的ではなく、多様な側面から見出すことができるという、より深い人生観や価値観を示唆している 19 。これは、完成や完璧さのみを追求しがちな現代社会においても、示唆に富むメッセージと言えよう。
第109段「高名の木登り」は、一見安全に見える状況にこそ油断が潜むという教訓であり、これは仕事や日常生活における危機管理の重要性として現代にも通じる普遍的な知恵である 21 。
また、第52段「仁和寺にある法師」や第91段「吉凶は人によりて、日によらず」などは、人間の思い込みや迷信に対する批判的視点を示しており、物事の本質を見極めることの重要性を教えてくれる。
これらの章段を通じて、兼好は具体的な逸話や自身の思索を巧みに織り交ぜながら、読者に対して、人生をいかに生きるべきか、物事をどのように捉えるべきかといった問いを投げかけている。その語り口は時に教訓的であり、時にユーモラスであり、時に鋭い批評精神に満ちているが、その根底には人間存在への深い洞察と共感が流れていると言えるだろう。
第三章:『徒然草』に通底する思想
無常観と隠遁思想の深層
『徒然草』全体を貫く最も重要な思想の一つが、仏教的な無常観である 6 。この世のあらゆるものは常に変化し続け、永遠不変なるものは存在しないという認識は、兼好が生きた鎌倉末期から南北朝時代という動乱の時代背景とも深く結びついている。しかし、兼好の無常観は、単なる悲観主義や厭世観に陥るものではない。むしろ、変化を受け入れ、限りある「今」という時間を大切に生きることの重要性を説く、積極的な側面をも含んでいる 17 。
隠遁思想もまた、『徒然草』における重要なテーマである。兼好は、世俗の喧騒や名利から離れ、静かな環境で思索にふける生活に一定の価値を見出している 7 。第75段では、「まぎるるかたなく、ただひとりあるのみこそよけれ」と述べ、孤独の中で精神の自由と安定が得られることを肯定している。しかし、兼好の隠遁は、社会との完全な断絶を意味するものではなかった。彼は出家後も和歌の会に参加したり、鎌倉と京都を往来したりするなど、俗世との接点を持ち続けていた形跡がある 1 。この点は、例えば鴨長明の『方丈記』に見られるような徹底した隠遁生活とは異なる特徴であり、兼好の隠遁観の複雑さを示している 24 。彼の心は、現世への関心と修道生活への志向の間で揺れ動いていたとも考えられる 7 。
処世術と人間洞察
『徒然草』は、単なる思弁的な随筆に留まらず、現実社会を生き抜くための実践的な知恵や教訓を数多く含んでいる 19 。これらの処世訓は、人間関係の機微、専門分野における心得、日常の立ち居振る舞いなど、多岐にわたる。
兼好の処世術の根底にあるのは、人間の本質に対する鋭い洞察力である。彼は、人間の喜怒哀楽、欲望、虚栄心、愚かさといった側面を、時にユーモラスに、時に辛辣に、しかし常に温かい眼差しを持って描き出している 19 。例えば、第117段では「よき友三つあり。一つには物くるる友。二つには医師(くすし)。三つには知恵ある友」と、実利的な視点も交えつつ友人のあり方を論じている。このような人間観察は、具体的な逸話を通じて語られることが多く、読者は物語を楽しみながら、自然と人間理解を深めることができる。
独自の美意識と自然観
『徒然草』には、兼好独自の洗練された美意識が随所に表れている。その基調には、平安時代以来の王朝的・都会的な価値観があるものの 6 、それに留まらず、簡素なもの、不完全なもの、そして移ろいゆくもののうちにこそ真の美や趣を見出そうとする姿勢が特徴的である 19 。
前述の第137段「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」はその代表であり、完成された美だけでなく、その過程や余情、あるいは想像の中に美を見出すという、日本的な美意識の原型とも言える考え方を示している。また、自然の美しさや四季の移ろいに対する鋭敏な感受性も、『徒然草』の大きな魅力の一つである 19 。兼好は、自然の中に人間の感情や人生を投影し、そこから深い感慨を引き出している。
「無常」の美学化と日本的美意識への接続
『徒然草』における無常観は、単なる仏教的諦念や厭世観に留まらず、むしろそれを美意識の次元にまで昇華させている点に大きな特徴がある。兼好は、移ろいゆくもの、不完全なもの、滅びゆくもののうちにかえって深い趣や美を見出そうとする。この視点は、後の「わび・さび」といった日本特有の美意識の形成に大きな影響を与えたと考えられる。
『徒然草』の根底には仏教的な無常観がある 6 。万物は常に変化し、永遠なるものは存在しないという認識である。しかし兼好は、この「無常」を単に否定的なものとして捉えるのではなく、むしろ美の源泉として積極的に評価する。第137段「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」はその象徴であり、満開の花や満月といった完璧な状態だけでなく、蕾や散りゆく花、欠けた月にも美を見出す 19 。
この美意識は、完成された静的な美よりも、生成と消滅の過程、つまり「動的な美」を重視するものである。これは、常に変化し続ける「無常」の理と深く共鳴する。このような「不完全さの美」「移ろいの美」は、後の茶道における「わび・さび」の精神 27 や、日本庭園における非対称性や自然らしさの追求 30 といった日本文化の核心的な美意識へと繋がっていくと考えられる。
兼好の美意識は、単に個人の趣味に留まらず、無常という普遍的な真理を美的体験へと転換させることで、日本人の美意識の深層に影響を与え、その後の文化的展開のひとつの源流となったと言える。このように、『徒然草』は、無常という概念を仏教思想から美意識へと架橋し、日本的な美のあり方を提示した点で画期的である。それは、完璧さや永続性ではなく、はかなさや変化の中にこそ真の美や趣があるという価値観であり、現代に至るまで日本文化の基層に影響を与え続けている重要な美的パラダイムを提示したと言える。
第三部:『徒然草』の文学的特徴と比較文学
この部では、『徒然草』が文学作品としてどのような技巧や特色を持っているのか、そして日本文学史の中でどのような位置を占めるのかを、他の代表的な随筆作品との比較を通じて明らかにする。
第一章:文体と表現技法
和漢混淆文と和文の巧みな運用
『徒然草』の文体は、一つの様式に固定されることなく、章段の主題や内容に応じて、和文と漢文訓読体が巧みに使い分けられている点が大きな特徴である 15 。平安時代以来の伝統を持つ優美な和文脈で情感豊かに語られる部分もあれば、漢籍の教養に裏打ちされた簡潔で論理的な漢文訓読調で思索や教訓が述べられる部分もある。この和漢の要素が融合した和漢混淆文は、時に歯切れの良い明晰な表現を生み出し、複雑な思想や微妙なニュアンスを効果的に伝えることを可能にしている 33 。この柔軟な文体の運用が、作品に深みと多様なリズム感を与えている。
簡潔性、暗示性、ユーモア、写実性の効果
『徒然草』の文章は、総じて簡潔であることを旨としており、冗長な表現を排し、短い言葉の中に豊かな内容を凝縮させようとする傾向が見られる 15 。この簡潔性は、読者に思索の余地を残し、深い余韻を与える効果も持っている。
また、直接的な表現を避け、暗示に富んだ言い回しを用いることで、行間に豊かな情感や含意を込める技法も随所に見られる 19 。これにより、読者は言葉の表面的な意味だけでなく、その奥に潜む作者の意図や感情を能動的に読み解くことが求められ、作品とのより深い対話が生まれる。
人間観察に基づくユーモアや皮肉も、『徒然草』の大きな魅力の一つである 17 。兼好は、人間の愚かさ、見栄、矛盾などを、時に辛辣に、しかし多くは温かい眼差しをもって描き出す。例えば、第236段「丹波に出雲といふ所あり」では、聖海上人が獅子・狛犬の配置に深遠な理由があると思い込み感涙するが、実は子供のいたずらであったという話が語られる 25 。ここでは、神官の真面目な態度がむしろ滑稽さを誘い、読者の笑いを誘う 25 。また、第243段の兼好自身の幼少期の逸話では、仏の根源について問い詰める子供と、それに窮する父親の姿がユーモラスに描かれている 22 。このようなユーモアは、作品に親しみやすさを与えるとともに、人間存在の愛すべき滑稽さを浮き彫りにする。
さらに、対象をありのままに捉えようとする写実的な描写も、『徒然草』の文学的価値を高めている 25 。人々の言動や心理、あるいは自然の風景などが、具体的なディテールをもって生き生きと描き出されており、読者はあたかもその場に居合わせるかのような臨場感を味わうことができる。これらの表現技法が複合的に作用することで、『徒然草』は単なる思索の記録を超えた、高度な文学作品としての品格を獲得している。
第二章:日本随筆文学史における位置づけ
日本三大随筆としての評価
『徒然草』は、平安時代中期の清少納言作『枕草子』、鎌倉時代初期の鴨長明作『方丈記』と並び、日本三大随筆の一つとして高く評価されている 39 。これらの作品は、それぞれ異なる時代背景と作者の個性のもとに書かれながらも、作者の身辺の見聞や思索を自由な形式で綴るという随筆文学の特性を共有し、後世の文学に大きな影響を与えてきた。
『枕草子』との比較:共通性と独自性(主題、構成、文体、美意識)
『徒然草』は、その構成や個々の章段において、『枕草子』からの影響が指摘されることがある 6 。『枕草子』が「ものはづくし」に代表される類聚的な章段や、宮廷生活の華やかな場面、自然の鋭い観察などを「をかし」の美意識のもとに描いたのに対し、『徒然草』はより思索的であり、仏教的な無常観を基調としながら、人生論や社会批評、逸話などを多様な筆致で展開している点で異なる 42 。
文体的には、『徒然草』に見られる雅文体の部分は、『枕草子』の洗練された和文の文体を模倣しようとしたもの(パスティーシュ)であるという見解もある 33 。一方で、安部清哉氏らの研究によれば、「あはれ」という語の用法において、係り結びとの共起率が『徒然草』(特にその第一部とされる序段から第32段まで)の方が『枕草子』よりも高いという特徴が見られる。これは、係り結びが衰退しつつあった鎌倉時代にあって、兼好が意識的に古典的な表現を用いた「古風表現」である可能性が示唆されている 44 。
このように、『徒然草』は『枕草子』という先行する偉大な随筆を意識しつつも、兼好自身の深い思索と独自の文体によって、新たな随筆文学の世界を切り開いたと言える。
『方丈記』との比較:無常観の捉え方と文学的達成
鴨長明の『方丈記』もまた、中世を代表する隠者文学であり、『徒然草』と同様に無常観を重要な主題としている点で比較されることが多い 6 。しかし、両作品における無常観の捉え方には顕著な違いが見られる。
『方丈記』における無常観は、長明自身が体験した天変地異や戦乱、そして自身の不遇な生涯を背景としており、より切実で悲哀に満ちたものとして描かれることが多い 24 。長明は、世の無常を嘆き、そこからの救済を求めて方丈の庵での隠遁生活を選ぶ。
これに対し、『徒然草』における兼好の無常観は、より客観的で、ある種の諦観と肯定を含んでいるとされる 24 。兼好は、無常を単に嘆くべきものとしてではなく、むしろ変化し移ろいゆくからこそ物事に趣があるのだと捉え、厭世観に陥ることなく、その中でいかに生きるべきかを問いかける。また、長明が自己の体験と内面に深く沈潜していくのに対し、兼好はより広い視野から人間社会や自然を観察し、多様な人々の生き様や知恵を描き出している点も異なる 24 。
『方丈記』が個人的な苦悩と救済の記録としての性格を強く持つのに対し、『徒然草』はより普遍的な人間論・人生論としての射程を持っていると言えるだろう。
表2: 『徒然草』と『枕草子』『方丈記』の比較表
|
比較項目 |
『枕草子』(清少納言) |
『方丈記』(鴨長明) |
『徒然草』(吉田兼好) |
|
作者と時代背景 |
平安時代中期、宮廷女房 |
鎌倉時代初期、元貴族・僧侶 |
鎌倉時代末期~南北朝初期、元官人・僧侶・歌人 |
|
主題・テーマ |
宮廷生活の観察、自然美、人事、「をかし」 |
天変地異、戦乱、世の無常、隠遁生活、仏教的救済 |
人生論、処世訓、無常観、美意識、社会批評、逸話、有職故実 |
|
構成 |
類聚的章段、日記的章段、随想的章段が混在 |
序盤に災害描写、中盤に隠遁生活の描写、終盤に仏教的思索。比較的構成的。 |
序段と独立した多数の章段。配列に明確な論理性なし。連想的。 |
|
文体 |
洗練された和文。機知に富む表現。簡潔明瞭。 |
漢文訓読の影響を受けた和漢混淆文。格調高い。 |
和文と漢文訓読体を巧みに使い分ける。簡潔かつ暗示的。時にユーモラス。 |
|
美意識 |
「をかし」(知的で明るい趣)、色彩豊かな美 |
静寂、閑寂、質素な美(わびの原型とも) |
「もののあはれ」に加え、不完全なもの、移ろいゆくものの美。簡素美。 |
|
無常観の捉え方 |
直接的な主題ではないが、人事の儚さへの言及あり。 |
世の無常を強く意識し、厭世的・悲観的に捉える傾向。仏教的救済を求める。 |
無常を理として受容。変化の中に趣を見出し、肯定的に捉える側面も。今を生きる姿勢。 |
|
ユーモア・風刺の質 |
機知に富んだ批評、時に皮肉。明るい笑い。 |
深刻な主題のためユーモアは少ない。 |
人間の愚かさや矛盾を突くユーモア、皮肉。温かい眼差しも。 |
|
社会との関わり方 |
宮廷社会への積極的関与と鋭い観察。 |
世俗を離れた隠遁。社会への批判的眼差し。 |
隠遁しつつも社会への関心は残る。傍観者的・批評的視点。 |
|
後世への影響 |
平安女流文学の代表。随筆文学の祖。 |
隠者文学の代表。無常観の文学的表現。 |
隠者文学、人生訓、美意識など多方面に影響。江戸時代以降広く愛読。 |
この比較表は、『徒然草』が、先行する『枕草子』の感覚的な世界や、『方丈記』の個人的な無常観の追求とは異なる地平を切り開いたことを示している。『徒然草』は、より広範な「知」――有職故実、先人の言行録、処世の知恵、そして深い人間洞察――を随筆文学の新たな中核に据えたと言える。兼好は、これらの多様な「知」を、時に教訓として、時に逸話として、時に批評として読者に提示し、それを読者自身の思索を促す触媒として機能させた。この「知の随筆」としての側面こそが、『徒然草』の文学史上の独自性と重要性を際立たせている。
『徒然草』における「知」のあり方と随筆文学の新たな地平
『徒然草』は、『枕草子』の感覚的な「をかし」の世界や、『方丈記』の個人的な無常観の追求とは異なり、「知」を随筆文学の新たな中核に据えた作品と言える。兼好は、有職故実、逸話、先人の言行、そして自身の深い思索を通じて得た多様な「知」を提示し、それを読者と共有しようとする。
『枕草子』は、清少納言の鋭い感受性によって捉えられた宮廷生活の「をかし」や自然の美しさが中心であり、感覚的・印象的な記述が特徴である 42 。一方、『方丈記』は、鴨長明自身の体験に基づき、災害や世の無常を克明に記し、個人的な救済としての隠遁生活と思索を深めた作品である 24 。
これに対し『徒然草』は、作者の直接的な体験や感情の吐露だけでなく、古今の書物から得た知識、人から伝え聞いた話(説話)、専門家の技術や心得など、広範な「知」が縦横に織り込まれている 2 。兼好はこれらの「知」を、時に教訓として、時に逸話として、時に批評として、多様な筆致で読者に提示する。例えば、有職故実に関する段 13 は知識の提供であり、名人たちの逸話 25 は専門的な知恵の紹介である。
重要なのは、兼好がこれらの「知」を絶対的なものとして押し付けるのではなく、むしろ読者自身の判断や思索を促すように提示している点である。彼はしばしば「~といへり」「~とかや」といった伝聞の形を取り、断定を避けることで、読者に対しても開かれたテクストとなっている。
この「知」の重視と、それを多様な形で提示する手法は、『枕草子』の感覚的世界や『方丈記』の個人的思索とは異なる、新たな随筆文学のあり方を示している。それは、読者を知的探求へと誘い、共に考えることを促すような、より開かれた知の空間を文学の中に創造しようとする試みと言えるかもしれない。『徒然草』は、多様な「知」を巧みに織り込み、それを読者との知的対話のきっかけとして提示することで、日本随筆文学に新たな地平を切り開いた。それは、感覚や個人的感情の表出に留まらず、より広範な知識や思索を文学の対象とする道を示し、後世の知識人たちに大きな影響を与えたと考えられる。
第四部:後世への影響と現代的意義
この部では、『徒然草』が後代の文学や文化にどのような影響を与え、現代社会においてどのような価値や意義を持ち続けているのかを考察する。古典としての生命力と、時代を超えて読み継がれる理由を探る。
第一章:後代の文学と文化への影響
江戸時代における受容と評価(注釈史を含む)
『徒然草』は、成立後しばらくの間は一部の知識人に知られる程度であったが、江戸時代初期になると急速にその価値が認識され、多くの読者を獲得するに至った 6 。この背景には、木版印刷技術の発達による書籍の普及があった。
江戸時代において、『徒然草』は多様な読まれ方をした。ある人々にとっては人生の指針となる教訓書として、またある人々にとっては趣味や風雅を論じた書として、あるいは単に面白い逸話集として楽しまれた 6 。このような多様な受容のされ方は、作品自体が持つ多面的な内容と魅力を反映している。
この時期には、『徒然草』の理解を助けるための注釈書も数多く出版された。その中でも代表的なものとして、秦宗巴(はたそうは)による『徒然草寿命院抄(じゅみょういんしょう)』(慶長9年(1604年)刊) 47 、加藤磐斎(かとうばんさい)による『徒然草抄』(寛文元年(1661年)刊) 15 、そして北村季吟(きたむらきぎん)による『徒然草文段抄(もんだんしょう)』(寛文7年(1667年)刊) 15 などが挙げられる。これらの注釈書は、語句の解釈だけでなく、作品の思想的背景や文学的価値についての論考も含んでおり、『徒然草』研究の基礎を築いたと言える 48 。
また、本居宣長のような江戸時代の国学者たちも『徒然草』に注目し、それぞれの学問的立場から評価や批判を行った 49 。例えば宣長は、兼好の美意識の一部に対して批判的な見解を示している 50 。江戸時代におけるこのような活発な受容と研究の歴史は、『徒然草』が日本文化の中に古典として確固たる地位を築いていく過程を示すと同時に、時代や個々の読者の関心によって解釈が多様に変化しうる古典作品の特性をも示している。
松尾芭蕉の俳諧理念や近世文学への影響
『徒然草』の思想や美意識は、江戸時代を代表する俳人・松尾芭蕉の文学にも影響を与えたと考えられる。芭蕉が追求した「わび・さび」の境地や、無常観、そして自然に対する深い眼差しは、兼好の思想と通底する部分が多い 51 。芭蕉の紀行文『おくのほそ道』などに見られる、旅の中での思索や自然との一体感といったテーマも、『徒然草』の精神性と響き合うものがある 54 。
また、近世の他の文学作品においても、『徒然草』からの引用や、その内容を踏まえた言及が見られることがある。これは、『徒然草』が当時の知識人にとって共有された教養の一部となっていたことを示している。
近代文学者への影響
『徒然草』は、明治以降の近代文学者たちにも大きな影響を与え続けてきた。樋口一葉、小林秀雄、坂口安吾といった多くの作家や批評家が、『徒然草』に言及し、その思想や文体に触発された作品を残している 56 。
例えば、小林秀雄は『徒然草』を高く評価し、その現代的な意義を論じた。また、島内裕子氏は「徒然草文化圏」という概念を提唱し、『徒然草』が単なる古典文学作品としてだけでなく、日本の文化全体に広範な影響を与えてきた様相を明らかにしようと試みている 58 。特に、樋口一葉の文学形成において『徒然草』が果たした役割は、従来あまり注目されてこなかったが、彼女の日記や初期作品の詳細な分析を通じて、その影響の大きさが指摘されている 58 。近代の知識人たちが、『徒然草』をどのように読み解き、それを自らの思想や作品にどのように昇華させていったのかを考察することは、作品の持つ普遍的な魅力と生命力を再確認する上で重要である。
日本美術(絵画、茶道、庭園、建築)における美意識への影響
『徒然草』の影響は文学の領域に留まらず、日本の美術や伝統文化にも及んでいる。江戸時代以降、『徒然草』の各章段を絵画化した絵入版本や絵巻、画帖などが数多く制作された 12 。土佐光起、住吉具慶・如慶、海北友雪といった当代一流の絵師たちが筆を執り、『徒然草』の世界を視覚的に表現した。これらの絵画作品は、『徒然草』が広く愛好され、その内容が人々の心に深く浸透していたことを示している。
また、『徒然草』に示される簡素美、無常観、自然観といった美意識は、日本の伝統文化の核心をなす茶道の「わび・さび」の精神と深く通底している 27 。不完全なものの中に美を見出す感覚や、質素で静寂なものを尊ぶ価値観は、兼好の思想と響き合い、茶の湯の美学形成に影響を与えた可能性が考えられる 61 。
さらに、日本庭園や建築における美意識、例えば自然との調和を重んじる心、非対称性や簡素さを好む傾向、借景といった技法などにも、『徒然草』に描かれた自然観や住まいに対する考え方が間接的に影響を与えていると見ることができる 30 。このように、『徒然草』の美意識は、文学という枠を超えて、日本人の美意識の基層を形成する上で重要な役割を果たしてきたと言えるだろう。
第二章:現代における『徒然草』の価値
現代社会の諸課題(情報過多、人間関係、精神的充足)への示唆
約700年前に書かれた『徒然草』であるが、その内容は現代社会が抱える様々な課題に対しても、驚くほど多くの示唆を与えてくれる。
情報が氾濫し、真偽を見極めることが困難な現代において、『徒然草』が示す本質を見抜く眼差しや、簡潔かつ的確な表現の価値は、改めて見直されるべきである 62 。また、SNSの普及などにより複雑化する人間関係の中で、他者を理解し、良好な関係を築くための知恵も、『徒然草』の中には数多く見出すことができる 19 。例えば、第117段の「友とするに、深き仲らひせんと思はば、その人の長じたる所を見てつくすべし」という言葉は、他者の長所を認め尊重することの大切さを教えてくれる。
物質的な豊かさが追求される一方で、精神的な空虚感やストレスを抱える人々が増えている現代において、『徒然草』が説く心の安らぎや精神的な充足の重要性は、大きな意味を持つ 19 。第75段の「家居、常に静かならんことを思ふべし」という言葉は、騒がしい現代に生きる私たちに、静けさの中で自己と向き合う時間の大切さを教えてくれる。
普遍的テーマ(生き方、死生観、自然観)と現代的メッセージ
『徒然草』が時代を超えて読み継がれる最大の理由は、そこに描かれているテーマが人間にとって普遍的なものであるからだろう。「いかに生きるべきか」という根源的な問いに対し、『徒然草』は様々な角度からヒントを与えてくれる 19 。
死生観についても同様である。死の必然性を受け入れ、限りある命だからこそ「今この瞬間」を大切に生きるべきだというメッセージは、現代人にとっても重く響く 70 。第155段「死期は序を待たず」は、その代表的な章段である。
また、兼好の自然観は、自然の移ろいを愛で、それと共生することの大切さを示唆しており、環境問題が深刻化する現代において、改めてその価値が見直されるべきである 19 。
ミニマリズムや精神的豊かさの観点からの再評価
近年注目されているミニマリズム(最小限主義)の思想とも、『徒然草』は深く共鳴する。兼好が説く簡素な生活のすすめや、物質的なものに過度に執着しない生き方は、現代のミニマリストたちが追求する価値観と通じるものがある 74 。例えば、第123段では「人間の大事、この三つには過ぎず。…この四つの外を求め営むを奢りとす」と述べ、食う物、着る物、居る所に医療を加えた四つ以外を求めることを贅沢としている 9 。
このような物質的な所有に重きを置かない姿勢は、精神的な豊かさを重視する生き方へと繋がる。『徒然草』が示す、内面を見つめ、知的好奇心を満たし、人との交わりや自然との触れ合いの中に喜びを見出すという生き方は、物質的な豊かさだけでは得られない真の幸福とは何かを、現代人に問いかけている 65 。
現代社会における『徒然草』の意義―「足るを知る」生活と「余白」の価値
情報過多で変化の激しい現代社会において、『徒然草』は物質的な豊かさよりも精神的な充足を重視し、「足るを知る」ことの価値や、生活の中に「余白」を持つことの重要性を教えてくれる。これは、現代人が抱えるストレスや空虚感に対する一つの解答となり得る。
現代社会は、常に新しい情報やモノが溢れ、人々はスピードと効率を求められがちである 19 。その結果、多くの人がストレスや精神的な疲弊を感じている。『徒然草』には、簡素な生活を良しとし 9 、過度な欲望を戒める記述が多く見られる。これは、現代のミニマリズムの思想とも共鳴する 74 。
また、兼好は「つれづれなるままに」という序段の言葉に象徴されるように、何もしない時間、思索にふける時間、つまり「余白」の価値を認めている。第75段「家居、常に静かならんことを思ふべし」 7 も、静かで穏やかな生活空間の重要性を示唆している。このような思想は、常に何かに追われ、情報を消費し続ける現代人に対し、立ち止まって自己の内面を見つめ、本当に大切なものは何かを考えるきっかけを与える。
「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」(第137段 19 )という言葉は、完璧さや結果だけを求めるのではなく、過程や不完全さの中にも美や価値を見出すという、より柔軟で豊かな生き方を提示している。これは、成果主義や効率主義に偏りがちな現代社会において、心のバランスを取り戻すための重要な視点である。人間関係においても、第117段「友とするに、深き仲らひせんと思はば、その人の長じたる所を見てつくすべし」 19 のように、他者の長所を認め尊重することの大切さを説いており、希薄になりがちな現代の人間関係に示唆を与える。
『徒然草』は、約700年前の作品でありながら、現代社会が抱える問題に対して驚くほど的確な洞察と処方箋を提示している。物質的な豊かさや効率性だけを追求するのではなく、精神的な充足、簡素な生活、人間関係における思いやり、そして生活の中の「余白」を大切にすることの意義を教えてくれる『徒然草』は、現代人にとって「よく生きる」ためのヒントに満ちた古典と言えるだろう。
おわりに
本報告書は、吉田兼好作『徒然草』について、その成立背景、作者実像、内容、文学的特徴、後世への影響、そして現代における意義を、多角的な視点から詳細に検討してきた。
まず、作者吉田兼好については、伝統的な神官の家系出身という説に加え、近年の研究によって鎌倉武士政権との関わりなど、より複雑な経歴を持つ人物像が浮かび上がってきたことを確認した。彼の思想形成には、仏教(特に無常観)、儒教、老荘思想、そして和歌や平安女流文学といった多様な要素が影響しており、この思想的重層性が『徒然草』の多面的な内容の源泉となっていることを論じた。また、作品が成立した鎌倉末期から南北朝初期という激動の時代背景が、直接的に描かれてはいないものの、作品の根底に流れる無常観や兼好の冷静な観察眼に影響を与えた可能性を指摘した。特に、「書かれなかったこと」の重要性に着目し、それが兼好の文学的スタンスや作品の普遍性に繋がっていることを考察した。
次に、『徒然草』の内容については、全243(または244)段から成る自由な構成と、人生論、無常観、美意識、社会批評、逸話など、極めて多様な主題を扱っていることを明らかにした。代表的な章段の読解を通じて、そこに込められた兼好の思想やメッセージを分析し、特に「無常」の概念を仏教思想から美意識へと昇華させ、後の日本的な美意識の形成に影響を与えた点を強調した。
文学的特徴としては、和漢混淆文と和文の巧みな運用、簡潔性、暗示性、ユーモア、写実性といった表現技法が、作品に深みと魅力を与えていることを論じた。また、日本三大随筆の一つとして、『枕草子』や『方丈記』と比較することで、『徒然草』が「知」を随筆文学の新たな中核に据え、読者との知的対話を促す新たな地平を切り開いた文学史的意義を明らかにした。
後世への影響については、江戸時代における多様な受容と注釈史の展開、松尾芭蕉や近代文学者への影響、さらには日本美術(絵画、茶道、庭園、建築)における美意識への波及を概観した。
最後に、現代における『徒然草』の価値として、情報過多、複雑な人間関係、精神的充足の希求といった現代社会の諸課題に対する示唆や、生き方、死生観、自然観といった普遍的テーマに関する現代的メッセージを考察した。特に、「足るを知る」生活や「余白」の価値を提示する点は、現代人にとって「よく生きる」ための重要なヒントとなり得ることを論じた。
『徒然草』は、時代を超えて読み継がれるべき豊かな内容と普遍的な価値を持つ古典である。本報告書が、その多角的な魅力と意義を再発見するための一助となれば幸いである。今後の『徒然草』研究においては、さらなる史料の発見による兼好の実像の解明、諸外国における受容の比較研究、そして現代社会の具体的な問題群との接続をより深化させることなどが課題として挙げられよう。本報告書が、そうした今後の研究への刺激となることを期待する。
引用文献
- 徒然草 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/tsureduregusa/
- 鎌倉好き集まれ!大佐和さんの鎌倉リポート(第7号) - 鎌倉Today https://kamakuratoday.com/suki/kayanomori/7.html
- 金沢八景に住んでいた吉田兼好 – えのしま・ふじさわポータルサイト https://enopo.jp/2023/07/11/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%85%AB%E6%99%AF%E3%81%AB%E4%BD%8F%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%9F%E5%90%89%E7%94%B0%E5%85%BC%E5%A5%BD/
- 吉田兼倶とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%85%BC%E5%80%B6
- 『徒然草』とその時代 - INSIGHT NOW!プロフェッショナル https://www.insightnow.jp/article/10805
- 徒然草(ツレヅレグサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89-99660
- 徒然草解説 - 日本の古典 https://n-koten.sakura.ne.jp/turezure/index.htm
- 探討古典文學中的無常観--以『方丈記』・『徒然草』為主 https://ndltd.ncl.edu.tw/r/36420986726622364389
- 『徒然草』と仏教のおしえ 河崎清作 https://www.bukkyo-kikaku.com/archive/no134_12.htm
- 老荘思想 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%81%E8%8D%98%E6%80%9D%E6%83%B3
- 嵆康(けいこう) - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0301-072_2.html
- www.nstc.gov.tw https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/84527181-2393-4278-9d9b-b50269333bed
- ﹃徒然草﹄の章段内容と分類 https://www.gakushuin.ac.jp/univ/let/top/publication/KE_66/KE_66_004.pdf
- 第一章 はじめに - 歴史ぱびりよん https://rekisi-pavilion.com/criticism/japanese/kusunoki/640/
- 徒然草|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2408
- 随筆|世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=385
- 徒然草はどんな内容? あらすじや作者について分かりやすく紹介【親子で古典に親しむ】 https://hugkum.sho.jp/367744
- 古典随筆の文章構成に関する試論 一『枕草子』と『徒然草』における章段の内部構成についで http://gendainihongo.sakura.ne.jp/gendainihongo/wp-content/uploads/2019/06/25%E5%8F%B7%EF%BC%92%EF%BC%8F%E5%8F%A4%E5%85%B8%E9%9A%8F%E7%AD%86%E3%81%AE%E6%96%87%E7%AB%A0%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A9%A6%E8%AB%96.pdf
- 徒然草(作者:吉田兼好):日本が誇る随筆文学の魅力と現代的意義 | サクッと解説 https://kick-freedom.com/16749/
- 徒然草 第二十五段 - 徒然草(吉田兼好著・吾妻利秋訳) https://tsurezuregusa.com/025dan/
- 兼好法師の『徒然草』は現代にも通じる教訓の宝庫だった! - ワン ... https://wancamera.com/tsurezuregusa/
- 徒然草 第二百四十三段 - 徒然草(吉田兼好著・吾妻利秋訳) https://tsurezuregusa.com/243dan/
- 【国語】徒然草 - 家庭教師のやる気アシスト https://www.yaruki-assist.com/tips/regular-exam/post-0128/
- 方丈記と徒然草の比較研究 http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1216/1/1104_shionaga_20_28.pdf
- 教材古典と しての「徒然草」について https://ynu.repo.nii.ac.jp/record/1152/files/KJ00004463355.pdf
- 「徒然なるままに」の意味を再発見! 日常に生かす古典の知恵 - Oggi.jp https://oggi.jp/7388229
- 侘び寂びの美学:日本文化が生み出す静寂と調和 - 株式会社文継 https://bun-kei.com/column/wabi-sabi/
- わび・さび - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%B3%E3%83%BB%E3%81%95%E3%81%B3
- 伝統文化における幽玄の美 https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/8238/files/JICS84_P037-066.Hou.pdf
- 第3節 日本人の感性(美意識)の変化 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h30/hakusho/r01/pdf/np101300.pdf
- 欧米(人)における日本庭園の写像 https://ynu.repo.nii.ac.jp/record/1320/files/KJ00004463685.pdf
- 徒然草 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Tradition/LiteratureTsureduregusa.html
- 『徒然草』 の文体は明晰か? - 宇都宮大学 学術情報リポジトリ(UU-AIR) https://uuair.repo.nii.ac.jp/record/4152/files/KJ00004510064.pdf
- 古典への招待 【第81回:弥次郎兵衛・北八論】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_81.html
- 体露金風 西芳寺 第七景ピーター・J・マクミラン(翻訳家・詩人) | into Saihoji https://intosaihoji.com/journal/100007/
- 能と「伝説」 石井 正己 - 日本口承文芸学会 https://ko-sho.org/download/K_019/SFNRJ_K_019-07.pdf
- 徒然草 題名の由来 - 古典の改め https://classicstudies.jimdofree.com/%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89/%E9%A1%8C%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%94%B1%E6%9D%A5/
- 【徒然草の内容解説】700年前の人生観とは?「徒然草」が描く価値観 | 家庭教師ファースト https://www.kyoushi1.net/column/other-trivia/tureduregusa/
- お灸が『徒然草』に - せんねん灸 https://www.sennenq.co.jp/blog/tureduregusa/
- 講義余話 - 河地修ホームページ https://www.o-kawaji.info/class/yowa/20170130.html
- 徒然草 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89
- 枕草子のジャンルは?世界最古の随筆文学 - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/hikarukimihe/makuranososhi-genre/
- 【AI動画】日本三大随筆をわかりやすく解説! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7Xe9GLdcT-0
- 『徒然草』における「あはれ」の現れ方 - 学習院大学学術成果リポジトリ https://glim-re.repo.nii.ac.jp/record/4841/files/kokugokokubungaku_63_61_76.pdf
- 『徒然草』~三大随筆との比較。 | 菊蔵の「旅は京都、さらなり」(旅と歴史ブログ) https://ameblo.jp/blogbears/entry-11277931522.html
- 『日本近世書物文化史の研究』 横田冬彦著 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/publications/public-relations/shishonodeban/2022/10/post-445.html
- 徒然草古注釈書の方法⁝−﹃徒然草寿命院抄﹄ https://ouj.repo.nii.ac.jp/record/7428/files/NO_18-206-188.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyotogakuen/10/1/10_1_1/_pdf
- 『徒然草』と本居宣長 - -青年期の受容と晩年の批判 - 上越教育大学リポジトリ https://juen.repo.nii.ac.jp/record/4923/files/hyogokyoikujissen8-85.pdf
- 『徒然草』と本居宣長-青年期の受容と晩年の批判 - 兵庫教育大学 https://www.hyogo-u.ac.jp/rendai/assets/images/media/view-id=1101&type=thumbnail&site=18_.pdf
- #全文公開 『現代エッセイ訳 徒然草 - すらすら読めて、すっきりわかる -』著:山口謠司|ワニブックスの電子書籍 - note https://note.com/digi_wani/n/n04652e13ddbc
- 江戸時代の日本文化と自然観 - 京都産業大学 学術リポジトリ https://ksu.repo.nii.ac.jp/record/10772/files/BIJCKSU_27_444.pdf
- おくのほそ道「漂泊の思ひ」・松尾芭蕉 - DCP https://dcp.co.jp/meikaits/2020/09/11/%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%AE%E7%B4%B0%E9%81%93%E3%80%80%E6%BC%82%E6%B3%8A%E3%81%AE%E6%80%9D%E3%81%B2/
- 芭蕉の人間像から読み解く『おくのほそ道』 - 奈良教育大学学術リポジトリ https://nara-edu.repo.nii.ac.jp/record/11910/files/CERD2013-H15.pdf
- 『おくのほそ道』と岩沼 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kanko/rekishi/nyumon/okunohosomichi.html
- 徒然草』における「まことの人 - 日本思想史学会 https://ajih.jp/backnumber/pdf/01_02_02.pdf
- 『徒然草』における有職故実的章段の研究 : 『中外抄』『富家語』を視野において https://omu.repo.nii.ac.jp/record/5064/files/2014300140.pdf
- 学位論文要旨詳細 - 東京大学 http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/gazo.cgi?no=217216
- 「絵巻で見る・読む 徒然草」 鎌倉時代の随筆を、江戸絵巻と共に楽しむ - くまねこ堂 https://www.kumanekodou.com/tayori/23451/
- 日本の美意識 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/144444241.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/75/0/75_23/_pdf
- 学ぶ意義を見いだす古典学習指導 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/109557/AN10088945-51-P001.pdf
- 語句・文脈の解説と脚問・発問(「徒然草 花は盛りに」) - 三省堂教科書 https://tb.sanseido-publ.co.jp/kokugo/hKokugo/25TB/pdf/25SANSEIDO_SeisenKokugoSogo_05.pdf
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/59/11/59_11_49/_pdf
- 卒業論文|哲学科 - 専修大学 https://www.senshu-u.ac.jp/education/faculty/letters/philosophy/paper.html
- 学術広報誌『こころの未来』|京都大学こころの未来研究センター - 京都大学 人と社会の未来研究院 https://ifohs.kyoto-u.ac.jp/jp/kokoronomirai/
- 方丈記(作者:鴨長明)の魅力と概要:鎌倉時代の名作から学ぶ人生の真理 | サクッと解説 https://kick-freedom.com/16746/
- 【葉隠解説】江戸の武士が教える生き方の極意――初心者のための『葉隠』入門書 - note https://note.com/kounkt/n/nf4dbc4e0bd9e
- ヘタな人生論より徒然草 | 荻野 文子 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E3%83%98%E3%82%BF%E3%81%AA%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%AB%96%E3%82%88%E3%82%8A%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89-%E8%8D%BB%E9%87%8E-%E6%96%87%E5%AD%90/dp/4309014739
- 研究者詳細 - 本村 昌文 https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/staff/motomura_masafumi/
- 卒業論文題目 - 聖心女子大学哲学科・大学院哲学専攻 https://philosophy.fla.u-sacred-heart.ac.jp/manabi/titlelist
- 第一章 日本人の美の倫理 https://utsukushii-nihon.themedia.jp/pages/715175/page_201611041511
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/58/7/58_7_57/_pdf
- 教授・宮﨑裕助|哲学科 - 専修大学 https://www.senshu-u.ac.jp/education/faculty/letters/philosophy/teacher/miyazaki.html
- 日本の「美意識」や「美の概念」説明できますか?「あはれ」「侘び寂び」「かわいい」などの概念を紹介 | 太鼓日和 https://magazine.wadaiko-kohasu.com/traditional/461/
- 倫理|日本思想 - 問答庫 https://mondouko.com/article/all/all/a0056
- 吉田兼倶と天台本覚思想 https://mu.repo.nii.ac.jp/record/1037/files/Bukkyoken35T-3.pdf