東方見聞録
『東方見聞録』のジパング伝説は、大航海時代を駆動。マルコ・ポーロは日本未訪で伝聞に基づく。日本は「銀の国」と認識され、イエズス会宣教師が詳細な報告をもたらした。
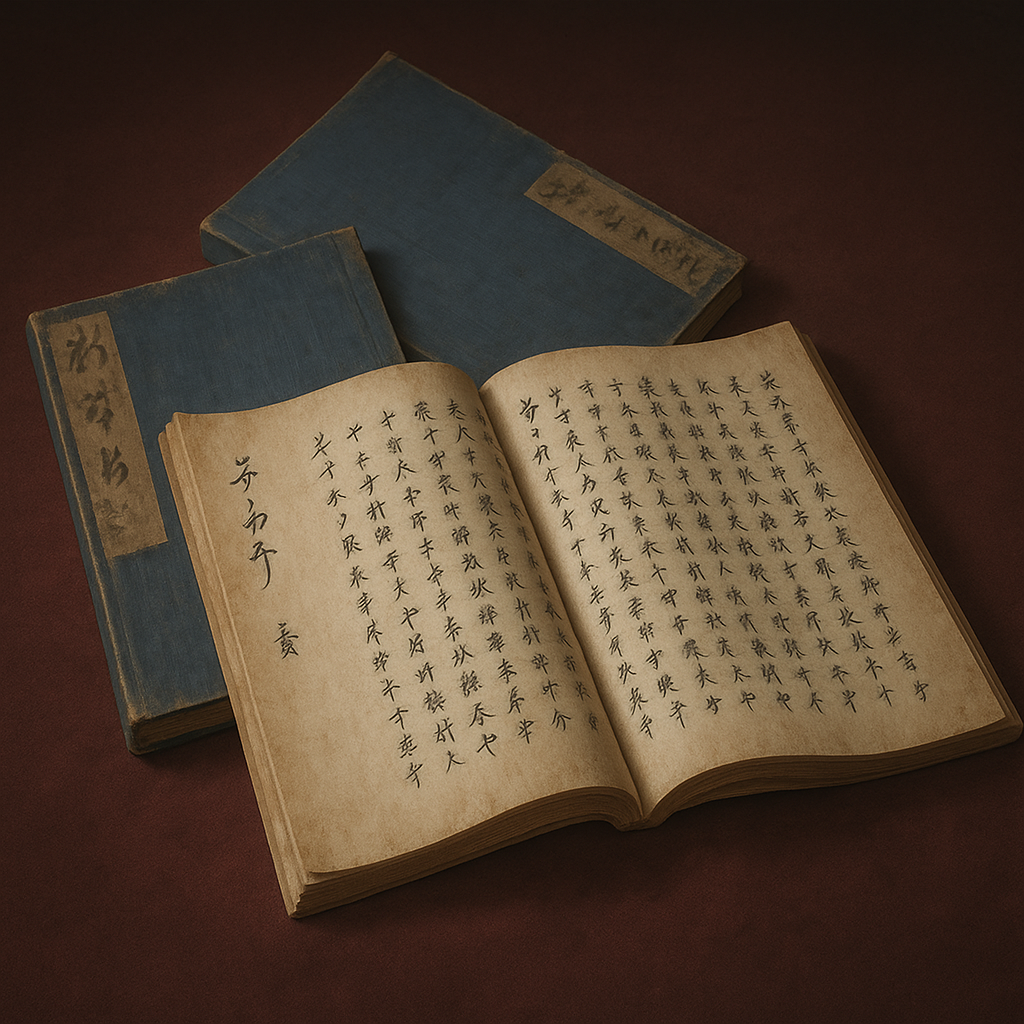
『東方見聞録』と戦国日本 ― 「黄金の国ジパング」の神話、その受容と変容
序論:『東方見聞録』と「黄金の国」伝説の誕生
13世紀末に成立したマルコ・ポーロの旅行記、通称『東方見聞録』は、ヨーロッパ人の世界観を根底から揺るがし、その後の歴史に計り知れない影響を及ぼした書物である。特に、本書が初めてヨーロッパに紹介した「ジパング」、すなわち日本に関する記述は、黄金に満ちた楽園として人々の想像力を掻き立て、大航海時代の幕開けを促す遠因となった。しかし、この書物が描くジパング像は、マルコ・ポーロ個人の純粋な見聞の記録ではなく、特定の時代背景と人的要因が複雑に絡み合って生まれた「合作」の産物であった。本報告書は、「日本の戦国時代」という歴史的文脈をプリズムとして『東方見聞録』を多角的に分析し、一個の「神話」がいかにして生まれ、受容され、そして日本の「現実」と衝突することで変容していったかの全貌を解明することを目的とする。
マルコ・ポーロの旅と元の実情
ヴェネツィアの商人マルコ・ポーロは、1271年に父ニコロと叔父マッフェオに同行して東方への大旅行に出発した 1 。彼の旅路はペルシャからパミール高原を越え、1295年にヴェネツィアに帰還するまで、実に四半世紀近くに及んだ 3 。この旅の大部分は、モンゴル帝国(元)の支配下で過ごされた。当時、フビライ・ハンの治める元は、西はハンガリーから東は朝鮮半島に至る、史上類を見ない広大な領域を誇る世界帝国であり、その宮廷は多様な民族と情報が集積する国際的な中心地であった 5 。マルコ・ポーロがフビライに重用され、帝国の各地に使節として派遣された経験は、彼にアジアに関する膨大な知識をもたらした。
ジェノヴァの牢獄にて:ルスティケロ・ダ・ピサとの共同作業と成立の経緯
マルコ・ポーロの驚異的な体験談が書物として結実したのは、意外な場所であった。帰国後の1298年、故国ヴェネツィアと敵対するジェノヴァとの海戦で捕虜となった彼は、ジェノヴァの牢獄に収監される 1 。そこで彼は、同じく捕虜となっていたピサ出身の物語作家、ルスティケロ・ダ・ピサと運命的な出会いを果たす 3 。マルコが自らの東方での見聞を口述し、それを当代随一の騎士道物語(アーサー王伝説など)の書き手として知られたルスティケロが、イタリア語訛りの古フランス語で筆記・編纂するという共同作業によって、本書は誕生した 4 。
この成立過程は、本書の性格を理解する上で極めて重要である。語り手である商人マルコ・ポーロの体験談は、聞き手であり書き手である物語作家ルスティケロの筆を通して再構成された。ルスティケロは単なる客観的な記録者ではなく、読者の心を捉える物語の専門家であった 8 。そのため、彼の編纂過程において、事実の誇張、劇的な構成の採用、あるいは当時の文学における約束事(トポス)の挿入が行われた可能性は高い。したがって、『東方見聞録』(原題は『世界の記述』など複数あり、特定されていない 3 )は、純粋な「見聞録」であると同時に、色濃い「文学作品」としての性格を帯びていたのである。
「ジパング」記述の源泉:伝聞情報の複合的構築
本書における日本、すなわち「ジパング」に関する記述は、後世に最も大きな影響を与えた部分の一つであるが、マルコ・ポーロ自身は日本を訪れていない 9 。記述のすべては、彼が元の宮廷や泉州のような中国南部の国際貿易港で、商人や船乗りたちから聞き集めた伝聞情報に基づいている 2 。
「ジパング(Cipangu)」という名称自体、当時の中国語における「日本国」の発音(「ジーベンゴオ」などに由来すると考えられている 9 。その内容は、事実と想像が巧みに織り交ぜられている。
- 黄金の宮殿 : 「君主の宮殿は屋根がすべて純金で葺かれ、床や窓さえも黄金でできている」という有名な記述の源泉は、平安時代末期に奥州藤原氏が建立した中尊寺金色堂の壮麗さが、中国商人などを介して著しく誇張されて伝わったものとする説が有力である 2 。
- 豊富な金 : 日本が莫大な金を産出するというイメージは、古くは遣隋使の時代から、日本の使節団が渡航や滞在の費用として砂金を持参していた事実が、中国において日本を豊かな産金国と見なす認識を形成したことに起因する可能性がある 4 。
- その他の記述 : 住民が「偶像崇拝者」(仏教徒)であることや、死者を火葬または土葬にする風習など、当時の日本の実情と合致する記述も散見される 10 。一方で、「捕らえた外国人を身代金が取れない場合に食べてしまう」といった食人文化の記述 2 や、豊富な「香辛料」に関する言及 12 は、事実とは異なる。これらは、当時のヨーロッパ人が東方の未知の島々に対して抱いていた紋切り型のイメージや、他の地域の情報との混同、あるいは聞き伝えの過程での誤解が反映されたものと考えられる 15 。
特筆すべきは、これらの記述が内包する矛盾である。ジパングの民は「色白で礼儀正しい」 14 と描写される一方で、食人の習慣を持つ野蛮な存在としても描かれている。この富と野蛮、文明と未開という相容れない要素の共存こそが、ジパングを単なる豊かな国ではなく、ヨーロッパ人の理解を超えた神秘的な「幻の島」として強く印象づける要因となった。このアンビバレントなイメージは、後の探検家たちにとって、富を求める探求の対象であると同時に、教化し征服すべき対象として、二重の魅力を放つことになったのである。
写本系統による記述の差異と信憑性を巡る学術的議論
『東方見聞録』の複雑さをさらに増しているのが、そのテキストの流動性である。原本は早くに散逸し、現在では138種以上もの写本がヨーロッパ各地に現存している 4 。これらは大きく二つのグループ、七つの系統に大別される。最も原本に近いとされる古フランス語で書かれた「F系統」(フランス語地理学協会版など)と、F系統には見られない記述を多数含むラテン語の「Z系統」(セラダ版)などがその代表である 4 。
写本ごとに章の欠落や追加、記述内容の細かな差異が見られ、どの写本を「正本」と見なすかによって、マルコ・ポーロが語った内容の解釈も変わってくる。この異本の多さは、本書が中世を通じていかに広く読まれ、筆写される過程で変容を重ねていったかを物語っている。本書の信憑性を巡る議論は、単に「マルコ・ポーロは中国へ行ったか否か」という二元論に留まるものではない。むしろ、どの記述がマルコ本人の口述に由来し、どれが編者ルスティケロや後代の筆写生による加筆・改変なのかを特定しようとする、緻密な文献学的探求の対象となっている。特にジパングのように、マルコ自身が訪れていない伝聞に基づく箇所は、写本が作成される過程で最も変容しやすかった部分であろう。このテキストの不安定さこそが、本書が後世に与えた影響を考察する上での重要な前提条件となるのである。
第一部:ジパングの幻影 ― 大航海時代を駆動した黄金の夢
『東方見聞録』に記されたジパングの物語は、中世末期のヨーロッパにおいて、単なる異国の珍談奇聞として消費されるに留まらなかった。それは人々の想像力を捉え、やがて探検家たちを未知の海洋へと駆り立てる具体的な「目標」へと昇華していった。本章では、ジパングの幻影が、いかにして大航海時代という歴史的事業を駆動する力となったのか、そのプロセスを検証する。
1.1. ヨーロッパにおける『東方見聞録』の受容と伝播
15世紀半ばの活版印刷技術の発明は、『東方見聞録』の伝播に決定的な役割を果たした。それまで一部の知識層や富裕層に限られていた写本が、印刷物として大量に生産されるようになると、本書はヨーロッパの幅広い読者層に届けられることになった 3 。東方の未知なる世界、壮麗な元の宮廷、そして何よりも「黄金の国ジパング」の物語は、ヨーロッパ人の東方への関心を爆発的に増大させた 19 。
当時、ヨーロッパは東方との交易、特に香辛料貿易をイスラム商人やヴェネツィア、ジェノヴァといったイタリアの都市国家に独占されていた。この状況を打破し、新たな富の源泉を求めるポルトガルやスペインといった新興海洋国家の王侯貴族や商人たちにとって、『東方見聞録』が描くジパングは、まさに夢の地であった 10 。ジパングは、現実の経済的閉塞感を打ち破る希望の象徴、富と未知への憧れが投影された一種のユートピアとして、熱狂的に受容されたのである 10 。
1.2. コロンブスの航海計画:『東方見聞録』への書き込みとトスカネリの世界図
このジパング熱に最も深く魅了された人物の一人が、ジェノヴァ出身の航海者クリストファー・コロンブスであった。彼は『東方見聞録』の愛読者であり、彼が所有していたフランチェスコ・ピピーノによるラテン語訳版(P系統写本)には、実に366箇所ものびっしりとした書き込みが残されている 4 。
その書き込みの内容を分析すると、コロンブスの関心の在りかが明確に浮かび上がる。彼は、本書に記された地誌や民族、歴史に関する情報にはほとんど注意を払っていない。彼の関心は、金、真珠、宝石、香辛料といった、具体的かつ物質的な価値を持つ「富」にほぼ限定されていた 24 。彼は本書を、東方の富のありかを記した一種の宝の地図として読んでいたのである。
コロンブスの計画を理論的に後押ししたのが、フィレンツェの地理学者パオロ・ダル・ポッツォ・トスカネリが作成した世界図であった 25 。地球球体説に基づいていたこの地図は、ヨーロッパから西へ航海すれば、アジア東岸、すなわちジパングに到達可能であることを示唆していた 26 。しかし、この地図は地球の周長を実際よりも25%ほど小さく見積もり、アジア大陸を東方へ大きく引き伸ばして描いていたため、ジパングは現実の日本の位置よりも遥か東、現在のメキシコ沖あたりに位置づけられていた 26 。
コロンブスは、このトスカネリの地図と『東方見聞録』の記述を分かちがたく結びつけ、西回り航路によるジパング到達こそが、アジアの富へ至る最短経路であると確信した。彼はこの壮大な計画を携えてスペイン女王イサベルを説得し、前代未聞の航海への支援を取り付けることに成功するのである 20 。
この一連の経緯は、人間心理における「確証バイアス」の働きを如実に示している。コロンブスは、自らの信念、すなわち「西へ行けばジパングに到達できる」という仮説を補強する情報(『東方見聞録』の黄金伝説、トスカネリの地図)を選択的に信奉し、それと矛盾する情報(当時存在した、より正確な地球の大きさの推定値など)を無視、あるいは過小評価した。彼はジパングの存在を疑うことなく前提とし、そこへ至る航路を「発見」することに全精力を傾けた。1492年、彼が率いる船団がカリブ海の島々に到達した際、そこで目にした先住民が身に着けていたわずかな金の装飾品を見て、その地がジパングの周辺に違いないと固く信じ込んだのは、この強力なバイアスが彼の認識を支配していたことの証左である 21 。結果としてアメリカ大陸に到達した彼の航海は、歴史を大きく動かす「偉大な発見」となったが、その動機は、ジパングという「神話」を追い求めた末の「偉大な誤算」であったと言えるだろう。
1.3. 地図上のジパング:幻想から地理的特定への変遷
大航海時代の幕開けと共に、地図製作は飛躍的な発展を遂げたが、その初期の地図における日本の姿は、依然として『東方見聞録』の幻影に強く支配されていた。15世紀から16世紀初頭にかけて製作された世界地図では、ジパングはアジア大陸の遥か東方に浮かぶ巨大な島として、しばしば想像たくましく描かれた 25 。その形状や大きさ、位置は製作者によってまちまちであり、地理的情報というよりは伝説の可視化といった趣が強かった。
しかし、1543年のポルトガル人の日本漂着を契機に、状況は徐々に変化し始める。実際に日本を訪れた商人や宣教師たちがもたらす断片的ながらも現実的な情報が、ヨーロッパの地図製作者たちのもとへ届くようになったのである。アブラハム・オルテリウスやゲラルドゥス・メルカトルといった当代一流の地図製作者たちは、これらの新しい情報を自らの地図帳に反映させ、日本の形状を少しずつ修正していった 29 。
この変遷における画期となったのが、1595年にオルテリウスの地図帳『世界の舞台(Theatrum Orbis Terrarum)』に初めて収録された、日本単独の地図であった 30 。この地図は、イエズス会の情報網を通じてポルトガルの地図製作者ルイス・テイシェラが作成した原図に基づくものであり、それまでのどの地図とも比較にならないほどの詳細さと正確さを備えていた 30 。本州、九州、四国といった主要な島々が明確に描き分けられ、日本の地理的輪郭が初めてヨーロッパの地図上に現実的な姿で現れたのである。
この16世紀を通じた日本図の変遷は、ヨーロッパの情報収集能力の進化そのものを映し出している。当初はマルコ・ポーロのテキスト情報という二次情報に全面的に依存していたものが、次第に航海者による沿岸測量図(ポルトラーノ)という一次情報が加わり、最終的には、日本社会の内部にまで深く浸透したイエズス会という組織的な情報ネットワークからもたらされる、体系的な地理情報へと情報源の質が劇的に向上していった。これは、ヨーロッパにおける日本認識が、「伝説」から「実測」へと移行する不可逆的なプロセスであった。こうして、地図上の「ジパング」は、ようやく現実の「日本」の姿へと収斂していったのである。
【表1:『東方見聞録』の主要写本系統とジパング記述の比較】
|
写本系統 |
主要言語 |
成立年代(推定) |
特徴 |
ジパングに関する特記事項 |
|
F系統 (フランス語地理学協会版) |
古フランス語 |
14世紀初頭 |
最も原本に近いと考えられている。ルスティケロの名前が明記されている 4 。 |
黄金の宮殿、豊富な金と真珠、偶像崇拝、元寇に関する詳細な記述が含まれる 6 。 |
|
P系統 (ピピーノのラテン語版) |
ラテン語 |
1302年以降 |
ドミニコ会修道士によるラテン語訳。分量は最も短く、広く流布した 4 。コロンブスが所持していた版 4 。 |
黄金伝説の核心部分は含まれるが、F系統に比べて記述は簡略化されている傾向がある。 |
|
Z系統 (ラテン語セラダ版) |
ラテン語 |
不明(1932年発見) |
F系統にはない宗教・民族誌的な記述が200箇所以上追加されている 4 。 |
F系統の記述に加え、より詳細な、あるいは異なる伝承が含まれている可能性があり、研究上の重要性が高い。 |
|
R系統 (ラムージオのイタリア語版) |
イタリア語 |
1559年(出版) |
P系統を底本としつつ、Z系統や他の写本の記述を集成した増補版 4 。 |
複数の系統の情報を統合しており、ジパングに関する様々な伝承が混在している可能性がある。 |
第二部:幻影との邂逅 ― 戦国時代の日本における「南蛮」との接触
『東方見聞録』が描いたジパングの幻影を胸に、ヨーロッパ人(南蛮人)はついに日本の地に足を踏み入れた。しかし、彼らがそこで目の当たりにしたのは、黄金に輝く宮殿ではなく、群雄が割拠し、絶え間ない戦乱に明け暮れる戦国時代の日本の厳しい現実であった。本章では、この幻影と現実の衝突が、ヨーロッパ人の日本認識をいかに根本から塗り替えていったかを検証する。特に、経済的実像の発見(「金」から「銀」へ)と、イエズス会による体系的な情報収集がもたらした認識の転換に焦点を当てる。
2.1. 1543年、種子島:ポルトガル人の漂着と最初の接触
日欧間の歴史的な邂逅は、1543年、一隻の中国船に同乗していたポルトガル商人が、嵐によって日本の南端、種子島に漂着したことから始まった 32 。彼らがもたらしたものは、黄金でも宝石でもなく、数丁の火縄銃であった。
この偶然の出会いは、その後の日本の歴史に決定的な影響を与えた。当時、日本は応仁の乱以来、100年近く続く戦国乱世の真っ只中にあった。全国の戦国大名たちは、自らの領国を拡大し、天下の覇権を握るために、より強力な軍事力を渇望していた。そこに突如として現れた鉄砲は、従来の弓矢や刀槍を中心とした戦術を一変させる可能性を秘めた、まさに革命的な兵器であった 32 。種子島領主・時堯がただちに鉄砲を購入し、その複製を命じた逸話は、当時の日本の支配者層がこの新技術に対していかに敏感であったかを物語っている。
この最初の接触が、黄金伝説の探求ではなく、実用的な軍事技術の導入から始まったという事実は象徴的である。それは、これ以降の日欧関係が、一方的な神話的憧れによってではなく、日本の軍事技術への渇望と、ヨーロッパの新たな貿易利権獲得への渇望という、双方の極めて現実的な利害によって駆動されていくことを予示していた。
2.2. 「黄金の国」から「銀の国」へ:石見銀山と南蛮貿易の経済的実像
ジパング伝説を信じて来航したポルトガル人やスペイン人たちが、日本の地で発見したのは、黄金の宮殿ではなかった。その代わりに彼らが発見したのは、世界史的な規模で流通するほどの莫大な銀を産出する、もう一つの「豊かな国」の姿であった。
16世紀の日本は、世界有数の銀産出国であり、特に山陰地方に位置する石見銀山は、その産出量において群を抜いていた 33 。一説には、16世紀後半の世界の銀産出量のおよそ3分の1が日本産であったとも言われる 36 。この豊富な銀は、当時の世界経済、特に東アジアの交易において絶大な価値を持っていた。隣国である明(中国)が、税制改革によって銀を主要な決済手段として採用していたため、銀に対する巨大な需要が存在したからである 37 。
しかし、当時の日明間には倭寇問題などを背景に公式な国交がなく、直接的な交易は制限されていた。この政治的・経済的な「歪み」に目を付けたのがポルトガル商人であった。彼らは、この間隙を縫う形で、日中間の仲介者として振る舞った。南蛮貿易の基本的な構造は、ポルトガル商人がマカオを拠点として中国産の良質な生糸や絹織物を日本に運び、その対価として日本から銀を獲得し、その銀を再び中国に持ち込んで莫大な利益を上げるという、三国間の中継貿易であった 33 。日本を目指すポルトガル船が、いつしか「銀の船(nau das pratas)」と呼ばれるようになったことからも 36 、この貿易における日本の銀の重要性が窺える。
この経済的現実の発見は、ヨーロッパ人の日本観を根底から変えた。「黄金の国」という伝説は、完全に否定されたわけではない。むしろ、日本の「富」の源泉が、神話的な「金」から、現実的で取引可能な「銀」へと「再定義」されたと見るべきである。この再定義は、ヨーロッパの世界戦略に大きな影響を与えた。略奪や探求の対象であった幻想の「黄金の国」は、グローバルな交易ネットワークにおける不可欠な「銀の供給地」へと姿を変えた。日本の価値は、より現実的かつ戦略的なものへと転換し、これこそがヨーロッパ諸国、とりわけポルトガルが、多大なコストとリスクを冒してまで日本との関係を維持・深化させようとした最大の動機となったのである。
2.3. イエズス会宣教師の報告:ザビエル、フロイス、ヴァリニャーノらによる新たな日本像
南蛮貿易が経済的な側面から日本の実像を明らかにしたとすれば、その文化や社会、政治の深層をヨーロッパに伝えたのは、イエズス会の宣教師たちであった。1549年に鹿児島に上陸したフランシスコ・ザビエルを皮切りに、多くの宣教師が日本を訪れ、布教活動の傍ら、日本のあらゆる事象に関する詳細な報告書を、ローマやゴアの拠点へと送り続けた 18 。
これらの報告書は、マルコ・ポーロの伝聞に基づく漠然とした記述とは比較にならないほど、具体的で、体系的で、そして分析的であった。それは、ヨーロッパ人の日本観を、神話のレベルから現実のレベルへと引き下ろし、再構築する上で決定的な役割を果たした。
- ルイス・フロイス : 織田信長や豊臣秀吉といった天下人と直接的な交流を持ち、30年以上にわたって日本に滞在したフロイスは、その見聞を大著『日本史』としてまとめた 42 。彼は、日本の支配者層が持つ合理的な精神性、武士の誇り高い気風、そしてヨーロッパとは根本的に異なる社会規範や風俗を、驚きと共感を交えながら克明に記録した。
- アレッサンドロ・ヴァリニャーノ : イエズス会東インド巡察師として来日したヴァリニャーノは、それまでの一部の宣教師に見られたヨーロッパ中心主義的な布教方針を批判し、日本の文化や習慣への「適応主義」を強力に推進した 45 。彼は、日本人をヨーロッパ人と対等な知性を持つ民族として高く評価する一方、その文化の特異性も鋭く指摘した 48 。また、天正遣欧少年使節を企画・派遣し、ヨーロッパの王侯貴族やローマ教皇に日本の若者たちを謁見させることで、日本の存在を政治的・文化的に直接ヨーロッパに知らしめた 49 。
彼らの報告書に描かれた日本人は、もはや黄金の宮殿に住む素朴な民ではない。それは、武具を金銀で飾ることを誇りとし 51 、名誉を重んじ、極めて礼儀正しい一方で、外国人に対しては侮蔑的な態度をとることもある、誇り高く複雑な人々であった 51 。
イエズス会は、単なる宗教団体ではなく、高度な情報収集・分析能力を持つ国際的な組織であったと評価できる。彼らが作成した書簡や報告書は、個人の感想を綴った旅行記ではなく、布教戦略の立案、人材育成、そして本国からの資金調達といった組織的な目的のために書かれた、極めて戦略的な「インテリジェンス・レポート」としての性格が強い 18 。この組織的かつ体系的な情報収集活動によって、マルコ・ポーロの時代には到底不可能であった、多角的で深層的な日本理解が初めて可能となった。その結果、「ジパング」の神話は急速に解体され、より複雑で現実的な「日本」像がヨーロッパの知識層の間に構築されていったのである。
【表2:マルコ・ポーロとイエズス会宣教師による日本記述の比較】
|
比較項目 |
マルコ・ポーロの記述(『東方見聞録』より) |
イエズス会宣教師の記述(フロイス『日本史』などより) |
|
統治者の宮殿 |
屋根、床、窓がすべて純金でできている 4 。 |
(信長の安土城など)金箔瓦や金碧障壁画で豪華に飾られているが、建物自体が純金製ではない。権威の象徴として金が用いられている 52 。 |
|
富の源泉 |
莫大な量の金。国外に持ち出されないため有り余っている 6 。 |
世界有数の産出量を誇る銀。南蛮貿易の主要な輸出品として世界経済に流通している 34 。 |
|
人々の気質 |
色白で礼儀正しい 14 。一方で、捕虜を食べる習慣があるとも記され、矛盾している 12 。 |
誇り高く、名誉を重んじ、武勇に優れる。互いに礼儀正しいが、外国人を見下す傾向がある。好奇心旺盛で理知的 48 。 |
|
宗教 |
偶像崇拝者である 14 。 |
神道と仏教が広く信仰されている。特に仏教勢力は強大な政治的・軍事的影響力を持つ(僧兵、一向一揆など) 42 。 |
|
軍事力 |
元の侵攻(元寇)を撃退したことが記されているが、詳細は伝聞に基づく 17 。 |
鉄砲を短期間で国産化し、戦術に組み込むなど軍事技術への適応力が高い。武士階級は常に武装し、戦闘を常としている 32 。 |
第三部:戦国大名とジパングの遺産 ― 織田信長、豊臣秀吉の視点
ヨーロッパ人がジパングの幻影を追い求めて日本へ到達した一方で、日本の支配者たちは、突如として現れた「南蛮人」とその背後にあるヨーロッパ世界をどのように認識し、自らの戦略に組み込んでいったのだろうか。本章では、視点を日本側に移し、戦国時代の天下人たちが、決して受動的な存在ではなく、南蛮人との接触を自らの覇権争いにおける重要な要素として、主体的かつ戦略的に利用していた実態を分析する。
3.1. 織田信長の合理主義:宗教勢力への対抗策としてのキリスト教容認
天下布武を掲げ、旧来の権威や秩序を次々と破壊していった織田信長にとって、南蛮人との出会いは、まさに時宜を得たものであった。彼の最大の敵の一つは、既存の仏教勢力、とりわけ全国に強固な信徒組織と武装を持ち、彼の支配に真っ向から抵抗した浄土真宗本願寺派(一向宗)であった 53 。石山合戦に代表される一向一揆との10年にも及ぶ死闘は、信長に宗教勢力が持つ政治的・軍事的パワーの恐ろしさを痛感させた。
イエズス会宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、信長は神仏や来世といった超自然的な存在を信じない、極めて合理主義的な思考の持ち主であったとされる 42 。彼にとって、イエズス会がもたらしたキリスト教は、信仰の対象というよりも、憎き仏教勢力に対抗するための有効な政治的・思想的カウンターウェイト(対抗勢力)と映った。彼はキリスト教を保護し、宣教師に布教の自由を与えることで、仏教勢力の権威を相対化し、その力を削ごうとしたのである 36 。
同時に、信長は南蛮貿易がもたらす経済的・軍事的利益も見逃さなかった。鉄砲の威力を最大限に活用した彼の軍団にとって、その弾薬の原料となる硝石は不可欠な戦略物資であり、南蛮貿易はその主要な供給源であった 36 。信長のキリスト教保護政策は、宗教的寛容さからではなく、極めて冷徹な政治的・経済的合理性に基づいていた。
この信長の合理性と権力志向を象徴するのが、彼が築いた居城・安土城である。天主の最上層には金箔瓦が葺かれ、内部は狩野永徳による金碧障壁画で豪華絢爛に飾り立てられた 52 。これは、彼が既存のいかなる権威(天皇、将軍、寺社勢力)にも屈しない、新たな時代の絶対的支配者であることを、視覚的に天下に誇示するための壮大な政治的パフォーマンスであった。
興味深いことに、信長がこの「黄金の城」を築いたのは、もちろんマルコ・ポーロの記述を知っていたからではない。しかし、結果として彼は、ヨーロッパ人が遥か東方に夢見た「黄金の宮殿」のイメージを、奇しくも日本の地で部分的にではあるが具現化して見せたのである。これは歴史の皮肉と言えよう。ヨーロッパ人が黄金の神話を求めて日本に来航したまさにその時代に、日本の新たな支配者は、自らの権力を誇示するために「黄金」というシンボルを最大限に政治利用していた。この偶然の一致は、時代や文化圏を超えて、権力者が「黄金」という素材に絶対的な富と権威という普遍的な価値を見出していたことを示唆している。
3.2. 豊臣秀吉の警戒:伴天連追放令と天下統一事業における南蛮認識の変化
信長の後を継ぎ、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉も、当初は信長の方針を踏襲し、南蛮貿易を奨励した。しかし、彼の南蛮認識は、天下統一事業の進展と共に劇的に変化していく。
転機となったのは、1587年の九州平定であった。この遠征の過程で、秀吉はキリシタンに改宗した大名が、領内の寺社を組織的に破壊している実態や、貿易港である長崎の地がイエズス会に寄進され、治外法権的な領域となっている事実を目の当たりにする 59 。さらに、ポルトガル商人が多くの日本人を奴隷として買い付け、海外へ売却しているという報告も、彼の警戒心を強める要因となった。秀吉は、キリスト教の無制限な拡大が、自らが築き上げようとしている統一的な支配体制を根底から揺るがしかねない、深刻な脅威であると判断したのである 36 。
この危機感から、秀吉は同年に「伴天連追放令」を発布する。この法令は、宣教師の国外退去を命じる一方で、貿易のためのポルトガル商船の来航は引き続き許可するという、二面性を持っていた 59 。これは、キリスト教の布教(宗教)と南蛮貿易の利益(経済)を切り離して管理しようとする、秀吉の巧みな政治判断を示すものであった。
秀吉の政策転換の根底には、単なる政治的計算だけではない、より深い思想的な対立があった。追放令の中で、秀吉は「日本は神国たる処」と明記し、キリスト教を日本の伝統的な価値観と相容れない「邪法」と断じている 59 。信長が既存の宗教秩序を破壊するための「道具」としてキリスト教を捉えたのに対し、天下を統一し、新たな支配秩序を構築しようとした秀吉にとって、唯一絶対神を掲げ、既存の神仏を否定するキリスト教の教義は、自らの支配の正統性を脅かす「危険思想」そのものであった。この支配イデオロギーの根本的な衝突こそが、信長と秀吉の対南蛮政策を分かつ決定的な分岐点となったのである。
3.3. 九州大名(大友氏、大村氏など)の戦略:貿易の利益と領国経営
信長や秀吉といった中央の天下人が、日本全体の秩序というマクロな視点から南蛮人との関係を捉えていたのに対し、南蛮船が直接来航する九州の諸大名にとって、それは領国の存亡に直結する、より切実でミクロな問題であった。
豊後の大友宗麟や肥前の大村純忠といった大名にとって、南蛮貿易は、領国に莫大な富をもたらし、その財力で軍備を増強し、毛利氏や島津氏といった強大なライバルと渡り合うための生命線であった 62 。彼らは、自らキリスト教に改宗し、領内での布教を積極的に許可することで、ポルトガル船を自らの港に誘致しようと互いに激しく競い合った。大村純忠は、貿易の拠点として長崎の港をイエズス会に寄進するという大胆な策に打って出て、その後の長崎の国際貿易港としての発展の礎を築いた。
このように、中央の天下人と九州の地方大名とでは、南蛮人に対する認識や距離感に大きな「温度差」が存在した。中央権力にとって南蛮人は、天下統一戦略における数ある要素の一つであったが、九州の大名にとっては、自らの領国の浮沈を左右する死活問題であった。この中央と地方の視点の違いが、戦国時代の対外関係を一層複雑でダイナミックなものにしていたのである。
【表3:南蛮貿易における主要な輸入品と輸出品】
|
日本への輸入品 |
日本からの輸出品 |
|
生糸・絹織物 (中国産が主力) 39 |
銀 (圧倒的な主力商品) 35 |
|
鉄砲・火薬・硝石 35 |
銅 39 |
|
ガラス製品・時計・眼鏡 40 |
刀剣・武具 39 |
|
葡萄酒・パン・カステラ 40 |
漆器・螺鈿細工 40 |
|
香辛料・砂糖・薬品 40 |
硫黄 40 |
|
地球儀・西洋の書籍 40 |
海産物 40 |
結論:神話から実像へ ― 戦国時代が変えたジパングの物語
マルコ・ポーロの『東方見聞録』が創出した「黄金の国ジパング」の神話は、中世末期のヨーロッパ人の世界観を拡張し、未知なる東方への憧憬を掻き立てた。それは、虚実ないまぜの情報でありながら、コロンブスをはじめとする探検家たちを大西洋へと駆り立て、結果的に大航海時代という新たな歴史の扉を開く強力な触媒として機能した。神話が現実の歴史を動かした顕著な例として、その歴史的意義は計り知れない。
しかし、この神話は、戦国時代という日本の激動期に「現実」と衝突することで、その姿を大きく変えざるを得なかった。16世紀、実際に日本の土を踏んだヨーロッパ人たちが発見したのは、黄金の宮殿ではなく、群雄が割拠する戦乱の国であり、世界経済を動かすほどの銀を産出する国であった。彼らは「黄金」の代わりに「銀」という現実の富を見出し、南蛮貿易という新たなグローバル経済関係を構築した。また、統一された穏やかな王国ではなく、高度な武士文化に支えられた誇り高い人々が生きる社会を目の当たりにし、日本を単なる富の略奪対象や素朴な布教地ではなく、複雑で手ごわい交渉相手として認識するようになった。この認識の転換は、イエズス会という組織的な情報ネットワークによって加速され、ヨーロッパにおける日本像は、幻想から実像へと急速に塗り替えられていった。
一方、日本の側でも、戦国大名たちはこの未知との遭遇を主体的に利用した。織田信長は、南蛮文化を自らの権威の象徴とし、キリスト教を既存の宗教勢力に対抗する政治的道具として活用した。豊臣秀吉は、キリスト教が自らの支配体制を脅かすと判断するや、これを巧みに制御しようと試みた。九州の諸大名は、南蛮貿易の利益を領国経営の生命線として、生き残りを賭けた。彼らは決して、ヨーロッパ人が描く物語の受動的な登場人物ではなかった。
この神話から実像への移行を象徴するのが、呼称の変遷である。マルコ・ポーロの伝聞に基づく幻想的な響きを持つ「ジパング(Cipangu)」が、直接的な交流を通じて、より現実的な国家を指す「ジャパン(Japan)」へと定着していく過程 9 。この変化は、ヨーロッパの世界認識の地図の上で、日本が「神話の島」から「実在の国家」へとその地位を確立していった歴史的プロセスそのものを物語っている。
『東方見聞録』が紡いだジパングの物語は、戦国時代の日本との出会いによって、一つの終わりを告げた。そして、その代わりに、政治、経済、文化の各層で世界と深く結びついた、新たな「日本」の物語が始まったのである。
引用文献
- 世界の記述/東方見聞録 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0403-060.html
- 黄金の国ジパングと日本が呼ばれた理由|中尊寺金色堂との関係とは - なんぼや https://nanboya.com/gold-kaitori/post/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8C%E3%80%8C%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%82%B8%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%8F%E3%81%91/
- 東方見聞録(トウホウケンブンロク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%A6%8B%E8%81%9E%E9%8C%B2-104160
- 東方見聞録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%A6%8B%E8%81%9E%E9%8C%B2
- 鎌倉時代の勉強をしよう(小学生の質問)14 - 玉川学園 https://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/el14.html
- 元寇 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%AF%87
- ルスティケロ・ダ・ピサ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%94%E3%82%B5
- マルコポーロとは?東方見聞録でアジアとヨーロッパの橋渡しをした旅人 - ターキッシュエア&トラベル https://turkish.jp/blog/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AD/
- 中学校社会 歴史/鎌倉時代/元寇 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3/%E5%85%83%E5%AF%87
- 日本はなぜ「黄金の国ジパング」と呼ばれているの?意味や由来・東方見聞録を解説 - 買取大吉 https://www.kaitori-daikichi.jp/column/gold-platinum/post-48573/
- 東方見聞録 - 東洋文庫 https://toyo-bunko.or.jp/wp-content/uploads/2024/03/6e6ba653dc3062e95801ecee9d5a9606.pdf
- 黄金の国ジパングとは?ジパング=日本とされる理由やマルコ・ポーロとの関係 | 玉光堂 https://kaitori.gyokkodo.co.jp/blog/zipangu-the-land-of-gold/
- マルコ・ポーロ『世界の記述』における 「ジパング」 https://seijo.repo.nii.ac.jp/record/3366/files/06-02.pdf
- 大航海時代の駿府の家康公 - 黄金の国ジパングの王様・徳川家康 https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/05_02.htm
- マルコ・ポーロ『世界の記述』における 「ジパング」 - 成城大学 https://www.seijo.ac.jp/pdf/graduate/gslit/azur/06/0602.pdf
- 『東方旅行記』ジョン・マンデヴィル - 読書感想文(関田涙) https://sekitanamida.hatenablog.jp/entry/thetravelsofsirjohnmandeville
- 欧州に希望と妄想を与えた東方見聞録|kengoken21go - note https://note.com/kengoken21go/n/n5807ef713a6d
- その2 解説|西洋の日本観 フロイスからシーボルトまで ... https://lib.ouj.ac.jp/gallery/seiyou_nihon/nihon-kaisetsu2.html
- マルコポーロの「東方見聞録」|スパイスの歴史に関するお話|エスビー食品株式会社 https://www.sbfoods.co.jp/sbsoken/jiten/history/04.html
- 連載⑦ 黄金の国ジパング伝説 その起点は東北の砂金 - 情報屋台 https://www.johoyatai.com/4830
- 【漫画】コロンブスの生涯を簡単解説(前編)【世界史マンガ動画 ... https://www.youtube.com/watch?v=urWYkY5Bx5c
- Materiality and Marginalia across the World: The Role of Things in Christopher Columbus's Annotations on Marco Polo - Fingerprint - Princeton University https://collaborate.princeton.edu/en/publications/materiality-and-marginalia-across-the-world-the-role-of-things-in/fingerprints/?sortBy=alphabetically
- The book of Marco Polo (copy with annotations by Christopher Columbus which is conserved at the Capitular and Columbus Library of Sevilla) - University of Pittsburgh https://pitt.primo.exlibrisgroup.com/permalink/01PITT_INST/1r83t0t/alma9911462763406236
- Materiality and Marginalia across the World: The Role of Things in Christopher Columbus's Annotations on Marco Polo - Princeton University https://collaborate.princeton.edu/en/publications/materiality-and-marginalia-across-the-world-the-role-of-things-in
- 地図の歴史 / 大航海時代 https://atlas.cdx.jp/history/voyage.htm
- トスカネリ - スタンプメイツ http://www.stampmates.sakura.ne.jp/Gv-sTskneri.htm
- Innovations from Mistakes. Learning from Marco Polo, Columbus, and… | by Phil Luza | Adventure Capitalists | Medium https://medium.com/adventure-capitalists/marco-polo-columbus-and-japan-innovations-from-mistakes-5bd9562308cb
- ゼンリンミュージアム | 常設展 | 世界の中の日本 https://www.zenrin.co.jp/museum/permanent/chapter01/
- Ortelius Atlas | General Atlases | Articles and Essays | General Maps | Digital Collections | Library of Congress https://www.loc.gov/collections/general-maps/articles-and-essays/general-atlases/ortelius-atlas/
- Japan by Abraham Ortelius. - Sanderus Antique Maps https://sanderusmaps.com/our-catalogue/antique-maps/asia/japan/japan-by-abraham-ortelius-31043
- 1595 / 1609 Ortelius - Teixiera Map of Japan and Korea - Geographicus Rare Antique Maps https://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/japankorea-ortelius-1595
- 大航海時代と日本 〜「長崎出島」は「鎖国」の象徴か? - 時空トラベラー The Time Traveler's Photo Essay http://tatsuo-k.blogspot.com/2017/05/blog-post_23.html
- 世界経済に影響を与えた石見銀山|オトナのための学び旅(4) - note https://note.com/honno_hitotoki/n/nbb186a1514ff
- 世界遺産「石見銀山」の価値 | 石見銀山世界遺産センター(島根県大田市大森町) / Iwami Ginzan World Heritage Center(Shimane Pref, Japan) https://ginzan.city.oda.lg.jp/value/
- 【中学歴史】「南蛮貿易の特色」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-2904/lessons-2949/point-3/
- 南蛮貿易 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nanbanboueki/
- 石見銀山遺跡 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/publication/index.data/2-1_sekaiisankouza_R1_2.pdf
- 石見銀山の歴史 - しまねバーチャルミュージアム https://shimane-mkyo.com/vol06/s02
- 南蛮貿易 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-108.html
- 南蛮貿易 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E8%9B%AE%E8%B2%BF%E6%98%93
- A very brief encounter: Jesuits in Japan - European studies blog https://blogs.bl.uk/european/2013/09/a-very-brief-encounter.html
- ルイス・フロイスの描く織田信長像について https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/8167/files/shigakukahen41_049-076.pdf
- Japan–Portugal relations - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Japan%E2%80%93Portugal_relations
- Luís Fróis - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Fr%C3%B3is
- Alessandro Valignano - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Valignano
- Alessandro Valignano and the Restructuring of the Jesuit Mission in Japan, 1579-1582 - Scholars Crossing https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=eleu
- Alessandro Valignano and the Restructuring of the Jesuit Mission in Japan, 1579-1582 https://digitalcommons.liberty.edu/eleu/vol1/iss1/4/
- Valignano's Sumario and the Early Modern Jesuit Discourse about Japan - JHI Blog https://www.jhiblog.org/2021/03/08/valignanos-sumario-early-modern-jesuit-discourse-about-japan/
- Representing Catholic Europe: Alessandro Valignano and De Missione (1590) https://journals.openedition.org/cecil/335?lang=en
- 『平成遣欧少年使節団として』 - 西都市 https://www.city.saito.lg.jp/f698c773e0acff4f1c46cb3c192d124d.pdf
- Letter from Japan, to the Society of Jesus in Europe, 15521 Francis Xavier was one of the first members of t https://my.tlu.edu/ICS/icsfs/EurosinAsiaSources9pg.pdf?target=f95413e2-209d-4e7f-a324-456e70da7a3d
- 特別展示「THE 金箔瓦」によせて https://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/410.pdf
- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/
- 一向一揆 - ホワイトヒーリング 越前加賀宗教文化街道 https://echizenkaga.jp/white-healing/key/key01.html
- 一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86
- 本願寺家 と 本願寺顕如(光佐)と 一向一揆 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/honganzi.htm
- ルイス・フロイス『日本史』を読みなおす⑧ – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/essay/20230830/
- 昨今の金箔瓦事情|大坂城豊臣石垣コラム https://www.toyotomi-ishigaki.com/hideyoshi/2004.html
- バテレン追放令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4
- バテレン追放令、秀吉は日本を守ったのか - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=Hcf6NrtEUGs&pp=2AEAkAIB
- 「大航海時代の日本」12 秀吉「バテレン追放令」①九州平定 | 粋なカエサル https://julius-caesar1958.amebaownd.com/posts/18117736/
- 10分で読める歴史と観光の繋がり 統治の今川義元と商業の織田信長、二人の偉才による経済戦争 桶狭間、南蛮貿易の始まり、合戦川中島と厳島/ ゆかりの熱田神宮・善光寺・世界遺産厳島と平戸の南蛮史跡 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/08/27/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8C%E7%9B%AE/
- 大友宗麟(おおとも そうりん) 拙者の履歴書 Vol.35〜南蛮の風に乗りし豊後の王 - note https://note.com/digitaljokers/n/nc21640eff29b