楊心流柔術書
楊心流柔術書は、戦国組討の記憶を内包しつつ、江戸期に生まれた武術なり。秋山四郎兵衛の伝説と大江千兵衛の実績が交錯し、「柔の理」と活殺自在の医学的知識を融合。天神真楊流を経て現代柔道へ継承されし。
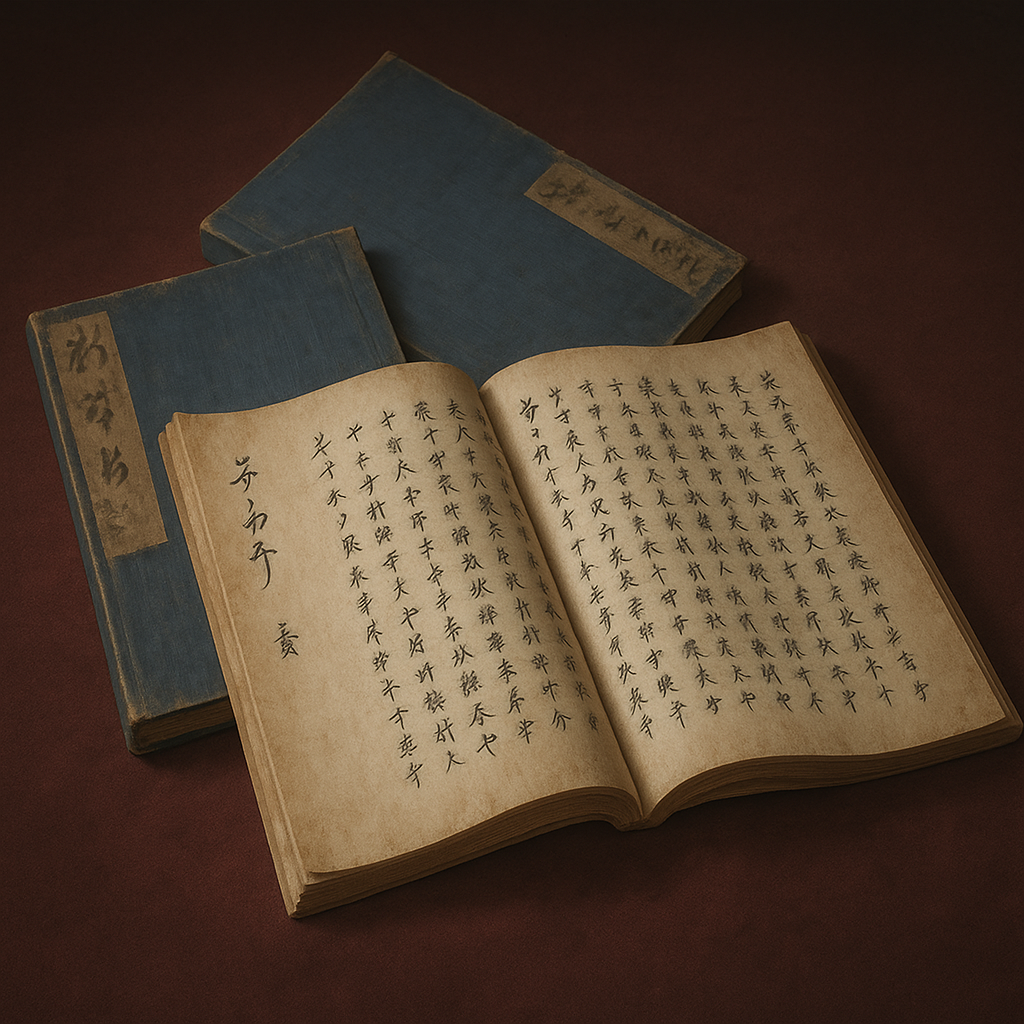
楊心流柔術書:戦国から江戸へ、武術の変容を解き明かす
序論:問いの再設定 — 戦国から江戸へ、武術の変容
本報告書は、「楊心流柔術書」を日本の戦国時代という視点から詳細に調査するものである。しかし、調査の初期段階で明らかになるのは、楊心流の成立が戦国時代(1467年頃-1615年頃)ではなく、徳川幕府による泰平の世が確立された後の江戸時代初期から中期にかけてであるという歴史的事実である。現存する楊心流の伝書には、元文五年(1740年)や明和四年(1767年)といった年紀が確認されており 1 、さらにその源流は寛文十年(1670年)や天和三年(1683年)頃に活動した人物にまで遡ることができる 2 。これは、戦国時代の終焉から半世紀以上が経過した後のことであり、両者の時代背景は根本的に異なる。
したがって、本報告書は「戦国時代に楊心流は存在したか」という問いに単純に「否」と答えるのではなく、より深く本質的な問いへと再設定する。すなわち、「戦国時代の過酷な実戦格闘術が、いかにして江戸時代の泰平の世で楊心流という洗練された武術へと昇華したのか」という、歴史的変遷の物語を解き明かすことを目的とする。
利用者の問いの根底には、「柔術のルーツは戦場にあるはずだ」という直感的な理解が存在する。この直感を肯定しつつ、その「ルーツ」が平和な時代の中でいかに「再解釈」され、「体系化」されたかを描くことこそが、楊心流の本質を理解する鍵となる。本報告書は、戦国時代の「組討(くみうち)」と江戸時代の「柔術」という、二つの異なる概念の断絶と連続性を解き明かすことで、楊心流柔術とその伝書が持つ真の歴史的価値に迫るものである。
第一章:戦国乱世の格闘術 — 柔術の前身「鎧組討」の実相
楊心流のような洗練された柔術が誕生する以前、戦国時代の武士たちが実践していた徒手格闘術は「鎧組討(よろいくみうち)」または「小具足(こぐそく)」と呼ばれていた 3 。これは、後の柔術とは似て非なる、生存に特化した実戦技術の集合体であった。
目的と環境
鎧組討の主目的は、戦場で甲冑を着用した武者同士が武器を失ったり、至近距離で組み合った際に、敵を無力化し、とどめを刺すことにあった 4 。そこには、後の武士道に見られるような精神修養の側面は薄く、ただ生き残るための極めて実利的な技法が求められた。戦場という極限状況下で、泥や血にまみれながら繰り広げられる、荒々しい生存術であった。
技術体系
鎧組討の技術は、「甲冑の着用」という絶対的な物理的制約によって規定されていた。平服での戦闘を想定した後の柔術とは、その技術思想の出発点が全く異なる。
第一に、攻撃は甲冑で覆われていない箇所に限定された。兜の隙間である顔面(特に目)や、関節の裏側などが主要な標的となった 6 。多くの打撃は硬い甲冑に阻まれ、効果が薄かった。
第二に、投げ技は相手の重心を崩して地面に叩きつけることに主眼が置かれた。特に、兜を鷲掴みにして相手の体勢を崩し、引き倒すといった技法が有効であった 6 。しかし、甲冑の重量と構造上、後の柔術に見られるような多彩で華麗な投げ技を繰り出すことは困難であった。
第三に、鎧組討は徒手のみで完結する体系ではなかった。相手を組み伏せた後、最終的には「鎧通し(よろいどおし)」と呼ばれる刃の厚い短刀で、甲冑の隙間から首や脇下を刺突してとどめを刺すことが想定されていた 6 。これは、徒手による関節技や絞め技の多くが、甲冑によって防がれてしまうためである。
これらの技術は、後の柔術の源流の一つではあるが、あくまで断片的な技法の集合体であり、一つの思想の下に体系化された「流派」としての洗練度は低かった 3 。楊心流柔術は、この「甲冑からの解放」という前提があって初めて可能になった、新しい時代の武術体系なのである。
第二章:泰平の世の武士道 — 楊心流誕生の社会的背景
関ヶ原の戦いを経て徳川幕府が成立すると、日本は二百数十年間にわたる平和な時代を迎えた。この社会の劇的な変化は、武士のあり方と武術の目的を根本から変容させ、楊心流のような高度に理論化された柔術が生まれる土壌を育んだ。
武士と武術の役割の変化
戦乱が終息し、武士の役割は戦場で武功を立てる「戦闘者」から、藩を統治する「行政官」「官僚」へと移行した 8 。もはや命のやり取りが日常ではなくなった武士にとって、武芸は実戦の道具であると同時に、武士としての階級的アイデンティティを維持し、心身を鍛えるための素養となった 8 。
これに伴い、武術の目的も、敵を殺傷するための「殺人の術(さつじんのじゅつ)」から、心身を鍛え、人格を陶冶し、ひいては社会の秩序を守るための「活人の道(かつじんのみち)」へと昇華した 10 。剣術が「活人剣」の思想を重視するようになったように、柔術もまた、単なる暴力技術ではなく、精神性を伴う修練の道として捉えられるようになったのである 11 。
流派の確立と理論化
平和な時代が訪れたことで、先人たちが戦場で培った貴重な戦闘経験を、後世に正しく伝えるための体系化が活発になった。「形(かた)」や「伝書(でんしょ)」が整備され、各々が独自の理論と技法を持つ「流派」として確立されていった 8 。楊心流が生まれた江戸時代初期には、竹内流や関口新心流といった柔術流派が同じく隆盛しており、互いに影響を与えながら発展していった 12 。
この時代、新興の流派が権威を確立するためには、単に技が優れているだけでなく、その背景にある思想や哲学が重要視された。武術の価値を、単なる暴力性から、より高次の精神性や知的体系へと引き上げるため、「神仏からの啓示」「故事来歴からの着想」といった、神秘的・哲学的な創始伝説がしばしば語られた。楊心流の「柳に雪折れなし」の逸話も、まさにこの時代の要請に応えるものであった。
この歴史的変遷を明確にするため、以下の表に戦国期と江戸期の格闘術の比較を示す。
表1:戦国期組討術と江戸期楊心流柔術の比較
|
項目 |
戦国期・鎧組討 |
江戸期・楊心流柔術 |
|
時代背景 |
戦乱の世 |
泰平の世 |
|
主目的 |
戦場での殺傷・捕縛 4 |
護身、心身の鍛錬 10 |
|
想定服装 |
甲冑(鎧兜) 4 |
平服(着物・袴) 13 |
|
主要技術 |
鎧の隙間を突く、投げ倒し後の刺突 6 |
逆手、投技、絞技、関節技 2 |
|
思想的基盤 |
実利主義、生存術 |
柔の理、心身合一、活人剣 15 |
|
付随技術 |
なし(または未分化) |
殺法・活法(医学的知識) 2 |
この表が示すように、楊心流は戦国時代の武術とは全く異なる社会的・思想的基盤の上に成り立っている。それは、新しい時代が求めた、新しい武士のための武術だったのである。
第三章:楊心流の創始 — 伝説と史実の狭間
楊心流の創始を語る上で、二人の重要人物が存在する。一人は、流派の創始伝説に登場する「秋山四郎兵衛義時」。もう一人は、史料から実在が確認され、事実上の流祖と目される「大江千兵衛義時」である。この二人の役割を考証することは、楊心流の本質を理解する上で不可欠である。
伝説の流祖・秋山四郎兵衛
楊心流の創始伝説は、後世に大きな影響を与えた天神真楊流の伝書などで、次のように語られている 2 。
肥前の国長崎の医師であった秋山四郎兵衛義時(伝書により義昌、則重など名は異なる)は、医術修行のために中国へ渡った。そこで博転という人物に出会い、拳法三手と活法二十八手という、人体を制し、また蘇生させる術を学んだという 2 。
帰国後、道場を開いたものの、技の数が少ないために門人が集まらなかった。深く悩んだ秋山は、太宰府天満宮に百日間参籠して一心に祈願した。ある雪の日、境内の木々を眺めていると、硬い桜の枝は雪の重みで無残に折れているのに対し、しなやかな柳の枝は雪を受け流し、少しも傷ついていないことに気づく。この情景から「柔よく剛を制す」の極意を悟った秋山は、三百三手の技を編み出し、柳(楊)の心にちなんで流名を「楊心流」と名付けたとされる 2 。
しかし、この物語には史実としていくつかの疑問点が指摘されている。第一に、江戸時代は鎖国政策が敷かれており、個人の海外渡航は原則として禁止されていたため、秋山の中国留学は極めて非現実的である 2 。第二に、この中国渡航説は、楊心流自身の初期の伝書には見られず、後世に書かれた天神真楊流の伝書に初めて登場する 2 。これは、当時の「中国崇拝」の風潮の中、流派の権威を高めるために創作された可能性が高い。
事実上の流祖・大江千兵衛義時
一方で、多くの信頼性の高い史料で楊心流の普及に大きく貢献したとされるのが、二代目とされる大江千兵衛義時(仙兵衛、専兵衛とも)である 2 。一部の系統では、この大江を開祖として扱っていることからも、その重要性がうかがえる 2 。
彼の存在を裏付ける最も強力な証拠は、現存する伝書である。熊本県立図書館には、大江千兵衛尉義時から門人へ宛てた寛文十年(1670年)付の伝書が所蔵されており、また天和三年(1683年)に発行された直筆伝書の存在も示唆されている 2 。これらの具体的な年代が記された史料は、大江が江戸時代初期に実在し、彼の代から楊心流が組織的な流派として本格的に広まったことを確実視させるものである。
これらの事実を総合すると、次のような構図が浮かび上がる。すなわち、大江千兵衛が自身の柔術体系を確立し、それを普及させるにあたり、既存の権威ある流派と伍していくための「箔付け」として、師である「秋山四郎兵衛」という人物像を創作、あるいは大きく脚色した可能性である。「医師」「中国渡航」「神仏の啓示」という三つの要素は、当時の人々が最も権威を感じるものであり、楊心流が単なる武術ではなく、医学的知識と東洋哲学に裏打ちされた高尚な体系であることを示す、巧みなブランディング戦略であったと言える。秋山が「思想的・伝説的シンボル」であるのに対し、大江は「技術体系の確立者・普及者」という、実務的な役割を担った人物として捉えるのが最も妥当であろう。
第四章:柳の哲学 — 「柔の理」の探求
楊心流の名称の由来となった「柳に雪折れなし」という故事は、単なる美しい逸話ではない。それは、流派の技術と思想の根幹をなす「柔の理(じゅうのり)」、すなわち相手の力に力で抗するのではなく、その力を利用して制するという柔術の根本原理を、見事に象徴している。
故事の深層と柔の理
柳の枝は、雪の重みという「剛」の力に対して、自らの硬さで対抗しようとはしない。むしろ、その力を受け入れ、しなやかにたわむことで雪を地面に落とし、結果として自らは折れることなく元の姿に戻る 16 。この自然現象に、楊心流は武術の極意を見出した。相手が力強く攻撃してくれば、それを正面から受け止めるのではなく、受け流し、誘導し、相手自身の力を利用して体勢を崩し、無力化する。これが「柔の理」である。
この思想は、戦国時代の鎧組討が、相手の動きを力で封じ込め、破壊することを目的としていたのとは対照的である。戦乱の世が「剛」の価値観に支配されていたとすれば、泰平の世に生まれた楊心流は、「柔」の価値観を武術として体系化したものであった。
技術への反映
「柔の理」は、楊心流の具体的な技法の中に明確に見て取れる。
第一に、全ての技の起点となるのが「崩し」である。相手の体勢を不安定にさせなければ、効率的に技をかけることはできない。楊心流では、相手が押してくれば引き、引いてくれば押すといった具合に、相手の力の方向を読み、その力を利用して最小限の力で相手を崩すことを重視する 20 。
第二に、そのための重要な要素が「体捌き(たいさばき)」である。相手の攻撃を直線的に受け止めるのではなく、体を移動させて攻撃をかわし、同時に相手の死角に入り込み、有利な体勢を作り出す 20 。これにより、力と力の衝突を避け、常に自分が主導権を握ることが可能となる。
精神性への昇華
さらに、「柳の哲学」は肉体的な技術論に留まらず、精神的な柔軟性の重要性をも説いている。いかなる状況に遭遇しても動揺せず、平静な心を保ち、相手や状況に応じてしなやかに対応できる精神を養うことこそ、楊心流が目指す真の強さであった 15 。頑固で折れやすい心ではなく、柳のような柔軟な心を持つこと。この教えは、単なる護身術の習得を超え、複雑な人間関係や社会秩序の中で生きる江戸時代の武士にとって、重要な処世術でもあった。楊心流の稽古は、身体を通して新しい時代の価値観を学ぶ、一種の思想教育の側面をも持っていたのである。
第五章:「楊心流柔術書」の深層分析 — 技法と伝承の全貌
「楊心流柔術書」として伝わる各種伝書は、単なる技の目録ではない。そこには、流派の哲学、高度な医学的知識、そして生命倫理観までが凝縮されている。特に、楊心流の真髄ともいえるのが、人を殺傷する「殺法(さっぽう)」と、人を蘇生させる「活法(かっぽう)」が表裏一体の技術として伝承されている点である。
伝書と技法体系
現存する伝書を分析すると、楊心流の技法体系の輪郭が浮かび上がる。大江千兵衛の直筆と伝わる『静間之巻』には、「真之位(しんのくらい)」「暫心目付(ざんしんめつけ)」「抜見目付(ぬきみめつけ)」「無刀別(むとうべつ)」「立合請別(たちあいうけべつ)」「車捕(くるまどり)」といった形名が記されている 2 。これらの技法名は、後の楊心流系の各流派、特に柔道の源流となった天神真楊流にもほぼそのままの名称で継承されており、楊心流が後世に与えた影響の大きさを物語っている 2 。
技は、座った状態での攻防術である「居捕(いどり)」と、立った状態での「立合(たちあい)」に大別される 1 。また、楊心流は特に絞め技に優れた流派であったとされ、着衣を利用した多彩な絞め技が伝承されていたことが記録からうかがえる 2 。
殺法と活法の二元性
楊心流を他の柔術流派と一線を画す存在にしているのが、殺法と活法の体系である。
殺法 は、単に人を傷つけるための暴力技術ではない。それは、人体の急所(経絡秘孔)に関する深い知識に基づいた、極めて精密な当身技(あてみわざ)を中心とする技術体系であった 14 。最高極意を記した『楊心流覚悟巻』には、「袖車殺」「稲妻殺」「月陰殺」など十ヶ条の秘伝が記されている。そして、これらの術は「神武不殺(しんぶふさつ)」、すなわち不義の心を殺し、罪なき身体は活かすための究極の技であると説かれている 23 。これは、武術が単なる破壊技術から、生命そのものを扱う哲学へと深化していく過程を象徴している。一部の伝書には、遠隔から敵を害するための毒薬殺法に関する記述も見られる 24 。
活法 は、絞め技などで意識を失った(「落ちた」という)人間を蘇生させる技術や、脱臼・骨折などを整復する医術である 2 。稽古の場では、絞め技によって仮死状態に陥ることが日常的にあり、活法の習得は門人にとって必須であった 21 。この活法の存在は、流祖を医師とする伝説と密接に結びついており、楊心流の医学的側面の裏付けとなっている。
医学的知識の集大成『胴釈図』
殺法と活法という表裏一体の技術の根底にあったのが、『胴釈図(どうしゃくず)』または『胴釈之巻』と呼ばれる人体解剖図の存在である 17 。これは、人体の骨格、内臓、そして急所の位置を詳細に示した図であり、楊心流が高度な医学的知識を武術体系に不可分な要素として組み込んでいたことを示す決定的な証拠である。「胴釈」とは人体解剖を意味する言葉であり、楊心流が人体の構造を深く理解することから出発していることを示している 17 。
「殺す」方法を知る者は、最も効果的に「活かす」方法も知る。この思想に基づき、破壊と再生の両方を内包する楊心流は、戦場で敵を破壊することのみを目的とした鎧組討から決定的な飛躍を遂げ、極めて高度で知的な武術体系へと進化したのである。
第六章:楊心流の遺産 — 後世への影響と展開
楊心流そのものの伝承は、現代においては限定的であるが、その技術と精神は数多くの分派を生み出し、特に講道館柔道を通じて現代武道の中に脈々と生き続けている。楊心流が日本武道史に与えた影響は計り知れない。
天神真楊流の誕生と講道館柔道への架け橋
楊心流の遺産を語る上で最も重要なのが、幕末期に創始された天神真楊流である。流祖の磯又右衛門は、楊心流と真之神道流という二つの流派の奥義を統合し、天神真楊流を興した 15 。特に、実戦における当身の有効性を重視し、楊心流の急所術や「柔の理」、そして殺活法といった要素を中核技術として受け継ぎ、さらに発展させた 22 。
この天神真楊流が、後の講道館柔道への直接的な架け橋となる。柔道の創始者である嘉納治五郎は、柔術修行の最初に天神真楊流を学び、その免許を得ている 13 。嘉納が制定した柔道の「極の形(きめのかた)」には、天神真楊流、ひいてはその源流である楊心流の形の影響が色濃く残されていることが指摘されている 13 。また、「山嵐」で有名な西郷四郎をはじめ、黎明期の講道館を支えた高弟たちの多くが天神真楊流の出身者であり 26 、楊心流の血を引く柔術家たちなくして講道館の発展はあり得なかった。
多彩な分派の隆盛
楊心流の影響力は、天神真楊流だけに留まらない。
江戸後期から幕末にかけて、戸塚彦介の代で隆盛を極めた「戸塚派揚心流(楊心古流)」は、明治初期には講道館の最大のライバルとして名を馳せた 27 。警視庁武術大会での講道館四天王との激闘は、小説や講談の世界でも有名である。
また、松岡克之助は天神真楊流と戸塚派揚心流を融合させ、さらに剣術の理合も取り入れて「神道揚心流」を創始した 21 。この流派は、後の和道流空手道の創始者である大塚博紀が学んだことでも知られている 29 。
これらの有力な分派の存在は、楊心流の技術体系がいかに魅力的で、発展の可能性を秘めたものであったかを物語っている。楊心流は、その子孫である天神真楊流や講道館柔道が世界的に普及したことで、結果的に「偉大なる源流」としてその名が再認識された側面がある。楊心流の技術と精神のDNAは、形を変え、柔道という現代武道として世界中に拡散し、今なお生き続けているのである。
結論:時代を映す武術の鏡としての楊心流
本報告書は、「楊心流柔術書」を戦国時代という視点から考察するという当初の問いに対し、歴史的変遷のダイナミズムを描き出すことで応えようと試みた。その結論として、以下の三点を挙げることができる。
第一に、楊心流は「戦国時代の武術」ではなく、「戦国時代の記憶を内包しつつ、江戸という新しい時代に生まれた武術」である。その根底には、戦場の過酷な実戦で培われた組討術の遺伝子が存在するが、その技術、思想、目的は、泰平の世の社会的要請の中で全く新しいものへと洗練・体系化された。
第二に、楊心流の誕生は、日本武術史における大きなパラダイムシフトを体現している。それは、甲冑を前提とした「剛」の武術から、平服を前提とした「柔」の武術へ。敵を破壊し殺傷することのみを目的とした「殺」の術から、人体への深い理解に基づき、蘇生・治療をも内包する「活」の術へ。この「力」から「理」への転換こそ、楊心流が武術史に刻んだ最大の功績である。
第三に、「楊心流柔術書」とは、単なる技の目録や技術解説書ではない。それは、江戸時代の武士たちが到達した、人体への深い洞察、自然の摂理に根差した哲学、そして生命を尊ぶ倫理観が凝縮された、一つの文化遺産である。その遺産は、天神真楊流を経て講道館柔道へと脈々と受け継がれ、現代に生きる我々が日本の武道を理解する上で、不可欠な歴史的座標軸を提供し続けている。楊心流は、まさに時代を映す鏡として、武術が社会といかに深く結びついているかを我々に教えてくれるのである。
引用文献
- 楊心流柔術巻物の史料調査 Historical research; Derived from the Mokuroku of Yoshin-ryu-jujutsu - 日体大リポジトリ https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/record/1263/files/44-1-1-7.pdf
- 楊心流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E6%B5%81
- 鎧組討(よろいくみうち)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%8E%A7%E7%B5%84%E8%A8%8E-1433614
- 体術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113209/
- 丈山流鎧組討術 - 日本武道協会 Japanese Budo Association https://www.japanesebudo-assoc.com/%E5%8A%A0%E7%9B%9F%E6%AD%A6%E9%81%93/%E4%B8%88%E5%B1%B1%E6%B5%81%E9%8E%A7%E7%B5%84%E8%A8%8E%E8%A1%93/
- 殺陣講座48話【組討Kumiuchi】戦国時代を知って楽しむ! The technique of "Kumiuchi" a warring nation - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsfusn-yFk4
- 甲冑組討と素肌武術 | 本部流のブログ - Motobu-ryu Blog - https://ameblo.jp/motoburyu/entry-12797488677.html
- ― 歴史と特性 ― - 日本武道館 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_full.pdf
- 第2章 戦国時代から江戸時代へ ~錦絵や洒落本、歌舞伎から - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/3/2.html
- 剣道の歴史をどこよりも簡単に解説!日本文化の紹介にも役立つ知識を | 武道・道場ナビ https://www.budo-dojo-navi.com/history-of-kendo/
- 武道の歴史 - 東京都柔道連盟 https://tojuren.or.jp/appeal/history.html
- 第7回 古流柔術の技ってどんなん? 柔術ザックリ発展史 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889327767
- 柔道整復師が伝えていきたい柔術3 流派 https://www.teikyo-jc.ac.jp/app/wp-content/uploads/2018/08/report2014_55-61.pdf
- 楊心流、長尾流躰術、天神眞楊流柔術「活流」につい て https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/13156/files/jinbunkagakukiyo_50_343.pdf
- 天神真楊流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/005/
- 柳に雪折れなし。|S・A - note https://note.com/quickresponse_/n/nb8e59b639d22
- 連載『先人に学ぶ柔道整復』三十九 楊心流柔術(後編)殺法、活法、急所(当身)について https://news-shinkyujusei.net/20240225-5/
- 秋山義時(あきやまよしとき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E6%99%82-1049267
- 柳に雪折れなし | 国語の先生のブログ - アメブロ https://ameblo.jp/kokugonosensei-nana/entry-11773905503.html
- 第 4 章 - 技能指導の要点 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/11/08/1333611_06.pdf
- 神道揚心流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%8F%9A%E5%BF%83%E6%B5%81
- 古流柔術「殺法」に関する文献研究 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/13196/files/jinbunkagakukiyo_54_335.pdf
- 楊心流覚悟巻 - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/31384142/
- 楊心流柔術の当身秘伝 Yôshin ryû jûjutsu Atemi Hiden https://japanbujut.exblog.jp/20517995/
- 連載『先人に学ぶ柔道整復』四十 真之神道流柔術(前編)武術(殺法)において陰陽を重視 https://news-shinkyujusei.net/20240525-4/
- 柔道の源流 幕末名門柔術「天神真楊流」 - KKH-BRIDGE.com https://www.kkh-bridge.com/feature/20231229/KH5248LFA
- 楊心古流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E5%8F%A4%E6%B5%81
- 楊心流と揚心古流 Yôshin ryû and Yôshinko ryû - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/20407792/
- 神道揚心流柔術|明治時代|歴 史 - 和道流空手道連盟 https://www.wado-ryu.jp/histor/meiji_01.html