気楽流武術書
気楽流は戦国実戦武術の記憶を宿す総合武術。流祖の謎、新町騒動を経て伊勢崎藩の御流儀となり、現代に継承される貴重な文化遺産。
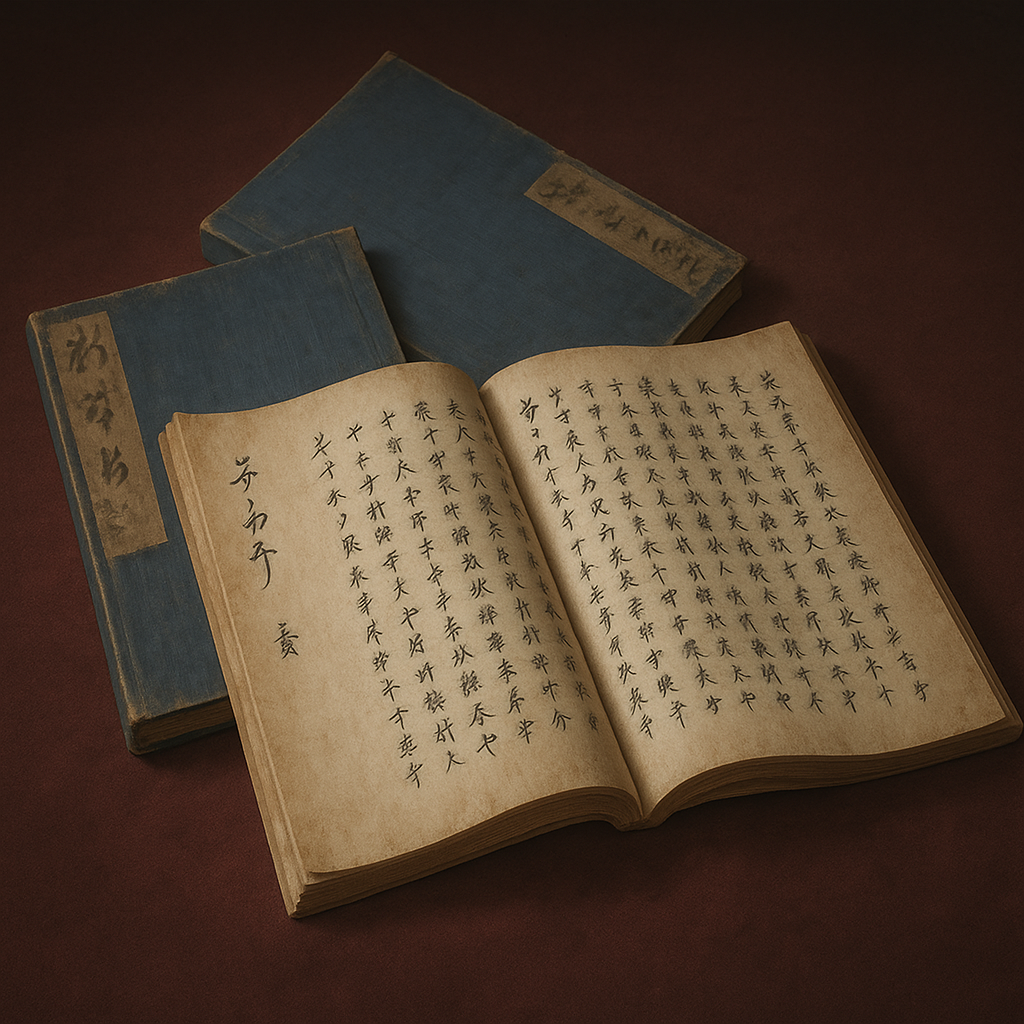
戦国の実相を秘めたる伝書―「気楽流武術書」の総合的考察
第一章:序論―戦国の実戦から生まれた武術、気楽流
日本の武術史において、戦国時代は技術革新と体系化が最も飛躍的に進んだ時代であった。絶え間ない戦乱の中で、武士たちは自らの生存を賭けて技を磨き、その精髄は数多の流派として結晶化した。その多くは江戸時代の泰平の世を経て変容し、あるいは失伝したが、中には戦場の苛烈な記憶を色濃く宿したまま現代に伝わるものも存在する。上野国伊勢崎藩に「御流儀」として伝わった気楽流(きらくりゅう)は、まさにそのような「生きた武術遺産」の一つである。
一般に気楽流は、柔術を中心に剣、棒、鉄扇など多様な武器の扱いを伝える総合武術として知られている 1 。しかし、その本質は単なる多芸にあるのではない。柔術、剣術、槍術、さらには契木(ちぎりき)や鎖鎌といった奇抜な武器に至るまでを一つの体系に内包するその姿は、戦場で遭遇しうるあらゆる状況、すなわち武器の喪失や破損といった不測の事態を前提とした、生存のための必然的な技術大系であったことを物語っている。戦場における一人の武士の戦闘は、多くの場合、槍や薙刀といった長柄武器による間合いの探り合いから始まり、それが失われれば太刀を抜き、最後は敵と組み合い、鎧の隙間から鎧通し(よろいどおし)でとどめを刺すという段階的な移行を辿る 4 。気楽流の技術構成は、奇しくもこの戦闘の全段階を網羅しており、それは個の武士が経験するであろう死闘の様相を、武術の「型」として体系化したものに他ならない。
本報告書は、この気楽流の核心を記した「気楽流武術書」、特に図解によって技法を伝える「絵目録」に焦点を当てる。伝書に記された技法の一つひとつを解読し、その背景にある思想を深く掘り下げることで、気楽流が単なる江戸期の武術ではなく、戦国時代の戦闘術の記憶を宿した、極めて実践的な武術体系であることを明らかにすることを目的とする。流祖を巡る錯綜した伝承の謎から、流派確立の経緯、そして伊勢崎藩で隆盛を極めるに至った歴史を追いながら、「気楽流武術書」というレンズを通して、失われた戦国の実相に迫るものである。
第二章:源流を巡る錯綜―戸田越後守と名人・富田重政
あらゆる古流武術の研究において、その源流を探る作業は、流派の思想的根幹を理解する上で不可欠である。しかし、それはしばしば霧中の探求となる。気楽流も例外ではなく、その起源には「戸田越後守(とだえちごのかみ)」という流祖を巡る、複雑にして魅力的な謎が存在する。
流祖「戸田越後守」という存在
気楽流の多くの伝承は、その流祖を戦国時代の末期、加賀藩主・前田利家の家臣であった戸田越後守信正(のぶまさ)であると記している 1 。伝によれば、彼は軍功によって一万三千六百七十石もの知行を賜った武将であり、剣術、槍術、柔術を統合した戸田流の元祖であったとされる 7 。この「前田家臣」「越後守」「武勇に優れた武将」という三つの要素が、流祖像の核となっている。
しかし、この戸田越後守信正という人物、同時代の確かな史料においてその具体的な活躍を追うことは困難である。一方で、ほぼ同じ時代、同じく前田家に仕え、そして同じ「越後守」の官位を名乗った、歴史に名を轟かす一人の剣豪が存在した。それが中条流(ちゅうじょうりゅう)の達人、富田重政(とだ しげまさ)である。
「名人越後」富田重政との関係
富田重政(1564-1625)は、能登末森城の戦いや関ヶ原の戦い、大坂の陣などで数々の武功を挙げた実在の猛将である 8 。その剣技は神の域に達していたとされ、官位である越後守から「名人越後」と称揚され、恐れられた 10 。彼が継承した中条流は、特に小太刀(こだち)の技法に優れ、力に頼らず敵を制する「柔よく剛を制す」の思想を旨としており、これは後の柔術の発展に大きな影響を与えた武術であった 11 。
この高名な富田重政と、気楽流の流祖・戸田越後守との関係は、流派の歴史における最大の論点となっている。気楽流の伝承の一部、特に研究者である飯嶌氏は、この二人を同一人物と見なす説を採っている 3 。音が近く、共に前田家臣の「越後守」であることから、この説は一定の説得力を持つ。
錯綜する伝承と「由緒の創造」
しかし、全ての伝承がこの説で一致しているわけではない。以下の表に示すように、気楽流の系統によって流祖の名前や出自は異なっており、事態はより複雑である。
|
系統名 |
流祖の名前 |
官位・通称 |
出身地 |
主な経歴・特徴 |
典拠 |
|
児島系 |
戸田越後守信正 |
越後守 |
(不詳) |
富田とも称したとされる。加賀藩主・前田利家の家臣。 |
3 |
|
飯塚系 |
戸田越後守綱義 |
越後守、新八郎一利 |
越後国頸城郡戸田村 |
元は長尾氏の旧臣で、箕輪城に仕えた戸田八郎高安を祖とする。 |
3 |
|
菅沼系 |
戸田越後守秀雄 |
越後守 |
(不詳) |
水橋隼人の子孫に戸田を置く。 |
3 |
|
(参考)富田重政 |
富田(山崎)重政 |
越後守、与六郎、大炊 |
越前国 |
朝倉氏旧臣の山崎景邦の子。富田景政の婿養子となり前田家に仕える。中条流の達人。 |
9 |
この伝承の多様性は、単なる記録の誤りや記憶の混濁として片付けるべきではない。むしろ、ここには江戸時代という新たな社会環境の中で、武術流派が自らの権威を高めるために行った、意図的な「由緒の創造」の痕跡が見て取れる。
戦国が終わり泰平の世となると、武術は戦場の実用技術から、武士の教養や心身鍛錬法としての性格を強め、道場経営が重要となる。多くの流派が競い合う中で、より古く、より輝かしい由緒を持つことは、門弟を集め、流派の箔付けをする上で極めて効果的であった。無名、あるいは実像が曖昧であった「戸田」という流祖を、具体的な武功が数多く伝わる高名な「名人越後」富田重政に結びつけることは、流派の権威を飛躍的に高める戦略であった可能性が高い。各系統がそれぞれに流祖伝承を発展させた結果、上表のような多様性が生まれたと考えられる。
この流祖を巡る謎は、気楽流が戦国という実力主義の時代から、由緒や権威を重んじる江戸の家元制度の時代へと移行していく、まさにその過渡期に生まれたことを示す歴史の証言なのである。
第三章:流派の確立と変遷―飯塚臥龍斎と「気楽流」の誕生
流祖・戸田越後守から数代を経て、気楽流の歴史は一人の傑出した武術家によって大きな転換点を迎える。流派中興の祖と称される飯塚臥龍斎興義(いいづか がりゅうさい おきよし)である 3 。彼は、それまで複数の流れに分かれていた技術体系を再編し、そしてある劇的な事件をきっかけに、その名を「気楽流」として確固たるものにした。
中興の祖・飯塚臥龍斎
飯塚臥龍斎は、気楽流の第十代または第十一代宗家とされる人物である。上州に生まれ、叔父より戸田流と気楽流を学んだ後、さらに広く諸流派を研究し、独自の境地を切り開いたと伝えられる 15 。彼の最大の功績は、戸田流、気楽流、そして無敵流という三つの流儀を統合し、これを総称して「気楽流」として大成させたことにある 16 。これにより、気楽流は柔術を中心としながらも、多彩な武器術を含む総合武術としての体系を確立した。
しかし、臥龍斎が「気楽流」の名を公に掲げるに至った背景には、単なる技術体系の完成だけではない、血生臭い社会的な事件が存在した。
「新町騒動」と流派名の確立
文化11年(1807年)、上州の中山道新町宿(現在の群馬県高崎市新町)で、気楽流の歴史を揺るがす刃傷沙汰が発生する。世に言う「新町騒動」である 3 。
当時、新町宿は中山道の要衝として多くの旅人や物資が行き交い、それに伴い様々な武術流派が道場を構え、勢力を競い合っていた 18 。この地で、飯塚臥龍斎率いる戸田流の門弟と、他流派(真之神道流または荒木流とされる)の門弟との間で大規模な抗争が勃発したのである 3 。この騒動の責任を問われた臥龍斎は、幕府の出先機関であった岩鼻陣屋(関東取締出役の拠点)の取り調べを受け、所払い(追放)の処分を受けると共に、公の場で「戸田流」を名乗ることを禁じられてしまった 3 。
この厳しい処分こそが、流派名を「気楽流」へと改称する直接的なきっかけになったというのが、現在最も有力な説である 3 。これは、流派の名称が、高尚な理念のみならず、社会的な制約と圧殺の中から生まれるという、武術史の生々しい一面を物語っている。
この一連の出来事は、気楽流がその性質を大きく転換させた象徴的な事件として捉えることができる。戦国時代において武術とは、敵を殺傷し自らが生き残るための純粋な実用技術であり、流派名よりもその実効性が全てであった。しかし、平和な江戸時代に入ると、武術は道場経営や社会的信望を巡る争いの道具となり、公権力の統制下に置かれるようになる。「新町騒動」という他流派との抗争、そして幕府役所からの裁きという経験は、臥龍斎にその現実を突きつけた。無法な実力主義が支配した戦国の世は終わり、武術もまた法と秩序の枠内で存続の道を探らねばならない。この圧力の下、「気楽流」と改称して再起を図った臥龍斎の決断は、戦国由来の「実戦武術」が、江戸期の社会秩序の中で生き抜くための「道場武術」へと、そのアイデンティティを変化させた歴史的瞬間であったと言えよう。
第四章:気楽流の技術体系―戦場を想定した総合武術の神髄
気楽流が戦国の記憶を宿す武術であることは、その多岐にわたる技術体系に最も明確に表れている。かつては360手に及んだとされる技は、時代の流れの中で失伝したものも多いが、現在伊勢崎に伝わる系統だけでも、柔術80手、棒術30手、太刀之術15手、薙刀之術15手、そして鉄扇、十手、契木、鎖鎌が各10手と、合計180手の技が継承されている 2 。この構成は、柔術を核としながらも、あらゆる間合いと状況に対応するための武器術が極めて重要な位置を占めていることを示している。
柔術技法―対甲冑戦闘の痕跡
気楽流の柔術は、単なる素手の格闘術ではない。その技法や用語の随所に、甲冑を纏った敵を無力化するという、戦国時代の組討術の思想が色濃く残されている。
その代表例が、当身技(打撃技)を指す「砕き(くだき)」という独特の呼称である 3 。これは、単に「当てる」のではなく、敵の鎧の隙間や兜の面頬(めんぽう)を打ち、あるいは骨を「砕く」という、より破壊的で決定的な打撃を意図した言葉と考えられる。初伝の段階である切紙で五つの「砕き」の形を学ぶことからも、この技術が気楽流の基本かつ最重要の技法と位置づけられていることがわかる 3 。
関節技においても、一般的な「小手返し」を「手ツ花(てつはな)」と呼ぶなど、流派固有の名称が用いられている 3 。江戸時代に佐賀藩士・石井又左衛門忠真が記した『拾華録』には、「喜楽流は立業、手足の固め、襟〆、当身を用いる」とその特徴が簡潔に記されており、立ったままの姿勢で相手を制圧する技法を重視していたことがうかがえる 3 。これは、泥濘や障害物の多い戦場で、安易に寝技に移行することの危険性を熟知した、実戦的な思想の表れであろう。
これらの技法は、平服の相手を想定した江戸期の多くの柔術流派の技法と比較すると、やや過剰なまでの威力と殺傷性を前提としているように見える。これは、気楽流の柔術が、元来存在した甲冑組討の技術を、甲冑を脱いだ泰平の世に合わせて稽古できるように「型」として再編成したものであることを示唆している。技の名称や想定する状況に、その「翻訳」の痕跡が深く刻まれているのである。
多彩な武器術―あらゆる状況への備え
気楽流の総合武術としての性格を際立たせているのが、その多彩な武器術である。太刀や棒、薙刀といった主たる武器はもちろんのこと、鉄扇や十手、契木、鎖鎌といった、いわゆる「小具足(こぐそく)」や「隠し武器」に分類される武具の技法が充実している点が特徴的である。
鉄扇や十手は、平時における護身用具として知られるが、戦場においては相手の武器を受け止め、あるいは鎧の隙間から喉や脇下といった急所を攻撃するための補助武器として絶大な効果を発揮した。また、鎖の先に分銅を付けた鎖鎌や、鎖で二本の短い棒をつないだ契木は、相手の刀や槍を絡め捕り、間合いの外から打撃を加えることができる変幻自在の武器である。
これらの多種多様な武器術は、戦場において主たる武器である槍や太刀を失った際に、いかにして生き延びるかという、武士にとって最も切実な問いに対する答えであった。状況に応じて懐中の鉄扇を抜き、あるいは腰の十手で敵刃を防ぎ、最後は組討で敵を制する。気楽流の武器術体系は、一つの武器に固執することなく、手元にあるあらゆるものを活用して勝利を得んとする、戦国武士の柔軟かつ徹底した実戦主義を体現している。
さらに、気楽流は負傷者を蘇生させ、あるいは脱臼などを治療する「活法」としての匡正術(きょうせいじゅつ)の体系も内包している 3 。これは、武術が敵を殺傷する「殺法」のみならず、味方を救う「活法」と表裏一体であったことを示すものであり、戦場で仲間を助けるという現実的な必要性から生まれた、これもまた戦国由来の思想と言えるだろう。
第五章:「気楽流武術書」の解読―絵目録に秘められた極意
気楽流の戦国的思想と技術体系の神髄は、その核心を記した伝書、とりわけ図解によって技の精髄を伝える「絵目録」に凝縮されている。この絵目録は、気楽流の戦闘哲学を体系的に示すものであり、以下の六つの分類で構成されていることが確認されている 17 。「上意取(じょういとり)」「小貝足(こがいあし)」「居詰(いづめ)」「腰の廻(こしのまわり)」「上意ぬけ身(じょういぬけみ)」「極意無刀取(ごくいむとうどり)」。これらの専門的な武術用語を解読することは、気楽流の、ひいては戦国時代の戦闘のリアリズムを理解する上で不可欠な作業である。
|
分類名 |
名称の解釈 |
想定される状況 |
主要な技術(推測) |
関連する武術概念 |
戦国時代との接続点 |
|
上意取 |
上位者(主君など)や油断ならぬ敵を捕らえる技。 |
主君への反逆者の制圧、要人警護、不意の襲撃への対処。 |
護身術、捕縛術、相手を傷つけずに制圧する技。 |
捕手(とりて) |
主君の身辺警護や、敵将を生け捕りにする際の技術。 |
|
小貝足 |
足捌き、足への攻撃、あるいは寝技に関する技法群。 |
足場の悪い場所での戦闘、乱戦での足払い、組み倒された後の対処。 |
足への関節技、足払い、寝技での抑え込みや脱出。 |
足緘(あしがらみ) |
乱戦や泥濘地での戦闘において、下半身の攻防は生死を分けた。 |
|
居詰 |
座った状態で敵に詰め寄られた際の対処法。 |
陣中での会談、室内での不意の襲撃、休息中の奇襲。 |
居捕(いどり)、座った状態からの抜刀、関節技、投げ技。 |
居合 |
武士の日常生活(座った状態)に潜む危険への備え。 |
|
腰の廻 |
脇差や短刀を腰に差した状態での至近距離戦闘術。 |
槍や太刀を失った最終局面、屋内での乱戦。 |
短刀術、組討、鎧通しによる刺突、逆手・固め技。 |
小具足、組討 |
戦場での白兵戦の最終形態。柔術の直接的な源流。 |
|
上意ぬけ身 |
上位者や敵に捕らえられた状態からの脱出術。 |
敵に捕縛された際、あるいは組み伏せられた際の逆転技。 |
身体操作による脱出、関節を外す技、当身による反撃。 |
抜身(ぬけみ) |
捕虜になることを最大の恥とした武士の、最後の抵抗術。 |
|
極意無刀取 |
素手で相手の太刀を奪う、流派の最高奥義。 |
武器を失い、丸腰で斬りかかられた絶体絶命の状況。 |
体捌き、入身、相手の力を利用した武器の奪取。 |
無刀取 |
武術の究極の境地。富田重政の逸話にも通じる。 |
「腰の廻」―戦国組討術の直系
この六分類の中で、気楽流の戦国的ルーツを最も雄弁に物語るのが「腰の廻」である。この言葉は、日本柔術の最古の源流の一つとされる竹内流(たけのうちりゅう)の正式名称「竹内流捕手腰廻小具足」にも含まれる、極めて重要な武術概念である 21 。
「腰の廻」とは、戦場で槍が折れ、太刀を失った武士が、最後の頼みである腰の小具足(脇差や短刀)を抜くか抜かないかの瀬戸際で行われる、超至近距離の組討術を指す 23 。敵の鎧の隙間を探り、関節を極め、鎧通しで喉を掻き切る。そこにはもはや華麗な剣技はなく、生存への渇望だけが支配する、泥臭くも究極的に洗練された技術が存在する。気楽流の絵目録が、この「腰の廻」を独立した一大項目として立てているという事実は、この流派の技術的アイデンティティが「戦場で脇差一本になった武士が、いかにして生き延びるか」という、具体的かつ切実な戦国の問いへの答えとして構築されていることを示す、何よりの証拠である。
他の分類もまた、戦国から江戸初期にかけての武士が直面したであろう、様々な危険な状況を網羅している。「居詰」は陣中や城内での不意の襲撃を、「上意取」や「上意ぬけ身」は主従関係という武家社会特有の緊張関係の中から生まれる危険を、そして「極意無刀取」は武器を失った際の最後の活路を、それぞれ想定している。富田重政が主君・前田利常を相手に見せたという無刀取の逸話は、まさにこの極意が単なる机上の空論ではなく、武士にとって現実的な課題であったことを示している 10 。
このように、「気楽流武術書」は抽象的な武術理論書ではない。それは、戦国の修羅場を生き抜いた者たちの知恵と経験が凝縮された、極めて実践的な「生存術教本(サバイバルマニュアル)」としての性格を色濃く持っているのである。
第六章:上州伊勢崎藩「御流儀」としての隆盛と継承
戦国の苛烈な記憶をその内に秘めた気楽流は、時代の流れと共にその在り方を変え、江戸時代後期、上州伊勢崎藩(現在の群馬県伊勢崎市)において、藩の公式武術、すなわち「御流儀(おとめりゅう)」として採用され、かつてない隆盛を極めることとなる。この歴史は、一つの武術流派が特定の地域社会に深く根付き、文化として継承されていく過程を示す好例である。
伊勢崎藩柔術指南役・斎藤武八郎
気楽流が加賀国金沢の地を離れ、上州に伝播したのは江戸時代中期のこととされ、1800年代には伊勢崎地方で伝承が行われていた 1 。この地で気楽流を大きく飛躍させたのが、第十四代宗家・斎藤武八郎在寛(さいとう ぶはちろう ありひろ、1794-1881)である 25 。
斎藤武八郎は、第十三代宗家・五十嵐金弥(いがらし きんや)に学び、その技量を認められて十四代を継いだ 25 。彼の武名は伊勢崎藩主・酒井侯の耳にも達し、やがて藩士として召し抱えられ、藩の柔術指南役という重責を担うに至る 3 。武八郎の指導は的確かつ厳格で、その門には伊勢崎藩士のみならず、近隣の農民や町人も含め、数千人もの人々が集ったと伝えられている 2 。彼の活躍により、気楽流は伊勢崎とその周辺地域に盤石な伝承基盤を築き上げたのである。
地域文化としての定着と近代への継承
伊勢崎藩の「御流儀」となったことは、気楽流にとって大きな栄誉であった。それは、戦場で培われた実戦技術が、江戸後期の藩体制を維持するための「武士の統制と教育の手段」として、その社会的役割を認められたことを意味する。幕藩体制に動揺が見え始めたこの時代、各藩は武備の充実と士気の高揚を喫緊の課題としていた。気楽流のような実戦的で総合的な武術は、藩士の心身を鍛え、武士としての自覚を促すための優れた教育プログラムとして、藩から大いに奨励されたのである。
斎藤武八郎以降、気楽流は伊勢崎の地に深く根を下ろし、地域の生活文化の一部として溶け込んでいった。境下渕名(さかいしもふちな)の大国神社で行われる秋季例祭での奉納演武など、その活動は道場内にとどまらず、地域社会における重要な役割を担うようになった 2 。
明治維新による廃藩置県は、指南役という職を失わせたが、気楽流の命脈を絶つことはなかった。斎藤家は道場を開いて指導を続け、その教えは多くの高弟たちによって各系統へと分かれ、受け継がれていった 3 。戦後の混乱期を経て、一時は伝承が危ぶまれたものの、先人たちの努力によりその技と心は守り抜かれた。現在では、第十九代宗家を継承する水科壽美氏の「練志館水科道場」や、同じく第十九代宗家である飯嶌文夫氏の「尚武館本部道場」などを中心に精力的な活動が続けられている 1 。そして、その長年の活動と歴史的価値が認められ、平成27年(2015年)には伊勢崎市の重要無形民俗文化財に指定されるに至った 7 。
藩の保護下に入ることで、気楽流は安定した伝承の礎を築いた。しかしそれは同時に、その最も根源的な「戦場の生存術」としての性格が、平和な時代の「武士の教養」や「地域の伝統文化」へと、その意味合いを変化させていく過程でもあった。この変遷の歴史そのものが、気楽流の持つ奥深さを示している。
第七章:結論―戦国の記憶を現代に伝える武術遺産
本報告書では、「気楽流武術書」を手がかりに、戦国時代という視点から気楽流の歴史、技術、そして思想を多角的に考察してきた。その分析を通じて明らかになったのは、気楽流が単なる古武道の一流派という枠に収まらない、日本の武士文化の重層的な記憶を内包した、極めて貴重な文化遺産であるという事実である。
第一に、「気楽流武術書」は、複合的な歴史資料としての価値を持つ。その錯綜した流祖伝承は、江戸時代の武術家たちが戦国の猛将に自らの理想と権威を投影した「由緒の創造」の過程を物語る。その技術体系、とりわけ「腰の廻」に代表される技法群は、甲冑を纏った武者が死闘を繰り広げた組討の理合を現代に伝える。そして、飯塚臥龍斎の「新町騒動」から伊勢崎藩「御流儀」への道程は、武術が時代の要請に応じてその社会的役割を変容させていく、生々しい社会史の記録に他ならない。
第二に、気楽流の技法は、失われた日本の身体文化と、その根底にあった精神性を追体験するための鍵である。現代のスポーツや格闘技の視点から見れば、その動きは一見非合理的、あるいは過剰な殺傷性を持つように映るかもしれない。しかし、それらは全て、「死」が常に隣り合わせであった戦国時代のリアリズムに深く根差している。鎧の隙間を打つ「砕き」、あらゆる状況を想定した多彩な武器術、そして殺法と一体であった活法の存在は、現代人が忘れ去った身体の可能性と、生への執着、そして仲間を救うという共同体の倫理観を我々に示唆してくれる。
気楽流を学ぶこと、そしてその武術書を研究することは、単に古い技をなぞる行為ではない。それは、戦国の風を肌で感じ、江戸の武士の矜持に触れ、そして幾多の困難を乗り越えてこの遺産を繋いできた先人たちの想いを受け継ぐ行為である。この貴重な武術遺産が、今後も正しく理解され、一人でも多くの後継者によって未来永劫に継承されていくことを切に願い、本報告書の結びとしたい。
引用文献
- 気楽流柔術 - 伊勢崎市 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kyoikubu/hogo/bunkazaihogo/shitei/mukei/1852.html
- 気楽流柔術 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/283030
- 気楽流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E6%A5%BD%E6%B5%81
- 甲冑を着用した剣術 再考 - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/24215532/
- 甲冑組討と素肌武術 | 本部流のブログ - Motobu-ryu Blog - https://ameblo.jp/motoburyu/entry-12797488677.html
- 殺陣講座48話【組討Kumiuchi】戦国時代を知って楽しむ! The technique of "Kumiuchi" a warring nation - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsfusn-yFk4
- 気楽流とは | 古武道氣樂流柔術練志館水科道場【公式】 https://kirakuryu.amebaownd.com/pages/1285619/profile
- 富田重政の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/maeda/b-toda-masa.html
- 富田重政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF
- 富田重政-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73538/
- 剣豪「名人越後」富田重政と摩利支天山 宝泉寺 https://gohonmatsu.or.jp/toda_shigemasa/
- 當田流剣術 - 弘前市 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/2021-0317-0919-141.html
- 小太刀術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%A4%AA%E5%88%80%E8%A1%93
- 富田重政(とだしげまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF-1094693
- 気楽流 - 上州に伝わる幻の武術 https://www.queststation.com/products/DVD/SPD-7504.html
- 氣樂流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/004/
- DVD 日本の古武道 気楽流柔術 https://www.hiden-shop.jp/SHOP/BCD33.html
- 新町宿-中山道(上州路) - 群馬県:歴史・観光・見所 https://www.guntabi.com/kaidou/nakasen/sin.html
- 中山道六十九次・街道歩き【第10回: 新町→高崎】(その2) - 株式会社ハレックス https://www.halex.co.jp/blog/ochi/20170414-10406.html
- 気楽流柔術 | DVD | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/dvd/dvd376/
- 竹内流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81
- 〔一〕形の目録 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%BD%A2/
- 第7回 古流柔術の技ってどんなん? 柔術ザックリ発展史 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889327767
- 「古武術/伝統武器術」の道場一覧 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guidecat/arms/
- 斎藤武八郎(さいとう ぶはちろう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%AD%A6%E5%85%AB%E9%83%8E-1076845
- 斎藤武八郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%AD%A6%E5%85%AB%E9%83%8E
- 古武道氣樂流柔術練志館水科道場【公式】 https://kirakuryu.amebaownd.com/