磯貝流柔術書査
磯貝流柔術書は謎多き伝書。創始者磯貝次郎左衛門は陳元贇に学びし三浪人の一人なれど、その系譜は不明瞭。戦国期の組討術から柔術への変遷期に消えし流派の証左なり。
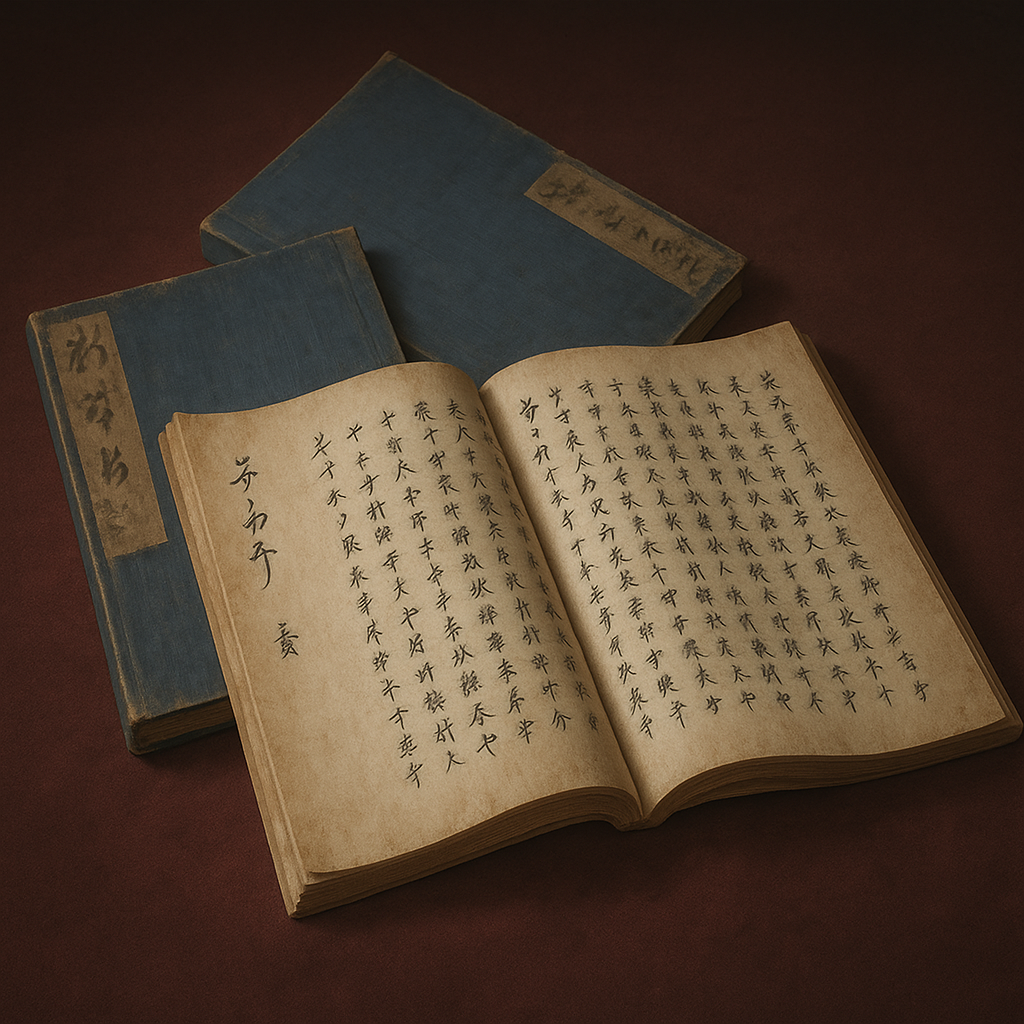
「磯貝流柔術書」の総合的考察:戦国期武術の遺産と江戸初期柔術の黎明
序章:戦国から江戸へ ― 武術の変容と柔術の黎明
日本の武術史において、江戸時代初期は一つの大きな転換期であった。戦乱の記憶が生々しい戦国時代が終焉を迎え、徳川幕府による泰平の世が訪れる中で、武士の在り方そのもの、そして彼らが修める武術の目的と形態は、根源的な変容を迫られた。本報告書は、「磯貝流柔術書」という一つの伝書、及びその創始者とされる磯貝次郎左衛門という人物を主題に据え、彼らが活躍した江戸時代初期という時代を、その直前である「戦国時代」の視座から深く考察するものである。
戦国期の武士にとって、武術とは戦場で敵を討ち、生き残るための実戦技術に他ならなかった。その中核をなすのが、甲冑を着用した状態での近接格闘術である「組討」である 1 。戦場で槍や刀といった主たる武器を失った、あるいは至近距離で乱戦となった際に、敵を組み伏せ、討ち取るための技法であり、後の柔術が持つ投げ技や締め技の直接的な源流となった 1 。また、戦場のみならず、屋内での不意の襲撃などを想定した護身術として、脇差などの短い武器を用いる「小具足」や「腰廻」といった技術体系も発展した 3 。これらは平時における戦闘技術であり、江戸時代の柔術へと繋がる重要な要素を内包していた 5 。
しかし、江戸時代に入り大規模な合戦がなくなると、武士の役割は「戦う者」から「治める者」へと移行し、それに伴い武術の目的も変化した。単なる殺傷技術から、心身を鍛錬し、武士としての道を追求する「術」へと、その価値観がシフトしたのである 6 。この変化は、技術の体系化、理論化、そして精神性の重視を促し、「柔術」という新たな武術概念が確立される土壌となった。
この時代のもう一つの特徴は、主家を失った多くの「浪人」の存在である 8 。彼らは自らの武技を以て生計を立てる、あるいは新たな武術体系を追求するため、数多くの新興流派を創始した。本報告書の主題である磯貝次郎左衛門、福野七郎右衛門、三浦与次右衛門義辰ら「三浪人」の物語は、まさにこの大きな時代の潮流の中に位置づけられる。彼らの活動は、旧来の価値観が通用しなくなった時代における、新たな武士の生き方の模索そのものであったと解釈できる。
以下の略年表は、本報告書で論じる柔術発展の歴史的文脈を概観するものである。
|
年代 |
主要な出来事 |
備考 |
|
天文元年 (1532) |
竹内久盛、竹内流を創始 |
歴史を遡れる最古の柔術流派とされる 6 。 |
|
元和5年 (1619) |
陳元贇、日本へ渡来 |
明末の動乱を避け長崎に来日 10 。 |
|
寛永2年 (1625) 頃 |
国昌寺にて三浪人に拳法を伝授 |
江戸麻布の国昌寺にて、福野、三浦、磯貝に柔術を伝授したとされる 12 。 |
|
安永8年 (1779) |
愛宕山に「起倒流拳法碑」建立 |
「拳法之有傳也、自投化明人陳元贇而始」と刻まれ、陳元贇鼻祖説の根拠となる 12 。 |
|
明治15年 (1882) |
嘉納治五郎、講道館を創始 |
起倒流と天神真楊流を基に講道館柔道を設立 14 。 |
この年表が示す通り、陳元贇の来日以前に日本独自の柔術の源流が存在したことは、柔術の起源を論じる上で極めて重要な前提となる。
第一部:磯貝次郎左衛門と「磯貝流柔術書」の実像
第一章:磯貝次郎左衛門の人物考証
「磯貝」の名を持つ武士として、歴史上、特に著名なのは元禄赤穂事件における赤穂浪士四十七士の一人、「磯貝十郎左衛門正久」(1679-1703)である 16 。しかし、本報告書の主題である柔術家「磯貝次郎左衛門」は、この赤穂浪士とは全くの別人である。両者は生きた時代が重なる部分もあるが、活動内容や経歴から明確に区別されねばならない。この混同は、後世において柔術家・磯貝次郎左衛門の人物像が希薄化する一因となった可能性も否定できない。
柔術家としての磯貝次郎左衛門は、福野七郎右衛門、三浦与次右衛門義辰と共に、明からの渡来人である陳元贇から拳法を学んだ「三浪人」の一人として、その名を武術史に留めている 18 。複数の文献によれば、彼らは寛永年間(1624-1644年)に江戸麻布の国昌寺に寄宿しており、同じく寺に滞在していた陳元贇と出会い、その武術を見聞、あるいは直接指導を受けたとされる 12 。
しかし、三浪人の中でも磯貝次郎左衛門個人の経歴は、最も謎に包まれている。福野七郎右衛門は摂津浪華の生まれで、陳元贇に出会う以前に柳生宗厳(石舟斎)に柳生新陰流を学んだという、一流の武術的背景が伝えられている 21 。また、三浦与次右衛門義辰は江戸の出身とされる 23 。これに対し、磯貝次郎左衛門の出自や、陳元贇に師事する以前にどのような武術を修めていたのかについての具体的な記録は、現存する資料からは見出すことができない。この情報の欠如は、彼の歴史的立ち位置を考察する上で、逆に重要な手がかりとなる。
以下の表は、陳元贇と三浪人の判明している経歴を比較したものである。
|
人物名 |
生没年 |
出身地 |
師事 |
創始流派 |
特記事項 |
|
陳元贇 |
1587-1671 |
中国・杭州府 |
少林寺(伝承あり) |
(伝授者) |
詩文、書、製陶、医学にも通じた文人 13 。 |
|
福野七郎右衛門正勝 |
不詳 |
摂津浪華など諸説 |
柳生宗厳、陳元贇 |
良移心当流(福野流) |
柳生新陰流の素養があった 21 。 |
|
磯貝次郎左衛門 |
不詳 |
不詳 |
陳元贇 |
磯貝流 |
陳元贇に師事する以前の経歴は不明。 |
|
三浦与次右衛門義辰 |
不詳 |
江戸 |
陳元贇 |
三浦流 |
陳元贇に師事する以前の経歴は不明 23 。 |
この対照表が示すように、福野の武術的経歴は他の二人と比較して突出しており、この差が後の流派の発展に決定的な影響を与えた可能性が考えられる。
第二章:「磯貝流柔術書」を巡る謎
磯貝次郎左衛門が著したとされる「磯貝流柔術書」は、その存在自体が極めて曖昧である。調査した資料群の中で、この伝書の名前に具体的に言及しているものは一件のみであった 26 。しかし、この資料も書名を挙げるに留まり、その内容、構成、あるいは現存の有無については一切触れていない。
この情報の乏しさは、福野七郎右衛門の系統である起倒流の伝書と比較すると、一層際立つ。起倒流には『天巻』『地巻』『人巻』『本體』『性鏡』といった体系的な伝書群が現存し、その思想や技法構成は詳細に研究されている 14 。これに対し、「磯貝流柔術書」に関する情報が皆無に近いという事実は、いくつかの可能性を示唆する。
第一に、伝書は作成されたものの、流派が早い段階で断絶、あるいは他の流派に吸収される過程で散逸してしまった可能性である。江戸時代には無数の武術流派が興ったが、その多くは後継者を得られずに歴史から姿を消している 7 。
第二に、そもそも「磯貝流」が、起倒流のように理論化・体系化された伝書を作成するほど、組織的な流派として確立されなかった可能性である。磯貝個人の技芸として、あるいはごく少数の弟子に口伝で伝えられるに留まり、流派としての組織を整える前に活動を終えたのかもしれない。
そして第三に、「磯貝流」という呼称自体が、後世の研究者によって、福野流、三浦流と対比させるために便宜的に用いられたものであり、当事者たちに独立した「流派」としての強い意識が希薄であった可能性も考えられる。
結論として、「磯貝流柔術書」の謎は、単なる一冊の伝書の行方の問題ではなく、磯貝流という流派そのものの盛衰と不可分であると言える。福野七郎右衛門が、自らの武術的素養を基盤に陳元贇の知識を融合させ、一大流派を築き上げた「成功者」であるとすれば、磯貝次郎左衛門は、同じ機会を得ながらも、歴史の傍流に留まらざるを得なかった人物であったのかもしれない。その記録の乏しさこそが、江戸初期における新興武術流派の厳しい生存競争の実態を物語っている。
第二部:陳元贇と日本柔術の起源論
第一章:陳元贇の来日と三浪人への武術伝授
磯貝流柔術の起源を語る上で、その源流とされる陳元贇の存在は不可欠である。陳元贇(1587-1671)は、明末の動乱を避けて元和5年(1619年)に来日した中国・杭州出身の文人であった 10 。彼は単なる武術家ではなく、詩文、書道、製陶(元贇焼)、医学、儒学など、多方面に深い造詣を持つ当代一流の文化人であり、石川丈山や元政上人など、日本の多くの知識人と交流した 11 。彼の武術は、その多彩な才能の一つとして日本にもたらされた。
彼と磯貝ら三浪人との邂逅の舞台となったのが、江戸麻布にあった国昌寺である。寛永2年(1625年)頃、この寺に寄宿していた陳元贇は、同じく寺に身を寄せていた浪人、福野七郎右衛門、三浦与次右衛門義辰、そして磯貝次郎左衛門に、中国の拳法を伝授したとされている 12 。
この伝承を裏付ける最も重要な史料の一つが、「国昌寺文書」である。この文書には、「大明国僧陳元贇於寛永二年四月上旬来居国昌寺、同年十六日向逗留於此之長州道浪人三浦与治右衛門、磯貝次郎右衛門、福野七郎右衛門之人伝授柔術」と、伝授の年月日と三人の名前が具体的に記されている 12 。これは、陳元贇が日本の柔術形成に直接的に関与したことを示す、同時代に近い貴重な記録である。
さらに、後世における陳元贇の評価を決定づけたのが、安永8年(1779年)に起倒流の関係者によって江戸の愛宕神社に建立された「起倒流拳法碑」である 12 。この石碑には、「拳法之有傳也、自投化明人陳元贇而始」(拳法の伝わりしは、化に投じた明人・陳元贇より始まる)と明確に刻まれている 6 。この碑文は、陳元贇を日本拳法、ひいては柔術の「鼻祖(始祖)」とする説の強力な物的証拠として、後々まで大きな影響力を持つことになった。
第二章:「柔術鼻祖説」の多角的検証
陳元贇を日本柔術の始祖とする「鼻祖説」は、上記の国昌寺文書や拳法碑を根拠として、江戸時代を通じて広く信じられてきた。丸山三造の『大日本柔道史』や原念斎の『先哲叢談』といった文献も、この説を支持している 12 。外来の先進文化への憧憬や、自らの流派の権威を高めたいという門人たちの意図も、この説が流布する背景にあったと考えられる 8 。
しかし、近代的な武道史研究の進展に伴い、この「鼻祖説」は多角的な検証に晒されることとなる。
第一の批判的見解は、陳元贇の来日以前に、日本にはすでに柔術の源流となる武術が存在したという事実である。その代表が、天文元年(1532年)に成立した竹内流である 5 。竹内流は「捕手腰廻小具足」を中核とする総合武術であり、その技術体系は戦国時代の組討術から発展した、紛れもない日本固有のものであった。したがって、「陳元贇が来るまで日本に柔術はなかった」という前提は、史実とは異なる。
第二に、陳元贇自身の言葉とされる記述が、彼の役割に疑問を投げかける。江戸時代の書物『大和事始』には、陳元贇が三浪人に語った言葉として、「明国に擒拿之術有り、我此の術を嫻(なら)はずと雖も、亦常に之を見る」(明国には人を捕らえる術がある。私はこの術を専門に学んだわけではないが、常々目にはしている)と記されている 8 。この記述が事実であれば、彼は専門的な武術指導者として体系的な技術を伝授したのではなく、見聞として中国拳法の概要や原理を語ったに過ぎない可能性が出てくる。
これらの検証を踏まえると、陳元贇の歴史的役割は、「無から有を生んだ創始者(鼻祖)」として絶対視するのではなく、むしろ「既存の日本武術に新たな刺激を与え、その発展を促した触媒」として捉え直すのが妥当であろう。彼が伝えた技術は、突きや蹴りを主体とする「当身」や、人体の急所に関する知識、蘇生術を含む「殺活法」といった、当時の日本の組討術には比較的手薄であった要素であった可能性が指摘されている 8 。戦国時代以来の日本の組討術という土壌に、陳元贇がもたらした大陸の拳法という新たな種が蒔かれ、福野ら日本の武術家たちの手によって、起倒流をはじめとする新たな柔術の流派が花開いた。磯貝次郎左衛門と「磯貝流」もまた、この歴史的交配の過程で生まれた、無数の試みの一つであったと位置づけることができる。
第三部:戦国期の遺産と江戸初期柔術の成立
第一章:源流としての竹内流 ― 戦国期組討の体系化
江戸初期の柔術の成立を「戦国時代」の視点から考察する上で、陳元贇の影響とは別に、日本独自の武術の系譜を理解することが不可欠である。その筆頭に挙げられるのが、竹内流である。天文元年(1532年)、竹内中務大輔久盛によって創始されたこの流派は、歴史を遡ることが可能な最古の柔術流派として、武道史において極めて重要な位置を占めている 5 。
竹内流の正式名称は「竹内流捕手腰廻小具足」といい、その名の通り、中核技術は「捕手」と「腰廻小具足」である 4 。これらは、戦国期に想定された多様な戦闘状況に対応する実戦的な技術体系であった。特に「腰廻小具足」は、脇差などの短い刀を抜くか抜かないかの間合いで、不意の襲撃から身を守り、敵を制圧するための技法であり、平時や屋内での戦闘を想定している点に特徴がある 3 。
さらに特筆すべきは、「羽手(はで)」と呼ばれる素手の技法群である 35 。これは小刀を持たない状態での組討術であり、小具足の技法と表裏一体のものとして発展した 35 。竹内流の存在は、陳元贇が来日する遥か以前から、日本において素手による格闘術が高度に体系化され、理論化されていたことを明確に示している。それは、戦国時代の過酷な実戦経験から生まれた、純然たる日本の武術の遺産であった。
第二章:起倒流の成立と発展 ― 陳元贇の影響の具体化
陳元贇の影響を最も色濃く受け、後世に大きな影響を与えた流派が起倒流である。この流派の成立過程は、日本の伝統武術と大陸からの新知識が如何に融合したかを具体的に示す好例と言える。
流祖とされる福野七郎右衛門は、前述の通り柳生新陰流の素養を持つ優れた武術家であった 21 。彼は陳元贇から学んだ拳法を自らの武術体系に取り入れ、「良移心当流」を創始した 37 。その後、弟子の寺田勘右衛門正重らによって改良が加えられ、「起倒流」と改名されたと伝えられる 22 。
起倒流の技術的特徴は、そのルーツに戦国時代の甲冑組討の記憶を色濃く留めている点にある。その技法は「戦場甲冑技法から高度な投げ技、捨て身技を完成させた」ものと評され 22 、その形(かた)には「錣取(しころどり)」や「錣返(しころがえし)」といった、甲冑の部位に由来する名称が残っている 14 。これは、起倒流が単なる素肌の武術ではなく、戦国期の組討術を直接の母体としていることを示している。
この日本古来の組討術を基盤としながら、陳元贇から伝わったとされる拳法、すなわち当身や活法といった要素が加わることで、起倒流独自の技術体系が完成したと考えられる 6 。まさに、戦国期の遺産と大陸からの新知識が見事に融合した成果であった。
この起倒流の優れた体系は、後に講道館柔道を創始した嘉納治五郎によって高く評価された。嘉納は起倒流の形を「古式の形」として講道館の体系に組み込み、その技と精神は現代柔道にまで脈々と受け継がれている 22 。
第三章:磯貝流、三浦流の歴史的位置づけ
福野の起倒流が詳細な伝書と明確な系譜を持ち、現代に至るまでその影響を残しているのとは対照的に、同じく陳元贇に学んだ磯貝次郎左衛門の「磯貝流」と三浦与次右衛門義辰の「三浦流」は、歴史の表舞台から姿を消した。彼らがそれぞれ流派を興したという記録は存在するものの 19 、その具体的な技法体系や、どのような弟子に受け継がれたのかを伝える史料は極めて乏しい。
この差異は、どこから生まれたのか。一つの可能性として、前述した各人の武術的素養の違いが挙げられる。柳生新陰流という確固たる基盤を持っていた福野は、陳元贇の知識を自らの体系に効果的に組み込み、理論化することができた。一方、磯貝と三浦にはそのような背景がなく、新たな知識を体系的な「流派」として確立し、後進に伝えていく上で困難があったのかもしれない。
武術流派が存続し発展するためには、独創的で合理的な技術体系、それを明文化した伝書、そして有能な後継者という三つの要素が不可欠である。江戸時代には、これらの要素のいずれかを欠いたために、創始者一代限りで消滅したり、より隆盛した流派に吸収されたりした無数の流派が存在した 7 。磯貝流と三浦流もまた、隆盛を極めた起倒流や、その他の柔術流派の陰で、同様の道を辿った可能性が高い。
したがって、磯貝流の歴史的位置づけは、「柔術の黎明期に、大陸文化の影響を受けて生まれた無数の試みの一つであり、歴史の淘汰の過程で消えていった一事例」として捉えるのが最も妥当であろう。
結論:「磯貝流柔術書」が映し出す武道史の転換点
本報告書は、「磯貝流柔術書」という謎多き主題を起点とし、その創始者とされる磯貝次郎左衛門、彼に拳法を伝えた陳元贇、そして彼らが生きた江戸時代初期という時代を、「戦国時代」という視座から多角的に考察してきた。
結論として、磯貝次郎左衛門と彼が創始したとされる「磯貝流」は、具体的な一つの流派として歴史に明確な足跡を残すことはなかった。しかし、その存在は、日本の武道史における極めて重要な転換点を象徴している。すなわち、戦国時代の「組討」という実戦武術が、泰平の世を迎え、陳元贇がもたらした大陸からの新たな知識という触媒を得て、理論化・体系化された「柔術」へと変貌を遂げる、まさにその過渡期に生きた一人の武術家の挑戦の証左である。
陳元贇の役割についても、再評価が必要である。彼は日本柔術の「父」ではなかったかもしれないが、その発展を促した「産婆役」の一人であったことは間違いない。彼の存在が、福野や磯貝といった日本の武術家たちに内省と革新の機会を与え、結果として柔術の多様性と深化を促したことは、歴史が証明している。
「戦国時代という視点」からこの時代を俯瞰するとき、江戸初期の柔術は、戦国という時代の「死の記憶」を色濃く内包しつつ、新たな時代を生き抜くための「生の哲学」を模索する中で生まれた、文化的な創造物であったことがわかる。「磯貝流柔術書」という、今やその内容を知ることのできない伝書の存在は、その壮大な歴史の一幕を構成する、ささやかだが示唆に富んだ挿話として、我々に武道史の奥深さを教えてくれる。
本調査は、現時点で公開されている文献資料に基づいて行われた。未発見の私文書や地方の郷土史料の中に、「磯貝流」に関する新たな記述が眠っている可能性は依然として残されている。今後の研究による新史料の発見が、この謎多き柔術流派の姿を、より鮮明に照らし出すことを期待したい。
引用文献
- 体術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113209/
- 柔術(柔道)と剣術(剣道)/ホームメイト - 柔道チャンネル https://www.judo-ch.jp/jujitsu_and_fencing/
- 第13話 相撲・組討・捕手・小具足・腰廻 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888332041
- 竹内流捕手腰廻小具足 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/
- 竹内流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81
- 柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E8%A1%93
- 江戸時代の剣術 - 「剣客商売」道場 http://kenkaku.la.coocan.jp/kenzyutu/kenzyutu.htm
- 【日本武術軼聞】這就是日本的起倒流了! - 方格子 https://vocus.cc/article/6280cd1efd897800013130eb
- 柔術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113207/
- 陳元贇(チンゲンピン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%99%B3%E5%85%83%E8%B4%87-18961
- 陳元贇 | 日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nipponica/sample_koumoku.html?entryid=3428
- 日本柔道“鼻祖”陈元赟考辨_参考网 https://m.fx361.com/news/2019/1125/11605896.html
- 陳元贇- 何創時雲端博物館 https://www.hcsartmuseum.com/authors/9997/
- 起倒流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81
- 柔術とは?柔術の派生や歴史について - IKEHIKO DIGITAL https://ikedigi.info/contents/purchase/knowlege/culture/2091/
- 磯貝十郎左衛門の画像、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 江戸ガイド https://edo-g.com/men/view/295
- 礒貝正久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%92%E8%B2%9D%E6%AD%A3%E4%B9%85
- 磯貝次郎左衛門(いそがいじろうざえもん)とは? 意味や使い方 ... https://kotobank.jp/word/%E7%A3%AF%E8%B2%9D%E6%AC%A1%E9%83%8E%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80-1268878
- 歴史 – 総合拳法 - Sogo Kempo https://www.sogokempo.org/ja/history-3/
- 柔術(ジュウジュツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9F%94%E8%A1%93-77051
- 福野七郎右衛門(ふくの しちろうえもん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E9%87%8E%E4%B8%83%E9%83%8E%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80-1104951
- 起倒流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/009/
- 三浦義辰(みうら よしとき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%BE%A9%E8%BE%B0-1112008
- 陳元贇- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%99%88%E5%85%83%E8%B5%9F
- 第十三章陳元贇——日本柔道的祖師 - 九九藏書 https://read.99csw.com/book/4747/169735.html
- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html
- 近世における起倒流柔術の歴史的実態 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/23905/files/NingenkagakuKenkyu_20_00_110_Nakajima.pdf
- 起倒流伝書 『天巻』 - 遊戯・スポーツ文化研究所 - ココログ http://sports-culture.cocolog-nifty.com/supojin/2016/12/post-44b2.html
- 古武道と現代武道/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/kobudo/
- 陳元贇 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B3%E5%85%83%E8%B4%87
- 陳元贇の伝記及び江戸初期の日中文化交流についての一考察 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/22865/files/meta_10_46.pdf
- 陳元贇について https://chenyuanyun.jp/about.html
- 名前 陳元贇 よみ ちんげんぴん 生年 天正十五(一五八七) 没年 寛文十一年六月九日(一六七一) 場所 愛知県名古屋市千種区 分類 陶芸・医者・漢学者・柔術 略歴 - 日本掃苔録 https://soutairoku.com/01_soutai/04-2_ti/10-2_n/tin_genpin/tin_genpin.html
- 竹内流の技術名称 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/7800/files/kyouyoronshu_258_39.pdf
- 〔一〕形の目録 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%BD%A2/
- 稽古の内容 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=93
- 良移心当流(りょういしんとうりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%89%AF%E7%A7%BB%E5%BF%83%E5%BD%93%E6%B5%81-1607333
- 良移心当流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E7%A7%BB%E5%BF%83%E5%BD%93%E6%B5%81
- 古武道歴史探訪 第十三回 2023年4月 - 貫汪館大阪支部 居合|剣術|柔術 https://kanoukan-kita-osaka.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E6%AD%A6%E9%81%93%E6%8E%A2%E8%A8%AA/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%9B%9E-2023%E5%B9%B44%E6%9C%88/
- 起倒流組討の形 https://nousojudo.sakura.ne.jp/kitoryujujutsu.html
- 嘉納治五郎の柔術修行とその展開に関する研究 - 工学院大学機関リポジトリ https://library-kogakuin.repo.nii.ac.jp/record/2001028/files/07-kiryu.pdf
- 形 - 講道館 https://kdkjudo.org/%E6%8A%80/685-2/
- 期刊篇目查詢-詳情 https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/JournalContentDetail?SysId=A01042091
- 槍術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8D%E8%A1%93