農業全書
『農業全書』は宮崎安貞が著した近世農学の金字塔。戦国期の技術革新と兵農分離で生まれた農民層を背景に、中国の知識を日本に合わせ体系化。農民の利益を重視し、江戸の平和と生産を支えた。
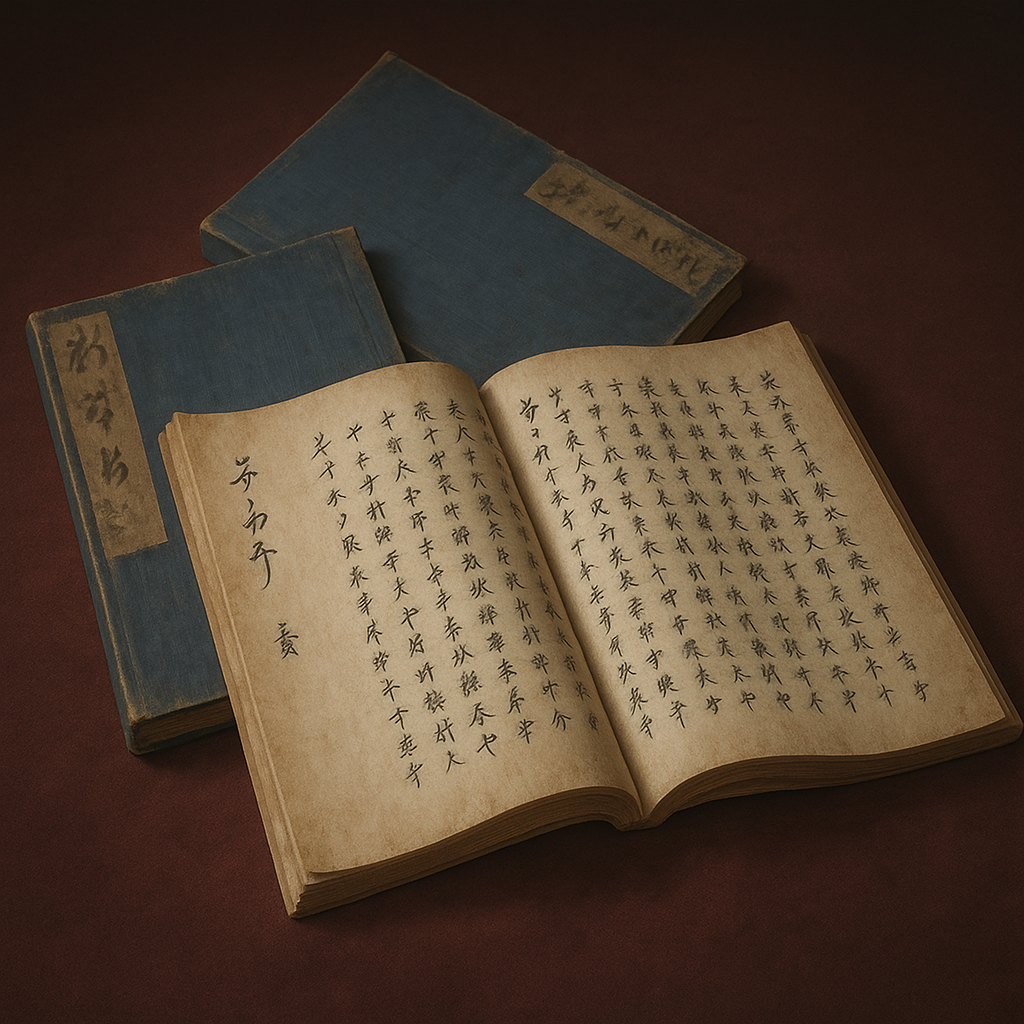
戦国という視座から読み解く『農業全書』:近世農学の成立と歴史的意義
序論:江戸の知の源流を求めて
元禄10年(1697年)、一冊の書物が世に出た。宮崎安貞が著し、貝原益軒らがその刊行を助けた『農業全書』である 1 。全11巻に及ぶこの大著は、日本で初めて農業技術を網羅的かつ体系的に解説した本格的農書として、後世に絶大な影響を与えた。刊行されるや否や、施政者から現場の農民まで広く受け入れられ、長く日本の農書の規範とあり続けたのである 3 。
しかし、この画期的な書物は、徳川の泰平の世に突如として生まれたものではない。その思想的・技術的根源は、直前の時代、すなわち百年にわたる戦乱の時代、戦国時代に深く根差している。通説では江戸時代の産物として静的に評価されがちな『農業全書』を、本報告書では、戦国の動乱が生み出した社会構造の変化と技術革新という「遺産」を、近世という新たな社会秩序に向けて再編・体系化した「歴史的産物」として捉え直す。この視座に立つことで、本書は単なる農業技術の解説書ではなく、戦乱のエネルギーを生産のエネルギーへと転換させた、日本近世社会の成立を象徴する記念碑的著作として、その真の歴史的意義を現すであろう。
第一章:『農業全書』を生み出した土壌 ― 戦国時代の農業革命
本章では、『農業全書』が成立する前提となった戦国時代の社会・技術的状況を詳述する。一見、破壊と混乱の時代に見える戦国期が、逆説的にも農業の発展を促し、近世的な農民社会の礎を築いた過程を明らかにすることで、来るべき農学体系の土壌がいかにして形成されたかを探る。
第一節:戦乱と富国強兵が拓いた農業基盤
戦国時代、米は単なる食糧ではなかった。それは兵を養う兵糧であり、経済活動の根幹をなす戦略物資であった 4 。領国の富と軍事力は米の生産量に直結するため、戦国大名たちは自らの勢力拡大のために、稲作の振興と生産性の向上に死活的な関心を寄せた 4 。この時代の戦争において、敵国の田畑を刈り取って兵糧を奪い、相手の国力を削ぐ「刈田狼藉(かりたろうぜき)」が常套手段であった事実は、食糧生産がいかに戦争と不可分であったかを物語っている 5 。このような過酷な生存競争の環境こそが、各大名に安定した食糧生産体制の構築を強く動機付けたのである。
その結果、多くの大名は「富国強兵」策の一環として、領内の農業基盤整備に積極的に乗り出した。武田信玄が甲斐国で築いたとされる信玄堤、佐々成政が越中で行った治水事業「佐々堤」 6 、そして熊本に入封した加藤清正による大規模な河川改修 6 など、各地にその痕跡が残る。彼らは、築城や鉱山開発で培われた当代最新の土木技術を、治水や灌漑、新田開発といった農業インフラの整備に大胆に応用したのである 7 。
特に水利の確保は最重要課題であった。各地で溜池の造成や用水路の開削が進められ、水の安定供給が図られた。豊臣政権下で片桐且元が手がけた狭山池の大改修では、貯水量を増やすだけでなく、配水地区と時間を定めた「水割符帳」を作成し、水の利用を厳密に管理するシステムが導入された 8 。また、加賀藩前田家が金沢城下の用水確保のために開削した辰巳用水も、この時代の高度な灌漑技術を示す好例である 8 。これらの事業は、個々の農民の努力だけでは不可能な、大名という強力な権力による広域的な資源管理の始まりであった。戦国大名の軍事・経済的要請から始まったこれらのインフラ整備は、結果として、後の江戸時代における安定的かつ集約的な農業生産を可能にする、不可欠な物理的条件を創出したのである。
第二節:社会構造の変革と「農民」の誕生
戦国時代は、日本の社会構造が根底から覆された時代でもあった。この変革の中心にあったのが、土地制度と身分制度の再編成である。
奈良時代以来、日本の土地制度は、権門寺社や貴族が支配する荘園制によって特徴づけられてきた。そこでは土地の所有権や収税権が複雑に入り組み、生産者である農民と領主の関係は重層的で不透明であった 9 。この旧来の制度は、戦国大名が領国を一元的に支配する上で大きな障害となった。彼らは領内の実効支配を強める中で荘園制を侵食し、最終的に豊臣秀吉が断行した太閤検地によって、この制度は完全に解体されるに至った 9 。
太閤検地は、それまでの指出検地のような自己申告制とは一線を画し、全国統一の基準(精度の高い検地竿が用いられた 12 )によって全ての田畑・屋敷地を測量し、その土地の米の標準収穫量、すなわち「石高(こくだか)」を算定した 9 。そして、その土地を実際に耕作する農民を検地帳に登録し、年貢を納める義務を負う者として法的に確定させたのである 9 。これにより、「一地一作人」の原則が確立され、領主と農民は直接結びつくことになった 10 。
この土地制度改革と並行して進められたのが、織田信長に始まり秀吉が刀狩令や身分統制令によって完成させた「兵農分離」である 9 。それまでの武士は、農繁期には農作業に従事する半農半兵の存在が多数を占めていた 14 。兵農分離は、武士を城下町に集住させて戦闘に専念させ、農民からは武器を取り上げて農業生産に専念させる政策であった。これにより、農民は土地に縛り付けられ、武装蜂起(一揆)の力を削がれると同時に、農業生産を担う専門の身分として社会的に固定化された 9 。
この一連の社会大変革がもたらした歴史的な帰結は、単に支配体制が強化されたという点に留まらない。それは、日本の歴史上初めて、農業生産を「専門職」とする巨大な社会階層を創出したことを意味する。もはや彼らは、戦があれば駆り出される兵士ではなく、土地に根差し、石高という客観的な数値で示される生産責任を負う、いわば「プロの農業経営者」としてのアイデンティティを付与された存在となった 13 。この新たな社会階層の出現は、自らの生産活動をより効率的かつ合理的に遂行するための、体系化された知識、すなわち「教科書」に対する潜在的な需要を爆発的に高めることになった。
元禄期に刊行された『農業全書』が広く受け入れられた背景には、その内容の卓越性もさることながら、戦国末期の社会大変革によって、まさにその「読者」となるべき人々が歴史の舞台に登場したという、この絶妙なタイミングが存在した。本書は、この新しい農民層の知的好奇心と経営改善への渇望に応えるべくして生まれたのである。
第三節:戦国期における農業技術の胎動
戦乱の時代は、技術革新の時代でもあった。絶え間ない食糧需要と労働力不足は、単位面積当たりの収量を高め、作業効率を向上させる技術への強い要請を生み出した。
農具の分野では、従来よりも深く土を耕すことを可能にした「備中鍬(びっちゅうぐわ)」が普及し始めた 16 。複数の鉄製の刃を持つこの鍬は、硬い土地や荒れ地の開墾にも威力を発揮し、土地生産性の向上に大きく貢献した。近世の新田開発の広がりは、こうした改良農具の登場によって可能になった側面が大きい 16 。
施肥技術もまた、大きな進歩を遂げた。従来の刈敷(かりしき)や草木灰(そうもくばい)といった自給肥料に加え 17 、鎌倉時代末期から都市部で利用され始めた人糞尿、すなわち「下肥(しもごえ)」が、戦国時代には一般的な肥料として広く使われるようになった 19 。これは、二毛作・三毛作の進展などによって土地からの収奪が激しくなる中で、地力を維持・向上させるための必然的な流れであり、より集約的な農業への移行を示す重要な指標である。
作物の種類も多様化した。米と麦の二毛作は各地に広まり、畿内などの先進地域ではソバなどを加えた三毛作も行われるようになった 21 。また、度重なる洪水によって稲作が困難になった河川沿いの土地では、代替作物としてソバが栽培されたり、さらには商品作物であるアブラナ(菜種)や綿花などが栽培されたりする例も現れた 22 。これは、農家が自給自足経済から、市場を意識した商品経済へと足を踏み出し始めた兆候である。越後の上杉氏が青苧(あおそ、麻の原料)の専売で莫大な利益を上げたように 24 、特定の作物が大名の重要な財源となるケースも見られ、農業が経済戦略の中に明確に位置づけられていった。これらの技術的・経営的な萌芽は、まだ断片的ではあったが、来るべき時代に体系化されるべき貴重な知見の蓄積であった。
第二章:近世農学の金字塔『農業全書』の全貌
戦国という激動の時代を経て、徳川の治世が安定期に入った元禄期に、『農業全書』は誕生した。本章では、この書物そのものに焦点を当て、著者たちの人物像、書物の構成、そしてその知識の源泉を詳細に分析することで、本書が持つ独自の価値と歴史的位置を浮き彫りにする。
第一節:著者たちの肖像 ― 宮崎安貞と貝原兄弟
『農業全書』の著者として記されているのは、宮崎安貞ただ一人である 2 。しかし、この大著の成立には、当代随一の碩学、貝原益軒・楽軒兄弟の協力が不可欠であった 1 。
主著者である宮崎安貞(1623-1697)は、安芸国(現在の広島県)出身の武士であった 2 。一時は福岡藩に仕官するも、わずか5年でその職を辞し、30歳で自ら浪人となって農業研究の道に進むという、異色の経歴を持つ 1 。彼は現在の福岡市西区周船寺に居を構えると、単に書斎で研究するのではなく、自ら鍬を手に取り土にまみれながら、実践を通じて農業技術を体得していった 25 。その探求心は自らの田畑に留まらず、諸国を巡って畿内地方などの先進的な農法を見聞し、さらには私財を投じて新田開発を行うなど、地域の農業発展にも尽くした 25 。彼の知識は、汗に裏打ちされた徹底した実践知であった。
一方、本書の序文と出版に深く関わった貝原益軒(1630-1714)は、福岡藩に仕える儒学者であり、本草学(博物学)、自然科学にも通じた知の巨人であった 26 。彼は書物から得た知識だけでなく、自らの足で各地を旅し、見聞を記録する実証的な学問態度を貫いた学者として知られる 26 。安貞は、藩命による京都遊学の際に益軒と出会い、その学識と知見に触れたことが、『農業全書』の執筆へと繋がった 2 。益軒は本書に序文を寄せ、その兄である貝原楽軒は巻末に農政論としての付録を執筆した 3 。彼らの協力は、安貞の実践知に学術的な体系性と権威を与え、本書を単なる一農夫の経験談から、普遍的な農学書へと昇華させる上で決定的な役割を果たした。
宮崎安貞の「武士から浪人、そして篤農家へ」という生涯は、一個人の特異な経歴としてのみならず、戦国から江戸へと移行する時代の大きな価値観の転換を象徴するものとして捉えることができる。武力による立身出世が社会の中心であった時代が終わりを告げ、生産活動こそが社会の基盤となる泰平の世が到来した。安貞が刀を鍬に持ち替えて生きたその軌跡は、この社会全体のエネルギーのベクトルが「闘争」から「生産」へと転換したことの縮図に他ならない。彼が元武士であったという事実は、本書に二重の権威を付与した。武士階級としての教養と、農民の現場に深く身を投じた実践者としての経験。この二つを兼ね備えた彼の言葉だからこそ、支配者である武士階級と、生産を担う農民階級の双方に対して、強い説得力を持ち得たのである。安貞という人物の存在そのものが、『農業全書』が内包する実践性と体系性の奇跡的な融合を体現していたと言えよう。
第二節:書物の構成と体系
『農業全書』は、全11巻10冊からなる壮大な体系を持つ 3 。その構成は、農家の生産活動と生活世界の全体を網羅しようとする、百科全書的な意図を明確に示している。
巻一の「農事総論」では、農業に取り組む上での心構え、土地の選定法、天候の見方、農具の解説など、農業全体に通底する基本原則が説かれる。続く巻二から巻十にかけては、具体的な品目別の栽培法が詳述される。巻二「五穀之類」では稲や麦といった主食、巻三・四「菜之類」では大根や茄子などの日常的な野菜、巻五「山野菜之類」ではワラビやウドといった山菜の利用法が扱われる。さらに、巻六「三草之類」では綿・藍・麻・煙草といった工芸作物や商品作物、巻七「四木之類」では桑・茶・漆など、巻八「菓木之類」では柿・栗などの果樹、巻九「諸木之類」では杉・檜などの用材と、その対象は広範にわたる。最終巻の巻十では、牛馬や鶏などの家畜飼育法(生類養法)や薬草(薬種之類)にまで言及しており、まさに農村生活の全てを視野に入れている 3 。
本書の最大の特徴は、その徹底した実践主義にある。各品目の解説は、耕作農民の視点に立ち、種まきの時期から土壌の選び方、施肥の方法、病害虫対策に至るまで、具体的かつ詳細に記述されている 3 。特に、鍬や鋤といった農具の形状や使用法を図を多用して解説している点は画期的であった 3 。これにより、必ずしも識字率が高くなかった当時の農民にも、内容が直感的に理解できるよう工夫されていた。
そして、巻十一は貝原楽軒の筆による「附録」となっており、個々の農家の技術論を超えて、国政や藩政を担う為政者の立場から、いかに農業を振興し、農民を保護すべきかという農政のあり方を論じている 3 。これは、本書が単なる技術指導書に留まらず、農業こそが国家経営の根幹であるという、近世社会の根本思想を体現する書物であったことを示している。
以下の表は、『農業全書』全11巻の構成をまとめたものである。この構成を見れば、本書が単なる稲作技術書ではなく、農家の生活世界全体を包括する知識体系であることが一目で理解できる。
表1:『農業全書』全十一巻の構成と概要
|
巻数 |
主題 |
主な内容 |
|
巻一 |
農事総論 |
農業の心構え、土地の選定、時候、農具など、農業全体の基本原則。 |
|
巻二 |
五穀之類 |
稲、麦、粟、黍、豆など主要穀物の栽培法。 |
|
巻三 |
菜之類(上) |
大根、蕪、瓜など、日常的な野菜の栽培法。 |
|
巻四 |
菜之類(下) |
茄子、葱、筍など、その他の野菜の栽培法。 |
|
巻五 |
山野菜之類 |
蕨、薇、独活など、山野に自生する食用植物の採取と利用法。 |
|
巻六 |
三草之類 |
綿、藍、麻、煙草など、工芸・商品作物の栽培法。 |
|
巻七 |
四木之類 |
桑、楮、漆、茶など、生活に有用な樹木の栽培法。 |
|
巻八 |
菓木之類 |
柿、栗、梨、桃など、果樹の栽培と管理法。 |
|
巻九 |
諸木之類 |
杉、檜、松、竹など、用材となる樹木の育成法。 |
|
巻十 |
生類養法・薬種之類 |
牛、馬、鶏などの家畜飼育法と、薬草の栽培・利用法。 |
|
巻十一 |
附録(貝原楽軒筆) |
為政者の立場から、農業政策の重要性や農民保護を論じる農政論。 |
第三節:知識の源泉 ― 『農政全書』との主体的対峙
『農業全書』の知識体系を考える上で、中国明代末期に徐光啓が編纂した農学の大著『農政全書』からの影響は無視できない 3 。『農政全書』は、中国歴代の農書を集大成したものであり、当時の東アジアにおいて最高峰の農業知識体系であった。宮崎安貞もこの書物を参照したことは確実視されている。
しかし、『農業全書』の価値は、その影響を単なる模倣や翻訳に留めなかった点にある。宮崎安貞が取った態度は、中国の先進的な知識を鵜呑みにするのではなく、それを日本の気候、風土、そして社会の実情に照らし合わせ、「日本で実践してみて利益となるもの」を厳しく取捨選択するという、極めて主体的かつ実証的なものであった 29 。彼は、中国の知識を日本の現場で自ら試し、その有効性を確認したものだけを自らの書物に採用した。このため、『農業全書』は『農政全書』に比べて為政者向けの民政的な色彩が薄く、あくまで耕作農民の立場に寄り添った実践的な耕作技術書としての性格を徹底している 29 。
安貞のこの態度は、単なる編集方針の違いを超えた、より深い意味を持っている。それは、長らく先進文明の源泉として絶対視されてきた中国の知識体系に対し、日本の現場で試行錯誤の末に培われた在来の知見(在来知)の価値を対等に置き、日本の農民にとっての「実利性」という新たな基準で知識を再評価・再構築しようとする、知的な「自立」の試みであった。
これは、政治の世界における豊臣秀吉の天下統一や徳川幕府の成立が、中国を中心とした従来の華夷秩序から距離を置き、日本独自の政治秩序を確立したことに呼応する動きと見ることができる。戦国時代を通じて、各大名領で、あるいは個々の農民レベルで蓄積されてきた、日本の多様な風土に根差した無数の農法や工夫。それらを、外来の権威に依拠することなく、日本の現実という土俵の上で統合し、普遍的な知識体系へと昇華させること。それこそが『農業全書』が成し遂げたことであった。その意味で、本書は農業知識の世界における「天下統一」と、中国からの「知的独立」を成し遂げた、画期的な書物であったと評価できる。
第三章:戦国の遺産、江戸の体系 ― 『農業全書』に見る連続と発展
本章では、第一章で示した戦国時代の「土壌」と、第二章で分析した『農業全書』という「果実」を具体的に結びつける。戦国期に生まれ、あるいは広まった技術や社会システムが、本書の中でいかにして体系化され、平和な江戸時代の社会論理へと昇華されたのかを論証する。
第一節:技術の集大成
『農業全書』に記述された技術は、戦国時代にその萌芽が見られたものを、江戸時代の安定した社会を前提に、より合理的で体系的な形に整理し直したものが数多く含まれている。
例えば、耕耘技術においては、戦国期に普及し始めた備中鍬による深耕が、土地の生産性を高める基本的な技術として推奨されている。施肥に関しても、戦国期に一般化した下肥の利用が前提とされ、その効率的な製造法(堆肥化)や、土壌や作物に応じた合理的な使用法が詳細に解説されている 19 。これらは、戦国期に生まれた集約的農法の技術的萌芽が、『農業全書』によって、誰もが実践可能な標準的農法として確立されたことを示している。
また、本書がまさに農業技術の大きな転換期に成立したことを物語る象徴的な事例が、脱穀具の記述に見られる。本書の口絵には、古くからの脱穀具である「扱箸(こきはし)」が描かれている 31 。これは二本の竹の棒で稲穂を挟んで籾をしごき落とす道具で、非常に手間のかかるものであった 32 。一方で、本書が刊行された元禄年間には、鉄の歯を櫛状に並べた画期的な新農具「千歯扱き(せんばこき)」が発明され、普及し始めていた 32 。千歯扱きは、扱箸に比べて作業効率を10倍以上に高めたとされ、その後の日本の農業生産性を飛躍的に向上させた 33 。『農業全書』が最新の千歯扱きではなく、旧来の扱箸を掲載しているという事実は、本書が長年の経験知の集大成であると同時に、まさに技術の過渡期に成立したことを示唆している。
さらに、商品作物栽培への目配りも重要である。戦国期にその萌芽が見られた綿、菜種、藍、麻といった商品作物の栽培法について、本書は「三草之類」として独立した巻を設けて詳述している 3 。これは、農家経営の基本をあくまで自給食糧の確保に置きつつも 3 、貨幣経済の浸透という時代の大きな流れを的確に捉え、農家が現金収入を得るための道を具体的に示そうとする視点があったことを示している。特に、肥料としてイワシを干した「干鰯(ほしか)」のような購入肥料(金肥)の利用法に触れている点 34 は、農業が自給自足の閉じた世界から、市場経済のネットワークへと組み込まれていく時代の変化を鋭敏に反映している。
以下の表は、本報告書の中心的な論旨である、戦国期から『農業全書』への技術と社会の連続性を示すものである。
表2:戦国時代から『農業全書』に至る主要農業技術の変遷
|
技術分野 |
戦国期の状況(課題と萌芽) |
『農業全書』における体系化(解決と発展) |
|
土地基盤 |
大名による軍事・経済目的の治水、新田開発が散発的に行われる 6 。 |
安定した社会を前提とした、計画的な土地改良や水利管理の重要性を説く。 |
|
耕耘 |
深耕が可能な備中鍬が普及し始める 16 。土地生産性向上の可能性が生まれる。 |
備中鍬などの改良農具の使用を前提とし、土壌に応じた耕耘法を詳細に解説。 |
|
施肥 |
刈敷・草木灰に加え、下肥が一般化 19 。集約化が進むが、知識は未整理。 |
下肥、草木灰、厩肥などの有機肥料の効率的な製造・利用法を体系的に記述。干鰯など金肥にも言及 34 。 |
|
脱穀 |
扱箸(こきはし)が主流で、労働集約的 31 。 |
扱箸を記述しつつも、同時代に千歯扱きが登場 32 。労働生産性向上の大きな転換期に位置する。 |
|
社会制度 |
兵農分離・検地により「専門職としての農民」が誕生 9 。知識への需要が生まれる。 |
この新たな農民層を読者とし、彼らの経営安定と利益増進を目的とした実践的知識を提供する 3 。 |
第二節:農民へのまなざし ― 支配者の視点から耕作者の視点へ
『農業全書』が持つ最も本質的な新しさは、その技術内容もさることながら、農業と農民に対する「まなざし」の転換にある。
第一章で見たように、戦国大名の農業政策は、その動機において、あくまで「富国強兵」という領主側の論理が最優先されていた 4 。農民は、石高を生み出し、兵糧を供給するための生産単位として捉えられていた。しかし、『農業全書』は、その序文から一貫して「耕作農民の立場」に立ち 3 、「農家の利益」をいかにして最大化するかという視点から、全ての技術と心得を説いている 3 。そこには、農民を単なる収奪の対象ではなく、自らの才覚と労働によって富を生み出す、主体的な経営者として捉える視点が存在する。
例えば、当時の商品作物生産の隆盛という風潮に対し、本書がまずもって自給食糧の確保を優先するよう繰り返し説いている点 3 は、その思想を象徴している。これは、目先の現金収入に目がくらんで投機的な作物に手を出し、凶作などで食糧を失うリスクを戒めるものである。戦国時代の飢饉の記憶がまだ生々しい中で 5 、農家経営の基盤安定こそが、農民自身の幸福に繋がり、ひいては社会全体の安定に繋がるという、江戸初期の社会秩序を支える根本思想の表れであった。
この視点の転換は、徳川幕府が目指した社会体制と深く関わっている。戦国時代は、力による収奪、すなわち刈田狼藉や合戦が富の再分配の手段として公然と行われる時代であった 5 。徳川幕府が目指したのは、そのような武力による秩序の破壊を禁じ、安定した農業生産とそれに基づく年貢徴収システムによって、恒久的な平和を維持することであった。この体制を盤石にするためには、生産の担い手である農民が自らの土地で安定して生産を継続し、重税や貧困を理由とした一揆などの社会騒乱を起こさないことが絶対条件であった 15 。
この文脈において、『農業全書』が説く「農民の利益の追求」や「自給自足による経営の安定」は、結果として、幕藩体制の支配イデオロギーと完全に軌を一にするものであった。農民がこの書に書かれた合理的な農法に従って生産性を上げ、豊かになり、安定した生活を送ることは、すなわち社会不安の要因が取り除かれ、支配体制が盤石になることを意味する。その意味で、『農業全書』は単なる一介の技術書ではない。それは、戦国という「闘争の時代」を乗り越え、徳川の「平和な統治の時代」を、生産現場のミクロなレベルで実現するための、いわば「農民向けの経典」としての社会的役割を担ったのである。
結論:戦国を総括し、江戸を拓いた書
本報告書で詳述してきたように、『農業全書』は、江戸時代の平和の中で突如として生まれた単なる農書ではない。それは、戦国百年という長期の動乱期に、日本社会が経験した巨大な地殻変動の帰結として生まれた、歴史の必然的な産物である。生き残りをかけて各地で試行錯誤された無数の農業技術、富国強兵の掛け声の下で推し進められた大規模な社会変革、そして飢餓と隣り合わせの過酷な経験から得られた生活の知恵。本書は、それら全てを内包し、近世という新たな時代の論理の下で昇華させた「歴史の集大成」であった。
その成立基盤には、二つの巨大な戦国の遺産がある。一つは、戦国大名が軍事目的で築き上げた治水・灌漑施設という物理的なインフラ。もう一つは、太閤検地と兵農分離が創出した、農業生産に専従する「近世的農民」という社会的なインフラである。
『農業全書』は、この二つの遺産の上に立ち、戦乱のエネルギーを生産のエネルギーへと転換させようとする時代の要請に応えた。そして、その具体的な方法論を、個々の農民が自らの田畑で実践可能な「合理性」と「実利性」という形で提示したのである。宮崎安貞が中国の知識体系と主体的に対峙し、日本の現実に即した農学を打ち立てたことは、政治における天下統一に続く、知の世界における日本の自立を象徴する出来事であった。
本書が示した実践知と体系性は、その後の日本の農業発展における揺るぎない規範となり、明治期に至るまで日本の農村社会を深く規定し続けた。それは、戦国という激動の時代を総括し、徳川三百年の平和の礎を生産現場から築き上げた、まさに不朽の金字塔と評価できるだろう。
引用文献
- 宮崎安貞(みやざきやすさだ) - 福岡史伝 https://www.2810w.com/archives/3925
- 日本最古の農業書 「農業全書」とは - マイナビ農業 https://agri.mynavi.jp/2018_04_08_24073/
- 農業全書(ノウギョウゼンショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E6%9B%B8-111870
- お米と戦国武将 戦国時代の稲作と経済の関係 - Manic Blend https://manicblend.com/2024/07/26/%E3%81%8A%E7%B1%B3%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E7%A8%B2%E4%BD%9C%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82/
- 農業と戦国時代 ~百姓から見た動乱の時代 - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/okawa_kanai/archives/8252623.html
- 戦国大名の治水事業ー城を造るときに川の流れを変える!?ー超入門!お城セミナー【構造】 https://shirobito.jp/article/922
- 【灌漑農業】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100010/ht040010
- 日本の河川技術の基礎をつくった人々・略史 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kasengijutsu11.html
- 「太閤検地」とはどのようなもの? 目的や、当時の社会に与えた影響とは【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/269995
- 土の章 - 我が国の農地の歴史について https://www.aric.or.jp/kiseki/jp/tsuchi/index.html
- 米が社会の土台となり新田開発が進められた時代 - 国土の基盤づくりの歴史 https://suido-ishizue.jp/daichi/part1/02/05.html
- 太閤検地 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/1104/index.htm
- 三大・藩政改革以外 https://kashu-nihonshi8.com/%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%83%BB%E8%97%A9%E6%94%BF%E6%94%B9%E9%9D%A9%E4%BB%A5%E5%A4%96/
- 兵農分離 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/heino-bunri/
- 豊臣秀吉は、なぜ検地や 刀狩をしたの https://kids.gakken.co.jp/box/syakai/06/pdf/B026109100.pdf
- Web版 図説尼崎の歴史-近世編 - 尼崎市立地域研究史料館 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/03kinsei/kinsei2-c2.html
- 【高校日本史B】「農業の発達」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12728/point-2/
- 日本での肥料の歴史 - 自然栽培米ササニシキ https://oita-shizen-kome.com/information/index-574.html
- 第2回 糞尿のリサイクル:株式会社日立システムズ https://www.hitachi-systems.com/report/specialist/edo/02/
- 【補講①】肥料から時代をみる|過去問講習 - note https://note.com/michinotori/n/nfc1ebe0d23ed
- 日本史の基本97(21-6・7 室町時代の農業と商業) https://ameblo.jp/nojimagurasan/entry-12263603007.html
- 環境史からみた信長の時代Ⅰ - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/645/645PDF/takahashi.pdf
- 環境史からみた信長の時代Ⅱ - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/656/656PDF/takahashi.pdf
- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751
- No.066 筑前の農書展 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/066/index.html
- 7 第1章 貝原益軒の生涯 https://www.musashino.ac.jp/mggs/wp/wp-content/uploads/2024/03/hakase_you_1syou.pdf
- 農業全書 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100259365
- 中国・日本における徐光啓研究 : 伝記・学術・信仰 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/27500/pa023.pdf
- 日本の農業経営と農業知識移転の歴史的考察 - 熊本県立大学 http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1958/6/2019-adomini-zenbun-miyata.pdf
- 下肥 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E8%82%A5
- 千歯扱きは江戸時代の発明農具 手扱き、コキダケ、コキバシ 臼と杵で脱穀した弥生人 https://www.city.settsu.osaka.jp/material/files/group/43/p46-47.pdf
- 時代とともに変化した「脱穀(だっこく)」するための道具 | 稲作の歴史とそれを支えた伝統農具 https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/tools/threshing.html
- 室町・戦国・安土桃山・江戸時代 | 稲作から見た日本の成り立ち - クボタ https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/formation/generation_03.html
- 40.諸産業の発達 - 日本史のとびら https://nihonsinotobira.sakura.ne.jp/sub40.html
- 農業全般の基礎知識として学んでおきたい、日本の農業の歴史 - カクイチ https://www.kaku-ichi.co.jp/media/tips/history-of-japanese-agriculture
- 農民反乱の歴史!百姓一揆の真実 https://chibanian.info/20240422-269/